高齢者雇用における再雇用拒否・雇止め等の問題点と対応策
はじめに

働き方会改革の取り組みの中に高齢者の活用として、再雇用制度における定年制度の撤廃や定年の延長等が検討されるのは素晴らしいことだと思いますが、同時に、高齢者の能力差を原因とする「再雇用拒否」や「雇止め」せざるを得ない状況になる可能性があることも事実です。
この問題について、あまり、はっきりした指針等が示されていないように思いますので、今日は、このテーマについて、解説をさせていただきます。では、よろしくお願いいたします。
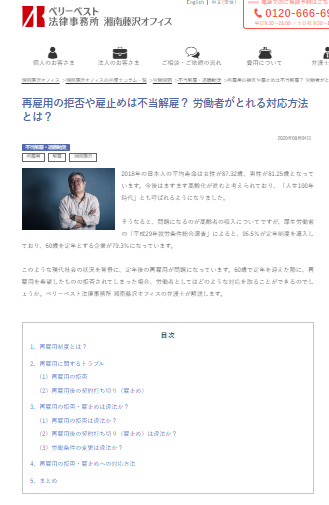

ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィス
再雇用の拒否や雇止めは不当解雇? 労働者がとれる対応方法とは?
https://fujisawa.vbest.jp/columns/work/g_dismissal/3845/
弁護士 家永 勲監修 正当な解雇事由とは
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/retirement/grounds_dismissal/
1.再雇用制度とは?
再雇用制度とは、一般に定年を迎えた労働者が希望した場合に継続雇用する制度、または妊娠・結婚などで一度退職した職員が希望する場合に再度雇用する制度のことをいいます。前者を「定年後再雇用」、後者を単なる「再雇用」と区別する場合もあります。
2013年度の年金法の改正で、男性は1961(昭和36)年4月2日生まれ以降の人、女性は1966(昭和41)年4月2日生まれ以降の人は、年金の支給開始年齢が65歳になりました。多くの企業が60歳定年とする中、年金の支給までに空白の5年間が生まれることから、それを埋め合わせるべく2012年に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、翌2013年に施行されました。
①定年年齢を65歳まで引き上げる
②希望者全員を65歳まで継続雇用する制度を導入
③定年制を廃止
①と③は、特に問題になることはありません。問題となるのは、②の継続雇用制度を導入する場合です。
継続雇用制度を導入する場合は、希望者全員を継続雇用しなければなりません。気にいらない社員だからと継続雇用を拒否することは許されません。ただし、雇用期間中も解雇事由に該当すれば解雇できるように、定年時に解雇事由に該当している場合には、継続雇用しないこともできます。
継続雇用制度は、定年に達した労働者を退職させることなく、継続して雇用する「勤務延長制度」と、定年に達した労働者に対し、一度は退職の形をとり、定年後に新たに雇用契約を結ぶ「再雇用制度」に分類されます。
勤務延長制度は、定年に達してもそのまま雇用契約を継続するものなので、労働時間や賃金等の労働条件は変更されないのが一般的です。また、退職金も勤務延長期間が終了するまで支給されないことが多いでしょう。
それに対し、再雇用制度は定年に達した時点で一度退職となるので、退職金が支給され、定年後新たな条件で雇用契約を結ぶことになります。新たに労働時間や賃金等の労働条件を定め、雇用契約期間を1年として更新により満65歳までとするのが一般的です。厚生労働省の「平成29年就労条件総合調査」によると72.2%の企業がこの再雇用制度を導入しています。
2.再雇用に関するトラブル
(1)再雇用の拒否
これまでも説明してきたとおり、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、企業は、定年年齢を65歳とするか、定年制度を無くす場合でない限り、継続雇用制度を導入しなければなりません。そのため、労働者が60歳以降も雇用継続を望んでいるのに、それを拒否することは原則として許されません。
しかし、会社の中にはこの法律の理解が十分でなく、60歳以降の再雇用は任意と考えている会社も少なくありません。そのため、60歳で定年を迎えた労働者に対して会社が再雇用を拒否するというトラブルが発生することがあります。
(2)再雇用後の契約打ち切り(雇止め)
定年後に一度は再雇用をしたものの、勤務態度の不良などを理由に雇止めをされるというトラブルもあります。契約期間が1年の場合、1年経過後は新たに契約が締結(更新)されることになりますので、その時点で労働者に問題がある場合には契約を更新しないということもすぐさま違法とはいえないからです。
しかし、65歳までの雇用継続は会社に課せられた法令上の義務ですので、再雇用をされた社員は65歳までの雇用継続に対する期待を有することになります。労働契約法では、「契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められる」場合には、会社側の再雇用の拒絶が客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と言える場合でない限り更新される旨を定めています(同法19条)。
したがって、会社が労働契約の更新を拒絶するためには、就業規則等に雇用契約更新の基準が明記されていて当該労働者がその基準に該当しない場合や、就業規則に定める解雇事由に該当する場合など、客観的で合理的な理由があり、更新しないことが社会通念上相当と認められることが必要になります。
3.再雇用の拒否・雇止めは違法か?
(1)再雇用の拒否は違法か?
前述のとおり、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、企業は定年年齢を65歳以上とするか、定年制度を無くす場合でない限り、継続雇用制度を導入しなければなりません。そのため、労働者が60歳以降も雇用継続を望んでいるにもかかわらず、それを拒否することは正当な理由がない限り違法となります。
この適法性の判断枠組みは、一般的に従業員が解雇される場合と同様です。60歳で定年を迎えた際に会社が正当な理由なく更新拒絶をするということは、不当解雇と同じように考えられているのです。
他方、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は会社に対して従業員が65歳まで働ける環境を整備することを義務付けているにすぎません。会社が欠格事由に該当するという理由で再雇用を拒否し、客観的にも欠格事由該当性が認められる場合には、会社が個々の従業員について再雇用を拒否することができます。一方、欠格事由該当性が客観的に認められず、かつ再雇用後の賃金・労働条件が特定できる場合には、会社と労働者の間で黙示の合意があったとみなされます。
(2)再雇用後の契約打ち切り(雇止め)は違法か?
定年後再雇用した社員の雇止めの可否については、有期労働契約である以上、有期労働契約について定める労働契約法第19条の要件該当性が問題となります。
労働契約法では、①過去に反復して更新されたことのある有期労働契約であって、その契約期間の満了時に当該労働契約を更新せずに終了させることが期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をして契約を終了させることと社会通念上同視できると認められるか、または、社員が当該有期契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められる場合であって、②当該有期労働契約の契約期間が満了するまでの間に労働者が当該契約の更新の申込みをしたか、または当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをしており、③使用者が当該申込みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされる旨、規定されています。
なお、労働者の更新の申込みは、明示的になされる必要はなく、雇止めされることが判明した時点で遅滞なく異議を述べれば足ります。
そこで、再雇用後の雇止めについてみると、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、会社に65歳までの雇用を義務付けていますので、65歳未満の労働者が更新されると期待することについては原則として合理的な理由があると認められることになります。
したがって、会社は労働者から継続雇用の希望を受けた場合には原則として雇止めをすることはできません。
会社が有効に雇止めをするためには、通常の解雇の場合と同様に心身の故障のため業務に堪えられないと認められることや、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと、職場規律違反や整理解雇の要件を満たす場合などに留まることになるでしょう。
つまり雇用されている人が解雇されるような場合でない限り、雇止めは許されないということです。労働者が再雇用を希望しているのに使用者が正当な理由なく拒否した場合は、不当解雇として、裁判で争うことも可能です。
解雇とは
労働契約法16条
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
使用者から労働者に対して雇用契約の終了を申し入れるのを「解雇」といい、労働者から使用者に対して申し入れるのを「退職」といいます。
解雇は自由にできるものではない
解雇は自由にできるわけではありません。しかし、解雇を制限する規定はあっても、具体的にどのような場合に解雇ができるのか、ということを労働基準法は明確にはしてくれていません。解雇は、労働者にとって従業員たる地位そのものひいては収入源を喪失することになるので、深刻な事態を引き起こしかねません。解雇に伴うトラブルを未然に防止するためには、解雇が有効となるために必要な事情を知っておくことが重要です。
労働者の解雇における正当な解雇事由の必要性について
民法は、雇用契約に期間の定めのない場合については、各当事者はいつでも解約の申込みをすることができ、この場合において雇用契約は解約の申込み後2週間の経過によって終了すると定めています(民法627条1項)。この規定のみを見れば、使用者には解雇の自由が認められるかのように見えます。しかしながら、労働者は、解雇されると生活の基盤を失うのみならず、社会的にもさまざまな不利益を受けることから、労働契約法(以下、労契法とします。)は、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない限りは、その権利を濫用したものとして、無効とすると定めて(労契法16条)、使用者による解雇が制限されており、労働者を解雇するには正当な解雇事由が必要とされています。
就業規則による解雇事由の明示
平成15年7月4日法律第104号の労働基準法(以下、労基法とします。)の一部改正において、就業規則の作成・届出義務の対象事項として、「退職に関する事項(解雇の事由を含む)」(労働基準法89条3項)が追加され、就業規則の必要的記載事項として、「解雇」が含まれることが明らかになりました。これにより就業規則の中に、解雇事由を記載しなければならないことが明確になりました。
解雇を行うにあたっては、まずは、就業規則において明示的な定めを根拠の有無を確認したうえで実施することになりますので、必要な解雇事由が就業規則に盛り込まれているか否かは、確認するほか、社内における問題が生じた場合には、今後の対策として、解雇事由への追加を検討する必要もあります。
解雇の種類
「解雇」とは、会社から社員に対して一方的に労働契約を終了させることをいい、3つの種類があります。
➀整理解雇
経営不振や天災事変等でやむを得ず事業を廃止、縮小するときに行われます。
➁普通解雇
病気や勤務怠慢等さまざまな理由で、社員として適格性が著しく低いと認定されたときに行われます。
③懲戒解雇
社員としてふさわしくない行動をし、会社秩序を著しく乱したときに行われます。
普通解雇における解雇事由
1.私傷病による就業不能
私傷病により業務遂行が困難になった者について、会社は、業務内容・勤務時間の配慮や、傷病欠勤、傷病休暇等の休職制度により療養の便宜と機会を与え、病状の回復・改善を待つのが通例です。しかしながら、療養による回復・改善の機会を十分に与えても、業務を遂行できるような回復がない場合には、就業規則の該当解雇事由に基づき、解雇を検討することになります。
2.勤務態度の不良、協調性の欠如
労働契約は、労働者が使用者の指揮命令に従って誠実に労務提供することが基本的要素になっています。誠実に労務提供するということは、使用者の指揮命令に従って労務を提供することであり、成果さえ出せれば自分勝手に働けば良いということではありません。特に、上司に反抗的であり指揮命令に従わない、正当理由のない遅刻、早退、無断外出による職務怠慢が認められれば、このような勤務態度の不良は契約内容違反として契約解消のための解雇事由となります。
また、会社は集団で労務を提供する「共働」の場ですから、会社運営の円滑な遂行のためには必然的に他の労働者との協調性が求められます。そのため、協調性が欠如するということは、労務提供に瑕疵がある、すなわち契約解消事由になります。
3.能力不足・成績不振
労務提供も単に働けば良いというものではなく、当該労働契約で約束された一定の成果を出す必要があります。したがって、能力不足を理由として当該労働契約において約束した一定の成果が出せない場合には、契約内容を守られていないため、能力不足や成績不振等も契約解消のための解雇事由になることがあります。
また、誠実に労務を提供するということは、労働契約で定められた労働時間を遵守するとともに、始業時刻や終業時刻の約束を守る必要があります。すなわち、欠勤、遅刻、早退等は契約違反であるので、それらの勤務成績不良についても契約解消事由になります。
就業規則における解雇事由の記載例
(解雇)
第42条 従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは解雇する。
(1)能力不足又は勤務成績不良で就業に適さないと認められるとき
(2)精神又は心身の障害、若しくは虚弱、疾病等によって業務に耐えられないと認められるとき
(3) 勤務態度が不良で従業員として不適格なとき
(4)協調性を欠き、他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき
(5)事業の縮小その他やむを得ない事由により雇用を維持することができなくなったとき
(6)その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
懲戒解雇における解雇事由
懲戒解雇とは、社員として相応しくない行動をし、そのことによって著しく経営秩序を乱し、会社の運営に悪影響を及ぼした場合に懲戒を行使して解雇処分とするものです。
1.法律に抵触する行為
就業規則においては、「法令に違反した場合」や「刑罰法規に反する行為を行い、その犯罪事実等が明らかになった場合」等が懲戒解雇の事由として定められていることがあります。
しかしながら、労働契約は、会社がその事業活動を円滑に遂行するに必要な限りでの規律と秩序を根拠づけるものにすぎず、労働契約に基づく労務提供以外の時間帯や労働者の私生活に対して使用者が支配できるわけではありません。たとえ、労働者の私生活上の行為において法令違反や犯罪行為が生じたとしても、事業活動に直接関連性を有するものや会社の社会的評価の毀損をもたらす場合に限って、のみが懲戒解雇になると考えるべきでしょう。
2.長期間の無断欠勤
無断欠勤は、それ自体では単なる債務不履行であって、直ちに懲戒解雇できるとはいえません。ただし、注意や指導を行ったにもかかわらず繰り返されたりすることで、それが就業に関する規律に反したり、職場秩序を乱したりしたと認められる場合には、懲戒解雇事由となり得ます。
3.重大な経歴詐称
労働契約は、労働者と使用者との間に継続的な関係をもたらすものです。重大な経歴の詐称は、会社秩序の根幹をなす会社と労働者間の信頼関係を破壊するものであり、懲戒解雇事由となり得ます。
実務上は、いかなる経歴が「重大」といえるかという点が問題となりますが、求人や面接の際に、求職者に求める能力や実績等が明らかにされている場合や、業務の内容から明確に必要とされる資格等が詐称されている場合等には、「重大」と評価されることが多いでしょう。
4.セクハラ、パワハラ
セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントは、いずれも、職場内の環境を害する性的言動や優越的な関係を背景とした言動等を含んでおり、これらの行為は著しく経営秩序を乱し、会社の運営に悪影響を及ぼす場合があるため、多くの会社で禁止する旨が就業規則に明記され、懲戒解雇事由とされることが多くなっています。
就業規則における諭旨退職、懲戒解雇の記載例
(諭旨退職、懲戒解雇の事由)
第53条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇若しくは諭旨退職に処する。ただし、情状により、前条の処分にとどめることがある。
(1)無断欠勤が14日以上に及び、出勤の督促に応じない又は連絡が取れないとき
(2) 正当な理由なくしばしば業務上の指示又は命令に従わないとき
(3) 故意又は重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき
(4) 重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出等を行ったとき
(5) 重大な報告を疎かにした、又は虚偽報告を行った場合で、会社に損害を与えたとき又は会社の信用を害したとき
(6)正当な理由なく配転・出向命令等の重要な職務命令に従わず、職場秩序を乱したとき
(7) 素行不良で、著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントによるものを含む。)
(8) 会社内で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する重大な行為をしたとき
(9) 会社及び会社の従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽の風説を流布若しくは宣伝し、会社業務に重大な支障を与えたとき
(10) 会社及び関係取引先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、あるいは漏らそうとしたとき
(11) 再三の注意及び指導にもかかわらず、職務に対する熱意又は誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき
(12) 職務の怠慢又は不注意のため、重大な災害、傷病又はその他事故を発生させたとき
(13) 職務権限を越えて重要な契約を行い、又は会社に損害を与えたとき
(14) 刑罰法規の適用を受け、又は刑罰法規の適用を受けることが明らかとなり、会社の信用を害したとき
(15) 会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為等、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い、会社に損害を与え、その信用を害したとき
(16) 前条の懲戒を受けたにもかかわらず、あるいは再三の注意、指導にもかかわらず改悛又は改善の見込みがないとき
(17) 第3章(服務規律)の各規定に違反する重大な行為があったとき
(18) その他前各号に準ずる重大な行為があったとき
整理解雇が有効となる解雇事由
整理解雇は経営者側の事情によるものですから、普通解雇や懲戒解雇以上に制約が多く、権利の行使や義務の履行にあたり、社会生活を営む者として労働者の信頼や期待を裏切らないよう誠意をもって解雇権を行使することが求められます。具体的には、
①会社の維持・存続をはかるために人員削減の必要性があること
②整理解雇を回避するための策を実行していること
③解雇する人選基準が合理的であること
④社員側に事情説明があること
という4つの要素を考慮して判断されます。
不当解雇とみなされる解雇事由とは
普通解雇と懲戒解雇のいずれであっても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます(労契法16条)。
まず、客観的に合理的な理由とは、通常は就業規則に定められた解雇事由に該当する具体的に明らかな事由(誰が、いつ、どこで、どのような行為をし、それが就業規則に規定するどの条項に該当するか)の存在が求められます。