障がい者雇用制度の簡易解説
参考資料・URL
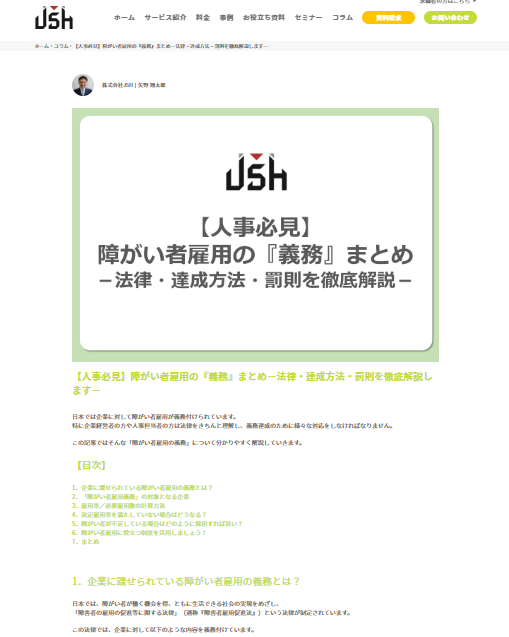

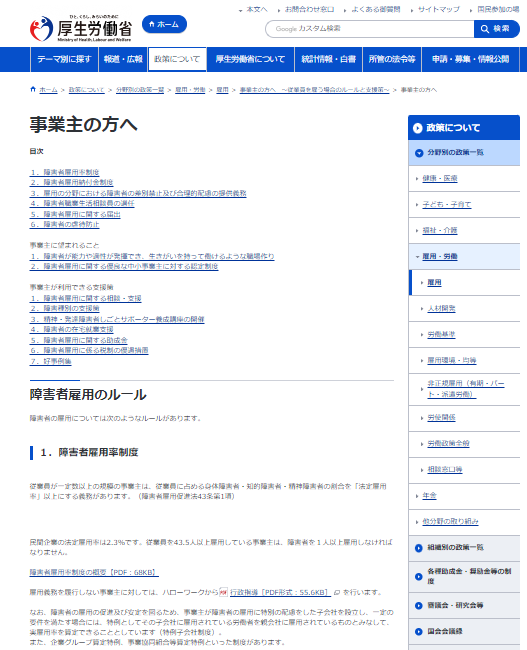
【人事必見】障がい者雇用の『義務』まとめ-法律・達成方法・罰則を徹底解説します-
https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/798/
【最新版】障害者雇用促進法の2020年改正を図解!企業が取るべき対応とは?
https://www.dodadsj.com/content/200602_employment-promotion-act-for-persons-with-disabilities/
厚生労働省 障害者雇用率制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
はじめに

画像の説明を入力してください
日本では企業に対して障がい者雇用が義務付けられています。
特に企業経営者の方や人事担当者の方は法律をきちんと理解し、義務達成のために様々な対応をしなければなりません。
今回、そんな「障がい者雇用の義務」について分かりやすく解説していきます。
1.企業に課せられている障がい者雇用の義務とは?
日本では、障がい者が働く機会を得、ともに生活できる社会の実現をめざし、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(通称『障害者雇用促進法』)という法律が制定されています。この法律では、企業に対して以下のような内容を義務付けています。
企業に課せられる4つの義務
①障がい者の雇用
全従業員に対して一定以上の割合で障がい者を雇用すること
②差別禁止と合理的配慮の提供
障がいを理由に不当な差別をせず、社会的障壁をなくすために個別の対応や支援を行うこと
③障害者職業生活相談員の選任
相談員を選任し、相談・指導を行わせること ※障がい者雇用数が5名以上の場合のみ
④障害者雇用に関する届け出
障がい者の雇用状況を毎年ハローワークへ報告すること ※従業員数43.5名以上の場合のみ障がい者を解雇しようとする場合はハローワークへ届け出すること
上記の義務を達成できないと、様々な罰則リスクが発生します。
ここでは、特に準備や管理に課題の多い「①障がい者の雇用」の義務について詳細を解説していきます。
最近の法改正について
「障害者雇用促進法」は、制定以来様々な改正が行われています。
直近では、2020年4月に以下2点の改正がありました。
①短時間であれば就労が可能な障がい者等の雇用機会を確保するため、
短時間労働者を雇用する事業主にも特例給付金を支給する
※これまでは短時間労働の場合は支給対象外だった
②障がい者雇用への取組実施状況が優良である基準に適合する中小事業主を認定する。
また、2021年3月には、全従業員に対する障がい者の雇用割合(=「法定雇用率」)が
「2.2%」から「2.3%」へ引き上げられました。
今後も社会情勢や様々なニーズに合わせ、適宜法改正が行われていくものと思われます。
2.「障がい者雇用義務」の対象となる企業
先ほどご紹介した4つの義務のうち、「①障がい者の雇用」については従業員数43.5名以上の企業が対象となっています。
43.5名未満の企業には雇用義務はありません。
3.雇用率/必要雇用数の計算方法
対象障がい者
障がい者としてカウントする対象になるのは、各自治体から発行される「障害者手帳」を保有している人です。
手帳が発行される障がいには以下のような種類があります。
身体障がい:身体上の障がいを持つ人
知的障がい:知的機能に障がいを持ち、知能指数(IQ)が一定の水準に満たない人
精神障がい:精神的な障がいを持ち、日常生活に困難をきたしている人
発達障がい:脳機能の発達の障がいを持つ人(アスペルガー、ADHDなど)
人数のカウント方法
通常、常用雇用で働いている障がい者を「1人」としてカウントしますが、
雇用側の負担等を考慮して以下のような例外も設けられています。
■重度の身体障がい者(障害者手帳で「1級」「2級」とされている人)
⇒「2人」とカウント
■重度の知的障がい者(障害者手帳で「A」区分とされている人)
⇒「2人」とカウント
■短時間労働者(週あたり所定労働時間20時間以上、30時間未満の人)
⇒「0.5人」とカウント
※ただし、雇用開始または手帳取得から3年以内で、かつ上記が
2023年3月中までに完了している精神障がい者の場合は「1人」とカウントできます。
■超短時間労働者(週あたり所定労働時間20時間未満の人)
⇒「0人」とカウント
なお、上記の条件が2つ以上重なる場合はその数字を掛け合わせてカウントします。
(例)重度身体障がい者で、短時間労働者の場合:2人×0.5人=1人
計算式
上記で対象者数をカウントできたら、自社の障がい者雇用率を計算してみましょう。
-----------------------
実雇用率=対象障がい者数÷常用労働者数
-----------------------
この数字が2.3%を下回っている場合は、新規雇用が必要です。
また、「自社に必要な障がい者の数」を求めたい場合は以下の方法で計算します。
-----------------------
必要障がい者数=常用労働者数×2.3%
-----------------------
4.法定雇用率を満たしていない場合はどうなる?
雇用義務があるにも関わらず障がい者雇用を行っていない企業や
法定雇用率を達成できていない企業には、以下のようなペナルティが課せられます。
①納付金を納めなければならない
障がい者雇用をする企業・しない企業の間の不均衡を解消するために「障がい者雇用納付金制度」が設けられています。
常用労働者数が100人を超える企業の場合、1人不足するごとに月額5万円を支払わなければなりません。
②行政指導が入る
ハローワークより雇用計画の作成が命じられます。計画作成後、それが遂行できていない企業にはさらに勧告が行われます。
③企業名が公表される
上記の指導によって状況が改善されない場合は追加の特別指導が入り、厚生労働省のホームページで企業名が公表されてしまいます。
法定雇用率を満たさないと、経済的な圧迫だけでなく、社名公表による企業イメージの低下も避けられない問題となるでしょう。
5.障がい者が不足している場合はどのように採用すれば良い?
法定雇用率を達成できていない企業では、すぐに障がい者の新規採用を進める必要があります。
障がい者を採用する主なルートをご紹介します。
ハローワークに求人を出す
国が設置するハローワークは、求人を出す場として最もポピュラーな場所の一つです。
障がい者専門の窓口を設けているので、比較的多くの求職者に出会えるというメリットがあります。
有料の媒体で求人広告を出す
有料の求人広告を利用すれば、ハローワーク以上の採用サポートが期待できます。
ただし、大手企業・有名企業が多く求人を出しており、比較的待遇の良い求人も多いため、
採用難易度は高めと考えた方が良いでしょう。
特別支援学校へ求人票を出す
中長期的に障がい者の雇用を続けていきたい場合、
特別支援学校とコネクションを持つことで継続的に卒業生を紹介してもらうことが期待できます。
特別支援学校が近隣にある場合は問い合わせをしてみるのもおすすめです。
障がい者雇用支援サービスを利用する
上記の方法でなかなか採用がうまくいかない場合や、採用してもすぐに退職してしまうケースに悩んでいる場合は、
採用・定着の総合的な支援サービスを利用するのもおすすめです。
障害者雇用に関する助成金
(1)障害者の雇い入れ等を支援する助成金
障害者を雇い入れた場合などの助成 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(2)障害者が働き続けられるよう支援する助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html#HID4
まとめ
以上、障がい者雇用の義務」について解説しました。
基本的な義務や、これから取り組むべき内容をご理解いただけたでしょうか。
障がい者雇用にお悩みの担当者様は、ぜひお問い合わせください。