「雇用契約と業務委託契約の違い」簡単解説
参考資料

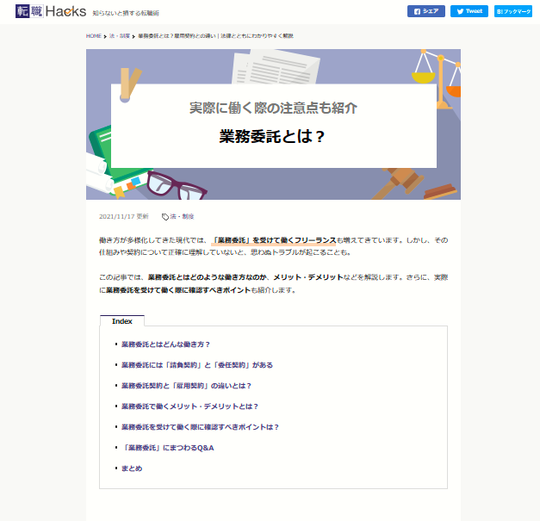
ジンジャー
雇用契約と業務委託契約の違いとは?違いを見分ける具体的な要素
https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_subcontracting/
転職
実際に働く際の注意点も紹介 業務委託とは?
はじめに
本日、お客さまから次のご依頼をいただきました。
「今度、雇用する社員ですが、雇用契約ではなく、業務委託契約にしたいと考えています。」「井上さん、何とかしていただけませんか」
私は、咄嗟にいただいたご依頼でしたので、雇用契約と業務委託契約の違いをうまく説明できませんでした。
ということで、あわてて、このファイルを作成した次第です。
出来る限り、わかりやすく解説させていただくつもりでので、
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
1.雇用契約と業務委託契約の違いとは
1-1.雇用契約とは
雇用契約とは、民法623条により定義されている労働供給契約の1つです。
具体的には、当事者である一方(労働者)が相手方に使用されて労働に従事し、使用者である相手方は、その労働に対して賃金を与える約束をする契約のことです。
雇用契約を締結した労働者は、労働保険や社会保険の加入や有給休暇の取得、使用者からの一方的な解雇の禁止など、労働法上の保護を受けることができます。
従業員の立場を守るために民法や労働基準法によってある程度のルールは定められていますが、契約成立に書面の作成が義務付けられているものではありません。
1-2.業務委託契約とは
一方で、業務委託契約とは、自社で対応できない業務を、他社やフリーランスなどの個人といった外部に任せる契約です。
業務委託契約は、その名がつく法律はありませんが、業務委託契約は請負や委任といった契約について記述されている民法に法的根拠を持つとされる民法第632条の「請負契約」や民法第643条の「委任契約」が該当すると考えられています。
①請負契約とは
請負契約とは、発注者に依頼された仕事の完成や、成果物を納めることを目的とした契約のことです。
受託者には、依頼された仕事を完成させる義務(瑕疵担保義務)が発生し、完成した仕事や成果物を納品して、はじめて報酬が支払われます。ただし、発注者の意に沿った結果や成果が得られないと、報酬を請求できません。
請負契約と同様に他人の労務を利用する契約類型である「委任契約」や「雇用契約」との違いとしては、仕事の完成を目的とする点に請負契約の特色があります。
②委任契約とは
委任契約と民法上同じルールが適用される契約類型に、 準委任契約というものがあります(民法656条)。
委任契約と準委任契約との違いは、 委任契約は、法律行為を委託する契約であるのに対し、準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約です。
法律行為とは、代理人契約などの契約を締結するための意思表示があげられます。
これに対して、事実行為(事務処理)とは、書類作業や開発業務など、あらゆる業務が想定されます。
仕事の過程ではなく結果や成果を求めらる請負契約に対し、委任契約は事務処理を目的とした契約であるため、発注者の意に沿っていない結果であっても、報酬の請求が可能な点が特色です。
2. 雇用契約と業務委託契約の違いの見分け方
雇用契約と業務委託契約の大きな違いは「使用従属性」にあります。
使用従属性があれば雇用契約、なければ業務委託契約と判断できます。
雇用契約を結んだ場合、働く人は「労働者」となり、雇用主からの命令や指示にある程度の拘束力が生じます。
一方、業務委託契約は、ある特定の仕事を行った個人や事業者に対して依頼主が報酬を支払うという形態の契約です。
業務委託契約には雇用主と労働者という「使用従属性」はなく、2つの独立した個人もしくは事業者間の契約ということになります。
したがって、仕事を請け負った側は労働者ではないため、労働基準法など法律の保護を受けることはできません。
2-1. 使用従属性が認められる具体的な要素
使用従属性が認められる要素には主に以下13個があります。
使用従属性が認められる具体的な要素➡使用従属性の有無
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無➡
自由がない場合は使用従属性がある
②業務内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無 ➡
業務遂行上の指揮関係が強い場合は使用従属性がある
③勤務場所・勤務時間の拘束性の有無➡
拘束性がある場合は使用従属性がある
④通常予定されている業務以外の業務の有無➡
業務がある場合は使用従属性がある
⑤労務提供の代替性の有無➡
代替性がある場合は使用従属性がある
⑥報酬の基準が結果基準か時間基準か➡
時間基準の場合は使用従属性がある
⑦欠勤時に、賃金が控除させるか➡
控除される場合は使用従属性がある
⑧残業手当がつくか否か➡着く場合は使用従属性がある
⑨報酬額が同様の業務に従事している正規従業員と比べて
著しく高額であるか➡高額である場合は使用従属性がある
⑩機械、器具、原材料の負担関係➡
会社負担である場合は使用従属性がある
⑪就業規則・服務規律の適用がされるかどうか➡
適用される場合は使用従属性がある
⑫退職金制度、福利厚生制度の適用を受けることができるかどう
か➡受けることができる場合は使用従属性がある
⑬給与所得として源泉聴取がされるかどうか➡
源泉聴取がされる場合は使用従属性がある
たとえば仕事をするための勤務場所や勤務時間などの決まりがあるかどうかが関係します。
また、業務を行うにあたって指揮命令があるかどうかも重要な要素です。
どちらも勤務地や勤務時間、業務上の指示を労働者が拒否できないのであれば、使用従属性があるため、雇用契約であると考えられます。
就業規則や服務規律があったり、福利厚生制度の恩恵を受けていたりする場合も雇用契約であると判断されるでしょう。
さらに、仕事の成果に対してではなく、働いたことそのものに対して報酬が支払われている場合には雇用契約となります。
こうした要素を総合的に見て、契約の形態が判断されます。
3.業務委託契約が雇用契約と判断された場合
さまざまな場面で「使用従属性」が認められる場合には、たとえ契約書に「業務委託契約書」と書かれていても雇用契約と見なされることが少なくありません。
雇用契約の場合、労働者に対しては労働基準法による保護が適用されます。
具体的には、以下のような労働法上の保護が適用されます。
雇用保険、健康保険、労災保険、厚生年金保険などの社会保険制度が利用できる
年次有給休暇を取得することができる
労働基準法に基づき、残業代を請求することができる。
4.雇用契約と業務委託契約は同時に結ぶことができる
雇用契約と業務委託契約は、同時に締結することができます。
アルバイトや契約社員などの雇用契約者が収入アップのため、業務時間外を利用して会社の仕事を請け負いという場合などに、雇用契約と業務委託契約を同時並行で締結することが多いです。
ここで注意すべき点は、業務委託契約が「雇用の延長」とみなされないように雇用契約の部分と業務委託の部分を切り離すことが重要です。
雇用契約が時間基準で報酬が発生するのに対して、業務委託契約は業務内容や成果物に対して報酬が発生するので注意が必要です
最後に
いかがでしたでしょうか。
要は、どのような契約にするということではなく
何をどのようにしてもらうのかについて
よく話し合い、会社と社員の双方が、納得した上で
契約を締結することが重要であると考えます。
いつも申し上げていることですが、要は
正々堂々と真正面から、話し合うことだと思います。