特定行政書士試験合格への招待
はじめに
昨年(2021年)6月29日(火)に「特定社会保険労務士試験合格への招待」をホームページにアップいたしましたが、毎月、毎月、尻上がりに検索者数が増加し、昨年の試験直前の10月と11月は、単月で1,000件を超える検索がございました。また、今月(2022年3月)も500件の検索をいただいております。また、たまたま、勉強会でお会いした社労士の方から、「井上先生のホームページ、参考にさせていただきました。ありがとうございました。」というようなお声もいただいております。改めて、特定社労士試験、特定行政書士試験は情報不足なんだなあと思い、不十分かもしれませんが、「特定行政書士試験合格への招待」を作成させていただいて次第です。少しでも、受験生の方の役に立てばと思い作成いたしました。よろしければ、ご利用ください。
受験者数・合格者数・合格率
令和3年11月17日 日本行政書士会連合会
〇申込者数 681名
〇受験者数 575名
〇終了者数 390名
〇合格率①(分母:受験者数) 67.8%(390/575)
〇合格率②(分母:申込者数) 57.3%(390/681)
出題科目、出題数及び出題範囲
試験時間 120分
合格ライン 特に定めはなし(ただし、おおむね6割程度の正解率は必要)
①行政法総論・②行政手続法
③行政不服審査法・④行政事件訴訟法
①~④ 20問
⑤要件事実・要件認定論・
⑥特定行政書士の倫理(複合問題を含む)
⑤~⑥ 10問
合計 30問
令和3年4月1日現在施行されている法令を出題範囲とする。
合否通知書等
令和3年度試験問題
日時 令和3年10月17日(日)14時~16時 2時間
テキスト・過去問・ハンドブック
1.配付されたテキスト等
①法定研修テキスト
②行政書士のための行政法
③要件事実の基礎
2.自分で用意したテキスト等
①特定行政書士試験 合格対策(要点解説と模擬問題)特定行政書士 岡田忠興氏著
②行政書士試験の過去問
③行政書士の教科書
④要件事実入門
⑤条文録音用レコーダー
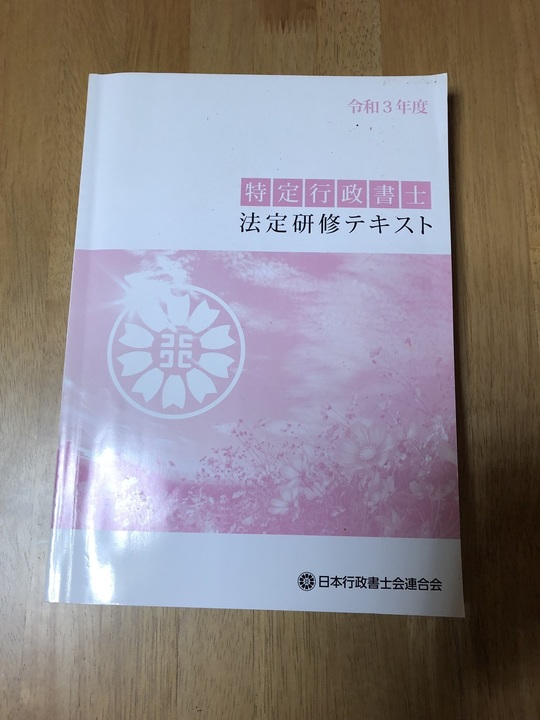
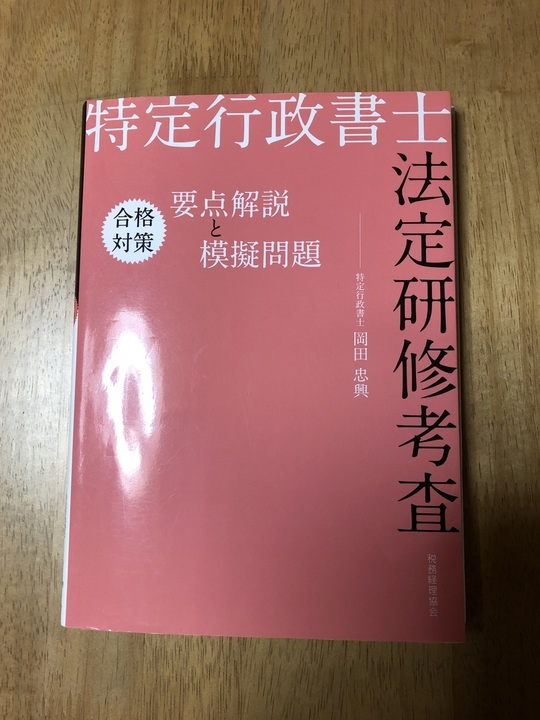
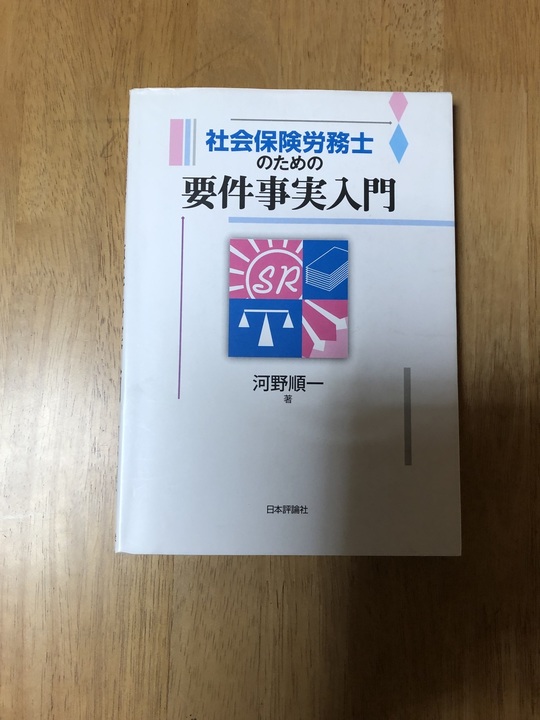
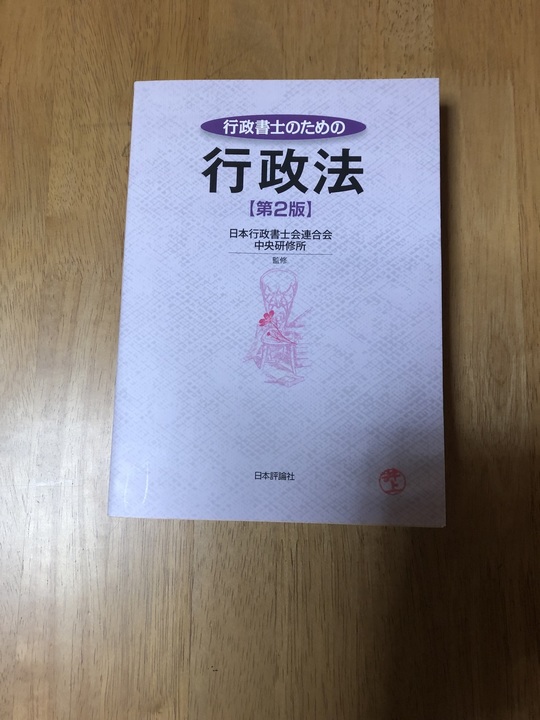
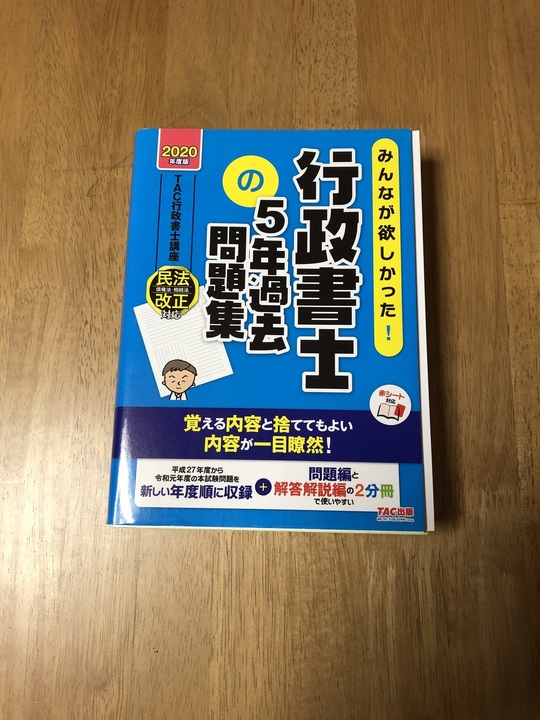
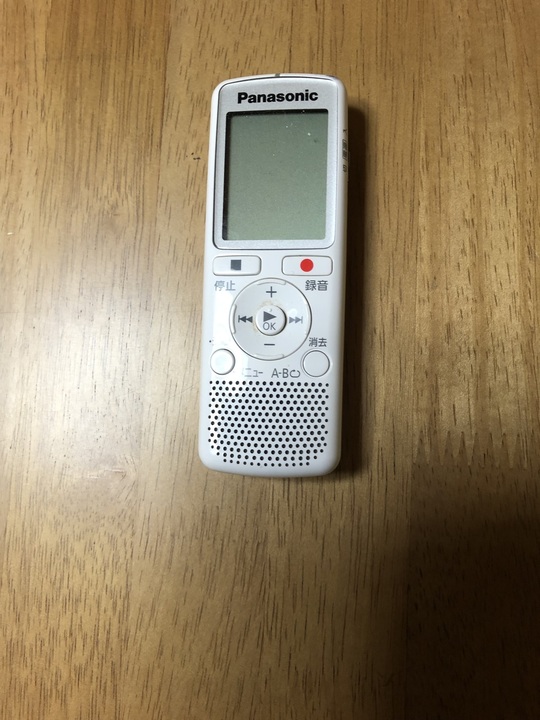
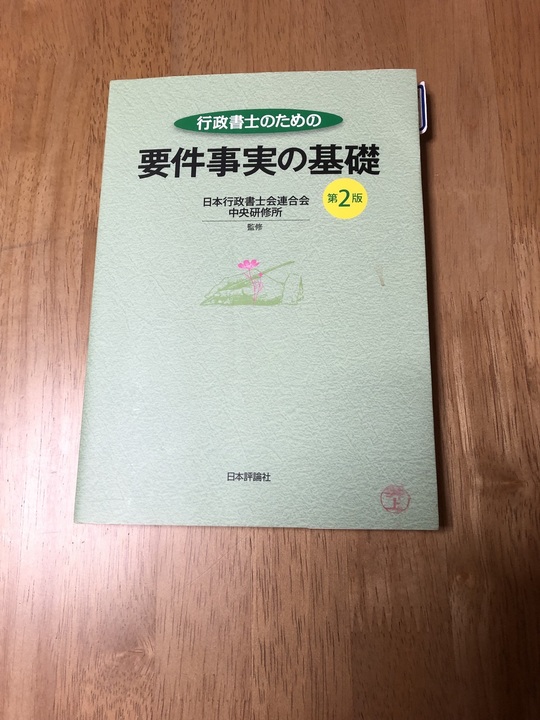
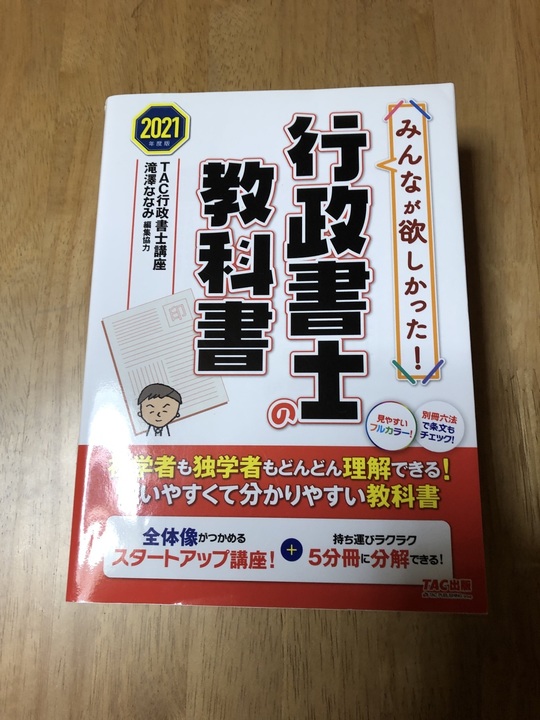
ダイジェスト版の条文
その他イノキュウ作成オリジナルファイルのご案内
1.これが説明できれば合格がみえるぞ「要件事実」
① 要件事実とは→「一定の法律効果(権利の発生、障害、消滅、阻止)を発生させる法律要件に該当する具体的事実」をいいます。P45
② 弁論主義とは→「裁判の基礎となる、訴訟物についての判断資料となる事実と証拠を提供することを当事者の権能かつ責任とする建前」をいいます。P46
③ 職権探知主義とは→「弁論主義の対極には職権探知主義という考え方があります。行政不服審査法は職権探知主義を採っています。P47
④ 弁論主義
1. 第一原則(第一テーゼ)→裁判所は、当事者が主張していない事実を認定して判決の基礎にしてはならない。→「主張責任」につながります。
②2.第二原則(第二テーゼ)→裁判所は当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎にしなければならない。→「裁判上の自白につながります。
3. 第三原則(第三テーゼ)→当事者間に争いのある事実について証拠調べをするには、原則として、当事者が申し出た証拠に拠らなければならない。(職権証拠調べの禁止)
(例外)職権証拠調べ(行訴法24条)、調査委託(民訴法186条)、当事者尋問(民訴法207条1項)
⑤ 主張責任→ある法律効果の発生要件に該当する事実が弁論に現れないために、裁判所がその要件事実の存在を認定することが許されない結果、当該法律効果の発生が認められないという一方の当事者の受ける訴訟上の不利益又は危険。P48
⑥ 立証責任→訴訟上、ある要件事実の存在が真偽不明(ノンリケット)に終わったために当該法律効果の発生が認められないという一方の当事者の受ける訴訟上の不利益又は危険。P48
⑦ 訴訟物→訴訟上の請求は、一定の権利又は法律関係の存否の形をとりますが、その内容である一定の権利又は法律関係を訴訟物といいます。P50
⑧ 請求原因→請求原因とは、訴訟物である権利又は法律関係を発生させるために必要な法律要件に該当する事実をいいます。P50
⑨ 自白・否認・不知・沈黙P51
・自白→相手方から主張された事実の存在を認めること
・否認→相手方から主張された事実の存在を認めないこと
・不知→相手方から主張された事実の存在を知らないと答えること→その事実を争ったものと推定される。
・沈黙→相手方から主張された事実の存在について黙っていること→弁論の全趣旨からその事実を争っていると認められるときを除き、自白したものとみなされます。(擬制自白、民訴法159条1項)
⑩ 単純否認・積極否認P51
・単純否認とは、→単に相手方の主張を否認する陳述
・積極否認とは、→相手方の主張事実と両立しない事情を積極的に述べて相手の主張を否定する陳述です。
⑪ 証拠裁判主義→事実認定は証拠に基づくことを求める建前P61
⑫ 主要事実・間接事実・補助事実P63
・主要事実→権利の発生、消滅という法律効果の判断に直接必要な要件事実
・間接事実→主要事実の存否を推認するのに役立つ事実
・補助事実→証拠の証拠力に影響を与える事実
⑬ 直接証拠・間接証拠・補強証拠P63
・直接証拠→要証事実である主要事実を直接に証明できる内容を持つ証拠
・間接証拠→間接事実や補助事実を証明する証拠
・補強証拠→証拠Aが提出されて甲事実の存否が証明される場合、Aの証明力を補充し強化する別の証拠B
⑭ 証拠・人証。物証P65
・証拠とは、→事実認定の基礎となる資料のこと
・人証→取り調べの対象が人(当事者本人、証人等)である場合→流動的・全体像
・物証→取調べの対象が物(文書等、書証)である場合→固定的・断片的
⑮ 証拠能力・形式的証拠能力・実質的証拠能力P65
・証拠能力とは→証拠資料を事実認定のために利用し得る資格のことをいいます。
・形式的証拠能力→書証の場合は、文書が証拠となり得る資格(文書の記載内容が作成者の思想を表現したものであること)。
・実質的証拠能力→書証の場合は、形式的証拠力を備えた文書が事実認定に役立つ程度。
⑯証明と疎明P65
・証明とは→裁判官が要証事実の存否につき確信を抱いた状態、あるいは、確信を得させるために証拠を提出する当事者の行為をいいます。
・疎明とは→証明の程度には至らないが一応確からしいという程度の蓋然性が認められる状態、または、その状態を実現させるために当事者が証拠を提出する行為のことです。
⑰自白とは、→相手の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述をいいます。P66
自白の考課は→①証拠調べの必要がなくなる。(民訴法179条、証明不要効)
②裁判所に対する拘束力がある(審判排除効、弁論主義の第2原則)
③当事者間にも拘束力がある(撤回禁止効)
⑱ 自白の撤回→裁判上の自白は、原則として撤回できませんが例外的に自白の撤回が認められます。
① 相手方が撤回に同意した場合
② 刑事上罰すべき他人の行為によって自白した場合
③ 自白が真実に反していて、かつ、錯誤にもとづいている場合 P67
⑲書証・処分書証・報告書証P67
・書証とは、→裁判官が文書を閲読して読み取った記載内容を証拠資料とするための証拠調べのことをいいます。
・処分書証とは、→意思表示その他の法律行為が文書によってされた場合のその文書→(例)契約書、手形、遺言書
・報告書証とは、→処分書証以外の文書で、事実に関する作成者の認識、判断、感想等が記載されたもの→(例)領収証、商業帳簿、日記、手紙
⑳自由心証主義とは→民事訴訟法247条は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定しています。これを自由心証主義といいます。
ただし、裁判官の恣意的判断を認めるものではなく、経験則・論理則に基づく合理的なものでなければなりません。
近代の訴訟法では、自由心証主義が採用されています。自由心証主義に対する考え方は法廷証拠主義です。P69以上
2.不明な言葉等
証明と疎明のちがい(コトバンクより)
証明は合理的な疑いを差し挟まない程度に真実らしいと裁判官に確信を抱かせること。またこの状態に達するべく証拠を提出する当事者の行為。疎明はこれより低く、一応確からしいとの推測を裁判官が得た状態、またそれに達するよう証拠を提出する当事者の行為。
イノキュウが実際に行ったこと
勿論、特定行政書士法定研修のe-ラーニングを学習し、修了したた上で、
1.行政書士試験の復讐
①条文を録音レコーダーに録音し、毎朝のウィーキングの際に聞きました。
②行政書士試験5年間の行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の問題を解きました。
2.要件事実対策
①河野順一氏の著書、「要件事実入門」を購入し、勉強しました。
②民事訴訟法の主要条文を録音レコーダーに録音し、毎朝のウィーキングの際に聞きました。
③これが説明できれば合格がみえるぞ「要件事実」を作成し、覚えました。
3.模擬問題を解きました(くり返し)
①TAC行政書士過去問
②特定行政書士試験対策(岡田忠興氏著)テキストの模擬問題
③中央研修所 研修サイト模擬問題
最後に
以上、私が実際に行ったことを記述させていただきました。
うまくお伝えできたかどうかわかりませんが、
もし、ご参考になれば幸いです。
以上