相続発生から相続税の申告までの流れ

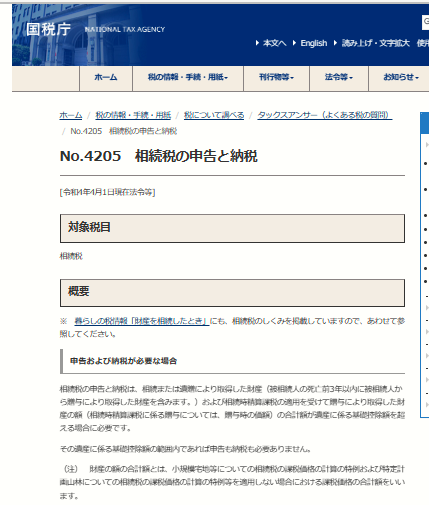
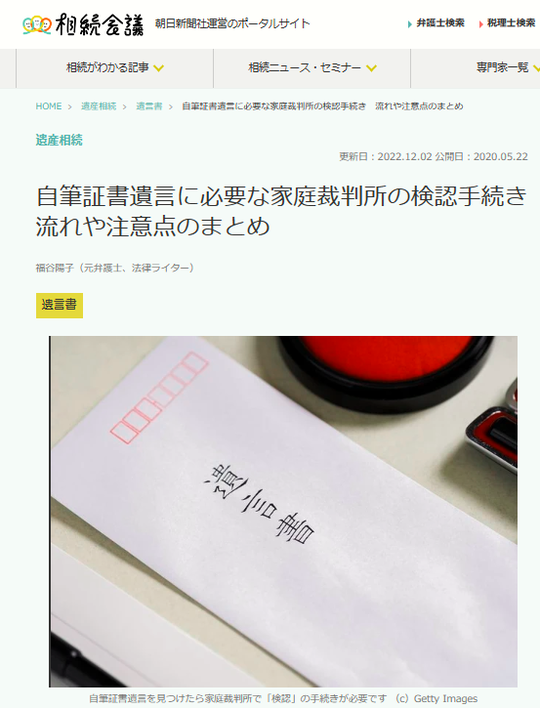
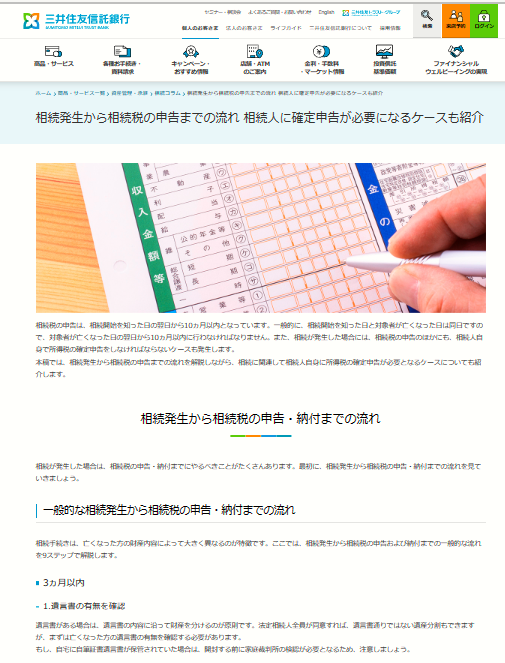
基礎資料
国税庁HP一覧(家の売却・住み替え関係)
{C}① {C}相続発生から相続税の申告までの流れ (三井住友信託銀行)
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/entrustment-column/column-14
{C}② {C}自筆証書遺言に必要な家庭裁判所の検認手続き(相続会議)
https://souzoku.asahi.com/article/13382798
③ No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)
No.4205 相続税の申告と納税|国税庁 (nta.go.jp)
{C}③ {C}遺産分割協議書とは?作成の流れや手続きを解説(三菱UFJ銀行)
https://www.bk.mufg.jp/sonaeru/souzoku/column/003/index.html
はじめに
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内となっています。一般的に、相続開始を知った日と対象者が亡くなった日は同日ですので、対象者が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。また、相続が発生した場合には、相続税の申告のほかにも、相続人自身で所得税の確定申告をしなければならないケースも発生します。
できるかぎり、簡単にわかりやすく、相続発生から相続税の申告までの流れをご案内させていただきます。
一般的な相続発生から相続税の申告・納付までの流れ
相続手続きは、亡くなった方の財産内容によって大きく異なるのが特徴です。ここでは、相続発生から相続税の申告および納付までの一般的な流れを9ステップで解説します。
3ヵ月以内
1.遺言書の有無を確認
遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って財産を分けるのが原則です。法定相続人全員が同意すれば、遺言書通りではない遺産分割もできますが、まずは亡くなった方の遺言書の有無を確認する必要があります。
もし、自宅に自筆証書遺言書が保管されていた場合は、開封する前に家庭裁判所の検認が必要となるため、注意しましょう。
【家庭裁判所の検認申し立てに必要な書類】
検認申立書
①遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類
②相続人全員分の戸籍謄本
(詳しくは、「自筆証書遺言に必要な家庭裁判所の検認手続き(相続会議)」https://souzoku.asahi.com/article/13382798
をご参照願います。)
2.相続財産・負債(債務)の調査
相続財産には、預貯金や有価証券、不動産などプラスの財産だけでなく、借金や未払金、保証債務など、マイナスの財産も含まれます。生前に、亡くなった方が会社経営をしていた場合は、経営法人の連帯保証人になっているケースも考えられるでしょう。
賃貸用不動産を所有して事業を行っていたり、会社経営を行っていたりした場合は、債務の調査が特に重要です。
3.法定相続人を確定させる
亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本などを取得して、誰が法定相続人となるのかを調査し、法定相続人を確定させます。戸籍を出生まで遡っていく際に、別の自治体に本籍がある場合は郵送手続きなどで入手に時間がかかることもあるため、早目に取りかかるようにしましょう。
4.単純承認・相続放棄・限定承認の選択
亡くなった方のすべての権利や義務を引き継ぐ場合は、「単純承認」となります。ただし、負債金額が多い場合は、相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がない「相続放棄」を検討することも必要です。
また、亡くなった方の債務がどのくらいあるのか分からない場合は、相続で得られる財産を限度として債務を引き継ぐ「限定承認」の方法を選択することも可能です。相続放棄や限定承認を選択したい場合は、家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
申し立てをせずに3ヵ月を超えてしまった場合や、相続財産を処分したり、隠匿や消費したりする場合は、原則、単純承認したとみなされるため、注意しましょう。
4ヵ月以内
5.被相続人の所得税の準確定申告をする
亡くなった方に収入があった場合は、亡くなったその年の1月1日から亡くなった時点までの収入を確定申告する必要があります。これを準確定申告といい、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に相続人が行います。
10ヵ月以内
6.相続財産・負債(債務)の確定
亡くなった方のすべての財産を調査して、葬儀費用や負債などを含めた相続財産を確定し、財産目録を作成します。ここで行う調査は、相続税の納税額を計算するベースとなるため、正確に行わなければなりません。
7.相続財産の分割割合を協議し、遺産分割協議書を作成
亡くなった方の遺言書がない場合は、「民法の法定相続割合で分割する」「特定の方が相続財産を多く引き継ぐ」など、分割割合を法定相続人全員で話し合って決めていきます。分割割合が決まった後は、遺産分割協議書を作成し、すべての法定相続人の自署と原則実印(不動産がある場合は必須)の押印が必要です。
8.遺産分割手続きを行う
遺言書にある分割割合・分割方法や、遺産分割協議書に沿って、不動産の名義変更や預金の解約などの手続きを行います。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
実印を押印して全員が1通ずつ所持
遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
なお、遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。慎重に内容を検討して合意する必要があるでしょう。
遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書は下記のような流れで作成します。
遺産分割協議書作成の流れ 1.相続人を確定させる 2.被相続人の財産を確定させる 3.遺産分割協議を行う 4.合意内容を記載した遺産分割協議書を作成する
それぞれの項目についてくわしくご説明しましょう。
1. 相続人を確定させる
遺産分割協議を行うためには、協議に参加する相続人を確定させなければなりません。相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認します。
認知した子どもも相続人となり、遺産分割協議を行う際には参加する必要があります。
相続人の範囲については、「相続は早めに対策を!相続の基礎知識と注意点」をご覧ください。
2. 被相続人の財産を確定させる
相続人を確定させる作業を行うと同時に、被相続人が所有していた財産を調べて確定させます。財産は現金・預金・不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金・ローンといったマイナスの財産もすべて把握することが必要です。
財産が確定したら、財産目録を作成しておくといいでしょう。
また、遺産分割協議の前には、必ず遺言書がないかも確認してください。後で遺言書が出てきた場合、トラブルになる可能性もあるため、注意しましょう。
3. 遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分割して相続するかを話し合います。しかし、遠方に住んでいる相続人や仕事の都合で参加できない相続人もいるかもしれません。その場合は、電話などで意思を確認するなどの方法をとる必要があります。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月後となっていますが、協議を何度も行い時間がかかると、期限に間に合わなくなることもあるでしょう。遺産分割協議では、それぞれの相続人の主張もあり、なかなか決まらないことも多々あります。何度も協議することを想定し、できるだけ早めに財産の特定を行い、遺産分割協議を開始しましょう。
なお、遺産分割協議が相続人の間で合意できなければ、家庭裁判所の調停委員会が加わる遺産分割調停を行います。それでも合意できなければ、家庭裁判所が遺産分割を決める遺産分割審判となります。
4. 合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で遺産分割について合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。
<遺産分割協議書に必要な記載事項>
被相続人の名前と死亡日
相続人が遺産分割内容に合意していること
相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
相続人全員の名前・住所と実印の押印
遺産分割協議書が必要ない場合
遺産分割協議を行う必要がなく、遺産分割協議書も作成しなくてもいい場合もあります。
例えば、相続人が1人であれば、財産を1人がすべて相続することになるため、遺産分割は発生しません。遺言書どおりに遺産分割する場合も、遺産分割協議は不要です。
一方で、遺産分割協議書が必要なかったとしても、トラブルを避けるために作成することもあります。例えば、遺言書がある場合でも、後から遺言に記載されていない財産が発覚することもあるかもしれません。このような場合に備えて、誰がどのように相続するかを協議して、遺産分割協議書を作成しておくという方法もあります。
以上