51 整理解雇の有効性(1)-東洋酸素事件
東京高判昭和4年10月29日(昭和51年(ネ)1028号)
事案の概要
事業部門閉鎖にともなう全員解雇は有効か。
事実
Y会社のアセチレン部門は、競争の激化、需要の低下、人件費の高騰等により、大幅な赤字となり、最終的に、同社のA工場のアセチレン部門は閉鎖されろことになった。そして、Y会社は、他部門への配転や希望退職の募集をしないまま、Xらを含む、A工場のアセチレン部門の従業員全員を、就業規則上の「やむを得ない事業の都合によるとき」という解雇事由に該当することを理由に解雇した。Xら13名は地位保全の仮処分を申請した。1審は解雇を無効と判断してXらの申請をにんようしたため、Y会社は控訴した。
判旨 原判決取消(Xらの申請棄却)
Ⅰ 特定の事業部の閉鎖によもない、その事業部門に勤務する従業員を解雇するについて、それが「やむを得ない事業の都合」nよるものといいうるためには、
第1に、この事業部門を、閉鎖することが企業の合理的運営上やむを得ない必要性のい基づくものと認められること、
第2に、この事業部門に勤務する従業員を同一または遠隔でない他の事業場における他の事業部門の同一または類似の職種のに充当する余地がない場合、あるいはそのような配置転換を行ってもなお全企業的にみて剰員の発生が避けられない場合であって、解雇か特定事業部門の閉鎖を理由に使用者の恣意によってなされるものであること、
第3に、具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであこと、
以上の3個の要件を充足することを要し、特段の事情がない限り、それをもってたりるものと解するのが相当である。
以上の要件を超えて、事業部門の操業を継続するとき、または、事業部門の閉鎖により、企業内に生じた過剰人員を整理せず放置するときは、企業の経営が全体として破綻し、ひいては企業の存在が不可能になることが明らかな場合でねければ従業員を解雇し得ないものとする考え方には、同調することができない。
Ⅱ 整理解雇につき、労働協約又は就業規則上いわゆる人事同意的約款または協議約款が存在するにもかかわらず、労働組合の同意を得ず、または、これと協議を尽くさなかったとき、あるいは解雇がその手続を尽くさなかったとき、あるいは解雇がその手続上信義則に反し、解雇権の濫用にわたると認められるときなどにおいては、いずれも解雇の効力が否定されるべきであるけれども、これらは、解雇の効力の発生を妨げる事由であって、その事由の有無は、就業規則所定の解雇事由の存在が肯定されたうえで検討されるべきものであり、解雇事由の有無の判断にあたり、考慮するべき要素とはならないものというべきである。
解説
経営上の理由により人員削減の手段として行われる解雇を整理解雇という。整理解雇についても、他の解雇と同様、解雇権濫用法理の適用を受けてきたし、現在では、労契法16条の適用を受けることになる。
整理解雇の場合には、とくに次の4つの要件が考慮されてきた。しれは、
第1に、人員削減の必要性があること
第2に、解雇回避の努力をしていること
第3に、被解雇者選定の基準が妥当であること
第4に、労働者側との協議をするなどの手続が相当であることである。
これらは、厳密な意味での法律要素ではなく、権利濫用性の判断要素にすぎないとする裁判例が最近では多い(4要素説。なお第1から第3の要素の主張立証責任は使用者にあり、それが、成功した場合に、労働者が第4の手続要素にゆいての主張立証責任を負うとする裁判例として、東京自転車健康保険組合事件ー東京地判平成18年11月29日等)。
本判決は、本件解雇が就業規則上の「やむを得ない事業の場合」という解雇事由に該当するかの判断として、まず前記の第1の要件から第3の要件に近い要件をあげ、かつ、それで足りるとしている。そのうえで、第4の要件については、解雇事由の有無の判断からは切り離して、独自の手続要件(消極的要件)として考慮するものとしている。
次に4要件の具体的な内容をみていくこととする。
第1に、人員整理の必要性については、「当該解雇を行わなければ、企業の維持が存続が危殆に瀕する程度にさし迫った必要性があること」と述べる裁判例もあった(大村野上事件ー長崎地大村支判昭和50年12月24日)が判旨Ⅰでは、このような考え方を否定している。
第2に、解雇回避努力については、本判決は、他部門への配慮転換をしなかったことや、希望退職者を募集しなかったことについて、使用者のマイナスには考慮していない(判旨外)。ただ、配置転換や希望退職された裁判例はすくなくない(あさひ保菊園事件ー最1小判昭和58年10月27日等を参照)。
第3に、被解雇者選定基準の妥当性については、本判決は、アセレン部門は他の部門から独立していたということを理由に、アセレン部門の閉鎖により、同部門の従業員全員を整理解雇の対象とすることは合理性を欠くものではないと判断ている(判旨外)。
第4に、労働者側との協議については、本判決は、Y会社は、労働組合と十分な協議を尽くさないで部門閉鎖と解雇を実行したが、事前協議に関する労働協約の規定がなかったことや、アセレン部門の将来が楽観を許さないことなどを事前に伝えていなかったことから、労使間の信義則に反するものではなかったと判断している(判旨外)。ただ、この判断については、解雇におけるて続を軽視しているとの批判もかのうであろう。
労契法16条(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
52 整理解雇の有効性(2)-千代田化工建設事件
東京高判平成5年3月31日(平成4年(ネ)1286号)
事案の概要
分社化にともなう転籍を拒否した労働者に対する解雇は有効か
事実
Xは、石油等の産業用設備の設計、設置、管理等を目的とするY会社のA工場に溶接工として勤務するものである。Y会社は、経営があっかしてきたことから、それに対応するために、まずA工場を分社化して、そこで働く従業員を移籍させることとした。この移籍に伴い賃金は30%減額されたが、退職金は加算され、これらの措置(第1次非常時対策)について、労働組合との協定も締結してしていた。この移籍には、A工場の技能従業員175名のうち、168名が移籍に同意し、6名が移籍に同意せず、退職を希望し、Xだけが、移籍を拒否して残留を希望した。そのため、Xは本社人事課に配属されることになった。
その後、Y会社は余剰従業員を移籍することにしたが、Xは移籍も拒否した。Y会社の人事部長のBは、Xと6回にわたり面談をし、その間に、Y会社内でXを活用できるポストを探したが、見つからず、また、Xの従来なみの処遇でできる仕事を同業他社や職業安定所に照会したが、適当な仕事は見つからなかった。そこで、Y会社はXを解雇したところ、Xは解雇は無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めて訴えを提起した。1審はXの請求を認容したため、Y会社が控訴した。
判旨 控訴棄却(Xの請求認容)。
Y会社の規模、経営内容からして、Xを直ちに解雇しなければならない切迫性、緊急性があったとは認め難い。そううすると、本件解雇の正当性は、他の移籍に応じた者との人事の公平を図ることにある。
たしかに、移籍の対象となった技能系労働者は、希望退職者を除き、すべてが、賃金の低下を受け入れて移籍におうじたのに、Xだけ従前の賃金を維持したまま居続けるのことは、不公平と映る面があるかもしれない。
しかし、もともと同意による移籍は、労働者と旧使用者との合意解約と新使用者との労働契約の締結であり、人員削減の相当の必要がある場合にかぎり、使用者の一方的意思表示により認められる整理解雇とは本質的に異にするから、単に移籍者と移籍に同意しないものとの待遇を比較し、その均質化のために整理解雇が許容されるということにはならない。
たしかに、移籍に応じない場合はそうなるかという労働者の質問に対して、Y会社の側で、その場合は社内に仕事がないので、社外で仕事を見つけてもらうほかない、などど暗に解雇を示唆した発言をしていたことも認められる。しかし、整理解雇の場合は、その認められる要件が条理上厳格にせいげんされるのであり、使用者の側で移籍に応じない者は解雇することをほのめかしてたからといって整理解雇の要件が何ら緩和されるものではないし、逆にそのような状況の下でXの側で移籍を拒否することが労働契約上の信義にもとり、被用者としての権利を濫用するものだると認め難い。なぜなら、業務縮小などにともなう整理解雇が許容される要件は、客観的に定まるのものであって、労働者として移籍か解雇かの二者択一を迫られるものではないからである。
以上より、本件解雇は、いわゆる整理解雇の要件を満たしておらず、解雇権を濫用したものとして無効である。
解説
整理解雇の4要件(要素)の1つである解雇回避の努力については、それがどこまで求められるかはケース・バイ・ケースの判断になる(→【51】東洋酸素事件)。配転や出向により解雇を回避できる具体的な可能性(その判断は企業規模や労働者の職種などによって異なりうる)があれば、使用者はそれを試みることが求められると解するべきである。一方、いわゆる限定正社員(勤務地限定正社員や職種限定正社員)に対しては、使用者は、その限定された勤務地や職種の範囲でしか、解雇回避の可能性を模索する必要がないのが原則である(ただし、勤務先を限定して採用された労働契約でも、転勤の可能性を検討する必要があるとした裁判例として、シンガポール・デベロップメント銀行事件ー大阪地判平成12年6月23日等)。いずれにせよ、使用者が配転や出向を打診したことは、労働者がその申し出を拒否したとしても、解雇回避努力の一環として使用者に有利に考慮されるべきであろう。
なお、就業規則等により、根拠づけられている配転命令や出向命令を、労働者が拒否した場合には、命令が有効であれば通常は懲戒処分の対象になる。
転籍については、労働者の個別的同意が必要とされている。(→【39】三和機材事件)が、同意を拒否して解雇された場合、使用者が転籍を打診したことは、やはり解雇回避努力の一環として使用者に有利に考慮されるべきであろう。Y会社の経営状況とも考慮すると、本判決の結論は、Y会社にやや酷と思われる。
53 整理解雇の有効性(3)-日本航空事件
東京高判平成26年6月3日(平成24年(ネ)3458号)
事案の概要
会社更生手続下でなされた整理解雇の有効性は、そのようにはんだんすべきか。
事実
Xら(71名)は、航空運送事業を業とするY会社の前身であるA会社と期間の定めのない労働契約を締結した客室乗務員であり、B労働組合の組合員であった。(A会社には、このほかC労働組合などがあった)が、A会社は、平成22年1月19日に会社更生法手続が開始されて、平成23年3月28日に同手続が終結した。
その間に、Xらは平成22年12月9日、同月31日付けで整理解雇される旨の解雇予告通知を受けた。同様の解雇は、運航乗務員の機長ないし副操縦士に対してもなされた。Xらは、この解雇が無効である旨を主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めて、訴えを提起した。原審は、Xらの請求を棄却した(東京地判平成24年4月30日)。そこで、Xらは控訴した(運航乗務員も同様の訴えを提起し、東京地判は棄却判決を下している「東京地判平成24年3月29日)。なお、本判決に対して、Xらは上告したが、棄却・不受理となっている(最2小決平成27年2月4日)。
判旨 控訴棄却(Xの請求棄却)
Ⅰ(1)「会社更生法手続は、・・・・事業の継続を前提としており、更生管財人が継続する事業において労働契約上の使用者としての地位を承継するものであること、・・・・更生管財人が、労働契約法などの規定の定める要件によらずに労働契約を解除することができる旨を定める法の規定がないことからすれば、更生手続の下で更生管財人がした整理解雇についても、労働契約法16条が適用されるものと解され、・・・・いわゆる整理解雇法理も適用されるものと解するのが相当である」。
(2)「いわゆる整理解雇法理における人員削減の必要性という要素は、解雇の時点において、破綻に至っていない企業の場合においては、債務超過や赤字の累積など高度な経営上の困難から人員の削減が必要であり、企業の合理的な運営上やむを得ないものとされるときには、これが存在すると解されるのである。これに対し、更生会社であるY会社の場合においては、・・・・本件解雇前、いったんは破綻状態にあって、その債権者及び取引先に対する取引上の信頼が失われた状態に陥っており、更生会社の事業の維持更生を目的とする会社更生法(同法1条)に基づく本件会社更生法手続開始決定がなされ、同法に基づく手続によって、本件、更生計画が債権者らの同意を得て、可決されて裁判所に認可され、本件更生計画が遂行されて事業の維持更生が図られることがなければ、破綻が避けられなかったのであって、同法に基づく更生計画案は、更生会社の当面の破綻を回避するにとどまらず、破綻原因を除去して更生計画を確実に遂行することができる業務体制の確立を図るものとして、そのために必要な諸施策を織り込んで作成することが同法の目的に適うものであることに十分配慮した上で、上記人員削減の必要性の要素を判断するのが相当である」。
ⅡXらに対する解雇は、「更生会社であるY会社を存続させ、これを合理的に運営する上でたむを得ないものとして、その人員削減の必要性が認められる」こと「一連の希望退職措置を講ずるなど十分な解雇回避努力を行ったこと、その対象者の人選が合理性の認められる本件人選基準に基づいて客観的、合理的に行われたことが認められ」ろこと、また、「解雇の手続においても、Y会社からXらの所属するB組合を含む従業員の所属労働組合に対する多数回の協議と説明をしており、C組合からの指摘に応じて本件人選基準案の内容の一部を変更して本件人事案を策定するなど、手続的相当性をそなえていることが認められ、整理解雇が許されないものと評価するに足りるような事情は認められないというべきである」。
解説
倒産手続には、清算型と再建型とがあるが、本件のような会社更生手続は後者である。清算型手続(および通常の会社解散)において、労働者が解雇される場合、整理解雇の4要件(要素)が適用されるかについては議論がある(適用を認めても、4要件をそのままてきようすべきでないとする考え方が多数である)が、少なくとも再建型手続の場合には、事業の継続が前提となるので、整理解雇の4要件(要素)をそのまま適用すべきとする見解が一般的である。本判決の判旨Ⅰ(1)もこの立場である。
そのうえで、判旨Ⅰ(2)は、人員削減の必要性の要素に関する判断は、会社更生手続下では、それ以外の場合と異なり、更生計画を確実に遂行するための必要な諸施策として合理的であるという観点からなされるべきものとしている。
したがって、事後的な経営改善などにより人員削減の必要性が軽減したかどうかは考慮されないことになり、本件でも結論として必要性が肯定された。ただ、こうした判断は、政府の強い介入による再建という本件の特殊性によるとみることもできよう。
なお、運航乗務員の控訴も棄却され、上告も棄却・不受理となっている(東京高判平成26年6月5日、最1小判平成27年2月5日)。
労働契約法16条(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
会社更生法1条(目的)
第一条 この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
54 解雇期間中の賃金と中間利益-いずみ福祉会事件
最3小判平成18年3月28日(平成15年(受)1099号)
事案の概要
解雇期間中の得べかりし賃金から、同じ期間内に他で働いて得た賃金はどこまで控除できるか。
事実
Xは、Yに雇用されていたが、平成11年5月18日に解雇された。そこで、Xは解雇が無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と、解雇後の賃金についての支払いを求めていった絵を提起した。1審および原審は、解雇を無効と判断し、解雇後の賃金は一部のみ認めた。
平成11年5月19日から同14年12月31日までの期間において、Xに支払われるべきであった賃金総額は、次のとおりである。まず、平成11年5月19日から同年13年4月30日までの間(本件期間)において、Xに支払われるべきであった月例賃金(本棒ぴよび特殊手当)の合計額は552万2346円であり、期末手当等の合計額は249万⑦060円である、本件期間のうち、平成11年9月から同13年4月までの間(就労期間)は、Xは他で就労して、合計358万①23円の収入を得ていた。本件期間で支払われるべきであった月例賃金のうち、就労期間に対応するものは、合計480万②040年である(労基法12条1項所定の平均賃金の合計額も同額)。
就労期間以外の期間に対応するものは72万306年であり、期末手当等のうち、就労期間に対応するものは合計196万8836円であり、就労期間以外の期間に対応するもの52万8224円である(平成13年5月1日から同14年12月31日までの期間については省略)。
1審および原審ともに、就労期間における月例賃金と期末手当等の合計額677万876円の4割が控除の限度額であるとした。そこで、Yは上告した。
判旨 原判決破棄、自判
Ⅰ「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益(以下「中間利益」という。)を得たときは、使用者は当該労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除することができるが、上記賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。したがって、使用者が労働者に対して負う解雇期間中の賃金支払債務の額のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支払対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されないものと解すべきであり、上記中間利益の額が平均賃金の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(同条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されると解される」。
ⅡXに支払われるべきであった就労期間の賃金の合計額480万2040円のうち、平均賃金の合計額の6割に当たる288万1224円は、そこから控除をすることが禁止され、その全額がXに支払われるべきである。残りの192万8ア6円については、就労期間中のXの中間利益の合計358万123円をまず控除することとなるので、支払われるべき金員はない。さらに、中間利益のうち192万816円については、就労期間中のXの中間利益の合計358万123円をまず控除することとなるので、支払われるべき金員はない。さらに中間利益のうち192万816円を控除してもなお残っている165饅307円については、これを、Xに支払われるべきであった就労期間における期末手当等の合計額196万8836円から控除すべきである。したがって、上記期末手当等は、合計30万9529円が支払われることとなる。結局、Yは、Xに対し、就労期間に係る賃金として288万1224円と、期末手当等のうちの30万9529円との合計額319万753円を支払うべきこととなる。Yは、これに加えて、本件期間のうちの就労期間に対応しない期間の月例賃金(72万306円)と期末手当等(52万8224円)も支払われなければならない。
解説
裁判所において解雇が無効と判断された場合における解雇期間中の賃金は、使用者は、原則として全額、労働者に支払わなければならない(民法536条2項1文)が、労働者が解雇期間中に他から収入を得ていた場合には、その中間利益(中間収入)は控除される(同条2文)。ただし、労基法26条の趣旨から、中間利益の額にかかわらず、平均賃金の6割は支払わなければならない(米軍山田部隊事件ー最2小判昭和37年7月20日)。
また、賃金か控除される中間利益は、「当該賃金の対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益」でなければならない(判旨Ⅰ。あけぼのタクシー事件ー最1小判昭和62年4月2日)。他方、以上のルールの下で控除しきれなかった中間利益の残余分については、平均賃金の算定基礎外の賃金(賞与等)から、やはり支給対象期間と時期的に対応する分が控除される(判旨Ⅰ。前掲・あけぼのタクシー事件も同旨)。
労基法12条1項
第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
労基法26条 (休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
民法536条2項1文(債務者の危険負担等)
第536条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
55 解雇と不法行為-吉村・吉村商会事件
京地判平成4年9月28日(平成3年(ワ)10231号)
事案の概要
解雇された労働者が、解雇の有効性を争わずに、不応行為による損害賠償を求めるころができるか。
事実
Xは、Y会社を懲戒解雇されたため、本件解雇がなければ少なくとも本件解雇後1年間は、Y会社で勤務を継続して賃金を得ていたはずであるとして、解雇後1年間に相当する賃金額の損害賠償請求等を求めて訴えを提起した。
判旨
損害賠償請求については一部認容(慰謝料40万円のみ認容、賃金分の損害の請求は棄却)。
Ⅰ「理由のない解雇がなされ、それが、労働者に対する不法行為を構成する場合、当該労働者が使用者に対して被った損害の賠償を求めることができるのは当然である。・・・・賃金は、雇用契約に基づく労働者の義務の履行、すなわち、労務の提供に対する対価として支払われるものであるから、使用者が違法な解雇の意思表示をして労働者による労務の提供を受けることを拒否する態度を明確にした場合であっても、労働者が賃金の対価にたる労務提供の意思を喪失するなどして使用者の労務受領拒否の態度がなくなっても、労務を提供する可能性が存在しなくなったときには、賃金不請求状態が当該解雇を原因とするものとはいえないことになるのであり、その場合は、当該賃金不支給は当該不法行為と相当因果関係のある結果とはいえない。
Ⅱ「当該解雇が不法行為を構成する違法なものであって、また、無効と解される場合には、当該労働者は、解雇無効を前提としてなお労務の提供を継続する限り、賃金請求を失うことはない。この場合には、当該労働者は賃金請求権をを有しているのであるから、特段の事情がない限り、右賃金請求権の喪失をもって損害とする余地はないことが明らかである。他方、当該解雇に理由がない場合であっても、当該労働者がその解雇を受け入れ、他に就職するなどして当該使用者に対し、労務を提供し得る状態になくなった場合には、前示のとおり、賃金が支給されない状態と違法な解雇との間には、相当因果関係がないから、賃金相当額をもって、直ちに違法解雇賀なければ、得べかりし利益をもって、直ちに違法解雇がなければ得べかりし利益として、その賠償を求めることはできないことになる。
Ⅲ 本件では、Xは解雇の有効性を争っておらず、Y会社に愛想をつかして確定的に他に就職しているので、少なくともその就職の時点で、XのY会社に対する労務提供の可能性は失われたものといわなければならず、他方、その就職までの期間は賃金請求権があるものというべきであるから、いずれについても賃金請求権の喪失を理由とする賃金相当額の賠償請求は失当である。
解説
使用者が不当な解雇をした場合には、その解雇は権利濫用したものとして無効となる(労契法16条)。では、原職復帰を望まない労働者が、解雇無効を主張せずに、退職することを前提に、不法行為を理由として、将来分の賃金の損害賠償請求をすること(民法709条)は認められるのであろうか。
不法行為が成立するためには、解雇が権利濫用というだけでは不十分であり、不法行為の要件を充足する必要があるが、仮に不法行為が成立したとしても解雇が無効である以上、労働者は賃金請求権を有する(民法536条2項)ので、賃金分についての損害は(逸失利益)は発生していないことになる。(判旨Ⅱ)
また、他に就職するなど、解雇後において使用者に対して労務を提供しうる状態になくなった場合にも違法な解雇と賃金の不支給との間には、相当因果関係がないので、やはり、逸失利益は否定される(判旨Ⅰ、Ⅱ)
もっとも、裁判例の中には、その場合でも一定期間の賃金相当額を逸失利益と認めるものがある(三枝宇治事件ー東京地判平成23年11月25日(3か月分)、学校法人村上学園事件ー東京地判平成24年7月25日(3か月分から中間収入を控除)、カワサ事件ー福井地判平成26年5月2日(採用内定取消しのケースで再就職までの約9か月分)等)。
このほか、違法な退職の強制等、客観的に復職ができない事情があったために解雇を受け入れたという場合(合意解約と判断される可能性もある)には、逸失利益が認められる余地はあるし、解雇事由が生じてからの使用者の対応(解雇回避の努力の程度や解雇の告知に至るまでの手続等)に問題があったような場合には、慰謝料の請求が認められることがある。本件でも、精神的損害は認められた(なお地位確認請求も同時に行っている事件では、地位確認が認められ、賃金が遡及的に支払われた場合には、精神的損害は慰謝されているとして、慰謝料の請求が認められない傾向にある。→【103】トーコ事件等)。
労契法16条(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法536条2項(債務者の危険負担等)
第536条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
56 解雇制限期間と打切補償-学校法人専修大学事件
最2小判平成27年6月8日(平成25年(受)2430号)(民衆69巻4号1047頁)
事案の概要
労災で休業中の労働者に打切補償相当額を支払うことにより解雇は可能となるか。
事実
学校法人Yの職員であるXは、頸肩腕症候群に罹患し、平成15年4月より欠勤を繰り返すようになった。Y法人は、Xの欠勤のうり、当初のものは有給休暇として処理し、同年6月3日からは、就業規則所定の私傷病による休職として処理した。その後、Xは復職したが、平成18年1月17日から長期欠勤をし、平成19年3月31日にいったん退職した。同年11月6日に、A労基署長は、Xの疾病を労災と認定し、療養補償給付の支給を決定した。これを受けて、Y法人はXの退職を取り消した。
Y法人は、平成21年1月17日、Xが長期欠勤を開始した平成18年1月17日以降の欠勤がY法人の災害補償規定所定の欠勤年数3年を経過したことから、Xを2年間の業務休職に付した。
平成23年1月17日、休職期間である2年が経過し、Y法人は、Xの職場復帰は不可能であると判断したことから、同年10月24日、Xに災害補償規定の定める打切補償として約1629万円を支給したうえで解雇した。
Y法人は、この解雇が有効であるとして、労働契約上の権利を有する地位の不在確認を求めて本訴を提起したところ、Xは、自らが労基法81条所定の「第75条の規定によって補償をうける労働者」に該当せず、したがって、解雇は労基法19条に反して無効であるとして、労働契約上の権利を有する地位の確認および損害賠償等を求めて反訴を提起した(その後、Y法人は本訴を取り下げた)。1審は、Xの制空をほぼ認容し、原審はY法人の控訴を棄却した。
判旨 原判決破棄、差戻し。
Ⅰ労災保険法は、労基法と同日に公布、施行され、その定める各保険給付は、労基法で使用者が災害補償を行うべき事由が生じた場合に行われるとされ、さらに、労基法84条1項が、労災保険法の各保険給付の内容は、労基法上の使用者の災害補償の内容に対応するものとなっている。
以上のことからすると、労災保険法上の保険給付は、その実質は、使用者の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであり、労基法上の災害補償に代わるものということができる。
Ⅱ Ⅰからすると、使用者により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合とで、労基法19条1項ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、打切補償がなされても、治るまでの間は労災保険法に基づき療養補償給付がされることなども勘案すれば、同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
Ⅲ そうすると、労災保険法上の療養補償給付療養補償給付を受ける労働者は、労基法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるとみるのが相当である。
解説
労基法19条は、業務上の負傷または疾病により療養のために休業する労働者に対する解雇を禁止している。ただし、同法81条に基づく打切補償が行われれば、この解雇制限は解除される(同法19条1項ただし書)。ところで、同法81条は、同法75条による療養補償を受ける労働者を対象としたものであるが、労基法上の災害補償給付は、労災保険によって代替されており、本件でもXは労災保険の療養補償給付を受け、労基法の療養補償は受けていなかった(同法84条1項)。一方、労災保険法においては、傷病補償年金が支給される場合には、療養開始から3年経過していれば、労基法81条の打切補償がされたものとになされ、解雇制限が解除される(労災保険法19条)。傷病補償年金は、療養の開始後、1年6か月経過後、治癒せずに、傷病等級3級以上の重度の者に支給される(同法12条の8第3項)。
治癒(症状固定)の場合には、療養は終了するので、解雇制限は解除されるし、治癒していないが、重度の傷病の場合には傷病補償年金に移行するので、やはり解除制限は解除される。一方、本件のように、治癒していないが、傷病の程度が重くない場合には、療養補償給付が継続支給される。このような場合に、労基法81条の定める3年経過後の打切補償によって、解雇制限解除できるのかが問題となる。
本判決は、この問題について、原審の判断を覆して、療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労基法75条による療養補償を受ける労働者が前記の状況にある場合と同様、使用者は、同法81条による打切補償の支払いをすることにより、同法19条1項ただし書きの適用を受けることができるとして、この問題に決着をつけた。
労基法81条(打切補償)
第81条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
労基法75条(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
労基法19条(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
労基法84条1項(他の法律との関係)
第84条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
② 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
労災保険法19条 〔労働基準法との関係〕
第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
〔介護補償給付〕
第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
労災保険法12条の8第3項 〔業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由〕
第12条の8 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付
② 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条 から第七十七条 まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項 、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項 にあつては、労働基準法第七十六条第一項 に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。
③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
④ 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項 に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
三 病院又は診療所に入院している間
57 労働基準法20条違反の解雇の効力-細谷服装事件
2小判昭和35年3月11日(昭和30年(オ)93号)(民衆14巻3号403頁)
事案の概要
解雇予告規定に違反して行われた解雇は有効か
事実
Y会社は、その雇用するXに対して、昭和24年8月4日に、予告手当を支給することなしに一方的に解雇の通告をした。その後、1審の口頭弁論の終結日である昭和26年3月19日に至り、昭和24年8月分の給料1万円と予告手当の額として給料1か月分に相当する1万円に当日までの遅延利息を加算した額をXに対して支払った。Xは、解雇の効力は、昭和26年3月19日までは生じなかったと主張して、昭和24年8月分から、昭和26年3月分までの賃金の未払分の支払い等を求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、Xの請求を棄却したため、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)。
Ⅰ「使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず、または予告期間の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇には考慮を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、または、土の後に同条所定の予告手当の支払いをしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであって、本件解雇の通知は30日の期間経過と共に解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である。」
Ⅱ「労働基準法114条の附加金支払い義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に、当然発生するものではなく、当労働者の請求により裁判所がその支払いを命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払いを完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同条による附加金請求に申立をすることができないと解すべきである」。
解説
労基法20条は、使用者が解雇を行う場合には、30日前までの予告が30日分以上の平均賃金(予告手当)を支払うことを義務づけている。(20条1項。予告手当を支払えば、予告日数を減少させることができる。同2項)。例外は、天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由がある場合(除外事由)である(20条1項ただし書。なお、解雇事由の適用除外については21条)。
労基法20条に違反して行われた解雇については、同条は強行法規なので無効とする見解(無効説)、同条違反の場合には、労働者には予告手当とは付加金(114条)の請求権が認められていることからすると、解雇そのものは有効と解すべきとする見解(有効説。もちろん、そのときでも解雇権の濫用として、無効となる余地はある)、労働者側で、解雇の無効か予告手当の請求かを選択できるとする見解(選択権説)があるが、判例は、判旨Ⅰで示されたとおり、即時解雇としての効力は生じないが、即時解雇に固執する趣旨で無ければbあ、30日の経過後か、予告手当の支払のいずれかの時から、解雇の効力が生じるとした(相対的無効説。行政解釈(昭和24年5月13日基収1483号)も同じ)。
有効説には、労基法20条だけの強行法規が性が否定される理由がはっきりしないという難点があるが、他方で、無効説は、予告期間をおかない場合に、予告手当(および付加金)の支払いが義務づけられていることの説明に窮する。判例の相対的無効説(判旨Ⅰ)は、両の難点を克服しようとしているが、即時解雇に固執する趣旨かどうかの判断は容易でないし、即時解雇に固執する趣旨でないとされれば、30日の経過後に解雇の効力が発生するので、そうなると予告手当も(就労していない以上は)賃金も支払われない(常に使用者の責めに帰す事由が認められるとはいえないだろう(民法536条)という労働者にとって酷な結果が生じるという問題点もある。そこで、選択権説が出てくるが、この見解には、労働者が選択権を行使するまで、解雇の効力が確定しないという問題点もある。
本判決は、労基法114条に基づく付加金の支払義務は、予告手当の支払義務違反があったときに発生するのではなく、裁判所の支払命令があったときに発生するとする(判旨Ⅱ)。なお、本判決によると、労働者が予告手当(割増賃金等も同じ)の支払を求める訴えを提起しても、支払いを命じるまで(訴訟手続上は事実審の口頭弁論終結時まで)に、使用者がそれを支払えば、裁判所はもはや付加金の支払を命じることはできないこととなる(ホッタ晴信堂薬局事件ー最1小判平成26年3月6日)。
労基法20条(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
労基法21条
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
労基法114条(付加金の支払)
第114条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
民法536条2項(債務者の危険負担等)
第536条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
58 変更解約通知の有効性ースカンジナビア航空事件
京地決平成7年4月13日(平成6年(ヨ)21204号)
事案の概要
新しい労働条件での雇用契約の締結の申込みを拒否したことを理由とする雇用契約の解約は有効か。
事実
外資系の航空会社であるY会社は、業績の急速な悪化のなかで、エア・ホステスと地上職の人員を削減することが必要であるとし、日本支社で早期退職者を募集し、その後、必要な人員のみ再雇用することにした。再雇用の際の労働条件は、これまでの賃金体系、労働時間、退職金制度等が変更され、労働契約の期間を1年とするという内容であった。
全従業員140名のうち、115名が早期退職に応じたものの、25名が応じなかった。そのためY会社は、この25名に対して解雇を通告した。その後、Y会社は、18名には再雇用の申入れをし、9名はこれに講じたため、解雇は撤回されたが、Xらを含む残り9名はをそての応じなかった。そこで、Y会社は、Xら9名を解雇した。そこで、Xら9名は、この解雇は無効であるとして、従業員たる地位の保全と賃金の仮払いを求めて仮処分を申請した。
判旨 申立て却下。
Ⅰ Y会社のXらに対する解雇の意思表示は、「雇用契約の特定された職種等の労働条件を変更するための解約、換言すれば、新契約締結の申込みをともなった従来の雇用契約の解約でであって、いわゆる変更解約告知といわれるものである」。
Ⅱ「労働条件の変更が会社業務の運営にとって必要不可欠であり、その必要性が労働条件の変更によって労働者が受ける不利益を受ける不利益を上回っていて、労働条件の変更にともなう新契約締結の申込みがそれに応じない場合の解雇を正当化するに足りるやむを得ないものと認められ、かつ、解雇を回避するための努力が十分に尽くされているときは、会社は新契約締結の申込みに応じない労働者を解雇することができるものと解するのが相当である」。
解説
1変更告知者は、労働条件の変更は申込みと解雇の意思表示が同時に含まれるものである。その具体的な態様はさまざまである。典型的な例は、労働条件の変更の申込みに応じないことを停止条件として解雇の意思表示が行われているというものである。本件は、このタイプとは異なり、「新契約締結の申込みをともなった従来の雇用契約の解約」が行われており、本決定は、これも変更解約告知に含まれると述べている(決定要旨Ⅰ)
変更解約告知は、労働条件の変更に応じなければ解雇となる。他方で、労働条件の変更に応じれば、雇用が継続することになるが、これは実質的に対して解雇の脅威の下で、労働条件の変更を迫るという面もある。その意味で、変更解約通知は、使用者が労働条件の変更を進めるための手段ということになる。
したがって、変更解約通知については、変更を拒否したことを理由とする労働者に対する解雇が有効となるのか(解雇としての相当性)、解雇の脅威の下における変更の承諾は、有効となるのか(労働条件変更手段としての相当性)が問題となる。
2 変更解約告知の解雇としての有効性については、従来、解雇権濫用法理(現在の労契法16条)の下では、消極的に解されていた。有効性の判断枠組みを設定しているが、その判断基準は、変更が会社業務の運営にとって必要不可欠であること、必要性が不利益を上回っていること、解雇回避努力が尽くされたいることなど、かなり厳格なものである(決定要旨Ⅱ)。本決定は、結論として、業務上の必要性が高度であり、不利益の程度は。それほど大きくなく、労働組合との交渉が十分に行われているという事情を重視して解雇を有効と判断した(決定要旨外)が、同時に行われていた、再雇用の申入れがなかったり7名に対する整理解雇も有効と判断しており、事案の性質上、変更解約告知が有効と認められやすいケースであったといえよう。
なお、裁判例の中には、変更解約告知という独自の類型を認めることに消極的で、通常の整理解雇と同様の基準で有効性を判断すべきと述べるものもある(大阪労働衛生センター第一病院事件ー大阪地判平成10年8月31日)。
3 変更告知者は、実質的には労働条件の一方的な変更と変わらない面があるので、労働条件変更手段として不適切であり、ドイツ法を参考にした「留保付き承諾」を認めるべきという見解もある。「留保付き承諾」とは、使用者による労働条件の変更の申込みに対して、裁判所等の第三者機関が変更内容を相当と認めるという条件を付けて承諾することである。第三者機関が相当と認めれば、労働条件の内容は変更され、相当と認めなければ、労働条件の内容は従来のままとなる。いずれにしても、解雇という結果は生じない。
日本の現行法上、使用者に「留保条件付き承諾」が認められるかついては、「留保付き承諾」を認める判断をして裁判例もあった(日本ヒルトン事件ー東京地判平成14年3月11日)が、その判断は控訴審で否定されている(東京高判平成14年11月26日)。
労契法16条 (解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
59 退職の意思表示の撤回ー大隅鐵工所事件
最3小判昭和62年9月18日(昭和57年(オ)327号)
事案の概要
労働者は、退職の意思表示を、いつまでなら撤回することができるか。
事実
Xは、大学在学中に日本民主青年同盟(民青)に加盟しており、昭和47年4月にY会社に入社した後も、同期入社のAとともに、Y会社内の民青の同盟拡大等の非公然活動に従事していた。あるとき、Aが失跡し、Y会社側の調査によって、AとXとの関係が判明したので、Xは連日Y会社の人事担当者からAの失跡に関し、事情聴取を受けた。その後、Y会社の人事管理の最高責任者である人事部長Bは、人事第1課長Cと人事第2課長Dとともに会社の応接室でXと面接し、その席上で、民青資料を机の上に置きながら、「この記事の中からAの手掛かりが出てこないか、君ひとつ見てくれないか」と申し出たところ、Xは、突然「私は退職します。私はAの失跡と全然関係ありません」と申し出た。
B部長は、Xを慰留したが、Xがこれを聞き入れなかったので、C課長に命じて、退職願の用紙を取り寄せ、Xに、交付したところ、Xはその場で必要事項を記入して署名拇印してB部長に提出し、B部長はこれを受け取った。その後、Xは退職手続を撤回したが、Y会社はこれを拒否したため、XはY会社の従業員たる地位の確認を求めて訴えを提起した。
1審はXの請求を認容し、原審はY会社の控訴を棄却した。そこで、Y会社は上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し。
原判決は、B部長がXの退職願を即時受理したことをもって、「Xの解約申込みに対するY会社の承諾の意思表示があったものと解することができないとしているが、その理由とするところは、「Xの入社するに当たっては、筆記試験の外に面接試験が行われ、その際E福社長、技術系担当取締役2名及びB人事部長の4名の面接委員からそれぞれ質問があり、これらの結果を総合して採用が決定されたことが認められる。この事実と対比するとき、Xの退職願を承認するに当たっても、人事管理の組織上一定の手続を履践した上Y会社の承諾の意思が形成されるものと解せられるのであって、人事部長の職にあるものであっても、その個人の意思にみによってY会社の意思が形成されたと解することはできない」というに尽きる」。
原判決の上記判断は、「企業における労働者の新規採用の決定と退職願に対する承認が企業の人事管理上同一の比重を持つものであることを前提とするものであるが、この前提を採ることは、たやすく是認し難いものといわなければならない。けだし、Y会社において原判決が認定するような採用制度をとっているのは、労働者の新規採用は、その者の経歴、学識、技能あるいは性格等について会社に十分な知識がない状態において、会社に有用と思われる人物を選択するものであるから、人事部長に採用の決定権を与えることは必ずしも適当でないとの配慮に基づくものであるのに対し、労働者の退職願に対する承認はこれと異なり、採用後の当該労働者の能力、人物、実績等について掌握しうる立場にある人事部長に退職承認についての利害得失を判断させ、単独でこれを決定する権限を与えることとすることも、経験則上何ら不合理なことではないからである」。
解説
労働者からの退職の意思表示の法的意味については、辞職の意思表示と合意解約の申込みの意思表示の2つの考えられる。辞職は労働者による労働契約の解約であり、期間の定めのない労働契約の場合には2週間の予告期間を置けば自由に行うことができ(民法627条)、期間の定めのある労働契約の場合には、やむをえない事由があれば直ちに解除できる(民法628条)。辞職は単独であり、その意思表示が使用者に到達すれば、効力が発生するので、それ以降の撤回は不可能となる。一方、合意解約の申込みについては、使用者の承諾の意思表示が労働者に到達すれば、それにより、労働契約の解消の効果が発生することになる。合意解約の申込みは、辞職と異なり、使用者に到達していても、使用者が承諾するまでは原則として、撤回が可能と解されている(学校法人白頭学院事件ー大阪地判平成9年8月29日を参照。
この点で、合意解約のほうが労働者に有利となるので、合意解約の申込みか辞職か、いずれの意思表示かがはっきりしない場合には、前者と解すべきであろう)。
この場合には、使用者側の誰に承諾権があるかが重要となり、本件の事実関係では、B部長に退職承認の決定権があって、B部長の即時承諾により合意解約が成立したと認定しうる可能性が高い事案であったといえよう(原審には、この点についての経験則違背があるとされ、事件では差し戻された)。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
60 退職勧奨の適法性ー日本アイ・ビー・エム事件
東京高判平成24年10月31日(平成24年(ネ)763号)
事案の概要
退職勧奨は、どのような場合に違法となるか。
事実
情報システムに係る製品、サービスの提供等を業とするY会社は、業績が低迷するなか、リーマン・ショックの影響も受けて、従業員の退職勧奨を行うことにした。この退職勧奨においては、
①所定の退職金に加えて、加算金(特別支援金)として、月額給与額の最大で15か月分を支給する、
②自ら選択した再就職支援会社から再就職支援を受ける、
という特別支援プログラムを用意し、それを実施するためのRAプログラムを立ち上げた。Y会社は、RAプログラムへの応募勧奨が退職強要にならないように、実施担当の管理職に対して、具体的方法についての講義や面接研修を実施していたが、他方で自覚と責任を持たせるため、応募予定者の達成いかんでは、結果責任を問う趣旨とも受け取れる注意喚起を行っていた。
Y会社の従業員であるXは、平成18年3月、うつ病を発症し、平成20年1月以降、在宅勤務をしていた。なお、Y会社の定年は、60歳でXの60歳の誕生日は、平成22年5月29日であった。
Xは、業績評価が相対的に低いことと、定年退職を控え、健康面での不安を抱えながら就労していることを主要な理由として、RAプログラムの対象者となり、平成20年10月28日、上司との面談で、特別支援プログラムに応募するよう求められたが、Xは60歳の定年まで勤めたい旨返答した。同年11月13日、再び、面談があり、説明を受けたが、Xは激しく反発した。そこで上司は、RAプログラムの対象とすることを断念して、業務改善を求めるメールをXに送ったが、Xはこれにも反発した。
Xは、Y会社の退職勧奨は、Xの自由な意思決定を不当に制約するとともに、Xの名誉感情等の人格的利益を侵害した違法な退職強要であり、Xは精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、330万円の支払等を求めて訴えを提起した。なお、本件では、X以外にRAプログラムの対象となり、退職勧奨を受けた3名の原告がいる。1審は、Xの請求を棄却したので、Xは控訴した。
判旨 控訴棄却(Xの請求棄却)
「労働契約は、一般に、使用者と労働者が、自由な意思で合意解約の申入れをすることができるというべきであるが、労働者も、その申入れに応ずべき義務はないから、自由に合意解約に応じるか否かを決定することができなければならない。したがって、使用者が労働者に対し、任意退職に応じるよう促し、説得等を行うこと(以下、このような促しや説得等を「退職勧奨」という。)があるとしても、その説得等を受けるか否か、説得等に応じて任意退職するか否かは、労働者の自由な意思に委ねられるものであり、退職勧奨は、その自由な意思形成を阻害するものではない。
したがって、退職勧奨の態様が、退職に関する労働者の自由な意思形成を促す行為として許容される態度を逸脱し、労働者の退職についての自由な意思決定を困難にするものであったと認められるよううな場合には、当該退職勧奨は、労働者の退職に関する自己決定権を侵害するものとして違法性を有し、使用者は、当該退職勧奨をうけた労働者に対し、不法行為に基づく損害賠償義務を負うものというべきである」。
解説
退職勧奨は、使用者からの合意解約の申込み(あるいは、辞職「解約」の誘引)と評価されることが多いであろう。このような申し込みは、労働者が、それに応じるか否かについて自由に決定できるかぎるは、違法性の問題は出てこない。しかし、労働者の自由な意思形成を阻害するような態様で行われた場合には違法となり、使用者は損害賠償責任を負わなければならない。本件では、XをRAプログラムの対象者としたことに恣意性はなく、退職勧奨の方法も相当であったとして、結論として違法性は否定された(判旨外)。
過去の判例には、執拗な退職勧奨が行われた精神的苦痛があったとして損害賠償が認められたものもある(下関商業高校事件―最1小判昭和55年7月10日。そのほか、長時間の面談などにより、違法な退職勧奨があったとされたものとして、日本航空事件ー東京高判平成24年11月29日やエム・シー・アンド・ピー事件ー京都地判平成26年2月27日等)。
実際に退職の意思決定がなされた場合でも、それが退職強要によるものであれば、強迫を理由に取り消すことができる(民法96条)。裁判例には、懲戒解雇事由がないにもかかわらず、ありうることを告知する場合には、一般論として強迫に該当すうるとしたものがある(ソニー事件ー東京地判平成14年4月9日等。懲戒解雇を避けるためにした退職の意思表示が錯誤により無効である「民法95条」とした裁判例として、富士ゼロックス事件ー東京地判平成23年3月30日等)。
民法95条 (錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法96条(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
61 早期退職優遇制度の適用ー神奈川信用農業協同組合事件
最1小判平成19年1月18日(平成16年(受)380号)
事案の概要
使用者が早期退職優遇制度の適用を承認しなかった場合、労働者は同制度に基づく割増退職金を請求することができないか。
事実
Xら2名は、Y信用金庫の従業員である。Y信組の就業規則には、満60歳を定年とする定年退職制と、本件選択定年制は、48歳以上で15年以上勤続する従業員が、制度の手続に基づき退職を申し出た場合に、割増退職金が支給されるというものであり、制度の適用をうけるためには、Y信組の承認を必要としていた。
平成13年7月、Y信組は経営が悪化していたため、他の信用組合等への事業譲渡を検討していた。Y信組は、事業譲渡をする前に退職者が増加し、事業譲渡が困難になることを懸念し、選択定年制の廃止を決定した。Y信組は、同年9月4日から7日にかけて、従業員に対して、経営悪化により合併が避けられないこと、選択定年制を廃止すること、選択定年制による退職の申出については、すでになされている分と今後の分の両方を承認しない趣旨の説明をした。
Xら2名はY信組に対して、本件選択定年制に基づく退職を申し出たが、承認されなかった。平成14年1月23日、Y信組はAに事業の全部を譲渡し、同年3月31日、全従業員を解雇した。Xら2名は、本件選択定年制に従った割増退職金債権を有することの確認を求めて、訴えを提起した。
1審はXの請求を認容した。原審は、Y信組には、本件選択定年制に基づく退職の申出を承認するか否かにつき裁量権があるが、Y信組の不承認は、Xらの退職の事由の制限となり、Xらに不利益を生じさせるものであるから、本件では、Y信組の不承認という裁量行使は、本来の制度が予定しえちたものと認められず、Xの申出に対してY信組の承認があった場合と同様に取り扱われるべきであると判断して、Xの請求を認容した(東京高判平成15年11月27日)。そこで、Y信組は上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xらの請求棄却)
Ⅰ 本件選択定年制による退職は、従業員の申出に対し、Y信組が承認することによって、雇用契約の終了や割増退職金債権の発生という効果が生ずるものとされており、Y信組がその承認をするかどうかに関し、就業規則において特段の制限が設けられていないことは明らかである。
Ⅱ「もともと、本件選択定年制による割増退職金は、従業員の申出とY信組の承認とを前提に、早期の退職の代償として特別の利益を付与するものであるところ、本件選択定年制による退職の申出に対し承認がされなかったとしても、その申出をした従業員は、特別の利益を受けることこそないものの、本件選択定年制によらない退職を申し出るなどすることは何ら妨げられるものではないので、したがって、従業員がした本件選択定年制による退職の申出に対してY信組の承認がなされなければ、割増退職金の発生を伴う効果が生じる余地はない」。
解説
定年前の早期退職の場合に、割増退職金を支払うという優遇措置が設けられている例は少なくない。こうした措置の適用について、使用者の承認が要件とされているとき、使用者の承認が要件とされている、使用者の承認を得ないままに退職した労働者が、割増退職金を請求する権利があるかどうかをめぐり紛争が生じることがある。こうしたケースでは、労働者が制度の適用要件を満たしてとしても、使用者が承認をしないかぎりは制度の適用が認められないというのが裁判例の傾向であり、本件判決の判旨Ⅰも同じである(使用者が早期退職を呼びかける行為は、申込みの誘引にすぎないということである)。判旨Ⅰが、使用者の不承認が信義則に反する場合には、使用者は承認を拒否できなくなるよいうような、下級審(たとえば、ソニー事件ー東京地判平成14年4月9日「ただし一般論のみ」や本件の原審)で時に認めらてきた例外の余地まで否定する趣旨かどうかは判然としない。
しかし、本判決は、判旨Ⅱに引き続いて、Y信組の不承認について、「理由が不十分であるというべきというべきものではない」と述べているので、少なくとも本件が信義則違反のケースには該当しないと解されていたとみることができよう。
判旨Ⅱは、ややわかりにくいが、割増退職金を支給されないことは、労働者から特別の利益を奪うだけであって、積極的に不利益を課すものではないこと、また、労働者が退職をすること自体は制限されていないこと、という両方の理由から、退職の自由は侵害されていないと判断したものと解することができ、その判断は相当と考えられる。
62 定年後の継続雇用ー津田電機計器事件
最1小判平成24年11月29日(平成23年(受)1107号)
事案の概要
定年後の雇用継続を拒否する雇止めを無効とした例
事実
Y会社は、60歳定年制を導入していたが、定年後1年間は嘱託として雇用する取扱いをしいぇいた。その後、高年法9条2項(平成24年改正前の規定)の定める継続雇用基準を含むものとして、高年齢者継続雇用規定(本件規定)を定めた。それによると、在職中の業務実態および業務能力の査定による総点数が0点以上の者のみを継続雇用することになっていた。
Xは、定年後嘱託になり、その後も、継続雇用を希望していたところ、Y会社は、Xが本件規定の継続雇用基準を満たさないとして、Zの雇用は嘱託雇用契約の終了日である平成21年1月20日をもって終了する旨の通知をした。なお、Xの査定等の内容は、Y会社は、評価方法を誤り、総点数を0点に満たないと評価していた。
Xは選定基準に定める要件を満たしていたことを理由に再雇用契約は成立しているとして、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めた。
1審(大阪地判平成22年9月30日)は、Y会社は本件規定の周知により、継続雇用基準を充足する者を再雇用する旨の契約の申込みをしており、Xはこれに承諾の意思表示をし、継続雇用基準を満たす場合、Y会社の不承諾は権力濫用にあたり、再雇用契約が成立したものと扱われるべきであるとして、Xの請求を認容した。そこで、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求認容)。
Y会社は、高年法9条2項に基づき、過半数代表者との書面協定により、「継続雇用基準を含むものとして本件規定を定めて従業員に周知したことによって、同条1項2号所定の継続雇用制度を導入したものとみなされるところ、期限の定めのない雇用契約及び定年後の嘱託雇用契約によりY会社に雇用されていたXは、在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を本件規定所定の方法で点数すると総点数が1点となり、本件規定所定の継続雇用基準を満たすものであったから、Xにおいて嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続されるものと期待することには合理的な理由があると認められる一方、Y会社においてXにつき、上記の継続雇用基準を満たしていないものとして本件規定に基づく再雇用をすることなく嘱託雇用契約の終期の到来によりXの雇用が終了したものとすることは、他にこれをやむを得ないものとみるべき特段の事情もうかがわれない以上、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものといわざるを得ない。したがって、・・・・Y会社とXとの間に、嘱託雇用契約の終了後も本件規定に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当である」。
解説
高年法は定年年齢は60歳以上でなければならないとしたうえで(8条)、65条までの高年齢者雇用確保措置を義務づけている(9条)。この規定に私法上の効力を認め、義務違反があった場合に、労働者に雇用継続請求権を認めるかについては、学説上争いがあるが、裁判例は、これを否定する傾向にある(NTT西日本事件ー大阪高判平成21年11月27日等)。
一方、本件のように使用者が独自に再雇用基準を設け、それに該当しないことを理由に雇用継続が拒否された場合(平成24年改正までは、過半数代表との労使協定があれば、継続雇用対象者の選別をすることができた(9条2項)、労働者のほうで基準該当性を主張して、再雇用を請求できるかも問題となる。本判決は、雇用継続に対する合理的な期待に言及し、雇止め制限法理(労契法19条)を参照して雇用の継続を認めた(1審と控訴審とは、これと異なる法律構成を採用していた)。
平成24年改正により、労使協定の特例が廃止され、希望者全員65歳までの雇用確保が事業主の義務となった(経過規定あり)。高年法9条の私法上の効力は否定されても、労働契約論(労契法19条を含む)をとおして、不当な雇用継続拒否に対する救済は、引き続き模索されていくであろう。
高年法8条(定年を定める場合の年齢)
第8条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
高年法9条2項(高年齢者雇用確保措置)
第9条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4 第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
労契法19条(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
63 定年後の賃金の引下げの適法性ー長澤運輸事件
東京高判平成28年11月2日(平成28年(ネ)2993号)
事案の概要
定年退職後の有期社員と無期の正社員との間の賃金格差は不合理なものか
事実
Y会社は、セメント輸送等の事業を営み、Xら3名は、同社で搬車の乗務員として勤務している。Xらは、当初は無期労働契約で雇用されていたが、平成26年にいずれも定年に到達し、その後は有期労働契約の嘱託社員となった。Xらは、一般労組のA関東支部のY会社の従業員で構成されたB分会に所属している。
定年再雇用された嘱託社員の就業規則は、正社員就業規則とは別途に作成され、さらに「定年後再雇用者採用条件」も設けられた。これらによると、嘱託会社の基本給は12万5千円と固定され、職務給、精勤手当、約付手当、住宅手当、家族手当、賞与、退職金はなくなる一方、無事故手当、超勤手当、通勤手当は維持され、能率給の一部は引上げられ、さらに老齢厚生年金の報酬比例部分が支給されない期間について、月額2万円の調整給が支給される。A組合は、Y会社に対して、定年前後で賃金水準が下がらないようにすることを要求してきたが、Y会社はこれに応じなかった。
Xらは、自分たちの労働条件とY会社の無期労働契約の労働者の労働条件の総意は、労契法20条でいう不合理な格差にあたり無効で、正社員就業規則等が適用されるべきであるとして、差額の支払い等を求めて訴えを提起した。
1審は、有期契約労働者の職務の内容、当該職務の内容および配置の変更の範囲が無期契約労働者と同一であるにもかかわらず、労働者にとって重要な労働条件である賃金の額について相違を設けることは、その程度にかかわらず、これを正当と解すべき特段の事情がない限り、不合理であると評価を免れないという一般論を述べたうえで、本件では、「嘱託社員と正社員との間に職務の内容、当該職務の内容及び配信の変更の範囲に全く違いがないにもかかわらず、賃金の額に関する労働条件に相違を設けることを正当と解すべき特段の事情が認められない」とし、Xらの賃金の定めは労契法20条違反で無効となるとした。そしてY会社の正社員就業規則は、嘱託者を適用除外としているが、嘱託社員の賃金の定めに関する部分が無効である場合には、これに対応する正社員就業規則の規定が適用されるとして、結論として、Xらの請求を認容した(東京地判平成28年5月13日)。そこで、Y会社が控訴した。
判旨 原判決取消(Xらの請求棄却)
Ⅰ「労働契約法20条は、有期労働契約者と無期契約労働との間の労働条件の相違が不合理と認められるか否かの考慮要素として、①職務の内容、②当該職務の内容及び配置の変更の範囲のほか、③その他の事情を揚げており、その他の事情として考慮すべきことについて、上記①及び②を例示するほかに特段の制限を設けていないから、労働条件の相違が不合理であるが否かについては、上記①及び②に関連する諸事情を幅広く総合的に考慮して判断すべきものと解される」。
ⅡY会社が高年齢雇用確保措置として選択した継続雇用たる有期労働契約は、社会一般で広く行われている。定年退職後も引き続いて雇用されるにあたり、その賃金が引き下げられるのは通例であるY会社が属する業種または規模の企業を含めて、定年の前後で職務の内容ならびに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が変わらないまま。相当程度賃金を引き下げることは、広く行われている。
年収で2割前後の減収は、Y会社の属する規模の企業の平均の減額率をかなり下回り、Y会社の本業で収支が大幅な赤字であることを併せて考慮すると、直ちに不合理とは認められない。Y会社は、歩合給を設けたり、無事故手当を増額支払したり、調整給を支払ったっことがあるなど、正社員の賃金の差額を縮める努力をしている。嘱託社員には昇給や退職金支給がないとしても、Xらが一旦退職して退職金を受給していること、その年齢等から長期にわたる勤続が予定されていないことを考慮すると、不合理性を基礎付けるものとはいえない、Y会社とA組合との間で、定年後再雇用者の労働条件に関する一定程度の協議が行われ、A組合の主張や意見を聞いて、一定の労働条件の改善を実施している。以上から、Xらと正社員との労働条件格差は労契法20条にい不合理なものではない。
解説
使用者が、高年法の義務づける高年齢者雇用確保措置として、定年後の労働者を有期労働契約で再雇用することは、広く行われている。再雇用後の労働条件は、本判決も述べるように、定年前よりも引き下げられるのが一般的である。本件では、定年前後で同一の職務に従事している場合にも、こうした賃金引下げが許されるのかが、無期労働契約の労働者との間の不合理な格差との可否という観点から争われた。原審は短時間労働者法9条の趣旨もふまえて、職務内容の同一性と人材活用の範囲の同一性があれば、これを覆す特段の事情がない限り、賃金格差は不合理となるという独自の考え方をとった。
本判決は、これとは異なり、「その他の事情」を広く考慮するという枠組みを採用し(判旨Ⅰ)、そのうえでY会社の行った扱いは社会通念等に照らして問題がないという考慮を強く押し出して格差の不合理性を否定した(判旨Ⅱ)(→【72】ハマキョウレックス事件)。
労働契約法20条
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
短時間労働法9条
(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条 事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
64 定年後再雇用時の労働条件ートヨタ自動車事件
名古屋高判平成28年9月28日(平成28年(ネ)149号)
事案の概要
定年後再雇用に提示された職務を拒否したために再雇用がなされなかった場合の高年法違反の成否。
事実
Xは、自動車の製造を目的とするY会社で、定年までデスクワークを主体とする事務職に従事してきた。Y会社では、就業規則上、60歳の誕生日に定年退職するとされ、再雇用希望者は、解雇事由に該当するものを除き、労使協定に基づき再雇用すると定められていた。平成24年の高年法改正にともない、労使協定が締結しなおされ、所定の基準(健康、職務遂行能力、勤務態度)を満たす者には「スキルドパートナーしての職務を提示し、この基準を満たさない者には、パートタイマ―就業規則に定める職務を提示することとされた(契約期間はどちらも1年だが、前者は65歳までの更新があったが、後者は更新を行わないとされていた)。
Xは、定年退職後、Y会社からパートタイマーとしての再雇用の勤務条件(労働時間は1日4時間で、勤務場所は、従前どおりだが、主な業務内容は清掃業務、時給は1,000円)が」提示された。しかし、Xは「スキルド・パートナー」としての再雇用を希望したため折り合わず、結局、Xは再雇用拒否は違法であるとして、労働契約上の地位確認等を求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求を棄却したので、Xは控訴した。
判旨 原判決変更(慰謝料請求のみ認容)
Ⅰ 「事業者においては、・・・・定年後の継続雇用としてどのような労働条件を提示するかについては一定の裁量があるとしても、提示した労働条件が、無年金・無収入の期間の発生を防ぐという趣旨に照らして到底容認できないような低額の給与水準であったり、社会通念に照らし当該労働者にとって到底受け入れがたいような職務内容を提示するなど実質的に継続雇用の機会を与えてと認められない場合においては、当該事業者の対応は、改正高年法の趣旨に明らかに反するものであるといわざるを得ない」。
Ⅱ 「改正高年法の趣旨からすると、Y会社は、Xに対し、その60歳以前の業務内容と異なった業務内容を示すことが許されることはいうまでもないが、両者が全く別個の職種に属するなど性質の異なったものである場合には、もはや継続雇用の実質を欠いており、むしろ通常解雇と新規採用の複合行為というほかないから、従前の職種全般について適格性を欠くなど通常解雇を相当とする事情がない限り、そのような業務内容を提示することは許されないと解すべきである。
解説
使用者が、定年退職者を、継続雇用制度の措置として、再雇用するとき(高年法9条1項2号)、労働条件をどのように定めるかについては、法律は何も規定していない。同号は、継続雇用制度を「現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」と定義しているが、高年齢者の希望する労働条件に応じることまでは使用者に義務づけていない。そのため、使用者が、定年後の労働条件について合意が成立しなかったことを理由に、継続雇用を拒否することは、それだけでは、高年法違反とはならない(この点は、厚生労働省の「高年齢者雇用安定法Q&A」AI-9も参照)。
もっとも、使用者の提示する労働条件が、労働者に到底受け入れられないような低いものであれば、実質的には、高年齢者雇用確保措置義務(高年法9条)に違反しているとの評価も可能となろう。この点違つき、本判決は、労働条件について使用者に一定の裁量があることは認めたうえで、賃金や職務内容について、実質的に継続雇用の機会を与えられたとは認められない場合には、高年法違反となるとする(判旨Ⅰ)
本件では、賃金面については、Xはパートタイムで再雇用されていたとしても、老齢厚生年金の報酬比例部分の約85%の収入になっており、本判決はこれを「無年金・無収入の期間の発生を防ぐという趣旨に照らして到底容認できないような低額の給与水準である」とはいえないとした(判旨外、ここではm賃金額を絶対的な基準で評価しているが、Y会社の無期雇用の社員との比較から評価すると、労契法20条の問題となろう「→【63】長澤運輸事件」)。
一方、職務面については、本判決は、定年後の業務ないようとして、定年前の業務内容とまったく別個の職種に属するなど性質の異なったものを提示することは、定年後の業務内容において、普通解雇を相当とする程度に適格性が低いばあいでないかぎり許されないとした(判旨Ⅱ。本件のXがスキルドパートナーズの基準に充足していないことは裁判所も認めている)。そして本件では、定年後に提示された職務は、それまでとはまったく別個の職種に属する単純労務職であることや、Xが従前行っていた事務職のいかなる業務においても、それに耐えられないなど普通解雇に相当する事情は認められないことに言及して、高年法の趣旨に反する違法なものであると結論づけた(なお、本判決は、Y会社は、Xを定年退職をせざるをえないように仕向けた疑いさえあると述べている)。
本判決は、不法行為による損害賠償として、Xがパートタイマーとして1年間継続勤務していたとすれば得ていたであろう賃金分に相当する額を慰謝料として認めた。
高年法9条1項2号(高年齢者雇用確保措置)
第9条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止
2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4 第六条第三項及び第四項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
労契法20条 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
65 有期労働者の雇止めー東芝柳町工場事件
最1小判昭和49年7月22日(昭和45年(オ)1175号)(民衆28巻5号927頁)
事案の概要
基礎的臨時工の有期労働契約の長期にわたる反復更新後の雇止めは有効か。
事実
Xら7名は、電気機器の製造販売を目的とするY会社において、契約期間2か月で採用された臨時工である。Xらは景気変動の調整弁として採用されていたが、Y会社の基幹作業に従事している基幹的臨時工であった。Xらは、正社員である本工と採用基準や適用される就業規則に差があり、労働組合への加入も認められていなかったが、仕事の内容や種類については、本工と差がなかった。」Xらは、採油の際に、Y会社側から「期間が満了しても真面目に働いていれば解雇されるようなことはない」と言われており、継続雇用への期待をもって契約書を交わしていた。
実際、Y会社では、基幹的臨時工は、本人が望むかぎり長期的に雇用が継続されており、Xらについても少ない者で5回、多い者で23回、契約の更新が行われてきた。Y会社では、契約期間の満了の都度、直ちに新契約締結の手続をとるということはしていなかった。その後、Y会社は、Xらに対して、勤務態度の不良や業務量の減少を理由に、その契約の更新を拒絶したので、Xらは、労働契約関係の存在確認等を求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、本件雇止めは、無効であると判断した。そこで、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却
Ⅰ「本件各労働契約においては、Y会社としても景気変動等の原因による労働力の過剰状態を生じないかぎり契約が継続することをよていしていたものであって、実質において、当事者双方とも、期間は一応2か月と定められてはいるが、いずれかから格別の意思表示がなければ、当然更新されるべき労働契約を締結する意思であったものと解するのが相当であり、したがって、本件各労働契約は、期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間のさだめのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、本件各傭止めの意思表示は右のような契約を終了させる趣旨のもとにされたのであるから、実質において解雇の意思表示にあたる」。
Ⅱ 原判決は、Ⅰのように認定したうえで、本件各傭止めの効力の判断にあたっては、その実質にかんがみ、解雇に関する法理を類推すべきであるとしており、その認定判断は、正当として首背することができる。
解説
1現行法上は、労働契約に期間を定めることについて、その理由を特に限定していない(いわゆる入口規制の欠如)。したがって、短期的・臨時的な仕事に就かせるような場合ではなくとも、使用者は期間を定めて労働契約を締結することができる(ただし、労契法17条2項も参照)。
他方、法律は、労働契約の期間の上限については制限を加えている。労基法は、労働契約の期間の上限は原則として3年とし(なお、137条も参照)、ただし一定の事業の完了を必要な期間を定める場合は例外とし、さらに、高度の専門的知識をもつ者との労働契約、満60歳以上の者との労働契約については、特例として期間の上限を5年としている(14条1項)。契約の更新は、形式上は、新たに契約を締結することなので、更新の結果、トータルで3年(特例の場合で5年)を超えることになっても、労基法違反とはならない。
ただ、更新が反復継続された後に、雇止め(更新拒絶)が行われた場合には、争いが生じることがある。本判決は、有期労働契約の反復更新後の雇止めは、当該契約関係が、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になっていれば、解雇に準じた制限が加えられるとした。さらに、その後の最高裁判決は、雇用継続の合理的期待が発生している場合にはおいても解雇に関する法理が類推されるとし(日立メディコ事件ー最1小判昭和61年12月4日)、雇止め制限法理を確立した。
現在では、この法理が労契法19条に取り入られ、実質的に無期労働契約と同視できる場合(1号)、または、更新の期待に合理的な理由がある場合(2号)において、労働者からの更新申込みの拒絶が、客観的に合理的な理由を欠き、社旗通念上相当と認められない場合には、使用者は、以前と同一の労働条件で、申し込みを承諾したものとみなすという規定になっている。
このほか、労契法の平成24年改正では、有期労働契約を更新して通算5年を超えた場合には、労働者に無期転換の申込権を認める規定(みなし承諾規定)も導入された(18条)
2 雇止めが経営上の理由による場合には、整理解雇の4要件(要素)(→【51】東洋酸素事件)が類推適用されることになる。ただし、有効性の判断は、正社員に対するよりも緩やかに行われる個々なわれる。判例は、その理由として、非正社員の雇用関係は、比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とするものだからであるとしている(日立メディコ事件・前掲)。
労契法17条2項(契約期間中の解雇等)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
労契法18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。
以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
労契法19条 (有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
労基法14条1項(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
労基法137条
第137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
66 派遣労働者の雇止めー伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件
高松高判平成18年5月18日(平成15年(ネ)293号)
事案の概要
同一派遣先で長期的に派遣労働に従事した後、労働者派遣契約が打ち切られて場合、派遣元からの雇止めは有効か
事実
Xは、派遣会社Y1の登録型の派遣労働者であり、Y1会社の株式の100%を保有するY2銀行のA支店で、昭和62年5月から業務に従事していた。XとY1会社の間の労働契約の期間は6か月であり、平成12年5月末まで、更新されてきた(XはB会社に採用され、その後、Y1会社がB会社の派遣事業部門の事業譲渡を受けて、Xとの労働契約も承認している)。Xは、平成10年頃から、Y2銀行のA支店に赴任してきた上司と折り合いが悪くなり、次第にその関係が悪化した。
Y2銀行は、Y1会社との労働者派遣契約を更新しないこととし、Y1会社は、平成12年5月31日に、Xとの労働契約の更新を拒絶して雇止めした。
Xは、この雇止めは権利濫用であるとし、また、XとY2銀行との間には、黙示の労働契約が成立しているとしてY1会社およびY2銀行に対し、労働契約上の地位確認等を求めて、訴えを提起した。1審はXの請求を棄却したため、Xは控訴した。本判決に対して、Xは上告したが、棄却・不受理となっている(最2小判平成21年3月27日)。
判旨 原判決ー一部変更(労働契約上の地位確認については、公訴棄却・請求棄却)。
Ⅰ 雇止めになった当時、XがA支店への派遣による継続雇用について強い期待を抱いていたことは明らかというべきである。「しかし、派遣法は、派遣労働者の雇用の安定だけでなく、常用代替防止、すなわち派遣先の常用労働者の雇用の安定も立法目的とし、派遣期間の制限規定をおくなどして、両目的の調和を図っているところ、同一労働者の同一事業所への派遣を長期間継続することによって、派遣労働者の雇用の安定を図ることは、常用代替防止の観点から、同法の予定するとことではないといわなければならない・・・・。そうすると、上記のようなXの雇用継続に対する期待は、派遣法の趣旨に照らして、合理性を有さず、保護すべきものとはいえないと解される」。
Ⅱ「派遣労働者と派遣先との間に黙示の雇用契約が成立したといえるためには、単に両者の間に事実上の使用従属関係があるというだけでなく、諸般の事情に照らして、派遣労働者が派遣先の指揮命令のもとに派遣先に労務を提供する意思を有し、この命令のもとに派遣先がその対価として派遣労働者に賃金を支払う意志が推認され、社会通念上、両者間で、雇用契約を締結する意思表示の合致があったと評価できるに足りる特段の事情が存在することが必要である。
本件では、「XがY2銀行の指揮命令のもとにY2銀行に労務の供給する意思を有し、これに関し、Y2銀行がその対価として、Xに賃金を支払う意思が推認され、社会通念上、XとY2銀行間で雇用契約を締結する意思表示の合致があったと評価できるに足りる特段の事情が存在したものとは、到底認めることができない」。
Ⅲ「Y1会社は、派遣元として必要な人的物的組織を有し、適切な業務運営に努めており、独立した企業としての実体を有し、派遣労働者の採用や、派遣先、就業場所、派遣対象業務、派遣期間、賃金その他就業条件の決定、派遣労働者の雇用管理等について、Y2銀行とは独立した法人として意思決定を行っており、Y1会社は、Y2銀行の第二人事部でもなければ、賃金支払代行機関でもない。したがって、法人格否認の法理を適用しうる場合とは、認められない。
解説
労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい」(労働者派遣法2条1項)、労働者派遣事業をする場合には、厚生労働大臣の許可が必要となる(同5条。平成27年の法改正で、届け出だけでよい特定労働者派遣事業は廃止された)。
本件では、まず、派遣労働者が、派遣会社との間で、期間6か月の有期労働契約をかわしていとところ、契約が長期にわたり、反復更新されたため、雇止め制限法理(現在では、労契法19条→【65】東芝柳町工場事件)が適用されるかが問題となったが、労働者派遣法は、同一労働者の同一事業所への長期的な派遣を予定していないとし、労働者の雇用継続の期待は合理的なものではないとして、同法里の適用を認めなかった(判旨Ⅰ。ただし、上告審での今井裁判官の反対意見は、本件でも同法理の適用の余地があるとする)。
なお、平成27年の法改正後は、有期労働契約で雇用されている労働者の派遣の上限期間は、従来の法規制を抜本的に改め、専門業務かどうかに関係なく、個人単位で組織ごとに3年となっている(労働者派遣法35条の3、40条の2、40条の3。なお、40条の4の雇用努力義務も参照)。
次に、派遣先との間での労働契約関係については黙示の労働契約契約関係を否定し(判旨Ⅱ→【14】パナソニックプラズマプレイ「パスコ」事件)、法人格否定の法理に基づく労働契約の成立も否定された(判旨Ⅲ→【15】黒川建設事件)。
労契法19条(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
労働者派遣法2条1項 (用語の意義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。
四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法 その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
労働者派遣法5条(労働者派遣事業の許可)
第5条 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
労働者派遣法35条の3
第35条の3 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
労働者派遣法40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第40条の2 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
三 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣
イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務四 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第六十五条第一項 及び第二項 の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
五 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号 に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣
2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。
3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。
5 派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。
6 派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。
7 派遣先は、第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
8 厚生労働大臣は、第一項第二号、第四号若しくは第五号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
労働者派遣法40条の3
第40条の3 派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。
労働者派遣法40条の4
(特定有期雇用派遣労働者の雇用)
第40条の4 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して一年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
67 地方公務員法上の非常勤職員の再任用拒否ー中野区(非常勤保育士)事件
東京高判平成19年11月28日(平成18年(ネ)3454号)
事案の概要
任期付きの非常勤保育士(地方公務員)は、再任用拒否の適法性を争うことができるか
事実
Xら4名は、平成4年7月1日から、同7年2月1日にかけて、地方自治法であるY区の保育園において、地方公務員法3条3項3号に定める特別職の非常勤の保育士として任用され、同15年まで、任用期間を1年として再任用されてきた。ところが、Yは、保育士に関して、施設の民営化等により、配備する職員や非常勤職員数を削減することとし、平成15年度末で」非常勤保育士の職を廃止した。それにともない、Xらは、平成16年4月に再任用されなかった。そこで、Xらは、本件再任用拒否は、解雇権を濫用したもので無効であると主張し、Yに対して、非常勤職員としての地位確認、再任用に対する期待権の侵害を理由とする損害賠償を求めて、訴えを提起した。1審は、地位確認請求は認めなかったが、再任用への期待権を侵害を理由として、1人あたり40万円の慰謝料を認めた。XらとYの双方が控訴した。
判旨 一部認容、一部棄却(地位確認請求は、棄却。慰謝料は報酬の1年分を認めた)。
Ⅰ Xらの任用関係については、地方公務員法3条3項3号により。規律されるとともに、その具体的内容は、Yの任用行為によって決定されるなどの行政処分であり、これに基づく本件勤務関係は、公法上の任用関係であると認められる。
Ⅱ(1)本件では、XらとYらとの間の勤務関係に、解雇権濫用法理を類推適用される実態と同様の状態が生じていたと認められ、Xらの職務の継続確保が考慮されてしかるべき事態であった。
(2)地方公共団体における非常勤職員については、期間の定めのない任命の意思を考えれことができず、また、任命行為は行政行為であって、当事者双方の意思を推定する規定である民法629条1項を類推適用することは困難であるし、雇止めに関する判例法理を適用することもできない。
Ⅲ 本件において、YはXらに対し、非常勤保育士の任用の際に本件任用が公法上の任用関係であることについて説明しなかったこと、採用担当者が長期の職務従事者を期待するような言動を示していたこと、Xらの職務内容が非常勤保育士と変わらず継続性が求められる恒常的な職務であること、それぞれ9回から11回にかけて再任用され、結果的に職務の継続が10年前後という長期間に及び、再任用が形式的でしかなく、実質的には当然のように継続していたことに照らすと、Xらが再任用を期待するような行為Yにおいてしていたという特別の事情があったものと認められる。したがって、Xらの任用継続に対する期待は、法的保護に値するものと評価できる。
解説
本件は、地方公務員法3条3項3号に基づく特別職の非常勤職員の再任用が拒否された場合に、民間部門と同じような雇止めの制限の法理が適用されるかどうかが争られた事件である。
公務員の勤務関係の法的性格については、これを公法上の勤務関係とみる見解と、労働契約とみる見解とがあるが、通説および判例は、前者の立場である。ただ、特別職の非常勤地方公務員については、民間の有期雇用の労働者と勤務の実質において差はないし、地公法の適用もない(地公法4条2項)ので、労働契約とみる余地がないのかが問題となる。裁判例は、任用行為に基づき成立する公務員の勤務関係である以上、公法上の勤務関係であり、私法上の労働契約関係とみることはできないと解している。判旨Ⅰもどうようである。
もっとも、公法上の勤務関係であるからといって、判例の雇止め制限法理が当然に適用されないということにはならない。雇止め制限法理が、一定の継続的な就労状態に着目して信義則上認められる法理であると解することができれば、公法上の勤務関係にも適用される余地はあるはずである。しかし、本判決は、結論として、公務員の勤務関係には、意思の要素が入りこむ余地がないので、雇止め制限法理を適用することはできないとしている(判旨Ⅱ(2))。
現在では、雇止制限法理は統計法19条に成文化されており、地方公務員は労契法の適用対象外とされているので(22条1項)、すくなくともこの法理の直接的な適用は困難であろう。
一方、本判決は、Xらに対して、期待権の侵害を理由とする慰謝料請求は、肯定した。従来、判例は、期間満了後も信用が継続されると期待することが無理からぬものとみることができるような特別の事情がある場合には、職員がそのような謝った期待を抱くことによる損害につき、国家賠償法に基づく賠償を認める余地がある、と述べていた(大阪大学(図書館事務補佐員)事件ー最1小判平成6年7月14日(日々雇用職員のケース)。ただし、同判決は、結論としては、賠償請求を認めておらず、従来の裁判例も、この種のケースで損害賠償請求を認めた例はほとんどなかった。しかし、本判判決は、任用の経緯、職務内容、勤務継続期間、再任用の手続の実態などから、Xらの持った期待は法的保護に値するとし(判旨Ⅲ)、報酬の1年間分という比較的多額の慰謝労を認めた点で注目される。
民法629条1項(雇用の更新の推定等)
第629条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
地方公務員法3条3項3号(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)
第三条1 地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。3 特別職は、左に掲げる職とする。一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職一の二 地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職一の三 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
地方公務員法4条2項(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条1 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
労契法19条(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
労契法22条1項(適用除外)
第22条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
68 不更新条項の効力ー本田技研工業事件
京高判平成24年9月20日(平成24年(ネ)1849号)
事案の概要
不更新条項が挿入された有期労働契約の終了時に、雇止め制限法理は適用されるか。
事実
Xは、平成9年12月1日、車の製造、販売を目的とするY会社に、期間契約社員として、採用された。その後、Xは、Y会社との間で有期雇用契約の締結と契約期間満了、退職を繰り返した。Xは、平成20年9月29日、Y会社との間で、同年10月1日から契約期間2か月とする有期労働契約を締結し、さらに、同年11月28日、Y会社との間で、同年12月1日から、契約期間1か月とする本件雇用契約を締結した。同月31日、Y会社は、本件雇用契約の契約期間が満了したとし、その後の契約の更新を拒絶した。
Xは、本件雇用契約の締結に先立つ平成20年11月26日にY会社が開催した説明会に出席し、リーマンショックによる自動車販売実績の急速な低迷により、Xの勤務してきたA製作所の部品生産の激減等について説明を受け、また、同月28日には、Y会社が勤務シフト別に期間契約社員に対して開催した説明会に出席しA製作所では、経営努力だけでは余剰労働力を吸収しきれず、期間契約社員を全員雇止めにせざるを得ないこと等について説明を受けた。
Xは上記の説明を理解し、もはや期間契約社員の雇止めは回避し難くやむえないものとして受け入れ、「本契約は、前項、「筆者注:契約期間の定めを指す」に定める期間の満了をもって終了し、契約更新はしないものとする。」という、本件不更新条項が盛り込まれた契約書に任意に署名した、Xは、この雇止めが、これまでのような、退職後に一定の空白期間経過後、再入社することが期待できる雇止めではないことは十分理解していた。
Xは、Y会社からの本社雇用契約の更新拒絶は違法無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位の確認等を求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求を棄却したため、Xは控訴した。なお、Xは、本判決について上告したが、棄却・不受理となっている。
判旨 控訴棄却(以下は、控訴審の引用する1審判決の内容である)。
Xは、事前に、Y会社からの説明を受け、本件不更新条項が、もはや再入社が期待できない雇止めを予定する条項で、やむなくこれを受け入れざるをえないと判断し、不更新条項を規定する本件雇用契約を締結した。そして、本件雇用契約が締結された平志恵20年11月28日から本件雇止めが実行された同年12月末日えの間、XはY会社側に不満はもとより異議をもべたり、契約継続することを求めたりするなどせず、粛々と雇止めを受け入れる行動態度をとって期間満了に至り、退職手続を整然と履行してY会社から支給される慰労金はおよび清算金を受領した。
そうすると、Xは、Y会社の説明会が開催された同年11月28日時点において、本件雇用契約の期間満了後における雇用契約のさらなる継続に対する期待利益を確定的に放棄したと認められるから、本件雇止めについては、解雇権濫用法理の類推適用の前提を欠く。
解説
有期労働契約の反復更新によって、雇用続に対する合理的な期待が発生した後の更新時の契約書に、次の更新はしない旨の不更新条項が挿入された場合、その条項通どおり、当該契約期間の満了時に契約が終了するのか、あるいは、なお、解雇権濫用法理が類推適用されるのは、学説上、争いがある。(現在では、労契法19条の提要の問題)。裁判例の中には、不更新条項の存在により、雇用終了の合意があるとして、不更新条項の存在により、雇用終了の合意があるとして、雇止め制限法理の適用を認めなかったものもある。(近畿コカ・コーラボトリング事件ー大阪地判平成17年1月13日)。
もっとも、不更新条項は、これに同意しなけらば有期雇用契約が締結できないため、これを受け入れて更新された契約の終了時に退職するか、受け入れを拒否して、即刻退職するかの二者択一の立場に置かれ、半ば、強制的に、不更新条項に同意せざるをえない可能性がある。
そのため、労働者の自由意思に基づく同意の存否は慎重に判断する必要がある。ただ本件は、その点を踏まえても、自由意思に基づく同意があり、「期待利益の放棄」が認められるとして、雇止め制限法理の適用が否定された。裁判例の中には、不更新条項があっても雇用終了の合意があったとはせず、雇止め制限法理の適用を認めたうえで、ただ、雇用継続の期待の合理性が低かったとして、結論として解雇権の濫用にはあたらないとしたものもある(東芝ライテック事件ー横浜地判平成25年4月25日)。
不更新条項は、労働者に無期転換申込み権が生じる通算5年の要件(労契法18条)の充足を回避するために用いられる可能性もあるため、同条項の有効性は、実務上重要な意味をもつ。、あや、更新回数の上限を設定する条項も不更新条項と類似の機能をもつため、その条項の有効性は慎重に判断されるだろう。
労契法19条 (有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
労契法18条(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
第18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が六月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が一年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
69 有期労働契約の雇止め変更解約告知ー河合塾事件
最3小判平成22年4月27日(平成21年(受)1527号)
事案の概要
予備校の非常勤講師が、期間1年の出講契約の多年にわたる更新後、担当授業数の削減に応じなかったために更新がされなかったことの違法性。
事実
Xは、昭和56年から、学校法人Yの経営する大学予備校で非常勤講師として、期間1年の出講契約を締結し、平成17年に至るまで契約を更新してきた。Xが担当する講義の週当たりのコマ数は、毎年の出講契約において定められ、講義料単価に担当コマ数を乗じて講義料が支払われることになっていた。Xはほぼ、Y法人からの収入だけで生活していた。
Y法人は、毎年、受講生に対して、講師や授業に関する講義を評価し、出講契約を更新する際には、上記の評価が担当コマ数の割合等を行うための参考とされていた。平成15年度から同17年度にかけて、Xの評価はいずれもかなり低かったのに対し、同じ科目を担当する他の講師らの評価は、高かった。Xは、平成17年度は、週7コマの講義を担当していたがY法人は、当該科目につき、評価の高い講師の担当コマ数を増やし、Xの担当コマ数を減らすこととし、平成18年度のXの担当講義を週4コマにしたい旨をXに告げた。
Xは、平成18年度も従前通りにのコマ数での出講契約をもとめたものの、Y法人はこれに応じず、同年度の出講契約を締結するのであれば、週4コマを前提とする契約書を返送するように通リした。
これに対し、Xは、週4コマの講義は担当するが、合意に至らない部分は、裁判所に労働審判を申し立てた上で解決を図る旨の返答をし、同契約書を返送しなかった。Y法人は、これにも応じず、契約書の返送を再度求め、返送がない場合には、Xとの契約関係は終了することになる旨通知した。Xはこれに返答せず、Y法人の担当者に契約書を提出する意思はない旨回答したため、平成18年度の出講契約は締結されなかった。
Xは、雇用契約上の地位確認、賃金および慰謝料の支払いを求めて訴えを提起したところ、1審はXの請求を棄却した。Xが控訴したところ、原審は、慰謝料の請求を一部認容した。そこで、Y法人が上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xの請求棄却)
「Y法人とXとの間の出講契約は、期間1年単位で、講義に対する評価を参考にして担当コマ数が定められるものであるところ、Y法人が平成18年度におけるものであるところ、Y法人が平成18年度におけるXの担当講義を週4コマに削減することとした主な理由は、Xの講義に対する受講生の評価が3年連続して低かったことにあり、受講生の減少が見込まれる中で、大学受験予備校経営上の必要性からみて、Xの担当コマ数を削減するというY法人の判断はやむを得なかったというべきである。Y法人は、収入に与える影響を理由に従来どおりのコマ数の確保等を求めるXからの申入れに応じていないが、Xが兼業を禁止されておらず、実際にも過去に兼業をしていた時期があったことなども併せて考慮すれば、Xが長期間ほぼY法人からの収入により生活してきたことを勘案しても、Y法人が上記申入れに応じなかったことが不当等はいい難い。
また、合意に至らない部分につき労働審判を申し立てるとの条件で週4コマを担当するとのXの申入れにY法人が応じなかったことも、上記事情に加え、そのような合意をすれば、全体の講義編成に影響が生じ得ることからみて、特段非難されるべきものとはいえない。
そして、Y法人は、平成17年中に平成18年度のコマ数削減をXに伝え、2度にわたり、Xの回答を待ったものであり、その過程で不適切な説明をしたり、不当な手段を用いたりした等の事情があるともうかがわれない。
以上のような、事情な下では、平成18年度の出講契約の締結に向けたXとの交渉におけるY法人の対応が不法行為に当たるとはいえない。
解説
有期労働契約の反復更新により、雇止め法理の適用要件を充足していた場合(現在の労契法19条)に、更新時に使用者が従来より、低い労働条件を提示したために労働者がそれに応じなかった場合、これが労働者による労働拒否とみるのか、それとも解雇の法理の類推適用を認めるかについては、見解が分かれる(後者の裁判例として、ドコモ・サービス事件ー東京地判平成22年3月30日)。後者とすると、変更解約告知(→【58】スカンジナビア航空事件)と類似の状況が生じることになる。
本件の原審は、Xが契約書を返送しなかった以上、自らの意思で出講契約の締結をしなっかたものである。自らの意思で出講契約の締結をしなったものであるから、Y法人からの雇止めはなされていないと判断した(福岡高判平成21年5月19日)。Xは、週4コマの講義は、担当するが、合意に至らない部分は、労働審判で解決を図る旨の返答をしていることから、担当授業数の減少の相当性については、労働審判の判断に従う旨の留保付き承諾をしたとみることもできそうであったが、裁判所は、Xの対応は、単なる新契約締結(更新)の拒否と評価した。なお、本件では、出講契約の労働契約条件についても争われたが、それは肯定されている。
労契法19条 (有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
70 有期の派遣労働者に対する中途解除の有効性ープレミアライン事件
宇都宮地栃木支決平成21年4月28日(平成21年(ヨ)1号)
事案の概要
派遣先会社による労働者派遣契約の解除がなされた場合、派遣元会社による有期の派遣労働者に対する期間途中での解雇は有効か。
事実
労働者派遣事業を営むY会社は、自動車製造を業とするA会社との労働者派遣契約に基づき、同社B工場に37名の労働者派遣を行っていた。Xは、Y会社との間で、有期の派遣労働契約を締結し、平成20年10月1日に、期間を同21年3月31日までとして契約を更新して雇用されており、B工場に派遣されていた。Y会社は、平成20年11月中旬に、A会社から同年12月26日付けで労働者派遣契約を解約するとの通知を受け、これを受けて同年11月17日付けで、Xら派遣労働者に対して同年12月26日をもって解雇する旨予約期間満了までの賃金の仮払いを求める仮処分を申し立てた。
決定要旨 一部認容。
Ⅰ(1)「期間の定めのある労働契約は「やむを得ない事由」がある場合に限り、期間内の解雇(解除)が許される(労働契約法17条1項、民法628条)。このことは、その労働契約が登録型を含む派遣労働契約であり、たとえ派遣先との間の労働者派遣契約が期間内に終了した場合であっても異なるところはない」。
(2)「この期間内解雇(解除)の有効性の要件は、期間の定めのない労働契約の解雇が権利の濫用として
無効となる要件・・・・(労契法16条)よりも厳格なものであり、このことを逆にいえば、その無効の要件を充足するような期間内解除は、明らかに無効であるということができる」。
「そこで、本件解雇の有効性について、解雇権濫用法理として、整理解雇の4要件(考慮要素)として挙げられている、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③被解雇者選択の合理性、④解雇手続の相当性の要件、(考慮要素)のうち、本件に顕われた事情を総合してはんだんすることとする」。
Ⅱ(1)Y会社は、A会社から労働者派遣契約を解除する通知を受けた後、Xら派遣労働者を解雇する以外の措置をなんらとっていない。Y会社が、本件のように直ちに派遣労働者の解雇の予告に及ぶことなく、派遣労働者の削減を必要とする経営上の理由を真摯に派遣労働者に説明し、希望退職を募集ないし、勧奨していれば、これに応じた派遣労働者が多数に及び、そうすれば残余の少数の派遣労働者の残期間の賃金支出を削減するために、あえて解雇に及ぶことはなかったであろうと推測することができる。
(2)Y会社は、Xとの派遣雇用契約書において、「派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない本契約の中途解約に関しては、他の派遣先を斡旋する等により、本契約に係わる派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする」と約定し、解雇予告通知書にも同旨の記載をしているにもかかわらず、本件解雇の予告以降、Xに対して、具体的な派遣先を斡旋するなど、就業機会確保のための具体的な努力を全くしていない。
(3)Y会社は、派遣労働者の解雇の必要性に関して、Xら派遣労働者に対して、A会社との労働者派遣契約が終了することを一方的に告げるのみであって、Y会社の経営状況等を理由とする人員削減の必要性を全く説明していない。のみならず、本件における解雇手続は、派遣労働者らに退職届を提出するよう指示するなど、有効な合意解約が成立しているとの主張を強行しており、この解雇の手続は、労使間に要求される信義則に著しく反し、明らかに不当である。
(4)Y会社の経営状況等は、相当に厳しいものと評価することができるが、他方、利益剰余金は多大で、自己資産比率も流動比率も当座比率も健在である。
解説
登録型派遣では、派遣元会社が派遣労働者と締結する労働契約の期間は、本件のように、労働者派遣契約が中途解約された場合、派派遣元会社が契約期間の満了前に、派遣労働者を解雇すると、有期労働契約の中途解除(解雇)となるので、労契法17条1項(および民法628条)の適用の問題となる(決定要旨Ⅰ(1))。そして、同項の「やむを得ない事由」は、期間の定めのない労働契約の解雇に関する労契法16条よりも厳格なものと解されている(決定要旨Ⅰ(29)。ただ、本件のような経営上の理由による解雇の場合の具体的な判断要素は、整理解雇の場合と同じ判断要素が考慮されることとなる(同→【51】東洋酸素事件)。
登録型派遣の場合には、当該派遣先会社に派遣することをぜんていとして、労働契約を締結するので、労働者派遣契約が中途解除されれば、派遣元会社の解雇回避の努力は通常の整理解雇の場合よりも軽減されるようにも思われる。しかし、本件では、派遣元会社は派遣労働者の就業機会の確保を図る約束をしていたという事情があることから、このような解雇回避努力の軽減は、認められていない。
なお、労働者派遣契約の中途解除を直接的に規制する規定はないが、平成24年の労働者派遣法改正により、派遣先会社には、労働者派遣法改正により、派遣先会社には、労働者派遣契約の解除にあたって、派遣労働者の新たな就業機会の確保や派遣先が支払う派遣労働者への休業手当の費用負担などの措置を講じる義務が課されている(29条の2)。また、平成27年労働者派遣法改正で、派遣元会社は、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込みであるなど一定の場合に、派遣労働者の派遣終了後の雇用安定措置を講じる義務が追加された(30条。派遣される見込みが3年未満の場合は努力義務)。なお、労働者派遣契約の中途解除の態様によっては、派遣先会社は不法行為責任を負う(三菱電機ほか事件ー名古屋高判平成25年1月25日)ことがある。このことは、期間満了後の不更新についても同様である(積水ハウスほか事件ー大阪地判平成23年1月26日を参照)。
民法628条(期間の定めのある雇用の解除)
第626条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
労契法16条(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労契法17条1項 (契約期間中の解雇等)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
労働者派遣法29条2項
第29条の2 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
労働者派遣法30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第30条 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。
一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
二 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
三 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。
71 賃金格差と不法行為ー丸子警報器事件
長野地上田支判平成8年3月15日(平成5年(ワ)109号)
事案の概要
正社員と非正社員の賃金格差について、不法行為による損害賠償請求が認められるか
事実
Xら(全員が女性)は、自動車警報器等の製造販売を業とするY会社において臨時社員として雇用されていた。臨時社員は雇用期間は2か月であったが、実施には何度も更新されていた。仕事の内容については、臨時社員と女性の正社員との間では、区別がなく、勤務時間も同一であった。正社員の給与は、月給制で、勤務時間も同一であった。正社員の給与は月給制で、基本給は原則として、年功序列であるが、臨時社員の給与は日給月給制で、基本給は勤続年数に応じて3段階に分かれていた。最も勤続年数も長い臨時社員の年収は、同じ勤続年数の正社員と比べた場合に約3分の2にとなっていた。Xらは、正社員との賃金の差額について損害を被っているとして、不法行為(民法709条)を理由とする賠償を求めて訴えを提起した。
Ⅲ 本件では、Xらの労働内容は、その外形面においても、Y会社への帰属意識という内面においても、女性正社員と同一であるにもかかわらず、Xらを臨時社員として採用したままこれを固定化し、女性正社員との顕著な賃金格差を維持拡大しつつ長期間の雇用を継続したことは、均等待遇の理念に違反する格差であり、公序良俗違反となる。
Ⅳ「均等待遇の理念も抽象的なものであって、均等に扱うための前提となる諸要素の判断に幅がある以上は、その幅の範囲内における待遇の差に使用者側の裁量も認めざるを得ないところである。・・・・前提要素として最も重要な労働内容が同一であることと、一定期間以上勤務した臨時社員については、年功という要素も正社員と同様に考慮すべきであること、その他本件に現れた一切の事情に加え、Y会社において同一(価値)労働同一賃金の原則が公序ではないということのほか賃金格差を正当化する事情を何ら主張立証していないことも考慮すれば、、Xらの賃金が、同じ勤続年数の女性社員の8割以下となるときは、許容される賃金格差の範囲を明らかに超え、その限度において、Y会社の裁量が公序良俗違反となる判断すべきである」
判旨 一部認容、一部棄却
Ⅰ「同一(価値)労働同一賃金の原則が、労働関係を規律する一般的な法規範として存在していると認めることはできない。・・・・使用者が雇用契約においてどのように賃金を定めるかは、基本的には契約自由の原則が支配する領域である。」同原則は、「不合理な賃金格差を是正するための一個の指導理念となり得ても、これに反する賃金格差が直ちに違法となるという意味での公序とみなすことはできない。」
Ⅱ「労働基準法3条4条のような差別禁止規定は、直接的には社会的身分や性による差別を禁止しているものではあるが、その根底には、およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在していると解される。」これは、「人格の価値を平等に見る市民法の普遍的な原理」であるので、「同一(価値)労働同一賃金の原則の基礎にある均等待遇の理念は、賃金格差の適法性判断において、ひとつの重要な判断要素として考慮されるべきものであって、その理念に反する賃金格差は、使用者に許された裁量の範囲を逸脱しないものとして、公序良俗違反の違法を招来する場合があると言うべきである。
Ⅲ 本件では、Xらの労働内容は、その外形面においても、Y会社への帰属意識という内面においても、女性正社員と同一であるにもかかわらず、Xらを臨時社員として採用したままこれを固定化し、女性正社員との顕著な賃金格差を維持拡大しつつ長期間の雇用を継続したことは、均等待遇の理念に違反する格差であり、公序良俗違反となる。
Ⅳ「均等待遇の理念も抽象的なものであって、均等に扱うための前提となる諸要素の判断に幅がある以上は、その幅の範囲内における待遇の差に使用者側の裁量も認めざるを得ないところである。・・・・前提要素として最も重要な労働内容が同一であることと、一定期間以上勤務した臨時社員については、年功という要素も正社員と同様に考慮すべきであること、その他本件に現れた一切の事情に加え、Y会社において同一(価値)労働同一賃金の原則が公序ではないということのほか賃金格差を正当化する事情を何ら主張立証していないことも考慮すれば、、Xらの賃金が、同じ勤続年数の女性社員の8割以下となるときは、許容される賃金格差の範囲を明らかに超え、その限度において、Y会社の裁量が公序良俗違反となる判断すべきである」。
解説
正社員とパートタイム労働者とが同じ内容の仕事をしているにもかかわらず賃金格差がある場合に、これがもし正社員で男性で、パートタイム労働者が女性という場合であれば、労基法4条違反を理由に違法と解することは可能である。このほか、非正社員としての身分が労基法3条の「社会的身分」に該当するかという論点もあるが、判例は、これを否定している。そのため、正社員とパートタイム労働者の賃金格差は、それが男女差別に該当しないかぎり、短時間労働者法の平均19年度改正までは、違法とすることは解釈論上は難しかった。
このようななか本判決は、まず、賃金の決定について、基本的には契約自由の原則が妥当することを認め、同一(価値)労働同一賃金の原則の法規範性を否定した(判旨Ⅰ)。しかし、労基法3条や4条の根底には「均等待遇の理念」があるといし、この理念は、賃金格差の違法性判断において、1つの重要な判断要素として考慮されるとした(判旨Ⅱ)。そして、本件では、「均等待遇の理念」に反して、公序良俗違反の違法性があると判断した(判旨Ⅲ)。ただし、使用者の裁量も考慮せざるを得ないとし、同じ勤務年数の女性正社員の8割以下となっている部分だけ違法になると判断した(判旨Ⅳ。
不法行為が成立する可能性を一般論としては認めながら、比較可能な正社員がいなかったなどの事情から、不法行為の成立を否定した裁判例として、京都市女性協会事件ー大阪高判平成21年7月16日。一方、本件と同種事案で、契約の自由を貫徹させて、格差の違法性はないとした裁判例として、日本郵便逓送事件ー大阪地判平成14年5月22日)。
その後、短時間労働者法の平成19年改正により、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対して、事業主は差別的取扱いを禁止されることになった。通常の労働者と同視されるための要件は、職務内容の同一性と人材活用の範囲の同一性である。なお、差別的取扱いに該当する場合でも、通常の労働者と同じ待遇を請求する権利を認められるわけではない(ニヤクコーポレーション事件ー大分地判平成25年12月10日)さらには平成26年改正で、有期雇用に関する労契法20条にならって、パートタイム労働者と通常の労働者との間の不合理な労働条件格差を禁止する規定が導入された(8条)。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
労基法3条(均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労基法4条 (男女同一賃金の原則)
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労契法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
パートタイム労働法8条(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条)
(短時間労働者の待遇の原則)
第8条 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
72 賃金格差と不合理性ーハマキョウレックス事件
大阪高判平成28年7月26日(平成27年(ネ)3037号)
事案の概要
正社員と契約社員の間の各種手当の格差は不合理か。
事実
Xは、Y会社と、平成20年10月6日ころ、契約期間1年で、時給1150円、通勤手当3000円、業務内容を配車ドライバーとする労働契約を締結した。この契約は、順次、更新され、本件当時の時給は、1160円となっていた。
Y会社の就業規則上、無期労働契約を締結した正社員と有期労働契約を締結した契約社員の間には、基本給が月給制と時給制という違いがあることに加え、契約社員には、正社員には支給される無事故手当、作業手当、休職手当、住宅手当、皆勤手当および家族手当の支給がなく、正社員にはある定期昇給が原則としてなく、正社員には原則として支給される賞与と退職金は原則なしとされている。通勤手当は、正社員には5万円を限度として通勤距離に応じて支給される(2Km以内は、一律5000円)のに対して、契約社員は、3000円が上限になっていた。Xは、平成23年10月1日ころ、一般労組AのB支部に加入し、Y会社における分会を結成して、その分会長に就任した。
Xは、各種手当等との関係で、Y会社の正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認と、正社員との差額の支払い等を求めて訴えを提起した。なお、Xは破産したため、破産管財人が訴訟を継承した。
1審は、通勤手当の格差のみ労契法20条の不合理なものに該当し、Y会社は差額について、不法行為責任に基づいく損害賠償責任を負うとした(大津地彦根支判平成27年9月16日)。XとY会社の双方が控訴した。
判旨 原判決を変更(無事故手当、作業手当、休職手当についても新たに格差を不合理と認定)。
Ⅰ 労契法20条にいう「期間の定めがあることにより」との文言は、ある有期契約労働者の労働条件が、ある無期契約労働者の労働条件と相違していることだけをとらえて当然に同条の規定が適用されるというものではなく、当該有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違が、期間の定めの有無に関連して、生じたものであることを要する趣旨であると解される。
Ⅱ 労契法20条の不合理性の判断は、有期労働契約者と無期労働契約者との間の労働条件の相違について、職務の内容、当該職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるべきものである。不合理性の主張立証責任については、相違のある個々の労働条件ごとに、当該労働条件が期間の定めを理由とする不合理なものであることを基礎づける具体的事実(評価根拠事実)についての主張立証責任を負い、使用者は、当該労働条件が期間の定めを理由とする不合理なものであるとの評価を妨げる具体的事実(評価障害事実)についての主張立証責任を負う。
Ⅲ労契法20条に違反する労働条件の定めは無効であるが、労契法は、同法12条や13条に相当する規定を設けておらず、労契法20条により、無効と判断された後の労働条件をどのように補充するかについては、労使間の個別的あるいは集団的な交渉にゆだねるられるべきものであることからすれば、裁判所が、明文の規定がないまま、労働条件を補充することは、できる限り控えるべきものである。したがって、関係する就業規則、労働協約、労働契約等の規定を、その合理的な解釈により適用しうるばあいはともかく、そうでない場合には、不法行為による損害賠償が生じうるにとどまるものと解するほかない。
解説
平成24年の労契法改正により。有期雇用労働者と無期雇用労働者との間に労働条件の格差がある場合において、①「労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」(職務の内容)、②「当該職務の内容美配置の変更の範囲」(人材活用の範囲)、③その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない、という規定が導入された(20条、さらに短時間労働者法8条も参照。)
同条の適用をめぐっては、いくつかの解釈上の論点がある。
第1に、文言上、期間の定めがあることによる格差のみを対象とされていることについて、判旨Ⅰは、格差が期間の定めの有無に関連して生じたものであればよいと広く捉える(長澤運輸事件【63】では、賃金格差が定年後の再雇用であることによるものか、有期でことによるものかが問題となり、本判決を同様の解釈から後者であると判断された(判旨外)。
第2に、不合理性の判断は、個々の労働条件ごとに判断されるのか、総合的に判断されるかが問題となり、判旨Ⅱは前者によって判断されるとした(労契法施行通達も同旨)。
第3に、労契法20条の民事上の効力について、判旨Ⅲは、強行的効力はあるが、補充(直律)的効力はないとし、就業規則等の合理的解釈による処理ができないかぎり、具体的な救済は、不法行為による処理ができないかぎり、具体的な救済は不法行為によるものとなるとした(労契法施行通達も同旨)。なお、最近の裁判例では、不合理性を認めた場合でも、格差全額ではなく、8割のみの損害を認めたものがある(日本郵便事件ー東京地判平成29年9月14日)。
第4に、比較の対象とする無期雇用労働者について、職務限定の有期労働者との比較対象者を、その職務に専従する正社員(無期労働者)ではなく、正社員一般としたもの(メトロコマース事件ー東京地判平成29年3月23日)と、有期労働者と業務等が類似の正社員に限定したものとがある(日本郵便事件・前掲)。
労契法20条 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
労契法12条(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
労基法13条(この法律違反の契約)
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
短時間労働者法8条 (短時間労働者の待遇の原則)
第8条 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
73 事業譲渡(1)ー東京日新学園事件
東京高判平成17年7月13日(平成17年(ネ)569号)
事案の概要
事業譲渡にともなう労働契約の承継排除が肯定された例
事実
Xは、A学園の運営するB校の教員であった。A学園は、経営が悪化したしたため解散することになり、学校の経営は新たに設立された学校法人がYが引き継ぐことになった。Yの設立過程で交わされた覚書によると、A学園の解散にともない、その雇用する教職員は退職し、Yは学校運営に必要な教職員を採用することになっていた。その後、Yでの採用を希望するA学園の教職員の中から面接した結果、154名を採用したがXは採用されなかった(応募者183名)。Xは、C労働組合のA学園分会の分会長であったが、採用面接の前に組合活動を公然化させていた。分会に所属する組合員の中には、XのようにYに採用されなかった者もいたが、採用された者もいた。
Yは、Xとの間に雇用関係が存在しないことの確認を求めて訴えを提起したところ、Xは反訴として、Yとの間の雇用関係の存在の確認等を求めた。1審は、Yの請求を棄却し、Xの請求を一部認容した。そこで、Yは控訴した。
判旨 原判決取消し(Yの請求認容)。
Ⅰ Yは、A学園が設置していた学校の教育内容を引き継ぎ、学校名、生徒、校舎も引き継ぎ、教職員にも継続性があるが、主たる事務所や理事の構成が異なり、独自の教育方針の下に運営しており、教職員もいったん解雇されたうえで、Yが認可されることを条件として新規採用されるという前提で採用されており、こうした事実によれば、YとA学園との間に、法的な教職員の雇用契約関係の承継を基礎づうるようなけ実質的な同一性はない。
Ⅱ 本件は、営業譲渡に類似するといえないものではないが、そうであるとしても、「営業譲渡契約は、債券行為であって、契約の定めるところに従い、当事者間に営業に属する各種の財産・・・・を移転すべき債権債務を生ずるにとどまるものである上、営業譲渡人と従業員との間の雇用契約関係を譲受人が承継するかどうかは、譲渡契約当事者の合意により自由に定められるべきであり、営業譲渡の性質として雇用契約関係が当然に譲受人に承継されることになるものと解することはできない。
本件では、覚書に基づきA学園が教職員を全員解雇し、これにより退職した教職員のうち、Yでの採用希望者の中から141名[筆者注:154名採用後、辞退者13名を除いた人数]を新規に採用したものであって、A学園とYとの間に、その雇用契約関係を承認しない旨の合意があったことが明らかである。
Ⅲ「営業譲渡契約において、雇用契約関係を引き継がない合意をすることが自由であるとしても、その合意が労働者を壊滅させる目的でされたり、一定の労働者につきその組合活動を嫌悪してこれを排除する目的でされたものと認められる場合には、そのような合意は公序(憲法28条、労働組合法7条)に反し、無効である」が、本件ではそのような無効事由を認めることはできない。
解説
事業譲渡(本件の当時は、営業譲渡)は、合併とは異なり特定承継と解されており、労働契約関係の承継についても、当事者間で合意により、決定される(かつては、事業譲渡にともない労働契約は当然に承継するという考え方をとる最判所や学説があったが、判旨Ⅱはこの考え方を否定している)。したがって、譲渡当事者は、特定の労働者を承継対象に含めたり、承継対象から排除したりすることができる。労働者は承継対象に含められたときでも、承継を望まない場合には、これを拒否することができる(民法625条1項)が、承継を望む労働者が、承継から排除された場合には、譲渡先に労働契約承継を強制させることは原則としてできない。ただし、事業譲渡後、譲渡元会社が解散し、承継から排除された労働者が解雇されたような場合には、その労働者の保護の必要性はないかが問題となる。
本判決は、本件では譲渡当事者であるYとA学園との間に、A学園の労働者を継承する旨の合意がなかったと認定している(判旨Ⅱ)。これまでの裁判例においては、事案によっては、黙示の承継合意、あるいは譲渡元の従業員を包括的に承継する旨の合意があったと認定したものもあるが、本件では、明示の承継排除の合意があるとされている。この点では、Yが、A学園を退職した教職員の中から、独自の理念と基準で新規採用をしていたという事実が重要である。
譲渡当事者間に承継の合意がない場合でも、譲渡元と譲渡先との間に実質的同一性があり、解雇法理の適用回避のための法人格を濫用が認められた場合には、労務契約の承継が認められることがある(新関西通信システム事件ー大阪地決平成6年8月5日等。なお、、解散ではなく、事業の部分的廃止の事案で、承継を認めた事例として、サカキ運輸ほか事件ー長崎地判平成27年6月16日)。ただし、本判決は、本件では折る同組合壊滅目的のための会社解散といった法人格の濫用はなかったと判断している。また、判旨Ⅲは、承継排除の合意は、不当労働行為に該当する場合等には無効となるとするが、本件では、そのような無効事由はないとされた(→【74】勝英自動車学校事件(大船自動車興業)事件。なお、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意するべき事項に関する指針」(平成28年厚生労働省告示318号)も参照。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
民法625条1項 (使用者の権利の譲渡の制限等)
第625条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
労働組合法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
74 事業譲渡(2)ー勝英自動車学校(大船自動車興業)事件
東京高判平成17年5月31日(平成16年(ネ)418号)
事案の概要
事業譲渡にともなう労働契約の承継排除が否定された例
事実
Y会社とA会社は、ともに自動車教習所の経営等を事業目的とする株式会社である。Xらは、いずれもA会社の従業員であり、B労働組合の組合員である。Y会社は、C会社から、その所有するA会社の全株式を取得した後、A会社が経営していたDモータースクールの事業の全部をA会社から譲りうけた。
A会社とY会社との間の営業譲渡契約によると、Y会社は、A会社の従業員の雇用は引き継がないが、Y会社での再就職を希望する者のうち、Y会社がA会社に通知した者については新たに雇用する、とされていた(営業譲渡契約4条)。
また、この営業譲渡契約の締結までに、Y会社とA会社との間で、
①モータースクールの事業をおこなうためにA会社の従業員をY会社に移行させる、
②ただし、資金等の労働条件が引き下がることに異議のある従業員については、従業員の移行に際して、個別的に排除する
③この目的を達成するために、A会社の全従業員に退職届を提出させ、退職届を提出した者をY会社が再雇用する形式をとる、退職届を提出しない従業員は、A会社の解散を理由に解雇するなどの本件合意が成立していた。
Xらは、Y会社での再雇用後の賃金等の労働条件がA会社にいるときより相当程度下回る水準になることに反対であったことから、退職届を提出しなかった。
その後、A会社は解散し、Xらを含む従業員が解雇された。そこで、Xらは、A会社の解散は偽装解散で、本件解雇は、反組合目的によるもので無効であり、Xらの雇用関係は、Y会社が承継するとして、Y会社に対し、労働契約はY会社が承継するとして、Y会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めて、訴えを提起した。1審は、解雇は無効で、労働契約関係は、Y会社に承継されると判示した。そこで、Y会社は控訴した。
判旨 原判決一部変更(未払い賃金額に関する判示部分は省略)。
Ⅰ Xらに対する本件解雇は、一応、会社解散を理由としているが、実際には、Y会社の賃金等の労働条件がA会社を相当程度下回る水準に改訂されることに異議のある従業員を個別に排除する目的で行われたものということができる。このような目的でおこなわれた解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができないことが明らかであるから、解雇権の濫用として無効になる。
Ⅱ 本件合意中、②と③の合意部分は、民法90条に違反するものとして無効になる。したがって、本件合意は、A会社と従業員との労働契約を、Dモータースクールの事業に同従業員を従事させるため、Y会社との関係で移行させるという原則部分(①)のみが有効なものとして残存することとなる。なお、本件営業譲渡契約4条の定めも、民法90条に違反して無効となる。
そうすると、本件解雇が無効になることによって、解散時においてA会社の従業員としての地位を有することとなるXらについては、A会社とY会社との本件合意の原則部分に従って、Y会社に対する関係で、営業譲渡が効力を生じた日をもって、労働契約の当事者として地位が継承されることとなる。
解説
譲渡元による会社解散を理由とする解雇については、偽装解散の法理などにより、譲渡先との雇用関係を認めるという理論構成もあるうるところではあるが、本判決は、本件の解散は、新たな事業展開を図るためのもので真実解散であると認定している(判旨外)。
しかも、本件では、当事者間に承継排除の合意もあった。ただ、事業譲渡の当事者間において承継排除の合意がある場合でも、その合意に無効事由が認められることがある。東京日新学園事件(→【73】では、承継排除が組合活動を嫌悪した都いうような反組合的な目的でなされた場合には無効となるというような反組合的な目的でなされた場合には、無効となるという一般論を述べていた。本判決では、労働条件の変更に異議を述べた労働者を排除する目的の承継排除の合意は無効とされている(判旨Ⅲ)。もっとも、厳密にいうと、譲渡元から譲渡先に労働契約が承継されるためには、承継排除の合意を無効とするだけでは不十分であり、承継を強制するためのの法的根拠が必要といえる。
本件では、覚書における承継排除に関する合意部分のみが無効(一部無効)となり、原則として承継させるという部分は有効であるという解釈によって、承継を法的に根拠づけている(判旨Ⅱ)。
なお、会社解散による解雇について、解雇権濫用法理(現在のと労契法16条)が適用されるかは議論がある。原則として、こうした解雇は濫用とならないと解すべきだが(大森陸運ほか2社事件ー大阪高判平成15年11月13日等)、裁判例には、適用を肯定するものもあり(三陸ハーネス事件ー仙台地決平成17年12月15日。ただし、結論は解雇有効)、本判決も同じ立場である(判旨Ⅰ)。
民法90条(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
労契法16条 (解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
75 会社分割と労働契約承継法ー日本アイ・ビー・エム事件
最2小判平成22年7月12日(平成20年(受)1704号)(民衆64巻5号1333頁)
事案の概要
会社分割にともなう労働契約承継を、事業主として従事する労働者は、拒否することができるか。
事実
コンピュータの製造、販売等を目的とするY会社は、A会社とHDD(ハードディスク)事業部門を統合するために、まず、Y会社のHDD事業部門の会社分割を実施してB会社を新設した。Y会社とA会社は、合弁会社Cを設立し、Y会社がもつB会社の株式をすべてC会社に譲渡した(B会社は、C会社の完全子会社)。その後、A会社のHDD事業部門もB会社に収集分割された。Xら15名は、Y会社のHDD事業部門の従業員であり、(D労働組合の組合員)、B会社の新設分割において、Y会社との労働契約が承継対象に含められたため、B会社に移籍することになった。そこで、Y会社に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めて訴えを提起した。
Y会社は、その事業場に過半数組合がなかったことから、労働組合承継法7条に定める労働者の理解と協力を得るよう努める措置(7条措置)を行うため、各事業場ごとに従業員代表者に対して、本件会社分割の目的と背景および承継される労働契約の判断基準等について、説明を行い、情報共有のためのデータベースをイントラナットに設置したほか、B会社の中核となることが予定されるE事業場の従業員代表者と別途協議を行い、その要望書に対して書面での回答をしていた。さらに、商法等の一部を改正する法律(平成17年法律第87号による改正前のもの)附則5条1項に定める労働契約の承継に関する労働者との協議(5条協議)としては、Y会社は、従業員代表者への説明に用いた資料等を使って、ライン専門職に各ライン従業員への説明や承継に納得しない従業員に対して、最低3回の協議を行わせ、その結果、多くの従業員が承継に同意する意向を示した。また、Y会社は、Xらに対する関係はでは、D組合との間で、7回にわたり協議をした。
1審および原審ともに、Xの請求を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)
Ⅰ 5条協議は、「労働契約の承継のいかんが労働者の地位に重大な変更をもたらし得るものであることから、分割会社が分割計画書を作成して個々の労働者の労働契約の承継について、決定するに先立ち、承継される営業に従事する個々の労働者との間で、協議を行わせ、当該労働者の希望等をも踏まえつつ分割会社に承継の判断をさせることによって、労働者の保護を図ろうとする趣旨にでたもの」であり、このような5条協議の趣旨からすると、労働契約承継法3条に基づき労働協約が承継対象となった特定の労働者との関係において5条協議が全く行われなかったときには、当該労働者は労働契約承継法3条の定める労働契約承継の効力を争うことができるし、また、5条協議が行われた場合であっても、その際の分割会社からの説明や協議の内容が著しく不十分であった場合にも5条協議義務の違反があったと評価してよく、当該労働者は、同法3条の定める労働契約承継の効力を争うことができる。
Ⅱ 7条措置は、分割会社に対して努力義務を課したものと解され、これに違反したこと自体は労働契約承継の効力を左右する事由になるものではなく、7条措置において十分な情報提供等がされなくなったがために5条協議がその実質を欠くことになったといった特段の事情がある場合に、5条協議違反の有無を判断する一事情として7条措置のいかんが問題になるにとどまるものである。
解説
会社分割とは、会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を別会社または新設会社に承継されることである。(会社法2条29号・30号)。会社分割においては、分割契約(吸収分割の場合)または分割計画(新設分割の場合)に記載された権利義務は、一括して吸収会社または新設会社に承継される(部分的包括承継。同法759条・764条)。労働契約については、労働契約承継法の規定があり、「承継される事業に主として従事するもの」の労働契約が承継対象とされた場合には、」当然に労働契約が承継され(3条)、承継対象とされなかった場合には、一定の期間内に異議を申し出れば承継される(4条)。承継される事業対象とされた場合には、一定の期間内に異議を申し出れば承継されない(5条)。
当該承継を定める労働契約承継法3条は、民法625条の例外を定めたものであるが、労働者の意思に反する承継を認める点で立法論的には批判がある。解釈論としても、5条協議における労働者との協議の手続は労働契約承継の有効要件を解すべきとする見解もある。
この点、本判決は、5条協議がまったく行われなかったとき、あるいは行われても説明や協議の内容が著しく不十分であった場合には、当然承継の効力を争うことができる、とする(判旨Ⅰ)。また、7条措置は努力義務であるため労働契約承継の効力に影響はないが、十分な情報提供等がなかったために5条協議がその実質を欠くといった特段の事情がある場合には、5条協議義務違反の問題となりうるとする(判旨Ⅱ)。ただし、本件では、結論として、7条措置違反もなく、5条協議違反もなかったと判断された(判旨外。逆に5条協議違反を認めた裁判例として、エイボン・プロダクツ事件ー東京地判平成29年3月28日)。
なお、会社分割の際に、労働条件の不利益変更を伴う転籍(新規契約締結・解約型)という形で労働契約を承継させる合意の有効性が問われた事件で、この合意は労働条件をそのまま承継させる利益を労働者から奪うため無効であり、2条1項所定の通知がなく異議申立ての機会が失われている以上、異議申立をしたのと同様の効果(従前の労働条件のままでの強制承継)を主張できるとした裁判例がある(阪神バス事件ー神戸地尼崎支判平成26年4月22日。「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」(平成12年労働省告示127号、平成28年8月改正)も参照)。
会社法2条29号・30号(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
会社法759条
第758条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。)及び株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号及び住所
二―八 〈略〉
会社法764条
第763条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
労働契約承継法3条(承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)
第3条 前条第一項第一号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割契約等に承継会社等が承継する旨の定めがあるものは、当該分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、当該承継会社等に承継されるものとする。
民法625条 (使用者の権利の譲渡の制限等)
第625条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
労働契約承継法4条第4条 第二条第一項第一号に掲げる労働者であって、分割契約等にその者が分割会社との間で締結している労働契約を承継会社等が承継する旨の定めがないものは、同項の通知がされた日から異議申出期限日までの間に、当該分割会社に対し、当該労働契約が当該承継会社等に承継されないことについて、書面により、異議を申し出ることができる。
2 分割会社は、異議申出期限日を定めるときは、第二条第一項の通知がされた日と異議申出期限日との間に少なくとも十三日間を置かなければならない。
3 前二項の「異議申出期限日」とは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日をいう。
一 第二条第三項第一号に掲げる場合 通知期限日の翌日から承認株主総会の日の前日までの期間の範囲内で分割会社が定める日
二 第二条第三項第二号に掲げる場合 同号の吸収分割契約又は新設分割計画に係る分割の効力が生ずる日の前日までの日で分割会社が定める日
4 第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、承継会社等に承継されるものとする。
労働契約承継法5条(その他の労働者に係る労働契約の承継)
第5条 第二条第一項第二号に掲げる労働者は、同項の通知がされた日から前条第三項に規定する異議申出期限日までの間に、分割会社に対し、当該労働者が当該分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継されることについて、書面により、異議を申し出ることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項に規定する労働者が同項の異議を申し出たときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該労働者が分割会社との間で締結している労働契約は、承継会社等に承継されないものとする。
労働契約承継法6条 (労働協約の承継等)
第6条 分割会社は、分割契約等に、当該分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約のうち承継会社等が承継する部分を定めることができる。
2 分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約に、労働組合法第十六条の基準以外の部分が定められている場合において、当該部分の全部又は一部について当該分割会社と当該労働組合との間で分割契約等の定めに従い当該承継会社等に承継させる旨の合意があったときは、当該合意に係る部分は、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定により、分割契約等の定めに従い、当該分割の効力が生じた日に、当該承継会社等に承継されるものとする。
3 前項に定めるもののほか、分割会社と労働組合との間で締結されている労働協約については、当該労働組合の組合員である労働者と当該分割会社との間で締結されている労働契約が承継会社等に承継されるときは、会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項の規定にかかわらず、当該分割の効力が生じた日に、当該承継会社等と当該労働組合との間で当該労働協約(前項に規定する合意に係る部分を除く。)と同一の内容の労働協約が締結されたものとみなす。
労働契約承継法7条(労働者の理解と協力)
第7条 分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
労働契約承継法2条第一項第一号(労働者等への通知)
第2条 会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、会社法第五編第三章 及び第五章 の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割に係る承継会社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七条 に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条第一項 に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条 の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項 の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第四条第三項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
一 当該会社が雇用する労働者であって、承継会社等に承継される事業に主として従事するものとして厚生労働省令で定めるもの
76 就業規則の法的性質ー秋北バス事件
事案の概要
就業規則の変更により定年制を新設し、定年を超えていることを理由に労働者を解雇することは許されるか
事実
Y会社は、就業規則における定年制に関する規定を変更した。従来は、主任以上の従業員には定年制は適用されていなかったが、本件就業規則変更により、満55歳定年制が適用されることとなった。Y会社の主任であったXは、この就業規則変更当時、すでに満55歳に達していたので、定年を理由に解雇通知を受けた。Xは、変更後の規定は自分には適用されなかったとして、就業規則の変更の無効確認等を求めて訴えを提起した。1審はXの請求を認容したが、原審はXの請求を棄却したため、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)
Ⅰ「元来、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」(労働基準法2条1項)が、多数の労働者を使用する近代企業においては、労働条件は、経営上の要請に基づき、統一的かつ画一的に決定され、労働者は、経営主体が定める契約内容の定型に従って、附従的に契約を締結せざるを得ない立場に立たされているのが実情であるり、この労働条件を定期的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件をさだめているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実だる習慣が成立しているものとして、その法的規範性が認められるに至っている(民法92条参照)ものということができる」。
就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否かにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受けるものというべきである」。
Ⅱ「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないと解すべきであるが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解すべきであり、これに対する不服は、団体交渉等の正当な手続による改善にまつほかはない」。
解説
1 就業規則の規定が、労働契約の規定が、労働契約の内容にどのように影響するかについては、労契法の制定前は、労基法の規定からでは明確でなかった。これについては、就業規則の法的性質の問題として、学説上さまざまな議論が展開されてきた。
代表的な見解は、就業規則の法的性質は契約のひな形(草案)であり、労働者の同意があって初めて拘束力が発生するとする契約説と、就業規則は労基法93条(労契法12条)にみられるような労基法と同じ効力(13条を参照)をしていることなどを根拠に、法規範としての性質があるのであり、労働者の同意がなくても拘束力があるとする法規範説であった。
本判決は、契約説、法規範説、のいずれの立場に立つかは必ずしも明確ではないが、結論として、合理的な内容であれば法的規範性が認められ、「就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受ける」とした(判旨Ⅰ)。労契法の制定後は、判旨Ⅰの内容は、同法7条に引き継がれることになった。
2 判旨Ⅱは、就業規則の変更による労働条件の不利益変更について判断した部分である。判旨Ⅱによりいわゆる合理的変更法理が確立することになった。それ以前の学説は、この問題については、契約説では当然だが、法規範説の立場においても、労働者の同意がなければ不利益変更は認められないという見解が有力であった。ところが、判旨Ⅱは、合理性があれば不利益変更も可能であるという独自の法理を創造した。
合理的変更法理については、労働条件の集合的処理という要請が、どうして労働者の同意のない労働条件の不利益変更を正当化するのか、という大きな理論的問題点があった(私的自治の原理との抵触)。他方、継続的な契約関係における労働条件の変更は、契約法上の考え方によると、変更解約告知(→【58】スカンジナビア航空事件)により実現できるはずであるが、変更解約告知は、解雇権濫用法理(→【46】日本食塩製造事件。現在の労契法16条)により、制限されている以上、合理性を条件とすることによって労働者の利益への配慮が担保されているかぎり、使用者に就業規則の変更を通して労働条件を一方的に変更することを認めることは、正当化できるという考え方もあった。
労契法の制定により、合理的変更方法は同法10条(および9条)に取り込まれた。これにより、就業規則により労働条件の不利益変更の有効性は、同法9条および10条の解釈・適用の問題となった。
労基法2条1項(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
民法92条(任意規定と異なる慣習)
第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
労基法93条(労働契約との関係)
第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。
労契法7条
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労契法 9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
労契法10条
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労契法12条(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
労契法13条 (法令及び労働協約と就業規則との関係)
第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
労契法16条 (解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
77 就業規則による労働契約内容の規律ー電電公社帯広電報電話局事件
最1小判昭和61年3月13日(昭和58年(オ)1408号)
判旨 原判決破棄、自判(Xの請求棄却)
Ⅰ「就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に従事すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて、当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる」。
ⅡY公社の就業規則等によれば、Y公社では、職員は常に健康の保持増進に努める義務があるとともに、健康管理上必要な事項に関する健康管理従事者の指示を誠実に遵守する義務があるばかりか、要管理者は、健康回復に努める義務があり、その健康回復を目的とする健康管理従事者の指示に従う義務があるとされているのであるが、以上のY公社の就業規則の内容は、Y公社の職員が労働契約上その労働力の処分をY公社にゆだねている趣旨に照らし、いずれも合理的なものというべきであるから、Y公社とY公社の職員との間の労働契約の内容となっているものというべきである。
解説
本件では、使用者が健康診断受診命令を発するうえで、労働契約上の根拠があるかどうかが問題となり、本判決は、就業規則の内容が合理的であれば、労働契約上の根拠となるという判断を示した(判旨Ⅰ)。そして、就業規則の規定内容の合理性が検討され、結論として、合理性があると判断された(判旨Ⅱ)。
秋北バス事件最高裁大法廷判決(→【76】では、合理性のある就業規則の法的規範性を認めただけで、その場合の労働契約との関係は明確ではなかったが、本判決は、合理的な就業規則は労働契約の内容となると明言した点に、判例としての意義がある。
この判示内容に関しては、現在では、労契法で規定されている。(同法7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない」と規定している。
つまり、労働契約の締結段階においては、労働契約の内容は、就業規則が周知されていて、合理性があることを要件として、原則として、就業規則で定める労働条件によるものとなり(契約内容規律効)。
なお、これに加えて、行政官庁(労働基準監督署長)への届出(労基法89条)や過半数代表からの意見聴取(同90条)が、効力要件となるかについては、これらの手続を踏むことを定める労契法11条は、就業規則の変更にしか言及していないことを理由とする否定説と、これを合意原則にかわる手続的要件として重視する肯定説とがある(なお、労契法10条の定める就業規則の不利益変更の効力、および、同12条の定める就業規則の強行的・直律的効力との関係でも、これらの手続的義務が効力要件となるかは問題となりうる)。
労契法7条による就業規則の拘束力の例外は、就業規則よりも有利な内容の個別的契約が結ばれている場合である。このときには、その個別的契約が優先的に適用される(同条ただし書。→【82】シーエーアイ事件)。
就業規則が制定されていなかった事業場(たとえば、常時10人以上の労働者を使用しておらず、労基法89条による就業規則の作成義務が課されていない事業場)において、新たな就業規則が制定された場合には、労働契約の締結時の問題ではないので、労契法7条は適用されない。就業規則の新設により労働条件が不利益に変更される場合には、就業規則の変更に関する同法10条が類推適用されると解すべきである。
労基法89条 (作成及び届出の義務)
第89条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
労基法90条 (作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
労契法7条第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労契法10条
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労契法11条(就業規則の変更に係る手続)
第11条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条の定めるところによる。
労契法12条 (就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
78 就業規則の周知ーフジ興産事件
最2小判平成15年10月10日(平成13年(受)1709号)
事案の概要
周知されていない就業規則の効力はどうなるか。
事実
A会社は、昭和61年8月1日、労働者代表の同意を得たうえで、同日から実施する就業規則(以下、旧就業規則)を作成し、同年10月30日、B労働基準監督署長に届け出た。旧就業規則は懲戒解雇事由を定め、所定の事由があった場合に懲戒解雇することができる旨定めていた。
A会社は、平成6年4月1日から旧就業規則を変更した就業規則(以下、新就業規則)を実施することとし、同年6月2日、労働者代表の同意を得たうえで、同月8日、B労働基準監督署長に届け出た。新就業規則も懲戒解雇事由を定め、所定の事由があった場合に懲戒解雇事由を定め、所定の事由があった場合に懲戒解雇をすることができる旨定めていた。
A会社は、同月15日、新就業規則の懲戒解雇に関する規定を適用して、Xを懲戒解雇した。その理由は、Xが、同5年9月から同6年5月30日までの間、得意先の担当者らの要望に十分応じず、トラブルを発生させたり、上司の指示に対して反抗的態度をとり、上司に対して暴言を吐くなどして職場の秩序を乱したりしたというものであった。
Xは、本件懲戒解雇以前に、勤務するCセンターの長であるY3に対し、Cセンターに勤務する労働者に適用される就業規則について質問したが、この際には、旧就業規則はCセンターに備え付けされていなかった。
Xは、本件懲戒解雇は違法であるとして、違法な懲戒解雇の決定に関与したA会社の代表取締役であるY1、取締役であるY2、およびY3に対して、民法709条、商法266条の3(現在の会社法429条)に基づき、損害賠償を求めるために提起した。1審および原審ともに、本件懲戒解雇は有効であるとして、Xの請求を棄却したため、Xは上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し
Ⅰ 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別および事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生じるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。
Ⅱ 原審は、A会社は、労働者代表の同意を得て、旧就業規則を制定し、これをB労働基準監督署長に届け出た事実を確定したのみで、その内容をCセンター勤務の労働者に周知させる手続が採られていることを認定しないまま、旧就業規則に法的規範としての効力を肯定し、本件懲戒解雇が有効であると判断している。原審のこの判断は違法である。
解説
労契法の制定前から、判例は、就業規則の拘束力が認められるためには、労働者への周知を必要とすると判示していた(判旨Ⅰ)。現在では、労契法において、就業規則が拘束力をもつためには、周知が効力要件として明記されている(7条。不利益変更の場合においても、周知は効力要件である(10条))。
就業規則の周知は、労基法106条1項で義務づけられており、それに違反した場合には罰則も科される(労基法120条1号)。そこでいう周知の方法は、「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法としては、「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること」が定められている(労規則52条の2第3号)
これに対して、労契法における周知の方法は、必ずしも、労基法上の周知義務の履行同じ方法による必要はなく、実質的に、労働者に集合規則の内容を知りうる状況がそんざいしていればよいと解されている(労契法施行通達も参照)。なお、前記通達は、労契法7条の周知については、同条の文言上、「周知させていた」となっていることから、当該作業場の労働者だけでなく新たに労働契約を締結する労働者に対しても行う必要があるが、後者への周知は、労働契約の締結と同時であってもよいとしている。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
労契法7条
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労契法10条
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労基法106条1項(法令等の周知義務)
第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
労基法120条1号
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
労基法施行規則52条の2第3号
第五十二条の二 法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
79 就業規則の不利益変更の合理性(1)ー第四銀行事件
最2小判平成9年2月28日(平成4年(オ)2122号)(民衆51巻2号705号)
事案の概要
定年延長にともなう就業規則の変更により、労働者の従来の定年後の賃金を不利益に変更できるか。
事実
Y銀行では、従来、定年は55歳となっていたが、健康に支障のない男性行員は58歳まで在職可能であった(その場合、定例給与は54歳時の額が引き続き支給された。)その後、Y銀行は行員の約90%で組織されているA労働組合の同意を得て、就業規則を変更し、定年を60歳にまで引き上げると同時に、55歳以降の賃金は、54歳時の賃金よりも引き下げられ、その結果、Xの賃金は54歳時の3分の2となった。
Xは、本件就業規則変更は無効であり、55歳以降も変更前の就業規則による賃金を請求する権利があるとして、その差額の支払いを求めて訴えを提起した。
1審は本件就業規則変更の合理性は認めなかったが、労働協約の拡張適用(労組法17条)により、本件変更がXに適用されるとした。原審は本件就業規則変更の合理性を認め、本件変更のXへの適用を認めたため、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)
Ⅰ「合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代替措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況を総合考慮して、判断しべきである。
Ⅱ(1)本件では、勤務に耐える健康状態にある男子行員において、58歳までの定年後在職をすることは確実であり、その間、54歳時の賃金水準等を下回ることのない労働条件で勤務できると期待することもごうりてきということもできる。そうすると、本件就業規則変更は、このような合理的な期待に反して、55歳以降の年間賃金が54歳時のそれの63ないし67%となり、定年後在職制度の下で58歳まで勤務して得られると期待することができた賃金等の額を60歳定年近くまで勤務しなければ得ることができなくなるというのであるから、勤務に耐える健康状態にある男子行員にとっては、実質的にみて労働条件を不利益に変更するに等しい。そして、その実質的な不利益は、賃金という労働者にとって、重要な労働条件に関するものであるから、本件就業規則変更は、これを受忍させることを許容することができるだけの高度な必要性に基づいた合理的な内容のものでなければならない。
(2)本件就業規則変更による不利益はかなり大きなものである。本件就業規則変更の当時、60歳定年制の実現が国家的な政策課題とされ、定年延長の高度の必要性があったとし、定年延長による人件費の負担増加などに対応するために、55歳以降の賃金水準等を変更する必要性も高度なものであった。変更後の就業規則の内容は、他行の賃金水準や社会一般の賃金水準と比較して、かなり、高いものであった。本件就業規則変更により、60歳まで安定した雇用が確保されるという利益は、決して小さいものではないし、福利厚生制度の適用延長等は、賃金減額の不利益を緩和するものである。
(3)本件就業規則変更は、行員の約90%で組織されているA組合との交渉、合意を経て、労働協約を締結した上で、行われたものであるから、変更後の就業規則の内容は、労使間の利益調整がされた結果としての合理的なものであると一応、推測することができる。
解説
1 判旨Ⅰは、判例上確立された合理的変更法理における合理性の判断要素について、従来の判例を集大成し、これを整理して示したものである。
その後、合理的変更法理を成文化した労契法10条は、合理性の判断要素として、
①不利益の態度、
②労働条件の変更の必要性、
③変更後の就業規則の内容の相当性、
④労働組合等との交渉の状況、
⑤その他の就業規則の変更に係わる事情
の5要素を明示している。判断要素が減少したようにもみえるが、実質的な変更はない(労契法施行通達)
2 本判決は、まず本件就業規則変更は、これまで58歳まで働いて得ていた賃金を60歳まで働かなければ得ることができない点で、労働条件の不利益変更があり(しかも、その不利益変更の程度は大きい)、しかも賃金に関する変更なので、高度の必要性がなければならないとする(判旨Ⅱ)。
これは、賃金などの重要な労働条件に実質的な不利益をもたらす場合には、高度の必要性を要するとした判例(大曲市農業協同組合事件ー最3小判昭和63年2月16日)を踏襲したものである。
他方、60歳定年制の導入と、それにともなう人件費抑制の必要性という観点から、変更の必要性は高度であるとし、また、変更後の労働条件の内容は同業他社や世間相場からみて相当性があり、変更にともなってさらに、Xは、非組合員ではあるが、圧倒的多数派である労働組合が変更に同意をしている
(判旨Ⅱ(3))。本判決は、以上の点を総合的に考慮して合理性を肯定した。
労組法17条 (一般的拘束力)
第17条 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
労契法10条
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
80 就業規則の不利益変更の合理性(2)ーみちのく銀行事件
最1小判平成12年9月7日(平成8年(オ)1677号)(民衆54巻7号2075号)
事案の概要
就業規則の変更により、高年従業員の賃金を不利益に変更できるか。
事実
Y銀行は、昭和62年1月に専任職制度を導入しようとした。その主たる内容は、55歳以上の行員の基本給を55歳到達直前の額で凍結し、管理職階の者を専任職に移行させ、専任職手当を基本給に追加して支払うというものであった。この提案について、従業員の73%を組織するA労働組合は同意したが、約1%しか組織していないB労働組合は反対した。Y銀行は、B組合の同意をえないまま、就業規則を変更して、専任職制度を実施した。
その後、Y銀行は、新たな専任職制度を導入しようとした。その主たる内容は、管理職階以外の者も55歳に達すれば原則として専任職手当は廃止し、賞与の支給率を削減するというものであった。A組合はその内容に同意したが、B組合は専任職制度自体に反対し続けた。Y銀行は、B組合の同意のないまま、就業規則を変更して新専任職制度を導入した。
判旨 原判決一部破棄、差戻し。
Ⅰ Y銀行は、発足時から60歳定年制であったので、55歳以降にも所定の賃金を得られるということは、単なる期待にとどまるものではなく、該当労働者の労働条件の一部となっていた。本件就業規則変更が、Xらの重要な労働条件を不利益に変更する部分を含むことは明らかである。
Ⅱ 本件就業規則変更は、Y銀行にとって高度の経営上の必要性があったが、Xらの不利益が全体的にみて小さいものであるということはできないし、本件就業規則変更後のXらの賃金は、その年齢、企業規模、賃金体系等を考慮すると、格別高いものであるということはできない。
Ⅲ 本件における賃金体系の変更は、短期的にみれば、特定の層の行員にのみ賃金コスト抑制の負担を負わせているであり、その負担の程度も大きく、それらの者は中堅層の労働条件の改善などといった利益を受けないまま退職することとなる。就業規則の変更によってこのような制度の改正を行う場合には、一方的に不利益を受ける労働者について不利益性を緩和するなどの経過措置を設けて適切な救済を併せ図るべきである。経過措置の適用にもかかわらず依然として大幅な賃金の減額をされているのであり、このような経過措置の下においては、Xらとの関係で賃金面における本件就業規則変更の内容の相当性を肯定することはできない。
B組合の組合員であったXら6名は、この2回の就業規則変更(本件就業規則変更)は無効であるとして、専任職制度が適用されなかった場合に得べかりし賃金との差額の支払いを求めて訴えを提起した。1審はXらの請求を一部認容したが、原審はXらの請求を棄却したため、Xらは上告した。
Ⅳ 本件では、行員の約73%を組織するA組合が変更に同意しているが、Xらの被る不利益の程度や内容を勘案すると、賃金面における変更の合理性を判断する際にA組合の同意を大きな考慮要素と評価することは相当ではない。
Ⅴ 本件就業規則変更を行う経営上の高度の必要性は認められるが、賃金体系の変更は、中堅層の労働条件の改善をする代わり55歳以降の賃金水準を大幅に引き下げたものであった、差し迫った必要性に基づく総賃金コストの大幅な削減をはかったものなどではない。そうすると、本件就業規則変更は、Xらのような高年層の行員に対しては、もっぱら大きな不利益のみを与えるものであって、他の諸事情を勘案しても、Xらに対し、高度の必要性に基づいた合理的な内容の者であるということはできない。したがって、本件就業規則変更のうち賃金減額の効果を有する部分は、Xらのその効力を及ぼすことができない。
解説
本判決は、第四銀行事件(→【79】)と比較した場合、その結論に違いがあるだけでなく、次の2点において注目すべき違いがある。
第1に、本判決は、変更の高度の必要性があると認めているにもかかわらず、55歳以降の行員の大幅な賃金削減が差し迫った必要性に基づくものではないとして、変更の必要性を結論としては否定している(判旨Ⅱ、Ⅴ)。
第2に、多数組合が変更に同意しているにもかかわらず、少数組合の組合員であるXらの不利益性の程度や内容を勘案すると、多数組合の同意を大きな考慮要素とすることはできないと述べている(判旨Ⅳ)。
本件では、企業にとっての賃金コストの削減による不利益が55歳以降の従業員に過度に偏っていたという事情が、変更の高度の必要性があり、多数組合の同意を得ていたという合理性を強く肯定する事情を覆すくらいの影響を与えたといえよう。
なお、本判決は、変更後の就業規則の効力をXらに及ぼすことができないとする(判旨Ⅴ)は、この判示部分が就業規則(賃金減額の効果を有する部分)に合理性がなく無効であるので、それらXらに適用することができないとしたのか、それとも就業規則には、合理性ががあるが、Xらに適用されるかぎりで合理性が否定されて無効になるとしたのか(相対的無効)については、解釈に争いがある(これは既判力の相対効とは別の問題である)。
81 労働者の同意による就業規則の不利益変更ー山梨県民信用組合事件
最2小判平成28年2月19日(平成25年(受)2595号)(民衆70巻2号123号)
事案の概要
労働者の同意による就業規則の不利益変更は、そのような場合に認められるか。
事実
A信用組合は経営破綻を回避するため、Y信用組合に平成15年1月に吸収合併されることとなった。この合併後の新規程を承認し、それにより、A信組の職員の退職金は、合併時のA信組の規程(旧規程)と比べて、退職金額の算定基礎給与額が半分になり、また、基礎給与額に乗じられる支給倍数に、旧規程にはなかった上限がもうけられた。
また旧規程では退職金総額から厚生年金給付額控除して支給する内枠方式が採用されていたが、新規程でも内枠方式が維持された(ただし、Y信組では、従前内枠方式は採用されなかった)。さらにA信組が加入していた企業年金保険が、合併時に解約されて還付された金額も、退職金総額から控除するとされた(Y信組は、企業年金保険には未加入であった)。
A信組の職員で管理職であったXらは、以上の変更について同意書に署名押印したが。事前の説明会で配布された同意書案には、Y信組の従前からの職員と同一水準の退職金額が保障される旨記載されたいた。
Y信組は、その後別信用組合と平成16年2月合併し、その際、新退職金制度がせいていされるまで、平成16年の合併前の在職期間は自己都合退職の係数が用いられ、同合併後の在職期間は自己都合退職者には、退職金を不支給とする変更が追加された。Xらはその説明を受けたうえで、説明報告書に署名した。
以上の変更により、Xらは退職時に退職金額がゼロとなったり、平成16年の合併後に自己都合退職した者は、退職金が支給されなかったりするなどの不利益を受けた。そこで、Xらは、旧規程に基づく退職金の支払いを求めて訴えを提起した。1審および原審は、Xらの請求を棄却したため、Xらは上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し。
Ⅰ「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり、このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要であるとされることを除き、異なるものではないと解される(労働契約法8条、9条本文参照)」。
Ⅱ「使用者が掲示した労働所条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服するべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば・・・・当該変更に対する労働者の合意の有無についての判断は、慎重にされるべきである。
そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更により労働者にもたれらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきでものと解するのが相当である」。
解説
就業規則による労働条件の不利益変更について、合理性を要件とすることなく労働者の合意だけで変更が認められるかについては、学説上争いがあったが、判旨Ⅰでは、積極的合意説を正面から定める労契法8条(および同法9条本文)に言及したうえで、これを肯定した(なお、過去の裁判例には、労契法9条の反対解釈によるものもあった(協愛事件ー大阪高判平成22年3月18日)。
また、同意の有効性については、賃金全額払いの原則から逸脱する合意の有効性についての判断基準を示したシンガー・ソーイング・メシーン事件(→【91】)および日新製鋼事件(→【92】)の最高裁判決を参照しながら、自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由の客観的な理由客観的な存否を問題とするというアプローチを採用した。(判旨Ⅱ。賃金の個別的合意による不利益変更について、同様のアプローチをとる下級審判決として→【94】ザ・ウインザー・ホテルズインターナショナル事件)
さらに本判決は、同意の有無を判断するうえでの具体的な判断基準として、不利益の内容・程度に加えて、変更を受け入れる行為に至る経緯やその態様、労働者への情報提供・説明の内容といった手続的な要素もあげており、結論としても、退職金額がゼロとなるような大きな利益がありうる変更であるにもかかわらず、その点についての情報提供や説明が不十分であったことを重視して、原判決を破棄している。
なお、Xらの中には、非管理職で、支給基準の変更を定める労働協約の適用を受けていた者もいたが、本判決は、労働協約を締結した執行委員長は規約上労働協約の締結権限があったか審理されていないとして、これも差戻しの理由の1つとされた(判旨外)。
労契法8条(労働契約の内容の変更)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
労契法9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
82 就業規則の不利益変更と附加変更特約ーシーエーアイ事件
事案の概要
個別的に合意された労働条件を、就業規則により引き下げることは認められるか。
事実
Xは、情報処理システムに関する調査研究コンサルタント業務等を目的とするY会社に、当初はアルバイトとして勤務し、その後、平成9年4月1日に、正社員として採用された。契約内容は、労働契約期間は1年で、賃金は年棒制として620万円であり、毎月の賃金は。36万⑤000円とされていた。同年8月1日に、Y会社は、業績の悪化を背景に就業規則を変更し、それにより年棒制は廃止され、Xの給与は、成果主義を採り入れた月棒制となった。Xはその業績評価が低く、8月の月例給与は16万5000円になった。その後、Xは、同年9月19日に退職した。Xは、未払い賃金の請求を求めて訴えを提起した。
判旨 一部認容。
「本件においては、XとY会社は期間を1年とする本件雇用契約により、旧賃金規定の支給基準等にかかわらず、支払賃金額は月額36万5000円、年棒額 620万円の確定がくとして合意をしているのであり、このような年棒額及び賃金月額を契約規則を変更したとして合意された賃金月額を契約期間の途中で一方的に引き下げることは、改定内容の合理性の有無にかかわらず許されないものといわざるを得ない」。
解説
個別的に合意された労働条件を、就業規則の変更により、不利益に変更することができるかどうかは、従来から議論があるところでであったが、本判決は、これを明確に否定している。
労契法の制定後は、これは同法10条の解釈問題となり、さらに同法7条とも関係してくる。7条のほうは、労働契約の締結時における就業規則の効力を規定するものであるが、そのただし書きにおいて、「労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分」は、就業規則の基準を上回っている限り、効力が維持されるということを定めている。この規定により、労使が個別的に労働条件について合意している場合、それが就業規則の基準を上回っているかぎり(同法12条も参照)、その合意は有効となる(つまり、就業規則の適用が排除される)ということが明確となった。
こうした個別的労働条件の特約がある場合には、その後に就業規則の不利益変更が行われた場合でも、「労働条件に4おいて、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」に該当すれば、変更後の就業規則の適用から免れることができる(10条ただし書)。
本件は労契法施行前の事件であるが、仮に労契法の規定にあてはめれば、どうなるであろうか。Xが採用時にY会社と合意した賃金等の個別的労働条件は、同情7条ただし書きにより有効となるが、それが10条のただし書の「就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」に該当するかどうかは意思表示の問題となる。特に本件では、変更前の旧就業規則の規定について、これを遵守する旨の誓約書を提出していたという事情があったので、変更後の就業規則にも従う趣旨と解することもできそうである。しかしその一方で、本件では、契約期間が1年と定められていて、特に年棒制で賃金が定められていたことからすると、少なくとも賃金は、その1年間は当初の合意額で確定的に支払うという内容の契約であったと意思解釈をするのが妥当であろう。そうすると、本件では、黙示的に、就業規則による変更を排除する特約が結ばれていたと解すべきことになる。
本件のような場合とは異なり、労働契約の締結当時は就業規則の適用を受けるが、その中の一定の労働条件については就業規則の不利益変更があっても維持される旨の特約を結ぶという場合もありうる。このような特約も、労契法10条ただし書の「就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」にがいとうすることになり、有効である。
労契法7条
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労契法10条第
10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労契法12条(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
83 政治的思想による差別と損害賠償ー東京電力(千葉)事件
千葉地判平成6年5月23日(昭和51年(ワ)698号)
事案の概要
共産党シンパであることを理由として査定差別された労働者は、使用者に損害賠償請求をすることが認められるか。
事実
電力会社であるY会社は、反共労務政策の徹底を図るため、共産党員が同党支持者である従業員に対して、職級、資格、役職位において差をつけたり、定期昇給、賞与における査定を著しく低位にしたりするなど、賃金関係の処遇において格差をつけてきた。Xらは、Y会社の従業員であり、共産党員またはその支持者であった。
Xらは、共産党員または同党支持者であることを理由として賃金差別等の差別を受けてきたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めて訴えを提起した。
判旨 一部認容、一部棄却
Ⅰ Y会社は、反共労務政策を有しており、Xらが共産党員または、同党支持者であることをしっていたこと、Xらは、集団として、他の従業員と比較すると、著しく低位の賃金関係の処遇を受けていること、その格差の程度およびXらがそろって最低というべき処遇を受けているという事態は、通常の効果査定の結果としての処遇格差とは到底考えにくいものであることから、特別の事情のないかぎり、Y会社は、Xらに対し、Xらが共産党員または同党支持者であることを理由の1つとして、他の従業員よりも賃金関係の処遇面での低い処遇を行ってきたものとすいにんするのが相当である。
ⅡY会社の立証にうよっては、Xらが並外れて劣悪な能力や勤務であって、それが顕著な格差発生の唯一の原因であるという見方を正当化するのは困難であり、Y会社が、Xらが共産党員または同党支持者であることを理由として不当に低い賃金関係の処遇をしたとの推認を覆すことはできない。
Ⅲ 従業員の配置、担当業務の決定、役職位の任用および資格の付与率は、使用者が企業運営上および人事管理上の必要性に基づきその裁量により行うものであるが、この裁量権は、法令および公序良俗の範囲内で行使されるべきであり、これを逸脱し、その結果従業員の法律上の権利利益を侵害する場合には、その権利行使は不法行為上の違法性を帯びることになる。
Ⅳ Xらは、政治的思想だけによって職級、職位、資格および査定の面で他の従業員と差別的処遇を受けないという期待的利益を、労基法3条等に反して、共産党であり同党を支持していることを理由としてしんがいされたのであり、Y会社は、Xらの被った損害を賠償する義務がある。
Ⅴ Xらの財産的損害の数額を高度の確実性のある程度に認定することは必ずしも容易ではないかが、本件では、財産的損害が発生していること自体は明らかであるから、諸般の事情を基礎として、社会通念および経験則に基づき可能な限り合理性のある損害額を認定して損害の公平な分担を図ることが要請される事案であり、この場合、相当程度確実性のある者として損害額を認定するためには、この点について立証責任を負担するXらにとって相当控えめな認定をせざるを得ない場合もある。
Xらの賃金関係の低い処遇は、その全部が違法な差別による結果生じたものではなく、Xらの能力、業績、資質に対する正当な考課査定の結果と差別的な考課査定の結果が混在した結果であると認められるものであり、とりらの影響が優越しているともいえない本件では、Xらが被った違法差別により生じた部分は、相当控えめに見ても、平均的賃金とXらが受けた賃金の間の格差の少なくとも3割程度は存在するものと認められる。
解説
労基法3条は、国籍、信条、社会的身分を理由とする労働条件についての差別的取扱いを禁止している。労基法3条に違反した法律行為は無効となるし、事実行為であれば不法行為(民法709条)を根拠として、労働者は損害賠償請求することができる。本件では、政治的思想に基づく賃金差別の事案であり、これは、「信条」による差別に該当する。昇格や査定については、原則として、使用者に広い裁量が認められているが、法令や公序良俗(民法90条)に違反する場合には、不法行為となる(判旨Ⅲ)。労基法3条違反の場合も同様である(判旨Ⅳ)。
本判決は、まず、Y会社の共産党員等に対する嫌悪とそれに基づく反共労務政策があったこととXらが著しく低い賃金であったことから、Y会社の組織的差別意思を推認し(判旨Ⅰ)、Xらの勤務ぶりからは、その推認を覆すことはできないとし(判旨Ⅱ)、Xらは「政治的思想だけによって職級、職位、資格および査定の面で、他の従業員と差別的処遇を受けないという期待的利益」を侵害されたとして、Y会社に対して損害賠償責任を認めている(判旨Ⅳ)。
損害額の算定については、同種事例で、財産的損害の認定の困難さから、慰謝料の支払いのみを認める裁判例もある(たとえば、松阪鉄工所事件ー津地判平成12年9月28日)が、本判決は、財産的損害も認めている。その際、Xらの低賃金の原因には正当な査定による」部分もあるとし、違法な査定による格差部分(3割)のみの賠償責任を認めている(判旨Ⅴ)。
労基法3条(均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法90条(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
84 男女同一賃金の原則ー兼松事件
東京高判平成20年1月31日(平成15年(ネ)6078号)
事案の概要
男女別コースに基づく男女の賃金格差について、損害賠償請求は認められるか。
事実
Xら6名は、総合商社Y会社の女性従業員である。Y会社では、その前身のA会社およびB会社のころから実質的には男女別の賃金体系が導入されていた。その後、昭和60年に職業別人事制度が導入されるにともない、男性のほとんどは一般職に、女性は事務職にそのまま編入された。なお、平成7年の賃金の額を比較すると、女性(事務職)は男性(一般職)の、25歳において、81.61%、30歳において67.40%、35歳において60.77%、40歳、45歳において約57%となっていた。
Xらは、同期の一般職の男性従業員との間に格差があるのは、違法な男女差別であるとして、平成4年4月以降の同年齢の一般職標準本棒(月例賃金、一時金)との差額の支払い等を求めて訴えを提起した。1審はXらの請求を棄却したので、Xらは控訴した。
判旨 控訴一部認容(Xらのうち2名は、男性重従業員との間に明確な職務内容の差があるとして請求棄却、その他は請求の一部認容)。
Ⅰ 「勤続期間が近似すると推認される同年齢の男女の社員間、あるいは、職務内容や困難度に同質性があり、一方の職務を他方が引き継ぐことが相互に繰り返し行われる男女の社員間において賃金について相当な格差がある場合には、その格差が生じたことについて合理的な理由が認められない限り、性の違いによって生じたものと推認することができる」。
Ⅱ 「格差の合理性について判断するには、男女間の賃金格差の程度、Xらの女性社員がY会社において実際に行った仕事の内容、専門性の程度、その成果、男女間の賃金格差を規制する法律の状況、一般企業・国民間における男女差別、男女の均等な機会及び待遇の確保を図ることについての意識の変化など、様々な諸要素を総合勘案して判断することが必要である」。
Ⅲ 昭和60年の人事制度の改定後、一般職と事務職との間で、截然と業務内容を区別することは難しくなっていたが、それにもかかわらず、Xらと職務内容に同質性がある一般職男性との間には相当な賃金格差があり、これは、性の違いによって生じたものと推認される。このような状態を形成、維持したY会社の措置は、労基法4条、不法行為の違法性の基準とすべき雇用関係についての私法秩序に反する違法な行為である。
Ⅳ 事務職の勤務地が限定されていることは、一般職と事務職の給与体系の格差を合理化する根拠とはならないし、「職掌別人事制度の導入と併せて旧転換制度が設けられてたが、その運用の実情は転換の要件が厳しく、転換後の格付が低いもので、・・・・給与の格差を実質的に是正するものとは認められない」。
解説
労基法4条は、女性であることを理由とした、男性との賃金差別を禁止している。同条違反には罰則の適用もある(労基法119条1号)が、私法上は、本件のような使用者に損害賠償を請求する事例が多い。
男女別賃金表を設ける場合が同条違反の典型例である(秋田相互銀行事件ー秋田地判昭和50年4月10日等)が、このほか、同じ職務内容であるにもかかわらず、賃金に差がある場合にも同条違反と認められる傾向にある(日ソ図書事件ー東京地判平成4年8月27日等)。
他方、男女を異なるコースで採用し、職務内容に差をつけるという男女別コース雇用制については、「女性であることを理由とする」格差ではなく、採用、配置、昇進等の違いによるものなのかで、労基法4条には違反しないと考えられてきた。
男女雇用機会均等法の制定後に広がった新たなコース別雇用制(総合職と一般職、本件では、一般職と事務職)においては、女性も総合職を選択することができる以上、女性の多くが一般職であるとしても、これを募集・採用における男女差別と評価することは困難である。
もっとも、従来の男女別コース雇用制を、そのまま新たなコース別雇用に転換しただけで、その後もなお男女間の格差が残存しているときには、配慮・昇進に関する男女差別禁止が強行規定となった改正男女雇用機会均等法の施行(平成11年)後は、同規定(現行の6条1号)に違反し、公序良俗となるとする裁判例もある(野村証券事件ー東京地判平成14年2月20日等)。これに対して、本判決は、同様の場合について、労基法4条違反と判断したものとして注目される。
本判決は、まず、職務内容や困難度に同質性がある男女間に相当な賃金格差がある場合は、合理的な理由がなければ性の違いによる格差であると推認されるとする(判旨Ⅰ)。合理的な理由の存否は、諸要素の総合的な考慮による(判旨Ⅱ)は、本判決は、具体的な判断において、Xら女性労働者の職務内容とその困難度が一般職の男性労働者と同質であるかという点を重視している(判旨Ⅲを参照)。
なお、本判決(判旨Ⅳ)に対しては、勤務地の限定が、賃金格差を合理化するものではないとしている点、および本件における一般職への転換制度の運用の実情は、賃金格差を正当化するものではないとしている点(1審の判断は逆)について議論の余地があろう。
労基法4条 (男女同一賃金の原則)
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労基法119条1号
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
男女雇用機会均等法6条1号第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
85 公民権の行使の保障一十和田観光電鉄事件
最2小判昭和38年6月21日(昭和36年(オ)1226号)(民集17巻5号754頁)
事案の概要
市議会議員に当選した従業員に対する懲戒解雇は有効か
事実
旅客運送事業等を営むY会社に雇用されたXは、労働組合の執行委員長の地位にあったところ、労働組合の推薦を受けて、市議会議員に立候補することになった。そこで、Y会社社長Aに了解を求めたところ、A社長は、一応書類を提出するように述べた。そこでXは、翌日書類を提出し、立候補の届け出をした。
昭和34年5月1日、Xは市議会銀選挙に当選した。Xは、同2日に選挙管理委員会から、当選証書を受領し、翌日が日曜日であったことから、同4日(月曜日)に社長に議員就任を伝え、公職就任中は休職扱いにして欲しいと述べた。ところが、Y会社は、Xの行為は、就業規則の懲戒解雇条項である「従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したとき」に該当するとして、5月1日付けでXを懲戒解雇した。
そこで、Xは、この懲戒解雇は無効であるとして、労働契約関係の存続確認を求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、Xの請求を認めたため、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求認容)。
懲戒解雇は、「普通解雇と異なり、譴責、減給、降職、出勤停止等とともに、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰であると解するのが相当である。ところで、本件就業規則の前記条項は、従業員が単に公職に就任したために懲戒解雇するというのではなくして、使用者の承認を得ないで公職に就任したために懲戒解雇するという規定ではあるが、それは、公職の就任を、会社に対する届出事項にするにとどまらず、使用者に証人にからしめ、しかもそれに違反した者に対しては制裁罰としての懲戒解雇を課するものである。しかし、労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の前記条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。従って、所論のごとく公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に付するは格別、同条項を適用して従業員を懲戒解雇に付することは、許されないものといわなければならない。
解説
労基法7条は、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は、公民の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる」規定し、労働者の公民権の行使を保障している。
本判決によると、使用者の承認を得ないで公職に就任したときには懲戒解雇を行うと定める就業規則の規定は、労基法7条の趣旨に反して無効となる。ただし、本判決は、使用者の業務遂行を著しく阻害するおそれのある場合に、普通解雇することまでは否定していない。下級審には、市議会銀に当選した63歳の労働者に対する普通解雇を有効と判断した裁判例(社会保険新報社事件ー東京高判昭和58年4月26日)や町議会議員就任を理由とする休職処分を有効と判断した裁判例(森下製薬事件ー大津地判昭和58年7月18日)がある。
なお、平成21年に導入された裁判員制度において、労働者が裁判員に選ばれた場合にも、この規定が適用されるため、使用者は、裁判員の職務を執行するために労働者が休暇を取得すりことを認めなければならない。
また、「最判員の参加する刑事裁判に関する法律」は、労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことなどを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしたはならない、と定めている(100条)これは、普通解雇をも否定する趣旨と解される。
「公の職務」には、このほか、
①国または地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務(たとえば、衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、検査審査員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務)
②国または地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務(たとえば、民事訴訟や労働委員会における証人)、
③地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務(たとえば、選挙管理人)が含まれる(昭和63年3月14日基発150号)。また、「公民としての権利」とは公職の選挙権および被選挙権、最高裁判所の裁判官の国民審査、特別法の住民投票、憲法改正の国民投票、地方自治法による住民の直接請求、選挙権および住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出などが例としてあげられている(同通達)。ただし、訴権の行使は、原則として、「公民としての権利」には含まれない(同通達)。
労基法7条(公民権行使の保障)
第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律100条(不利益取扱いの禁止)
第百条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
86 違約金の約定一野村証券事件
東京地判平成14年4月16日(平成10年(ワ)19822号)
事案の概要
海外留学後に退職した労働者に対する留学費用の返還請求は認められるか
事実
平成元年4月1日証券会社に入社したYは、会社に選抜されて同4年2月から6年7月までフランスに留学し、MBA資格を取得した後、帰国した。Yは、帰国後は、ニューヨークのA会社に出向し、その後、同8年5月15日にX会社を退職した。
X会社は、留学から帰国後5年以内に自己都合で退職した者に対する留学費用の一部の返還を定める「海外留学生派遣要綱」等を根拠に、Yの留学費用は、留学を終え、帰国後5年間X会社において就業した場合には債務を免除する旨の免除特約付きで渡した貸金であるとして、その一部の返還を求めて訴えを提訴した。
判旨 請求認容
Ⅰ 「会社が負担した海外留学費用を労働者の退社時に返還を求めるとすることが労働基準法16条違反となるか否かは、それが労働契約の不履行に関する違約金ないし損害賠償額の予定dえあるのか、それとも費用の負担が会社から労働者に対する貸付けであり、本来労働契約とは独立して返済すべきものであり、一定期間労働した場合に返還義務を免除する特約を付したものかの問題である」。その「いずれであるかは、単に契約条項の定め方だけではなく、・・・・当該海外留学の実態等を考慮し、当該海外留学が業務性を有しその費用を会社が負担すべきものか、当該合意が労働者の自由意思を不当に拘束し、労働関係の継続を強要するものかを判断すべきである。」
Ⅱ Yの海外留学は、業務命令の形式をとっているが、労働者個人の意向による部分が大きく、留学中の行動はすべて労働者が個人として利益を享受することができ、業務との関連性は抽象的、間接的なものにとどまり、費用債務免除までの期間が5年であることなどを考慮すると、海外留学費用は、会社からの貸付けの実質を有し、その返還規定は労働者の自由意思を不当に拘束し労働者の継続を強要するものではないので、労基法16条には違反しない。
解説
労基法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約を禁止している。ここでいう「労働契約の不履行」の典型例は労働者の退職(藤堂義務の不履行)である。同条は、違約金や損害賠償額の予定をにより、労働者を労働契約に縛り付けることを禁止する規定であって、前借金相殺の禁止(労基法17条)や強制貯金の禁止(同18条)と同趣旨の規程であり、強制労働の禁止(同5条)とも関連する。
労働者が使用者の費用で海外留学に派遣された後に退職するとき、その労働者に留学費用を返還させるという契約を結ぶことは、形式的には、労基法16条に違反する可能性があり、この点の判断は、過去の裁判例では分かれていた(こうした契約を有効としたものとして、長谷工コーポレーション事件ー東京地判平成9年5月26日、無効としたものとして、富士重工事件ー東京地判平異性10年3月17日、新日本証券事件ー東京地判平成10年9月25日)。
本判決は、本件の海外留学費用についてmそれが労働契約の不履行に関する違約金ないし損害賠償額の予定であるのか、それとも労働契約とは独立した消費貸借契約で、一定期間労働した場合の返還義務免除特約が付いたものかの判断は、「当該海外留学の実態等を考慮し、当該海外留学が業務性を有しその費用を会社が負担すべきものか、当該合意が労働者の自由意思を不当に拘束し労働関係の継続を強制するのかを判断すべき」ものとする(判旨Ⅰ)。
本件では、業務とに関連性は抽象的、間接的なものにとどまり、返還義務免除特約付きの消費貸借契約として有効と判断している(判旨Ⅱ)。
技能実習の期間に使用者が負担した費用を、労働者が退職した場合返還させる場合にも、労基法16条違反が問題となる。裁判例では、看護学校の入学生への修学資金について、将来、貸与者の経営する病院で一定年数以上勤務すれば返還を免除するという取扱いは同条違反とされ(和幸会事件ー大阪地判平成14年11月1日)、また、美容師が使用者の意向に反して退職した場合には採用時に遡って美容指導の講習手数料を支払う旨の約定が同条違反とされている(サロン・ド・リリー事件ー浦和地判昭和61年5月30日)。一方、タクシー事件ー浦和地判昭和61年5月30日)。一方、タクシー運転手の第二種免許取得のための研修費用を、一定の勤続をしない場合に返還させる条項は、同条違反でないとされている(コンドル馬込交通事件ー東京地判平成20年6月4日等)。
裁判所の中には、労働契約締結時期に支払われる一時金(サイニングボーナス)を、1年以内の退社の場合には返還する旨の規定も労基法16条に違反するとしたものもある(サイニングボーナス)を、1年以内の退社の場合には返還する旨の規定も労基法16条に違反するとしたものもある(日本ポラロイド事件ー東京地判平成15年3月31日)。
労基法5条(強制労働の禁止)
第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労基法16条(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
労基法17条(前借金相殺の禁止)
第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
労基法18条(強制貯金)
第18条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
② 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
③ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
④ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
⑤ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
⑥ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
⑦ 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
87 労働基準法上の労働者一横浜南労基署長(旭紙業)事件
最1小判平成8年11月28日(平成7年(行ツ)65号)
事案の概要
傭車運転手に対する労災保険の適用は認められるか。
事実
Xは、A会社のB工場において、自らの持ち込んだトラックを運転して、A会社の製品の運送業務に従事してきたところ、ある日、B工場の倉庫内で、運送品をトラックに積み込む作業をしていた際に転倒し傷害を負った。XはY労基署長に対して、労災保険法に基づいて療養補償給付と休業補償給付の請求をしたことろ、YはXが同法上の労働者にあたらないことを理由に不支給処分を行った。
Xの就労の実態は次のようなものであった。
①A会社のXに対する業務の遂行に関する指示は、原則として、運送物品、運送先、および納入時刻に限られ、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばず、また、1回の運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、運送以外の別の仕事が支持されることはなかった、
②勤務時間については、A会社の一般の従業員のように始業時刻および終業時刻を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受け、その荷積みを終えたならば帰宅することができ、翌日は、出社することなく、直接、最初の運送先に対する運送業務を行うこととされていた、
③報酬は、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表に基づき出来高が支払われていた、
④Xの所有するトラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金もすべてXが負担していた、
⑤Xに対する報酬の支払いにあたっては、所得税の源泉徴収ならびに社会保険料および雇用保険料の控除はされておらず、Xはこの報酬を事業所得として確定申告をしていた。
Xは、Yの不支給処分の取消しを求めて、訴えを提起した。1審はXの請求を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)。
「Xは、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、A会社は、運送という業務の性質上、当然に必要とされる運送物品、運送先の及び納入時刻の指示をしていた以外には、Xの業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、XがA会社の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、Xが労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、Xは、専属的にA会社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送系の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送量よりも1割5分低い額とされちたことなど・・・・を考慮しても、Xは、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである」。
解説
労基法の適用を受ける労働者は、同法9条において、「職業の種類を問わず、事業または事業所に・・・・に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されている。本判決は、労災保険法上の労働者も労基法上の労働者と同じであることを前提としている。
具体的に、どのようなタイプの労働者が労基法9条の「労働者」に該当するのかについては、法文上の基準は明確でないが、通常は、労働者の判断は、使用従属関係の下での労働提供といえるかどうかという観点から行われるものとされ、その判断は雇用・請負等の法形式にかかわらず、その実態に基づき行われるべきとされている(新宿労基署(映画撮影技師)事件ー東京高判平成14年7月11日等を参照)。上記裁判例はその具体的な判断について、
「業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容・支払われる報酬の性格・額・使用者とされる者と労働者とされる者との間における具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無、時間的及び場所的拘束性の有無・程度、労務提供の代替性の有無、業務用機材等機械、器具の負担関係、専属性の程度、使用者の服務規律の適用の有無、公租などの公的負担関係、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断するのが相当である」と述べている(昭和60年の労働基準法研究会「労働基準法の「労働者」の判断基準について」も参照)。
本件は、いわゆる傭車運転手の労働者性が争われた事件であるが、Xが「業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事して」おり、事業者性が強いこと、A会社から受けていた指示は、「運送という業務の性質上当然に必要とされる」ものにすぎないとされ、時間的、場所的な拘束も、A会社の従業員よりも緩やかであることが考慮され、労働者性が否定された。
過去の判例には、証券会社の外務員および大工について労働者性を否定したもの(それぞれ、山崎証券事件ー最1小判昭和36年5月25日、藤沢労基署事件ー最1小判平成19年6月28日)、研修医の労働者性を肯定したもの(関西医科大学事件ー最2小判平成17年6月3日)などがある。
労基法9条(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
88 労務の不提供と賃金請求権一片山組事件事件
最1小判平成10年4月9日(平成7年(オ)1230号)
事案の概要
病気で自宅療養中の労働者が、従来よりも軽易な仕事を申し出て、使用者が断った場合に、地慇懃請求は認められるか。
事実
Xは、土木建築の施工、請負等を行うY会社に昭和45年に雇用された。Xは、平成2年夏、バセドウ病に罹患し、Y会社に申告しないまま通院して治療をうけていた。Xは、同3年8月に本件耕司現場において現場監督業務を行うように指示されたが、その際に、自己の病気を申告し、本件耕司現場での現場作業業務ができないこと、残業は1時間に限り可能であり、日曜と休日の勤務は、不可能である旨の申出をした。
Y会社は、Xが現場監督業務に従事することは不可能であり、Xの健康面、安全面でも問題を生じると判断して、平成3年10月1日から当分の間の自宅治療命令を発した。Xは、同命令に対して、事務作業を行うことはできるとして、主治医作成の診断書を提出したが、Y会社は自宅治療命令を持続した。その後、同4年2月5日に、Xは本件工事現場における現場監督業務に復帰した。
Y会社は、平成3年10月1日から、平成4年2月5日までの間は、Xが、現実に労務提供を行わなかったので、その期間の賃金を支給せず、平成3年冬期一時金を減給支給した。Xは、この不支給期間における賃金及び一時金の未払分の支払いを求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求を認容したが、原審は、Xの請求を退けたので、Xは上告した。なお、再戻審では、Xの請求が認容されている(その上告審は、最3小決平成12年6月27日(上告棄却、上告不受理)
判旨 原判決破棄、差戻し。
「労働者が職種や職務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。
そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じれれている業務によって、労務の提供が債務の本旨にしたがったものとなるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である」。
解説
労働者が実際に労務に従事していない場合においても、債務の本質に従った履行の提供をしていると判断されれば(民法493条を参照)、賃金の請求が認められる。その場合、の理論構成は、通常、債務の本旨に従った労務の提供の受領が拒否されることにより、労働債務は履行不能となり、それは、使用者の責に帰すべき事由によるので、民法536条2項に基づく労働者の賃金請求権は失われない、というものである。
本判決は、労働者が提供を申し出ている労務の内容が、使用者に命じられた業務以外であっても、それが、「その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして、当該労働者が配置される現実的可能性があれば、債務の本旨に従った履行の提供があると解すべきとしている。
労働者の職種や業務内容が特定されていない場合には、労働者は使用者の配転命令に服して広範囲の労務に従事しなければならない可能性が労働契約上あるのであり、(→【36】日産自動車事件)、そうである以上、罹患したときにたかたか従事していた業務を基準に債務の本旨に従った労務提供の有無を判断するのは妥当ではない、ということであろう。
このことから、使用者は、労働者が病気等によって従来の業務が遂行できなくなった場合、その労働者の労務提供に関して、労働契約上可能な範囲で配転を行うなどの配慮をすることが求められるという考え方が、判旨には含まれると解することができるであろう。同様の配慮の要請は、休職期間満了にともなう労働契約の終了の場合にまで及ぼされている(→【40】JR東海事件)。
債務の本旨に従った履行の提供は、解雇の場合のように使用者が受領拒絶の意思を明確に表明している場合には、不要とされるが、客観的に就労する意思と能力を有していることは必要である(ペンション経営研究所事件ー東京地判平成9年8月26日等)。
民法493条(弁済の提供の方法)
第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
民法536条2項(債務者の危険負担等)
第536条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
89 年棒制一日本システム開発研究所事件
東京高判平成20年4月9日(平成18年(ネ)5366号)
事案の概要
年棒制が適用されている労働者の次年度の年棒額について合意が成立していない場合、次年度の年棒額はどのようにしてけっていされるべきか。
事実
Yは、中央官庁等からの受託調査・研究等を事業内容とする公益法人である。Xらは、この研究室長、研究員であり、Y法人と期間の定めのない労働契約を締結していた。Y法人では、20年以上前から年棒制が導入されていた(ただし、就業規制に根拠をもつものではなかった)。年棒制の適用者(年棒者)の賃金の決定過程は、まず毎年5月までに個人業績評価が行われ、Y法人の役員がこの個人業績評価等を参考にして、交渉開始の目安額を計算し、6月に労使の個別交渉が行われ、最終的な合意額と支払方法が決定されていた。決定された額は7月から支給され、4月から6月までに支給された額との清算が行われた。
平成17年3月、Y法人は研究員らに対して、年棒交渉に向けて、業績成績等の提出を命じたが、提出されなかったため、Y法人の理事が受託実績収支をもとに個人業績評価を自ら行い、年棒者との交渉にあたった。
なお、同年9月にY法人は、経営悪化から組織体制を変更し、個人業績評価の仕方を改め、評価資料の作成は研究室長が行うのではなく、理事自ら作成することとなった。Y法人は、年慕王交渉で合意に達しなかったXらの給与を、暫定的に算定して支給したが、支給額は、前年度よりも大幅に減少していた。そこで、Xらは、従前の年棒額との差額の支払いなどを求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求をほぼ認めた(年棒賃金の差額支払いについては認容)。そこで、Y法人は控訴した。
判旨 原判決変更(年棒賃金の差額支払いについては認容)。
Ⅰ 「期間の定めのない雇用契約における年棒制において、使用者と労働者との間で新年度の賃金額についての合意が成立しない場合は、年棒額決定のための成果・業績評価基準、年棒額決定手続、減額の限界の有無、不服申立手続等が制度化されて就業規則等に明示され、かつ、その内容が公正な場合に限り、使用者に評価決定権があるというべきである」。本件では、上記要件が満たされておらず、前年度の年棒額をもって、次年度の年棒額とせざるを得ない。
Ⅱ「年棒額は、各年度(当年4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、年棒交渉によって決定されていたこと、年棒交渉は、各年度開始後に実施され、年棒額が決定された後に、その後に支給される賃金により、それまでに支給された賃金と決定された年棒額との差額が精算されていたことからすると、交渉期限の次年度への延期が合意されるなどの特段の事情の認められない限り、当該年度中に年棒額について合意が成立しなかった場合には、前年度の年棒額をもって、次年度の年棒額とすることが確定するものと解すべきである。
解説
本件では、賃金額を本人の業績等を評価して年単位で決定するという年棒制が導入されていた研究員らについて、労使間で年棒額の合意が得られなかった場合の年棒額をどのように決定するかが問題となっている。考え方としては、使用者に決定権があるというもの(その場合でも、決定権の濫用ということはありうる。中山書店事件ー東京地判平成19年3月26日を参照)と、前年度の賃金額となるというものがありうる。
本判決は、使用者に決定権が認められるのは、年棒額決定のための評価基準、決定手続、減額の限界の有無、不服申立手続等が就業規則に明示されていて、その内容が公正な場合にかぎるとし(判旨Ⅰ)、その要件を満たさない場合には、年棒額は前年度の額となるとした。本件では、そもそも年棒額が就業程度で明示されておらず、使用者の決定権が否定されたため、Xらの賃金は前年度の水準で維持されることとなった。
このような決定方法をとる場合に、交渉のどの段階までに合意が成立しなければ前年度の額に確立するのかという点が問題となるが、本件では、当年度中(3月末まで)であると判断されている(判旨Ⅱ)。
なお、有期労働契約の途中での一方的な賃金の引下げが許されないとした裁判例として【82】シーエーアイ事件がある。
90 賃金直接払いの原則一電電公社小倉電話局事件
最3小判昭和43年3月12日(昭和40年(オ)527号)(民集22巻3号562頁)
事案の概要
使用者は、労働者から退職金債権を譲り受けた者に、退職金を支払わなければならないか。
事実
AはXに対して加えた暴行の償いのために、AがY公社を退職するときに支払われるべき退職金の債権を昭和37年4月7日に、弁護士Bにいったん譲渡し、Bはこれを同年8月15日にXに譲渡した。Aは同年5月19日にY公社を退職したところ、Y公社は同年6月7日にAに対して退職金を支給した。Y公社は、Aから債権譲渡の通知を受けていたが、その後、Aはこの債権譲渡は強迫によることを理由に取り消す旨、Y公社に通知していた。Xは、Y公社に対し、譲り受けた退職金債権の支払を求めた。1審は、退職金債権の譲渡の取消しが無効であったとしても、Aは債権の準占有者であり、Y公社は善意無過失の弁済により、その債務が消滅している(民法478条)として、Xの請求を棄却した。原審は、労基法24条1項の賃金直接払いの趣旨から、XはAを介して、退職金の支払いを受けるしかないとして、Xの控訴を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)。
「労働基準法24条1項が「賃金は直接労働者に支払わなければならない。」旨を定めて、使用者たる賃金支払義務者に対し、罰則をもってその履行を強制している趣旨に徴すれば、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、その支払いについてはなお同条が適用され、使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、したがって、右賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払いを求めることは許されるものと解するのが相当である」。
解説
1 労基法24条は、賃金直接払いの原則を定めている。直接払いの原則の趣旨は、賃金のいわゆるピンハネを防止することにある。この原則については、同条の定める通貨払いの原則や全額払いの原則とは異なり、例外が認められていない。
直接払いの原則があるため、使用者は、賃金を、労働者の委任を受けた代理人に支払うことは許されないし、未成年者の代理人に支払ことも許されない(労基法59条も参照)。ただし、使者(秘書など)への支払いは、本人に対する支払いと同視できるものなので適法と解されている(昭和63年3月14日基発150号)
2 本判決は、労働者がその賃金債権を、自己の債権者に譲渡した場合に、使用者は、賃金をその債権の譲受人人支払うことは許されないとしている(なお、退職金が労基法上の賃金(11条)に該当することについては、→【91】シンガー・ソーイング・メシーン事件の判旨Ⅰ)。通常の債権譲渡であれば、譲渡人が債務者に債権譲渡を通知していれば、譲受人は債務者に対応することができる(民法467条1項)が労基法24条はその例外を定めたものと解されているのである。
本判決の考え方からすれば、労働者が、自己の第三者に対する債務について、使用者に対して自己の賃金から弁済することを委任した場合にも、使用者がその第三者に賃金を支払えば、労基法24条に違反することになるであろう。しかし、このような場合は、使用者が委任契約に基づき弁済をし、その委任費用んぼ償却請求権(民法650条)と労働者の賃金支払請求権との相殺をしたものと法律構成することも可能である。そうすると、これは、賃金全額払いの原則との抵触の問題となる(関西精機事件ー最2小判昭和31年11月2日)。また、合意相殺として適法となる可能性もある→【92】日新製鋼事件)。
3労働者の賃金が差し押さえられた場合に、使用者が労働者の差押え債権者賃金を支払うことは、労基法違反にならないと解されている。ただし、その支払い期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない(民事執行法152条1項。その上限は33万円なので、賃金が44万円を超える場合は、には、33万円を超える額は差押が可能となる。民事執行法施行令2条を参照)。また、国税徴収法に基づく差押えについても、労基法24条は適用されないが、やはり、差押え限度額が定められている(76条)なお、賃金ではないが、労基法上の災害補償や労災保険給付は差押え(および譲渡)それ自体が禁止されている(前者は、労基法83条2項、後者は、労災保険法12条の52項)。
民法478条(弁済の提供の効果)
第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
労基法24条1項(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労基法59条
第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
労基法11条
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
民法467条1項(債権の譲渡性)
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法650条(受任者による費用等の償還請求等)
第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
民事執行法152条1項(差押禁止債権)
第152条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
民事執行法施行令2条
第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
二 支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円
三 支払期が毎旬と定められている場合 十一万円
四 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
五 支払期が毎日と定められている場合 一万千円
六 支払期がその他の期間をもつて定められている場合 一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。
国税徴収法76条
第七十六条 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。この場合において、滞納者が同一の期間につき二以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第四号又は第五号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。
労基法83条2項 (補償を受ける権利)
第83条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
② 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
労災保険法12条の5第2項
第12条の5 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
② 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
労災保険法12条の5第2項
第12条の5 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
② 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
91 賃金全額払いの原則(1)一シンガー・ソーイング・メシーン事件
最2小判昭和48年1月19日(昭和44年(オ)1073号)(民集27巻1号27頁)
事案の概要
労働者により退職金債権の放棄は有効か。
事実
Y会社における西日本の総責任者の地位にあったXは、Y会社を退職することになったが、その際、「XはY会社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してY会社に差し入れた。その背景には、次のような事情があった。Y会社は、Xが退職後、直ちにY会社の一部門と競合関係にある他の会社に就職することを知り、さらにXの在職中におけるXとその部下の旅費等経費の使用につき、書面上つじつまの合わない点から幾多の疑問をいだいていたので、この疑問にかかる損害の一部を補填する趣旨で、Xに対し前記の書面に署名をもとめたところ、これに応じて、Xがこの書面に署名したというものであった。
Y会社が退職金を支給しなかったところ、Xは、就業規則所定の退職金の支払いを求めて訴えを提起した。1審はXの請求を認めたが、原審は、退職時の退職金債権の放棄は労働者の抑圧された医師によるものでないので、有効であると判断し、Xの請求を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)
Ⅰ 「本件退職金は、就業規則において、その支給条件が予め明確に規定され、Y会社が当然にその支給義務を負うものというべきであるから、労基法11条の「労務の対償」としての賃金に該当し、したがって、その支払いについては、同法24条1項本文の定めるいわゆる全額払いの原則が適用されるものと解するのが相当である」。
Ⅱ「全額払の原則の趣旨するところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者の賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者んたるXが退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金を債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、全額払の原則が意思表示の効力を否定する旨のものであるとまで解することはできない」。
Ⅲもっとも、右全額払の原則の趣旨とすることろはなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それがXの自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないと解すべきであるが」、原審の認定した「事実関係に表れた諸事情に照らすと、右意思表示がXの自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたということができるから、右意思表示の効力はこれを肯定して差し支えない」。
解説
1 労基法11条の賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問がわず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいう。退職金も、就業規則においてその支給条件があらかじめ明確に規定され、使用者が当然にその支払義務を負うものであれば、同条の賃金に該当し、そのため、全額払いの原則をはじめとする労基法24条1項で定められている原則の適用されることになる(判旨Ⅰ)。
2 全額払の原則の趣旨は、労働者に賃金が確実に支払われないことによって、その経済生活が不安定となるのを防止することにある。さらに、未払い賃金が残ることにより、労働者に対する足止め(労働継続の強制)となることの防止も、その趣旨とされている。
全額払いの原則の例外は、法令に別段の定めがある場合または過半数代表との書面による労使協定がある場合である。法令による例外としては、所得税の源泉徴収(所得税法183条)、社会保険料の控除(厚生年金保険法84条、健康保険法167条、労働保険の保険料徴収に関する法律32条)、財形貯蓄金の控除(勤労者財産形成促進法6条1項1号ハ)がある。
3 本件では、労働者が賃金債権の放棄したために、使用者が賃金を支払わなかったことが、全額払いの原則に反するかどうかが問題となった。判旨Ⅱは。Xの退職に際し、みずから退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合には、全額払いの原則に反しないという注目すべき判断を示した。
もっても、判旨Ⅲでは、労働者の賃金債権の放棄を常に有効とするのではなく、「自由な意思に基づくものであることが明確でなければならない」という限定を付している。原審では、在職中の意思表示は自由意思によるものとはいえないが、退職時における意志表示は自由意思によるものといえるいえると判断していたが、最高裁はそのような二分法は採用していない。
本判決は、Xの放棄の意思表示は、Xの自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたと判断した。ここでいう合理的な理由には、労働者が賃金債権を放棄することによって、事実上ないし法律上の利益を得るといった事情があげられる。その後の判例には、本件と同じ全額払いの原則との関係で放棄の有効性を否定したもの(北海道国際航空事件ー最1小判平成15年12月18日)、労基法37条の割増賃金請求権との関係で放棄の有効性を否定した割増賃金請求権との関係で放棄の有効性を否定したもの(テックジャパン事件ー最1小判平成24年3月8日)がある。
労基法11条
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
労基法24条1項(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
所得税法183条(源泉徴収義務)
第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。
厚生年金保険法84条
第84条 基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。
3 前項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。
健康保険法167条(保険料の源泉控除)
第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
労働保険の保険料徴収に関する法律32条(賃金からの控除)
第32条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項又は第三項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
2 第八条第一項又は第二項の規定により事業主とされる元請負人は、前条第一項の規定によるその使用する労働者以外の被保険者の負担すべき額に相当する額の賃金からの控除を、当該被保険者を使用する下請負人に委託することができる。
3 第一項の規定は、前項の規定により下請負人が委託を受けた場合について準用する。
勤労者財産形成促進法6条1項1号ハ
労基法37条(勤労者財産形成貯蓄契約等)
第六条 この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。)をいう。
一 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第一項(第五号を除く。)において同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの
ハ 当該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。次項第一号ニ及び第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
92 賃金全額払いの原則(2)一日新製鋼事件
最2小判平成2年11月26日(昭和63年(オ)4号)(民集44巻8号1085頁)
事案の概要
労働者の退職金債権と使用者の労働者に対する債権とを相殺する合意は有効か
事実
Aは、Y会社に在職中、住宅資金として、Y会社、B銀行、C労働金庫から借入れをした。これらの借入金は、Aの退職の際に、退職金等から返済することになっていた(B銀行とC労働金庫への返済は、Y会社にあらかじめ委任していた)。Aは、交際費の出費に充てるために借財を重ね、破産宣告を受けた。Y会社は、事前の取決め通り、Aの依頼もあって、退職金等からAの借入金の返済をし、退職金等は、その返済費用を控除した額を支払った。Aの破産管財人は、Y会社による退職金等からの残債務の控除は労基法24条に違反して違法であるとして、未払の退職金の支払いを求めて訴えを提起した。1審は、Xの否認権の行使を認めて、その請求の一部を認容したが、原審は、否認権の対象とならないとして請求を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)
Ⅰ(1)労基法24条1項本文の定める賃金全額払いの原則は、「労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規程にいはんするものとはいえないを解するのが相当である。
(2)もっとも、右全額払いの原則の趣旨にかんがみると、右同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならないことはいうまでもない」。
ⅡAは、Y会社の担当者に対し、各借入金の残債務を退職金等で返済する手続をとるように自発的に依頼しており、委任状の作成、提出の過程においても強要にわたるような事情はまったくうかがわれず、各清算処理手続が終了した後においてもY会社の担当者の求めに異議なく応じ、退職金計算書、給与等の領収書に署名押印しているのであり、また、本件各借入金は、いずれも、借入れの際には、抵当権の設定はされず、低利かつ相当長期の分割弁済の約定のもとにAが住宅資金として借り入れたものであり、特にY会社借入金およびB銀行借入金については、従業員の福利厚生の観点から、利子の一部を会社が負担するなどの措置が執られるなど、Aの利益になっており、Aについても、各借入金の性質および退職するときは退職金等により、その残債務を一括返済する旨の前記各規定を十分認識していたことがうかがえるのであって、これらの点に照らすと、本件相殺におけるAの同意は、同人の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在していたというべきである。
解説
賃金は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺が禁止されている(労基法17条)が、さらには、使用者からの一方的な相殺は、全額払いの原則(労基法24条)にも反するとしてきた(関西精機事件ー最2小判昭和31年11月2日、日本勧業経済界事件ー最大判昭和36年5月31日)。本件は、使用者と労働者の合意による相殺にも、同様に解すべきかが問題となった。労基法24条は、強行法規なので同条により使用者に禁止されている行為は、たとえ労働者の同意があっても適法となるわけではない。ところが、本判決は、賃金債権の放棄に関する判例(→【91】シンガー・ソーイング・メシーン事件)を受けtw、合意相殺の場合にも「労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合には、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」は適法になると判示した。
この判例は、労基法の規制の個別的同意による適用除外(デロゲーション)を認める趣旨にも読めるために、注目されるところである。なお、自由意思かどうかの認定は、「厳格かつ慎重におこなわなければならない」としており、最高裁も、こうした適用除外が例外的なものであることを示している。
本件では、AにY会社に対する債務があり、総裁に対する同意の意思表示の形成過程に強要にわたる事情がなく、また、その債務自体がAに有利な面もあったという事情が、Aの自由意思を認めるに足りる合理的な理由になったといえよう。
労基法24条1項(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労基法17条(前借金相殺の禁止)
第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
93 賃金全額払いの原則(3)一福島県教組事件
最1小判昭和44年12月18日(昭和40年(行ツ)92号)(民集23巻12号2495頁)
事案の概要
過払い賃金の清算のための調整的相殺は、どのような場合に有効とみとめられるか。
事実
Y(県)の県立高等学校の教職員であるXらは、昭和33年9月5日から15日まで、勤務評定反対のために職場離脱行為を行った。Yは、その時間分について給料の減額おおび勤勉手当の減額をすべきであったが、事務が間に合わなかったため、昭和33年9月分の給料(支給日は9月21日)と後期勤勉手当(支給日は12月15日)はXらに全額支給した。その後、Yは、昭和34年1月に過払いの返納を求め、それに応じない場合には翌月の給料から減額する旨通知したところ、Xらは返納に応じなかったため、Yは過払い分を同年2月分と3月分の給料から減額した。そこで、Xらは、この減額措置は、労基法24条1項の全額を払いの原則に違反することなどを理由に、減額分の支払い地公法25条2項で全額払いの原則が定められ、その一方で労基法24条1項は適用除外となっている(地公法58条3項)
1審は、9月分の給料の過払い分の減額は、その通知をしたのがその請求権の発生時から約4か月も経過した後のものなので違法であるとし、勤勉手当の過払いの減額は、その通知は請求権の発生時の翌月になされたものであるので適法であると判断した。XらとY双方が控訴したが、原審は、いずれも棄却した。そこで、Xらだけが上告した。
判旨 上告棄却
「賃金支払事務においては、一定期間の賃金がその期間の満了前に支払われることとされている場合には、支払日後、期間満了前に減額事由が生じたとき」または、減額事由が賃金の支払日に接着して生じたこと等によるやむを得ない減額不能または計算未了となることがあり、あるいは賃金計算における過誤、違算等により、賃金の過払が生ずることのあることは避けたいところであり、このような場合、これを避けがたいところであり、このような場合、これを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除できるとすることは、右のような賃金支払事務における実情に徴し合理的理由があるといいうるのみならず、労働者にとっても、このような控除をしても、賃金と関係のない他の債権を自働債権とする相殺の場合とは趣を異にし、実質的にみれば、本来支払われるべき、賃金は、その全額の支払いを受けた結果となるのである。
このような事情と前記24条1項の法意とを併せて考えれば、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この見地からすれば、許されるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でねければならないものと解せられる。
解説
本件では、使用者が、過払い賃金を、翌月以降の賃金から控除するという調整的相殺(法的には使用者の不当利得返還請求権と賃金債権の相殺)は、賃金全額払いの原則に抵触するか(労基法24条1項ただし書の例外的要件を満たさなければ適法とならないか)が争点となっている。本判決は、「その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないもの」であれば、全額払いの原則には抵触しないと判示している。その根拠は、賃金支払い事務における合理的理由(前払い方式をとっている場合には過払いは不可避的に生じること)と労働者にとって過払い賃金の清算は不当な結果をもたらすものではないこと(本来、支払われるべき賃金が支払われたにすぎないこと)というものである。
判旨は、調整的相殺の適法性に関する具体的な判断基準を「過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でねければならない」とし、本件の勤勉手当の過払いの減額のほうは、この基準に合致していると判断した。
なお、行政解釈は、「前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は、賃金それ自体の計算に関するものであるから、法24条の違反とは認められない」としているあああ(昭和23年9月14日基発1357号)。
労基法24条1項(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
地公法25条2項
第二十五条 職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
2 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
地公法58条3項
第五十八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
3 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。
94 賃金減額合意の有効性一ザ・ウインザー・ホテルズインターナショナル事件
札幌高判平成24年10月19日(平成23年(ネ)330号・527号)
事案の概要
賃金減額に対する合意は、どのような場合に有効に成立したものとされるか。
事実
Xは、平成19年2月に、Y会社の経営するホテルに料理人として、採用された。当初の賃金は、前の職場の水準を考慮して、基本賃金年額624万2300円(基本賃金月額52万191円)であった。しかし、職場内での賃金が不統一であり、公平でないということから、同年4月、料飲部のゼネラルマネージャーAから、賃金年額を500万円に減額する旨の提案を受けたところ、Xは「ああわかりました」などと応答するにとどまった(以下、本件応答)。同年6月25日から、Y会社は、Xに対して、基本給22万4800円、職務手当15万4400円を支払うようになった。
Xは、賃金が不当である旨の講義はせず、Y会社から支払われる賃金を受領していたところ、平成20年4月になって、Y会社から、減額された賃金が記載された労働条件確認書に署名押印するように求められ、Xは、同月29日、これに応じて、Y会社に書面を提出した。Xは、平成21年4月に退職した。Xは、賃金減額の同意がないのに減額されたと主張して、未払い賃金の支払を求めて訴えを提起した(その他の請求もあるが割愛する)。1審は、平成20年4月29日に減額の合意があったとして、Xの請求を一部認容した。Y会社は控訴し、Xも附帯控訴した。
判旨 控訴棄却
Ⅰ 「賃金減額の説明ないし提案を受けた労働者が、これを無下に拒否して経営者の不評を買ったりしないよう、その場では当たり障りのない対応をすることは往々にしてあり得る一方で、賃金の減額は、労働者の生活を大きく左右する重大事であるから、軽々に承諾できるはずがなく、そうであるからこそ、多くの場合に、労務管理者は、書面を取り交わして、その時点における賃金減額の同意を明確にしておくのであって、賃金減額に関する口頭でのやり取りから労働者の同意の有無を認定するについては、事柄の性質上、そのやり取りの意味等を慎重に吟味検討する必要があるというべきである。
これを本件についてみるとXの上記応答(筆者注:本件応諾)は、・・・・Xの立場からすれば、入社早々で、しかもまだ試用期間中の身であり、この提案を拒否する態度を明確にして会社の不評を買いたくないという心理が働く一方で、入社早々これほどの賃金減額を直ちに受け入れる心境になれるはずのないことは見易い道理であって、Aの提示額の曖昧さと相まって、上記のとおり、抽象的な言い回しであることも併せて考えれば、・・・・この応対をもって、年額124万円余りの賃金減額にXが同意したと認めることはできない」。
ⅡXの本件応答は、「会社からの説明は分かった」という趣旨に理解されること、減額された賃金の支払いに対して明示的な講義をしていないこと、労働条件確認書は簡略で、とくに複雑なものではないこと、などから、Xは、平成20年4月時点では、賃金年額について、自由な意思で同意したものと認められる。
解説
労契法によると、労働者と使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる(8条)。これは、労契法の基本にある合意原則の中核的な内容であるが、その合意原則には、労働者の同意がない場合には、労働条件の変更が認められないという意味(消極的合意原則)と、労働者の合意があれば労働条件の変更が認められるという意味(積極的合意原則)がある。合意原則をめぐって問題となるのは、労働者にとって不利益な内容の合意に、積極的合意原則がどこまで妥当するのかである。
オーソドックスな労働法の発想によると、労働者と使用者との間には、対等性が欠如されているため、労働者に不利な内容の合意については、その有効性を容易には、認めるべきではないことになる。
この点については、特に賃金減額の黙示の合意の成否や有効性をめぐって議論がなされてきた。裁判例の中には、賃金減額は、実質的に、賃金放棄と類似の問題状況となるので、賃金放棄の意思表示の有効性に関する判例の厳格が基準(→【91】シンガー・ソーイング・メシーン事件)を適用して、労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することを要するとするものもある(更生会社三井埠頭事件ー東京高判平成12年12月27日等)
本判決は、Xの本件応対について採用から2か月後のものであることも考慮して同意がなかったと判断したのに対して(判旨Ⅰ)、その1年後において、減額について減額条件確認書がかわされたときには、「自由な意思」による同意があったと判断された(判旨Ⅱ)。使用者からの減額の説明を受け、そのことについて、十分理解したうえで、書面をかわしたことから、「自由な意思」による同意があったと判断されたのであろう。
労働条件の不利益変更に対する労働者の同意については、裁判例の傾向は、必ずしも明確でなく、学説上も、同意内容の合理性を問うもの、使用者に信義則上の情報提供義務や説明義務が課せられていると解し、その履行の有無を重視するおのなど多様な見解が出されている。
労契法8条(労働契約の内容の変更)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
95 賞与の支給日在籍要件一大和銀行事件
最1小判昭和57年10月7日(昭和56年(オ)661号)
事案の概要
賞与の支給日に在籍していることを、賞与の支給要件とすることは認められるか。
事実
Xは、昭和51年4月1日にY銀行に採用され、昭和54年5月31に退職した。Y銀行の就業規則(32条)には、「賞与は決算期毎の業績により、支給日に在籍している者に対し、各決算月につき1回支給する」という規定があった。「支給日に在籍している者に対し」という文言は、同年5月1日の改訂により追加されたものであるが、それは従来の慣行を従業員組合の提案に基づき明文化したものであった。
Y銀行では、昭和54年6月15日と同年12月10日に賞与が支給されたが、各賞与は、それぞれ、前年10月1日から同年3月31日までおよび同年4月1日から9月30日までの査定に基づくものであった。Y銀行は、支給日まえに退職したXにはいずれの賞与も支給しなかった。そこで、Xは、賞与の支払いを求めて訴えを提起した。1審はXの請求を棄却し、原審も、Xは改訂就業規則を黙示的に承諾しているし、また、就業規則の改訂には合理性があるとして、Xの控訴を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)。
「Y銀行においては、本件就業規則32条の改訂前から年2回の決算期の中間時点を支給日と定めて、当該支給日に在籍している者に対してにのみ決算期間を対象とする賞与が支給されるという慣行が存在し、右規則32条の改訂は、単にY銀行の従業員組合の要請によって、右慣行を明文化したにとどまるものであって、その内容においても合理性を有するというのであり」、この事実関係に下では、Xの請求を棄却した原審の判断は、正当そして是認できる。
解説
賞与については、支給日に在籍している者にのみ支給すという支給日在籍要件が付されていることがある。使用者がこのような支給日を在籍要件を設けるのは、賞与が過去の労働に対する対価というだけでなく、将来の労働に対する意欲向上策としての意味も持つからである。
支給日要件の有効性をめぐっては、いくつかの論点がある。まず、賞与の算定がそれ以前の期間の業績等の査定に基づき行われるおとが多いため、その期間に勤務していた者には、賞与の請求権が認められるべきではないか、という点である。いったん発生した請求権を、支払い日前に退職した者に認められないとなると、賃賃金全額払いの原則(労基法24条1項)と抵触することになる。しかし、支給日在籍要件がある場合には、支給日に在籍していてはじめて賞与請求権が発生しない。したがって、賃金全額払いの原則の問題は生じないことになる。本判決は、支給日在籍要件を明確化する就業規則変更について合理性を肯定しているので、同要件が賃金全額払いの原則と抵触しないことを当然の前提としていると解される(同旨の判例として、京都新聞社事件ー最1小判昭和60年11月28日)。
支給日在籍要件は、賞与の支給をうけるためには、支給日まで在籍していなければならないという意味で、退職の自由を制限する可能性もある。しかし、これは、長期的なものではないので、通常は、退職の自由を制限するとは解されていない。なお、裁判例には、年内の退職予定者と非退職予定者について、将来の活躍に対する期待という観点から賞与の支給額に差をつけることはただちに違法ではないが、2割以上の差をつけることは公序良俗に反するとしたものがある(ベネットコーポレーション事件ー東京地判平成8年6月28日)。
支給日在籍要件には、前述のように、将来の労働に対する意欲向上策としての意味があることからすると、定年退職者や整理解雇による退職者については、労働者の意思にかかわりなく、その将来の労働への可能性が奪われている以上、支給日に在籍しなくとも賞与の対象期間に勤務しているかぎり、賞与は支給されるべきである(リーマン・ブラザーズ証券事件ー東京地判平成24年4月10日)。このほか、労使交渉が長引いて支給日が遅くなったためにその年の支給日には在籍していなかったというケースでは、判例は賞与請求権認めるを傾向にある(ニプロ医工事件ー最3小判昭和60年3月12日、須賀工業事件ー東京地判平成12年2月14日等)
労基法24条1項 (賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
96 懲戒解雇と退職金一小田急電鉄(退職金請求)事件
東京高判平成15年12月11日(平成14年(ネ)6224号)
事案の概要
懲戒解雇の場合の退職金不支給は条項は有効か。
事実
Xは、電鉄会社Yの従業員である。Xは、平成12年5月1日、電車内で痴漢行為を行い、逮捕され、東京都迷惑防止条例違反で略式起訴され、20万円の罰金刑に処せられた。Y会社は、Xの普段のまじめな勤務態度を考慮して、昇給停止および降職の処分とし、始末書を提出ただし、。Xは、同年11月21日に再び電車内で痴漢行為を行い、逮捕され埼玉県迷惑防止条例違反で起訴された(その後、懲役4月執行猶予3年の有罪判決を受けている。なお、Xは平成3年、同9月にも痴漢行為をして逮捕され罰金刑に処せられており、そのことをY会社は本件の一連の事情聴取から知ることになる)。Y会社は、賞罰委員会の討議を経て、Xを懲戒解雇とし、退職金規則における、懲戒解雇により、退職する者には、原則として退職金を支給しないという規定に基づき、退職金を支給しなかった。ただし、Xおよびその家族の当面の生活設計を考慮し、即時解雇をせず、解雇予定手当と冬期一時金は支払った(合計で約90万円)。
Xは。退職金の支給を求めて訴えを提起した。1審は、懲戒解雇は有効であるとしたいえで、本件痴漢行為は、Xのそれまでの勤続の労を抹消してしまうほどの不信行為と言わざるをえないと述べて、Xの請求を棄却した。そこで、Xは控訴した。
判旨 原判決変更(Xの請求の一部認容、一部棄却)。
Ⅰ「退職金の支給制限規定は、一方で、退職金が功労褒賞的な性格を有することに由来するものである。しかし、他方、退職金は、賃金の後払い的な性格も有し、従業員の退職後の生活保障という意味合いも有するものである。ことに、本件のように、退職金支給規則に基づき、給与及び勤続年数を基準として、支給条件が明確に規定されている場合には、・・・・賃金の後払い的意味合いが強い」。「このような・・・・退職金について、その退職金全額を不支給とするには、それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。ことに、それが、業務上の横領や背任など、会社に対する直接の背信行為とはいえない職務外の非違行為である場合には、それが、会社の名誉信用を著しく害し、会社に無視しえないような現実的損害を生じさせるなど、上記のような犯罪行為に匹敵するような強度な背信性を有することが必要であると解される」。
Ⅱ「退職金が功労褒賞的な性格を有するものであること、そして、その支給の可否については、会社の側に一定の合理的な裁量の余地があると考えられることからすれば、当該職務外の非違行為が、上記のような強度の背信性を有するとまではいえない場合であっても、常に退職金の全額を支給すべきであるとはいえない」。「そうすると、このような場合には、当該不信行為の具体的内容と被解雇者の勤続の功などの個別的事情に応じ、退職金のうち、一定割合を支給すべきものである」。
解説
退職金は、法律上の制度ではないが、多くの会社で導入されている。退職金には、賃金の後払い的性格と功労報奨的な性格、さらに生活保障的な性格があるとされている。多くの会社では、就業規則において、懲戒解雇処分を受けた場合や退職後の競業避止義務違反の場合には、退職金を減額または不支給とする条項を設けている(競業避止義務については、→【9】三晃社事件)。このような条項が有効と解されている(民法90条違反ではないし、就業規則における合理性のある条項(労契法7条)と解されている)のは、功労報償的な性格が重視されえちるからである。しかし、全額不支給条項については、賃金後払い的性格(あるいは生活保障的な性格)も考慮し、その適用範囲を限定する解釈が行われるのが通常です。
本判決も、懲戒解雇が有効であっても、退職金の全額不支給は、永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があるとが必要であるという限定解釈をしている(判旨Ⅰ)
ただ、そうすると重大な不信行為がない場合には、使用者は退職金を支給すべきことになりそうであるが、本判決は、そのような場合でも、退職金の功労報償的な性格を考慮すれば、全額不支給が妥当ではないこともあり、そのときには、個別的事項に応じて一部支給をすべきであるという注目すべき判断をしめしている(判旨Ⅱ)本判決は、Xの非違行為の性格、内容や、本件懲戒解雇に至った経緯、Xの過去の勤務態度等の諸事情に加え、とりわけY会社における過去の割合的な支給事例(懲戒解雇のケースで退職金の3割が支給されたという先例)等を考慮して3割の退職金の支給を認めた(判旨外。NTT東日本事件ー東京高判平成24年9月28日も参照)。
民法90条(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
労契法7条
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
97 企業年金の減額一松下電器産業グループ事件
大阪高判平成18年11月28日(平成17年(ネ)3134号)
要旨
退職者が受給中の企業年金を、会社が一方的に減額することは認められるか。
事実
Xらは、Y会社とそのグループ会社の元従業員である。Xらは、Y会社との間で、本件福祉年金契約に基づき、年2回、年金が支払われることになっていた。Y会社の年金制度は、本件年金規程に基づいて運営されてきたところ、同規定には、「将来、経済的情勢もしくは社会保障制度に大幅な変動があった場合、あるいは法制面での規制措置により、必要が生じた場合には、この規定の全般的な改定または廃止を行う」という条項(本件改廃規程)が含まれていた。
Y会社は、平成14年4月に現役従業員に対しては、この年金制度を廃止し、また既受給者に対しては、本件改廃規程に基づき、給付利率を2%引き下げた(本件利率改定)。そこで、Xらは、この給付利率の引き下げの効力を争うために訴えを提起した。1審は、Xらの請求を棄却したので、Xらは控訴した。
判旨 控訴棄却(Xらの請求棄却)。
Ⅰ 本件年金規程は、合理性を有しており(本件改廃規程についてはⅡ)、その内容を知ろうとすれば、知り得た状況にあるので(周知性)、本件年金規程によらない旨の特段の合意がない以上、Xらは、本件年金規程に従うとの意思で本件福祉年金契約を締結したとするのが相当であり、本件年金規程は、本件福祉年金契約の内容となっていると解される。
Ⅱ 本件改廃規程は、厳格な要件を規定していること、本件福祉年金契約に基づく年金支給は、受給者の死亡までの長期間継続するものであること、また、本件改廃規程によって変更できる」自工は、年金制度の目的趣旨に照らせば、自ずと限界があることに照らせば、その内容には合理性がみとめられる。
Ⅲ 本件では、本件改廃規程が規定する経済情勢、社会保障制度に大幅な変動が存することは認められる。もっとも、Y会社は、本件改廃規程が定める要件が認められれば、自由に本件年金規程を改訂できるわけではなく、本件利率の内容の必要性、相当性を必要とすることは、事柄の性質上明らかである。また、本件利率改定にあたり、Y会社の年金制度は、退職労働者の福祉政策の一環として労働組合との協議のうえ発足したものであるから労働組合に対し理解を求めることが必要であるし、また、年金受給者は退職して、労働組合員ではないから、不利益を受ける年金受給者に対し、理解を求める努力をするなど、手続の相当性が必要である。
解説
給付額が事前に確定している確定給付型の企業年金については、年金資産の運用益が下がると、企業の負担が重くなる。特に企業運営が悪化してくると、退職者の受給する年金水準を維持するために企業が負担を続けることは、現役の従業員や株主の利益と対立することになる(企業年金の中でも、確定拠出年金となると、運用のリスクは労働者側が負うので、こうした問題はおきにくい)。
しかしながら、退職者の年金受給権は、退職にともない確定しているので、その支給基準や不利益に変更することについては、受給者本人の同意が必要となる(幸福銀行事件―大阪地判平成12年12月20日を参照)。退職前の段階であれば、就業規則の不利益変更法理(現在の労契法10条)が適用され、実際に合理性を認めた裁判例もある(名古屋学院事件ー名古屋高判平成7年7月19日等)が、退職後は、労働契約関係は存在しないので、就業規則の法理の適用はできない(そのときでも、事情変更の原則が適用される場合には、不利益変更が認められる可能性はあるが、この原則の適用はきわめて厳格である)。
もっとも、退職後の不利益変更であっても、企業年金の支給に関する合意や協定において、将来における減額を根拠づける条項が設けられていれば、それい基づく変更は、可能となろう。
本件では、本件改廃規程を含む年金規程があったため、この年金規程が需給者に対して、拘束力をもつか、もつとした場合、給付利率の引き下げが、本件改廃規程の定める要件に合致するかが問題となった。
判旨Ⅰは、年金規程はその内容の合理性と周知性があれば、本件福祉年金のないようになるとする。ここには、就業規則の法理(労契法7条)との類似性が見て取れる。判旨Ⅱは、本件改廃規程の合理性を認め、判旨Ⅲでは、その解釈の一般的な基準を定め、結論としては、本件では、その要件に合致しているとする。手続の相当性に関しては、利率改定に先立って既受給者に説明会を開催するなど、その94.6%の同意を得ているという事情があり、この点が、本判決の結論に大きな影響を及ぼしていると思われる。(手続の重要性については、早稲田大学事件ー東京高判平成21年10月29日も参照)。
本件のような自社年金ではなく、法律で規制されている確定給付企業年金については、受給額の引下げには、厳格な実体性・手続的要件が課されている(確定給付企業年金法。要件の充足が否定された事件として、NTTグループ企業事件ー東京高判平成20年7月9助)。
労契法10条
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
労契法7条
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
98 労働時間の概念一三菱重工長崎造船所事件
最1小判平成12年3月9日(平成7年(オ)2029号)(民集54巻3号801頁)
要旨
本来の業務の準備行為に要した時間は労働時間か。
事実
Xは、Y会社の従業員でA造船所で就業している。A造船所の始業基準は、始業に間に合うよう更衣等を完了して、作業場に到着し、所定の作業時間に作業場において実作業を開始するものとされ、されに、始終業の勤怠把握基準として、始業の勤怠は更衣を済ませ始業時に体操をすべく所定の場所にいるか否かを基準として判断する旨定められていた。また、Xらは、Y会社から、実作業にあたり、作業服のほか所定の保護具、工具等の装着を義務付けられ、その装着を所定の更衣室、または控所等において行うものとされていた。さらに、Xらの中には、材料庫等からの副資材や消耗品等の受け出しを午前ないし午後の始業時刻前に行うことや、午前の始業時刻前に月数回散水をすることを義務付けられている者もいた。
Xらは、午前の始業時刻前に、
①所定の入退場門から事業所内に入って更衣所まで移動し、
②更衣所等において作業服および保護具を装着して、準備体操場まで移動し、
③作業場または実施基準線から食堂等まで移動し、また
④現場控所等において作業服および保護具の一部を脱離するなどし、午後の始業時刻前に、
⑤食堂から作業場または準備体操場まで移動し、また、
⑥脱離した作業服および保護具を再び装着し、午後の終業時刻後に
⑦作業場または実施基準線から更衣所等まで移動し、作業服および保護具等を脱離し、
⑧手洗い、洗面、洗身、入浴を行い、その後に
⑨通勤服を着用し、
⑩更衣所等から入退場門まで移動して事業所外に退出し、また、
⑪Xらの一部は、午前または午後の始業終業時刻前に副資材や消耗品の受け出しをし、また、午前の始業時刻前に散水を行った。
Xらは、①~⑪野行為に要する時間は、労基法上の労働時間であるとして、これらの行為に要した時間について、就業規則等に基づく割増賃金の支払を求めて、訴えを提起した。1審および原審は、②⑦⑪については、労基法上の労働時間と認めたが、それ以外は、労働時間と認めなかった。そこで、双方が上告した。
判旨 上告棄却(以下、Y会社の上告した事件の判旨である)。
Ⅰ「労働基準法・・・・32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働者緒行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することが」できるか否かにより、客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労から働協約等の定めのいかんにより、決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事務所内において行うことを使用者から義務付けられ、又は、これを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、労働基準法の労働時間に該当すると解される」。
Ⅱ 「Xらは、Y会社から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、また、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされていたということであるから、右装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、Y会社の指揮命令下に置かれたものと評価うことができる。また、Xらの副資材等の受出し及び散水も同様である。また、Xらは、実作業の終了後も、更衣所等において作業服及び保護具等の離脱等を終えるまでは、おまだY会社の指揮命令下に置かれているものと評価することができる。
解説
労基法32条は、休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないをする(例外は、労基法40条、労規則25条の2)。それを超える時間外労働は、原則として許されない(→【102】日立製作所武蔵工場事件「解説」)。休憩時間は、労働時間と途中に45分(労働時間が6時間超の場合)または、60ふん(労働時間が8時間超の場合)を、原則として一斉に付与しなければならない(労基法34条)。
どのような時間が、労働時間に該当するかは、法文中に明確にされていない。この点、本判決は、「労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたもの」がこれに該当するとする(判旨Ⅰ)
さらに、本判決は、このような時間に該当するかどうかは、客観的に判断されるべきものとしている(判旨Ⅰ)。就業規則等で定められた労働時間を所定労働時間というが、その所定労働時間外であっても、客観的に使用者の指揮命令下に置かれていると判断されれば、労働命令下に置かれているかどうかの判断基準として、本判決は、就業を命じられた業務の準備行為などを事業所内において行うことを業務の準備行為などを事業所内において行うことを、使用者から「義務付けられたとき」、または、「これを余儀なくされたとき」は、使用者の指揮命令下におかれたものと評価することができる(判旨Ⅰ)。
この判断基準を本件事案において具体的にあてはめたのでが、判旨Ⅱでる。結論として、午前の始業時刻前における事業所内の更衣室での作業服・保護具等の装着の脱離、午前ねいし午後の始業時刻前における副資材等の受け出しや散水の作業は、指揮命令下におかれていると評価することができるとし、これらの行為に要した時間は労働時間と判断した。
労基法32条
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労基法40条(労働時間及び休憩の特例)
第40条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
〈編注:「別段の定め」は、「労働時間」について労働基準法施行規則第25の2条、26条、「休憩時間」について同31条、32条、33条、国家公務員法第106条、同附則16条を参照〉
② 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
労基則25条の2(労働時間の特例)
第二十五条の二 使用者は、法別表第一第八号、第十号(映画の製作の事業を除く。)、第十三号及び第十四号に掲げる事業のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二条の規定にかかわらず、一週間について四十四時間、一日について八時間まで労働させることができる。
労基法34条 (休憩)
第34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
99 仮眠労働時間の労働時間制一大星ビル管理事件
最1小判平成14年2月28日(平成9年(オ)608号・609号)(民集56巻2号361頁)
要旨
実作業に従事していない仮眠時間は、労働時間か。
事実
Xらは、ビル管理業務を目的とするY会社の従業員としてビル巡回監視の業務に従事しており、毎月、数回24時間勤務に従事していた。この24時間勤務の間に、休憩時間を仮眠時間(本件仮眠時間)が与えられていた。Xらは、配属先のビルからの外出を原則として禁止され、仮眠室における在室や、電話の接受、警報に対応した必要な措置をとることなどが義務づけられていた。Xらは、その仮眠時間中に突発的に実作業の必要が生じた場合に、これに従事して所定の手当をうけたことも数回あった。
Y会社では、24時間勤務における仮眠時間は、所定労働時間に算入されておらず、泊り勤務手当が支給されるのみで、時間外勤務手当や深夜就業手当の対償となる時間として取り扱われていなかった。ただし、仮眠時間中に突発作業が発生した場合、残業申請をすれば、実作業時間に対し、時間外勤務手当が支給されていた。
Xらは、仮眠時間も労働時間にあたると主張して、労働契約、就業規則所定の時間外勤務手当、深夜就業手当、さらに労基法37条所定の時間外割増賃金および深夜割増賃金の支払いを請求した。1審は、Xらの請求をすべて認容し、原審はXらの請求の一部のみ認容した。
判旨 原判決破棄、差戻し
Ⅰ 労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という)がそれに該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。
Ⅱ 不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には、労基法上の労働時間にあたるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務づけられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当です。
Ⅲ Xらは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義実として、仮眠室における待機と警報や電話等に対してただちに相当の対応をすることを義務づけられており、実作業への従事がその必要性が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務づけがされていないと認めることができるような事情も存してないから、本件仮眠時間は、全体として、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。したがって、本件仮眠時間は、労基法上の労働時間にあたる。
解説
1 本判決は、まず、仮眠時間帯において、労働者において、労働者が実際に労務に従事していない時間(不活動仮眠時間)であっても、使用者からの指揮命令下に置かれていると客観的に評価される時間であれば、労基法上の労働時間に該当するという一般的な判断基準を示した(判旨Ⅰ)。
そして、具体的な判断をするうえでは、労働者が労働からの解放が保障されていてはじめて労働時間制を否定することができるとし、仮眠時間であっても、労働契約上の労務の提供が義務づけられていれば、労基法上の労働時間に該当するとしている(判旨Ⅱ)。
本件では、Xらは、仮眠時間中においても労働契約上の義務として、警報や電話等への対応を義務づけられているので、労働からの解放は保障されていないと判断され、その結果、本件仮眠時間は労基法上の労働時間に該当するという結論になっている(判旨Ⅲ)
なお、判旨Ⅲでは、たとえ形式的には労働契約上の義務づけがあったとしても、義務づけられた業務に従事する必要性が皆無に等しいといった、実質的に義務づけがされていない事情が認められれば、労働からの解放の保障があったと判断できる余地を残している(このような事情が認められて、仮眠時間の労働時間制を否定した裁判例として、ビル代行事件ー東京高判平成17年7月20日、ビソー工業時間ー仙台高判平成25年2月13日等)。
また、労働契約上の義務づけがあるとにんていされねい場合でも、それだけでただちに労働時間性が否定されるわかではない。判例には、マンションの住込みの管理人が、所定労働時間外においても、管理業務マニュアルに基づき住民からの黙示の指示があったとして、労働時間であると判断したものがある(大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件ー最2小判平成19年10月19日。病院の医師の宅直制度につおては、黙示の指揮命令を否定した裁判例として、奈良県事件ー大阪高判平成22年11月16日)。
2仮眠時間が労基法上の労働時間に該当すると判断されても、その時間帯の賃金は当事者が契約で決めることができる。ただし、時間外労働や深夜労働が発生していれば、割増賃金の支払いは義務づけられる(労基法37条)
労基法32条(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労基法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
100 変形労働時間制一JR西日本(広島支社)事件
広島高判平成14年6月25日(平成13年(ネ)254号)
要旨
変形労働時間制における労働時間の特定要件は、そのような場合に満たされるか。
事実
旅客鉄道会社であるY会社は、一部の事業場を除き、1か月単位の変形労働時間制(労基法32条の2)を導入していた。Y会社は、その従業員で動力車運転士であるXら2名に対して、次のような勤務指定の変更を行った。」X1についていえば、平成9年5月分の勤務について、同年4月25日に、乗務員の余剰があったため、安全診断問題の作成等の乗務員以外の乗務を内容とする勤務日の指定を7日間(7~9、22・23・27・28日)受けていた(労働時間はいずれも7時間45分)が、その後、Y会社は、勤務指定を変更して乗務員勤務の指定をし、それにより労働時間は7日は14俯瞰48分、8日はゼロ、9日は11時間12分、22日は13時間37分、23日はゼロ、27日は15時間14分、28日はゼロとなった(勤務日が2日にまたがっている場合は、勤務開始日の労働時間)。就業規則においては、「業務上の必要がある場合は、指定した勤務を変更する」という規程(本件変更通知)があった。
Xらは、この勤務指定の変更により、当初特定されていた勤務時間を超渇することになった時間の労働については、超過勤務手当が支払われるべきであるとして、その支払いを求めて、訴えを提起した。1審はXの請求を認容した。そこで、Y会社は控訴した。
判旨 原判決一部変更(Xの請求の一部認容、一部棄却)。
Ⅰ 労基法32条の2に基づく1か月単位の変更労働時間制がその要件として労働時間の「特定」と要求した趣旨に鑑みると、同条の特定の要件を満たすためには、労働者の労働時間を早期に明らかにし、勤務の不均衡等配分が労働者の生活にいかなる影響を及ぼすのかを明示して、労働者が労働時間外における生活設計をたてられるように配慮することが必要不可欠であり、そのためには、各日および週における労働時間をできる限り具体的に特定することが必要である。
Ⅱ 「勤務変更は、業務上のやむを得ない必要がある場合に限定的かつ、例外的措置として認められるにとどまるものと解するのが相当であり、使用者は、就業規則等において、勤務を変更し得る旨の変更条項を定めるにあたっては、・・・・一旦特定された労働時間の変更が使用者の恣意により、みだりに変更されることを防止するとともに、労働者にどのような場合に勤務変更が行われるかを了知させるため、上記のような変更が許される例外的、現手的事由を具体的に記載し、その場合に限って勤務変更を行う旨定めることを要するものと解すべきであって、使用者が任意に勤務変更しうるような条項では、同条(筆者注:労基法32条の2)の要求する「特定」の要件を満たさないものとして無効である」。
解説
変形労働時間制は、単位となる時間内における所定労働時間を平均して、週の法定労働時間を超えていなければ、その期間内の日または週において法定労働時間を超えていても時間外労働としての扱いをしないという制度である。労基法には、1か月以内の期間を単位とするもの(32条の2)、1年以内の期間を単位とするもの(32条の4)、1週間単位以内のもの(32条の5)の3種類の変形労働時間制が定められている。このほか、始終業時刻を労働者が決定できるフレックスタイム制もある(32条の3)。
1か月以内の単位をおよび1年以内の単位の変形労働時間制の導入の際には、どの日またはどの週に法定労働時間を超える労働をさせるかを特定していることが求められている。その趣旨は、労働者の生活設計への配慮にある(判旨Ⅰ)。
本件は、特定された日の変更が、どのような場合に認められるかが問題となった。使用者としては、いったん勤務指定をすれば、その後は、勤務変更ができないとなると、業務に支障がでてくることもあろう。特に本件のように、公共性を有する事業では、本判決は、「勤務指定前に予見することが不可能なやむを得ない事由が発生した場合につき、使用者が勤務指定を行った後もこれを変更しうる変更条項を就業規則等で定め、これを使用者の裁量に一定程度まで委ねたとしても、直ちに・・・・
「特定」の要件を充たさないとして違法となるものではない」と述べている(判旨外)。
そこで、労働者側の利益と使用者側の必要性とを調整するために、判旨Ⅱは、就業規則において勤務指定後の勤務変更を定めることは禁止されないが、その場合には「変更が許される例外的、限定的事由を具体的に記載し、その場合に限って勤務変更を行う旨定めるJR東日本(横浜土木技術センター)事件ー東京地判平成12年4月27日、岩手第一事件ー仙台高判平成13年8月29日)。本件変更条項は、この要件を満たしていないとして無効となった。
労基法32条の2〔一ヵ月単位の変形労働時間制〕
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
労基法32条の3
第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
② 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。
③ 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。
④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。
第32条の3の2 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
本資料の作成につきましては、私が尊敬申し上げております大内 伸哉一先生の「最新重要判例200労働法第5版」を参考に、私のお客さまへのプレゼン資料として、作成させていただきましたので、その旨、記載させていただきます。
新着情報・お知らせ
井上久社会保険労務士・行政書士事務所
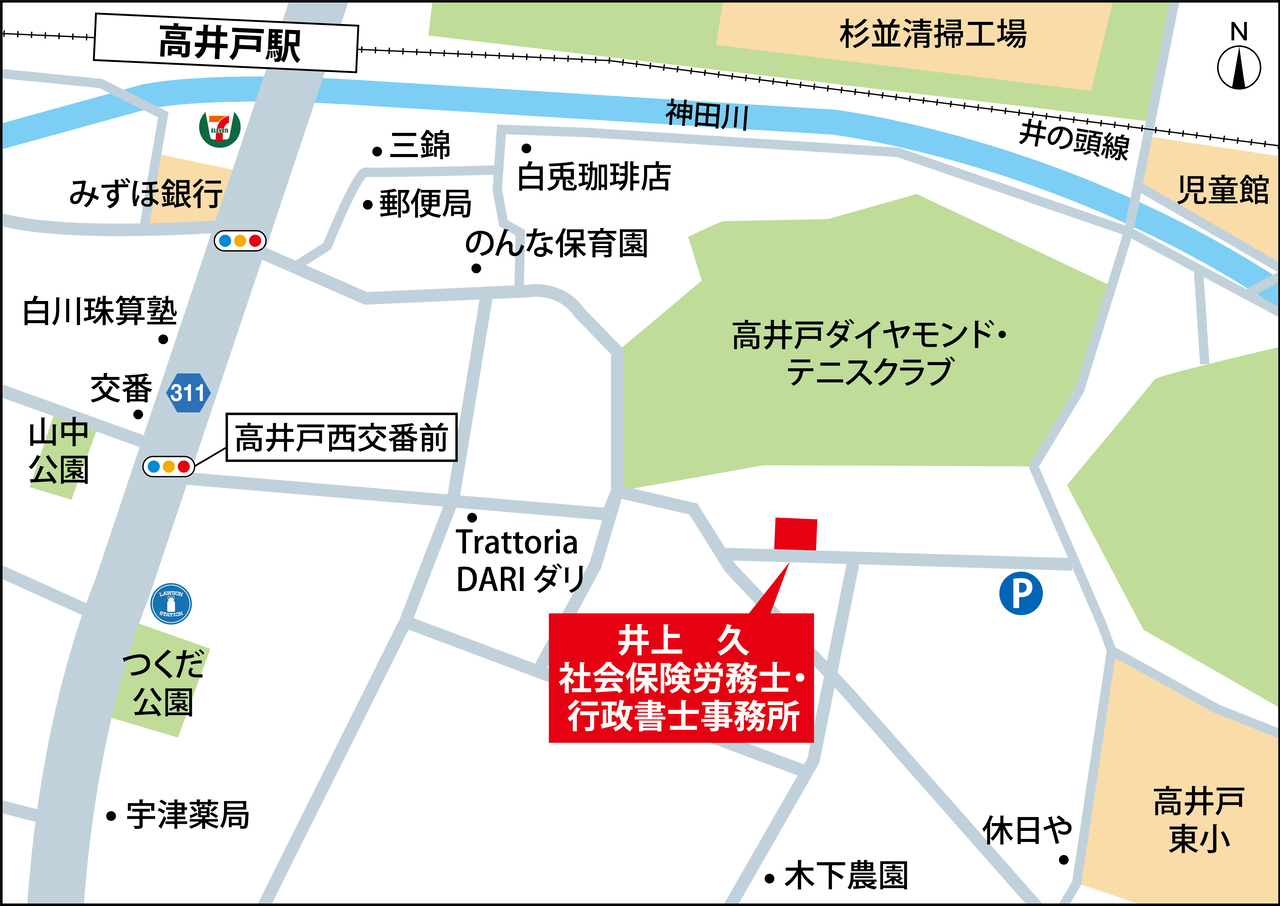
住所
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
アクセス
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

