医療労務管理支援事業(医療機関向けの働き方改革支援事業)
担当の心得
はじめに
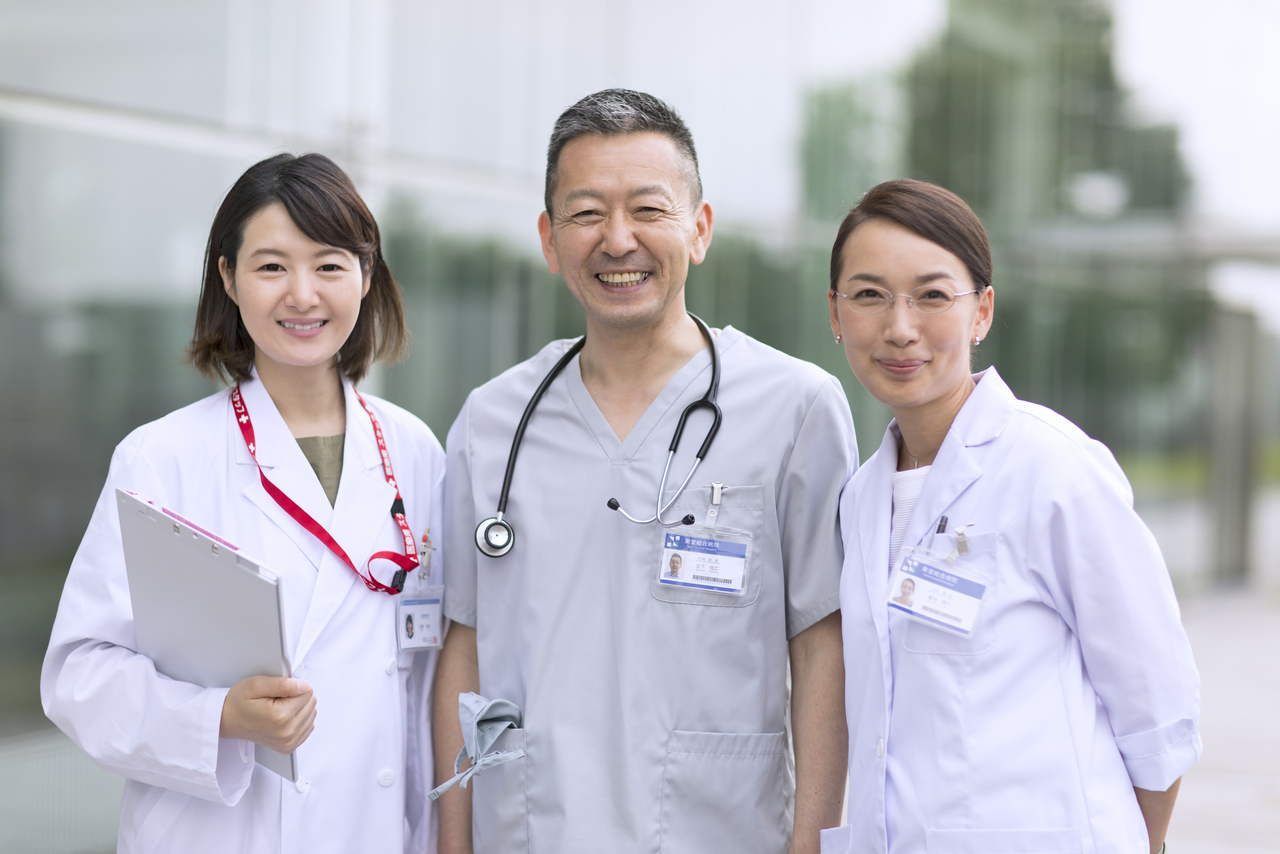
医療労務管理支援事業(医療機関向けの働き方改革支援事業)を担当するにあたり、基本的な事項をまとめてみました。 あくまでも自分の勉強用ですが、もし、ご参考にしえちただける方がおられれば幸いです。では、よろしくお願い申し上げます。
参考資料・URL
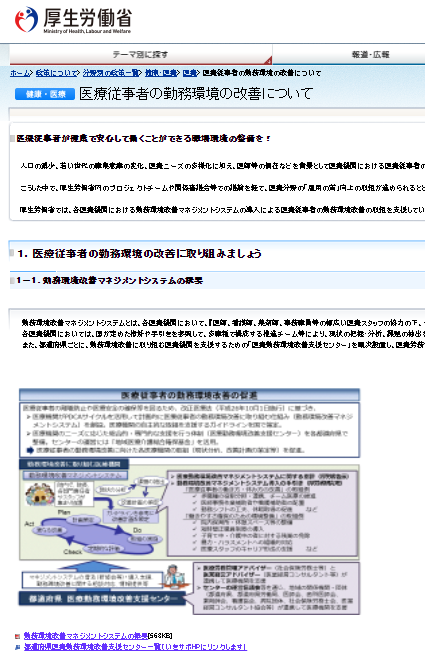
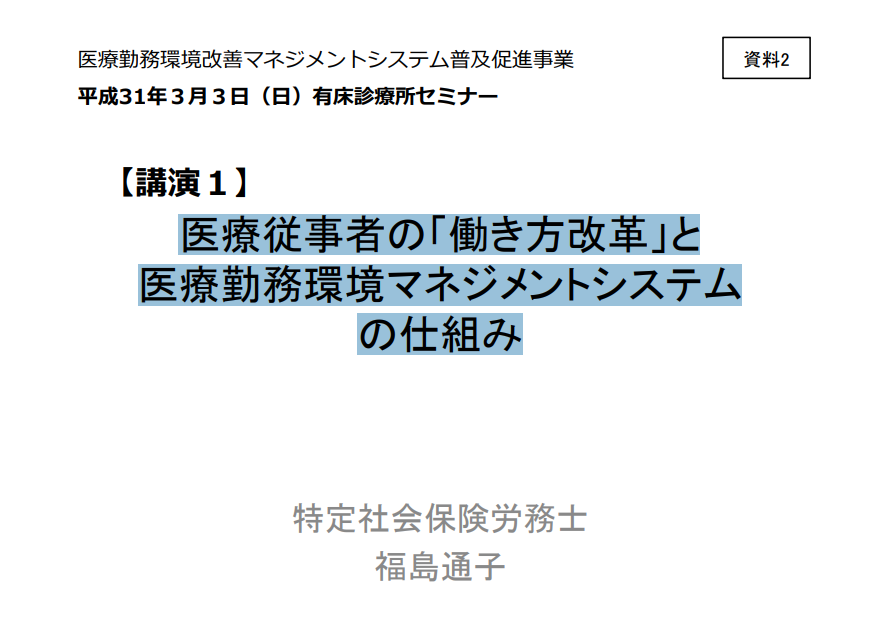
①医療従事者の勤務環境の改善について 厚生労労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/quality/
②医療従事者の「働き方改革」と 医療勤務環境マネジメントシステム の仕組み
医療従事者が健康で安心して働くことができる職場環境の整備を!
人口の減少、若い世代の職業意識の変化、医療ニーズの多様化に加え、医師等の偏在などを背景として医療機関における医療従事者の確保が困難な中、質の高い医療提供体制を構築するためには、勤務環境の改善を通じ、医療従事者が健康で安心して働くことができる環境整備を促進することが重要です。
こうした中で、厚生労働省内のプロジェクトチームや関係審議会等での議論を経て、医療分野の「雇用の質」向上の取組が進められるとともに、平成26年10月1日には医療機関の勤務環境改善に関する改正医療法の規定が施行され、各医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に勤務環境改善に取り組む仕組み(勤務環境改善マネジメントシステム)が導入されました。
厚生労働省では、各医療機関における勤務環境改善マネジメントシステムの導入による医療従事者の勤務環境改善の取組を支援しています。
1-1.勤務環境改善マネジメントシステムの概要
勤務環境改善マネジメントシステムとは、各医療機関において、『医師、看護師、薬剤師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主的な勤務環境改善を促進することにより、快適な職場環境を形成し、医療スタッフの健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資すること』を目的として、各医療機関のそれぞれの実態に合った形で、自主的に行われる任意の仕組みです。
各医療機関においては、国が定めた指針や手引きを参照して、多職種で構成する推進チーム等により、現状の把握・分析、課題の抽出を行い、できることから改善計画を策定して取組を始めてみましょう。
また、都道府県ごとに、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するための「医療勤務環境改善支援センター」を順次設置し、医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士等)や医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント等)が専門的・総合的な支援を行っています。取組に当たってお困りごとや相談がありましたら、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターへお問い合わせください。
1-2.勤務環境改善の意義
医療の質の向上や経営の安定化の観点から、医療機関が自らのミッションに基づき、ビジョンの実現に向けて組織として発展していくことが重要です。
そのためには、各医療機関において、医療従事者が働きやすい環境を整え、専門職の集団としての働きがいを高めるよう、勤務環境を改善させる取組が不可欠です。
医療従事者、患者、経営にとってWIN-WIN-WINとなるような好循環を作っていきましょう。
1-3.いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)をご利用ください
各医療機関の勤務環境改善の取組に役立つ情報を、ウェブサイト「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきサポ)」に掲載しています。
勤務環境改善に関する法令や通知のほか、都道府県や関係団体が行っている施策や事業の内容、勤務環境改善の取組により成果を出している医療機関の事例も紹介しています。取組の参考としてぜひご利用ください。
1-4.医療現場における暴力・ハラスメント対策
医療現場における暴力・ハラスメント対策は、医療従事者の離職防止、勤務環境改善の観点からも近年重視されています。平成30年版過労死等防止対策白書では、医療分野における労災認定事案のなかで、患者からの暴言・暴力やハラスメントによるストレスが要因と考えられる看護職員の精神障害の事案が多くあげられています。
このような問題に対し、医療従事者が患者やその家族からの暴力・ハラスメント対策について学習することができる教材を作成しました。スタッフ、管理者双方の視点から、基本的な考え方についてコンパクトに学ことができます(1コンテンツにつき、約20分)。
各医療機関が適切な対応策を組織的に講じることができるよう、研修や個人学習等でぜひご活用ください。
1-5.医療機関勤務環境評価センターの指定について
厚生労働省では、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により、改正法第2条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「第5号新医療法」という。)第107条第1項の規定の例により、「医療機関勤務環境評価センター」を指定することとしております。
申請の受付は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令公布後に行うこととしておりますが、申請を検討している一般社団法人又は一般財団法人の準備に資するよう、申請方法等をお示ししていきますので適宜ご参考にしていただきますようお願いいたします。
なぜ、今、働き方改革が必要なのか
〇医療従事者は、他の職種と比較しても抜きんでた長時間労働の実態にある
〇一人ひとりの崇高な理念により医療は支えられてきた
〇しかし、医療従事者とはいえ一人の人間であり、長時間労働による健康への影響が懸念される
「働き方改革」でやらなければならないこと
法改正スケジュールの確認
「管理監督者」って?
• 「役職名」がついているから「管理監督者」ではない
①経営と一体的な立場で仕事をしている
②出勤、退勤、勤務時間等制限なし
③ふさわしい処遇がなされている
• それ以外は「管理職」であっても「管理監督者」ではない
• 残業代支給の必要あり
まず現状を確認
Q 残業する場合がありますか?
⇒ある場合は、36協定届を締結、届出していますか?
Q 医師を含め年間10日以上有給休暇を付与される職員
が有給休暇を5日以上とっていますか?
Q 有給休暇について、付与日数や残日数を職員に知らせ
ていますか?
Q 労働時間をタイムカード等で把握していますか?
Q 産業医は選任されていますか?
「働き方改革」でやらなければならないこと労働時間とは?
• 労働時間=使用者の指揮命令下にある時間
• 診療開始時刻 ≠ 始業時間
・着替え、清掃等も労働時間
「うちの看護師さん、朝早く来て掃除してって言ってるのに、
始業時間にぎりぎりに来るんですよ。患者さんが来ちゃうのに」‥この発言どうでしょう?
• 手待時間
院内で緊急時に備えて待っている=労働時間
• 研修・教育時間、会議・委員会等への出席時間
強制・命令であれば明らかに労働時間
出席は任意としながらも出ないと不利益な取り扱いがあるならば労働時間
「働き方改革」でやらなければならないこと
労働時間の把握義務
• 管理監督者も含め、医師も含め、全ての職員の労働時間の把握が必要
• 客観的な方法その他適切な方法で把握
・使用者が現認
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等を確認し、適正に記録
• 賃金台帳に、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数を記入
「働き方改革」でやらなければならないこと
労働時間の把握義務
• 自己申告制の場合
・適正な運用について十分な説明
・自己申告とタイムカード等の記録にかい離がある場合は調査し、補正を
・自己申告できる時間数の上限を設けてはならない
・記録上、36の範囲内に収まっているように守らせるなどしてはならない
• 労働時間の記録に関する書類は3年保存
「夜勤」と「当直」の違い
• 夜勤は休憩時間を除いてすべて労働時間
• 当直は、許可があれば労働時間ではない
• 当直途中に緊急対応などをした場合はその時間だけが労働時間
• 緊急対応が恒常的であると、当直と認められず、取り消しも有り得る
• 当直は労働時間ではないので、連続勤務制限にも係らない
「働き方改革」でやらなければならないこと
36協定届の見直し
• 1日8時間、1週40時間(法律上の労働時間の限度)
• 1週1日又は4週4休の休日(法定休日)
(医療機関の場合は変形労働時間制における労働時間及び休日)
• これを超えて働かせるには、36協定届の締結・届出が必要
*届出なく時間外労働をさせると違法
*法改正により、罰則あり!
• 特別な事情がなければ月45時間、年360時間を超えることはできない
⇒特別条項の締結が必要
• 経過措置あり
2019年4月1日(中小規模医療機関は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定届に上限規制
• 時間外労働・休日労働を行う業務の区分の細分化、範囲の明確化が必要
• 36協定届の範囲内でも安全配慮義務を負う
「働き方改革」でやらなければならないこと36協定届に関する留意点
• 「1日」「1カ月」「1年」について時間外労働の限度
⇒ それぞれの限度を超えないよう管理
• 協定期間の「起算日」
• 特別条項
時間外労働+休日労働<月100時間
≦複数月平均80時間
*施行日以後は36協定届の対象期間に関わらず計算の必要あり
• 過半数代表者
・管理監督者でないこと
・投票、挙手等の方法で選出
• 施行前までは旧様式で可、施工後は新様式で作成・届出
• 「常時使用する労働者」 ≠ 常勤
*臨時に雇入れた労働者以外の数(パート、アルバイトであっても臨時的でなければ含める)
• 派遣労働者に関しては、36協定届は派遣元で締結・届出。36協定越えの場合は派遣先が法違反となる
• オンラインで36協定届の作成ツール、電子申請も
・使用者の意向で選ばれた者でないこと
「働き方改革」でやらなければならないこと
年次有給休暇の時季指定義務
• 自ら申し出て取得した日数
+計画的付与
+時季指定付与 ≧ 5
• これまで年次有給休暇の付与日(基準日)か
ら1年以内に5日とれていない者がいた?
なぜ? どうする?
• 就業規則の改定
(例)
第〇条 年次有給休暇が10日以上付与された職員に対しては、付
与日から1年以内に、5日について、職員の意見を聴取したうえで、
時季を指定して取得させる。但し、〇項の規定による年次有給休暇を
取得した場合は、その日数分を5日から控除するものとする。
• 基準日統一の検討
• 管理の方法(年次有給休暇管理簿等)の検討
「働き方改革」でやらなければならないこと
同一労働同一賃金
• 均衡待遇規程の明確化
・基本給、賞与、役職手当、福利厚生、教育訓練などについて、待遇差の判断のもとにな
るルール
*例
・職務内容、責任の範囲・程度の違い
・配置の変更範囲の違い
罰則
1.時間外労働の上限規制
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
2.年休取得義務化
30万円以下の罰金
*取得義務以外の有休拒否は6か月以下の懲役または30万円以下の
罰金
3.労働時間の適正把握義務
なし
4.勤務間インターバル
なし
5.産業医・産業保健機能の強化
なし
6.パートタイム・有期雇用労働者の待遇格差の是正
なし
(派遣については30万円以下の罰金あり)
注意! 安全配慮義務
〇 長時間労働をさせた場合の管理職の責任について
管理職に周知
労基法違反、安全配慮義務違反
・ 労働時間規制、割増賃金支払い義務違反については、刑事罰あり
(6か月以下の懲役または30万円以下の罰)
・過労死などの重大な事故を起こした場合は刑事責任を問われることもある。
・自殺の原因が使用者側にあるとされた場合、多額の損害賠償を求められる可能性がある。
・安全配慮義務に対する社会的責任を果たしていないとされ信用失墜につながる可能性がある。
最後に(まとめ)

いかがでしたでしょうか?
今回は、医療従事者の「働き方改革」と医療勤務環境マネジメントシステムの仕組みについて解説させていただきました。
医師の働き方改革の施行は「2024年4月から」と言われておりますが、未だ、確定している訳ではありません。
いずれにしても、社労士として、真正面から取り組まなければならない重要課題であると思います。
今後も自己研鑽に努め、少しでもお客さまにわかりやすい説明ができる社労士を目指します。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
新着情報・お知らせ
井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
アクセス
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

