151 義務的団交事項-根岸病院事件
東京高判平成19年7月31日(平成19年(行コ)23号)
要旨
使用者は、初任給について、労働組合と団体交渉をする義務があるか。
事実
X病院の非常勤職員の賃金は、基本給と諸手当とで構成されており、基本給は、初任給額をベースに加算して決定されていた。X病院は、その職員で組織されている唯一の労働組合であるA組合に対して、毎年、初任給額について通知していた。
X病院は、平成11年2月26日に、A組合に対し、同年3月1日以降の新規採用者について、その初任給額を引き下げると通知し、実際に大幅な引下げを行った。これに対して、A組合は同年3月、X病院に対し、初任給引下げについて団体交渉を申し入れ、同月17日と同30日の2回、団体交渉が行われた。
A組合は、同年4月21日、B労働委員会に対して、初任給引下げが支配介入に該当し、また2回の団体交渉におけるX病院の対応が不誠実であるとして、不当労働行為の救済申立てを行った。同年4月22日、3回目の団体交渉が行われたが、初任給引下げについては、X病院は、Bの判断にゆだねるとして、何らの交渉も行わなかった。
その後、Bは、X病院に対して、断交命令、初任給額の是正、謝罪文の掲示を命じる救済命令を発した。X病院は、Y(中央労働委員会)に対して再審査を申し立てたところ、Yは、初任給額の是正を命じた部分を取り消し、謝罪文の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。X病院とA組合はともに取消訴訟を提起した。1審はX病院とA組合はともに取消訴訟を提起した。1審はX病院の請求を認容し、A組合の請求を棄却した。そこで、A組合は控訴した。なお、X病院は本判決に対して上告したが、最高裁は、上告棄却、上告不受理の決定をしている。
判旨 原判決一部取消し(断交拒否の成立は肯定したが、初任給引下げの支配介入該当性は否定した。以下は、断交拒否に関する判示部分である)。
Ⅰ「誠実な団体交渉が義務付けられる対象、すなわち義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的行使関係の運営に関する事項であって、使用者の処分可能なものと解するのが相当である」。
Ⅱ「非組合員である労働者の労働条件に関する問題は、当然には上記断交事項にあたるものではないが、将来にわたり組合員の労働条件、権利等に影響を及ぼす可能性が大きく、組合員の労働条件との関わりが強い事項については、これを断交事項に該当しないとするのでは、組合の団体交渉力を否定する結果となるから、これも上記断交事項にあたると解するべきである」。
解説
使用者は、労働組合からの団交の申込に対して、すべての要求事項について応じなければならないわけではない。使用者が応じなければならない義務的団交事項の法律上の定義はないが、従来から、裁判例および学説は、判旨Ⅰの「団体交渉を申し入れた労働者の団体構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」という定義(あるいは、類似の定義)を採用してきた。
使用者の経営や生産に関する事項は、原則として、義務的団交事項に該当しないか、それが、組合員の労働条件や雇用に影響がある場合には、その面については、義務的団交事項となると解されている。
本件では、初任給という非組合員の労働条件が問題となっている。本判決は、非組合員の労働条件については、原則として、義務的団交事項には該当しないとする。ただし、「将来にわたり、組合員の労働条件、権利等に影響を及ぼす可能性が大きく、組合員の労働条件との関わりが強い事項」は例外的に義務的団交事項に該当するとする(判旨Ⅱ)。
この事件では、初任給の適用を受ける将来の組合員と既存の組合員との間に賃金格差が生じて団結力を減殺するおそれがあるということから、「将来にわたり、組合員の労働条件、権利等に影響を及ぼす可能性が大きく、組合員の労働条件との関わりが極めて強い事項であることが明らかである」ので、本件初任給引下げは義務的団交事項にあたると判断されている(判旨外)。このように、本判決は、初任給という交渉時点では非組合員の労働条件について、組合員の労働条件との関わりが」強いという観点から、義務的団交事項となることを正面から認められたものではないことには注意を要する。
なお、X病院の初任給はこれまで団体交渉事項とされたことはなかった。それは、初任給の引下げがなかったことによるものであるが、本篇決は、X病院側がこれを経営事項としてm」一方的に決定できると考えていたことにも相当な理由があり、組合弱体化の意図はみとめられないとして、支配介入の成立は認めなかった。
152 団体交渉拒否に対する司法救済-国鉄事件
東京高判昭和62年1月27日(昭和61年(ネ)682号)
要因
団体交渉を求める法的地位の確認請求はできるのか。
事実
Yは、鉄道事業等を営む法人であり、Xは、主としてYに雇用されている職員で構成される労働組合である。Yは、規定に基づき、その職員らに対して、乗車証を交付してきたが、第3次臨時行政調査会の基本答申に応じて、乗車証制度を見直そうとした。これに対し、X組合は、乗車証制度は、職員の労働条件の一部となっているとして、その存続を求めることとし、Yに対して、乗車証制度問題について、団体交渉を再三申し入れた。しかし、Yは、乗車証制度の改廃は、管理運営事項であり、公共企業体等労働関係法8条(当時の規定)に定める団体交渉事項ではないとして、この申し入れに応じないばかりか、通達を発して、乗車証制度の改廃措置をとった。そこで、X組合は、
①鉄道乗車証等に関する労働協約の締結、
②前記通達等の改廃、
③精勤乗車証等の存続の事項
について、団体交渉を申し入れたが、Yはこれを拒否した。
そこで、X組合は、Yが前期各事項について、X組合と団体交渉を行う義務があることの確認と、違法な行為により、被った損害の賠償を求めて、訴えを提起した。1審は、X組合が断交を求める法的地位にあることの確認はしたが、損害賠償請求は認めなかった。Yは控訴し、X組合も附帯控訴した。なお、本判決はYにより上告されたが、最高裁は、前記各事項につき、団体交渉を求め得る地位にあることの確認を求める本件訴えは確認の利益を欠くものとはいえず、適法であるとした原審の判断は、正当と是認できるとして、上告を棄却している(最3小判平成3年4月23日)。
判旨 控訴、附帯控訴棄却(以下は、控訴審の引用する1審判決の内容である)。
Ⅰ「労働組合法は、団体交渉が侵害された場合には、労働委員会の救済命令手続により、その侵害を回復する制度を採用していることは、その規定の文言自体から明らかである。しかし、このような救済命令制度があるからといって、直ちに、労働組合の団体交渉権が労働委員会に対する救済命令の申立権であるにとどまり、使用者は、労働委員会の救済命令に従うべき義務(使用者の国に対する公法上の義務)を負うにすぎず、団体交渉に関しては、労働組合と使用者との間に私法上の法律関係は全く存在しないものと解するには、なお、一層の検討が必要であろう」。
Ⅱ 団体交渉の性質、労組法7条の規定に違反する法律行為の効力、同法の他の関連規定や労働委員会規則の内容(労組法6条には団体交渉の権限の委任に関する規定があり、同27条ならびに同法の規定には基づき制定された労働員会規則は、団体交渉権の侵害に対して、労働組合の労働委員会への救済申し立て権を定め、労働委員会における審問の手続は、当事者主義的構造を執ることを定めている)、さらに同法と憲法28条との密接な関係を考慮すると、労組法7条の規定は、単に労働委員会における不当労働行為救済命令を発するための要件を定めたものであるにとどまらず、労働組合と使用者との間でも私法上の効力を有するものと解すべきであって、労働組合が使用者に対して、団体交渉を求める法律上の地位を有し、使用者は、これに応ずべき地位にあるものと解し、これを前提として、その侵害に対して、労働委員会に対する救済申立権が発生するものと解するのが相当である。
解説
労働組合は、使用者の団交拒否に対して、労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てることができる(行政救済。労組法7条2号、27条)が、さらに、裁判所に対して、団体交渉請求権を根拠として、断交応諾仮処分を申請することもあった。しかし、学説、裁判例上、断交応諾仮処分における被保全権利としての団体交渉請求権が認められるかどうか(つまり、断交拒否について、司法救済が認められるかどうか)については争いがある。
これを否定する見解は、
①労使間の交渉において、使用者が誠実に交渉していたかどうかは、微妙な判断を要することがらであり、労使問題の専門的機関である労働委員会にしか適切な判断ができないこと、
②誠実交渉義務でいう義務とは、労働組合側に具体的な権利(請求権)を付与したものではないこと、
③私法上の団体交渉請求権を認めるとしても、使用者の債務の内容をどのように特定するかが難しいこと、
④団体交渉の履行を裁判上強制してみても実効性を期し難しいこと、
などを理由にあげている。
これに対して、本判決は、憲法28条や労組法の関連条文を根拠として、私法上も、労働組合が使用者に対して断交を求める法律上の地位を有すると認められ、その確認を裁判所に求めることはできるとしている。
なお、使用者の不当労働行為が不法行為に該当する場合には、民法709条等を根拠に、労働組合は損害賠償請求をすることもできる(労働組合の社会的評価の低下による無形損害の賠償を認めた裁判例として、日本レストランシステム事件ー大阪地判平成22年10月28日、国(神戸刑務所)事件ー神戸地判平成24年1月8日等)。これは、断交拒否だけでなく、支配介入や不利益取扱いの場合にも認められうる司法救済の1つである(横浜税関事件ー最1小判平成13年10月25日も参照)。ただ、本件では、労働組合に損害が発生していないということを理由に、結論として損害賠償請求は否定された。
このほか、使用者の不利益取扱い(労組法7条1号)は、私法上も無効とされている(医療法人新光会事件ー最3小判昭和43年4月9日を参照)ので、この面からも私法救済が可能である。
公共企業体等労働関係法8条(当時の規定)(団体交渉の範囲)
第八条 第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、国営企業の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。
一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項
三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
労組法6条(交渉権限)
第6条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
労組法27条(不当労働行為事件の審査の開始)
第27条 労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
2 労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
153 労働協約の成立要件-都南自動車教習所事件
最3小判平成13年3月13日(平成12年(受)192号)(民集55巻2号395頁)
要因
労働組合を使用者との間の書面化されていない合意にも規範的効力が認められるか。
事実
Xらは、Y会社のA自動車教習所に勤務する従業員である。Y会社には、Xらが所属するB労働組合とその他のC労働組合とがある。Y会社は、毎年、B組合との間ででベースアップ(ベア)交渉を行い、そこで締結された労働協約に基づき賃金を支給していた。
平成3年、Y会社は、新しい賃金体系を導入しようとしたところ、C組合はこれに同意したが、B組合はこれにどういしないまま、就業規則の改訂により新賃金体系が導入された。平成3年度のベア交渉で、Y会社は、初任給に5000円を加算してベアを行う旨の回答をしたが、この回答は、新賃金体系を前提としたものであった。そのため、B組合は、ベア分には同意したが、新賃金体系の導入には同意せず、結局、協定書の作成には至らなかった。Y会社は、労働協約が書面に作成されていなかったことを理由に、ベア分をB組合の組合員には、支給せず、C組合の組合員と非組合員にのみ支給した。平成4年度以降も、B組合とY会社との間でベア交渉が行われ、引き上げ額については合意が成立したが、平成3年度と同様の理由でB組合は協定書の作成が拒否し続けた。そのため、Y会社は、平成4年度以降も、B組合の組合員にはベア分を支給しなかった。
Xらは、主位的請求として、平成3年から同7年までの間のベア分およびベアにともなう時間外労働の増額分等からなる未払賃金を、また、予備的請求として、不法行為による損害賠償を求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、Xらの請求を認容した。そこで、Y会社は上告した。
判旨 Y会社敗訴部分について原判決破棄、差戻し。
Ⅰ「労働協約は、利害が複雑に絡み合い対立する労使関係の中で、関連性を持つ様々な交渉事項につき団体交渉が展開され、最終的に妥結した事項につき締結されるものであり、それに包含される労働条件その他の労働者の待遇に関する基準は労使関係に一定期間安定をもたらす機能を果たすものである」。
Ⅱ 労組法は、労働協約にこのような機能があることにかんがみ、16条で規範的効力を規定しているほか、17条で、一般的拘束力を規定しているし、労基法92条は、就業規則が当該事業等について適用される労働協約に反してはならないこと等を規定している。
Ⅲ 労基法14条が、労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、または、記名押印することによって、その効力を生ずることとしているゆえんは、労働協約に前記のような法的効力を付与することとしている以上、その存在および内容は、明確なものでなければならないからである。
Ⅳ 労働協約は複雑な交渉過程を経て団体交渉が最終的に妥結した事項につき締結されるものであるから、口頭による合意または、必要な様式を備えない書面による合意のままでは、後日、合意の有無およびその内容につき、紛争が生じやすいので、その履行をめぐる不必要な紛争を防止するために、団体交渉が最終的に妥結し、労働協約として、結実したものであることをその存在形式自体において明示する必要がある。
Ⅴ「したがって、書面に作成され、かつ、両当事者がこれに署名押印しない限り、仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与することはできないと解すべきである」。
解説
労組法14条は、労働協約が効力を発生するためには、書面により作成され、両当事者が署名または記名押印することが必要である(要式性)、と定めていり。要式性を欠く労働協約の効力については、
①一切の効力がない、
②規範的効力や一般的拘束力はないが、債務的効力はある、
③一般的拘束力はないが、規範的効力と債務的効力はある、
という考え方に分かれる。
本判決は、労働協約の定める労働条件は、労使関係に一定期間あんていをもたらす機能があり(判旨Ⅰ)、その機能にかんがみて、労組法および労基法は労働協約に規範的効力、一般的拘束力、就業規則に対する優先効を付与しているのであり(判旨Ⅱ)、労働協約の要式性は、こうした効力をもつ労働協約について、その存在およびないようを明確にするために定められたものとする(判旨Ⅲ)。そして、こうした要式性は、合意の有無や内容をめぐる紛争を防止するためにも必要であり(判旨Ⅳ)、結論として、要式性を欠く場合は、規範的効力は認められない(判旨Ⅴ)。
この判決により、最高裁が、前記の考え方の中の③を支持しないことは明らかになったが、①と②のいずれの立場であるかは、明確ではない。理論的には、要式性を欠くとはいえ、労使間に合意がせいりつしている場合には、少なくとも債務的効力は発生するという考え方はありえよう。また、労働組合と使用者との間の合意が、黙示の合意や労使慣行等を根拠として個別的労働契約の中に取り込まれていると解釈される場合には、労働者は、労働契約を根拠として、労使間の合意内容の履行を使用者に請求することが認められるであろう。
労組法16条 (基準の効力)
第16条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
労組法17条(一般的拘束力)
第17条 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
労組法14条(労働協約の効力の発生)
第14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
労基法92条 (法令及び労働協約との関係)
第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
154 労働協約の規範的効力(1)-朝日火災海上保険(石堂)事件
最1小判平成9年3月27日(平成7年(オ)1299号)
要因
退職金基準や定年年齢を引き下げる労働協約に規範的効力は認められるか。
事実
Y会社は、昭和40年に、A会社の鉄道保険部を引き継いだが、それにともないA会社の従業員であったXらは、Y会社に移籍することになった。Y会社は、同社に元からいた従業員と、A会社から移籍した従業員との間の労働条件を直ちに統一せず、Y会社の従業員で組織されたB労働組合との交渉を通じて、順次、統一化を進めてきた。しかし、定年年齢の統一については、合意に至らないまま時が経過し、A会社出身の者は、満63歳であるのに対し、それ以外の従業員は満55歳とされていた。
Y会社は、昭和52年、経営が悪化したため、従業員の定年年齢の統一について、B組合との間で、交渉を続けた。その結果、同58年5月に、定年年齢の統一、退職金支給率の変更について口頭で合意し、同年7月、この合意内容を書面化した労働協約に労使双方が署名押印した。この労働協約の締結にともない、Y会社は、就業規則も同一内容に改訂した。
この労働協約の主たる内容は、昭和58年4月1日よりマン7歳の誕生日をもって定年とすること、定年後引き続き勤務を希望し、かつ、心身ともに健康な者は、原則として、満60歳まで特別社員として、再雇用されること(特別社員の給与は、定年時の本人給および職務給の合計額の60%、退職金は、満57歳の定年時に支給し、退職金の基準支給率は、現行の「30年勤続・71箇月」から「30年勤続・51箇月」とし、本件変更にともなう代償金が支給されること、というものであった。
A会社出身で、B組合の組合員であったXは、本件労働協約が締結されたときに53歳であった。Xは、労働協約の変更による定年年齢の引き下げと退職金基準支給率の引き下げは無効であると主張し、65歳定年制(Xは、労使慣行により、定年年齢は65歳と主張)を前提とする退職金の支払いを受ける地位にあることの確認を求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、Xの請求を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)。
Ⅰ「本件労働協約は、Xの定年及び退職金算定方法を不利益に変更する者であり・・・・これによりXが受ける不利益は決して小さいものではないが、同協約が締結されるに至った・・・・経緯、当時のY会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特定の又は、一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働協約の目的を逸脱して、締結された者とはいえず、その規範的効力を否定すべき理由はない。
Ⅱ「本件労働協約に定める基準がXの労働条件を不利益に変更するものであることの一事をもって、その規範的効力を否定することはできないし・・・・、また、Xの個別の同意又は組合に対する授権がない限り、その規範的効力を認めることができないものと解することもできない」。
解説
労組法16条は、「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする」という強行的効力を規定し、「無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする」という直律的効力も規定している。両者の効力を合わせて規範的効力という(労働協約よりも有利な労働契約の効力を否定するかは、有利原則の問題として、議論がある)。
労働条件を不利益に変更する労働協約にも、この規範的効力が生じるかについては、議論があった。労組法2条は、労働組合の主たる目的を、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ること」と定めており、組合員の労働条件を不利益に変更することは、労働組合の目的に反するもので、組合員個人の同意を必要とするという裁判例もあった(大阪白急タクシー事件ー大阪地決昭和53年3月1日等)。しかし、労働組合の交渉は、ギブ・アンド・テイクの要素があり、労働条件の不利益変更を一切、認めないのは、現実的ではないとして、変更内容について、合理性が否定されるばあいでなければ、規範的効力を認めるべきではないという考え方が強まってくる(たとえば、日本トラック時間ー名古屋高判昭和60年11月27日)。
本判決は、労働条件を不利益に変更する労働協約の規範的効力を原則として肯定した(→【156】朝日火災海上保険(高田)事件も参照)うえで、例外的に、「同協約の特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して、締結されたもの」である場合には、規範的効力が否定されるとした。これは、従来の裁判例とは異なり、労働協約の内容について、労働組合が組合内部の少数派の利益を不当に侵害する内容の労働協約を締結訴ていないかに着目する公正代表審査の考え方を示したものとみることができる。
その具体的な判断は、協約締結の経緯、使用者側の経営状態、協約の定めた基準の全体としての合理性等を考慮して行われる(判旨Ⅰ。中央建設国民健康保険組合事件ー東京高判平成20年4月23日も参照)。
労組法16条(基準の効力)
第16条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
155 労働協約の規範的効力(2)-中根製作所事件
東京高判平成12年7月26日(平成11年(ネ)4601号)
要因
高年齢組合員の賃金を変更する労働協約に規範的効力は認められるか。
事実
Y会社は、赤字が続いていることから、同社の従業員で組織されているA労働組合との間で、平成8年に、53歳以上の組合員の基本給を引き下げる内容の労働協約(本件労働協約)を締結した(第1次減額)。協約締結に至るまでの過程は、次のようなものであった(なお、A組合の規約上、労働協約の締結は、大会付議事項であった)。まず、同年4月6日に、Y会社の会長、役員、顧問と組合三役が出席した賃金改訂会議が開かれ、その場で会長から、高齢者の賃金減額と若年者の昇給の提案が行われた。同23日、Y会社は全従業員に対する説明会を開き、この提案の説明を行った。同25日、A組合の大銀会が開催され、同26日、各職場での職場会における意見聴取が実施された。同27日、再度、代議員会が開催され、そこでの決議を受けて、A組合は、前記労働協約を締結した。同年11月1日、A組合の提起大会で協約締結についての報告が行われた。
なお、その後、労働協約の改訂を経ずに、再度の賃金減額が行われている(第2次減額)。
以上の第1次減額、第2次減額について、A組合の組合員であったXら(いずれも協約締結時には53歳を超えていた)が、いずれの減額も無効であるとして、月額給与等の減額分の支払いを求めて訴えを提起した。1審は、本件労働協約の規範的効力を否定した(第2次減額についても無効)。そこで、Y会社は控訴した。なお、本判決に対する上告は、棄却・不受理となっている。
判旨 控訴棄却(Xらの請求の一部認容、一部棄却、第1次減額についての判断のみとりあげる)。
Ⅰ 労働協約の締結は、組合大会付議事項であるが、本件労働協約の締結にあたって組合大会で決議されてはいないので、本件労働協約は、組合の協約締結権限に瑕疵があり、無効である。
Ⅱ A組合では、昭和50年ころ以降、労働協約締結のために臨時組合大会が開催されたことはなく、職場会における意見聴取、(代議員会における決議によって組合の意思決定がなされてきた。本件労働協約の締結にあたっても、同様の手続を経て締結されたが、職場会における意見聴取の様子は、これに代議員の決議が加わったことをもって、組合大会の決議に代替しうるものと評価することはできない。
Ⅲ A組合が前記の手続で意思決定をしてきた労働協約は、賃金等重要な労働条件についての不利益変更を内容とするものではないところ、本件労働協約は、53歳以上の労働者のみを対象とした、きわめて大きい不利益変更を内容とするものであり、前記の経緯があるかえあといって、組合大会の付議事項としない扱いを肯定することはできない。
Ⅳ 本件労働協約の締結後に開催された組合大会において、報告事項として承認されたとしても、そのことをもって協約締結に必要な決議があったとみることもできない。
Ⅴ Y大会は、営業利益が赤字となり、その傾向が今後も続くと判断しているが、平成8年4月当時、直ちに経営危機に陥るほどの悪化した経営状態にあったとは到底いえないこと、株主への配当や役員報酬の支払はおこなっていること、52歳以下の従業員に対しては、昇給をおこなっていることからすると、53歳以上の労働者に対しても、個々の同意をえることなしに、基本給を減額しなければならない必要性があったものとはいえない。
また、本件労働協約は、53歳に達した労働者に対し、その時点での基本給の21.7%の、また、58歳以上の労働者に対して23%の減額をおこなうことを内容とする者であり、合理性を欠く。
解説
本件は、53歳以上の労働者に対して基本給を引き下げるないようの労働協約が規範的効力をもつか争われた事件である。
本判決は、まず、A組合では、労働協約の締結は、規約上大会付議事項となっているので、大会決議を経ていない協約締結は、組合の締結権限に瑕疵があり、無効であるとする(判旨Ⅰ)、その瑕疵は、事後の大会で協約締結の報告を承認されたとしても、治癒されない(判旨Ⅳ)。もっとも、A組合では、従来、協約締結のための事前手続は、大会を開かず、職場会の意見聴取と代議員会の決議だけであったという事情があるが、それは重要な労働条件の不利益変更をもたらすような内容のものではなかったので、先例とはならないし(判旨Ⅲ)、今回の労働協約締結の一連のプロセスだけでは、大会決議に代替する決議があったと評価することもできない(判旨Ⅱ)とした。そのうえで、協約という判断を付加して(判旨Ⅳ)、結論として、規範的効力を否定している。
判例(→【154】朝日火災海上保険(石堂)事件)に照らして考えると、本判決は、労働協約の改訂により、一部の組合員に大きな不利益をもたらし、協約の内容面での合理性が十分にないような場合、それが、一部の組合員を殊更不利益に取り扱うものでないというためには、協約締結過程において、不利益を受ける組合員に配慮する手続の履践が重視されるということを示したとみることができる(類似の裁判例として、鞆鉄道事件ー広島高判平成16年4月15日)。
156 労働協約の一般的な拘束力-朝日火災海上保険(高田)事件
最3小判平成8年3月26日(平成5年(オ)650号)(民集50巻1008頁)
要因
労働協約の拡張適用による労働条件の不利益変更は認められるか。
事実
Xは、昭和26年6月にA会社の鉄道保険部の職員として採用された。同40年にA会社の鉄道保険部は、Y会社に引き継がれた。Xは、同58年4月1日現在、Y会社のB支店の営業担当調査役の地位にあり、すでに満57歳に達していた。Y会社とC労働組合との間で、締結された労働協約では、調査役は、非組合員と定められていて、Xも非組合員であった。B支店では、常時使用されている従業員の4分の3以上がC組合の組合員であった。
労働協約の締結に至るまでの経緯は、朝日火災海上保険(石堂)事件(→【154】)と同じである。Xは、本件労働協約および改訂就業規則は自らに適用されないとして、労働契約上の地位の確認、変更前の規定に基づく賃金との差額の支払いを求めて、訴えを提起した。1審は、労働契約の拡張適用および就業規則の変更の拘束力をともに肯定して、遡及的に不利益変更をした部分を除き、Xの請求を棄却した(一部認容)。原審も基本的には1審判決を支持し、Xが原審で追加した退職金の差額請求については、一部認容した。そこで、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求の一部認容、一部却下、一部棄却。以下は、労働協約の一般的拘束力の部分のみとりあげる)。
Ⅰ「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても、右労働協約の規範的効力が及び旨の一般的拘束力が認められている。ところで、同条の適用にあたっては、右労働協約上の基準の一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのことだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の規範的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないのである。
また、右規程の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故故に、労働協約の規範的効力がこれに及ばないとするのは相当でない」。
Ⅱ「しかしながら、他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場はなく、また、逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協約によって、特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度、内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが、著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である」。
解説
労働組合法17条は、労働協約が「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたとき」は、当該労働協約を締結した労働組合の組合員でない者にも労働協約の適用を認めることを定めている。これを労働協約の拡張適用(一般的拘束力)という(地域レベルの拡張適用もある(労組法18条))。
労働協約の拡張適用による労働条件の不利益変更が認められるかについて、本判決は、文言上否定されていないこと、労働協約は総合的に労働条件を定めていくので、その一部をとらえて有利、不利をいうべきでないこと、という規範的効力と共通する理由をげたうえで、17条の趣旨(労働条件の統一化、団結権の維持強化、公正妥当な労働条件の実現)にも言及して、原則としてこれを肯定する(判旨Ⅰ)。ただし、未組織労働者は労働組合の意思決定に関与する立場になく、また、労働組合のほうも未組織労働者の利益を擁護する立場にないことも考慮して、「特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるとき」は、一般的拘束力は否定されるとした(判旨Ⅱ)。具体的な判断要素としては、不利益の程度・内容・協約締結に至った経緯、当該労働者の組合員資格の有無などがあげられている(判旨Ⅲ)。本件では、不利益の程度が大きく、Xに組合員資格がないことが重視されて、一般的拘束力は否定された。
本判決は、未組織労働者への拡張適用の事例であるが、少数組合の組合員への拡張適用は、とりわけ労働条件の不利益変更につては、通説、裁判例は、少数組合の団結権や団体交渉権を尊重するという観点から、拡張適用を認めない立場である(大輝交通事件ー東京地判平成7年10月4日等を参照)。
労働組合法17条 (一般的拘束力)
第17条 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
労働組合法18条(地域的の一般的拘束力)
第18条 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
2 労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。
3 第一項の決定は、公告によつてする。
157 労働協約の一部解約-ソニー事件
東京高判平成6年10月24日(平成6年(ラ)801号)
要因
労働協約中の一部の条項を解約することは適法か。
事実
Xらは、Y会社の従業員であり、同社内で組織されるA労働組合の組合である。Y会社には、A組合以外にY会社を含む3会社の従業員によって組織されるB組合がる。組合員数は、A組合が120名、B組合が総計で約9600名である。
平成4年4月に、Y会社は、A組合との間で労働協約を締結した。この協約は「賃金に関する項目」と「その他の項目」とに分かれており、「その他の項目」の中の1つに「労働時間の短縮について」という項目があった。この「労働時間短縮について」という項目では、「生産性向上、業務の効率化、その他制度の多面的な見直し等経営体質強化に必要な対応を行うことを前提として、次の施策を実施する」という前文があり、それを受けて、所定労働時間を、平成5年は、1896時間、平成6年は1856時間と段階的に短縮することが定められていた(本件時短協定)。そして、平成5年の時短分40時間は、年5日の個人別休日とする旨の合意がなされ、実際、Xらはすでに有していたものと合わせて合計11日の休日を取得した。
平成5年10月、Y会社は、A組合に対して、円高など経営環境の悪化を理由に、本件、時短協定による平成6年の時短を1年延期したい旨の申し入れをし、団体交渉が行われたが、A、組合はこれを受けいれなかった。B組合は同様の申し入れに対して同意をしていた。
Y会社は、平成5年12月17日、A組合に対して、平成6年の時短を行わない旨通知し、同27日に本件時短協定のうち所定労働時間を平成6年から1856時間とする部分を解約した。これに対し、Xらはこの解約は無効であると主張し、平成6年の時短分として、各自が指定した日を個人別休日として行使できる地位を有すること、予備的に、年間6日の個人別休日を有する地位にあること、および所定労働時間時間が平成6年1月以降1856時間である地位にあることを仮に定めることを申し立てた。原審は、被保全権利は未だ抽象的なものにとどまり、保全の必要性もないとして、申立てを許可したため、Xらは抗告した。
判旨 抗告棄却(Xらの申立て却下)。
Ⅰ「多くの場合には、一々の労働協約は、その内部において相互に関連を有する一体的な合意であるから、一方の当事者が自己に不利と考えるその一部を取り出して解約しようとすれば、残された他の部分により他方の当事者が当初予想していなかった危険、損害を被ることもないではなく、解約は当該1つの労働協約全部に及ぶのを原則とすべきものと解するのがことができる」。
Ⅱ 本件時短協定には、前文が付されており、その前文は「生産性向上等のための諸施策を講ずることができなくなったときには労働時間短縮を義務付けられるものでない趣旨であると解するのが常識的である」。「当事者双方において、このように前掲条件の付せられた他とは性質の異なる条項をおいたからには、これを他の部分と切り離して扱うこととなることも当然に予想されるべきことであったといわなければならない」。
Ⅲ「協約自体のなかに客観的に他と分別することのできる部分があり、かつ、分別して扱われることもあり得ることを当事者としても予想し得たと考えるのが合理的であると認められる場合には、協約の一部分をとりだして解約することもできると解するのが相当である」。
解説
労働協約の中の一部の規定のみを解約する一部解約は、原則として、許されない。労働協約は、労使双方が全体を一体的な合意として妥結するのが通常であり、その中の一部分だけを解約できるとすると、一方当事者が都合の悪い部分のみを解約することも認められてしまい妥当でないからである。
ある裁判例は、定年延長にともない一括してごういされた退職金条項と賃金条項を含む労働協約について、会社側が退職金条項のみを解約しようとした事案で両条項は、「互いに密接な関連性を有し、そのいずれかが欠けても協約の締結はきたいできなかったこと」を理由に解約を無効としていた(光洋精工事件―大阪地判平成元年1月30日)。本判決も、原則として、一部解約は認めない立場である(決定判旨Ⅰ)。
この原則の例外は、「協約自体のなかに客観的に他と分別することのできる部分があり、かつ、分別して扱われることもあり得ることを当事者としても予想し得たと考えるのが合理的であると認められた場合」である(決定判旨Ⅲ 債務的部分の一部解約を認めた裁判例として、→【186】日本アイ・ビー・エム事件[解説])。
本件で、問題となった時短協定については、本決定は、「前提条件の付せられた他とは性質の異なる条項」があることから、「他の部分と切り離して扱うこととなることも当然に予想されるべきことであったといわなければならない」として、その部分のみの解約も許されると判断した(決定要旨外)。
158 労働協約失効後の労働条件-香港上海銀行事件
最1小判平成元年9月7日(昭和60年(オ)728号・719号)
要因
退職金協定が失効した場合でも、退職金の請求は認められるか。
事実
Y会社の就業規則には、退職金は「支給時の退職金協定による」と定められていた。Y会社には、Xの属する少数派のA労働組合と多数派のB労働組合とがあり、Y会社がB組合と締結したのと同じ内容の退職金協定がA組合との間で締結されていた。Y会社は、B組合と締結した退職金協定の写しを添付した変更就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出ていた。
Y会社の臨時職員であるXは、Y会社との労働契約においては、雇用期間は昭和54年6月30日までとされていたが、昭和58年6月30日までの間は、1年ごとに雇用期間を更新することが可能とされており、実際、更新されていた。ただし、退職金の支給については、昭和55年6月30日に退職したものとみなして、同日に支払うものとされていた。
ところで、Y会社がXの加入していたA組合と締結していた退職金協定は、すでに昭和53年12月末に、失効していた。そのため、Y会社は、Xに対して退職金を支給しなかった。そこで、Xは、退職金の支給を求めて訴えを提起した。1審はXの請求を認容した。なお、Y会社では、昭和59年7月25日に、B組合との間で、昭和55年度退職金協定が締結されており、さらにその協定に基づき就業規則の変更を行い、昭和59年8月21日に所轄労働基準監督署長に届け出た。原審は、このB組合との協定が、労働協約の一般的拘束力(労組法17条)に基づきXにも及ぶとして、(これにより当初の退職金よりも減額される)、1審判決を変更した。Xは上告して、Y会社も附帯上告した。
判旨 X敗訴部分について、原判決破棄、自判(Xの請求認容)
Ⅰ XとY会社との間の労働契約上は、退職時に退職金の額が確定することが予定されており、就業規則の規定も、Y会社が従業員の支払義務を負うことを前提として、その額の算定だけを退職金協定に基づき行おうとする趣旨のものと解されるから、A組合との間で、新たな退職金協定が締結されていないからといって、Xの退職金額が確定せず、具体的な退職金請求権も発生しないと解するのは、相当でなく、労働協約、就業規則等の合理的な解釈により、退職時において、その額が確定されるべきである。
Ⅱ Y会社は、B組合と締結した退職金協定書の写しを添付した就業規則変更届を所轄労働基準監督署長に届け出ており、同協定に定められた退職金の支給基準は、就業規則に取り入れられてその一部となったというべきである。そして、就業規則は、労働協約が失効しても空白となる労働契約の内容を補充する機能も有すべきでものであることを考慮すれば、就業規則に取り入れられ、これと一体となっている退職金協定の支給基準は、退職金協定が有効期間の満了により、失効しても、当然には効力は失わず、退職金協定のない労働者については、この支給基準により、退職金額が決定されるべきものと解するのが相当である。
Ⅲ「既に発生した具体的権利としての退職金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分、変更することは許されないというべきであるから、昭和59年にB組合との間で締結された昭和55年度退職金協定のXへの拡張適用はそもそも認められない。就業規則の変更についても、同様の理由により、遡及適用を認めることはできない。
解説
1 労働協約が期間満了や解約により終了した場合、その後の労働条件がどうなるかについては、労働協約の規範的効力が労働協約にどのように作用するかという論点とかかわる。これについては、労働協約は労働契約の内容に化体するという説(化体説)と、労働協約は労働契約をその外部から規律するという説(外部規律説)とがある。化体説によれば、労働協約が失効しても、労働協約の内容は労働契約の内容として残存することになる。一方、外部規律説によると、労働協約が失効すれば、労働協約の内容は、空白になる。学説、裁判例上は、外部規律説が有力である。ドイツでは、労働協約の失効後も、労働協約の直律的効力は継続するという余後効が法律の明文で認められているが、日本では、そのような規定はなく、余後効は認められないと解されている。
外部規律説によると、労働協約の失効後は、空白となった労働契約の内容を補充することが必要となる(判旨Ⅰも参照)。就業規則等の補充規範がないかぎり、従前の労働協約上の労働条件が、労働契約の内容を補充することになる(組合員の労働契約の合意的意思解釈。鈴蘭交通事件ー札幌地判平成11年8月30日、音楽之友社事件ー東京地判平成25年1月17日を参照)。
本判決は、就業規則の届出の過程などから、労働協約が就業規則の内容に取り込まれているとして、就業規則の効力として、従来の労働協約の規定が適用されるとした(判旨Ⅱ)。
2労働協約や就業規則の遡及的適用により、労働条件を不利益に変更することは、それがすでに発生した具体的な権利の処分や変更をもたらすものである場合には、認められない(判旨Ⅲ)。既往の労働に対する対価としての賃金請求権が、その典型例である(→【156】朝日火災海上保険[高田]事件[判旨外])。
158 労働協約失効後の労働条件-香港上海銀行事件
最1小判平成元年9月7日(昭和60年(オ)728号・719号)
解説
1 労働協約が期間満了や解約により終了した場合、その後の労働条件がどうなるかについては、労働協約の規範的効力が労働協約にどのように作用するかという論点とかかわる。これについては、労働協約は労働契約の内容に化体するという説(化体説)と、労働協約は労働契約をその外部から規律するという説(外部規律説)とがある。化体説によれば、労働協約が失効しても、労働協約の内容は労働契約の内容として残存することになる。一方、外部規律説によると、労働協約が失効すれば、労働協約の内容は、空白になる。学説、裁判例上は、外部規律説が有力である。ドイツでは、労働協約の失効後も、労働協約の直律的効力は継続するという余後効が法律の明文で認められているが、日本では、そのような規定はなく、余後効は認められないと解されている。
外部規律説によると、労働協約の失効後は、空白となった労働契約の内容を補充することが必要となる(判旨Ⅰも参照)。就業規則等の補充規範がないかぎり、従前の労働協約上の労働条件が、労働契約の内容を補充することになる(組合員の労働契約の合意的意思解釈。鈴蘭交通事件ー札幌地判平成11年8月30日、音楽之友社事件ー東京地判平成25年1月17日を参照)。
本判決は、就業規則の届出の過程などから、労働協約が就業規則の内容に取り込まれているとして、就業規則の効力として、従来の労働協約の規定が適用されるとした(判旨Ⅱ)。
2労働協約や就業規則の遡及的適用により、労働条件を不利益に変更することは、それがすでに発生した具体的な権利の処分や変更をもたらすものである場合には、認められない(判旨Ⅲ)。既往の労働に対する対価としての賃金請求権が、その典型例である(→【156】朝日火災海上保険[高田]事件[判旨外])。
159 労働協約の債務的効力-弘南バス事件
最3小判昭和4312月24日(昭和39年(オ)773号)(民集22巻13号3194頁)
要因
平和義務違反の争議行為の正当性は認められるか。
事実
一班乗合自動車運送事業を営むY会社の従業員らで組織されたA労働組合は、昭和35年、賃上げおよび協約改定の要求をしてY会社と団体交渉を行ったが、妥結には至らなかったので、同年3月7日に指名ストに入った(協約改訂目的の指名ストは同月21日から)。Y会社は、同年4月15日に、A組合の車掌支部の支部長X1と副支部長X2とに対して、ビラ等の掲示、無許可職場集会の強行、車掌控室における労働歌の合唱等をしたことを理由として懲戒解雇を行ったところ、Xらは、この懲戒解雇は無効であるとして、従業員としての地位を有することの確認を求めて訴えを提起した。
なお、Y会社とA組合との間では、昭和34年の賃上げ争議妥結協定では「今後の労使関係について双方は良識と理解と信義に立脚し企業繁栄のための最善の努力と協力の関係を確立する」、細目協定では「組合は会社の昭和34年度事業計画達成のため全面的に会社に協力するとともに、労使間は、問題を常に平和的に解決する」とさだめられていた。さらに、昭和33年に締結された労働協約には、「本協約の有効期間は、調印の日から、昭和35年6月7日迄とする。期間満了後1か年を限り有効とする。但し、期間内でも両者の合意により変更することが出来る」という条項が含まれていた。
1審は、本件懲戒解雇は解雇権の濫用であるとして、Xらの請求を認容し、原審は、Y会社の控訴を棄却した。原審は、争議妥結協定と細目協定が絶対的平和義務を定めたと解しうるとしても、組合の債務不履行責任を生じるにとどまり、個々の組合員に関し争議行為の正当性を失わせるものではないとした。また、相対的平和主義については、労働協約の有効期間満了の相当の期間前に、満了後の労働条件を定めるべき次期労働協約の締結の要求をなすことには合理的理由があるとして、本件のように協約有効期間満了から約2か月半前に行われた争議行為は、相対的平和主義に反しないと判断した(仙台高秋田支判昭和39年4月14日)。そこで、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xらの請求認容)
平和主義に違反する争議行為は、その平和主義が労働協約に内在するいわゆる相対的平和主義である組合においても、また、いわゆる絶対的平和主義条項に基づく平和義務であるばあいにおいても(争議妥結協定および細目協定は、紛争解決に関する当事者のたんなる心構えの相互確認の域をでるものではなく、いわゆる絶対的平和主義条項ではありえない)。これに違反する争議行為は、たんなる契約上の債務の不履行であって、これをもって、企業秩序の侵犯にあたるとすることはできず、個々の組合員がかかる争議行為に参加することも、労働契約上の債務不履行にすぎないものと解するのが相当である。
したがって、使用者は、労働者が平和主義に違反する争議行為をし、またはこれに参加したことのみを理由として、当該労働者を懲戒処分に付しえない。
解説 労働協約には、労働条件その他の労働者の待遇に関する基準を定める部分とそれ以外の部分とがある。前者を規範的部分といい、後者を債務的部分という。規範的部分には、規範的効力が認められている(労組法16条)。債務的部分には、規範的効力は生じないが、債務的効力(契約としての効力)は生じる。労働協約には、労働組合と使用者との間の契約としての面もあるからである。
労働協約の債務的効力のなかには、通常の契約とは異なる独自の考察が必要となるものもある。その典型例が平和主義である。平和義務とは、協約当事者が協約有効期間中に争議行為に訴えないという義務であり、これはさらに、相対的平和主義とは、協約所定の事項の改廃を目的とした争議行為をしない義務であり、絶対的平和主義とは、このような目的に限定せず、いっさいの争議行為をしない義務である。
相対的平和主義の根拠については、協約の性質のあるいは信義則上当然に認められるとする説(内在説)と協約当事者の明示または黙示の合意に根拠を求める説(合意説)とがある。他方、絶対的平和主義については、当事者がこのような義務について特に合意をした場合にのみ認められると解されている。本判決は、本件では、争議妥結協定および細目協定は絶対的平和主義条項とはいえないとはんだんしている。
本件では、争議行為が平和義務に違反して行われた場合に、それに参加した労働者に懲戒処分を課すことができるかが問題をなっている。本判決は、一般論として、平和義務違反の争議行為は、労働組合の契約(労働協約)上の債務不履行にすぎないし、これだけでは企業秩序侵犯にあたるものではないとしている。さらに、組合員個人をみても、これは労働契約上の債務不履行にすぎないので、当然に懲戒処分ができるわけではないとしている。労働契約上の債務不履行であっても、争議行為に正当性が認められれば、懲戒処分が無効とされる可能性はあるからである(労組法7条1号民法90条。なお、本件では懲戒事由該当性が否定されたとみることもできる)。ただ、平和義務違反の事実は、直ちに争議行為の正当性を否定することにはならなくても、正当性を否定する要素とはなる。
労組法16条 (基準の効力)
第16条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
民法90条(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
労組法7条1号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
160 労働協約中の事前協議約款の効力-洋書センター事件
東京高判昭和61年5月29日(昭和56年(ネ)1140号)
要因
労働協約中の事前協議約款に違反してなされた懲戒解雇は有効か。
事実
X1およびX2は、洋書および教育機器の展示・販売等を目的とするY会社の従業員であり、昭和48年にA労働組合を結成した。Y会社は、賃借していたビルの建て替えのために、一時的な立ち退きを要請されたため、仮店舗に移転する旨をA組合に通告したところ、A組合は、職場面積が小さくなる、労働条件の低下につながるとして、これに反対した。Y会社は、別の仮店舗の案をいくつか出したが、A組合はこれに応じなかった。Y会社が、最終的に仮店舗移転を強行したところ、Xらは、仮店舗に出勤してきたY会社のB社長を、旧社屋に連れて行き、長時間にわたり軟禁し、暴行傷害を実行するという事件を起こした。その後も、Xらは旧社屋ビルを占拠するなどのトラブルを起こした。
そこで、Y会社は、Xら両名を懲戒解雇した(本件解雇)。なお、Y会社とA組合の間で締結された労働協約には、「会社は運営上、機構上の諸問題ならびに従業員の一切の労働条件の変更については、事前に、組合、当人と充分に協議し同意を得るよう努力すること」という条項(本件事前協議約款)が含まれていた。
Y会社は、本件解雇に際して、事前にA組合および本人と協議しなかったので、Xらは、本件解雇は、本件事前協議約款に違反して、無効であることなどを理由として、雇用契約上の地位を有することの確認を求めて訴えを提起した。1審は、Xらの請求を棄却した。そこで、Xらは控訴した。
判旨 控訴棄却(Xらの請求棄却)。
「組合の構成員は、パートタイマーのX3を除けば本件解雇をされたX1およびX2の両名ののみであり、A組合の意思決定は主として右両名によって行われ、A組合の利害と右両名の利害とは密接不可分であlちたところ、Xら両名は、本件解雇理由たる、前叙の両名共謀によるB社長にたいしての長時間に及ぶ軟禁、暴行傷害を実行した当の本人であるから、その後における組合闘争としての、Xら両名らによる旧社屋に不法占拠などの前叙の事態をも併せ考えると、もはや、Y会社とA組合及びXら両名との間には、本件解雇に際して、本件事前協議約款に基づく協議をおこなうべき信頼関係は全く欠如しており、前叙の「労働者の責に帰すべき事由」に基づく本件解雇については、A組合及び当人の同意を得ることは勿論、その協議をすること自体、到底期待し難い状況にあった、といわなければならないから、かかる特別の事情の下においては、Y会社が本件事前協議約款に定められた手続を履践することなく、かつ、A組合及び当人の同意を得ずに、X1及びX2を即時解雇したからといって、それにより、本件解雇を無効とすることはできない。
解説
労働協約の中には、労働組合との協議などの手続が定められていることがすくなくない。たとえば、解雇や配転の際には、労働組合と協議をする。あるいは、労働組合の同意を得るといった条項がその典型例である。このような条項に違反して行われた解雇や配転などの効力については議論がある。こうした条項には規範的効力が認められているとして、条項違反の解雇を無効とする見解や、条項には債務的効力しか認められないとして、せいぜい、条項に違反した使用者に債務不履行による損害賠償責任が認められるにすぎないという見解がある。もっとも、債務的効力しか認められないとしても、こうした条項に違反した解雇や配転などは、重大な手続的違背があるとして、権利濫用により無効となるという考え方もある。最後の考え方によると、本件のような解雇の事例で、事前協議約款の違反があった場合には、解雇権濫用法理(現在の労契法16条)により、無効となるとする法律構成がとられることになる。
本判決は、事前協議約款が解雇に及ぼす効力自体については、明言していない。本判決が、本件においては、事前協議約款に違反していないと判断したのか、違反しているが、本件の事情を考慮すると、解雇の効力には影響しないと判断したのかは判然としないが、解雇権が濫用となるかどうかにつき、事前協議約款違反の事実も、その他の諸事情と併せて考慮したうえで、判断するという枠組みを採用したとみることができよう。
いずれにせよ、本件は、Y会社側は、軟禁や暴行傷害をした当の組合員と、その件について、事前協議をする信頼関係は失われているので、事前協議をしていなくても重大な手続違背とはいえず、解雇の効力に影響をしないケースであったといえよう。
労契法16条(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
161 公務員の労働基本権-全農林警職法事件
最大判昭和48年4月25日(昭和43年(あ)2780号)(刑集27巻4号47頁)
要因
公務員の労働基本権を制限する公務員法上の規定は合憲か。
事実
昭和33年10月、内閣が警察官職務執行法の一部を改正する法律案を衆議院に提出したとき、これに反対するために、農林水産省の職員によって組織されているA労働組合は、同年11月5日に所属長の許可なしに正午出勤の行動に入ることとし、同日の午前9時から11時40分までの間、庁舎前における職場集会を計画し(実際の開始時間は午前10時)、同省職員に参加を懲慂して、争議行為をあおった。このため、A組合の役員であるXら5名が、国公法110条1項17号に該当するとして起訴された。1審は、全員無罪、2審では全員有罪となった。そこで、Xらは上告した。
判旨 上告棄却(Xらは有罪)
Ⅰ「公務員は、・・・・自己の労務を提供することにより生活の資を得ているものである点において一般の勤労者と異なるところはないから、憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶものと解すべきである。ただ、この労働基本権は、・・・・それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、おのずと勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない」。
Ⅱ「公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として、公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきである。けだり、公務員は、公共の利益のために勤務するものであり、公務の円滑な運営のためには、・・・・それぞれの職場においてその職責を果たすことが必要不可欠であって、公務員が争議行為に及ぶことは、その地位の特殊性および職務の公共性と相いれないばかりでなく、多かれ少なかれ公務の停廃をもたらし、その停廃は、勤労者を含めたコム民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすか、または、その虞れがあるからである。
Ⅲ「組む員の場合は、その給与の財源は、国の財政と関連して主として税収によって賄われ、・・・・その勤務条件は、すべて政治的、財政的、社会的その他諸般の合理的な配慮により適当に決定されなければならず、しかもその決定は民主国家のルールに従い、立法府において論議のうえなされるべきもので、同盟罷業等争議行為の圧力による強制を容認する余地は全く存しないのである。・・・・被審の勤務条件の決定に関し、政府が国会から適法な委任を受けていない事項について、公務員が政府に対し、争議行為を行うことは、・・・・民主的に行われるべき公務員の勤務条件決定の手続過程を歪曲することともなって、憲法の基本原則である議会制民主主義(憲法41条、83条等参照)に背馳し、国会の議決権を侵す虞れすらなしとしないのである」。
Ⅳ「一般の私企業においては、その提供する製品または役務に対する需要につき、市場からの圧力を受けざるをrない関係上、争議行為に対しても、いわゆる市場の抑制力が働くことを必然とするのに反し、公務員の場合には、そのおうな市場の機能が作用する余地がないため、公務員の争議行為は場合によっては、一方的に強力な圧力となり、この面からも公務員の勤務条件決定の手続をゆがめることとなるのである。
Ⅴ 被審は、労働基本権に対する制限の代償として、人事院勧告等、制度上整備された生存権擁護のための関連措置により保障を受けている。
解説
公務員の争議行為は、全面的に禁止されている(国公法98条2項、地公法37条。このほか、行政執行法人の労働関係に関する法律7条等も参照)。公務員も憲法28条の勤労者に該当する(判旨Ⅰ)ことからすると、このような争議行為禁止規定は、憲法28条に違反しないかが問題となる。昭和40年代初めは、判例は、合憲的限定解釈により合憲となるとする立場(実質的には違憲判断に近い)をとっていた(全逓東京中郵事件ー最大判昭和41年10月26日等)がる、本判決により、全面合憲論に修正された。
本判決は、まず、労働基本権は「国民全体の共同利益の見地からする制約」があるとしたいえで(判旨Ⅰ)、「公務員の地位の特殊性を職務の公共性」にかんがみ、「労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由がある」とする(判旨Ⅱ)。そして、議会制民主主義の観点、市場の機能が代用する余地がないこと、労働基本権の制限の代償があることなどを理由に、公務員の労働基本権の制限を合憲としてい(判旨Ⅲ~Ⅴ)。
その後の判例は、公務員は、財政民主主義に表れている議会制民主主義の原則により、その勤務条件の決定に関し、国会または地方議会の直接、間接の判断を待たざるをえない特殊な地位に置かれているので「労使による勤務条件の共同決定を内容とするような団体交渉権ひいては争議権を憲法上当然には主張することのできない立場にある」と述べている(全逓名古屋中郵事件ー最大判昭和52年5月4日)。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法41条〔国会の地位・立法権〕
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
憲法83条〔財産処理の基本原則〕
第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
国公法98条2項
第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
○2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
国公法110条1項17号
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
地公法37条(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
行政執行法人の労働関係に関する法律17条(争議行為の禁止)
第十七条 職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
2 行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。
162 ピケッティング-御園ハイヤー事件
最2小判平成4年10月2日(平成元年(オ)676号)
要因
タクシー会社における、労働組合の争議行為としての車輛確保には正当性が認められるか。
事実
Yらは、A県下のタクシー労働者の個人加盟による単一組織であるB労働組合C地法本部の組合員(執行委員長、書記長ら)およびX会社の従業員で組織されたD分会の分会長等である。タクシー会社を営むX会社は、賃金引上げなどをめぐり、C地本と団体交渉をしてきたが、交渉が物別れに終わったため、C地本はストライキを実施することとした。その際、組合員は、乗務することとなっていたタクシー6台をX会社側が稼働させるのを阻止するため、タクシーの傍らに座り込んだり寝転んだりしてタクシーが格納された車庫を2日にわたり占拠した。そこで、X会社は、Yらに対して、Yらの行動はX会社が本件タクシーを搬出し稼働させることを不可能にして、違法にX会社の営業を妨害したものであるとして、不法行為に基づく損害賠償を求めて、訴えを提起した。1審はX会社の請求をほぼ認容したが、原審は、Yらの行動は正当な争議行為に該当するとして、X会社の請求を棄却した。そこで、X会社は上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し。
Ⅰ「ストライキは、必然的に企業の業務の正常な運営を阻害するものではあるが、その本質は、労働者が労働契約上負担する労務供給の不履行にあり、その手段方法は、労働者が団結してその持つ労働力を使用者に利用させないことにあるのであって、不法に使用者側の自由意思を抑圧しあるいはその財産に対する支配を阻止するような行為をすることは許されず、これをもって正当な争議行為を解することはできないこと、また、使用者は、ストライキの期間中であっても、業務の遂行を停止しなければならないものではなく、操業を継続するために必要とする対抗措置を採ることができること」は、判例の趣旨とするところである。
Ⅱ 以上の理は、「非組合員等により操業を継続してストライキの実効性を失わせるのが容易であると考えられるタクシー等の運行を業とする企業の場合にあっても基本的には異なるものではなく、労働者側が、ストライキの期間中、非組合員等による営業用自動車の運行を阻止するために、説得活動の範囲を超えて、当該自動車等を労働者側の排他的占有下に置いてしまうなどの行為をすることは許されず、右のような自動車運行阻止の行為を正当な争議行為とすることはできないといわなければならない」。
Ⅲ」「これを本件についてみるに、・・・・Yらは、互いに意思を通じて、X会社の管理に係る本件タクシーをB組合の排他的占有下に置き、X会社がこれを搬出して稼働させるのを実力で阻止したものといわなければならない。・・・・Yらの右自動車運行阻止の行為は、・・・・争議行為として正当な範囲にとどまるということはできず、違法の評価を免れないというべきである」。
解説
労働組合の団体行動は、正当な場合には、刑事免責と民事免責が認められ、さらに使用者の不利益扱いからの保護も認められる(それぞれ、労組法1条2項、8条、7条)。団体行動には、争議行為と組合活動があり、両者には、正当性の判断基準に違いがある。
争議行為の概念については、事業の正常な運営を阻害する行為(労組法7条を参照)とする見解が多数説であるが、異論もある。いずれの立場でも、ストライキ、怠業、ピケッティング、ボイコットが争議行為に含まれることには異論はない。
ピケッティングの正当性に関しえては、すでに判旨Ⅰの前半部分の枠組みに基づき、厳格に判断をする先例があった(朝日新聞小倉支店事件ー最大判昭和27年10月22日。国労久留米駅事件ー最大判昭和48年4月25日も参照)。本判決も、ピケッティングと類似の機能をもつ争議占術に対して、ピケッティングと同様の判断枠組みを採用している。
学説上は、刑事責任に関する判例を含めて(札幌炭鉱事件ー最大判昭和33年5月28日等)、判例の平和的説得論(ピケッティングの正当性の範囲を平和的説得の範囲までしか認めないこと)に対しては批判的なものが多く、むしろ、団結の示唆の行使までは、正当と認めるべきとする見解が有力である。
判旨Ⅰの後半部分は、争議行為においても、使用者には、操業継続の自由があるとする判例(→【175】山陽電気軌道事件)を踏襲している。ストライキの実効性を確保するためには、使用者の操業継続を阻止する争議戦術が効果的であるとしても、正当性の判断枠組みが緩和されるわけではないということである(判旨Ⅱ)。ここでも、積極的な態様争議行為に対して否定的な判例のスタンス(判旨Ⅰ)が現れている。
労組法1条2項 (目的)
第1条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
労組法8条(損害賠償)
第8条 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
労組法7条 (不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
163 政治スト-三菱重工長崎造船所事件
最2小判平成4年9月25日(平成4年(オ)1310号)
要因
原子力船入港に反対する目的で行われたストライキに正当性が認められるか。
事実
Xら、3名は、Y会社の従業員であり、A労働組合のY会社支部のB分会の幹部であった。B分会は、昭和53年10月16日、原子力船むつの佐世保港への入港と、それをめぐる政府、長崎県、佐世保市の方針決定や施策等に抗議する目的をもって、同日午後4時30分からストライキの名の下にその所属組合員たるY会社の社員(241名)を職場離脱させた。Xらは、闘争委員長および副闘争委員長として、この政治ストを指揮あるいはこれを補佐し、あわせてX1とX2は自らも職場離脱した。Y会社は、Xらを出勤停止の懲戒処分にした。そこで、Xらは、この処分の無効確認を求めて訴えを提起した。
1審は、この処分を有効としてXらの請求を棄却した。原審(福岡高判平成4年3月31日)も、「本件ストライキが『むつ』入港及びそれをめぐる政府・長崎県・佐世保市の方針決定並びに施策等に抗議する目的であったことは争いがないところ、もともと右のような事項は、Xらの労働条件とは直接関係しない事項であり、X会社に対し、これを対象に団体交渉を求めることはできない」として、1審の判断を維持した。そこで、Xらは上告した。
判旨 上告棄却(Xらの請求棄却)。
「使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治的目的のために争議行為を行うことは、憲法28条の保障とは無関係なものと解すべきことは、当該裁判所の判例・・・・とするところであり、これと同旨の原審の判断は正当と是認することができ、原判決に所論の違憲はない」。
解説
政治ストとは、国または地方公共団体等の公的団体を名宛人とする要求や抗議のために行われるストライキである。労ぢ関係の当事者である使用者にとっては、労働組合との団体交渉によって解決できない事項をめぐるストライキであるので、こうしたストライキに正当性が認められるかについては議論もある。
学説上は、
①政治ストは、使用者に処理できない政治的要求を掲げるものなので、正当性はないものとする(否定説)。
②政治的要求を掲げているかどうかは、正当性に影響しないものとする(肯定説)。
③労働者の経済的利益に直接かかわる経済的政治ストと純粋政治ストを区別し、前者のみ憲法28条による保障の範囲内であるとして正当性を認めるもの(二分説。純粋政治ストは憲法21条の表現の自由によって保障されるにとどまる)、とに分かれている。
本判決は、「使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的のために争議行為を行うことは、憲法28条の保障とは無関係なものと解すべき」として正当性を否定している。この判決が引用する判例では、「とくに勤労者なるがゆえに、本来経済的地位の向上のための手段として認められた争議行為をその政治的主張貫徹のための手段として使用しうる特権をもつものとはいえないから、かかる争議行為が表現の自由として特別に保障されることは、本来、ありえないというべきである」(→【161】全農林警職法事件)と述べており、この判旨、政治ストは、憲法28条のみならず、21条によっても保障されない趣旨と解することができる。その意味で、判例は、①の否定説の立場に立っているとみられる。
なお、使用者にとって、労働組合との団体交渉によって解決できない事項をめぐるストライキであるという点では、同情ストの正当性についても、政治ストと同じような議論があてはまる。同情ストとは、主として他社の労働者の争議を支援する目的で行われるストライキを指す。政治ストについて、団体交渉による解決可能性のないことを重視して正当性を否定する学説は、同じ理由で同情ストについても否定説を支持する。
もっとも、学説のなかには、支援対象となる争議で争われている労働条件が、同情ストに参加する労働者の労働条件あるいは経済的利益と実質的な関連性があれば正当性を認めるべきとして、同情ストの正当性を原則的に肯定する立場もある。
裁判例のなかには、同情ストの正当性を否定したものもある(杵島炭礦事件ー東京地判昭和50年10月21日)が、この判決の事案は、企業別組合の産業別連合体が、傘下の労働組合の要求実現のために他の傘下組合に統一的にストライキを実施させたケースであり、これを同情ストとみて正当性を否定することについては、学説の否定説の立場からも批判がある。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法21条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
164 抜打スト-国鉄千葉動労事件
東京高判平成13年9月11日(平成12年(ネ)4078号)
要因
使用者のスト対抗措置に抗議するために前倒しで行われたストライキに正当性は認められるか。
事実
Xは、旅客鉄道事業等を営む株式会社であり、Yは、X会社のA支社管内における動力車に関係する業務に従事する従業員などで構成される労働組合である。Y組合は、かねてからの諸懸案要求事項に対するX会社の対応が不誠実であるとして、X会社から誠意ある対応がない限り、平成2年3月19日からストライキを実施することを決定し、同月16日に、19日午前0時以降48時間ないし72時間、ストライキを行う旨の通知を行った(労調法37条に基づく通知は、すでに行っている)。
同月18日、X会社側が、Y組合の組合員らに対してA運転区への入構や庁舎への立入り制限をしたり、組合事務所前にフェンスを設置したりしたため、Y組合はこれに抗議した。しかし、解決しなかったので、Y組合は、同日午前11時55分ころ、X会社側に対し、正午以降全乗務員を対象としたストライキを実施することを口頭で正式に通告し、これを実行した。
X会社は、本件前倒しストライキによって、対策要員経費や代替輸送費などの損害が生じたとして、Y組合に対して損害賠償を求めるために訴えを提起した。1審は、X会社の行った入構制限等は、不当労働行為とはいえず、Y組合の前倒しストライキは正当性を欠くとして、X会社の請求を認めた(一部認容)。そこで、Y組合は控訴した。
判旨 原判決を変更(X会社の過失を認め、過失相殺により損害額を減額)
Ⅰ「使用者は、」ストライキの期間中であっても、業務の遂行を停止しなければならないのではなく、操業を継続するために必要な対抗措置を採ることができると解するのが相当である」。
Ⅱ「労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動に当たらないと解される」。
「争議行為時ないし、その準備行為時であることから、当然に、使用者の所有し管理する物的施設に対する権限が制限されると解すべき根拠はなく、同行為時であることが上記特段の事情の存否を判断するに当たり一事情として考慮されることがあるとしても、上記一般論自体が修正されるべきものということはできない」。
Ⅲ 本件におけるX会社の措置は、「本件スト時における操業継続を図るために必要かつ相当な対抗措置であったということができ、施設管理権を濫用したというような特段の事情があるということもできないというべきである」。Y組合のストライキの前倒し実施は、「X会社の正当な施設管理権の行使に抗議し、これに対抗するために行われたみるべきである。したがって、本件前倒し実施の目的には、自らの事前の争議通告に反してストライキを行うことを正当化するに十分な緊急性・重要性が存しないというべきである」。
解説
争議行為については、労調法8条で定める公共事業に関しては、当事者は、少なくとも10日前までに労働委員会および厚生労働大臣または都道府県知事にその旨を通知しなかればならない(37条)。その他の場合には、争議行為の予告は、対使用者との関係でも、労働組合の義務とはされていない(労働協約上、特に予告義務が定めされている場合は、別である。)そのため、予告をしないで行う抜打ストは、当然に正当性が否定されるとは解されていない。ただし、抜打ストによって、使用者の事業に多大な混乱をもたらしたような場合には、正当性が否定される可能性はある。
本件は、すでに争議行為の予告通知をしていた労働組合に対して、使用者が争議対抗措置をとったことに抗議をするために、予告していた時よりも半日早く争議行為をしたという事案である。この点について、本判決は、使用者は争議行為中であっても操業継続のための対抗措置をとることができるとする判例(→【162】御園ハイヤー事件)や施設管理権と組合活動に関する判例(→【171】国鉄札幌運転区事件)を参照しながら(判旨Ⅰ、Ⅱ)、本件のX会社の対抗措置は正当であるので、それに抗議するための前倒しストには、それを「正当化するに十分な緊急性・重要性が存しない」と判断した(判旨Ⅲ)。
なお、本件ストには抗議ストとしての側面もある。抗議ストとは、労働組合のほうから積極的に要求を出すのではなく、使用者の態度に対する講義のために行われるものであるが、抗議ストの正当性については裁判例上争いがあるが、雇用や労働条件に関する具体的な要求を含んでいると判断できる場合には、正当性を認めるべきであろう。本件では、抗議ストとしての正当性が否定されたわけではなく、前倒し実施の点で、正当性が認められないという判断がなされたものである。
労調法37条〔公益事業の争議行為の予告〕
第37条 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
② 緊急調整の決定があつた公益事業に関する事件については、前項の規定による通知は、第三十八条に規定する期間を経過した後でなければこれをすることができない。
労調法8条〔公益事業及びその追加指定〕
第8条 この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
一 運輸事業
二 郵便、信書便又は電気通信の事業
三 水道、電気又はガスの供給の事業
四 医療又は公衆衛生の事業
② 内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。
③ 内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。
165 指名スト-新興サービス事件
東京地判昭和62年5月26日(昭和60年(モ)1596号)
要因
配転命令拒否の指名ストに正当性は認められるか。
事実
X1~X3は、Y会社の従業員であり、A労働者の組合員である。Y会社は、昭和59年10月24日は不正労働行為であり、労働協約上の事前協議義務に反するを主張して、その撤回を求めて団体交渉を行う一方で、10月25日以降、Xらに対して、配転命令による新任地への赴任を拒否する指名ストに入るよう指令した。その後も、団体交渉が継続されたが決裂したため、Y会社は、Xら5名を配転命令に従わないことを理由に懲戒解雇した(本件懲戒解雇)。そこで、Xらは、この懲戒解雇は、正当な争議行為を理由とする不利益扱いであり、無効であるとして、地位保全、賃金未払の仮処分の申請をした。原審は、この申請を認容したので、Y会社は異議申立てをした。
判旨 仮処分決定認可。
Ⅰ「組合が使用者の従業員に対する配転命令を不当として争議行為を実施するに際し、争議手段として配転対象者の労務不提供という手段を選択し、当該従業員がこの指令に従い配転命令を拒否して新勤務に従事しないという争議行為は、労務不提供にとどまる限り、正当性を有するものと解すべきである」。
Ⅱ「本件ストライキ権の行使は、組合は本件配転命令を不当労働行為であると考えて、その撤回を要求する組合の指令に基づいて実施されるものであるから、その目的においても本件配転命令自体を拒否しては移転先の勤務に従事しないという労務の不提供にとどまるものであるから、正当というべきである」。
Ⅲ「本件懲戒解雇は、申請人らが正当な争議行為をしたことを理由としてなされたものであるから、労働組合法7条1号に該当した不当労働行為として、無効というべきである」。
解説
特定の組合員を指定してストライキを行わせることを、指名ストという。指名ストには、本件のように、配転命令を受けた組合員が、それを拒否するまめにストライキに入るというケースもある。こうした配転拒否のための指名ストについては、一定の要求事項のための手段としてストライキを行うものではなく、ストライキによって、その要求事項を直接実現してしまうものなので、正当性は認められないという考え方もある。
本判決は、本件の指名ストについて、まず、目的面において、「本件配転命令を不当労働行為に基づいて実施されたもの」で、正当と判断している(判旨Ⅱ)。また、手段面においても、「本件配転命令自体を拒否して配転先の勤務に従事しないという労務の不提供にとどまるっもの」であり、正当と判断している(判旨Ⅰ、Ⅱ)。
本件では、前者の目的面については、労働組合が配転命令の撤回を求めて団体交渉を求めており、その交渉過程において、圧力手段として指名ストという争議行為を利用したという事情が、正当性判断において重視されたと解すべきであろう。このような団体交渉をしないまま、いきなり配転拒否の指名ストに入る場合には、単なる配転命令拒否と異ならず、正当性を失うと解すべきである(単なる配転命令拒否であると、配転命令が有効であれば、懲戒解雇は通常は有効とされるであろう)。
なお、指名スト事案の先例となる裁判例として、青森銀行事件(青森地判昭和45年4月9日)がある。同判決は、「赴任拒否は闘争は、単に新任店に赴任しないという限度では、消極的に使用者に対し、労働力の提供を拒否する点で、ストライキ的争議手段と解しうるが、さらに進んで使用者の就労拒否命令を排除して旧任店で強制的に就労を続行することは、使用者の人事権を無視し、その人事権能の一部を労組において行使せんとするものであるから、たとえ、争議行為が多かれ少なかれ使用者の労務指揮権を排除する性質を帯びているものであるとしても、かような争議行為は前記目的との関連を考慮し、その闘争期間が極めて短期間であるとの特段の事情が存在しないかぎりは、違法性を帯びるものといわなければならない」と述べている。すなわち、赴任の拒否にとどまらず、旧任地での就労を強行するという態様となると、その争議行為は原則として正当性を欠くということである。
労働組合法7条1号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
166 争議行為と賃金-水道機工事件
最1小判昭和60年3月7日(昭和56年(オ)39号)
要因
出張・外勤拒否闘争として、使用者の業務命令に反して内勤業務に従事した労働者に対し、賃金カットを行うことは認められるか。
事実
Xらは、Y会社の従業員であり、A労働組合に所属している。Y会社は、昭和48年2月5日から、同14日までの間、Xらに対し、出張・外勤を命じる業務命令を発した。ところが、A組合は、同年1月30日、Y会社に対し、同年2月1日以降、外勤・出張拒否闘争および電話応対拒否闘争に入る旨を通知していた。そして、Xらは、この通知に基づく争議行為として、出張・外勤を行わず、Y会社に出勤し、内勤業務に従事した。Y会社においては、出張・外勤の必要が生じた場合、従業員が自己の担当業務の状況を考慮し、注文主を打ち合わせのうえ、上司から出張・外勤を命じられた場合にも、出張日程等については上司と協議のうえこれを決定するなど、従業員の意見が相当に尊重されていたが、このような取扱いは、Y会社が業務命令を発する手続を円滑にするため事実上許容されていたにすぎなかった。
Y会社は、外勤・出張拒否闘争に従事したXらの賃金を全額カットしたため、Xらはその賃金分の支払いを求めて、訴えを提起した。1審および原審ともに、Xらの請求を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xらの請求棄却)。
「原審は、・・・・本件業務命令は、組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、Xらが、本件業務命令によって、指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、また、Y会社は、本件業務命令を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、Xらが提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、したがって、Y会社は、Xらに対して右の時間に対する賃金の支払義務を負うものではないと判断している。原審の右判断は、・・・・正当として是認することが出来、原判決に所論の違法はない」。
解説
争議行為の際には、労働者は労務を提供していないので、使用者には賃金の支払義務はない。ここでは、労働契約における解釈準則としてのノーワーク・ノーペイの原則があてはまる。
本判決は、使用者が出張・外勤勤務を命じられたにもかかわらず、組合員が争議行為として内勤業務に従事したという事案において、組合員は「債務の本旨に従った労務の提供」をしたことにはならず、使用者が、内勤業務の労務提供を受領したとは認められない以上、使用者は賃金の支払義務を負わないと判断した。本件のようなケースでは、使用者の指示した出張・外勤業務に関する労務不提供という点では、ストライキを行っているのと同じである。内勤業務での労務提供は、使用者が指示したものではないので、たとえ争議行為として行ったとしても、賃金請求権が認められるものではない。
使用者の業務命令に従わない労務提供を争議行為として行う例としては、怠業もある。怠業は、労務提供義務の一部不履行であり、不履行の程度に応じて賃金のカットが認められていると解されている(怠業は争議行為として行われる以上、全体として、債務の本旨に従った労務の提供がないので、賃金金額をカットすべきという見解もある)。裁判例の中にも、怠業に従事している労働者の賃金について、その不完全履行の割合が特定できないかぎり、その部分を除いた賃金請求権しか生じない。
と述べるものがある(西区タクシー事件ー横浜地判昭和40年11月15日)。これは「応量カット」と呼ばれる。
なお、本件のようなケースや怠業の場合でも、事実上は、不完全とはいえ労務を提供しているのであり、それにより使用者に利益が生じている場合には、労働者に不当利得返還請求権が認められる可能性はある(民法703条、704条)。
このほか、勤務時間中の組合活動(たとえば、勤務時間中に労働組合の要求を掲げたリボンをつけて労務に従事する場合)についても、使用者からの指揮命令に従わずに労務を提供するという点では、やはり、怠業と同様に、賃金の請求ができるかが問題となりうる。まず、組合員に対してリボンを着用した就労を禁止すること(使用者が労務の受領を拒否すること)は、そのような就労が業務に支障があると判断される場合には適法と解されるし、その結果、組合員が労務の提供ができなくなったとしても、使用者には帰責事由はなく、賃金支払義務はないと解すべきである(民法536条2項)。他方、いったん労務に従事させた後については、理論的には応量カットはできるであろうが、現実には、不完全履行の割合を特定するのは容易ではないと思われる。ただ、使用者としては、賃金面では対処できないとしても、服務規律に違反することを理由に懲戒処分を課すことができる場合はあろう(こうした組合活動び正当性につては、→【170】大成観光事件)。
民法703条(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法704条(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法536条2項(債務者の危険負担等)
第536条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
167 賃金カットの範囲-三菱重工長崎造船所事件
最2小判昭和56年9月18日(昭和51年(オ)1273号)(民集35巻6号1028頁)
要因
争議行為の場合に家族手当をカットすることは許されるか。
事実
Xらは、Y会社のA造船所に勤務する従業員であり、B労働組合に所属している。B組合は、昭和47年7月および8月の両日にわたってストライキを行い、Y会社は、Xらに対して、各ストライキ期間に応じた家族手当を支払わなかった。この家族手当は、Y会社の就業規則の一部である社員賃金規則により、扶養家族数に応じて、毎月支給されていたものである。
A造船所においては、昭和23年ころから、同44年10月まで、就業規則の一部である社員賃金規則中に、ストライキ期間中、その期間に応じて家族手当を含む時間割賃金を削減する旨の規定を置き、この規定に基づいてストライキ期間に応じた家族手当の削減をしてきた。そして、Y会社は、昭和44年11月1日賃金規則から家族手当削減の規定を削除し、そのころ作成した社員賃金細目取扱のなかに同様の規定を設けた。
その際には、Y会社従業員の過半数で組織されたC労働組合の意見を徴していた。Y会社は、この改正後も昭和49年に家族手当が廃止され、有扶手当が新設されるまで、従来どおり、ストライキの場合の家族手当の削減を継続してきた。
B組合は、昭和47年8月、Y会社に対し、家族手当削減分の返済を求めたが、Y会社はこれに応じなかった。そこで、Xらは、家族手当の支払を求めて訴えを提起した。1審および原審ともにXらの請求を認容した。そこで、Y会社は上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xらの請求棄却)。
Ⅰ Y会社のA造船所においては、ストライキの場合における家族手当の削減が昭和23年ことから昭和44年10月までは就業規則(賃金規則)の規定に基づいて実施されており、その後も、細部取扱いのうちに定められ、同様の取扱いが引き続き異議なく行われてきたというのであるから、ストライキの場合における家族手当の削減は、Y会社とXらの所属するB組合との間の労働慣行となっていたものと推認することができる。
Ⅱ「ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのを相当とし、Y会社のA造船所においては、昭和44年11月以降も本件家族手当の削減が労働慣行として成立していると判断できることは前述したとおりであるから、いわゆる抽象的一般的賃金二分論を前提とするXらの主張は、その前提を欠き、失当である」。
Ⅲ 労基法37条5項が「家族手当を割増賃金算定の基礎から除外すべきものと定めたのは、家族手当が労働者の個人的事情に基づいて支給される性格の賃金であって、これを割増賃金の基礎となる賃金に算入させることを原則とすることがかえって不適切な結果を生ずるおそれのあることを配慮したものであり、労働との直接の結びつきが薄いからといって、その故にストライキの場合における家族手当の削除を直ちに違法とする趣旨までを含むものではなく、また、同法24条所定の賃金全額払の原則は、ストライキに伴う賃金削減の当否の判断とは何ら関係がない」。
解説
争議行為の場合の賃金の控除は、労働契約の解釈問題であり、(→【166】水動機工事件[解説])、したがって、控除の範囲につても、労働契約の解釈についても、労働契約の解釈に委ねられていることになる。もっとも、この点については、賃金には日々の労働の提供に対応して交換的に支払われる部分(交換的部分の賃金)と生活保障的に従業員の地位にたいして支払われる部分(生活保障的部分の賃金)の2つに分けられ、ストライキによって控除しうるのは前者の交換的部分に限られるという考え方もある(賃金二分説)。これは、最高裁によっても支持されたことがあった(明治生命事件ー最2小判昭和40年2月5日)。ただし、この最高裁判決も、「労働協約等に別段の定め」がある場合には、その定めを優先するという考え方を示していた。
本判決は、ストライキの際に家族手当を控除するということが労使慣行となっていると認定されており(判旨Ⅰ)、こういう場合には、賃金二分説は妥当しないとされている(判旨Ⅱ)。これは、先の判例に照らすと「労働協約等」には、「労使慣行」も含まれるということであろう。いずれにせよ、賃金二分説は強行的なルールではないということである。
なお、本件では、B組合は、労基法37条5項が家族手当を割増賃金の算定基礎から除外しているのは、これが労働時間に対応した賃金ではないことを認めているからであり、このような賃金の生活保障的部分は、ストライキなどにより、不就業となった場合には、控除できない趣旨だと主張していた。しかし、本判決は、同項の趣旨は、家族手当のような労働者の個人的事情に基づいて支給される性格をもつものが、割増賃金の算定基礎に含まれるのは適切でないということであって、ストライキの場合の家族手当の削減を直ちに違法とする趣旨までを含むものではないとした(判旨Ⅲ)。
労基法37条5項 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
労基法24条(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
168 争議不参加者の賃金請求-ノース・ウエスト航空事件
最2小判昭和62年7月17日(昭和57年(オ)1189号・1190号)(民集41巻5号1283頁・1350頁)
要因
部分ストの場合の争議行為不参加者に賃金請求権は認められるか。
事実
Xらは、民間定期航空運輸事業を営むY会社の従業員で、A労働組合に所属し、沖縄営業所または大阪営業所に勤務していた。Y会社は羽田地区でグランドホステス業務や搭載業務に他社の労働者を従事させていたが、A組合は、これは職安法44条に違反するとして中止を求めた。Y会社は、改善案を発表したが、A組合は、それでは不十分であるとして改善案の実行を阻止するため、東京地区の組合員でストライキを決行し、業務用機材の占拠をした。このストライキの結果、東京―沖縄便、東京―大阪便は大幅に減便となった。そのため、Y会社は、Xらに対して、就労が不要になったとして休業を命じた。そこで、Xらは、主位的に休業期間中の賃金の支払い、予備的に休業手当の支払を求めて訴えを提起した。1審は、請求を全部棄却したが、原審は休業手当の請求のみ認容した。そこで、XらとY会社がともに上告した。
判旨(1)Xら上告事件(賃金請求関係(昭和57年(オ)1190号))、上告棄却(Xらの請求棄却)。
Ⅰ「企業ないし事業場の労働者の一部によるストライキのが原因で、ストライキに参加しなかった労働者が労働をすることが社会通念上不能又は無価値となり、その労働義務を履行することができなくなった場合、不参加労働者が賃金請求権を有するか
否かについては、当該労働者が就労の意思を有する以上、その個別の労働契約上の危険負担の問題として考察すべきである。このことは、当該労働者がストライキを行った組合に所属していて、組合意思の形成に関与し、ストライキを行った組合に所属していて、組合意思の形成に関与し、ストライキを容認しているとしても、異なるところはない。
Ⅱ「ストライキは労働者に保障された争議権の行使であって、使用者がこれに介入して制御することはできず、また、団体交渉において組合側がいかなる回答を与え、どの程度譲歩するかは、使用者の自由であるから、団体交渉の決裂の結果、ストライキに突入しても、そのことは、一般に使用者に帰責させるべきものということはできない」。
Ⅲ したがって、労働者の一部によるストライキが原因で、ストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となった場合は、使用者が不当労働行為の意思その他不当な目的をもってことさらストライキを行わしめたなどの特別の事情がない限り、民法536条の「債務者の責めに帰すべき事由」にはあたらない。
(2)Y会社上告事件(休業手当請求関係(昭和57年(オ)1189号)、原判決破棄、自判(Xらの請求棄却)。
Ⅳ 労基法26条は、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に、使用者の負担において労働者の生活をその規定する限度で保障しおうとする趣旨によるものであって、同条項が民法536条2項の適用を排除するものではなく、休業手当請求権と賃金請求権とは競合しうるものである。
Ⅴ 休業手当の制度は、賃金の全額を保障するものではなく、しかも、その支払義務の有無を使用者の帰責事由の存否にかからしめていりことからみて、労働契約の一方当事者たる使用者の立場をも考慮すべきである。そうすると、労基法26条の解釈適用にあたっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の生活保障のために使用者に負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とする。このようにみると、「使用者の責めに帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点も踏まえた概念というべきであって、民法536条の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。
解説
本件では、自らの所属する労働組合の一部の組合員の行ったストライキ(部分スト)の影響により、そのストライキに参加しなかった労働者の終了が、社会通念上不能または無価値となった場合の賃金請求権の存否が争点となっいぇいる。本判決は、これは危険負担の問題であり(民法536条2項)、使用者の帰責事由の存否によって決まるとする(判旨Ⅰ)。そして、団体交渉の決裂は、原則として、使用者の帰責事由ではない(判旨Ⅱ)が、例外として、「使用者が不当労働行為の意思その他不当な目的をもってことさらストライキを行わしめたなどの特別の事情」があれば、帰責事由は認められる、とする(判旨Ⅲ。本件では、このような「特別の事情」は否定された)。
賃金請求が認められない場合でも、労基法26条の休業手当は認められる可能性がある(判旨Ⅳは、両請求権は競合可能とする)。休業手当の要件にも、使用者の帰責事由があるが、これは民法536条2項の帰責事由よりも広く、「使用者側に起因する経営、管理上の障害」を含むと解されている(判旨Ⅴ。ただし、本件では労基法26条の帰責事由も否定された)。
なお、従業員の一部を組織する労働組合の行ったストライキ(一部スト)により、非組合員が就労できなくなった場合については議論があるが、少なくとも休業手当の請求は認められるべき場合があるだろう。
職安法44条(労働者供給事業の禁止)
第44条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
労基法26条 (休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
民法536条2項(債務者の危険負担等)
第536条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
169 違法争議行為と損害賠償責任-書泉事件
東京地判平成4年5月6日(昭和54年(ワ)5308号)
要因
違法な争議行為に対して労働組合と組合員はともに損害賠償責任を負うか。
事実
Xは、書籍、雑誌の販売を業とする会社で、従業員数は100名余りである。Y1は、X会社の正社員とパートタイム労働者で結成された労働組合であり、組合員数は30名弱であった。Y2~Y5はY1組合の組合員であり、Y6~Y8は、Y1組合を支援していた者である。昭和53年、Y1組合は、賃上げ等の春闘要求の実現を目指して、同年4月から翌54年4月にかけてストライキを実施した。特に、昭和53年11月22日以降は、無期限の全日ストライキに突入した。ストライキはピケッティングをともなうものがあったが、その態様は、X会社のA店舗、B店舗の出入口ドア、ショウウインドウおよび外部に面したガラスにステッカーやビラを多数貼付し、あるいは、Y1組合名やソローガンの入った横断幕を張り、店の出入口の前にY1組合員や支援労働者が各数名ずつ腕章、ゼッケン、鉢巻きを着用するなどして佇立や座り込みをし、あるいはハンドマイク等を使用して顧客にストライキ中なので、入店購入をしないように呼びかけて気勢をあげ、これに応じないで入店を試みた顧客に対しては罵声を浴びせて入店を阻止し、強引に入店した顧客については組合員ら数名が取り囲んだうえ押し戻して書籍購入を断念させるというものであった。
X会社は、この本件争議行為のため、売上が激減し、会社側の危機感を抱いたため、争議の解決と操業継続のために、臨時従業員50名を雇い入れ、その後、Y1組合員を排除して営業を再開した(なお、その過程で、臨時従業員の行動には行き過ぎもあり、Y1組合からX会社への損害賠償請求訴訟が起こされY1組合勝訴の判決が確定している)。
X会社は、本件争議行動は違法であるとして、Yらに対して、昭和53年11月から同54年2月までの間に被った損害9771万1000円の賠償を求めて、訴えを提起した。
判旨 請求認容。
Ⅰ 本件争議行為は、Y1組合が、書籍販売を阻止してX会社に損害を与えることにより、交渉を有利に進めようとの意図のもとに、店内に入ろうとする顧客を対象として、行われたものであるところ、その態様は、顧客に対する不買の呼びかけやビラの配布にとどまらず、およそ顧客は自由に出入りして購入したい本を探せるような雰囲気ではない状況を作り出したうえ、Y1組合員らの説得に応じずあえて店内に入ろうとする顧客に対しては、罵声を浴びせたり取り囲んで押し戻すなど実力をもって入店を阻止するというものであり、これらの事情を総合すると、本件争議行為は平和的説得の範囲を超えたものであって違法であるといわざるをえない。
Ⅱ Y2らは、いずれもY1組合役員として、違法な本件争議行為の実施を決定し、他の組合員と共同してこれを実行した者であるから、X会社に対し、共同不法行為(民法709条1項)に基づき本件争議行為によりX会社が被った損害を賠償すべき責任がある。そして、本件争議行為当時、Y2ら4名はいずれもY1組合の役員であったから、権利能力なき社団であるY1組合は、民法44条1項(現行の一般社団・財団法人法78条)
の類推適用により、本件争議行為実施についての不法行為責任を負う。
Ⅲ「争議行為が集団的団体行動の性質を有していることは事実であるとしても、そのことが直ちに個々の組合員の行為が法的評価の対象外になるとの結論には、結びつかず、むしろY1組合員の行動は、一面社団であるY1組合の行為であると同時に、組合員個人の行為である側面を有すると解されるから、組合員個人についても前記のとおり、不法行為責任が成立するものというべきである。
支援労働者であるY6らも、本件争議行為の実施につき、助言、指導を与えていたことを推認することができ、しかも争議行為にも一部参加していたということができるから、本件争議行為実施について、共同不法行為者(民法719条)としての責任を負うべきである。
解説
1 争議行為が正当性を欠く場合には、民事免責は認められないので、労働組合および組合員は、不法行為(民法709条)や債務不履行(同415条)を理由に損害賠償責任を負うことになる。もっとも、学説には、争議行為の「二面集団的本質」論を説いて、個人責任を否定する見解も少なくない。すなわち、争議行為は労働組合という団体の行為であると同時に、個々の労働者の集団的行為としてのみ実現されるという二面的に集団的な性格をもち、個々の組合員の行為は労働組合という団体の争議行為の構成部分にすぎないので、団体だけが責任主体となるとするのである。しかし、本判決は、そうした考え方を明確に否定しており(判旨Ⅲ)、結論として、労働組合と組合員の共同不法行為の成立を認めている(判旨Ⅱ)。
なお、学説のなかには、労働組合の正規な決定による場合には、団体責任が第一次的で、個人責任は、附従的なものとすべきとする有力説もある。
2 違法な争議行為がなされた場合の懲戒処分については、組合幹部であるが故に当然に重い責任を負うという解釈は妥当ではない(七十七銀行事件ー仙台地判昭和45年5月29日も参照)が、その責任や役割の大きさから重い責任を負うことはあるだろう(ミツミ電機事件―東京高判昭和63年3月31日を参照)。
民法719条1項(共同不法行為者の責任)
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇(ほう)助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
旧民法44条1項→現在の
一般社団・財団法人法78条(代表者の行為についての損害賠償責任)
第78条一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法415条(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
170 就業期間中の組合活動-態勢観光事件
最3小判昭和57年4月13日(昭和52年(行ツ)122号)(民集36巻4号659頁)
要因
リボン闘争の正当性は認められるか。
事実
Xは、ホテル業を営む会社である。X会社の従業員で結成されたA労働組合は、昭和45年9月、賃上げを要求してX会社と団体交渉をしたが、要求が受け入れられなかったので、同年10月6日午前9時から、同月8日午前7時までの間および同月28日午前7時から同月30日午後12時までの間の2回にわたり、X会社の経営するホテルB内において、就業時間中にもかかわらず組合員たる従業員の一部が各自「要求貫徹」または、これに添えて「C労連」と記入した本件リボンを着用するというリボン闘争を実施した。X会社は、このリボンを取り外すように警告したが、A組合はこれに応じなかった。リボン闘争は、主として、結成後、3か月のA組合の内部における組合員間の連帯感ないし、仲間意識の昂揚、団体強化への士気の鼓舞という効果を重視してじっしされたものであった。
X会社は、リボン闘争を指令した組合三役であるDら6名を減給ないし、譴責処分にした。
そこで、A組合とDらは、この処分は、不利益取扱いの不当労働行為にあたるとして、Y労働委員会に救済を申し立てた。Yは、救済命令を発したところ、X会社は、その取消しを求めて訴えを提起した。
1審は、不当労働行為の成立を否定して、X会社の請求を認容した。1審では、リボン闘争の違法性を、「一般違法性」と「特別違法性」については、リボン闘争の組合活動としての側面では、勤務時間中は、労働者が使用者の業務上の指揮命令に服して労務の給付ないし労働をしなければならない状況にあるのであり、「勤務時間の場で、労働者がリボン闘争による組合活動に従事することは、人の褌で相撲を取る類の便乗行為であるというべく、経済的公正を欠く」し、誠意に労務に服すべき労働者の義務に違背すると述べ、さらに争議行為としての側面でも違法であるとした。また「特別違法性」については、「ホテル業におけるいわゆるリボン闘争は、その業務の正常な運営を阻害する意味合いに深甚なものがある」として、労働組合の正当な行為たりえないとした(東京地判昭和50年3月11日)。原審も、1審の判断をほぼ維持してYからの控訴を棄却した(東京高判昭和52年8月9日)ので、Yは上告した。
判旨 上告棄却(X会社の請求認容)。
「本件リボン闘争は就業時間中に行われた組合活動であって、A組合の正当な行為にあたらないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる」。
解説
終業時間中に組合員が、組合の要求を事項などを記載したリボンを着用して勤務するリボン闘争の正当性については、職務専念義務に反するかという観点から議論がされてきた(また、これが争議行為に該当するかも争われてきた)。下級審では、当初は、リボン闘争を正当とするものがあったが、のちに正当性を否定するものが主流となっていった。正当性を否定する裁判例では、リボン闘争は、その具体的な実害の発生の有無にかかわらず、職務専念義務に違反するという判断が基礎になっていた。本件の1審判決はも、リボン闘争は誠実労働義務に違反するとして、厳格な職務専念義務論(抽象的危険説)に立脚しており、本判決も、この考え方を支持したものといえる(ただし、1審判決は、本件では、「特別違法性」として、業務の阻害が甚大であったという点にも言及しており、実害の発生を考慮している点には、注意を要する)。
すでに、最高裁は、政治的な要求を記載したプレートを着用して勤務した旧電電公社の職員の事案で、厳格な職務専念義務論に立って、その職員に対する懲戒処分の有効性を認めており、(→【25】電電公社目黒電報電話局事件)、その後の判例の多くも、厳格な専務専念義務論を踏襲している(裁判例の中には、勤務時間中の職場離脱の事案で、団結権確保のために必要不可欠で、組合活動に至った原因が専ら使用者にあり、業務に具体的な支障がないときは、組合活動としての正当性が認められるとした裁判例もある(オリエンタルモーター事件ー東京高判昭和63年6月23日)。
なお、本判決には伊藤正巳裁判官による補足意見が付されている。伊藤裁判官は、電電公社目黒電報電話局事件は、
①プレート着用が組合の活動ではなかったこと、
②プレートに記載された文言が政治的な内容のものであって、その着用が政治活動にあたること、
③それが、法律によって職務専念義務の規定されている公共部門の職場における活動であったこと
を指摘して、本件とは事案を異にすると述べた。そして、「職務専念義務といわれるものも、労働者が労働契約に基づきその職務を誠実に履行しなければならないという義務であって、この義務を何ら支障なく両立し、使用者の業務を具体的に阻害することのないと解する。そして、職務専念義務に違背する行動にあたるかどうかは、使用者の業務や労働者の職務の性質・内容、当該行動の態様など諸般の事情を勘案して判断されることになる」という、いわば、緩和された職務専念義務(具体的危険説)を展開した。
学説の多くは、伊藤裁判官の述べるような緩和された職務専念義務論を支持している。ただし、同裁判官も、本件においては、ホテルBに実害が生じていたとして、結論として、組合活動の正当性を否定している。
171 企業施設を利用した組合活動(1)-国鉄札幌運転区事件
最3小判昭和54年10月30日(昭和49年(オ)1188号)(民集33巻6号647頁)
要因
企業施設内における無許可のビラ貼付に対する懲戒処分は有効か。
事実
Y(旧国鉄)の職員で、組織されているA労働組合は、昭和44年3月ころ、合理化案反対の要求を目的とした春闘に臨むにあたり、全国各地方本部にビラ貼付の指令を出した。これを受けたA組合B地方本部の指令に基づいて、B駅分会あるいはC運転区分会所属の組合員であるXらは、B組のロッカー合計199個に約400枚のビラを貼ったり、その他の所のロッカーにも大量のビラを貼った。助役らは再三、Xらの行為を抑止しようとしたが、Xらはそれを振り切ってビラ貼付行為を行った。
Yでは、その管理する施設に許可なく文字等を記載または、掲示することを禁じ、A組合に対しても掲示板の設置は認めるが掲示板以外の場所に組合の文書を掲示するすることを禁じられていた。
もっとも、本件ビラの貼付がされた当時、A組合がYから文書の掲示を許可されていた組合掲示板には、必要な多数の文書が掲示されていたため、本件のビラを貼付する余地はなかった。また、本件ビラが貼付されたところは、旅客その他の一般公衆の出入りはまったくなく、Xら職員が休憩等のために使用する場所であって、同所を使用する大部分の職員はA組合の組合員であった。
Yは、Xらを戒告処分にした。Xらは、戒告処分の無効確認を求めて訴えを提起した。1審は戒告処分を有効と判断したが、原審は戒告処分を無効と判断した。そこで、Yは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xらの請求棄却)。
Ⅰ「労働組合法又はその組合法であるからといって、使用者の許諾なしに右物的施設を利用する権限をもっているということはできない」。
Ⅱ「もっとも、当該企業に雇用される労働者のみをもって組織される労働組合(いわゆる企業内組合)の場合にあっては、当該企業の物的施設内をその活動の主要な場とせざるを得ないのが実情であるから、その活動につき右物的施設を利用する必要性の大きいことは否定することができないところではあるが、労働組合による企業の物的施設の利用は、本来、使用者との団体交渉による合意に基づいておこなわれるべきもの・・・・であって、利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において、企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない、というべきである」。
Ⅲ「労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設であって、定立されて企業秩序のもとに事業の運営の用に供されるているものを使用者の許諾を得ることなく、組合活動のために利用することは許されないものというべきであるから、労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで叙上のような企業の物的施設の利用して組合活動を行うことは、これらの者に対してその利用を許さないことがが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、職場環境を適正良好に保持し規律物的施設を管理使用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動として許容されるところであるということはできない」。
解説
企業施設を利用した組合活動については、学説上、日本で中心的な組織形態である企業別組合に」とって、その必要性が高いため、憲法28条における団結権や団体行動権の保障の趣旨にかんがみて、使用者にはこうした企業施設を利用した組合活動を受忍する義務があるとする見解(受忍義務説)がある。他方、こうした受忍義務説には、十分な実定法上の根拠がないとして否定したうえで、組合活動の必要性や企業に与えた損害の程度等を考慮して、一定の場合には、無許可の企業施設の利用の違法性の阻却が認められるとする見解(違法性阻却説)もある。
学説のこのような対立状況のなか、本判決は、判旨Ⅰおおび判旨Ⅱにおいて、受忍義務説を明確に否定した。そのうえで、許諾のない企業施設の利用は原則として許されないとし、許諾をしないことが、使用者の権利濫用と認められるような「特段の事情」がある場合以外は、組合活動の正当性は認められないという判断枠組みを示した(判旨Ⅲ)(いわゆる許諾説)。
許諾があれば組合活動が認められるのは、当然のことなので、「特段の事情」が実際にどの程度広く認められるかが重要なポイントとなる。その後の判例は「特段の事情」を限定的に解したため、企業施設を利用した組合活動が正当と認められる余地は著しく小さくなった。「特段の事情」の認められる典型例は、企業施設の利用の拒否が反組合的意図による場合や、組合併存状況において、合理的な理由なく、一方の組合にのみ利用を認め、他方の組合に利用を認めないという組合間差別の場合である。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
172 企業施設を利用した組合活動(2)-済生会中央病院事件
最2小判平成元年12月11日(昭和63年(行ツ)157号)(民集43巻12号1786頁)
要因
無許可で開催された職場集会に対する警告書の交付等は、支配介入の不当労働行為に該当するか。
事実
Aは、Xが設置運営する病院である。B労働組合は、Xの従業員が組織する労働組合の連合団体の支部で、A病院の従業員らで組織されている。A病院には、このほかにC労働組合がある。
B組合は、A病院が看護婦不足に対応するために行おうとしている勤務体制の変更について協議するため、勤務時間中に病院内の一室で職場集会を開いた。これに対し、A病院は「警告並びに通告書」を交付した。B組合は、無届け、無許可でこの職場集会を行ったが、これまでは、こうした場合でも警告や注意等を受けたことはなかった。
また、A病院はB組合のために過去15年間チェック・オフをしてきたが、新たにC組合が結成され、B組合から大量の組合員の脱退があったので、A病院はチェック・オフの中止を決めた。その後、A病院は、B組合に対し、C組合に提示したものと同一内容のチェック・オフ協定案を提示したが、意見があわず、B組合は協定案に調印しなかった。そのため、チェック・オフは行われないままとなった。
B組合およびその上部団体は、D労働委員会に対し、XおよびA病院は、支配介入の不当労働行為をしているとして、救済を申し立てたところ、Dは救済命令を発した。Xらは、Y(中央労働委員会)に再審査申立てをしたが、棄却された。そこで、Xらは、Yの命令の取消しを求めて、訴えを提起した。1審は請求を棄却し、原審はXらの控訴を棄却した。そこで、Xらは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xの請求認容)。
Ⅰ「一般に、労働者は、労働契約の本旨に従って、その労務を提供するためにその労働時間を用い、その労務にのみ従事しなければならない。したがって、労働組合又はその組合員が労働時間中にした組合活動は、原則として、正当なものということはできない」。
Ⅱ「労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動にあたらない。そして、もとより、労働組合にとって、利用の必要性が大きいことのゆえに、労働の組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用し得る権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うと解すべき理由はない」。
Ⅲ いわゆるチェック・オフは、労基法24条1項ただし書の要件を具備しないかぎり、これをすることができないことは当然である。B組合がA病院の従業員の過半数で組織されていたといえるかこかは疑わしく、書面による協定もなかったことからすると、本件チェック・オフの中止が労基法24条1項違反を解消するものであることは明らかである。これに加えて、A病院がチェックオフを中止いたこと、およびA病院がチェック・オフ協定案を提示したことなどを併せて考えると、本件、チェック・オフの中止は、A病院(X)の不当労働行為に基づくものとはいえず、結局、不当労度行為に該当しないというべきである。
解説
判旨Ⅱは、企業施設を利用して行われた組合活動の正当性について、民事事件で構築された判例(→【171】国鉄札幌運転区事件)を、最高裁が不当労働行為事件(行政訴訟)においてはじめて適用した部分である。本判決は、結論として、職場集会の開催につき、A病院の許諾がなく、その開催を許さないことがA病院の権利の濫用であるとする特段の事情もないので不当労働行為に該当する余地はないと判断している。しかし、不当労働行為事件では、当該労使関係において、組合活動の必要性や使用者の業務への影響、使用者の反組合的意図等を総合的に考慮して救済の要否を(不当労働行為の該当性等)を判断すべきであり、本判決の判断枠組み、結論のいずれにも疑問が残る。
チェック・オフに関する判旨Ⅲについても、私法上適法な行為をしたという点を重視して、不当労働行為意思を否定しており、チェック・オフの中止が労使関係に及ぼす影響が十分に考慮されていないのではないかという疑問が残る。
なお、判旨Ⅰは、勤務時間中の組合活動の正当性を原則として否定する立場を示したものである(→【170】大成観光事件)。しかし、勤務時間中の組合活動であっても、業務への支障や使用者の対抗行為の内容いかんでは、不当労働行為と認められる余地のあると解すべきであろう。
労基法24条1項〔家族生活における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
173 ビラ配布-倉田学園事件
最3小判平成6年12月20日(平成3年(行ツ)155号)(民集48巻8号1496頁)
要因
学校の職員室内で組合活動として行うビラ配布行為に正当性は認められるか。
事実
Xは、学校法人であり、AはXのB校の教職員をもって結成された労働組合である。A組合は、昭和53年5月8日、始業時刻(午前8時25分)前の午前7時55分から8時5分までの間に、職員室内の各教員の机上に職場ニュースを、印刷面を内側に二つ折りにして置く方法で配布した。この職場ニュースの記事は、県下の私立学校教員の労使間の妥結額や交渉状況等を内容とする者であった。同日、XのB校の校長は、A組合の執行委員長Cに対し、このような配布行為をしないよう注意した。
A組合は、翌9日の午前8時から8時5分までの間に、職員室内の各教員の机上に表面を内側に二つ折りにして置く方法で職場ニュースを配布した。この職場ニュースは両面印刷のもので、表面の記事は、同日予定されていた団体交渉の議題等が中心であり、裏面の記事は、不当労働行為について労組法7条を引用して、説明したものであった。
さらに、A組合は、同月16日の午前8時から8時10分までの間に、職員室内の各教員の机上に印刷面を内側に二つ折りにして置く方法で職場ニュースを配布した。この職場ニュースの記事は、9日に行われたX法人との団体交渉の結果を報告するものであった。
この3回のビラ配布(本件ビラ配布)の途中に配布をめぐってトラブルが生じたことはなく、また、始業時刻から職員室で開かれた職員朝礼に支障が生じたこともなかった。
B校の校長は、Cに対し、同月8日と9日にされた職場ニュースの配布は、無許可の印刷物等の頒布等を禁止する就業規則に違反するとして、9日付けで訓告処分をし、16日の配布後には、戒告処分をした。A組合は、その後の団体交渉で、本件各懲戒処分の撤回を要求したが、X側は、これを拒否した。A組合は、Xの一連の行為は、不当労働行為であるとして、Y労働委員会に救済を申し立てた。Yが救済命令を発したので、Xは、その取消しを求めて、訴えを提起した。1審はXの請求を棄却したが、原審は不当労働行為の成立を否定し、救済命令を取り消した。そこで、Yは上告した。
判旨 原判決破棄、一部自判、一部最戻し(ビラ配布の部分については、Xの請求棄却)。
Ⅰ 本件ビラ配布は、許可を得ないで行われたものでるから、形式的には就業規則の禁止事項に該当する。しかしながら、この規定はXの学校内の職場規律の維持および生徒に対する教育的配慮を目的としたものと解されるから、ビラの配布が形式的にはこれに違反するようにみえる場合でも、ビラの内容、ビラ配布の態様等に照らして、その配布が学校内の職場規律を乱すおそれがなく、また、生徒に対する教育的配慮に欠けることとなるおそれのない特別の事情が認められるときは、実質的には右規定の違反になるとはいえず、したがって、これを理由として就業規則所定の懲戒処分をすることは許されないというべきである。
Ⅱ 本件ビラ配布については、学校内の職場規律を乱すおそれががなく、また、生徒に対する教育的配慮に欠けることとなるおそれがない特別の事情が認められるものということができ、本件各懲戒処分は、懲戒事由を定める就業規則の根拠を欠く、違法な処分というべきである。そして、校内での組合活動をいっさい否定する等のX側の組合嫌悪の姿勢、本件各懲戒処分の経緯等に徴すれば、本件各懲戒処分はXの不当労働行為意思に基づくものというほかなく、労組法7条1号、3号の不当労働行為を構成する。
解説
本判決が参照している電電公社目黒電報電話局事件【25】は、組合活動とは無関係の事案であったが、無許可のビラ配布について、形式的には就業規則に違反する場合でも、秩序風紀を乱すおそれのない「特別の事情」が認められるときは、規定違反とは」ならないという判断基準を示していた。同判決は、結論としては「特別の事情」の存在を否定したが、その後の判例(組合活動の事例)には、「特別の事情」を認めて、懲戒処分を無効としたものがあった(明治乳業事件ー最3小判昭和58年11月1日、住友化学工業事件ー最2小判昭和54年12月14日等)。他方、同じ企業施設を利用した組合活動であっても、ビラ貼付や職場集会等については、許諾説(→【171】国鉄札幌運転区事件)の枠組みに基づき正当性について厳しい判断が行われてきた。最高裁は、ビラ配布は、施設管理権の侵害の程度が小さいことから、ビラ貼付の場合とは異なる正当性の判断基準を適用しているのかもしれない。
本判決は、不当労働行為事件であったが、「特別の事情」論に立ち、結論として、懲戒事由該当性を否定している(判旨Ⅰ)。その他の類型の組合活動の事案よりも、柔軟な判断が行われている点が特徴的である(→【172】済生会中央病院事件と比較せよ)。なお、本件は、学校内での組合活動という特徴があり、「生徒に対する教育的配慮」も考慮要素に加えられているが、ビラ配布が始業時刻前に平和的態様で行われて、トラブルも生じていなかったため、教育的配慮という一般的配慮という一般的見地を強調するのは適切でないとはんだんされている(判旨外)。
労組法7条 (不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
174 該当宣伝活動-教育社事件
東京地判平成25年2月6日(平成23年(ワ)25999号)
要因
労働組合の組合員らに対する街頭宣伝活動等の差止めは認められるか。
事実
X1は、雑誌等の販売を行うX2会社おおびコンピューター機器等の販売を行うX4会社の代表取締役である。(X3はその妻)。Y1は、A会社の従業員で組織された労働組合であり、Y2とY3は、A会社から懲戒解雇された者であった。Y4~Y8は、定年退職しているが、A会社に対して別訴で確定した未払賃金等が残っていた。Yらは、A会社、X2会社とX4会社(以下、X2会社ら)の株式はX1らが所有し、X2会社らは、A会社から事業譲渡を受け、A会社の銀行債務も引き受けていることなどから、X1らの身辺や自宅前およびX2らの本店所在地のビル前で、X1を非難したり、「未払賃金を支払え」などという趣旨の記載された立て看板を設置したり、拡声器等を使用して同内容の演説をしたりするなどの街頭宣伝活動等を繰り返した。Xらは、Yらに対して、人格権および営業権に基づき、こうした活動の差し止めを請求した。
判旨 請求認容。
Ⅰ「団体的労使関係といえども、労働者の労働契約関係上の諸利益についての交渉を中心として展開するものであるから、労働契約関係をその基盤として成立するのが通常であり、そうでないとしても、労働契約関係に近似ないし隣接した関係をその基盤として必要とするものというべきである」。
Ⅱ「本来、雇用主でなくとも、・・・・当該労働契約関係に近似ないし隣接した関係を有する者は、当該労働者の団体交渉の相手方である『使用者』となる余地がある・・・・としても、雇用主である企業や上記の当該労働契約関係に近似ないし隣接した関係を有する企業の役員等までもが上記の『使用者』に含まれるということはできない」。
Ⅲ「X2会社らは、いずれもYらとの関係で、労契法上の使用者とは認められないから、・・・・YらによるX2会社らに対する組合活動としての街宣活動等は、憲法28条ないし労組法の保護を受ける余地のないものといわざるを得ない」。加えて、Yらによる街宣活動等は、その目的、内容、態様、頻度等から、現にX2会社らの平穏を営業を営む権利を侵害しているのであるから、その差し止めを認めることは、憲法21条1項に違反しない。
Ⅳ「一般的に」、労使関係の場で生じた問題は、労使関係の領域である職場領域内で解決すべきものであって、企業経営者といえども、個人として、住居の平穏や地域社会ないし私生活の領域における名誉・信用が保護、尊重されるべきである・・・・。したがって、労働組合の活動が企業経営者の私生活の領域において行われた場合には、当該活動は、労働組合の活動であることの故をもって正当化されるものではなく、それが、企業経営者の住居の平穏や地域社会(ないし私生活)における名誉・信用という具体的な法益を侵害しないものである限りにおいて、表現の自由の行使として相当性を有し、容認されることがあるにとどまる」。
解説
労働組合が、労働紛争をかかえている相手方の会社や関係会社の社屋、あるいはそれらの会社の役員の自宅などにおいて、面会を求めたり、ビラをまいたり、拡声器で組合の要求や主張を訴えていする街頭宣伝活動(街宣活動)をした場合における、その組合活動の正当性の判断基準は必ずしも明確でない。
本件は、組合員の街宣活動の相手方が、労働契約関係が消滅している別会社とその経営者(兼株主)であったことから、まず、団体的労使関係の存否が問われた。
そこでは、組合活動が相手への要求を行うというタイプのものである場合、その相手方は団体的労使関係上の使用者でなければならないという理解が前提となっている。この判断は不当労働行為法上の使用者性(労組法7条を参照)の判断と理論的に同一ではないが、本判決は、実質的に同様の基準で判断をしている(判旨Ⅰ)。本件では、X2会社らもX1ら個人も、A会社との間の密接な関係はうかがわれるが、いずれについても使用者性を肯定するには至らないと判断された(役員等は、そもそも」団体的労使関係上の使用者性は肯定できない[ 判旨Ⅱ ]。直接には、労使関係に立たない者への団体行動も憲法28条の保障対象となりうるが、正当性の判断は、厳格になるという趣旨の裁判例として、富士美術印刷事件ー東京高判平成28年7月4日)。
本判決は、以上の使用者性の判断から、組合活動の正当性を否定し、さらに平穏に営業を営む権利が侵害されていることを理由に、X2会社らの求めた差止めを肯定した(判旨Ⅲ)。また、X1ら個人については、労使関係上の問題は、労使関係の領域(職場領域)内で解決すべきであるとし、個人の私的領域での組合活動には正当性を認めず、また表現の自由としても、住居の平穏や地域社会(ないし私生活)における名誉・信用という具体的な法益を侵害しないかぎりで容認されるすぎず(判旨Ⅳ)、本件はそのような場合に該当しないので、差止めがが認められるとした(判例には、出向先での出向反対の情宣活動の正当性を否定したものもある[ 国労高崎地本事件ー最2小判平成11年6月11日 ])。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法21条1項〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
労組法7条 (不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
175 争議行為時における使用者の操業継続の自由-山陽電気軌道事件
2小判昭和53年11月15日(昭和52年(あ)583号)(刑集32巻8号1855頁)
要因
バス会社における争議対抗措置に対抗するための労働組合の車両確保戦術に、正当性は認められるか。
事実
バスおよび電気軌道による旅客運送業を営むA会社では、昭和36年5月当時における従業員約1300名のうち約500名は、B労働組合にして、その余の約800名は、B組合から分裂して誕生したC労働組合に所属していた。昭和36年の春季闘争に際し、A会社とB組合交渉が難航し、B組合のストライキが必至の情勢となったので、A会社は、この争議に参加しないC組合の就労を前提に争議中もできるだけバスの運行を図るために、車両の確保をしようとした。前年の春季闘争の際に、B組合に会社の車両の約9割を確保されてほとんど運行できなかった経験から、再び同様の事態が発生することを強く危惧したからである。具体的には、A会社は、同年5月25日ころから車両の分散を始め、翌26日およびB組合がストライキに入った27日以降は、第三者の管理する建物等を選び、その日の営業を終えた貸切車等から順次回送する方法で数か所に車両を分散し、これを保全看守した。
B組合は、これに対抗するため、A会社が回送中または路上に駐車中のバスを奪ってB組合側の支配下に置いたり、A会社が取引先の整備工場または系列下の自動車学校に預託中のバスを搬出しようとして看守者の意思に反して建造物に侵入したりして、バス約260台のうちの半数近くを確保した。B組合がこれらの車両確保戦術を実行するうえでは、暴力をともなうこともあった。
B組合の組合員や支援組合の組合員であるXらは、威力業務妨害罪、暴行罪、傷害罪、建造物侵入罪(刑法234条、208条、204条、130条)等で起訴された。1審および原審ともに、Xらを有罪とした。そこで、Xらは上告した。
決定判旨 上告棄却(Xらは有罪)。
Ⅰ「使用者は、労働者がストライキを行っている期間中であっても、操業を継続することができる・・・・。使用者は、労働者側の正当な争議行為によるって業務の正常な運営が阻害されることは受忍しなければならないが、ストライキ中であっても、業務の遂行自体を停止しなければならないののではなく、操業阻止を目的とする労働者側の」争議手段に対しては操業を継続するために必要とする対抗措置をとることができると解すべきである」。「従って、使用者が操業を継続するために必要とする業務は、それが労働者側の争議手段に対する対抗措置として行われたものであるからといって、威力業務妨害罪によって、保護されるべき業務としての性格をうしなうものでなない」。
Ⅱ「A会社のした右車両分散等の行為は、ストライキの期間中でも、これに参加しないC組合所属の従業員によって操業を阻止する手段としてB組合の計画していた車両の確保を未然に防いで本来の運送事業を継続するために必要とした業務であって、これを威力業務妨害罪によって保護されるべき業務とみることに何の支障もないというべきである」。
Ⅲ「ストライキに際し、使用者の継続しようとする操業を阻止するために行われた行為が犯罪構成要件に該当する場合において、その刑法上の違法性阻却事由の有無を判断するにあたっては、当該行為の動機目的、態様、周囲の客観的状況その他の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否かを判定しなければならない」。
解説
使用者は、ストライキの期間中であっても、操業を継続するために必要とする対抗措置をとることができる(決定判旨Ⅰ)。こうした争議対抗措置は、ストライキに参加しない従業員や管理職を用いたり、代わりの労働者を雇い入れたりして行われることになる。操業継続は、ストライキの効果を減殺することになるが、争議権は、使用者の操業継続を阻止する権利まで含まないと解されている。
使用者の争議対抗措置として継続される業務を、労働組合が阻止しようとする場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性がある(決定判旨Ⅰ、Ⅱ)。本件のような車両確保戦術も、それが当初のストライキの実効性をか維持するためのものであったとしても、正当性を欠くものであれば刑事免責は認められない。
本判決は、「法秩序全体の見地」から正当性をはんだんするという判例のアプローチ(国労久留米事件ー最大判昭和48年4月25日)を踏襲している(決定判旨Ⅲ)。具体的な判断においては、B組合が、A会社の最も重要な生産手段であるバス車両を対象として、A会社の支配管理権を侵害しようとしたものであること、それらの行為が、多数の威力を示して行われたものであること、それらの行為が、多数の威力を示して行われたものであることを指摘して、結論として、本件車両確保戦術の正当性を否定している(判旨外)(→【162】御園ハイヤー事件)。
刑法234条(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法208条(過失傷害)
第209条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法204条(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法130条(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
176 ロックアウト-丸島水門製作所事件
最3小判昭和50年4月25日(昭和44年(オ)1256号)(民集29巻4号481頁)
要因
使用者はロックアウトにより賃金支払債務を免れることができるか。
事実
Yは水門の製作、請負工事等を業とする会社である。Aは、Y会社の従業員で組織された労働組合である。A組合は、昭和34年5月、賃上げをめぐって、Y会社と数回にわたる団体交渉を重ねたが、双方その主張に固執して譲らず、妥結に至らなかったので、同月19日、争議行為の通告をした。A組合は、その後、ビラ貼付、事務所内のデモ行進、拡声器を用いたY会社役員の非難、怠業、主張拒否、一斉休暇、会社職制の巡視に対する妨害等をし、それにより、Y会社の作業能率が著しく低下し、正常な業務の遂行が困難となった。そこで、Y会社は、このままの状態では、会社の経営も危なくなるおそれがあると考え、同年6月2日にロックアウトを通告した。A組合の組合員であるXらは、Y会社に対して、ロックアウト期間中に支払われなかった賃金の支払いを求めて訴えを提起した。1審は請求を容認したが、原審は請求を棄却したため、Xらが上告した。
判旨 上告棄却(Xらの請求棄却)。
Ⅰ「争議権を認めた趣旨が争議行為の一般市民法による制約からの解放にあり、労働者の争議権について特に明文化した理由が専らこれによる労働者等の促進と確保の必要に出たもので、究極的には公平の原則に立脚するものであるとすれば、力関係において、優位に立つ使用者に対して、一般的に労働者に対するのと同様な意味において争議権を認めるべき理由はなく、また、その必要もないけれども、そうであるからをいって、使用者に対し、一切、争議権を否定し、使用者は労働争議に際し、一般市民法による制約の下においてすることができる対抗措置をとるにすぎないとすることは相当でなく、個々の具体的な労働争議の場において、労働者側の争議行為により、かえって、労使間の勢力の均衡が破れ、使用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合には、衡平の原則に照らし、使用者側においてこのような圧力を阻止し、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗手段として相当性を認められるかぎりにおいては、使用者の争議行為も正当なものとして是認されると解すべきである」。
Ⅱ 使用者のロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認されるかどうかは、「個々の具体的な争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事実に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として、相当と認められるかどうかによってこれを決すべく、このような相当性を認めうる場合には、使用者は、正当な争議行為をしたものとして、右ロックアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務をまぬがれるものといわなければならない」。
解説
労働者側が行う争議行為とは異なり、使用者が争議行為を行うことができるかについては、現行法上、特段の定めは置かれていない。しかし、本判決は、憲法28条や労組法が、労働組合の争議権のみ保障しているのは、「労使対等の促進と確保の必要に出たもので、窮極的には公平の原則に立脚するものである」とし、衡平の原則に基づき、使用者の争議行為も正常なものと是認される余地を認めている(判旨Ⅰ)。その要件は、労働者側の争議行為により、労使間の勢力の均衡が破れ、使用者側が著しく不利な圧力を受ける状況になることである。ここから、使用者の争議行為の正当性は、使用者側がこのような圧力を阻止し、労使間の勢力の均衡を回復するための対応防衛手段として相当性が認められるかどうかにより判断されることになる。
つまり、使用者にとって許される争議行為は、労働組合の争議行為に対する防衛的なものにかぎられ、使用者から労働条件の変更(賃金の引下げ等)を求めて行う攻撃的ロックアウトや、労働者側の争議行為を予測して、その影響を未然に防止するために行う予防的ロックアウト等の先制的ロックアウトには、正当性は認められないことになる。
本判決は、ロックアウトの正当性の判断要素として、「労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情」をあげている(判旨Ⅱ)。本件では、A組合の争議行為は、暴力行為をともなう相当熾烈なものであったこと、怠業状態が深刻化していたこと、一連の争議行為によって、Y会社の正常な運営が著しく阻害され、作業能率も低下していたこと、このため中小企業であるY会社の経営に支障をきたすおそれが生じたことという事情があり、それに対して、Y会社は、一時的に作業所を閉鎖して、賃金の支払いを免れて、当面の著しい損害の発生を阻止しようとしたものであり、正当性が認められると判断された(判旨外。その後、同様にロックアウトの正当性を肯定した判例として、安城川生コンクリート工業事件ー最3小判平成18年4月18日)。
なお、ロックアウトの相当性は、その開始の際だけでなく、継続の際にも必要である(第一小型ハイヤー事件ー最2小判昭和52年2月28日)。
177 不当労働行為救済制度の趣旨・目的-第二鳩タクシー事件
最大判昭和52年2月23日(昭和45年(行ツ)60号・61号)(民集31巻4号93頁)
要因
解雇が不利益取扱いに該当する場合の救済命令において、バックペイから中間収入を控除しないことは適法か。
事実
タクシー事業を営むX会社の運転手であるAらは、B労働組合の組合員であった。X会社は、人員過剰等を理由にAらを解雇したので、AらとB組合は、Y労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。Yは不当労働行為の成立を認めて、現職復帰命令を発し、同時に中間収入を控除しないでバックペイの支払いも命じた。X会社は、バックペイの全額支払いを命じた部分の取消しを求めて訴えを提起した。1審および原審ともにYの救済命令は、原状回復という救済命令の範囲を超えているとして、これを取り消した。そこでYは上告した。
判旨 上告棄却(X会社の請求認容)。
Ⅰ「労働組合」法27条に定める労働委員会の救済命令は、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した法7条の規定の実効性を担保するてめに設けられたものであるところ、法が、右禁止規定の実効性を担保するために、使用者の右規定違反行為に対して、労働委員会という行政機関による救済命令の方法を採用したのは、使用者による組合活動侵害行為によって、直接是正することにより、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図るとともに、使用者の多様な不当労働行為に対してあらかじめその是正措置の内容を具体的に特定しておくことが困難かつ不適当であるため、労使関係について専門的知識経験を有する労働委員会に対し、その裁量により、個々の事案に応じた適切な是正措置を決定し、これを命ずる権限をゆだねる趣旨に出たものと解される。このような労働委員会の裁量権はおのずから広きにわたることになるが、もとより、無制限であるわけではなく、右の趣旨、目的に由来する一定の限界が存するのであって、この救済命令は、不当労働行為による被害の救済としての性質をもつものでなければならず、このことから導かれる一定の限界を超えることはできないものといわなければならない。
しかし、法が、右のように、労働委員会に広い裁量権を与えた趣旨に徴すると、労働委員会に広い裁量権を与えた趣旨に徴すると、敗訴において労働委員会の救済命令の内容の違法性が争われる場合においても、裁判所は、労働委員会の右裁量権を尊重し、その行使が右の趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、又は、著しく不合理であって濫用にわたると認められるものでない限り、当該命令を違法とすべきではないのである」。
Ⅱ「法7条1号に違反する労働者の解雇に対する救済命令の内容について考えてみると、法が正当な組合活動をした故をもってする解雇を特に不当労働杭として禁止しているのは、右解雇が、一面において、当該労働者個人の雇用関係上の権利ないしは利益を侵害するものであり、他面において、使用者が右の労働者を事業所から排除することにより、労働者らによる組合活動一般を抑圧ないし制約する故なのであるから、その救済命令の内容は、被解雇者に対する侵害に基づく個人的被害を救済するという観点からだけでなく、あわせて、組合活動一般に対する侵害の面をも考慮し、このような侵害状態を除去、是正して法の所期する正常な集団的労使関係秩序を回復、確保するという観点からも、具体的に、決定されなければならないのである。
解説
不当労働行為の救済制度は、「正常な集団的労働関係秩序の迅速な回復、確保を図る」ことを目的とするもので、その実現のために、労使間経緯ついて、専門的知識経験を有する労働委員会に、命令により組合活動侵害によって生じた状況を是正する権限が与えられている。特に、救済命令の内容については、裁判所は、労働委員会の裁量権を尊重すべきであり、その行使を不当労働行為の趣旨、目的に照らして是認される範囲を超えたり、著しく不合理であって濫用にわたると認められないかぎり、命令を違法とすべきでないとされる(判旨Ⅰ)。
解雇が不利益取扱いとなる場合の救済命令の内容については、本判決は、解雇には、個人の権利や利益の侵害という面とがあり、その両者の点を考慮して、救済命令の内容を決定すべきとする(判旨Ⅱ)。通例では、原職復帰とバックペイについては、中間収入の控除が行われる(民法536条2項2文)が、不当労働行為の救済命令では、必ずしも私法規範に従う必要はない(ただし、【194】ネスレ日本事件を参照)。当初の判例は、中間収入を控除しないバックペイ命令は、原状回復という本来の目的の範囲を逸脱し、使用者に懲罰を科するもので違法としていた(在日米軍調達部事件ー最3小判昭和37年9月18日)が、労働委員会は本件のようにこれに従ってこなかった。このようななか、本判決は、判例を変更し、中間収入控除は必要的でないとしたが、Aらは、容易に再就職先を見つけ、そこでの収入が高かったなど、解雇による打撃が比較的軽少で、そのため組合活動意思に対する制約的効果も、通常の場合とかなり異なっていたことを考慮して、結論として全額バックペイ命令を違法を判断した(判旨外。その後も、あけぼのタクシー事件ー最1小判昭和62年4月2日)。
労働組合法27条(不当労働行為事件の審査の開始)
第27条 労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
2 労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
民法536条2項(債務者の危険負担等)
第536条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
労働組合法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
178 不当労働行為の主体(1)-朝日放送事件
最3小判平成7年2月28日(平成5年(行ツ)17号)(民集49巻2号559頁)
要因
社外の労働者を受け入れて自社の業務に従事させている会社は、その労働者で組織される労働組合との団体交渉に応じなければならないか。
事実
Xは、テレビの放送事業等を営む会社であり、Aは近畿地方所在の民間放送会社等の下請事業を営む企業の従業員で組織された労働組合である。X会社は、B会社およびC会社との間で、テレビの番組制作の業務につき請負契約を締結して、継続的に業務の提供を受け、D会社はB会社と請負契約を締結し、B会社がX会社から請け負った業務のうち照明業務下請をしていた。B、C、D請負3社は、各請負契約に基づきその従業員をX会社のもとに派遣して(労働者派遣法施行前なので、労働者派遣ではない)、番組制作の業務に従事させており、各請負契約においては、作業内容および派遣人員により、一定額の割合をもって算出される請負業をX会社が支払う旨の定めがされていた。
番組制作にあたって、X会社は、毎月、日別に制作番組名、作業時間、作業場所等が記載された編成日程表を作成して請負3社に交付した。請負3社は、その編成日程表に基づき、番組制作連絡票書を作成して、誰をどの番組制作業務に従事させるかを決定することとしていたが、実際には、派遣される従業員はほぼ固定されていた。請負3社の従業員は、その担当する番組性格業務につき、編成日程表に従うほか、X会社が作成交付する台本および制作進行表による作業内容、作業手順等の指示に従い、同社の器材等を使用し、同社の従業員とともに番組制作業務に従事していた。請負3社の従業員の業務の遂行にあたっては、実際の作業の進行は、すべてX会社のティレクターの指揮監督のもとに行われ、ディレクターは、請負3社の従業員に対しても、作業時間帯の変更や作業時間の延長、休憩について、その判断で指示していた。
請負3社は」、それぞれ独自の就業規則をもち、労働組合との間で賃上げ、一時金等について団体交渉を行い、労働協約を締結していた。
A組合は、X会社に対して、賃上げ、一時金の支給、下請け会社の従業員の社員化、休憩室の設置を含む労働条件の改善等を議題として団体交渉を申し入れたが、X会社は、使用者でないことを理由として」、交渉事項のいかんにかくぁらず、いずれもこれを拒否した。
そこで、A組合は、E労働委員会に対して、X会社の団交拒否は不当労働行為にあたるとして、救済申立てしたところ、Eは、X会社の関与する事項についての団交と文書手交を内容とする命令をはっしたので、X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査申立てをした。Yは、命じる団交の範囲を組合員の就労に関するものに変更した上で、その余の再審査申立てを棄却した。そこで、X会社は、Yの命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審はX会社の請求を棄却したが、原審は、X会社の使用者性を否定し、Yの命令を取り消した。そこで、Yは上告した。なお、差戻審では、X会社の控訴棄却となっている。
判旨 原判決破棄、差戻し
「労働組合法7条にいう、『使用者』の意義について検討するに、一般に使用者とは労働契約上の雇用主をいうものであるが、同情が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみると、雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、その限りにおいて、右事業主は同条の『使用者』に当たると解するのが相当である」。
解説
労働契約関係にない労働者を受け入れて業務に従事させている事業主は、その労働者を組織している労働組合との関係で、不当労働行為責任が問われる使用者となることがあるか。本判決は、原則そして、使用者とは、労働契約上の雇用主指すが、団結権侵害にあたる一定の行為を排除・是正して、正常な労使関係を回復するという不当労働行為制度の目的にかんがみ、雇用主以外の事業主であっても、
①雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させており、
②その労働者の基本的な労働条件について、
③雇用主と部分的とはいえ、同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には、
④そのかぎりにおいて、使用者性が認められるとする。
そして、本判決は、X会社は、実質的にみて、請負3社からの従業員の勤務時間の割振り、労務提供の態様、作業環境等を決定していたので、これらの従業員の基本的な労働条件等について、雇用主である請負3社と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にあったものとして、そのかぎりにおいて、労組法7条の使用者にあたると判断している(判旨外)。
本件のような事案には、法人格否認の法理などの私法上の使用者概念の拡張のアプローチもありうるが、不法労働行為事件では、原則として、本判決の法理を端的に適用していくべきであろう。
なお、本判決は、「雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ」た事案に対する判断で」ある(①)が、その他の事案にも、①の文言を外したうえで、適用されることもある(親子会社の事案で、高見澤電機製作所ほか2社事件ー東京高判平成24年10月30日)。
本件は、労働者派遣法の制定前の事件であったが、同法の制定後の派遣については、派遣先は原則として労組法7条の使用者ではないものの、当該派遣が、労働者派遣法の原則的な枠組みによらない場合、または、同法で使用者とみなされ労基法上の責任を負うとされる場合には、本判決の枠組みを用いて使用者側の判断がなされるとした裁判例もある(阪急交通社事件ー東京地判平成25年12月5日)。
労働組合法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
179 不当労働行為の主体(2)-JR北海道・日本貨物鉄道事件
最1小判平成15年12月22日(平成13年(行ヒ)96号)(民集57巻11号2335頁)
要因
国鉄からJRへの民営化の際の採用差別についてJRは不当労働行為責任を負うか。
事実
X1およびX2は、それぞれ、国鉄の分割・民営化に伴い設立されたJR会社のの1つである。JR会社の職員の採用法方法は、日本国有鉄道改革法(以下、改革法)に定められており、それは、JR各社の設立委員が、職員の労働条件と採用基準を提示し、国鉄が、それを提示して職員ンお募集を行い、職員となる意思を表示した者の中から、設立委員の示した基準に従って採用候補者名簿を作成し、設立委員は、その中から採用する者を決定するということになっていた。A労働組合の組合員Bらは、採用候補名簿に記載されず、X1会社およびX2会社に採用されなかったため、採用候補者の選定や名簿の作成過程において不当労働行為があったとして、C労働委員会に救済を申し立てた(追加採用(6月採用)においてもBらは採用されなかったので、その点も不当労働行為として救済を求めた)。なお、JRに採用されなかった労働者は、国鉄の清算事業団(以下、事業団という)の職員となった。
Cは、不当労働行為の成立を認めて、X1・X2両社の設立時からの採用取扱い等を命じる救済命令を発した。X1・X2両社は、Y(中央労働委員会)に再審査を申し立てたが、YはBらのうち、一定の要件を満たす者について、選考をやり直し、採用すべきものと判定した者を採用することを命じる救済命令を発した。そこで、X1・X2両社は、Yの命令のうち救済を認めた部分の取消しを求めて訴えを提起した。1審は、Yの救済命令を取り消し、原審は、Yの控訴を棄却した。そこで、Yは上告した。
判旨 上告棄却(Xらの請求認容)
Ⅰ「改革法は、・・・・その採用手続の各段階における国鉄と設立委員の権限については、これを明確に分離して規定しており、このことに改革法及び関係法令の規定内容を併せて考えれば、改革法は、設立委員自身が不当労働行為を行った場合は別として、専ら国鉄が採用候補者の規定及び採用候補者名簿の作成に当たり組合差別をしたという場合には、労働組合法7条の適用上、専ら国鉄、次いで事業団にその責任を負わせることとしたものと解さざるを得ず、このような改革法の規定する法律関係の下においては、設立委員ひいては、承継法人が同条にいう『使用者』として不当労働行為の責任を負うものではないと解するのが相当である」。
Ⅱ 企業者は、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、原則として自由に決定することができるものであり、他方、企業者は、いったん労働者を雇い入れ、雇用関係上の一定の地位を与えた後においては、その地位を一方的に奪うことにつき、雇入れの場合のような広い範囲の自由を有するものではない。労組法7条1号本文は、雇入れにおける差別的取扱いが前段の類型に含まれる旨を明示的に規定しておらず、雇入れ段階と雇入れ後の段階に区別を設けたものと解される。そうすると、雇入れの拒否は、それが従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにほかならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合にあたるなどの特段の事情がないかぎり、労組法7条1号本文にいう不利益な取扱いにあたらないと解するのが相当である。
解説
戦後における最大の労働事件の1つといえるJR採用差別事件は、JRの使用者性を否定する最高裁の判断により、法的な面での決着はほぼついた。国鉄の行った不当労働行為の責任は承継法人であるJRが引き継ぐのが当然のように思えるが、本判決は、改革法が、国鉄と設立委員の権限を明確に分離していることを重視して、不当労働行為の責任は専ら国鉄のみが負うと判断した(判旨Ⅰ)。なお、1審と原審は、朝日放送事件最高裁判決(→【178】)の判断枠組みを用いたうえで、結論として、使用者性を否定していたが本判決は、改革法があるという点で、朝日放送事件とは事案を異にするとかいしたのであろう。ただ、判旨Ⅰに対しては、改革法の規定に対しては、改革法の規定にとらわれすぎているという批判は強く、Yも、国鉄が設立委員の補助機関の地位にあり、国鉄において不当労働行為があった場合には、設立委員にその責任が帰属するという法解釈を展開していたが、本判決の多数意見のとるところとならなかった(反対意見では採用されている)。
JRへの移行後の追加募集における採用拒否については、新規採用の拒否が不利益取扱いになるのかという点が争われた。本判決は、労組法7条1号の前段と後段(黄犬契約の禁止)とを分けて、原則として、新規採用の拒否は後段に該当する」場合にしか不当労働行為は成立しないという限定的な解釈を示している(判旨Ⅱ)。ここには、本判決が引用する、採用の自由を広く認める判例の立場が影響している(→【17】三尾樹脂事件)ただし、本判決も、雇入れ拒否が、従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにあたるなどの特段の事情が認められる場合には、不利益取扱いに該当する余地を認めている。有期労働契約の反復更新後の雇止めや定年後の再雇用拒否のような場合が、これに該当するものであろう(→【65】東芝柳町工場事件)
労働組合法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
180 不当労働行為の主体(3)-クボタ事件
東京地判平成23年3月17日(平成21年(行ウ)550号)
要因
派遣会社は、直用化が決まっただけで、まだ労働契約が成立していない派遣労働者との関係で、労組法7条の使用者と認められるか。
事実
内燃関連機器の製造・販売を営む会社は、A会社との間で、請負契約を締結し、それに基づきX会社の構内でA会社の従業員が作業に従事していたが、平成18年9月に請負契約を労働者派遣契約に切り替えた。その後、X会社は、同社の関連会社が、労働者派遣法で定める制限期間を超えた派遣の役務の提供を受けていたことを理由として労働局の是正指導を受けたことを契機に、製造派遣に従事する派遣労働者を平成19年4月1日を目処に直用することにした。Bらは、X会社のC工場で勤務する者で、同工場で勤務する者により組織された分会Dの組合員である。
D組合は、平成19年2月1日にX会社に対して、直用化や組合員の労働条件等を交渉事項とする団体交渉を申し入れたところ、X会社は同月26日に1度は、直用化に関して団体交渉に応じたが、同月28日、同年3月14日および同月23日の団体交渉申入れには応じなかった。そこで、D組合は、X会社の行為は、労組法7条2号および3号の不当労働行為に該当することを理由に、E労働委員会に救済を申し立てたところ、EはX会社が2回目以降の団体交渉に応じなかったことは、2号の不当労働行為に該当するとして文書手交を命じた。X会社は、これを不服としてY(中央労働委員会)に再審査を申し入れたところ、Yはこれを棄却する命令を発した。そこで、X会社はその取消しを求めて訴えを提起した。なお、本判決に対する控訴は棄却されている(東京高判平成23年12月21日)。
判旨 請求棄却
「不当労働行為禁止規定(労組法7条)における『使用者』について、不当労働行為救済制度の目的が、労働者が団体交渉その他の団体行動のために労働組合を組織し運営することを擁護すること及び労働協約の締結を主目的とした団体交渉を助成することにあること(同法1条1項参照)や、団体労使関係が、労働契約関係又はそれに隣接ないし近似した関係をその基盤として労働者の労働関係上の諸利益についての交渉を中心として展開されることからすれば、ここでいう『使用者』は、労働契約関係ないしはそれに隣接ないし近似する関係を基盤として成立する団体労使関係上の一方当事者を意味し、労働契約上の雇用主が基本的に該当するものの、雇用主以外の者であっても、当該労働者との間に、近い将来において労働解約関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存する者もまた、これに該当するものと解すべきである」。
解説
1 労働契約が成立する前の段階の労働者を組織する労働組合からの団体交渉申込みの拒否が労組法7条2号の不当労働行為に該当するかどうかは、同号の「使用者が雇用する労働者」かどうかという観点から論じることもできるが、本判決は労組法7条(柱書)の使用者性の問題としてこの問題を扱っている。
労契法7条の使用者については、朝日放送事件最高裁判決(→【178】)で示された判断枠組みがあるが、本判決は、これに加えて、「近い将来において労働契約関係が成立する現実的かつ具体的な可能性が存する者」も含めて判断をしている。その後の裁判例も、労働契約関係に「隣接ないし近似」する関係があれば、労組法7条の使用者と認めるという判断枠組みのもとに、朝日放送事件の類型を「近似」型、本件のような類型を「隣接」型として整理して、事案を2つの類型に分類し、それぞれの判決で示された判断基準をあてはめる傾向にある。
本件は、派遣会社は、派遣労働者の直用化を決定していたことから、「近い将来において労働契約関係が成立する現実的かつ具体的な可能性」が認められて、使用者と判断された。
現在では、一定の違法派遣を行ったため労働者派遣法40条の6が適用されて労働契約の申込みをしたとみなされる派遣会社も、この基準により使用者とみなされるであろう(派遣労働者が労働契約の申込みを承諾した後は、労働契約が成立するので、当然使用者となる)。
2 本件のような労働契約関係の成立前とは逆に。4労働契約関係の終了後においても、労組法7条2号の雇用関係(あるいは使用者性)が認められる場合もある。その典型は、労働者が解雇されたが、その解雇の有効性が争われている場合である。(日本鋼管鶴見造船所事件ー最3小判昭和61年7月15日)。有期労働契約の雇止めや定年後の再雇用の拒否のような場合も、解雇に準じて扱われるであろう。ただし、解雇後、合理的期間を超えた場合には、使用者性は否定される(オンセンド事件―東京高判平成21年6月18日[雇止めの事件]を参照)。また、労働契約関係終了時に、係争対償となっっていた労働条件をめぐる団体交渉については、労働契約関係終了後においても使用者性は肯定されよう。以上の場合に該当しないケースでは、原則として、退職した労働者との間では、使用者性は認められない。ただし、石綿被害のように、在職中の被害が退職後かなりの期間を経過した後に顕在化した裁判例もある(住友ゴム工業事件ー大阪高判平成21年12月22日)。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
労組法1条1項 (目的)
第1条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。
労働者派遣法40条の6
第40条の6 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。
一 第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
二 第二十四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
三 第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること(同条第四項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第一項の規定に違反することとなつたときを除く。)。
四 第四十条の三の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
五 この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第二十六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
181 不利益取扱い(1)-北辰電機製作所事件
東京地判昭和56年10月22日(昭和52年(行ウ)6号)
要因
労働組合内部に上部団体支持派と反対派がある場合、上部団体支持派に所属していることを理由とする賞与差別や昇格差別は不利益取扱いに該当するか。
事実
Xは、工業計測器の製造販売を主たる業務とする会社である。X会社の従業員で結成されたA労働組合は、B労働組合を上部団体とするX会社における支部であった。A組合の内部には、生産性向上に協力するかどうかをめぐり、これに反対するB組合の指導を尊重する「B組合派」と、生産性向上に協力することに積極的な「批判派」が対立しており、それを反映して、A組合の執行委員選挙では、激しい選挙戦が行われてきた。
その後、昭和46年度のA組合の総会でB組合からの脱退が決議され、名称もC労働組合に変更された。しかし、A組合の組合員のうち、「B組合派」は、脱退決議は組合規約に違反して無効であり、従前のA組合は依然としてB組合に加盟して存続しているとして、組合活動を継続してきた。
A組合の組合員であるDほか19名およびB組合、A組合らは、X会社が、Dらを「B組合派」であることを理由として、昭和46年度昇給および夏季賞与の査定額の決定、ならびに主事補への昇格において差別したことを理由に、不当労働行為の救済を申し立てたところ、Y労働委員会は、Yが是正した考課点を基礎として査定額を算定し、差額を支払うこと、Dほか11名につき昭和46年6月に遡って主事補に昇格させることなどを内容とする救済命令を発した。そこで、X会社は、この命令の取消しを求めて、訴えを提起した。
判旨 一部認容、一部棄却(昭和46年度昇給・夏季賞与における差別に関して不当労働行為に該当するとした判断、およびD以外の主事補昇格差別が不当労働行為に該当するとした判断は、取り消された)。
Ⅰ「企業内の唯一の組合に特定の傾向を有する組合活動を行う集団が存在する場合において、組合員が右集団に属して右特定の傾向を有する組合活動を行う故をもって、使用者である企業が右組合員個人の賃金・昇給を差別的に取り扱うことは、当然、労働組合法7条1号の不当労働行為に該当し、また、右のような差別的取扱いをすることは、同法7条3項の不当労働行為に該当すると解される」。
Ⅱ Dの昭和44年度、昭和45年度、昭和46年度昇給査定額および昭和46年度夏季賞与査定額をみれば、中位より低い位置にはあるが、著しく低いと認められず、また、すでに主事補に昇格している他の申立人の昇給査定額あるいは考課点に比べて劣っているものとは認められず、入社年月日も昭和31年4月1日であるから、同人を昭和46年6月に主事補に昇格させなかった合理的理由を見いだすことはできず、一方、Dは昭和43年8月からA組合書記長の要職にあってB組合を支持する組合員の中核として活動していたと認められるから、Dを昭和46年6月に主事補に昇格させなかったことは、Dが「B組合派」のなかでも特に活発に組合活動を行っていたことを理由に不利益に取り扱ったもので、B組合の方針を支持する組合員らの活動に打撃を与えることをいとしていたものと認めるのが相当であり、X会社のDに対する前記の行為は、労組法7条1号、3号所定の不当労働行為に該当すると解される。
解説
労組法7条1号で定める不利益取扱いが成立するためには、
①「労働組合の組合員であること」、
②「労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと」、または
③「労働組合の正当な行為をしたこと」の
④「故をもって」、
解雇その他の不利益な取扱いが行われたものでなければならない。④の関係では、不当労働行為意思が要件となるかが問題となり、これを必要とする見解が通説である(否定説は、①から③の要件と使用者の不利益な取扱いとの間に客観的な因果関係があればよいとする)。
本件は、①の要件について、労働組合の」内部において、複数の組合員集団(執行部支持派と批判派)があり、その一方に所属することを理由として不利益な措置がとられた場合にも、この要件を満たすかが争われたものである。本判決は、このような場合にも、不利益取扱いとなると認めた(判旨Ⅰ)
同種の問題は、③の要件との関係で、労働組合内の少数派が独自の活動を行ったことを理由とする不利益取扱い場合にも問題となる。労働組合が明示的に指示していなくても、組合の方針に反せず、組合が黙示的に承認をしていたと評価することができる行動については、「労働組合の行為」と解すべきであろう。また、労働組合の役員などの選挙において少数派が行う選挙活動や、組合内部での意思形成過程において少数派が執行部を批判する言論活動についても、民主的な団体である労働組合において当然に想定されている行動であると考えられるので、やはり「る同組合の行為」と解すべきである(JR東日本ー東京高判平成25年3月27日も参照)。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
182 不利益取扱い(2)-青山会事件
東京高判平成14年2月27日(平成13年(行コ)137号)
要因
事業譲渡の際に、譲渡先の組合員の採用を拒否したことは、不利益取扱いとなるか。
事実
医療法人財団Xは、医療法人財団Aから、Aの経営するB病院の施設、業務を引き継ぎ、平成7年1月1日から、新たにC病院として開設した。この事業引き継ぎに際して、XとAとの間で合意文書が交わされており、そこには、Aの職員をXが雇用するか否かはXの専権事項であるという文言が含まれていた。Xは、B病院の職員(55名)のうち、C病院での採用を希望する者の中から採用面接を行い、平成7年1月1日付けで32名を採用した。Aは平成6年12月31日、B病院の全職員に解雇を通告した。
Xは、DとEが属していた看護科の職員33名については、DとEおよび採用を希望しなかった3名の合計5名について、採用面接を行わず、採用面接をした28名のうち採用を希望しなかった者と労働条件が折り合わなかった者を除く21名を採用した。
さらにXは、採用面接の際に採用を希望しなかった看護科の職員の一部の者に対し、その後C病院開設までの間に、Xの就職するよう改めて説得している反面、看護科に属していたDとEの両名については、両名が採用を希望していたにもかかわらず、採用面接もせず、採用しなかった。DとEは、D病院に唯一存在するF労働問題の組合員であり、組合員は両名以外にはいなかった。
そこで、F組合は、本件不採用は不当労働行為であるとして、G労働委員会に救済申立てをしたところ、Gは不当労働行為と認定した。Xはこれを不服としてY(中央労労働委員会)に再審査を申し立てたところ、Yは再審査申立てを棄却したので、Xは、その命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求を棄却した。そこで、Xは控訴した。
判旨 控訴棄却(Xの請求棄却)
Ⅰ AとXとの間ではAの職員をXが雇用するか否かはXの専権事項であるとされており、XはAの職員の雇用契約上の地位を継承しないとの合意があった。しかしながら、XによるC病院の職員の採用の実態をみると、Xは、実質的にはAの職員の雇用関係を承継したに等しいものになっている。そして、XがDおよびEの両名をことさらに採用の対象から除外したのは、この両名がF組合に所属し、組合活動を行っていたことをXが嫌悪したことによるものである。
Ⅱ XによるB病院の職員のC病院の職員への採用の実態は、新規採用というよりも、雇用関係の承継に等しいものであり、労組法7条1号本文前段が雇入れについて適用があるか否かについて、論ずるまでもなく、本件不採用については、同規定の適用があるものと解すべきである。
B病院の職員の雇用をXの専権事項とする旨の合意は、AとXとがF組合とその構成員であるDとEを排除することを主たる目的としていたものと推認されるのであり、このような目的をもってされた合意は、前記規定の適用を免れるための脱法の手段としてされたものとみるのが相当である。したがって、Xは、このような合意があることをもって、同法7条1号本文前段の適用を免れることはできず、DとEの不採用は、C病院の職員の採用の実態に照らすと、同人らをその従来からの組合活動を嫌悪して解雇したに等しいものというべきであり、本件不採用は、労組法7条1号本文前段の不利益取扱いに該当するものといわざるをえない。
解説
本件の争点は、事業譲渡にともない、多くの従業員の労働契約が承継される一方、労働組合の組合員2名が、承継をきぼうしたにもかかわらず、承継が認められなかったことが不当労働行為となるかである。本件では、譲渡先Xの不当労働行為意思は認められているが、問題は、XによるDらの不採用が、客観的に不当労働行為の要件に該当するかである。判例に照らすと(→【179】JR北海道・日本貨物鉄道事件)、黄犬契約に該当する場合(労組法7条1号後段を)除き、原則として、新規採用の拒否は、不利益取扱いには該当しないとされているからである。
この点について、本判決は、本件の採用の実態は、新規採用というよりも、雇用関係の承継に等しいと判断している(判旨Ⅰ)。そのため、Xが、C病院の職員として、B病院の職員から誰を採用するかをXの専権事項とするAとX間の合意は、新規採用のようなXの広い裁量を前提としたものと解すべきではなく、むしろ、反組合的目的で組合員を排除したもので、実質的には解雇がおこなわれたに等しい判断としている(判旨Ⅱ)。
仮に本件を新規採用の事案とみたとしても、判例のいう「従前の雇用契約関係における不利益な取扱いにあたるなどの特段の事情が認められる場合」(→【179】)にあたるとして、労組法7条1号前段の不利益取扱に該当すると判断できる可能性もあったであろう。なお、民事事件でも、事業譲渡の際に、譲渡元の従業員の労働契約を包括的に承継する合意(黙示のものも含む)があるにもかかわらず、反組合的な理由で、一部の組合員を承継から排除する合意は公序良俗違反として無効(民法90条)と判断されることになろう(→【73】東京日新学園事件)。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
民法90条(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
183 不利益取扱い(3)-西神トラパック事件
東京高判平成11年12月22日(平成11年(行コ)141号)
要因
配転は、どのような場合に不利益取扱いになるか。
事実
紙パックの製造等を業とするX会社には、その従業員で組織されるA労働組合があり、Bはその執行委員長である(平成4年10月以降)X会社は、平成4年10月以降、コスト低減計画の一環として、直接部門における人員削減の方針を示し、余剰人員には、配転もありうるとの見方をしめしたところ、A組合はこれに反発し、労使が真っ向から対立した。なお、A組合は、同年6月にも、経営合理化改革の一環として行われたパートタイム労働者の雇止めをめぐって無期限全面ストライキを行っており、BはA組合の執行副委員長としてストライキを指導していた。
X会社では、紙パックの製造に直接携わる製造部門と機械の保全、据付、改善を行う工務部門とがあり、それぞれ別枠で募集が行われ、工務部門のほうが高い学歴を条件とするなどの違いがあった。
Bは、これまで所属していた工務部門における部署が解散したため、製造部門における機械のオペレーター(専門技術を要しない単純作業)への配転を命じられた。工務部門から製造部門の機会のオペレーターへの配転は、これまで例がなかった。この配転(本社配転)により、Bは、給与等級上はBよりも下にいるチームリーダーの指揮監督を受ける立場に置かれた。
A組合は、本件配転は、不利益取扱いにあたるとして不当労働行為の救済を申し立てた(そのほか、脱退勧奨などが支配介入にあたるとして、救済を申し立てている)。C労働委員会が、救済命令を発したところ、X会社はY(中央労働委員会)に再審査を申し立てた。Yは、配転命令については、不当労働行為の成立を認めなかった。そのため、A組合は、その取消しを求めて訴えを提起した(なお、Yは支配介入の成立は認めたので、X会社は、その部分の取消しを求めて訴えを提起している)。1審は、A組合の請求を認容した。そこで、X会社は控訴した。
判旨 控訴棄却(A組合の請求認容)。
Ⅰ「本件配転が不利益なものといえるか否かは、・・・当該職場における職員制度上の建前や経済的側面のみからこれを判断すべきものではなく、当該職場における従業員の一般的認識に照らしてそれが通常不利益なものと受け止められ、それによって、当該職場における組合員らの組合活動意思が萎縮し、組合活動一般に対して制約的効果が及ぶようなものであるか否かという観点から判断されるべきものというべきである」。
Ⅱ「本件配転が会社側の配転権の濫用により私法上違法、無効とされるものであるか否かの判断がそのまま不当労働行為の成否の判断につながるものでないことはいうまでもないところである。むしろ、仮に会社側に不当労働行為意思がなかったとすれば配転先として別の部門が選ばれたであろうことが認められ、しかも、従業員の一般的認識に照らして、その部門への配転に比して現に選ばれた配転先への配転が不利益なものとうけとめられるものである場合には、そのこと自体からして、当該配転行為について不当労働行為の成立がみとめられるものというべきである」。
解説
労組法7条1号の不利益取扱いに該当する行為として、条文上は、解雇が例示されているだけであり、その他の「不利益な取扱い」に何があたるかは解釈に」ゆだねられている。雇用の喪失、懲戒処分、さらに賃金等の労働条件が明確に低下する措置が不利益取扱いに該当することは、ほぼ異論がない(一方、採用拒否については、→【179】JR北海道・日本貨物鉄道事件)。昇進や昇格における差別的な取扱いも、不利益取扱いの典型例である。配転、出向、転籍等の人事異動についても、不利益取扱いとなりうる。本判決は、配転のケースにおいて、「当該職場における組合員らの組合活動意思が委縮し、組合活動一般に対して制約的効果が及ぶようなものであるか否かという観点からはんだんされるべき」という判断基準を示している(判旨Ⅰ)。
X会社は、本件では、Bが以前に所属していた部署の解散にともなう業務上の必要性がある配転であり、賃金の低下もないことから、不利益取扱いに該当しないと主張したが、本判決は、これを認めなかった。むしろ、本件では、工務部門から製造部門への異動は、これまで例のなかったもので、しかもグレードの低い職種への配転であったこと、また、X会社には、反組合的意図があったことから、不利益取扱いの不当労働行為が成立すると判断された。
判旨Ⅱは、不当労働行為の成否は、使用者の処分や措置の私法上の有効性とは別に判断されるべきものであることを示したもので、妥当なものであろう。
なお、有利な取扱いであるはずの栄転であっても、組合活動に支障が出るような場合であれば、組合活動に対する不利益取扱いとして、不当労働行為の成立が認められる。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
184 職制の発言と支配介入-JR東海[新幹線・科長脱退勧奨]事件
最2小判平成18年12月8日(平成16年(行ヒ)50号)
要因
下級職制の脱退勧奨は、どのような場合に使用者に帰責される支配介入が成立するか。
事実
X会社のT運転所には、現場長である所長の下に、所長を補佐する現場責任者として助役が配置されていた。各科に所属する助役の中から指定された科長が、各科に所属する助役の責任者として、助役の業務をとりまとめ、必要に応じて他の助役に指示を与えていた。所長以外は、組合員資格を有していた。
X会社には、X会社と協調的なA労働組合があったが、上部団体への加盟やストライキ権の確立をめぐりA組合の内部で対立が生じ、平成3年8月、A組合の委員長であったBは、脱退して新たにC労働組合を結成した。A組合の組合員数は約1万4600名、C組合の組合員数は約1200名であった。しかし、B委員長の出身であるT運転所区域では、A組合の組合員数は約100名、C組合の組合員数は283名であった。
そのような状況のなか、平成3年8月19日ころ、D科長は。C組合の書記長であるEらと居酒屋で飲食した際、Eに対し、A組合とC組合との組合員数の割合について、「何とかフィフティーフィフティーにならない者か」と述べたり、「会社による誘導をのんでくれ」という発言を拒否したEに対して、「もし、そういうことだったら、あなたは本当に職場にいられなくなるよ」等の発言を(本件発言)を」行った。また、同月22日には、D科長がC組合の組合員であるFの自宅に電話をし、脱退勧奨をする発言をした。
C組合は、G労働委員会に対し、D科長の発言は支配介入の不当労働行為であるとして救済申立てを行ったが、Gは救済申立てを棄却した。C組合は、Y(中央労働委員会)に対して再審査の申立てをしたところ、Yは不当労働行為の成立を認め、救済命令(ポストノーティス)を発した。」そこで、X会社は、Yの命令取消しを求めて訴えを提起した。1審はYの救済命令を適法としたが、原審はYの救済命令を取り消した。そこで、Yは上告した。なお、差戻審では、X会社の控訴は棄却されている。
判旨 原判決破棄、差戻し。
Ⅰ「労働組合法2条1号所定の使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合には、使用者との間で具体的な意思の連絡がなくとも、当該支配介入をもって使用者の不当労働行為と評価することができるものである」。
Ⅱ T運転所の助役は、組合員資格を有し、使用者の利益代表とはされていないが、現場長である所長を補佐する立場にある者であり、特に課長は、各科に所属する助役の中の責任者として他の助役の業務をとりまとめ、必要に応じて他の助役に指示を与える業務を行っていたというのであるから、D科長は、使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にあった。A組合から脱退した者らがC組合を結成し、両者が対立する状況において、X会社は労使協調路線を維持しようとするA組合に対して好意的であったところ、D科長によるEおよびFに対する働き掛けが去れた時期は組合分裂が起きた直であり、D科長の働き掛けがA組合の組合活動として行われ側面を否定できないとしても、本件発言には、X会社の意向に沿って上司としての立場からされた発言と見ざるをえないものが含まれている。
Ⅲ 以上のような事情のもとでは、D科長の本件発言は、A組合の組合員としての発言であるとか、相手方との個人的な関係からの発言であることが明らかであるなどの特段の事情がないかぎり、X会社の意を体してされたものと認めるのがそうとうである。そして、そのように認められるのであれば、D科長の本件発言は、X会社の不当労働行為と評価できる。
解説
下級職制による言動(特に、脱退勧奨)が不当労働行為に該当するためには、その行為が使用者に帰責できるものでなければならない。使用者との間での具体的な意思の連絡が認定できれば、使用者に帰責することができるが、そのような事実が認定できない場合に問題となる。この点について、本判決は、「使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にある者が使用者の意を体して労働組合に対する支配介入を行った場合」には使用者に帰責されるとする(判旨Ⅰ)。利益代表者(労組法2条ただし書1号)への該当性は、不当労働行為における使用者の帰責性と直接的には関係しないものであるが、これに該当する者の行為は、それだけで原則として使用さhの意を体したものと推認してよいであろう。他方、本判決によると、利益代表はに該当しないが、これに近接する者の行為は、使用者の意を体したものと認定されれば、具体的な意思の連絡がなくとも、使用者に帰責されることになる。
本件では、発言主体であるDは、使用者の利益代表者に近接する職制上の地位にあり、使用者の意向に沿った発言をしていた(判旨Ⅱ)。一方でDは、対立する組合(使用者とは協調関係)の組合員であるので、組合員としての発言であるとか、あるいは、個人的な発言であるという場合には、意を体したものとは判断されないが、そのような特段の事情が認められないかぎり、その発言は使用者に帰責されることになる(判旨Ⅲ)。差戻審では、特段の事情はないと判断された)。会社と協調的な関係にある組合の組合員でもある下級職制が、ライバル組合にある組合の組合員である下級職制が、ライバル組合の組合員を引き抜こうとする行為は、組合の組織拡大というよりも、使用者の意を体した脱退勧奨行為と判断されやすいということであろう。
労働組合法2条1号 (労働組合)
第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
三 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
185 ビラの撤去と支配介入-JR東海事件
東京高判平成19年8月28日(平成18年(行コ)155号)
要因
組合掲示板の掲示物の撤去は支配介入に該当するか。
事実
X会社と、その従業員で組織されるA労働組合との間には、労働協約が締結されており、そこには組合との間には、労働協約が締結されており、そこには組合掲示板に関して「掲示板は、組合活動の運営に必要なものとする。また、掲示類は、会社の信用を傷つけ、政治活動を目的とし、個人を誹謗し、事実に反し、または職場規律を乱すものであってはならない」(228条)、「会社は、A組合が前2条の規定に違反した場合は、掲示類を撤去し、掲示場所の使用の許可を取り消すことができる」(229条)という規定が含まれていた。
X会社は、平成7年7月から同8年5月にかけて、A組合およびB分会は、この撤去行為は支配介入の不当労働行為に該当するとして、C労働委員会に救済をもうしたてたところ、Cは14点すべてについて不当労働行為の成立を認め、X会社に謝罪文の交付を命じた。そこで、X会社はY(国・中央労働委員会)に再審査を申し立てたところ、Yは11点の掲示物について、不当労働行為が成立すると判断した。そこで、X会社は、この命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審は、2点の掲示物の撤去についてのみ不当労働行為の成立を認めた。そこで、X会社おおびYがともに控訴した。
なお、本判決に対して、X会社は上告したが、最高裁は上告棄却・不受理の決定をしている。
判旨 X会社の請求の一部認容(9点の掲示物の撤去について、不当労働行為が認められた)。
Ⅰ 掲示物の撤去が不当労働行為に該当するか否かの判断に際しては、労働協約の定める撤去要件に該当するか否かをまずけんとうすべきであり、「X会社が撤去要件に該当しない掲示物を撤去した場合には、組合活動に対する支配介入として不当労働行為に当たるというべきである」。
Ⅱ「掲示物の記載内容の一部が形式的に上記各要件に該当するとみられる場合であっても、そのことの一事をもって当該掲示物全体として、上記撤去要件を充足するものというべきではなく、A組合らの正当な組合活動として許容される範囲を逸脱し、会社の運営等に支障を与え、あるいは個人の名誉を著しく傷つけたか否か等々について、その内容、程度、記載内容の真実性等の事情が実質的かつ総合的に検討されるべきであり、その結果、当該掲示物が不可分一体のものである限り、全体としても、A組合らの正当な組合活動として許容される範囲を逸脱していないと認められる場合には、X会社の掲示物の撤去が実質的に組合活動に対する妨害行為として不当労働行為(支配介入)に該当するというべきである」。
Ⅲ 「当該掲示物の掲示がA組合らの正当な組合活動として許容される範囲を逸脱したか否かを検討するに当たっては、まず、当該掲示物が掲示された当時の会社と組合との全体もしくは職場での労使関係の状況、掲示物が掲示された経緯に加え、掲示物の記載内容が会社の安定性、顧客へのサービスその他の会社の中心的業務自体の信用に関わる性質のものか、社外の第三者又は社旗全般との関係において問題となる性質のものか、社外の第三者又は社会全般との関係において問題となる性質のものか、会社内職員の信用、名誉に関わるものか、当該記載内容が上記の信用又は名誉をどの程度侵害するものか等々の具体的な事情が考慮されるべきである。
次に、上記の判断に当たっては、掲示物は掲示板を日常的に使用する組合組織により掲示されるものであるところ、その文書作成主体と性質如何により、掲示板の設置される場所がどのような場所であり、掲示物の対象たる読者が主としてそのような者が等の具体的な事情も、軽視しがたい要素として、勘案考慮されるべきである」。
解説
労働組合が、使用者の許諾なしに、企業施設に組合ビラ等の掲示物を貼付した場合、使用者がその撤去を求めることができるかは、組合の企業施設の利用権限の有無にかかわっており、受忍義務説と違法性阻却説とでは結論を異にする。前者においては組合に利用権限が認められうるのに対して、後者では利用権限自体は否定されることになる。また、判例の許諾説の立場においても、利用権限は否定される(→【171】国鉄札幌運転区事件)。もっとも、支配介入の成立の可能性については、こうした私法上の利用権限の問題とは別に、当該労使関係における妥当性を考慮に入れるべきであり、組合側に使用権原がなくても、場合によっては使用者の撤去行為が支配介入の不当労働行為(労組法7条3号)に該当する可能性もある。
本件は、労働協約上、労働組合には掲示物を掲示する権限が与えられていたものの、使用者には撤去県も留保されていたという事案である。本判決は、撤去要件を具備している場合には、撤去は不当労働行為に該当しないとしている(判旨Ⅰ)。この点については、より実質的に労使関係における妥当性を考慮しうる判断枠組みほうが適切であるといえるが、判旨Ⅱおよび判旨Ⅲでは、撤去要件の該当性の判断のところで、労使関係面の考慮を組み入れることのできる柔軟な判断基準を設けており、その結論も含め妥当なものと評価することができる。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
186 支配介入と不当労働行為の意思-日本アイ・ビー・エム事件
東京高判平成17年2月24日(平成15年(行コ)275号)
要因
不当労働行為意思は支配介入の成立要件か。
事実
X労働組合とA会社との間の労働協約には、「ライン専門職および専任の✕✕✕部員以上のスタッフ専門職は非組合員とする」という条項があった。これは、昭和57年に、送信昇格差別を契機とする紛争をめぐり、中央労働委員会の関与下での和解の際に確認書として交わされたものであった。ところが、X組合は、A会社に対して、この条約の解約(協約の一部解約)を通告した(平成4年5月27日)。90日経過後に、一部解約の効力が生じた(労組法15条4項参照)として、専任以上のスタッフ専門職であったB,C,Dの3名がX組合に加入した。
X会社は、一部解約は無効であるとして、Bらの組合員資格を認めず、X組合が申請したBら3名の組合費のチェック・オフを拒否した。また、Bの分会執行委員就任の撤回と役員名簿の訂正を求め、Cに対し「上級管理職としての職務と責任に反するような活動を行った場合は相応の処分を行う」と通告し、Dに対し「ストライキに参加すると処分の対象になりうる」と通告した。
X組合とその上部団体は、A会社のこれらの行為が不当労働行為にあたるとして、Bら3名とともにY労働委員会に救済を申し立てたところ、Yは、これらの行為はいずれも不当労働行為にあたらないとして申立てを棄却する命令を発した。そこで、X組合らは、この命令の取消しを求めて、訴えを提起した。1審は、A会社の各行為が不当労働行為に当たると判断して命令を取り消し、請求を認容した。そこで、Yは控訴した。
判旨 原判決取消し(X組合らの請求棄却)。
「労組法7条3号にいう支配介入の不当労働行為が成立するためには、使用者側に主体的要件すなわち不当労働行為意思が存することを要するというべきであるが、この不当労働行為意思とは、直接に組合弱体化ないし具体的反組合的行為に向けられた積極的意図であることを要せず、その行為が客観的に組合弱体化ないし反組合的な結果を生じるおそれがあることの認識、認容があれば足りると解すれべきである。そして、不当労働行為に該当するか否かは、その行為自体の内容、程度、時期のみではなく、問題となる行為が発生する前後の労使関係の実情、使用者、行為者、組合、労働者の認識等を総合して判断すべきものである」。
解説
不当労働行為意思という主観的要件が、支配介入の成立に必要であるかどうかについては、学説上、議論がある。判例には、使用者の発言により、「組合の運営に対し影響を及ぼした事実がある以上、たとえ、発言者にこの点につき主観的認識にいたる目的がなかったとしても、なお、労働組合法7条3号に言う組合の運営に対する介入があった」と述べて、不当労働行為意思を不要にとするかのようにみえるものもある(山崎内燃事件ー最2小判昭和29年5月28日)。もっとも、併存組合状況下での組合間差別の事案で、組合嫌悪の意図に言及して支配介入を認めた判例もある(→【191】日産自動車(残業差別)事件、【192】日産自動車(組合事務所)事件)。
本判決も、支配介入の成立には、不当労働行為意思を必要とすると明言した上で、本件では、不当労働行為意思は認められないと判断したものである。
本件では、組合員の範囲を定めている条項のX組合による解約(一部解約)が認めれれてるかが前提問題として争われているが、本判決は、「その条項の労働協約の中での独立性の程度、その条項が定める事項の性質をも考慮したとき、契約締結後の予期せぬ事情変更によりその条項を維持することができなくなり、又は、これを維持させることが客観的に著しく妥当性を欠くに至っているいるか否か、その合意解約のための十分な交渉を経たが相手方の同意が得られず、しかも協約全体の解約よりも労使関係上相当な手段であるか否かを総合的に考え合わせて、例外的に協約の一部の解約が許される場合があるとするのが相当である」という一般論を述べて、(→【157】ソニー事件)、本件の非組合員の範囲を定める条項は、締結されてから約10年が経ち、組合組織の再編により、合理性が低下しているなどの事情を考慮して、一部解約を有効と判断している(判旨外)。
ただし、本判決は、本件の一部解約の有効性は、法律専門家にとっても微妙な判断となることを考えると、A会社が同条項の一微解約を無効と考えるのも無理からぬものがあり、本件のA組合側の発言はいずれも、一部解約を否定するA会社の意見を敷衍したにすぎないものであるし、チェック・オフの拒否もBらの組合員資格に疑義をいだいていたからというのであるから、A会社には、不当労働行為意思は認められないと判断した(判旨外)。
労組法15条4項(労働協約の期間)
第15条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
187 使用者の言論と支配介入-プリマハム事件
東京地判昭和51年5月21日(昭和49年(行ウ)128号)
要因
団体交渉決裂直後に発表された、労働組合の態度を批判する内容の社長声明文の発表は支配介入に該当するか。
事実
X会社は食肉の加工製造・販売を目的とする会社であり、A労働組合はその従業員で組織されている。昭和47年3月13日、A組合はX会社に対し、昭和47年度の賃金引上げや一時金等に関する要求を提出し、団体交渉を重ねたところ、同年4月15日の中央交渉においてX会社は組合員一人当たり平均1万1145円の賃金増額を回答した。X会社は、これをもって最終回答であるとの態度を明らかにしたので、A組合は団体交渉の決裂を宣言したが、決裂後も団体交渉の後も団体交渉を継続する意思があることを会社に表明し、現実にその後も5回にわたり団体交渉が行われた。
同年4月17日、X会社は、社長名において、声明文を会社の全事業所に一斉に掲示した。
「従業員の皆さん、本年の賃上げ交渉も大変不幸な結果になってしまいました。・・・・本年度の皆さんの要求に対しては、支払能力を度外視して労働問題として解決すべく会社は、素っ裸になって金額においては、妥結した同業他社と同額を、その他の条件については、相当上回る条件を、4月15日提示しました。これは、速やかに妥結して、今後は、会社と従業員の皆さんが一体となって生産に、販売に協力して支払資源を生み出す以外に、X会社の存続はあり得ないと判断したからであります。ところが組合幹部の皆さんは会社の誠意をどう評価されたのか判りませんが、断交決裂を宣言してきました。これはとりもなおさず、ストライキを決行することだと思います。私にはどうもストのためのストを行わんとする姿にしか写ってこないのは、甚だ遺憾であります。会社も現在以上の回答を出すことは絶対不可能でありますんので、重大な決意をせざるをえません。・・・・」
この声明文が出た後、A組合の内部でストライキに反対する声が高まり、同月27日に行われたストライキでは組合本部よりストライキ実施の指令を受けた約2000名の組合員のうち、193名はストライキに参加しなかった(前年の賃上げ闘争のときのストライキでは脱落者はでなかった)。A組合はストライキにおいて脱落者が相当数出たため、翌28日、ストライキを中止することを決定した。
A組合は、B労働委員会に対して、本件社長声明文の掲示は、支配介入に該当するとして、不当労働行為の救済を申し立てたところ、Bはこれを認めた。X会社はY(中央労働委員会)に再審査を申し立てたが、Yは、支配介入の成立を認めて、「X会社は、今後。このような行為を繰り返してはならない」という命令を発した。X会社は、この命令の取消しを求めて訴えを提起した。本判決に対して、X会社は、控訴したが、控訴審は、本判決を引用して棄却し、その上告も棄却された(最2小判昭和57年9月10日)。
判旨 請求棄却。
「およそ使用者だからといって憲法21条に掲げる言論の自由が否定されるいわれがないことはもちろんであるが、憲法28条の団結権を侵害してはならないという制約をうけることを免れず、使用者の言論が組合の結成、運営に対する支配介入にわたる場合は不当労働行為として禁止の対象となると解すべきである。これを具体的にいえば、組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し、当該言論が組合員に対し、威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に影響を及ぼすような場合は、支配介入となるというべきである」。
解説
使用者の言論が支配介入の不当労働行為に該当するかについては、大きく分けて2つの考え方がある。
1つは、使用者の反組合的発言は、組合の結成・運営に影響を与える可能性があれば、およそ支配介入となりうるとするもの、
もう1つは、使用者の発言は原則として支配介入とはならないが、報復や暴力の威嚇または利益供与を示唆している場合には支配介入となるとするものである。
判例は、本判決も含め、後者の立場であるといえよう。たとえば、ある判決は、社長が、ある工場の労働組合が企業連に加入したことを非難し、脱退しなければ人員整理もありうると発言したことについて支配介入と認めている(山岡内燃機事件ー最2小判昭和29年5月29日)。
本判決は、本件声明文は従業員を対象とするとはいえ、ユニオン・ショップ制が協定されているので組合員を対象としたものと認められること、「重大な決意」というような威嚇的効果をもつ表現を使って、ストライキを牽制する内容をであること、全事業所に一斉に掲示されるていること、団体交渉決裂の直後に発表されたものであること、会社の最高責任者である社長名義のものであること、A組合内部の執行部の方針に批判的な勢力を勇気づけて、初めてスト脱落者をもたらしたこと、という事情を総合的に考慮して、本件声明文は、「ストライキをいつどのような方法で行うか等という、組合が自主的に判断して行動すべきいわゆる組合の内部運営に対する支配介入行為にあたる」と判断した(判旨外。最近の否定例として、JR東日本事件ー東京高判平成26年9月25日)。
憲法21条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
188 大量観察方式-紅屋商事事件
最2小判昭和61年1月24日(昭和55年(行ツ)40号)
要因
組合員に対する査定差別は、どのように認定すべきか。
事実
X会社には、A労働組合とB労働組合があった。X会社の昭和50年度夏季賞与は、両組合と妥結し、支給されているが、支給額の算出方法は、いずれも「基本給×成果比例配分率×人事考課率×出勤率」という算式によるものであった。
昭和50年度夏季賞与における人事考課率(百分率)は、50から130の範囲内で定められていたが、A組合員は、最低の50が最も多く、最高でも80であり、その平均は58であるのに対し、B組合員については、最低の者でもA組合員の最高の者より高い90であり、その平均は101であった。また、同年度冬季賞与における人事考課率は、A組合員の平均は79であるのに対し、B組合員と非組合員については、その大半がA組合員の最高である100以上の評価を得ており、その平均は101であった。
X会社は、A組合がその結成を同社に通知して公然化した直後から、A組合を嫌悪し、A組合員とB組合員とを差別する行動を繰り返した。
A組合結成前の昭和49年度夏季と冬期の各賞与における人事考課率を、昭和50年度各賞与支給当時のA組合員とB組合員とに分けて、その平均を比較すると、昭和49年度各賞与については101と102であり、同年度冬季賞与につては91と92であった。
昭和50年度夏季賞与の考課期間の後にA組合を脱退して非組合員またはB組合員となった労働者の平均人事考課率は59で、その当時のA組合員全員の平均人事考課率58とほとんど差がなかったのに対して、同年度冬期賞与におけるそれは96となり、その当時のA組合員の平均人事考課率79と比べても17もの差が生じている反面、従来からB組合員または非組合員であった者の平均人事考課率101との差は、わずかに5となった。なお、昭和50年度各賞与の考課期間におけるA組合員の平均出勤率は93.4%4であって、B組合員の平均出勤率89.1%を上回っている。
事実
A組合は、人事考課率の格差は、不利益取扱いにあたるとして、C労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てをしたところ、Cはこれを認めて救済命令を発した。X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査を申し立てたが、Yはこれを棄却した。そこで、X会社は、その取消しを求めて訴えを提起した。1審はX会社の請求を棄却し、原審はX会社の控訴を棄却した。そこで、X会社は上告した。
判旨
A組合員らとそれ以外の者らとの勤務成績等に全体として差異がなかったものというべきである。他方、本件各賞与における人事考課率をA組合員らとそれ以外の者らとの間で比較してみると、その間に全体として顕著な差異の生じていることが明らかである。そして、これらの事実にA組合が結成されこれが公然化した後、X会社においてA組合員とB組合員と差別する行動を繰り返していること、A組合を脱退して非組合員やB組合員となった者らの平均人事考課率がにわかに上昇していることなどの事実を併せて考えると、A組合員らとそれ以外の者らとの間に生じている差異は、X会社においてA組合員らの人事考課率をその組合所属を理由として低く査定した結果しょうじたものとみるほかない。
解説
賃下げ、一時金の支給、昇格等において、査定が必要な役割を示すことが多いが、その査定において組合員差別があったときには、不当労働行為となる。しかし、このような査定差別の立証は、個々の組合員ごとに、」労働組合側が行わなければならず、それはかなり難しいものとなることが多い。
そこで労働委員会の実務では、「大量観察方式」という審理方式を採用し、実質的に、労働者側の立証の負担を緩和させる試みが行われてきた。この方式によると、労働者側が差別の外形的な立証(すなわち、同期・同学歴・同職種のグループの他の者と比較して、査定が全体的に低位であること、および、使用者の当該組合に対する嫌悪についても立証)がなされなければ、不当労働行為の一応の推定が求められ、逆に、使用者のほうが、当該格差に個々の組合員らの勤務成績等に基づく合理的な理由が存否することを個別的に立証しなければならない。本判決は、こうした大量観察方式を肯定したものとみることができよう。
ただ、この手法は、本件のように、差別されたと主張する組合員と比較される集団との間に全体として同質性がある場合にのみ利用できるものであり、そうでない場合には、組合員個人が他の集団の構成員と能力や勤務実績が同等であることも、労働者側において、入手可能な資料の範囲で立証をすることが必要となる(オリエンタルモータース事件―東京高判平成15年12月17日。
さらに、JR東日本事件ー最1小判平成24年2月23日も参照)。なお、差別されたと主張する側の人数が僅少でも、勤務成績等が特に劣っていなければ、この手法を用いることができる(昭和シェル石油事件ー東京高判平成22年5月13日)。また、勤務成績の差が従前の労使関係に起因するものであれば、その差を考慮して集団間の同質性を否定してはならない(シナン学園事件ー東京高判平成26年4月23日)。
189 会社解散-東京書院事件
東京地判昭和48年6月28日(昭和47年(行ウ)6号)
要因
解散した会社に対して、救済命令を発することができるか。
事実
X会社は、従業員9名を雇用している出版会社である。昭和43年6月19日、従業員Aら6名が、会社運営の刷新と従業員の待遇改善を等を含む13項目の建議書をX会社の会長Bに手交し、労働組合結成の意思を明示したところ、B会長は、これに反発して、労働組合の結成を阻止するために全従業員に対して解雇の通告をした。X会社は、同年5月、6月いことは経営不振であったが、急に事業を中止するほどの状況ではなかった。その後、同年6月24日、Aらは労働組合を結成し、団体交渉を申し込んだが、B会長はこれに応じなかった。X会社は、同年7月15日に解散を決議し、同月30日に解散登記を行い、B会長が清算人となって清算手続に入った。
Aらは、C労働委員会に、不当労働行為の救済を申し立てたところ、Cは不当労働行為の成立を認めて、X会社に対して、原職復帰とバックペイを命じた。X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査を申し立てたが、Yは申立てを棄却した。そこで、X会社は、その取消しを求めて、訴えを提起した。なお、本判決に対しては、X会社から控訴がなされているが、控訴審は本判決を引用して控訴を棄却している。上告審でも、上告は棄却されている。
判旨 請求棄却。
Ⅰ X会社の解雇通知は、労働組合結成の意思を明示したことに反発し、労働組合の結成を阻止するために、経営不振に籍口してなされたものと推認するほかはないので、当組法7条1号、3号違反の不当労働行為に該当するものである。また、X会社の団体交渉拒否には、正当な理由がないと認めざるをえない。
Ⅱ「不当労働行為たる解雇に対して与えられる労働委員会の救済命令は、その不当労働行為によって生じた結果を排除し、当該解雇がなかったのと同一の状態を回復させること(事 実状態の原状回復)を本来の使命とするものであるとともに、その限度にとどまるべきものであるから、不当解雇がなされた後に被解雇者の従業員たる地位(その解雇がなかったとしての)に何等か変動を及ぼすような事実、たとえば、適法な解雇或いは雇用契約の合意解約の事実が生じているときは、その救済命令の内容は、被解雇者が後の解雇或は、雇用契約の合意解約の日まで従業員たる地位にあったものとして取り扱うべきことを使用者に命ずるをもって足り、且つその限度にとどまるべきものと解するのが相当である。
しかるにX会社は、Yが本件命令を発した時点において前示のごとくX会社の清算手続中であり、積極財産は皆無であるということのみを主張するにとどまり、被解雇者たるAらに対し、その地位の変動を生ぜしめる何等かの措置をとったということにつき、何等主張立証しないのであるから、本件命令(原職復帰等)の履行は、法律上は勿論事実上も未だ不能であると称し得ず、本件命令につき、被救済利益が喪失したものとは認められない」。
解説
使用者が労働組合の結成等を嫌悪して、それを阻止したり、潰減させたりするために、会社を解散し、従業員を全員解雇したような場合に、不当労働行為が成立するのか、また仮に不当労働行為が成立したとしても、どのような救済方法があるのか、という点は、使用者尾4経済活動の自由(憲法22条1項、29条)との関係で問題となる。
会社解散が不当労働行為に該当することがあるかについては、企業の廃止は憲法の保障する経済活動の自由の一環であるので、これを制限することはできず、会社解散にともなう解雇は不当労働行為になり得ないという考え方もあるうる。しかし、通説は、会社解散の場合でも、それが組合壊滅という反組合的な目的で行われたものである以上、不当労働行為になりうると解しており、本判決も、同じ立場である。もっとも、不当労働行為が成立するとしても、救済命令として、操業継続命令や事業再開命令等を出すことまではできないと解されている。企業の経済活動の自由を、そこまで制限することは適切でないからである。
したがって、救済命令の内容としては、本件のように、原職復帰とバックペイとなるのであり、原職復帰は精算手続の終了により合法的な解雇がなされるまでのものになる。逆にいうと、清算手続の継続中は、雇用存続の可能性があるので、その範囲であれば、労働委員会は原職復帰の命令を出すことができるということである。
なお、会社解散には、形式的に解散をするが、実質的に同一の事業を別の会社で継続するという偽装解散もある。偽装解散の場合には、それが組合の壊滅を目的とした不当労働行為であると判断される場合には、実際上の同一企業に対して、従業員としての取扱いとバックペイを命じることができると解されている。なお、民事事件であれば、法人格否認の法理を適用できるような場合でないかぎり(→【16】第一交通産業ほか(佐野第一交通)事件)、別会社との間で労働契約関係の存続を認めることは難しいが、行政救済では、私法上の法理には必ずしも縛られずに、実際に則した柔軟な救済が可能となる。
労組法7条1号・3号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
憲法22条1項〔居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
憲法29条〔財産権〕
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
190 併存組合間の一時金差別-日本メールオーダー事件
最2小判昭和59年5月29日(昭和50年(行ツ)77号・78号)(民集38巻7号802頁)
要因
併存組合双方に生産性向上に協力するという差し違え条件を提示して、これを受け入れない労働組合に年末一時金を支給しないことは不当労働行為になるか。
事実
X会社の(従業員数230余名)には、A労働組合とB労働組合とが併存しており、組合員数はA労働組合が120名以上、B組合が20名余であった。X会社は、昭和47年の年末一時金の交渉において、当初は基本給の3.71か月分とする回答をしていたが、組合側の要求を受けて、基本給の3.77か月分とするかわり、「生産性の向上に協力すること」という前提条件を付けた。A組合はこれに応じたため労働協約が成立し、A組合の組合員と非組合員には年末一時金が支給された。ところが、B組合にもA組合と同一の前提条件を付けて同一の回答をしたところ、B組合は前提条件について、拒否の態度をとった。X会社は、年末一時金の支給と前提条件とは不可分一体であると主張し、年末一時金について交渉が妥妥結するに至らなかったので、B組合の組合員には一時金を支給しなかった。
そこで、B組合は、X会社がB組合にとって同意できない前提条件に固執して年末一時金を支給しないのは、B組合の組合員に対する不利益取扱いであるとし、B組合毛の支配介入であるとしでY労働委員会に救済申立てをし、Yは救済命令を発した。X会社はその取消しを求めて訴えを提起したところ、1審は請求を棄却したが、原審は、本件前提条件は、従業員の多数を占めるA組合が同意しており、その内容にも合理性があるのであり、B組合がそれに同意しないために一時金の支給を受けられないのは、B組合の自由意思により選択の結果にほかならないとして、不当労働行為の成立を否定した(東京高判昭和50年5月28日)。そこで、Yは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(X会社の請求棄却)。
B組合が本件前提条件の受諾を拒絶して団体交渉を決裂させて、B組合の組合員が一時金の支給を受けることができなくなったことについては、X会社がB組合の受け入れることのできないような合理性のない前提条件を、B組合が受諾しないであろうことを予測しえたにもかかわらずあえて提案し、これに固執しとことに原因があるといわなければならず、B組合の前提条件受託拒否の態度は理由のないものではない。
A組合が一時金について労働協約を成立させたのに、B組合が労働協約を成立させないとなれば、両組合所属の組合員の間に一時金の支給につき差異が生じるのは、当然の成り行きであり、B組合が少数派組合であることからすると、B組合の組合員が一時金の支給を受けられないことになれば、同組合員らの間に動揺をきたし、そのことがB組合の組織力に少なからぬ影響を及ぼし、ひいてはその弱体化をきたすであろうことは、容易に予想しうることであった。そうすると、X会社が前提条件にあえて固執したことは、B組合の組織を弱体化させようとの意図の下に行われたものであり、労契法7条1号および3号の不当労働行為を構成する。
解説
本件では、併存組合下において、一時金交渉の際に同一の前提条件(差し違え条件)を提示し、多数組合がこれを受託したためにその組合員には一時金が支給され、少数組合がこれを受託しなかったためにその組合員には一時金が支給されなかったのが不当労働行為となるかが争点となった。原審は、前提条件には合理性があること、および、多数組合が受諾していることを重視し、前提条件の受諾を拒絶して一時金の支給の前提となる労働協約が成立しなかったのは、B組合の自由な意思決定の結果であるとした。」これに対して、最高裁は、生産性の向上という前提条件の内容は抽象的であり、労働強化につながるなどの疑念を生じさせるにもかかわらず、X会社がその内容について十分な説明をしていないことを考慮して、B組合が前提条件を受諾しないのにも無理からぬところがあるとしている。X会社は、合理性のない前提条件に固執し、その結果、一時金の支給に差異が出てB組合が弱体化することは容易に予想しうるとして、そこに反組合的意図を認めている(判旨外)。
同一の前提条件の提示は、両組合に対する中立的な取扱いなので、そのことだけをみれば問題はなさそうであるが、一方の組合にとって受諾しにくいことをわかっていてそれに固執するということになれば、その行為は不当労働行為となりうるということである(→【191】日産自動車(残業問題)事件)。
その後、同一の合理的な前提条件を提示している場合には、一方の労働組合がその条件を受け入れないことを理由に不利益を受けたとしても、不当労働行為は成立しないと判断する最高裁判決もでている(一時金支給に関して、広島・4ときわタクシー事件ー最3小判平成6年10月25日、時間外労働に関して、高知県観光事件ー最2小判平成7年4月14日)。
労組法7条1号・3号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
191 併存組合間の残業差別-日産自動車(残業問題)事件
最3小判昭和60年4月23日(昭和53年(行ツ)40号)(民集39巻3号730頁)
要因
併存組合のうちの一方の労働組合に対してのみ残業を命じないことは支配介入に該当するか。
事実
昭和41年8月にA会社を吸収合併したX会社には、B労働組合とC労働組合があった。C組合は、かねてから深夜勤務に反対していたところ、同42年2月から、X会社は、C組合対して何ら申入れ等を行うことなく、B組合とのみ協議しただけで、昼夜二交代の勤務体制と計画残業方式を導入した。それ以来、B組合の組合員のみを交替勤務に組み入れ、かつ、残業(時間外勤務と休日勤務)をさせ、一方、C組合の組合員には、一方的に早番のみの勤務に組み入れ、残業をいっさい命じなかった。C組合は、同年6月、C組合の組合員にも残業させるようX会社に申し入れ、団体交渉を行ったが、X会社は、交代制勤務と計画残業という勤務体制に服すべきと主張し、他方、C組合は交代制にともなう夜間勤務に反対すると主張し、妥結をみなかった。
C組合とその上部団体は、X会社がC組合の組合員に対し残業を令じないことは不当労働行為であるとして、D労働委員会に救済申立てをしたところ、Dは救済命令を発した。X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査の申立てをするとともに、C組合との間で残業問題に関する団体交渉を行ったが、合意には至らなかった。その後、Yは再審査を棄却する命令を発した。X会社は、その取消しを求めて訴えを提起したところ、1審はX会社の請求を認めたが、原審は1審判決を取り消した。そこで、X会社は上告した。
判旨 上告棄却(X会社の請求棄却)。
Ⅰ「複数組合併存下にあっては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務付けられているといわなければならず、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で、使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、格組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されない」。
Ⅱ「使用者において複数の併存組合に対し、ほぼ同一時期に同一内容の労働条件についての提示を行い、それぞれに団体交渉を行った結果、従業員の圧倒的多数を擁する組合との間に一定の条件で合意が成立するに至ったが、少数派組合との間では意見の対立点がなお大きいという場面に、使用者が、右多数派組合との間で合意に達した労働条件で少数派組合とも妥結しようとするのは自然の成り行きというべきであって、少数派組合に対し、右条件を受諾するよう求め、これをもって譲歩の限度とする強い態度を示したとしても、そのことから直ちに使用者の交渉態度に非難すべきものがあるとすることはできない」。
Ⅲ「団体交渉の場面においてみるならば、合理的、合目的的な取引活動とみられうべき使用者の態度であっても、当該交渉事項については既に当該組合に対する団結権の否認ないし同組合に対する嫌悪の意図が決定的動機となって行われた行為があり、当該団体交渉がそのような既成事実を維持するために形式的に行われているものと認められる特段の事情がある場合には、右団体交渉の結果としてとられている使用者の行為についても労組法7条3号の不当労働行為が成立するものとかいするのが相当である。
解説
本件では、併存組合下において、多数組合の同意した条件での残業に少数組合が同意しなかったために、使用者が少数組合の組合員に残業を命じなかったことが支配介入の不当労働行為となるかが争点となった。
使用者は、各組合に対して中立保持義務が課されていることからすると(判旨Ⅰ)、自らに協力的な組合と敵対的な組合があったときに、前者のみを優遇して、後者を冷遇するということは許されない。とはいえ、使用者は、同一の労働条件での残業をするよう申し入れているので、それを受諾するかどうかは各組合がそれぞれの方針や状況判断に基づいて決定できることであるから、各組合が異なる選択をしたために結果に差異がでたとしても、不当労働行為の問題は生じないともいえる。また、各組合の使用者に対する交渉力に大小の差異があれば、使用者が各組合との団体交渉において、それぞれの交渉力に対応してその態度を決することは是認しなければならない(判旨Ⅱを参照)。
ただし、「当該交渉事項については、既に、当該組合に対する団結権の否認ないし同組合に対する嫌悪の意図が決定的動機となって行われた行為であり、当該団体交渉がそのような既成事実を維持するために形式的に行われているものと認められる特段の事情がある場合には」、支配介入の不当労働行為が成立する(判旨Ⅲ)。本件では、昼夜二交代の勤務体制および計画残業方式について、深夜勤務に反対してきたC組合とは何も協議せずに、B組合との協議だけで導入を実施し、その後のC組合との団体交渉も確実には行われていなかったということから、支配介入の成立が認められた。
労組法7条3号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
192 併存組合間の便宜供与差別-日産自動車(組合事務所)事件
最2小判昭和62年5月8日(昭和57年(行ツ)50号)
要因
併存組合のうちの一方の労働組合のみ組合事務所を貸与しないことは、不当労働行為となるか。
事実
昭和40年当時、A会社には、B労働組合C支部が存在し、同支部はA会社から、組合事務所と掲示板の貸与をうけていた。同41年2月、3月に臨時大会が開催され、C支部はB組合から脱退することになり、D組合に名称変更し、さらに同年8月のX会社とA会社の合併後、E労働組合に組織統合された。これに対し、C支部の委員長Fらは、この決議を含む一連の手続はC支部の規約に基づかないと主張し、C支部の規約に基づかないと主張し、C支部の名称を使用した組合活動を続けた。
昭和41年3月2日、D組合とA会社との間で、従前C支部がA会社から貸与されていた組合事務所等はD組合によって、使用が継続されることにより、同組合の組合員らが、Fらの占有を排除して、事務所の使用を開始した。C支部は、同年4月11日、A会社に対し、組合事務所不法占拠の排除等について団体交渉を申し入れたが、A会社は、C支部はすでに脱退により消滅したとして、これを拒否し続け、合併後のX会社もC支部との団体交渉を拒んだ。
その後、X会社はC支部の団体交渉申入れに応ずることになったが、X会社は、C支部の求める組合事務所等の貸与問題は、Fら6名の専従者を職場復帰させるという専従問題の解決を抜きに交渉することはできないという態度をとり続け、交渉は進展しなかった。
組織統合後は、E組合が組合事務所等の使用を継続しているが、その貸与の交渉に際しては、ことさら条件が付されたり、また何らかの前提となる取引がおこなわれたりしたことはなかった。当時、G、H、の各工場では、会社敷地の一画を堀で仕切った部分に建てられた建物が組合事務所として器具備品も併せて貸与されており、1工場では、組合専従者の常駐がないため、倉庫の1個が連絡事務所として貸与されている。また、掲示版は、3工場を通じて各職場ごとにその実情に応じた大きさのものが貸されており、その合計は大小を合わせ182個である。
一方、C支部は、組合事務所等が貸与されないため、会議や連絡のための場所を欠き、教宣活動も十分できないなど、その組合に大きな支障をきたしている。なお、3工場における組合員数は、E組合は8595名、C支部は89名である。
C支部はY労働委員会に、不当労働行為の救済を申し立てた。Yは支配介入の成立を認めて救済命令を発したところ、X会社は、この命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、X会社の請求を棄却した。そこで、X会社は上告した。
判旨 上告棄却(X会社の請求棄却)。
「使用者の中立保持義務は、組合事務所等の貸与といういわゆる便宜供与の場面においても異なるものではなく、組合事務所等が組合にとってその活動にとってその活動上重要な意味を持つことからすると、使用者が一方の組合の組合事務所等を貸与しておきながら、他方の組合に対して一切貸与を拒否することは、そのように両組合に対する取扱いを異にする合理的な理由が存しないかぎり、他方の組合の活動力を低下させその弱体化を図ろうとする意図を推認させるものとして、労働組合法7条3号の不当労働行為に該当すると解するのが相当である。
(右合理的な理由の存否については、単に使用者が表明した貸与拒否の理由について表面的、抽象的に検討するだけでなく、一方の組合に貸与されるに至った経緯及び貸与についての条件設定の有無・内容・他方の組合に対する貸与をめぐる団体交渉の経緯及び内容、企業施設の状況、貸与拒否が組合に及ぼす影響等諸般の事情を総合勘案してこれを判断しなければならない)」。
解説
判例の認める使用者の中立保持義務(→【191】日産自動車‘残業差別)事件)は、本判決において、組合事務所や掲示板の貸与という便宜供与の場面においても妥当することが明らかにされた。本判決は、一方の組合に事務所等を貸与しながら、他方の組合に貸与しないのは、合理的な理由がないかぎり、組合弱体化の意図を推認させ、不当労働行為に該当すると述べている。組合事務所等の便宜供与は、団体交渉において決定されるべきものであるが、本件では、使用者が、断交において、組合専従問題の解決を先決事項とし、その解決ができないことを理由に貸与に応じないことには、合理的な理由がないと判断された。
なお、本件ではのYの救済命令は、「X会社は、C支部に対して、組合事務所および掲示板を貸与しなければならない・・・・この貸与の具体的条件についてC支部との間で合理的な取り決めをしなければならない」というものであり、「合理的な取り決め」の内容が具体的には明らかにされていない。しかし、本判決は、組合事務所等の貸与の具体的な内容・方法は、一義的に決めることはできず、当事者間の協議にゆだねざるを得ないので、こうした救済命令の内容は違法ではないと判断している。また、本判決は、「合理的な取り決め」は、X会社がE組合と同一の取り決めをC支部とすることではないと明言している(判旨外)。組合員数や会社施設の状況等を考慮したうえでの違いは許容するという趣旨である。
労組法7条3号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
193 併存組合下における誠実交渉義務と中立保持義務-NTT西日本事件
東京高判平成22年9月28日(平成22年(行コ)110号)
要因
使用者は、多数組合に対して経営協議会で行った資料の提示や説明を、少数組合との団体交渉においても行わなければならないか。
事実
X会社は、グループの構造改革の一環として、平成14年度より、新たな退職・再雇用制度(以下、新制度)を実施することとした。この構造改革について、平成13年4月以降、X会社は、多数組合であるA(従業員の98.9%を組織)と少数組合であるB(従業員のお。74%を組織)との間で、交渉・協議を進め、平成14年5月に新制度を実施した。
X会社は、新制度について、平成13年4月6日にA組合との間で、中央経営協議会を開催して説明を行い、同月26日にも、A組合との間で経営協議会と団体交渉を実施して、具体的な提案を行った。B組合に対しては、同月27日および5月8日に簡単な資料をファックスで送付しただけで、同月11日にB組合の要求により、最初の団体交渉が行われた。その後、A組合はX会社の提案を受け入れることとし、6月15日の団体交渉において、X会社は新制度における労働条件についての具体的説明を行った。
X会社はB組合との間で団体交渉を行っていたが、新制度の導入に密接に関係する経営上の諸問題について、抽象的な説明に終始したり経営事項であるとして交渉を拒否したりし、また新制度の導入に関連する労働条件面について、A組合と同程度の説明が可能であるにもかかわらず、それをしていなかった。そのほか、B組合との初回の団体交渉を実施していなかったり、団体交渉期日の設定に機敏に回答していないなどの態度もとっていた。
B組合は、こうしたX会社の姿勢は、労組法7条2号・3号の不当労働行為にあたるとして、C労働委員会に救済命令を申し立てたところ、Cは当初の提案におけるX会社の対応は、企業の中立義務に反するとして支配介入の成立を認め、文書手交を命じたが、誠実義務違反は認めなかった。そこで、X会社とB組合双方が再審査を申し立てたところ、Y(中央労働委員会)は、支配介入の成立は認めなかったが、誠実義務違反を認めた。ただ、すでに新制度は導入されているとして、救済の利益がないとし、文書手交のみを命じた。
そこでX会社は、Yの発した命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審はYの判断を大筋において、ほぼ認め、請求を棄却した(東京地判平成22年2月25日)。そこで、X会社が控訴した。なお、本判決に対して、X会社は上告したが、最高裁は、上告不受理・棄却とした。
判旨 控訴棄却(X会社の請求棄却)
以下の判旨内容は、控訴審が引用した1審判決判示内容である。
Ⅰ 複数労働組合併存下においては、使用者に各労働組合との対応に関して、平等取扱い、中立義務が課せられているとしても、各労働組合の組織力、交渉力に応じた合理的、合目的的な対応をすることが、同義務に反するものとみなされるべきではない。
Ⅱ(1)使用者が一方の労働組合のみとの間での経営協議会で行った説明との間の経営協議会設置に関する取決めに基づくものであって、使用者はそのような取決めを行っていない他の労働組合に対して、これと同様の対応を行うべき義務を負うものではないと解される。
(2)使用者が一方の労働組合との経営協議会において提示した資料や説明内容が、当該労働組合とのその後の団体交渉における使用者の説明や協議の基礎となる場合には、使用者は、経営協議会を行っていない他の労働組合との間の同一の交渉事項に関する団体交渉において、当該他の労働組合から、団体交渉を行うに当たって必要なものとして経営協議会におけるものと同様の資料の提示や説明を求められたときには、団体交渉における使用者の実質的な平等取扱いを確保する観点から、必要な限りで、同様の資料の提示や説明を行う必要があるというべきである。
解説
使用者は、労働組合が併存する場合に、いずれの労働組合との間でも中立保持義務を負うが、各労働組合の組織力と交渉力に応じた差異を設けることはひていされていない(→【191】日産自動車(残業差別)事件、判旨Ⅰ)。そのため、使用者は、多数組合との間で経営協議会を設けて、その経営協議会において、同様の経営協議会を設けていない少数組合とは違う説明や協議を行うことも、中立保持義務違反となるものではない(判旨Ⅱ(1))。しかしながら本判決は、使用者は、一定の場合には、少数組合にも、多数組合と同様の説明や協議をしなければならないと述べて(判旨Ⅱ(2))、後者の結論に重要な留保を付けている。具体的には、使用者が多数組合との経営協議会で提示した資料や説明内容は、その後の団体交渉における使用者の説明・協議の基礎となる場合において、同一の団体交渉事項に関して、少数組合から同様の資料の提示や説明を求められたときは、必要な限りで、それに応じなければならない、ということである。
本判決は、こうした判断の根拠として、「団体交渉における使用者の実質的な平等取扱いを確保するかんてん」に言及している。これは、使用者の誠実交渉義務の内容は、併存組合下においては、他組合との交渉態度も影響するという考え方をしめしたものといえよう。どう影響するかはケース・バイ・ケースとなるが、本件では、使用者が経営協議会を設けることは、各組合との交渉等に応じて自由にきめてよいものの、そうであるからといって、団体交渉の基礎となる情報の提供について、格差を付けてよいことにはならず、そこで不当な格差を付ければ誠実義務違反となるということである。
労組法7条2号・3号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
194 救済命令の裁量(1)-ネスレ日本事件
最1小判平成7年2月23日(平成3年(行ツ)91号)(民集49巻2号281頁)
要因
自組合の組合員のチェック・オフされた組合費を別組合に支払う行為が支配介入にあたる場合に、チェック・オフ相当額を申立組合に支払うよう命じる救済命令は適法か。
事実
X会社には単一のA労働組合が存在したが、組合の内部抗争の結果、2つの労働組合が併存するに至った(B労働組合とC労働組合)。B労働組合の組合員らは、従来、A組合とX会社のチェック・オフ協定に基づき組合費のチェック・オフを受けていたが、B組合とそのD支部とE支部は、独立した労働組合としての存在を認められるに至る直前から、組合員名を明示してチェック・オフの中止および控除された組合費相当額の返還などを要求した。なお、X会社は、昭和58年4月には、B組合およ両支部の存在を認識し、所属組合員の指名を把握していた。
B組合と両支部は、チェック・オフを継続してC組合の支部に組合費を支払うことは不当労働行為に該当するとして、F労働委員会に救済を申し立てた(その他、断交拒否の救済も申し立てている)。初審は救済命令を発したので、X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査の申立てをした。Yは、同様に不当労働行為の成立を認めたが、初審の救済命令を少し改め、支部に所属する組合員の給与から、昭和58年4月分以降、チェック・オフした組合費相当額およびこれに対する年5分の割合による金員を付加して支部に支払わなければならない、という救済命令を発した。そこで、X会社は、Yの本件命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、救済命令は適法と判断したのでX会社は上告した。
判旨 原判決一部破棄(Z会社の請求認容)。
Ⅰ 本件命令部分は、チェック・オフの継続と控除額のC組合の支部への交付という不当労働行為に対する救済措置として、X会社に対し、控除した組合費相当額等を、組合員個人に対してではなく、D支部へ支払うことを命じたものである。しかし、チェック・オフにより控除された組合費相当額は、本来、組合員自身がX会社から受け取るべき賃金の一部であり、また、不当労働行為による組合活動に対する制約的効果や支配介入的効果も、組合員が賃金のうち組合費に相当する金員の支払いを受けられなかったことにともなうものであるから、X会社をして、今後のチェック・オフを中止させたうえ、控除した組合費相当額をD支部所属の組合員に支払わせるならは、これによって、不当労働行為によって生じた侵害状態は除去され、不当労働行為がなかったと同様の事実上の状態が回復されるものというべきである。
Ⅱ 本件救済命令は、B組合とX会社との間にチェック・オフ協定が締結され、B組合所属の個々の組合員がX会社に対し、その賃金から控除した組合費相当額をD支部に支払うことを委任しているのと同様の事実上の状態を作り出してしまうこととまるが、本件では、このような協定の締結や委任の事実は認められないのであるから、本件命令部分により作出される状態は。不当労働行為がなかったのと同様の状態から著しくかけ離れるものであることが明らかである。
Ⅲ さらに、救済命令によって、作出される事実上の状態は必ずしも私法上の法律関係と一致する必要はなく、また、支払を命じられた金員の性質は控除された賃金そのものではないことはいうまでもないが、本件命令部分によって作出された事実上の状態は、私法的法律関係から著しくかけ離れるものであるのみならず、その実質において労基法24条1項の趣旨に抵触すると評価される状態であるといわなければならい。
解説
労働委員会の救済命令は、「正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図る」ために。「個々の事実に応じた適切な是正措置を決定」することが求められるが、その具体的な内容について、労働委員会に広い裁量権が認められる(→【177】第二鳩タクシー事件。ただし、この事件では、中間収入を控除しない全額バックペイ命令を違法と判断した)。
本件のように組合が分裂した場合、判例は、労働者からチェック・オフの中止の申出があれば、使用者は中止しなければならいとしており(→【147】エッソ石油事件)、本件のように、使用者が、チェック・オフを中止せず、しかも控除した組合費を労働者が所属していない組合に引き渡すことが支配介入の不当労働行為に該当することには異論がないであろう。
問題は、救済命令の内容であるが、本判決は、組合員個人に引き渡すよう命じられるべきとする(判旨Ⅰ)。B組合の組合費のチェック・オフが認められるためには、チェック・オフ協定の」
締結と組合員からの支払委任が必要であるが、それがないにもかかわらず、支部に組合費の支払いを命じることは、不当労働行為がなかったのと同様の状態からも、また、私法的法律関係からも著しくかけ離れるものであり、違法となると判断している(判旨Ⅱ、Ⅲを参照)。
本判決は、「救済命令によって作出される事実上の状態は必ずしも私法上の法律関係と一致する必要はない」とするが、私法上の法律関係から「著しくかけ離れ」、かつ労基法24条という強行規定にも抵触するという点で違法と判断した。しかし、労働委員会の救済命令についての広い裁量を考慮すると、この判断妥当性には議論のよちがあろう(最近では、労組法7条1号の不利益取扱いに関する事件でバックペイ命令において、同一事案の民事確定判決で命じられた額を超えることができるかが問題となった事件でもある(平成タクシー事件ー広島高判平成26年9月10日)。
労基法24条1項(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労組法7条1号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
195 救済命令の裁量(2)-紅屋商事事件
最2小判昭和61年1月24日(昭和55年(行ツ)40号)
要因
査定差別の場合の救済命令の内容はどうあるべきか。
事実
紅屋商事事件【188】と同じ事案である。A労働組合、同組合の組合員とB労働組合の組合費との人事考課率の格差は不利益取扱いにあたるえおして、C労働委員会に不当労働行為の申立てをしたころ、Cは、X会社に対し、本件各賞与におけるA組合の組合員の人事考課率に、昭和50年度夏季賞与については40を、同年度冬季賞与については22を加算した人事考課率により、各賞与を再計算した金額をすでに支給した金額の差額等をA組合の組合員に支払うべきことを命ずる旨の救済命令を発した。X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査を申し立てたが、Yはこれを棄却した。そこで、X会社は、その取消しを求めて訴えを提起した。1審はX会社の請求を棄却し、原審はX会社の控訴を棄却した。X会社は上告した。
判旨 上告棄却(X会社の請求棄却)。
Ⅰ「本件の事実関係の下においては、X会社は、本件各賞与におけるA組合員の人事考課率を査定するに当たり、各組合について、A組合に所属していることを理由として、昭和50年度夏季賞与についてはA組合員全体の平均人事考課率とB組合員全体の平均人事考課率とB組合員全体の平均人事考課率の差に相応する率だけ、同年度冬季賞与についてはA組合員全体の平均人事考課率とB組合員及び非組合員全体の平均人事考課率の差に相応する率だけ、それぞれ低い査定したものとみられてもやむを得ないところである。以上によれば、本件においては、X会社により、個々のA組合員に対し賞与の人事考課率の査定において組合所属に理由とする不利益取扱いがされるとともに、組合間における右の差別的取扱いによりA組合の弱体化を図る行為がされたものとして、労働組合法7条1号及び3号の不当労働行為の成立を肯認することができる」。
Ⅱ「使用者において賞与の人事考課率を査定するに当たり個々の組合員の人事考課率をその組合所属を理由として低く査定した事実が具体的に認められ、これが労働組合法7条1号及び3号の不当労働行為に該当するとされる以上、労働委員会において、これに対する救済措置として、使用者に対し、個々の組合員につき不当労働行為がねければ得られたであろう人事考課率に相応する数値を示し、その数値により賞与を再計算した金額と既に支給した金額との差額の支払いを命ずることも、労働委員会にゆだねられた裁量権の行使として許されるものと解することができる」。
解説
査定差別が不当労働行為と判断された場合の救済方法については、直接是正命令と再査定命令とがありうる。直接是正命令とは、本件のC労働委員会が行ったものであり、すなわち、不当労働行為がなければ得られていたであろう人事考課率に相応する数値を示し、その数値に基づき再計算した額と実際に支給された額との差額の支給を命じるというものである。本判決は、こうした命令は、労働委員会にゆだねられた裁量権の行使として許されると述べている。本件のように、A組合から脱退した組合員の査定が、B組合員や非組合員と近似しており、A組合に対する差別から生じる格差が基準として明確である場合には、直接是正命令も適法といえるであろう。
他方、再査定命令とは、賃金や賞与等についての差別が認められた場合に、使用者に再査定を命じたうえで、それと旧査定による場合との差額分の支払いを命じるというものもある。再査定命令は、原則として適法と解されるが、ただ、再査定の際に、労働委員会が、具体的な査定基準を示して命じることが可能かは議論がありうる。
この点について、ある裁判所は、再査定命令に関しては、「使用者の査定権(裁量権)や人事権との関係が問題となるが、使用者が人事考課において当該労働者を殊更に低く評価している事実が疎明・・・・され、他の具体的事実とを併せて考えると、そのことが使用者の当該労働者に対する不当労働行為意思に基づくものと推認できるときには、当該労働者についての評定に関し、使用者が具体的事実に基づく根拠を示さず、当該労働者にその是正に必要な機会を与えられていない場合には、労働委員会が裁量により再査定を人事考課査定中の中間評価とするよう命じることも適法であると解する」と述べている(朝日火災海上保険事件ー東京高判平成15年9月30日)。
また、同判決は、昇格について、同年同期入社者に遅れないように取り扱うことを命じた救済命令について、課長職までの昇格は年功序列的色彩をもっていたので、使用者の人事権を著しく不当に制約するとまではいえないが、副部長職以上への昇格(職能資格の上昇およびそれに応答する職位の付与)は、「会社の基幹的職員であるべき管理職に相応しい適者を、会社経営の観点から人事権による裁量により選抜する要素が強くなる」ので、これに介入する命令は、会社の人事権を著しく不当に制約する違法なものとなるとしている。
労組法7条1号・3号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
196 申立人適格-京都市交通局事件
最2小判平成16年7月12日(平成15年(行ヒ)109号)
要因
支配介入の不当労働行為の救済について、個人申立ては認められるか。
事実
Xは、Y(市)のA局に勤める地方公営企業法上の企業職員であり、平成11年3月時点で、A局の施設部車両工場勤務の主事であった。Xは、B労働組合に加入しており、支部長をしていた。B組合の内部には、主流派があり、Xは反主流派の中心的な活動家であった。
Xは、同年4月1日、A局の職員の任免権限をもつC局長から、A局D営業所の庶務係長に昇格させる旨の人事異動通知を受けた。B組合とA局との間で締結された労働協約によると、掛長以上の職にある指定職員は、非組合員とされているため、この人事異動により、Xは組合員資格を失い、支部長としての資格も失った。A局には、これまで、現職の支部長が掛長級に昇任し、支部長を退任した例はなかった。また、Xのように主任を経ずして係長に昇任することも異例の取り扱いであった。
B組合は、本件異動に関して、A局に白紙撤回の検討を求めたが、最終的には、不当労働行為に該当しないという趣旨の判断をしていた。
Xは、本件の昇任措置は、不利益取扱いと支配介入の不当労働行為にあたるとして、Y労働委員会に救済を申し立てたところ、Yは、不利益取扱い該当を否定し、支配介入については、個人申立てができないとして却下した。そこで、Xは、この命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審は控訴を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 原判決一部破棄、一部棄却。
「労働委員会による不当労働行為救済制度は、労働者の団結権および団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した労働組合法7条の規定の実効性を担保するために設けられたものである。この趣旨に照らせば、使用者が同条3号の不当労働行為を行ったことを理由として、救済申立てをするについては、当該労働組合のほか、その組合員も申立て適格を有するとするのが相当である。
前記事実関係によれば、Xは、本件異動が同条3号の不当労働行為に当たることを理由として救済申立てをする適格を有するものというべきである」。
解説
不当労働行為の救済を申し立てる資格をもつのは、まず、不利益取扱い事件においては、その不利益取扱いを受けた労働者と、その所属する労働組合である。団交拒否事件では、団体交渉を拒否された労働組合であり、支配介入事件では、支配介入を受けた労働組合というのが原則である。労働組合が申し立てをする場合には、資格審査をパスしなければならない(労組法5条1項。なお、不利益取扱い事件における個人申立てについては、所属組合の資格の有無とは関係なく行うことができる「同項ただし書」)。
問題となるのは、団交拒否事件や支配介入事件において、組合員個人が申立人適格をもつかである。団交拒否事件については、否定説と肯定説が対立しているが、実際には、個人申立てはあまり想定できない。これに対して、支配介入事件については、労働組合が御用組合化していて、不当労働行為事件として争う意思をもたない場合には、個人に申立人適格を認める必要性があるといえる。また、本件のように、組合内部に主流派と反主流派の対立がある場合に、使用者の行った支配介入について、主流派が不当労働行為事件として争う意思をもたない場合にも、反主流派からの申し立てを認めた場合があるといえる。
この点について、本件の1審は、「使用者の労働組合を運営することを支配し、又は、これに介入するなどの行為が法7条3号により不当労働行為として禁止されている趣旨は、労働組合の自主性及び組織力が使用者の干渉行為により弱体化されていることを防止するところにあると解される。したがって、支配介入は労働組合に対する不当労働行為であって、その救済の申立ては労働組合がするのが原則であり、労働者個人は救済申立ての適格を有しないと解するのが相当である。もっとも、労働組合自体が御用組合化しているような場合で、組合員個人の申立てが認められることで労働組合の自主性や組織力が回復、維持されるような特段の事情がある場合には、組合員個人による申立てを認めるべきである」と述べ、原則否定であるが、特段の事情がある場合にのみ例外的に肯定という判断枠組みを示していた(京都地判平成14年3月22日)。
原審もこれを支持した(大阪高判平成15年1月29日)が、最高裁は、このような特段の事情に言及せず、支配介入事件でも、特に条件を付さずに個人申立てを認めると判断している。
なお、本件においては、昇進が組合員資格の喪失に結びつく場合に、不当労働行為にがいとうするかという争点もあった。1審および原審は、本件異動(昇任)は、組合活動への不利益とはなりうるものの、使用者には不当労働行為意思はなかったと判断している。なお、逆に組合員資格のない管理職へと昇進させないことは、不利益取扱いに該当しうる(ただし、放送映画製作所事件ー東京地判平成6年10月27日は反対)。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
労組法5条 (労働組合として設立されたものの取扱)
第5条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在地
三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
197 継続する行為-紅屋商事事件
最3小判平成3年6月4日(平成元年(行ツ)36号)(民集45巻5号984頁)
要因
賃金差別に対する救済申立ての際の除斥期間の起算点はいつか。
事実
X会社では、従業員の基本給額の一部を考課査定に基づき決定していた。A労働組合は、組合員の賃金が、非組合員と比べて低い昇給昇格査定を受けているとし、昭和54年7月17日にB労働委員会に」、救済申立てを行った。Bは、A組合の主張を認め、救済命令を発した。そこで、X会社は、その取消しを求めて、訴えを提起した。
本件救済命令の対象になっている賃金は、昭和53年4月の支払い分からであるが、給与は、昭和53年4月に昇給昇格査定が行われ、同月28日に4月分給与が支給され、その後、同年7月8日に賃はけいぞくすr上げ協定が締結され、同年7月15日に4月から6月までの昇給差額が支払われた。そこで、X会社は、労組法27条2項にいう「行為の日」は、昭和53年7月15日(差額分の支払日)であり、いずれの日であるにしても、本件申立ては、1年間の除斥期間が経過しているので、不適法であると主張した。
1審は、査定または賃上げ額決定とこれに基づく賃金支払いとを全体として1個の不当労働行為とみるべきであり、この査定または決定に基づく賃金が毎月支払われているかぎり、不当労働行為は継続することになるので、その賃金支払いの最後のもの、すなわち次期昇給査定または賃上額決定に基づく賃金支払いの前月の賃金支払いから1年以内であれば、救済申立ては適法ということができると述べて、昭和54年3月31日から1年以内であれば、申立ては適法と判断し(青森地判昭和61年2月25日)、原審も同旨であった(仙台高判昭和63年8月29日)。そこで、X会社は上告した。
判旨 上告一部棄却、一部却下。
「X会社が毎年行っている昇給に関する考課査定は、その従業員の向後1年間における毎月の賃金額の基準となる評定値を求めるものであるところ、右のような考課査定において使用者が労働組合の組合員について組合員であることを理由として他の従業員より低く査定した場合、その賃金上の差別的取扱いの意図は、賃金の支払によって具体的に実現されるのであって、右査定とこれに基づく毎月の賃金の支払とは一体として、1個の不当労働行為をなすものとみるべきである。
そうすると、右査定に基づく賃金が支払われている限り、不当労働行為は継続することになるが、右査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済の申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から1年以内にされたときは、右救済の申立ては、労働組合法27条2項ぼ定める期間内にされたものとして適法というべきである」。
解説
不当労働行為の救済申立ての期間は、1年となっている(この期間は除斥期間と解されている)。その起算点は、不当労働行為の行われた日であり、不当労働行為が継続する行為である場合には、その行為の終了した日である(労組法27条2項)。この期間を経過した後の申立ては却下される。
ところで、昇給差額の事案において、除斥期間の起算点がどこになるのかについては、見解の対立がある。昇給差別においては、査定の際に差別が行われ、その低査定に基づき昇給額が決定され、そして、実際に賃金が支払われることになる。その賃金の支払も、通常は、同一査定に基づくものが1年間繰り返されることになる。差別が行われたのは査定の段階なので、この時点が起算点であるという考え方もあるが、他方で、査定→昇給額の決定→賃金の支払という一連の行為が、1つの「行為」となるか、あるいは「継続する行為」となり、その終了時点である現査定に基づく最後の賃金支払日から起算されるという考え方もありうるところである。
本判決は、後者の考え方を採用したものである。なお、学説の中には、いったん差別的な査定がなされると、その効果は、実際にそれが是正されるまでは残存するということを考慮に入れると、その是正がなされるまでは、「継続する行為」として判断すべきであるという見解もある。
昇給、昇格について毎年差別が繰り返され、差別が蓄積されてきたという場合については、労働委員会の実務では、これが一貫した「継続する行為」であると認める傾向にある。
また、本判決と同様に、同一査定に基づく賃金支払いの範囲での「継続する行為」しか認めないものの、救済命令においては、蓄積された現存格差を将来に向けてまとめて解消する内容のものも適法とした裁判例もある(千代田化工建設事件ー東京地判平成9年7月23日)。この考え方によると、救済内容については、「継続する行為」を広く認める立場と実質的に同じ効果がもたされることになる。
労働組合法27条2項(不当労働行為事件の審査の開始)
第27条 労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
2 労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
198 組合員資格の喪失と救済利益-旭ダイヤモンド工業事件
最3小判昭和61年6月10日(昭和58年(行ツ)79号)(民集40巻4号793頁)
要因
労働組合は組合員資格を喪失した元組合員の救済を求めることができるか。
事実
X会社の従業員で組織するA労働組合(支部)は、昭和49年春闘の際にストライキを行ったところ、X会社は、A組合の組合員25名について、時限ストであったにもかかわらず、1日分の賃金をカットした。そこで、A組合は、この本件賃金カットは不利益取扱いおよび支配介入の不当労働行為に該当するとして、Y労働委員会に救済を申し立てた。
ところが、救済命令が出される前に、組合員25名のうち9名は退職し、2名は配転により、A組合の組合員資格を失っていた。これらの11名は、組合員資格の喪失に際し、X会社に対し、賃金カットに係る資金に関し何らの意思表示もしなかった。A組合はこの11名が組合員資格を喪失した後、この11名に対し、X会社に代わり本件賃金カットに係る賃金相当額を支払い、その賃金がX会社から支払われることとなった場合の受領権限を11名から与えられた。
Yは、本件賃金カットはストライキに対する報復として行われたもので不当労働行為に該当するとし、X会社が、A組合員25名に対し、賃金カットされた賃金分とこれに対する年5分の割合による加算金を支払うべきことを命じ、さらに、ポストノーティスを」命じた。X会社は、この命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審は、組合員資格を喪失した11名に対する救済命令は認められないとして、Yの命令を一部取り消した。X会社とYの双方が控訴したが、原審は、ポストノーティスを取り消した以外は、1審の判断を維持した。そこで、Yは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(カットされた賃金の支払命令は適法)
Ⅰ「思うに、労働組合法27条に定める労働委員会の救済命令制度は、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止した同法7条の規定の実効性を担保するために設けられたものである。本件賃金カットは、A組合のストライキに対する報復としてなされたものであって、前記25名の個人的な雇用関係上の権利利益を侵害するにとどまらず、右25名に生ずる被害を通じ、A組合の組合員の組合活動意思を委縮させその組合活動一般を抑圧ないし制約し、かつ、A組合の運営について支配介入するという効果を必然的に伴うものであり、労働組合法7条1項及び3号の不当労働行為に当たるとされる所以である。しはがって、A組合らは、本件賃金カットの組合活動一般に対する抑圧的、制約的ないしは支配介入的効果を除去し、正常な集団的労使関係秩序を回復・確保するため、本件救済命令の・・・・命ずる内容の救済をうけるべき固有の利益を有するものというべきである」。
Ⅱ 本件救済命令は前記25名に対する本件賃金カットに係る賃金の支払を命じているが、これも、本件賃金カットの組合活動一般に対する侵害的効果を除去するため、本件賃金カットがなかったと同じ事実上の状態を回復させるという趣旨を有しており、A組合らは、この救済をうけることにつき、組合員の個人的利益を離れ固有の利益を有しているのであり、組合員が本件賃金カットの後にA組合の組合員資格を喪失したとしても、A組合らの固有の救済利益に消長をきたすものではない。
Ⅲ「もっとも、本件のように、労働組合の求める救済内容が組合員個人の雇用関係上の権利利益の回復という形をとっている場合には、たとえ労働組合が固有の救済利益を有するとしても、当該組合員の意思を無視して実現させることはできないと解するのが相当である。したがって、当該組合員が積極的に、右の権利利益を放棄する旨の意思表示をなし、又は、労働組合の救済命令申立てを通じて右の権利利益の回復を図る意思のないことを表明したときは、労働組合は右のような内容の救済を求めることはできないが、かかる積極的な意思表示のない限りは、労働組合は当該組合員が組合員資格を喪失したかどうかにかかわらず、救済を求めることができるものというべきである」。
解説
本判決は、組合員の賃金カットについて、それは雇用関係上の権利利益を侵害するにとどまらず、組合員の組合活動を委縮させ、組合活動一般を抑圧したり制約したりする効果をもつとし(→【177】第二鳩タクシー事件)、その観点から、個別的な不利益措置についても、組合には救済を求める固有の利益があるとする(判旨Ⅰ)。そして、賃金カットされた組合員が組合員資格を喪失したとしても、組合に対する侵害的効果がなくなったわけではないので、組合の救済の利益は失われないと判断した(判旨Ⅱを参照)。
もっとも、カットされた賃金分の支払いを命じるという救済内容は、組合員の意思を無視して実現させることはできないので、組合員資格の喪失は、救済命令の違法性に影響が及びうる。そのときでも、本判決は、組合員が、その権利利益を放棄するか、救済申立てを通じてその権利利益の回復を図る意思がないことを積極的に表明しないかぎり、やはり組合はこうした救済を求めることができるとし(判旨Ⅲ)、本件ではそのような意思表示はなかったと判断されている(判旨外)。
労働組合法27条(不当労働行為事件の審査の開始)
第27条 労働委員会は、使用者が第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び申立人に対し、証拠を提出し、証人に反対尋問をする充分な機会が与えられなければならない。
2 労働委員会は、前項の申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
199 緊急命令-吉野石膏事件
東京高判昭和54年8月9日(昭和54年(行ス)8号)
要因
緊急命令はいかなる場合に発することができるか。
事実
AおよびBは、X会社の従業員で組織するC労働組合の職場委員であった。X会社はAとBに対して、地方への配転を命じたところ、両名がこれを拒否したために解雇した。そこで、C組合とAおよびBは、D労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたところ、Dはこれを認め、配転前の現職への復帰を命じた。X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査を申し立てたが、Yは申立てを棄却した。X会社は、救済命令の取消しを求めて、訴えを提起した。そこで、Yは、東京地裁に対して、緊急命令の申立てを行ったが、東京地裁は、これを却下する決定を下した。そこで、Yは、その取消しを求めて抗告した。
決定要旨 抗告棄却(Yの申立て却下)。
Ⅰ「いわゆる『緊急命令』の制度は、労働委員会の救済命令の取消を求める訴が提起された場合において、受訴裁判所が、当該労働委員会の申立てにより、使用者に対し、当該事件の判決の確定に至るまで、暫定的に、当該救済命令の全部又は一部に従うべき旨を命ずることができることとし、もって団結権の侵害を防止することを目的とするものと解される。
そして、緊急命令の制度の目的がこのようなものであるとすれば、緊急命令の申立の拒否を決するに当たっては、受訴裁判所は、当該救済命令の適否及びいわゆる『即時決済の必要性』の有無について審査することができるものと解するのが相当である。
けだし、右に述べた同制度の目的に照らし、労働委員会の救済命令の適法性に重大な疑義があるときは、当該労働委員会の申立てがあったものとしても、受訴裁判所が緊急命令を発することは相当でないというべきであり、その重大な疑義の有無は当該救済命令の審査を経ることなくして判断し得ないのである。
もっとも、緊急命令の手続においては、確定的に当該救済命令の適否を判断することは要請されていないから、右審査は、緊急命令の手続の過程に現れた疎明資料をもって、当該救済命令の認定判断に重大な疑義があるかどうかを検討すれば足りるものというべきである」。
Ⅱ「本件救済命令には、その重要な論拠の部分に事実の誤認があり、その適法性について疑義があるから、現段階において緊急命令を発するのは相当でないというべきである」。
解説
使用者が緊急命令の取消訴訟を提起したときは、訴訟をうけた裁判所(受訴裁判所)は、労働委員会の申立てに基づき、取消訴訟の確定に至るまで当該救済命令の全部または一部に従うことを決定によって命じることができる(労組法27条の20)。このような命令を緊急命令という。使用者が緊急命令に違反した場合には、50万円(断交応諾者等の作為を命じるものであるときは、その命令の不履行の日数が5日を超える場合に、その超える日数1日につき10万円の割合で計算した金額を加えた金額)以下の過料が科される(同32条。確定した命令と同じ制度である)。救済命令が提起されてもその効力が停止するものではない(行政事件訴訟法25条1項、29条)が、命令違反に対する罰則が適用されるのは命令を支持する判決が確定した時点からなので、取消訴訟の進行中に暫定的な強制執行させることをできるようにしたのが、この緊急命令制度である。
緊急命令の要件としては、まずあげられるのは、暫定的な履行強制をする「必要性」、すなわち、救済命令をただちに履行させなければ、救済の実現が困難になるような緊急の必要性である。
それに加えて、救済命令の適法性も緊急命令の要件となるか否かについては議論がある。たしかに、受訴裁判所に、同一救済命令について本案で取り消す可能性が大きい場合にまで緊急命令を発して救済命令を暫定的に履行させるべきとするのは妥当ではない。そのため、本決定においても、「労働委員会の救済命令の適法性に重大な疑義があるときは、当該労働委員会の申立があったとしても、受訴裁判所が緊急命令を発することは相当でないというべき」と述べている(決定要旨Ⅰ)。とはいえ、適法性の審査も「緊急命令の手続の過程に現れた疎明資料をもって、当該救済命令の認定判断に重大な疑義があるかどうかを検討すば足りる」とも述べていることである。
本件では、「重要な論拠の部分に誤認があり、その適法性について疑義がある」ということで、緊急命令を出さない決定が適法とされた(決定判旨Ⅱ)。
労組法27条の20 (緊急命令)
第27条の20 前条第一項の規定により使用者が裁判所に訴えを提起した場合において、受訴裁判所は、救済命令等を発した労働委員会の申立てにより、決定をもつて、使用者に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は当事者の申立てにより、若しくは職権でこの決定を取り消し、若しくは変更することができる。
労組法32条
第32条 使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。
行政事件訴訟法25条1項 (執行停止)
第25条 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
行政事件訴訟法29条(執行停止に関する規定の準用)
第29条 前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。
200 労働組合の消滅と救済命令の拘束力-ネスレ日本・日高乳業事件
最1小判平成7年2月23日(平成4年(行ツ)120号)(民集49巻2号393頁)
要因
不当労働行為の救済命令が出された後、労働組合が消滅した場合に、使用者が取消訴訟を提起することは適法か。
事実
X2会社は、X1会社とは別法人であるが、X1会社と業務提携をし、X1会社の製品を製造し、かつ、X2会社の従業員の中にはX1会社からの出向社員もいた。X1会社には、その従業員で組織するA労働組合があり、X2会社のB工場には、A組合B支部があった。団体交渉に関するルールについては、X1会社とA組合ろの間で合意され、それに基づき、B工場だけに関する事項についての団体交渉は、従前からB工場の工場長とA組合B支部との間で行われていた。その後、A組合は分裂して、新たにC組合とD組合が併存することになり、X2会社B工場においても、それぞれC組合B支部とD組合B支部が併存するようになった。
C組合B支部は、X2会社が、D組合B支部しか労働組合と認めず、団体交渉を拒否したこと、C組合B支部の組合員の組合費を控除したこと、脱退勧奨があったことが不当労働行為にあたるとして、Y労働委員会に救済申立てをしたところ、Yは控除組合費のC組合B支部への支払いなどを内容とする救済命令を発した(以下では、団体交渉、支配介入についての救済命令の部分は割愛する)。その後、C組合B支部は、残っていた最後の組合員3名が脱退をした結果、組合員がいなくなり、さらにX2会社が、B工場の営業施設を第三者に譲渡したことにより、B工場においてC組合の組合員が労務に従事する可能性が当面失われたため、自然消滅した。
X1会社とX2会社は、救済命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審は請求を棄却したため、Xらが控訴したが、原審は控訴を棄却した。そこで、Xらは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xらの請求を却下)。
「救済命令で使用者に対し労働組合への金員の支払が命ぜられた場合において、その支払いを受けるべき労働組合が自然消滅するなどして労働組合としての活動をする団体としては存在しないこととなったときは、使用者に対する右救済命令の拘束力は失われたものというべきであり、このことは、右労働組合の法人格が清算法人として存続していても同様である。けだし、使用者に対し労働組合への金員の支払いを命ずる救済命令は、その支払いをさせることにより、不当労働行為によって生じた侵害状態を是正し、不当労働行為がなかったと同様の状態を回復しようとするものであるところ、その労働組合が組合活動をする団体として存続しなくなっているいる以上、清算法人として存続している労働組合に対し、使用者にその支払いを履行させても、もはや侵害状態が是正される余地はなく、その履行は救済の手段方法としての意味を失ったというべきであるとし、また、これを救済命令の履行の相手方の存否という観点からみても、右のような救済命令は、使用者に国に対する公法上の義務を負担させるものであって、これに対応した使用者に対する請求権を労働組合に取得させるものではないのであるから、右支払を受けることが清算の目的の範囲に属するといういうことはできず、組合活動をする団体ではなくなった清算法人である労働組合は、もはやこれを受ける適格を失っているといわなければならないからである」。
解説
労働委員会の発した不当労働行為の救済命令に対する取消訴訟において、救済命令の適法性を判断する基準時は、裁判所における口頭弁論終結時点か、救済命令が出された時点かについては争いがある。救済命令が出された後に、労働組合の消滅のような事情の変化があり、救済命令を維持するのが妥当でないという場合に問題となるが、通説は後者の立場である。
もっとも、本判決は、労働組合の消滅の事案において、救済命令が拘束力を失っている場合には、使用者の取消しを求める法律上の利益が失われるので、訴えは却下されるべきであると述べている。原判決は、控除された却下されるべきであると述べる。原判決は、控除された組合費の組合への支払命令について、組合が清算の目的で存在している以上、救済命令の有効性は失われないと判断していたが、本判決は、救済命令の目的は、不当労働行為によって生じた侵害状態を是正し、不当労働行為がなかったと同様の状態を回復しようとするものであるところ、労働組合が消滅している以上、清算法人として存在している労働組合に対し使用者にその支払いを履行させても、もはや侵害状態が是正される余地はなく、その履行は救済の手段としての意味を失ったと、述べている。
なお、その後の裁判例では、労働委員会の発した誠実交渉命令について、在籍組合員である労働者が退職し、現に雇用される労働者である組合員が1人もいなくなったというだけの理由で、使用者の団体交渉応諾義務が当然に消滅するものではないとして、労働組合が消滅していないケースでは、救済命令の拘束力の掃滅を認めない傾向にある(ネスレ日本(島田工業)事件ー東京高判平成20年11月12日、ネスレ日本(霞ヶ浦工場)事件ー東京高判平成21年5月2日、熊谷海事工業事件ー最2小判平成24年4月27日等)。
本資料の作成につきましては、私が尊敬申し上げております大内 伸哉一先生の「最新重要判例200労働法第5版」を参考に、私のお客さまへのプレゼン資料として、作成させていただきましたので、その旨、記載させていただきます。
新着情報・お知らせ
井上久社会保険労務士・行政書士事務所
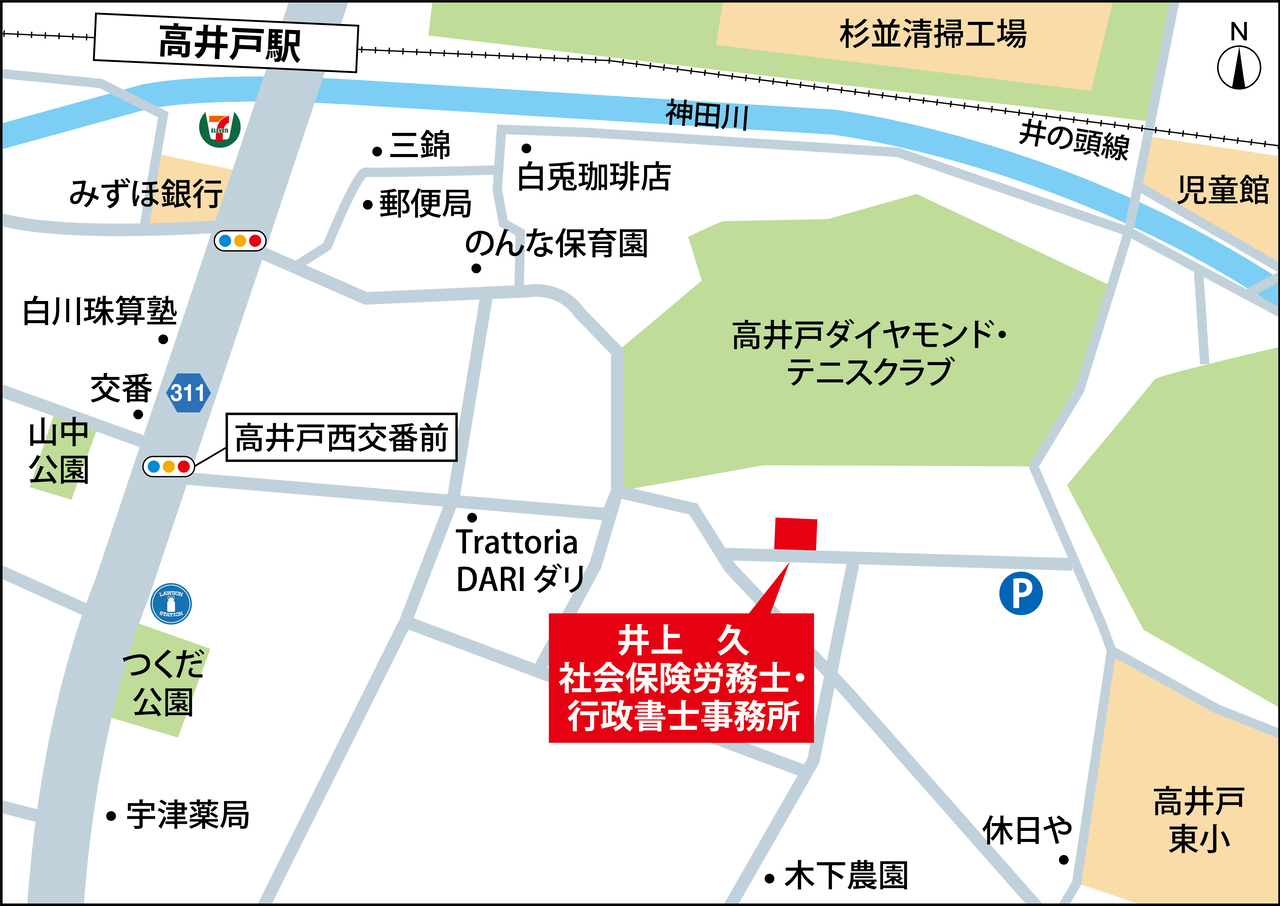
住所
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
アクセス
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

