行政法の重要な判例をご紹介いたします。
行政法重要判例
1.浦安鉄抗撤去事件(最判平3.3.8)
本件鉄抗撤去は違法な行為といえるか。請負代金の支出・時間外勤務手当の支給は違法か。
2. 自作農創設特別措置法と民法177条(最大判昭28.2.18)
本件農地の所有権取得につき登記手続を完了していないXは、民法177条に基づき、第三者である地区農地委員会に対抗できないとするYの判断は適法か。
3. 国税滞納処分と民法177条(最判昭31.4.24)
国税滞納処分による差押えに民法177条の適用はあるか。
4. 公営住宅の使用関係と信頼関係の法理(最判昭59.12.13)
公営住宅の住居者が公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合にも、信頼関係の法理は適用されるか。
5. 公営住宅の入居者の死亡と相続(最判平2.10.18)
入居者死亡の場合における公営住宅の承継問題につき、民法の相続の規定は適用されるか。
6. 建築基準法65条と民法234条1項の関係
建築基準法65条所定の建築物の建築に民法234条1項は適用されるか。
7. 位置指定道路の通行妨害(最判平9.12.18)
道路位置指定を受け開設されている道路を通行する講習の利益は、法律上の利益といえるか。当該道路の通行を敷地所有者に妨害されたよきには、公衆はその排除を求める権利を有するか。
8. 自衛隊内の事故と安全配慮義務(最判昭50.2.25)
国は国家公務員に対して安全配慮義務を負うか。
9. 温泉審議会による諮問手続(最判昭46.1.22)
持ち回りの方法による審議会の決議は有効か。
10. 公共用財産の時効取得(最判昭51.12.24)
明示の公用廃止がなされなくとも、公共用財産を時効取得することは可能か。再度水路に復することが容易であっても、取得時効の成立を認めてよいか。
11.予定公物の時効取得(最判昭44.5.22)
建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地につき、取得時効の成立は認められるか。
12.村道の自由使用(最判昭39.1.16)
村民が村道を使用することについての法的権利性をどう解すべきか。その権利が侵害された場合に、妨害排除を求めることは可能か。
13.幼年者との面会(最判平3.7.9)
拘置所長が未決拘留者と14歳未満の者との接見を許さなかったことは、国家賠償法1条1項の適用を受ける違法行為といえるか。
14.銃刀法14条に基づく委任の範囲(最判平2.2.11)
鑑定基準の対象を日本刀に限定する銃砲刀剣類登録規制(文部省令第2項は、銃刀法14条の委任の範囲を超えたものとして無効となるか。
15.学習指導要領の法的性質(最判平2.1.18)
文部省告示たる高等学校学習指導要領に法規性は認められるか。
16.通達に対する取消訴訟(最判昭43.12.24)
本件の通達は、行政事件訴訟法に基づく取消しの訴えの対象となりうるか。
17.みなし道路の一括指定(最判平14.1.17)
告示により一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は、抗告訴訟の対象となる処分に該当するか。
18.パチンコ球遊器事件(最判昭33.3.28)
本件課税処分は、法律に基づかない「通達課税」であり、租税法律主義に反するのではないか。
19,市街地再開発事業計画の決定・公告(最判平4.11.26)
都市再開発法に基づく第二種事業の事業計画決定は抗告訴訟の対象となるか。
20.工場誘致計画の変更(最判昭56.1.27)
地方公共団体が一定の継続的な施策を計画・決定し、それに基づき特定の者に対して当該施策に適合する活動を個別具体的に勧告・誘致した後に当該施策を変更した場合、相手方に対して違法な加害行為を行ったものとして損害賠償責任を負うか。
21.病院開設中止勧告に対する抗告訴訟(最判平17.7.15)
病院開設の中止勧告は、行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」といえるか。
22.執拗な退職勧奨に対する慰謝料請求(最判昭55.7.10)
執拗な退職勧奨は、国家賠償法に基づく慰謝料請求の対象となるか。
23.指導要綱に基づく開発負担金(最判平5.2.18)
建設指導要綱に基づく寄付の要請は、国家賠償法1条1項に規定する違法な権力の行使にあたるか。
24.品川区マンション事件(最判昭60.7.16)
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することは、国家賠償法1条1項に規定する違法な公権力の行使にたるか。
25.営業許可を受けない食肉買入契約の効力(最判昭35.3.18)
食品衛生法に基づく食肉販売業許可を受けない者との間でなした食肉の売買契約は、単なる取締法規違反か。
26.行政庁の承認を受けない農地賃借権移転(最判昭31.4.13)
市町村農地委員会が(改正前の)農地調整法4条に基づいて行う農地賃借権の設定・移転に関する承認は、同委員会の自由裁量行為といえるか。
27.マクリーン事件(最判昭53.10.4)
出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由の有無に関する判断について、法務大臣の裁量権はどの程度認められるものであり、それに対する裁判所の司法審査はどの範囲で及ぶのか。
28.個室付浴場事件(最判昭53.6.16)
風俗営業等取締法4条の4に規定する児童福祉法7条に基づく児童福祉施設として、山形県知事がなした本件児童遊園設置の許可処分には、行政権の濫用に相当する違法性があるといえるか。
29.公立大学の学生に対する懲戒処分(最判昭29.7.30)
公立大学の学生に対する懲戒処分は、学長の羈束裁量行為と解すべきか、それとも自由裁量行為と解すべきか。
30.朝日訴訟(最判昭42.5.24)
被保護者が死亡しても、相続人により生活保護処分に関する採決取消訴訟は承認され得るか。
31.公務員の懲戒処分と裁量権の範囲(最判昭52.12.20)
公務員に対する懲戒処分の適否について、裁判所の審査はどこまで及ぶか。
32.個人タクシー事件(最判昭46.10.28)
個人タクシー事業の免許申請に対する審査として、いかなる手続公正ながものといえるか。
33.群馬中央バス事件(最判昭50.5.29)
諮問を経て行政処分がされるべき場合における当該諮問機関の真理・決定(答申)の過程における違法性は、行政処分自体の違法性にいかなる影響を与えるか。
34.伊方原発訴訟(最判平4.10.29)
原子炉設置許可処分の取消訴訟における審理・判断の方法をいかに解すべきか。
35.第三次家永教科書検定訴訟
教科用図書の検定にあたって文部大臣が改善意見・修正意見を付すことは、国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使にあたるか。
36.行政行為の効力の発生時期(最判昭29.8.24)
公務員の任免に関する行政行為の効果の発生時期と官報による工事との関係をいかに解すべきか。
37.内部的意思決定と異なる表示行為(最判昭29.9.28)
行政機関の内部的意思決定と相違する書面が作成され交付された場合においても、当該書面に表示されているとおりの行政行為が成立するか。
38.「明白な瑕疵」の意義(最判昭36.3.7)
行政処分の瑕疵が明白であるか否かについては、いつの時点におけるどのような内容により決すべきか。
39.課税処分と当然無効(最判昭48.4.26)
行政処分が無効である旨を主張するためには、当該処分に存する瑕疵重大性が明白であることが、常に必要とされるか。
40.瑕疵の治癒が認められた例
農地買収計画についての訴願が提起されたにもかかわらず、その採決を経ないまま進行させた手続は有効といえるか。
41.瑕疵の治癒が認められなかった例(最判昭48.4.26)
更正処分に対する審査請求において、裁決庁により詳細な理由が示された場合には、付記理由不備の違法性は治癒されるか。
42.違法行為の転換が認められなかった例(最判昭29.7.19)
自作農創設特別措置法施行令43条によって定められた農地買収計画を、訴願に対する採決によって、同令45条によるものとして維持することが認められるか。
43.事実上の公務員の理論(最大判昭35.12.7)
村が吸収合併により消滅した後において、村長解職賛否投票の無効確認を求めることについて、訴えの利益は認められるか。
44.旅券発給拒否における理由付記(最判昭60.1.22)
一般旅券発給拒否処分の通知書に、「旅券法13条1項5号に該当する。」とのみ理由に記載した本件拒否処分には、理由付記の不備による違法性があるのではないか。
45.違法性の承継が認められた例(最判昭25.9.15)
買収計画についての出訴期間が経過した後に、当該買収計画の違法性を主張してその後になされた買収処分の取消しを主張することはできるか。
46.不可変更力に反してなされた採決の効力(最判昭30.12.26)
訴願に対する採決を裁決庁自らがその後に取り消した場合は、当該取消しの採決は当然に無効となるか、それとも取消原因となるにとどまるか。
47.行政行為の撤回と損失補償(最判昭49.2.5)
行政財産たる土地についての使用許可の取消し(撤回)に当たっては、存実補償を要するか。
48,菊田医師赤ちゃんあっせん事件(最判昭63.6.17)
優生保護法に基づく指定医師の指定といった授益的行政行為の撤回は、当該撤回を認める直接の明文規定がなくても許されるか。
49.宝塚市パチンコ条例事件(最判平17.7.9)
地方公共団体が、条例に基づく行政上の義務の履行を求めて民事訴訟を提起することは認められるか。
50.行政上の強制執行と民事上の強制執行(最判昭41.2.23)
農業協同組合が、農作物等の共済掛金や賦課金・拠出金を滞納する組合員に対して、民事訴訟法の手続に従って徴収することは認められるか。
51.豊中給水装置拒否事件(最判昭56.7.16)
違法建築物についての給水装置新設工事の申込の受理を市が事実上拒否することは、不法行為法上の損害賠償責任を構成するか。
52.川崎民商事件(最判昭47.11.22)
所得税法(旧)70条10号・63条は規定する税務職員による質問検査は、裁判所の判断を経ることなく行政庁の判断だけで行えるとしている点で、検索・押収には正当な理由に基づいて裁判所が発する令状が必要であるとする憲法35条に違反しないか。
53.鉄道公安職印の実力行使(最大判昭48.4.25)
鉄道公安職員が、鉄道営業法42条1項に基づき不法行為者を鉄道施設外に退去させるにあたって強制力を用いることは、憲法31条等との関係において認められるか。
54.刑罰と秩序罰の併科(最判昭39.6.5)
同一の行為につき刑事訴訟法160条に基づく過料と同法161条に基づく罰金・拘留を併科することは、罰刑法定主義を定める憲法31条および二重処罰の禁止を定める同法39条後段に違反しないか。
55.課外クラブ活動中の事故
公立中学校の生徒が課外クラブ活動中の他の生徒との喧嘩から左眼を失明した事故につき、当該クラブ活動に立ち会っていなかった顧問の教諭には過失があるといえるか。
56.スナック事件(最判昭57.1.19)
泥酔してナイフを出しながら客などを脅した者からナイフを提出させて一時保管の措置などをとることなく、これを帰宅させた警察の行為(不作為)は、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
57.砲弾回収措置の不作為(最判昭59.2.23)
海辺に打ち上げられた旧日本軍の砲弾により人身事故が発生した場合において、警察官がその回収等の措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
58.水俣病の拡大と規制権限の不行使(最判昭59.2.23)
国や熊本県が、それぞれ水質二法や県漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。
59.宅配郷社に対する権限の不行使(最判平元.11.24)
宅配業法所定の免許基準に達しない免許の付与ないし更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
60.クロロキン網膜症訴訟(最判平7.6.23)
厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認等の行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。
61.在宅投票事件(最判昭60.11.21)
国会議員による立法行為(立法の不作為を含む)は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使を構成するか。在宅投票制度を廃止し、これを復活させなかった行為は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使に該当するか。
62.在外邦人選挙権制限違憲事件(最判平17.9.14)
在外国民が、平成10年改正前の公職選挙法により衆議院銀選挙・参議院議員選挙における選挙権を行使できなかったことが憲法・条約に違憲することの確認を求める訴訟を提起することは認められるか。また、平成10年改正後の公職選挙法附則8項により衆議院小選挙区選出議員の選挙と参議院選挙区選出銀の選挙についての選挙権ができなかったことが憲法・条約に違反することの確認を求める訴訟を提起することは認められるか。さらに、衆議小選挙区選出議員の選挙と参議院選挙区選出議員の選挙についての選挙権を有することの確認を求める訴訟を提起すること、認められるか。
63.議員の免責特権と国家賠償責任(最判平9.9.9)
国会議員が国会の質疑・演説・討論等の中でした個別の国民の名誉または信用を低下させる発言につき、国は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うか。
64.裁判行為と国家賠償法1条1項(最判昭57.3.12)
裁判官がした訴訟の裁判は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使を構成するか。
65.「その職務を行うについて」の意味(最判昭31.11.30)
当初より職務執行の意思がなく、単に他人の金品を不法に領得する目的を有するに過ぎない公務員の行為も、国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」の要件を充たすか。
66.加害公務員の特定(最判昭57.4.1)
公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合、具体的に加害行為を特定できなければ国または公共団体は損害賠償責任を負わないか。
67.無罪の刑事判決と国家賠償(最判昭53.10.20)
刑事裁判において無罪判決が確定した場合、当該事件における捜査や公訴の提起・追行は違法な公権力の行使にあたるか。
68.パトカー追跡中の事故(最判昭61.12.27)
警察官が運転するパトカーの追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した交通事故により第三者が損害を被った場合、当該追跡行為が国家賠償法上違法なものとして評価されるのはどのような場合か。
69.公務員個人の責任(最判昭30.4.19)
公権力の行使にあたる公務員の職務行為に基づく損害につき、当該公務員は被害者に対して直接に責任を負うか。
70.国家賠償請求訴訟と抗告訴訟の関係(最判昭36.4.21)
行政処分の無効確認訴訟が提起された後に当該処分が職権により取り消されても、国家賠償請求との関係で、なお無効確認を求めることについての訴えの利益は存するか。
71.高地落石事件(最判昭45.8.20)
国家賠償法2条1項における営造物の設置・管理の「瑕疵」の意味をいかに解すべきか、また、当該瑕疵を判断するにあたって、管理者における過失は必要とされるか。
72.大阪国際空港公害訴訟(最判昭56.12.16)
民事上の請求として、一定の時間帯に航空機の離発着のためにされる国営空港の併用の差止めを求めることはできるか。
73.営造物の通常の用法に即しない行動(最判昭53.7.4)
営造物の通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、当該営造物の設置・管理者は、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任を負うか。
74.赤色灯事件(最判昭50.6.26)
他車により工事個所を示す工事標識版や赤色灯標柱などが倒され、赤色灯が消えた場合にも、その直後に同所を通過して事故に遭遇した者との関係では、道路管理者に管理の瑕疵があったこととなるか。
75.87時間事件(最判昭50.7.25)
国道上に故障した大型貨物自動車が約87時間にわたって放置されたことは、国道の管理の瑕疵といえるか。
76.大東水害訴訟(最判昭59.1.26)
河川管理についての瑕疵の有無は、そのような基準ではんだんすべきか。
77.多摩川水害訴訟(最判平2.12.13)
河川の改修整備がなされた後に水害発生の危険の予測が可能になっていた場合には、それについての河川管理の瑕疵はそのように考えるできか。
78.法定外公共用物の瑕疵(最判昭59.11.29)
国家賠償法2条1項が定める「公の営造物の設置又は管理」を解釈するにあたっては、当該営造物の所有の有無や管理についての法律的根拠をそのような考えるべきか。
79.補助金の交付と国家賠償法3条の費用負担者(最判昭50.11.28)
地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対して国が補助金を交付している場合、国は、国家賠償法3条1項に規定する「国の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」に該当するか。
80.郵便法違憲事件(最大判平14.9.11)
郵便法68条および73条のうと、書留郵便物について国の損害賠償責任を免除または制限している部分は、憲法17条に違反しないか。
81.消防職員の過失と失火責任法(最判昭53.7.17)
公権力の行使にあたる公務員の失火には、「失火ノ責任ニ関スル法律」が適用されるか。
82.河川附近地制限令事件(最判昭43.11.27)
損失補償に関する規定を定めていない河川附近地制限令4条2号およびその制限違反についての罰則を定める同令10条は、憲法29条3項に違反するか。
83.奈良県ため池条例事件(最判昭38.6.26)
災害防止のために財産権を制限した場合、憲法29条3項の保障は必要か。
84.収用目的の消滅と返還の是非(最判昭46.1.20)
買収農地の旧所有者は、買収農地を自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、農林大臣に対して当該農地の売払いを求めることができないか。
85.自作農創設特別措置法事件(最大判昭28.12.23)
憲法29条3項の「正当な補償」とは、いかなる補償をいうか。
86.土地収用法事件(最判昭48.10.18)
土地収用法に基づき収用された土地の「補償」は、いかなる補償か。
87.ガソリンタンク事件(最判昭58.2.18)
道路工事の施行の結果、危険物の移転を余儀なくされたことによる損失は、道路法70条1項の定める損失補償の対象となるか。
88.損失補償の支払時期(最大判昭24.7.13)
政府が食糧管理法に基づき個人の産米を買い上げるにあたっては、産米の供出と同時にその代金を支払わなければ、「正当な補償」の下に私有財産権を公共のために用いることを規定する憲法29条3項に違反することになるか。
89.予防接種事故(最判平3.4.19)
痘そうの予防接種によって重篤な後遺障害が発生したばあいにおいて、(旧)予防接種実施規則(厚生省令)4条が規定する禁忌者に該当していたか否かの判断はいかに解すべきであるか。
90.長野県勤務評定事件(最判昭47.11.30)
勤務評定にかかわる自己観察表示義務の不存在確認といった公法上の義務の不存在確認訴訟は、行政事件訴訟法上認められるか。
91.土地区画整理事業の事業計画決定(最判平20.9.10)
余地区画整理法に基づく土地区画整理事業の事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか。
92.輸入禁制品当該通知の処分性(最判昭54.12.25)
関税定率法21条3項に基づく通知、同条5項に基づく決定およびその通知は、抗告訴訟の対象である処分に該当するか。
93.交通反則金の納付通告と取消し訴訟(最判昭57.7.15)
道路交通法127条1項の規定に基づく反則金の納付通告は、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象となるか。
94.主婦連ジュース事件(最判昭53.3.14)
一般消費者は、不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項の規定による校正取引委員会の処分について不服があるもの」に含まれるか。
95.公衆浴場業距離制限規定事件(最判昭37.1.19)
都道府県知事が第三者に対してなした公衆浴場許可処分について、既設業者は無効確認を求める原告適格を有するか。
96.小田急高架化訴訟(最判平17.12.7)
鉄道事業許可の取消しを求める原告適格は、当該鉄道事業地内に不動産上の権利を有する者に限られ、付属街路事業の事業地内に不動産上の権利を有する者を含めて、周辺地域に居住する者には一切認められないか。
97.原子炉もんじゅ事件(最判平4.9.22)
設置許可申請に係る原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし約58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当するか。
98.選挙の立候補と免職処分の取消し訴訟(最大判昭40.4.28)
免職された公務員が当該免職処分の取消訴訟の係争中に公職の立候補者として届出た場合において、行政事件訴訟法9条の訴えの利益をどのように考えるべきか。
99.会議の公開の瑕疵と原告の死亡(最判昭49.12.10)
免職された公務員が当該免職処分の取消訴訟の継続中に死亡した場合、その相続人には訴訟承継が道められるか。
100.工事の完了と訴えの利益(最判昭59.10.26)
建築確認を受けて着手していた建築工事が完了した場合には、確認処分の取消しを求める訴えの利益は消滅するか。
101.皇居前広場事件(最大判昭28.12.23)
公園使用についての不許可処分の取消しを求める訴えについては、使用すべき日が経過することにより判決を求める法律上の利益が失われることとなるか。
102.運転免許停止処分と訴えの利益(最判昭55.11.25)
自動車運転免許の効力停止処分後無違反・無処分で1年を経過した場合には、当該処分の取消しを求める訴えの利益は消滅するか。
103.審査決定における附記理由の不満(最判昭37.12.26)
審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行った青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません。」とのみ決定理由を記載することは、当該審査決定の取消事由になるか。
104.条例違反者に対する罰則(最大判昭37.5.30)法令に特別な定めがあるものと除くほかは、地方公共団体がその条例中に条例違反者に対して一定範囲の刑罰を科する旨の規定を設けることができると定める地方自治法14条およびそれに基づく本件条例は、憲法31条に違反しないか。
105.売春条例事件(最大判昭33.10.15)
地方公共団体が各別に制定する売春の取締りに関する条例は。憲法14条に違反しないか。
106.徳島市公安条例事件(最大判昭50.9.10)
道路交通法77条1項4号・3項、119条1項13号と、昭和27年徳島市条例第3号(いわゆる徳島市公安条例)3条3号、5号、5条との関係をどのように考えるべきか。国法と条例との関係が問題となる。
107.普通河川管理条例と河川法(最判昭53.12.21)
普通河川の管理について定める普通地方公共団体の条例と河川法との関係はいかに解すべきか。
行政法重要判例(判例名・事案・争点・判旨・ポイント)
行政書士重要判例
Ⅲ 行政法
1. 浦安鉄抗撤去事件(最判平3.3.8)
(事案)
Aクラブは、二級河川である境川において、ヨットの保留施設とする目的で、鉄道レール約100本を全長850メートルにわたって、河川法の許可を受けないまま打ち込んだ。そのため、船舶の航行が困難となり、時に夜間や干潮時に航行する船舶にとっては非常に危険な状況が生じた。そこで、浦安町(当時)はAクラブ側に至急撤去を要請したが、撤去実施の様子が全く認められないため、町長(Y)がB建設との間で請負契約(代金130万円)を締結し、職員1名(時間外勤務手当4万8274円)とともに撤去にあたらせた。
以上の行為に対し、浦安町の住民(X)は、本件鉄杭の撤去は、何ら法律上の根拠に基づかない違法な行為であるから、その撤去に要した費用は違法な公益の支出にあたり、Yは合計額134万8274円についての損害を浦安町に与えたとして、地方自治法242条の2第1項に基づき、同額分を浦安市(昭和56年に市制施行)に変換するよう求めて住民訴訟を提起した。
(争点)
本件鉄抗撤去は違法な行為といえるか。請負代金の支出・時間外勤務手当の支給は違法か。
(判旨)
「本件判決は、右の設置場所、その規模等に照らし、浦安漁港の区域内の境川水域の利用に著しく阻害するものと認められ、同法39条1項の規定による設置許可の到底あり得ない。したがってその存置の許されないことの明白なものであるから、同法6項の規定の適用をまつまでもなく、漁港管理者の右管理権限に基づき漁港管理規定によって撤去することができるものと解すべきである。しかし、当時、浦安町においては漁港管理規定が制定されていなかったのであるから、上告人が浦安漁港の管理者たる司町の町長として本件撤去を強行したことは、漁港法の規定に違反しており、これにつき行政代執行法に基づく代執行としての適法性を肯定する余地はない。
浦安町は、浦安漁港の区域内の水域における障害を除去してその利用を確保し、さらに地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持する(地方自治法2条3項1号参照)という任務を負っているところ、同町の町長として右事務を処理すべき責任を有する上告人は、右のような状況下において、船舶航行の安全を図り、住民の危難を防止するため、その存置の許されないことが明白であって、撤去の強行によってもその財産的価値がほとんど損われないものと解される本件鉄杭をその責任において強行的に撤去したものであり、本件鉄杭撤去が強行されなかったとすれば、千葉県知事による除去が同月9日以降になされたとしても、それまでの間に本件鉄杭による航行船舶の事故及びそれによる住民の危難が生じた場合の不都合、損失を考慮すれば、むしろ上告人の本件鉄杭撤去の強硬はやむを得ない適切な措置であったと評価すべきである(原審が民法720条の規定が適用されない理由として指摘する諸般の事情は、航行船舶の安全及び住民の急迫の危難の防止のため本件鉄杭撤去がやむを得なかったものであることの認定を妨げるものとはいえない。)。
そうすると、上告人が浦安町の町長として本件鉄杭撤去を強行したことは、漁港法及び行政代執行法上適法と認めることのできないものであるが、右の緊急の事態に対処するためにとらえたやむを得ない措置であり、民法720条の法意に照らしても、浦安町としては、上告人が右撤去に直接要した費用を同町の経費として支出したことを容認すべきものであって、本件請負契約に基づく公金支出ついては、その違法性を肯認することはできず、上告人が浦安市に対し損害賠償責任を負うものとすることはできず、上告人が浦安町に対し、損害賠償責任を負うものとすることはできないといわなければならない。」
民法720条
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
(ポイント)
本件鉄杭撤去は、漁港法および行政代執行法上、適法性を肯定できないが、緊急の事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であり、民法720条(緊急避難)の法意に照らしても、当該費用を支出したことの違法性までは肯定できない。
どのような行政活動に法律の根拠を必要とするか(「法律の留保」の原則の適用範囲)が争われているが、判例は、本件のような根拠法がない行政活動について、ケースバイケースの対応をした。なお、学説上は、国民の権利自由を侵害したり、新たな義務を課すような侵害行政を行うには法律の根拠を必要とする、侵害留保説が通説である。
2. 自作農創設特別措置法と民法177条(最大判昭28.2.18)
Xは、戦前に本件農地をAより買い受け、代金を支払い、土地引渡しを済ませていたが、所有権移転登記については諸般の事情から行わないでいた。その上で、戦後の農地改革の際に、地区農地委員会は、本件農地の章勇者は登記簿上の名義人であるAであり、Aは不在地主であるといて、自作農特別措置法3条1項1号に基づき、本件農地の買収計画を定めた。そこで、Xは、異議申立てを経て、県農地委員会(Y)に訴願したが、認容されなかったため、Yのなした裁決の取消しを求めて出訴した。
(争点)
本件農地の所有権取得につき登記手続を完了していないXは、民法177条に基づき、第三者である地区農地委員会に対抗できないとするYの判断は適法か。
(判旨)
「自作農創設特別措置法(以下自作法と略称する)は、今次大戦の終結に伴い、我国農地制度の急速な民主化を図り、耕作者の地位の安定、農業生産力の発展を期して制定されたものであって、政府は、この目的達成のため、同法に基づいて、公権力を以て同法所定の要件に従い、所謂不在地主や大地主等の所有地を買収し、これを耕作者に売渡す権限を与えられているのである。即ち政府の同法に基く農地買収処分は、国家が権力的手段を以て農地の強制買上を行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とは、その本質を異にするものである。従って、かかる私経済上の取引の安全を保障するために設けられた民法177条の規定は、自作法による農地買収処分には、その適用を見ないものと解すべきである。されば、世府が同法に従って、農地の買収を行うには、単に登記簿の記載に依拠して、登記簿上の農地の所有者を相手方として買収処分を行うべきものではなく、真実の農地の所有者から、これを買収すべきものであると解する。」
民法177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(ポイント)
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家が権力的手段をもって農地の強制買上げを行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とはその本質を異にするので、民法177条を適用すべきでなく、政府は真実の農地所有者から農地を買収すべきである。
つまり、農地買収には民法177条は適用されない。
●民法177条の適用の可否
農地買収処分 ・・・✕
滞納処分の差押え・・・〇(「国税滞納処分と民法177条」参照)
3. 国税滞納処分と民法177条(最判昭31.4.24)
(事案)
Xは、A会社より本件土地を買い受け、代金も支払ったが、A会社の場合により所有権移転登記手続は未了であった(ただし、Xは、魚津税務署長に対し、本件土地を自己の所有とする財産税の申告をし、これを納入している。)。その後、魚津税務署長から事務の引継ぎを受けた所轄の富山税務署長(Y)は、A会社の租税の滞納を理由に本件土地を押さえ、その登記も経由した上で、翌年、Zを本件土地の買受人とする公売処分を執行して、Zへの移転登記手続も完了した。そこで、Xは、①Yに対する公売処分の無効確認と、②Zに対する本件土地の所有権移転登記手続を求めて出訴した。
(争点)
国税滞納処分による差押えに民法177条の適用はあるか。
(判旨)
「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押さえた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱いを受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても民法177条の運用があるものと解するのが相当である。
(ポイント)
国税滞納処分による差押えには民法177条が適用される。
民法177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
4. 公営住宅の使用関係と信頼関係の法理(最判昭59.12.13)
(事案)
Yは、東京都(X)の所有にかかる本件公営住宅に入居していたが、Xの許可をうけずに同住宅の敷地上に建物を増築し、また、2年2か月にわたり割増賃料の支払いを滞納したため、公営住宅法22条1項(現行32条1項)に基づき、Yに対する使用許可を取り消すとともに、その明け渡しを求めて出訴した。
これに対し、Yは、本件無断増築が公営住宅法の定める引渡事由に該当するとしても、本件においては、XとYとの間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるとして、Xの明渡請求には効力がな旨の抗弁を行った。
公営住宅法32条1項
(公営住宅の明渡し)
第三十二条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。
一 入居者が不正の行為によつて入居したとき。
二 入居者が家賃を三月以上滞納したとき。
三 入居者が公営住宅又は共同施設を故意に毀き損したとき。
四 入居者が第二十七条第一項から第五項までの規定に違反したとき。
五 入居者が第四十八条の規定に基づく条例に違反したとき。
六 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(争点)
公営住宅の住居者が公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合にも、信頼関係の法理は適用されるか。
公営住宅法22条1項
(入居者の募集方法)
第二十二条 事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。
(判旨)
「入居者が右使用許可を受けて事業主体とし入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあっても、事業主体と入居者の間の法律関係は、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異ることなく、このことは、法が賃貸(1条、2条)、家賃(1条、2条、12条、13条、14条)等私法上の賃貸借関係に通常用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかであるといわなければならない。したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法にして民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を決定するについては入居者を選択する事由を有しないものと解されるが、事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には信頼関係の基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情がある時には、事業主の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。
右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、右事実関係によれば、上告人の増築した本件建物は、構造上、現状回復が容易であり、かつ、本件住宅の保存にも適しているとはいいえず、また、被上告人が本件建物の増築を事後に許容したものとも認め難いところであるから、上告人の家庭に前記上告人の主張するような事情があるからといって、被上告人との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるということはできない。そうすると、被上告人の本訴明渡請求は、その余の点につて判断するまでもなく、理由があるものというべきである。」
(ポイント)
公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例に特別の定めがない限り、一般法である民法および借家法(現行「借地借家法」)の適用があり、その契約関係に規律するにつて、信頼関係の法理の適用がある。もっとも、本件におけるYの無断増築には、Xとの間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるということはできないので、Yは本件住宅を明け渡さなければならない。
5. 公営住宅の入居者の死亡と相続(最判平2.10.18)
(事案)
Yの祖父Aは、本件建物を東京都(X)から賃借していたが、その後死亡したため、Yが訴外Bらとともに、Aの地位を代襲相続した。一方、Xは、本件建物を含む都営住宅の老朽化が著しいことから、住人達に対し他の都営アパートへの移転斡旋を開始したが、本件建物につては、斡旋請求当時居住していたのは訴外Bらであったとして、Yに対し、所有権に基づく明渡しと不法占拠を理由とする不法行為に基づく損害賠償を請求した。
これに対し、Yは、都条例には使用権の譲渡・転貸を禁止した規定はあるが、入居者死亡の場合における使用権の継承の有無を定めた規定はなく、したがって、これについては一般法である民法の相続に関する規定が適用されるべきだと主張した。
(争点)
入居者死亡の場合における公営住宅の承継問題につき、民法の相続の規定は適用されるか。
(判旨)
「公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の推進に寄与することを目的とするmんであって(1条)、そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限定し(17条)、政令の定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、入居者を決定しなければならないものとした上(18条)、さらに入居者の収入が政令で定める基準を超えることになった場合には、その入居年数に応じて、入居者については、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない旨(21条の2第1項)、事業主体の長にちゅいては、当該公営住宅の明渡しを請求することができる旨(21条の3第1項)を規定しているのである。
以上のような公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を使用する権利を当然に承継すると解する余地はないというべきである。」
(ポイント)
公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない。
6. 建築基準法65条と民法234条1項の関係
(事案)
Yは、自己の所有する土地上に、隣接する土地の所有者Xの了解を得ることなく、境界線に近接して鉄骨造3階建ての建物の建築を始めた。そこで、Xは、本件建築が、境界線から50センチメートル以上の距離を置くべきことを規定する民法234条1項に違反するとして、Yに対して、境界線から50センチメートル以内に建物部分の収去を求めて出訴した。
これに対し、Yは、本件建物の敷地は準防火地域内にあり、しかも本件建物の外壁は耐火構造のものであるから、建築基準法65条により、隣地境界線に接して建築することができると抗弁した。
民法234条1項
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
(争点)
建築基準法65条所定の建築物の建築に民法234条1項は適用されるか。
(判旨)
「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除推される旨を定めたものと解するのが相当である。けだし、建築基準法65条は、耐火構造の外壁を設けることが防火上望ましいという見地や、防火地域又は準防火地域における土地の合理的ないし効率的な利用を図るという見地に基づき、相隣関係を規律する趣旨で、右各地域内にある建物で外壁が耐火構造のものにつては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができることを規定したものと解すべきであって、このことは、次の点からしても明らかである。すなわち、第一に、同条の文言上、それ自体として、同法6条1項に基づく建築申請の審査に際しよるべき基準を定めたものと理解することはできないこと、第二に、建築基準法及びその他の法令において、右確認申請の審査基準として、防火地域又は準防火地域における建築物の外壁と隣地境界線との間の距離につき、直接規制している原則的な規定はない(建築基準法において、隣地境界線と建築物の外壁との間の距離につき、直接規制しているものとしては、第一種住居専用地域内における外壁の後退距離の限度を定めている54条の規定があるにとどまる。)から、建築基準法65条を、何らかの建築確認申請の審査基準を緩和する趣旨の例外規定と理解することはできないことからすると、同条は、建物を建築するには、境界線から50センチメートル以上の距離を置くべきものとしている民法234条1項の特則を定めたものと解して初めて、その規定の意味を見出しうるからである。
本件についてこれをみると、上告人所有地は準防火地域に指定され、上告人建物の外壁は耐火構造であるというのであるから、建築基準法65条により、上告人建物は、本件土地部分においても許容されるというべきである。
(ポイント)
建築基準法65条は、民法234条1項の特則を定めたものであり、同条所定の建築物の建築に限っては、民法234条1項の規定の適用が排除される。
つまり、建築基準法65条の方が優先するということ。
建築基準法65条>民法234条1項
7. 位置指定道路の通行妨害(最判平9.12.18)
(事案)
Yは、川崎市長から道路位置指定を受けた本件土地につき、その所有者から贈与を受けた者であるが、その後、本件土地近辺に居住する住民に対し、通行契約を締結しない車両等の通行を禁止する旨のビラをまいた上で、本件土地に簡易ゲートを設置し、さらに通行を不可能にする工事を施行する旨を自治会に通知した。
これに対し、居住者から自動車で公道に出るには、本件土地を通行することが不可欠な状態にある付近住民のXらが、Yに対し、本件土地について通行妨害行為の排除および将来の通行妨害行為の禁止を求めて提訴した。
(争点)
道路位置指定を受け開設されている道路を通行する講習の利益は、法律上の利益といえるか。当該道路の通行を敷地所有者に妨害されたよきには、公衆はその排除を求める権利を有するか。
(判旨)
「建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定(以下、『道路位置指定』という。)を受け現実に開設されてる道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者から右通行を受任することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情がない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格的権利)を有するものというべきである。
けだし、道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することができるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害された者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則であるが、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活に属するものであって、これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通についての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関する利益は私法上も保護に値するというべきであり、他方、道路位置指定に伴い建築基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、少なくとも道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、右の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私法上の通行受任義務をおうこととなってもやむを得ないものと考えられるからである。
(ポイント)
道路位置指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて、日常生活上不可欠の利益を有する者は、当該道路の通行を敷地所有者によって妨害され、妨害されるおそれがあるには、妨害行為の排除・将来の妨害行為の禁止を求める人格権的権利を有する。
8. 自衛隊内の事故と安全配慮義務(最判昭50.2.25)
(事案)
陸上自衛隊員のAは、八戸駐屯地内の武器車両整備工場内に勤務していた昭和40年7月に、他の隊員が運転する大型自動車に轢かれて死亡した。
遺族である原告(Xら)には、同月中に計807万4,000円の遺族補償金が国家公務員災害補償法に基づき支給されたが、その際に他の請求手段についてはヾ何の説明もなかったため、Xらは、一般の交通事故死と比較してあまりに低額であることに不満を抱きつつも、恩恵による遺族補償金の増割を期待する他ないと考えていた。
しかし、その後、他の請求手段があることを知り、昭和44年10月になって、国(Y)を被告とする自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償請求訴訟を提起したが、原審(東京高判昭48.1.31)は、民放724条前段が定める消滅時効(損害および加害者を知った時から3年)が成立しているとするとともに、Xらが主張した国の安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任については、公務員と国との関係においては特別権力関係が成立することを理由に否定したため、Xらが上告した。
(争点)
① 国は国家公務員に対して安全配慮義務を負うか。
② 安全配慮義務を負うとした場合には、その債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、何年と解すべきか。
(判旨)
「思うに、国と国家公務員(以下、「公務員」という。)との間における主要な義務として、法は、公務員が職務に専念すべき義務(国家公務員法101条)1項前段、自衛隊法60条1項等」並びに法令及び上司の命令に従うべき義務(国家公務員法98条1項、自衛隊法56条、57条等)を負い、国がこれに対応して公務員に対し給与支払義務(国家公務員法52条、防衛庁職員給与法4条以下等)を負うことを定めているが、国の義務は右の給付義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきである。もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものであり、自衛隊員の場合にあっては、更に当該勤務が通常の作業時、訓練時、防衛出動時(自衛隊法76条)、治安出動時(同法78条以下)又は災害派遣時(同法83条)のいずれにおけるものであるか等によっても異なるべきものであるが、国が、不法行為規範のもとにおいて私人に対し、その生命、健康等を保護すべき義務を負っているほかは、いかなる場合においても公務員に対し安全配慮義務を負うものではないと解することはできない。けだし、右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として、一般的に認められるべきものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、公務員が前期の義務を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対し安全配慮義務を負いmこれを尽くすことが必要不可欠であり、また、国家公務員法93条ないし95条及びこれに基づく国家公務員法災害補償法並びに防衛庁職員給与法27条等の災害補償制度も国が公務員に対し安全配慮義務を負うことを当然の前提として、この義務が尽くされたとしてもなお発生すべき公務災害に対処するために設けられたものと解されるからである。
そして、会計法30条が金銭の給付を目的とする国の権利及び国に対する権利につき5年の消滅時効期間を定めたのは、国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜に考慮したことに基づくものであるから、同条の5年の消滅時効の定めは、右のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であって他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである。そして、国が、公務員に対する安全配慮義務を懈怠し違法に公務員の生命、健康等を侵害して損害を受けた公務員に対し損害賠償の義務を負う事態は、その発生が偶発的であって多発するものとはいえないから、右義務につき前記のような行政上の便宜を考慮する必要はなく、また、国が義務者であっても、被害者に損害を賠償すべき関係は、公平の理念に基づき被害者に生じた損害の公平な填補を目的とする点において、私人相互間における損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではないから、国に対する右損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法30条所定の5年と解すべきではなく、民放167条1項により10年と解すべきである。
会計法30条
第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
民放167条1項
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
(ポイント)
① 国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所・施設・器具等の設置管理または公務員が国や上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命・健康等を危険から保護するように配慮すべき義務を負う。つまり、安全配慮義務を負う。
② 国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任については、主として行政上の便宜を考慮して5年の短期消滅時効を定める会計法30条は適用されるべきでなく、債権の一般的消滅時効を定める民放167条1項に基づき、10年の消滅時効が適用される。
9. 温泉審議会による諮問手続(最判昭46.1.22)
(事案)
島根県知事(Y)は、温泉業者Aによる温泉湧く出量を増加させるための動力装置の設置許可申請に対し、温泉法20条に基づく温泉審議会への諮問手続につき、持ち回りの方法による決議を経たのみで許可処分を行った。(なお、その後開かれた審議会において、当該許可処分を相当とする意見が事後的には表明されている。)
これに対し、他の温泉業者であるXは、この動力装置により、その所有する温泉の湧出量が激減する等の被害を被ったとして、当該処分の有効性をめぐり提訴した。
(争点)
① 持ち回りの方法による審議会の決議は有効か。
② 事後的になされた審議会による意見表明により、瑕疵は治癒されるか。
③ 法廷の諮問手続を経なかった瑕疵は、取消原因にとどまるか、それとも無効原因となるか。
(判旨)
「原判決の確定したところによれば、本件許可処分によれば、本件許可処分にあたり、温泉審議会は開かれず、知事による温泉審議会の意見聴取は持回り決議の方法によりされたものであるというのであり、また、温泉法19条、島根県温泉審議会条例(昭和25年同県条例第31号)6条等の規定に徴すれば、右審議会の意見は、適法有効なものということはできず、右処分後に開かれた審議会の意見によっても、右の瑕疵が補正されていないことは、原判決の判示判断の通りである。
ところで、温泉法20条によれば、知事が同法8条1項等所定の規定による処分をしようとするときは、温泉審議会の意見を聞かなけらばならないこととされていることは、所論のとおりであるが、同法19条は、都道府県知事の諮問に応じ温泉およびこれに関する行政に関し調査、審議させるため、都道府県に温泉審議会を置く、右審議会の組織、所掌事務、委員その他の職員については都道府県の条例で定める旨規定しており、その他、同法の目的を定める1条、許可不許可の基準を定める4条等の規定に徴すれば、前記20条が知事に対し、温泉審議会の意見を聞かなければならないこととしたのは、知事の処分の内容を適正ならしめるためであり、利害関係人の利益の保護を直接の目的としたものではなく、また、知事は右の意見に拘束されているものではないと解される。そして、これらの諸点を併せ考えれば、本件許可処分にあたり、知事のした温泉審議会の意見聴取は前記のようなものではあるが、取消の原因としてはともかく、本件許可処分を無効ならしめるもおということはできない。
(ポイント)
① 持ち回りの方法による審議会の決議は有効ではない。
② 処分がなされた後に開かれた審議会の意見表明によって、従前の瑕疵は治癒されない。
③ 温泉法20条に基づく知事による諮問手続は、利害関係人の利益保護を目的としたものではなく、知事の処分の内容を適正ならしめるためのものにすぎないため、取消原因としてはともかく、本件許可処分を当然に無効とするものではない。
10. 公共用財産の時効取得(最判昭51.12.24)
(事案)
Xは、自作農創設特別措置法により、国(Y)から本件田の売り渡しを受け、平穏・公然に耕作を継続していたが、その土地の一部は、公図上は水路として表示されている国有地であった。そこで、Xは、売渡日より10年経過した時点で、当該部分の所有権を時効取得したとして、所有権確認の訴えを提起した。
(争点)
明示の公用廃止がなされなくとも、公共用財産を時効取得することは可能か。再度
水路に復することが容易であっても、取得時効の成立を認めてよいか。
(判旨)
「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての携帯、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されてものとして、これについて取得時効の成立を妨げないと解するのが相当である。
これを本件についてみるに、原審の確定するところによれば、1)本件係争地は、公図上水路として表示されている国有地であったが、古くから水田、あるいは畦畔に作りかえられ、本件田あるいはその畦畔の一部となり、水路としての外観を全く喪失し、本件係争地及び本件田は、被上告人の祖父が訴外Aから借り受けて小作していた当時から、幅60糎ないし75糎程度の細い畦畔によって合計45枚の水田に区分けされていた、2)被上告人は、昭和22年7月2日自作農創設特別措置法により上告人から本件田の売渡を受けたが、その当時の本件田と本件係争地の位置関係及び使用状況は、被上告人の祖父が耕作していた状態と全く同様であったため、被上告人は、本件田及び本件係争地を含んだ水田と畦畔全体を売り渡されたものと信じ、水田あるいは畦畔として平穏かつ公然に本件係争地の占有を続けたというのであり(この事実の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。)、右事実によれば、本件係争地は、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、被上告人の祖父の時代から引き続き、私人に占有されてきたが、そのために実際上公の目的が害されることもなく、もはやこれを公共用財産として維持すべき理由がなくなったことは明らかであるから、本件係争地は、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となりうるものと解すべきである。これと同旨の見解に立って本件係争地に対する被上告人の取得時効の成立を肯定した原審の判決は、正当としてぜにんすることができる。
(ポイント)
公共用財産が、長年の事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態・機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続した場合には、当該公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を認めることができる。
つまり、黙示的に公用が廃止されば、取得時効が成立する。
11.予定公物の時効取得(最判昭44.5.22)
(事案)
Xの先代Aは、自作農創設特別措置法により国から本件土地の売渡しを受け、耕作を続けていたが、その後、旧都市計画法3条に基づき、建設大臣が都市計画上の公園として当該土地を京都市(Y)の市有地として決定した。
そこで、Aの相続人であるXが、当該決定後も耕作を継続したAには取得時効の成立が認められるとして、本件土地の所有権確認を求めて提訴した。
(争点)
建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地につき、取得時効の成立は認められるか。
(判旨)
「自作農創設特別措置法の規定に基づき、政府から売渡を受けて現に被上告人らの先代が耕作していた本件土地に対し、建設大臣が都市計画法上公園に決定したとしても、上告人行都市は右土地につき直ちに現実に外見上児童公園の形態を具備させたわけではなく(公用解し行為がないことは上告人も自認している)、したがって、それは現に公共用財産としてその使命をはたしているものではなく、依然としてこれにつき被上告人らの先代の耕作占有状態が継続されてきたというのであるから、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人らの先代の本件土地に対する取得時効の進行が妨げられるものとは認められない。」
(ポイント)
予定公物であっても、取得時効が成立する。
12.村道の自由使用(最判昭39.1.16)
(事案)
Xらが生活および農業経営のため村道を利用していたところ、Yがその道路上に木を植えるとともに石材を堆積したため、Xを含む一般住民の通行が不可能となり、その上、Yが納屋を増築するに至って道路としての機能一切が消滅した。そこで、XらがYに対して通行妨害の排除を求めて提訴した。
(争点)
村民が村道を使用することについての法的権利性をどう解すべきか。その権利が侵害された場合に、妨害排除を求めることは可能か。
(判旨)
「地方公共団体の開設している村道に対しては村民各自は他の村民がその道路に対して有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行い得べきところの使用の自由権を有する。この通行の自由は公法関係から由来するものであるけれども、各自が日常生活上諸般の権利を行使するについて欠くことのできない要具であるから。これに対しては民放の保護を与うべきは当然の筋合である。故に一村民がこの権利を妨害されたときは民法上不法行為の問題の生ずるのは当然であり、この妨害が継続するときは、これが排除を求める権利を育てる。」
(ポイント)
村民は、村道を自己の生活のために使用する自由権を有するので、継続的な妨害がされた場合には、当該妨害の排除を請求できる。
13.幼年者との面会(最判平3.7.9)
(事案)
連続企業爆破犯として死刑判決を受け最高裁に上告中のXは、死刑廃止運動に関係するA女から援助を受け、その後A女の母親Bと養子縁組を結んだ。その上で、Xは、かねて文通により交流のあったA女の娘C(義理の姪、当時10歳)との面会の許可を拘置所長に求めたところ、拘置所長は、14歳未満との接見(面会)を原則として禁止する監獄法施行規則120条を理由に、許可しなかった。
そこで、Xは、規則120条が監獄法50条による委任の範囲を超えるものであって、憲法31条・13条・14条の保障する在監者と幼年者の面会権を制限するものとして違憲であること、仮に違憲でないとしても拘置所長の判断には裁量権を濫用した違法であることを理由に、本件不許可処分の取消しを求めるとともに、国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した。
憲法31条
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法13条
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法14条
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(争点)
① 監獄法施行規則(旧)120条および(旧)124条は、憲法ならびに監獄法に違反しないか。
② 拘置所長が未決拘留者と14歳未満の者との接見を許さなかったことは、国家賠償法1条1項の適用を受ける違法行為といえるか。
(判旨)
「被拘留者には一般市民としての自由が保障されるので、法45条は、被拘留者と外部の者との接見は原則としてこれを許すものとし、例外的に、これを許すと支障を来す場合があることを考慮して、(ア)逃亡又は罪証隠滅のおそれが生ずる場合にはこれを防止するために必要かつ合理的な範囲において右の接見に制限を加えることができ、また、(イ)これを許すと監獄内の規律又は秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が認められる場合には、右の障害発生の防止のために必要な限度で右の接見に合理的な制限を加えることができる、としているにすぎないと解される。この理は、被拘留者との接見を求める者が幼年者であっても異なるところはない。
これを受けて、50条は、『接見ノ立会・・・其他接見・・・ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム』と規定し、命令(法務省令)をもって、面会の立会、場所、時間、回数等、面会の態様についてのみ必要な制限をすることができる旨を定めているが、もとより命令によって右の許可基準そのものを変更することは許されないもである。
ところが、規則120条は、規則121条ないし128条の接見の態様に関する規定と異なり、『14歳未満ノ者ニハ在監者ト接見ヲ為スコトヲ許サス』と規定し、規則124条は「所長ニ於テ処遇上其他必要アリト認ムルトキハ前4条ノ制限ニ依ラサルコトヲ得」と規定している。右によれば、規則120条が原則として被拘留者と幼年者との接見を許さないこととする一方で、規則124条がその例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととしていることが明らかである。しかし、これらの規定は、たとえ事物を弁別する能力の未発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても、それ自体、法律によらないで、被拘留者の接見の自由を著しく制限するものであって、法50条の委任の範囲を超えるものといわなければならない。
しかし、規則「20条(及び124条)は明治41年に公布されて以来長きにわたって施行されてきたものであって(もっとも、規則124条は、昭和6年私法省令第9号及び昭和41年法務省令第47号によって若干の改正が行われた。)、本件処分当時までの間これらの規定の有効性につき、実務上特に疑いを挟む解釈をされたことも裁判上とりたてて問題とされたこともなく、裁判上これが特に論議された本件においても第一、第二審がその有効性を肯定していることはさきにみたとおりである。そうだとすると、規則120条(及び124条)が右の限度において法50条の委任の範囲を超えることが当該法の執行者にとって容易に理解不能であったということはできないのであって、このことは国家公務員として法令に従ってその職務を遂行すべき義務を負う監獄の長にとっても同様であり、監獄の長が本件処分当時右のようなことを予見し、又は予見すべきであっいたということはできない。
本件の場合、原審の確定した事実関係によれば、所長は、規則120条に従い、本件処分をし、被上告人とCとの接見をきょかしなかったというのであるが、右に説示したところによれば、所長が右の接見を許可しなかったことにつき国家賠償法1条1項にいう『過失』があったということはできない。」
(ポイント)
① 監獄法施行規則(旧)120条および(旧)124条は、未決交流を14歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法50条の委任の限度を超え、無効である。
② しかし、拘置所長が行った不許可処分は、長きにわたって施行され、その有効性につき実務上特に疑いを差し挟む解釈がなされていなかった規定に基づいてなされたものであるため、国家賠償法1条1項にいう過失はない。
14.銃刀法14条に基づく委任の範囲(最判平2.2.11)
(事案)
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)14条は、一般的には所持が禁止されている銃砲刀剣類のうち、美術品もしくは骨董品として価値のある古式鉄砲または美術品として価値のある刀剣類に限り、文化庁長官の登録を受ければ例外的に所持・保管が許される旨の規定を定め、同条5項において登録の方法など登録に関し、必要な細目については文部省令で定めることが規定されていた。
これに対し、Xは、自己所有の外国製刀剣(サーベル)が「美術品として価値のある刀剣類」にあたり、例外的に所持が許される刀剣であることを主張して登録を申請したところ、文化庁長官から権限の委任を受けた都教育委員会(Y)から、登録に関わる鑑定基準の対象を規定する銃砲刀剣類登録規則(文部省令)4条2項には日本刀のみが規定されていることを理由に、申請を拒否された。
そこで、Xは、銃刀法14条が外国製刀剣を署外せずに登録の基準を文部省令に委任しているにもかかわらず、登録規制が登録に関わる鑑定基準の対象を日本刀に限定していることは、法の委任の趣旨を逸脱した違法なものであるとして、当該登録規制に基づくYの申請拒否処分の取消しを求めて出訴した。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)14条
(登録)
第十四条 都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
(争点)
鑑定基準の対象を日本刀に限定する銃砲刀剣類登録規制(文部省令第2項は、銃刀法14条の委任の範囲を超えたものとして無効となるか。
(判旨)
「どのような銃刀類を我が国において文化財的価値を有するものとして登録の対象とするのか相当であるかの判断には、専門的知識経験を有する登録審査委員の鑑定に基づくことを要するものとともに、その鑑定の基準を認定すること自体も専門技術的な領域に属するものとしてこれを規則に委任したものというべきであり、したがって、規則においていかなる鑑定の基準を定めるかについては、法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内において、所轄行政庁に専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているものと解するのが相当である。
要件が法の委任の趣旨を逸脱したものであるか否かをみるに、刀剣類の文化財的価値に©着目してその登録の途を開いている前記法の趣旨を勘案すると、いかなる刀剣類が美術品として価値があり、その登録を認めるべきかを決する場合にも、その刀剣類が我が国において有する文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱するものというべきではない。」
(ポイント)
登録規制4条2項が鑑定基準の対象を美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃刀法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものであるから、法の委任の趣旨を逸脱する無効のものではできない。つまり、委任の範囲内である。
15.学習指導要領の法的性質(最判平2.1.18)
(事案)
福岡県伝習館高校の社会科教諭のXらが、学習指導要領の目標および内容うぃ逸脱した指導や教科書の不使用、考査の不実施などを理由に県教育委員会から懲戒免職処分を受けたため、当該処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
① 文部省告示たる高等学校学習指導要領に法規性は認められるか。
② 懲戒権者による裁量権の逸脱があるか。
(判旨)
「思うに、高等学校の教育は、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とするものであるが、中学校の教育の基礎の上に立って、所定の修業年限の間にその目的を達成しなければならず(学校教育法41条、46条参照)、また、高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な影響力、支配力を有しており、生徒の側には、いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。これらの点からして、国が、教育の一定水準を維持しつつ、高等学校教育の目的達成に資するために、高等学校教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり、特に法規によってそのような基準が定立されている事柄については、教育の具体的内容及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存在するのである。
本件における前記事実関係によれば、懲戒事由に該当する被上告人らの前記各行為は、高等学校における教育活動の中で枢要な部分を占める日常の教科の授業、考査ないし生徒の成績評価に関して行われたものであるところ、教育の具体的内容及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量を前提としてもなお、明らかにその範囲を逸脱して、日常の教育の在り方を律する学校教育法の規定や学習指導要領の定め等に明白に違反するものである。
以上によれば、上告人が、所管に属する福岡県下の県立高等学校の教諭等職員の任免其の他の人事に関する事務を管理執行する立場において、懲戒事由に該当する被上告人らの態様、懲戒処分歴等の諸事情を考慮のうえ決定した本件各懲戒処分を、社会通念上著しく妥当を欠くものとまではいい難く、その裁量権の範囲を逸脱したものと判断することはできない。
(ポイント)
① 学校教育法とともに、文部省告示たる高等学校学習指導要領にも法規性は認められる。
② {C}Xらの行為には学校教育法・学習指導要領の定めに明白に違反する事実が認められるのため、懲戒権者たる福岡県教育委員会の処分に裁量権の範囲を逸脱していない。
16.通達に対する取消訴訟(最判昭43.12.24)
(事案)
本件通達は、昭和35年3月8日に厚生省公衆衛生環境衛生部長から各都道府県指定都市衛生主管部長にあてて発せられたものであるが、それは、当時、創価学会と他の既成宗教団体との間の対立から、創価学会員の家族の埋葬拒否事件が全国の墓地において頻発したため、これを是正すべく、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由として埋葬の求めを拒むことは墓地、舞相当に関する法律13条が認める「正当な理由」にはあたらないとの内閣法制局第一部長の趣旨に沿って今後の事務処理を行うよう求める内容のものであった。
そのため、墓地を経営する真言宗の一寺院であるXが、本件通達は、従来慣習法上認められていた異宗派を理由とする埋葬拒否権の内容を変更し、新たにXに対して一般第三者の埋葬請求を受忍すべき義務を負わせたものであって、この通達により、以後このような理由による埋葬拒否に対しては刑罰を科せられるおそれがあるとともに、現にこの通達が発せられてから多くの損害や不利益を被っているとして、本件通達の取消しを求める訴えを提起した。
(争点)
本件の通達は、行政事件訴訟法に基づく取消しの訴えの対象となりうるか。
(判旨)
「本件通達は、厚生省公衆衛生局環境衛生部長から都道府県指定都市衛生主管部局長にあてて発せられたので、その内容は、墓地、埋葬等に関する法律13条に関し、昭和24年8月22日付東京都衛生局長あて回答に示しオタ見解を改め、今後は内閣法制局第一部長の昭和35年2月15日付回答の趣旨にそって、解釈、運用することとしたことを明らかにすると同時に、諸機関において、この点に留意して埋葬等に関する事務処理をすると同時に、諸機関において、この点に留意して埋葬等に関する事務処理をするよう求めたものであり、行政組織および右法律の施行事務に関する関係法令を参酌すれば、本件通達は、被上告人がその権限にもとづき所掌事務について、知事を含めた関係行政機関に対し、法律の解釈、運用の方針を示して、その職務権限の行使を指揮したものと解せられる。
元来、通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員に対する行政機関内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に拘束されることはあっても、一般の国民は直接これに拘束されるものではなく、、このことに、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。
このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用あたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合いである。
このような通達一般の性質、前述した本件通達の形式、内容および原判決の引用する一審判決認定の事実(挙示の証拠に照らし背認することができる。)その他原審の違法に確定した事実ならびに墓地、埋葬等に関する法律の規定を併せて考えれば、本件通達は従来とらえられていた法律の解釈や取扱いを変更するものではあるが、それはもっぱら知事以下の行政機関を拘束するにとどまるもので、これらの機関は右通達に反する行為をすることはできないにしても、国民は直接これに拘束されることはなく、従って、右運動が直接に上告人の所論墓地経営権、管理権を侵害したり、新たに埋葬の受忍義務を課したりするものとはいえない。また、墓地等に関する法律21条違反の有無に関しても、裁判所は本件通達における法律解釈に拘束されるものではないのみならず、同法13条にいわゆる正当の理由の判断にあたっては、本件通達に示されている事情以外の事情をも考慮すべきものと解せられるから、本件通達が発せられたからといって直ちに上告において刑罰を科せられるおそれがあるともいえず、さらにまた、原審において上告人が主張するような損害、不利益は、原判示のように、直接本件通達によって被ったものということもできない。
そして、現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達中所轄の趣旨部分の取消しを求める本件訴は許されないものとして却下すべきものである。」
(ポイント)
通達は、原則として、法規の性質をもたず、上級行政機関が関係下級行政機関・職員に対しての職務権限の行使を指揮し、職務に対して命令するために発するものにすぎないので、一般の国民は直接これに拘束されない。行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になりうるのは、国民の権利義務や法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼす行政処分等でなければならない。したがって、通達の取消しを求める訴えは許さない。
つまり、通達は訴えの対象とならない。
17.みなし道路の一括指定(最判平14.1.17)
(事案)
Xは、奈良県御所市内の都市計画区域内に土地を所有していたところ、奈良県知事(Y)は、昭和37年12月28日付けの奈良県告示第327号により、「都市計画区域内において建築基準法施行の際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満1.8m以上の道については、建築基準法42条2項の規定により、同1項が規定する道路とみなすところの道路(みなし道路)に当たる」旨を指定した。
そのため、Xがその所有地上に建物の新築工事をするための建築確認申請に先立って、当該土地の一部である通路上の土地(本件通路部分)がこの「みなし道路(2項道路)」にあたるか否かを奈良県高田土木事務所に照合したところ、平成元年1月30日に建築主事から本件道路部分が「みなし道路(2項道路)」にあたる旨の回答がされた。
そこで、Xは、本件道路が建築基準法42条2項の要件をみたしておらず、本件通路部分についての指定部分は、存在しないことの確認を求める訴訟を提起したが、原審(大阪高判平10.6.17)は、Yによる当該告示は、包括的に一括して幅員4m未満1.8m以上の道を「みなし道路(2項道路)」とすることを定めたにとどまるものであって、本件通路部分といった特定の土地について個別具体的に指定したものではなく、不特定多数の者に対して一般的抽象的な基準を定立するものにすぎないから、これにより直ちに建築制限等の私権の制限を生じるものとして抗告訴訟の対象となる行政処分にあたると解することはできないとして、Xの訴えを却下した。そこで、Xが上告した。
(争点)
告示により一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は、抗告訴訟の対象となる処分に該当するか。
(判旨)
「本件告訴は、幅員4m未満1.8m以上の道を一括して2項道路として指定するものであるが、これによって、法第3章の規定が適用されるに至った時点において現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道のうち、本件告示の定める幅員1.8m以上の条件に合致するものすべてについて2項道路としての指定がされたこととなり、当該道につき指定の効果が生じるものと解される。原判決は、特定の土地について個別具体的に2項道路の指定をするものではない本件告示自体によって直ちに試験制限が生じるものではない旨をいう。しかしながら、それが、本件告示がされた時点では2項道路の指定の効果が生じていないとする趣旨であれば、結局、本件告示の定める条件に合致する道であっても、個別指定の方法による指定がない限り、特定行政庁により2項道路の指定がないことに帰することとなり、そのような見解は相当とはいえない。
そして、本件告示によって2項道路の指定の効果が生じるものと解する以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路とされ、その敷地所有権は当該道路につき道路内の建築物が制限され(法44条)、私道の変更又は廃止が制限される(法45条)等の具体的な試験の制限を受けることになるのである。そうすると、特定行政庁による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
したがって、本件告示のような一括指定の方法による2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解すべきである。
そして、本件訴えは、本件通路部分について、本件告示による2項道路の指定の不存在確認を求めるもので、行政事件訴訟法3条4項にいう処分の存否のかくにんを求める抗告訴訟であり、同法36条の要件を満たすものということができる。
行政事件訴訟法3条4項
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法36条
(無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
(ポイント)
特定行政庁による2項道路の指定が一括指定の方法でされた場合でも、それにより指定の効果が及び道における敷地所有者は、当該道路内の建築物等が制限され、私道の変更・廃止が制限されるといった具体的な私権の制限を受けることになるので、そのような一括指定の方法による2項道路の指定も、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものであり、抗告訴訟の指定も。個人の権利義務に対して直接影響を与えるものであり、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
18.パチンコ球遊器事件(最判昭33.3.28)
(事案)
旧物品税法1条1項は、課税対象物品の一つとして「遊戯具」を挙げていたが、パチンコ球技器については同法にも同法施行規則にも明記がなく、約10年間にわたって物品税が賦課されない状態が続いていた。昭和26年3月2日の東京国税局長から管下税務署長に対する通達においてパチンコ球遊器が「遊戯具」にあたる旨が示され、これに従い、品川・大森・蒲田・墨田の各税務署長(Yら)に対し、物品税課税処分行った。
そこで、Xらは、被課税累計額計約238万円を納付した上で、本件処分の無効確認と納付金の返還を求めて出訴した。
(争点)
本件課税処分は、法律に基づかない「通達課税」であり、租税法律主義に反するのではないか。
(判旨)
「物品税は、物品税法が施行された当初(昭和4年4月1日)においては、消費税として出発したものではあるが、その後次第に生活必需品その他いわゆる資本的消費財も課税品目中に加えられ、現在の物品税法(昭和15年法律第40号)が制定された当時、すでに、一部生活必需品(たとえば隣寸)(第1条大3号)や「撞球台」(第1条第二種甲類1)」「乗用自動車」(第1条第二種甲類14)等の資本財もしくは資本財らり得べきものも課税品目として揚げられ、その後の改正においてさらにこの種の品目が数多く追加されたこと、いわゆる消費的消費財と生産的消費財との区別はもともと相対的なものであって、パチンコ球遊器も自家用消費財としての性格をまったく持っていたとはいい得ないこと、その他第一、第二判決の揚げるような理由にかんがみれば、社会通念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり、現判決も、もとより、所論のように、単に立法論としてパチンコ球遊器をぁ税品目に加えることの妥当性を論じたものではなく、現行法の解釈として「遊戯具」中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、右判決は正当である。
なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであったとしても、通達の内容が正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであって、採用し得ない。」
(ポイント)
課税が通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上。その課税処分は法の解釈に基づくs誤聞であり、租税法律主義に反しない。
19,市街地再開発事業計画の決定・公告(最判平4.11.26)
(事案)
大阪市(Y)は、都市再開発法54条1項に基づき、阿部野地区における第二種市街地再開発事業の事業計画を決定し、その公告をしたが、当該地区内に不動産を所有するXは、本件事業計画決定の違法性を主張してその取消しを求めた。これに対し、第一審(大阪地判昭61.3.26)は事業計画決定の処分性を否定し、訴えを却下したが、第二審(大阪高判昭63.6.24)は事業計画決定の処分性を認め、本件を一審に差し戻したため、Yが上告した。
(争点)
都市再開発法に基づく第二種事業の事業計画決定は抗告訴訟の対象となるか。
(判旨)
「都市再開発法51条1項、54条1項は、市町村が、第二種市街地再開発事業を施行しようとするときは、設計の概要について都道府県知事の認可を受けて事業計画(以下「再開発事業計画」という。)を決定し、これを抗告しなければならないものとしている。そして、第二種市街地再開発事業については、土地収用法3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなして同法の規定を適用するものとし(都市再開発法6条1項、都市計画法69条)、都道府県知事がする設計の概要の許可をもって土地収用法20条の規定による事業の認定に代えるものとするとともに、再開発事業計画の決定の公告をもって同法26条1項の規定による事業の認定の告示とみなすものとしている(都市再開発法6条4項、同法施行令1条の6、都市計画法70条1項)。したがって、再開発事業計画の決定は、その広告の日から、土地収用法上の事業の認定と同一の法律効果を生ずるものであるから(同法26条4項)、市町村は、右決定の公告により、同法に基づく収用権限を取得するとともに、その結果として、施行地区の土地の所有者は、特段の事情のない限り、自己の所有地等が収用されるべき地位に立たされていることになる。しかも、この場合、都市再開発法上、施行地区内の宅地の所有者等は、契約又は収用により施行者(市町村)に取得される当該宅地等につき、公告があった日から起算して30日以内に、その対償の払渡しを受けることとするか又はこれに代えて建築施設の部分の譲受け希望の申出をするかの選択を余儀なくされるのである(同法118条の2第1項1号)。
そうであるとすると、公告された再開発事業計画の決定は、施行地区得内の土地の所有者等の法的地位を直接的な影響を及ぼすものであって、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。」
(ポイント)
都市再開発法に基づき地方公共団体により定められ公告された第二種市街地再開発事業の事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
20.工場誘致計画の変更(最判昭56.1.27)
(事案)
沖縄県宜野座村(Y)の村議会は、X会社の工場を誘致するため、村所地を工場敷地の一部として譲渡する旨の決議を行った。そのため、X側も村有地の耕作者らに補償料を払い、整地工事等の行為も完了した。ところが、その後行われた村長選挙で本件工場進出反対の候補が当選し、Xが提出した工場の建築確認申請に不同意の旨の通知をした。
そこで、Xは、Yの協力拒否のために工場の建設・操業が不可能になり損害を被ったとして、損害賠償請求訴訟を提起した(元本額5574万5614円)。
(争点)
地方公共団体が一定の継続的な施策を計画・決定し、それに基づき特定の者に対して当該施策に適合する活動を個別具体的に勧告・誘致した後に当該施策を変更した場合、相手方に対して違法な加害行為を行ったものとして損害賠償責任を負うか。
(判旨)
「地方公共団体の施策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆる住民自治の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する見本原則であり、また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基礎として維持されるものと信頼し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右活動ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき審議衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかる信頼に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのではない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして前記住民自の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方を保護しないことが許されるものと解すべきではない。
(ポイント)
地方公共団体が計画・決定した施策に基づきなされた勧告・勧誘に動機づけられて活動に入った者が、その後の施策の変更により社会通念上看過することのできない程度の積極的損害を被った場合には、これにつき補償等の代償的措置を講じないまま施策を変更した当該地方公共団体は、やむを得ない客観的事情がない限り、損害賠償責任を免れない。
つまり、損害賠償責任を負う場合あり。
21.病院開設中止勧告に対する抗告訴訟(最判平17.7.15)
(事案)
Xは、富山県高岡市内にて病院の解説を計画し、富山県知事(Y)に対して医療法7条1項に基づく許可申請をしたところ、Yは、高岡医療圏における病院の病床数が富山県地域医療計画に定める必要病床数に達していることを理由に開設を中止するよう勧告した。これに対し、Xが、当該勧告を拒否するとともに、速やかに本件申請に対する許可をするよう文書で求めたため、Yは本件申請を許可する旨の処分をしたが、その際、富山県厚生部長名で「中止勧告にもかかわらず病院を開設した場合には、厚生省通知において、保険医療機関の指定の拒否をすることとされているので、念のため申し添える」との通告文書が送付された。
そこでXは、本件勧告は医療法30条の7に反するもので違法であり、また本件勧告とともになされた許可処分はいわば負担付きの許可であるとして、本件勧告の取消しまたは本件通告部分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
① 病院開設の中止勧告は、行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」といえるか。
② 本件の保険医療機関の指定の拒否があり得る旨の通告は、同法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」といえるか。
(判旨)
「富山県厚生部長名の本件通告部分をもって被上告人がした病院開設中止勧告と解することはできないから、その取消しを求める訴えを却下するべきものとした原審の判断を是認することができる。
しかし、医療法及び健康保険法の規定の内容やその運用の実情に照らすと、医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められているけれども、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当限度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。そして、いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては、健康保険、国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどなく、保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから、保険医療機関の指定を受けることができない場合には、実際上病院の開設自体をだんねんせざるを得ないことになる。このような医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。後に保険医療機関の指定拒否処分の効力を抗告訴訟によって争うことができるとしても、そのことは上記の結論を左右するものではない。
したがって、本件勧告は、行政事件訴訟法3条2項の『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』に当たるというべきである。」
(ポイント)
① 医療法30条の7に規定に基づく病院開設中止の勧告は、行政指導として定められてはいるが、これに従わない場合には相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものであり、その効果・意義から、当該勧告は行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」にあたる。
行政指導は、事実行為であることから、原則として処分性が否定される。この判決は、行政指導である病院開設中止の勧告の処分性を肯定したものであり、要注意である。
●行政指導の処分性
原則・・・否定
例外・・・病院開設中止の勧告→肯定
② ただし、富山県厚生部長名でなされた通告は、富山県知事がした病院開設中止勧告と解することはできないから、同法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」ではない。
22.執拗な退職勧奨に対する慰謝料請求(最判昭55.7.10)
(事案)
下関市立商業高校に勤務するXら3人の教諭に対し、下関市教育委員会が長期・多数回にわたり退職勧奨(いわゆる「肩たたき」)を継続したため、当該一連の行為により精神的苦痛を受けたとして、Xらが下関市(Y)に対して国家賠償法に基づく慰謝料の支払いを求めて出訴した。
(争点)
執拗な退職勧奨は、国家賠償法に基づく慰謝料請求の対象となるか。
(判旨)
「被勧告者は何らの拘束なしに自由にその意思を決定しうるのはもとより、いかなる場合でも勧奨行為に応ずる義務もないと解するのが相当である。なお勧奨は一定の方法にしたがって行われる必要はなく、退職を求める人事行政上の事情や、被勧奨者の健康状態、勤務に対する適応性、家庭の事情その他被勧奨者の要望等具体的状況に応じて、退職の同意を得るために適切な種々の観点から説得方法を用いることができるが、いずれにしても、被勧奨者の任意の意思形成を妨げ、あるいは名誉感情を害するごとき言動が許されないことは言うまでもなく、そのような勧奨行為は違法な権利侵害として不法行為を構成する場合があることは当然である。」
(ポイント)
本来の目的である被鑑賞者の自発的な退職意思の形成を促す限度を超える心理的圧力を加えた場合には、違法な権利侵害として不法行為を構成する。
23.指導要綱に基づく開発負担金(最判平5.2.18)
(事案)
武蔵野市(Y)は、相次ぐマンション建設から市民の生活環境を守るため、一定規模以上の宅地開発または中高層建築物の建設を行おうとする事業主等に対する行政指導の内容を定める「武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱」を制定してきたが、その中には、事業主が「寄付願」を市長に提出して教育施設負担金を納付することも規定されていた
そこで、昭和52年に3階建てマンションの建築を計画し、教育施設負担金として1523万2000円の寄付を要請され、減免等の懇願も拒絶された結果、やむなく同額を納付したXが、当該寄付行為が強迫に基づくものであることを理由とした取消しと、武蔵野市による行政指導が違法な公権力の行使に当たることを理由とした国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を主張して出訴した。
(争点)
建設指導要綱に基づく寄付の要請は、国家賠償法1条1項に規定する違法な権力の行使にあたるか。
(判旨)
「行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、適法ということはできない。
被上告人がAに対し指導要領に基づいて教育施設の納付を求めた行為も、被上告人の担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、Aに対し、指導要綱所定の教育施設負担金をのうふしてなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって、マンションを建築しようとする以上右行政指導に従うことを余儀なくされるものであり、Aに教育施設負担金の納付を事実上強制しいようとしたものということができる。指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持をうけていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」
(ポイント)
本来の行政指導は、事業主の任意性を損なうことがない限り違法ではないが、事実上の強制にあたり、従うことを余儀なくされるものである場合、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使にあたる。
24.品川区マンション事件(最判昭60.7.16)
(事案)
Xは、昭和47年10月28日に本件マンションの建築確認申請を東京都(Y)にしたところ、付近住民からの反対運動を考慮したYが、Xに対して付近住民との話合いによる円満解決を指導し、Xもこれに応じて十数回の話合いを付近住民と行ったが、解決には至らなかった。
そうこうするうちに、Yは、昭和48年2月15日になって新高度地区案を発表し、その中で付近住民との紛争が解決しない事案については確認処分を行わない旨を定め、これに従い、Xに対しても、新高度地区案に沿った形での設計変更を求めるとともに、付近住民との話合いをさらに進めるよう勧告した。
そこで、Xは、確認処分留保を背景とするYの行政指導にはもはや服さない旨を表明し、同年3月1日に建築審査会に本件確認申請についての審査請求をしたが、結局、3月30日に至って金銭補償により住民との紛争を解決するとともに審査請求を取り下げたため、Yの建築主事も本件申請についての建築確認処分をした。しかし、Xは、当該確認申請に対する審査が終了しているにもかかわらず付近住民との話合いを強制的に指導し、その期間中確認処分を留保したYの行政処分は違法であるとして、確認留保期間中の請負代金の増加額と金利相当額の損害賠償をYに求める訴訟を提起した。
(争点)
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することは、国家賠償法1条1項に規定する違法な公権力の行使にたるか。
(判旨)
「建築基準法(以下「法」という。)6条3項及び4項によれば、建築主事は、同条1項所定の建築確認の申請書を受理した場合においては、その受理した日から21日(ただし、同条1項4号に揚げる建築物に係るものについては7日)以内に、申請に係る建築物の計画が当該建物の計画が当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは確認の通知を、適合しないと認めたときはその旨の通知(以下あわせて「確認処分」という。)を当該申請者に対して行わなければならないものとさだめられている。
しかしながら、建築主事の右義務は、いかなる場合にも例外を許さない絶対的な義務であるとまでは解することができないというべきであって、建築主事が確認処分の留保につき任意にしているものと認められる場合のほか、必ずしも右の同意のあることが明確であるとはいえない場合であっても、諸般の事情から直ちに確認処分をしないで応答を留保することが法の趣旨目的に照らし社会通念上合理的と認められるときは、その間確認申請に対する応答を留保することをもって、確認処分を違法に遅滞するものということはできないというべきである。
もっとも、右のような確認処分の留保は、建築主事の任意の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受任を強いることは許されない筋合いのものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導がおこなわれているとの理由だけで確認処分を留保することは、違法であると解するのが相当である。
したがって、いったん行政指導に応じて事業主と付近住民との間に話合いによる紛争解決をめざして協議が始められた場合でも、右協議の進行状況及び四囲の客観的状況により、建築主において建築主事に対し、確認処分を留保したままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、当該確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めているものと認められるときには、他に前記特段の事情が存在するものと認められない限り、当該行政処分を理由に建築主に対しっ確認処分の留保の措置を受忍せしめることの許されないことは前述のとおりであるから、それ以後の右行政指導を理由とする確認処分の留保は、違法となるものといわなければならない。
(ポイント)
建築主が確認申請に対する処分が留保されたままでの行政指導には協力できない旨の意思を真摯かつ明確に表明して申請に対する応答を求めたときには、特別の事情がない限り、行政指導が継続していることだけを理由とする確認処分の留保は国家賠償法1条1項に規定する違法な公権力の行使に該当する。
なお、平成6年10月から施行された行政手続法33条によって、本件のような場合を、明確に規制した。
25.営業許可を受けない食肉買入契約の効力(最判昭35.3.18)
(事案)
X社は、食品衛生法による許可を受けて食肉の販売を営んでいるA社に精肉を卸していたが、A社の支払いが滞りがちだったため取引を一時中止した。そのため、A社の代表取締役YがY個人として食肉を買い受けたい旨を懇請し、X社もこれを承諾して取引を再開したが、Yは内金を支払ったのみで残代金を支払わないことから、X社が残代金および遅延損害金の支払いを求めて出訴した、これに対して、Yは、Y個人が食品衛生法に基づく営業許可を受けていないことを理由に、本件契約が民放90条に違反し無効である旨を主張した。
民放90条
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(争点)
食品衛生法に基づく食肉販売業許可を受けない者との間でなした食肉の売買契約は、単なる取締法規違反か。
(判旨)
「本件売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食品販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。それ故右許可の有無は本件取引の私法上の効力に消長を及ぼすものではないとした原審の判断は結局正当であり、所論を採るを得ない。
(ポイント)
営業許可を受けない者がした食肉の買入契約は無効ではない。つまり、無許可の行為でも、その効力自体は有効である点に注意。
26.行政庁の承認を受けない農地賃借権移転(最判昭31.4.13)
(事案)
Aは、その所有する農地の賃借権をBからXに移転させていたころ、当該農地は政府に買収された上で、兵庫県知事(Y)により一部がCほか3名に、残部についてはXに売り渡す処分がなされた。これに対し、Xは、当該農地は全体について自作農創設特別措置法17条1項1号により自分に売り渡されるべきものであるとして、Cらに対する売渡処分の取消しを求めて出訴したが、Yは、BからXへの本件農地に関する賃借権の移転については、農地調整法に基づく村農地委員会の承認を受けていないことから無効であり、Cらへの売渡処分は自作農創設特別措置法施行令17条1項7号により正当である旨を主張した。
なお、本件農地に関する賃借権の移転については、AとXから耕作変更届が村農地委員会に提出されていたが、同委員会はこれを単なる陳情書として取り扱い、未承認のままになっていた経緯があり、この点につき、Yは、農地賃借権の移転に関する承認は合議制の行政庁たる農地委員会の自由裁量行為に属する旨を主張している。
(争点)
市町村農地委員会が(改正前の)農地調整法4条に基づいて行う農地賃借権の設定・移転に関する承認は、同委員会の自由裁量行為といえるか。
(判旨)
「論旨は、昭和24年法律第215号による農地調整法改正前の同法4条は、承認について何等客観的基準を設けておらず、従って承認は行政庁の自由裁量に属するに関わらず、原判決が改正後の規定を類推して羈束行為であるとしたのは、法律の解釈を誤った違法があるというのである。
しかし、農地に関する賃借権の設定移転は本来個人の自由契約に委ねられていた事項であって、法律が小作権保護の必要上これに制限を加え、その効力を承認にかからせているのは、結局個人の自由の制限であり、法律が承認について客観的な基準を定めていない場合でも、法律の目的で必要な限度においてのみ行政庁も承認を拒むことができるのであって、農地調整法の趣旨に反して承認を与えないのは違法であるといわなければならない。換言すれば、承認するかしないかは農地委員会の自由な裁量に委せられているのではない。
論旨は被上告人が提出したのは耕作変更届であって、法令に規定する承認申請所ではないというのである。しかし、かかる書面の趣旨が届出であるか承認申請であるかは、書面の文字によってのみ判断すべきものではない。農地調整法4条によって賃借権の設定、移転について承認、許可が必要である以上、当該行政機関としては耕作変更届と記載されていてもこれを承認許可を求める趣旨と解するか或は書面の訂正を求めるかすべきであって、届と記載してあるからといって、単なる陳述書として取り扱うことはゆるされないものと解すべきである。」
(ポイント)
農地賃借権の設定・移転に関する承認は、市町村農地委員会の自由裁量に委ねられていない。
自由裁量行為ではなく、羈束裁量行為である。
●羈束裁量行為と自由裁量行為
羈束裁量行為・・・裁判所が社会通念を基準に行政庁が行うべき行為の限界を判断す
ることができる裁量行為をいう。
自由裁量行為・・・どのような行為をするか、広く行政庁に委ねられている裁量行為
をいう。
27.マクリーン事件(最判昭53.10.4)
(事案)
アメリカ人であるXは、当時の出入国管理令に基づき、在留期間を1年とする許可を受けてわが国に滞在していたが、さらに1年間の在留期間の更新を法務大臣(Y)に申請したところ、在留期間中の無届転職と政治活動を理由に、出獄準備期間としての120日間の更新を許可されただけで、1年間の更新については、それを適当と認める足りる相当な理由があるとはいえないとして拒否された。そこで、Xは、当該不許可処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由の有無に関する判断について、法務大臣の裁量権はどの程度認められるものであり、それに対する裁判所の司法審査はどの範囲で及ぶのか。
(判旨)
「憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内にうけいれるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていること、その考えを同じくするものと解される。したがって、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。そして、上述の憲法の趣旨を前提として、法律としての効力を有する出入国管理令は、外国人に対し、一定の期間を限り特定の資格によりわが国への上陸を許された外国人は、その在留期間が経過した場合には当然わが国から退去しなければならない。もっとも、出入国管理令は、当該外国人が在留期間の延長を希望するときには在留期間の更新を申請することができることとしているが(21条1項、2項)、その申請に対しては法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限りこれを許可することができるものと定めている(同条3項)のであるから出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものではないことは、明らかである。
右のように出入国管理令が原則として一定の期間を限って外国人の我が国への上陸及び在留を許しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と道メルに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可することとしているのは、法務代位人に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨に出たものであり、そして、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される。すなわち、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保険・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って、申請者の申請事項の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼穣など諸般の事情をしんさくし、時宣に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができないものと考えられる。このような点にかんがみると、出入国管理令21条3項所定の『在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由』があるかどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲が広汎なものとされているのは当然のことであって、所論のように上陸拒否事由又は過去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許されないとかいすべきものではない。
したがって、裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたっては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が社会通念に照らしい著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。」
(ポイント)
出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は、法務大臣の(自由)裁量に任されているものであり、裁判所はこの判断が裁量権の範囲を超えまたはその濫用があった場合にのみ、いほうとすることができる。
●自由裁量行為に対する司法審査
原則・・・否定
例外・・・逸脱または濫用→肯定
28.個室付浴場事件(最判昭53.6.16)
(事案)
被告Y社は個室付公衆浴場を開始したが、当該施設から134.6メメートルしか離れていないとことには山形県余目町立のA児童遊園があり、風俗営業等取締法4条の4(現行風俗営業法28条1項)では、児童福祉法7条に規定する児童福祉施設から200メートル以内で個室付公衆浴場を営むことは禁止されていることから、Y社は風俗営業等取締法違反に問われて国(X)から起訴された。
これに対して、Y社は、当該児童福祉施設の設置に係る山形県知事の認可処分は、もっぱらY社の営業を阻止する目的で余目町が申請したものに対してなされたものであり、行政圏の濫用に相当して違法であるとして、無罪を主張した。
(争点)
風俗営業等取締法4条の4に規定する児童福祉法7条に基づく児童福祉施設として、山形県知事がなした本件児童遊園設置の許可処分には、行政権の濫用に相当する違法性があるといえるか。
(判旨)
「本件の争点は、山形県知事のA児童遊園設置認可処分(以下「本件認可処分」という。)の違法性、有効性にある。すなわち、風俗営業等取締法は、学校、児童福祉施設などの特定施設と個室付浴場業の一定区域内における併存を例外なく全面的に禁止しているわけではない(同法4条の4第3項参照)ので、被告会社の営業に先立つ本件認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているときには、A児童遊園の存在を被告会社の営業を規制する根拠にすることは許されないことになるからである。
ところで、原判決は、余目町が山形県の関係部局、同県警察本部と協議し、その示唆を受けて被告会社の営業の規制をさしあたっての主たる動機、目的として本件認可の申請をしたこと及び山形県知事もその経緯を知りつつ本件認可処分をしたことを認定しながら、A児童遊園を認可施設にする必要性、緊急性の有無については具体的な判断を示すことなく、公共の福祉による営業の自由の制限に依拠して本件認可処分の違法性、有効性を肯定している。また、記録を精査しても、本件当時余目町において、被告会社の営業の規制以外に、A児童遊園を無認可施設から認可施設に整備する必要性、緊急性があったことをうかがわせる事情は認められない。
本来、児童施設は、児童に健全な遊びを与えてその健康に増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設(児童福祉法40条参照)なのであるから、児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社の営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえない。
そうだとすれば、被告会社の本件営業については、これを規制しうる児童福祉法7条に規定する児童福祉施設の存在についての証明を欠くことになり、被告会社に無罪の言渡をすべきものである。したがって、原判決及び第一審判決は、犯罪構成要件に関連する行政処分の法的評価を誤って被告会社を有罪としたものにほかならず、右の違法は判決に影響を及ぼすもので、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
(ポイント)
個室付浴場業の規制を主たる動機・目的とする知事がした本件児童遊園設置認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。
29.公立大学の学生に対する懲戒処分(最判昭29.7.30)
(事案)
京都府立医科大学付属女子専門部の教授会は、同専門部に属するA教授の進退問題を審議するための会議を開こうとしたが、A教授の解雇反対を主張する学生達によって会議室は混乱し、教授会は流会となった。このため、京都府立医科大学学長Yは、専門部教授会における学生達の行為は学生の本分にもとり学内の秩序を乱すものであるとして、本科の学生5名(Xら)の放学処分を行った。
これに対して、Xらは、当該懲戒処分は学長としての裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとして、本件放学処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
公立大学の学生に対する懲戒処分は、学長の羈束裁量行為と解すべきか、それとも自由裁量行為と解すべきか。
(判旨)
「大学の学生に対する懲戒処分は、教育施設としての大学の内部規律を維持し教育目的を達成するために認められる自律的作用にほかならない。そして、懲戒権者たる学長が学生の行為に対し懲戒処分を発動するに当り、その行為が懲戒に値するものであるかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかを決するについては、当該行為の軽重のほか、本人の性格および平素の行状、右行為の他の学生に与える影響、懲戒処分の本人および他の学生におよぼす訓戒的効果等の諸般の要素を考量する必要があり、これらの点の判断は、学内の事情に通ぎょうし直接教育の衝に当るものの裁量に任すのでなければ、適切な結果を期することができないことは明らかである。それ故、学生の行為に対し、懲戒処分を発動するかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶかを決定することは、その決定が全く事実上の根拠に基づかないと認められる場合であるか、もしくは社会通念上著しく妥当を欠き懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えるものと認められる場合を除き、懲戒権者の裁量に任されているものと解するのが相当である。原審が上告人等に対する退学処分は懲戒権者たる学長の裁量権の範囲内の行為であると判断したことは正当であって、論旨は採用に値しない。」
(ポイント)
公立大学の学生の行為に対して懲戒処分を発動するかどうか、および懲戒処分のうちのいずれの処分を選ぶかを決定することは、その決定が全く事実上の根拠に基づかないと認められる場合であるか、または社会観念上著しく妥当を欠き懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものと認められる場合を除き、学長の裁量権に任される。つまり、学長の自由裁量行為である。
30.朝日訴訟(最判昭42.5.24)
(事案)
Xは、昭和17年から国立岡山療養所に単身の肺結核患者として入所し、厚生大臣(現厚生労働大臣)の設定した生活扶助基準で定められた最高金額たる付き600円の日用品費の生活扶助と現物による給食医療扶助とを受けていたが、昭和31年8月以降において実兄Cから毎月1500円の送金を受けるようになったため、津山社会福祉事務所長はこれを収入と認定し、月額600円の生活扶助を打ち切り、右送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部としてXに負担させる旨の保護変更を決定した。
これに対して、Xは、岡山県知事に対する不服申し立てを経て厚生大臣(Y)に不服を申し立てたが、昭和32年2月15日にこれを却下する旨の本件裁決を受けたため、600円の基準金額は生活保護法が規定する健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するに足りない違法なものであるとして、厚生大臣がなした本件却下裁決の取消しを求めて出訴した。
第一審東京地裁昭和35年10月19日判決はXの主張を認めて請求を任用したが、第二審の東京高等裁判昭和38年11月4日判決は請求を棄却したためXが上告したところ、Xが間もなく死亡した。そこで、その養子夫婦A・Bが生活保護受給権を相続したとして訴訟承継を主張した。
(争点)
① 被保護者が死亡しても、相続人により生活保護処分に関する採決取消訴訟は承認され得るか。
② 生活保護法8条に基づく厚生大臣の保護基準設定行為は、厚生大臣の自由裁量行為といえるか、また、いえるとしても本件基準につき裁量権の逸脱または濫用は認められないか。
(判旨)
「おもうに、生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれをお譲渡し得ないし(59条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。また、被保険者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、医療扶助の場合はもちろんのこと、金銭給付を内容とする生活扶助の場合でも、それは当該被保険者の最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであって、法の予定する目的以外に流用することを許されないものであるから、当該被保険者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ない、と解するのが相当である。また、所論不当利得返還請求権は、保護受給権を前提としてはじめて成立するものであり、その保護受給権が右に述べたように一身専属の権利である以上、相続の対象となり得ないと解するのが相当である。
されば、本件訴訟は、上告人ンお死亡と同時に終了し、同人の相続人A、同Bの両名においてこれを承継し得る余地はないもの、といわなければならない。
なお、念のために、本件生活扶助基準の適否に関する当裁判所の意見を付加する。
憲法25条1項は、『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』
と規定している。この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みえるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない(昭和23年9月29日大法廷判決参照)。具体的権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護によって、はじめて与えられているというべきである。生活保護法は、『この法律の定める要件』を満たすものは、『この法律による保護』を受けることができると規定し(2条参照)、その保護は、厚生大臣の設定する基準に基づいて行うものとしているから(8条1項参照)、右の権利は、厚生大臣が最低限度の生活水準を維持するにたりると認めて設定した保護基準による保護を受け得ることにあると解すべきである。もとより、厚生大臣の定める保護基準は、法8条2項所定の事項を遵守したものであることを要し、結局には憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するにたりるものでなければならない。しかし、健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定的要素を総合考慮して初めて決定できるものである。したがって、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬがれない。
原判決は、保護基準設定行為を行政処分たるかは、厚生大臣の羈束裁量行為であると解し、なにが健康で文化的な最低限度の生活であるかは、厚生大臣の専門技術的裁量に委されていると判示し、その判断の誤りは、法の趣旨・目的を逸脱しないかぎり、当不当の問題にすぎないものであるとした。羈束裁量行為といっても行政庁に全然裁量の余地が認められていないわけではないので、原判決が保護基準設定行為を羈束裁量行為と解しながら、そこに厚生大臣の専門技術的裁量の余地を認めたこと自体は、理由齟齬の違法をおかしたものではない。また、原判決が本件生活保護基準の適否を判断するにあたって考慮したいわゆる生活外的要素というのは、当時の国民所得ないしその反応である国の財政状態、国民の一般的生活水準、都市と農村における生活の格差、低所得者の生活程度とこの層に属する者の全人口において占める割合、生活保護を受けている者の生活が保護を受けていない多数貧困者の事情である。以上のような諸要素を考慮することは、保護基準の設定について厚生大臣の裁量のうちに属することであって、その判断については、法の趣旨・目的を逸脱しないかぎり、当不当の問題を生ずるにすぎないのであって、違法の問題を生ずることはない。」
(ポイント)
{C}① 生活保護法の規定に基づき被保護者が国から生活保護を受けることを内容とする生活保護受給権は、当該個人に与えられた一身専属の権利であるため、相続の対象となり得ず、生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保険者の死亡により当然終了する。
{C}② 何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられており、保護基準の設定に関する判断につては、法の趣旨・目的を逸脱しない限り当不当の問題が生ずるにすぎず、違法の問題は生じない。
31.公務員の懲戒処分と裁量権の範囲(最判昭52.12.20)
(事案)
神戸税関職員のXら(3名)は、同僚職員に対する懲戒処分についての抗議行動や各種の組合活動において指導的役割を果たして業務の処理を妨げたとして、国家公務員法(以下、国公法という。)に定める争議行為の禁止や職務専念義務および人事院規制に定める勤務時間中の総合活動の禁止に違反することを理由に、国公法82条に基づく懲戒免職処分を受けた。
そこで、Xらは、本件処分の無効確認ないし取消しを求めて出訴した。
(争点)
公務員に対する懲戒処分の適否について、裁判所の審査はどこまで及ぶか。
(判旨)
「公務員に対する懲戒処分は、当該公務員に職務上の義務違反、その他、単なる労使関係の見地においてではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することをその本質的な内容とする勤務関係の見地において、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、公務員関係の秩序を維持するため、科される制裁である。ところで、国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者がすべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択するべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかと決するについては、厚生であるべきこと(74条1項)を定め、平等取り扱いの原則(27条)及び不利益取扱いの禁止(98条3項)に違反してはならないことを定めている以外に、具体的基準を設けていない。したがって、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等・諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかふどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分にすべきか、を決定することができるものと考えられるのであるが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平磯から町内の事情に通暁し、都下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるものでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、懇意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがって、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場にたって懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分と比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」 裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてなされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分をすべきであったかどうか、または、いかなる処分をせんたくすべきであったかについて判断し、その結果と実際になされた処分とを比較してその軽重を論じるべきではなく、それが社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合にのみ違法と判断すべきである。
●自由裁量行為の主な具体例(判例)
① 外国人の在留許可の更新
② 国公立大学の学生の処分
③ 生活保護基準の設定
④公務員の懲戒処分
32 .個人タクシー事件(最判昭46.10.28)
(事案)
Xは、新規の個人タクシー営業免許を陸運局長(Y)に申請し、道路運送法(⑨)122条の2に基づく聴聞を受けたが、同法6条1項3号ないし5号の要件を満たさないとして、当該申請の却下処分を受けた。これに対し、Xは、陸運局長はあらかじめ審査基準を定めてその内容を申請人に告知することにより申請人に主張と証拠提出の機会与えるべきであるにもかかわらず、それがなされないままXの申請を却下したのは、職業選択の自由に関わるXの法的利益を侵害するものであり違法であると主張して、当該却下処分の取消しを求めて提訴した。
(争点)
個人タクシー事業の免許申請に対する審査として、いかなる手続公正ながものといえるか。
(判旨)
「聴聞担当官のうち前記基準の協議に関与した7,8名の係長以外のものは、被上告人の担当官を含め、前記基準事項の存在すら知らず、聴聞開始前に上司から聴聞書の項目および聴聞内容について証明をうけただけで、右基準事項については何らこれを知らされることなく、被上告人の聴聞担当官にあっても、被上告人の申請の却下事由となった他業関係(転業の難易)および運転歴(軍隊における運転経験を含む)に関しても格別の支持はなされず、したがって、右担当官は、被上告人が洋品店を廃業してタクシー業に専念する意思があるかどうか、軍隊における運転経験があるかどうか等の点について思いいたらず、これらの点を判断するについて必要な事実については何聴聞が行われなかった、というものである。
おもうに、道路運送法においては、個人タクシー事業の免許申請の諾否を決する手続について、同法122条の2の聴聞の規定のほか、審査、判定の手続、方法等に関する明文規定は存しえない。しかし、同法のよる個人タクシー事業の免許の諾否は個人の職業選択の自由にかかわりを有するものであり、このことと同法6条および前記122条の2の規定等とを併せて考えれば、本件におけるように、多数の者のうちから少数特定の者を、具体的個別的事実関係に基づき選択して免許の諾否を決しようとする行政庁としては、事実の認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的にもっともと認められるような不公正な手続をとってはならないものと解せられる。すなわち、右6条は抽象的な免許基準を定めているにすぎないのであるから、内部的にせよ、さらに、その趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用すべく、とくに、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するようなものである等の場合には、右基準を適用するうえで必要とされる事項について、申請人に対し、その主張と証拠の提出の機会を与えなければならないというべきである。免許の申請人はこのような公正な手続によって免許の諾否につき判定を受くべき法的利益を有するものと解すべく、これに反する審査手続によって免許の申請の却下処分がされたときは、右利益を侵害するものとして、右処分の違法事由となるものというべきである。」
(ポイント)
道路運送法に定める個人タクシー事業免許にあたり、多数の申請人のうちから少数特定の者を選択するときは、同法の趣旨に沿う具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべきで、そのために適切な方法により申請人に対して主張と証拠提出の機会を与えることが必要であり、これに反する審査手続に基づく申請の却下処分は違法となる。
33.群馬中央バス事件(最判昭50.5.29)
(事案)
X会社は、運輸大臣(Y)に対して定期バス路線の延長を目的として道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の免許を申請したので、Yは、東京陸運局長に道路運送法(旧)122条の2に基づく聴聞を行わせた後、運輸審議会に諮問した。これを受けて、同審議会は、運輸省設置法16条に基づく公聴会を開催した後、利害関係人等の意見を聴取した上で、Yに対して本件申請を却下することが適当である旨を答申した。そこで、Yは、本件申請が道路交通法6条1項1号および5号に適合しないことを理由に却下し、その旨をX会社に通知した。
これに対して、X会社は、本件申請に対する審理は、陸運局長による簡単な聴聞がおこなわれただけで、現地調査その他十分な資料収集がされておらず、また、運輸審議会の審理手続において、独立公正な立場による独断のおそれのない手続によってなされたものではないことを主張して、本件却下処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
① 諮問を経て行政処分がされるべき場合における当該諮問機関の真理・決定(答申)の過程における違法性は、行政処分自体の違法性にいかなる影響を与えるか。
② 一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関して諮問を受けた運輸審議会が開催した公聴会の審理手続に瑕疵があった場合、この諮問を経てされた運輸大臣の免許許否処分は取消しの対象となるか。
(判旨)
「法は、運輸大臣が運輸審議会の決定を尊重すべきことを要求するにとどまり、その決定が運輸大臣を拘束するものとしていないから、運輸審議会は、ひっきょう、運輸大臣の諮問機関としての地位と権限を有するにすぎないものというべきであるが、しかしこのことはm運輸審議会の決定が全体として免許の許否の決定過程において有する意義と重要性、したがってまた、運輸審議会の審理手続のもつ意義と重要性を軽視すべき理由となるものではない。一般に、行政庁が行政処分をするにあたって、諮問機関に諮問し、その決定を尊重して処分をしなければならない旨を法が定めているのは、処分行政庁が、諮問機関の決定(答申)を慎重に検討し、これに十分な考慮を払い、特段の合理的な知友のないかぎりこれに反する処分をしないように要求することにより、当該行政処分客観的な適正妥当と公正を担保することを法が所期しているためであると考えられるから、かかる場合における諮問機関に対する諮問の理由は、極めて重大な意義を有するものとおいうべく、したがって、行政処分が諮問を経ないでなされた場合はもちろん、これを経た場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどにより、その決定(答申)自体に法が右諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、これを経てなされた処分も違法として取消をまぬがれないこととなるものと解するのが相当である。そして、この理は、運輸大臣による一般乗合旅客自動車運送事業の免許の許否についての運輸審議会への諮問の場合にも、当然に妥当するものといわなければならない。
ところで、一般乗合旅客自動車運送事業の免許の申請があった場合には、運輸大臣は原則として運輸審議会に諮問すべく、これを受けた運輸審議会は原則として公聴会を開いて審理したうえ決定をしなければならないことは、右に述べたとおりであるが、右の運輸審議会における審理及びこれに基づく決定の手続については、運輸省設置法及び運輸審議会一般規則にかなり詳細な定めが置かれている。しかし、これらの手続規定がいかなる趣旨、目的を有するものであり、したがってその手続の運用についていかなる配慮を施すべきものであるかは、これらの規定自体からはなく、専ら審理手続の意義と性格に照らしてこれを決すべきものであるところ、公聴会の審理を要求する趣旨が、前記のとおり、免許の許否に関する運輸審議会の客観性のある適正かつ公正な決定(答申)を保障するにあることにかんがみると、法は、運輸審議会の公聴会における審理を単なる資料の収集及び調査の一形式として定めたにとどまり、右規定に定められた形式を踏みさえすれば、その審理の具体的方法及び内容のいかんを問わず、これに基づく決定(答申)を適法なものとする趣旨であるとすることはできないのであって、これらの手続規定のもとにおける公聴会審理の方法及び内容自体が、実質的に前記のような要請を満たすようなものでなければならず、かつ、決定(答申)が、このような審理の結果に基づいてなされなければならないいと解するのが相当である。
右の見地に立って本件を見るに、上告人をして進んでこれらの点についての補充資料や釈明ないし反駁を提出させるための特段の措置はとられておらず、この点において、本件公聴会審理が上告人に主張立証の機械を与えるにつき必ずしも十分でないところがあったことは、これを否定することができない。しかしながら十分でないところがあったことは、これを否定することができない。しかしながら、仮に運輸審議会が、公聴会審理においてより具体的に上告人の申請系アックの問題点を指摘し、この点に関する意見及び資料の提出を促したとしても、上告人において、運輸審議会の認定判断を左右するに足る意見及び資料を追加提出しうる可能性があったと認め難いのである。してみると、右のような事情のもとにおいて、本件免許申請についての運輸審議会の審理手続における上記のごとき不備は、結局において、前記公聴会審理を要求する法の趣旨に違背する重大な違法とするには足りず、右審理の結果に基づく運輸審議会の決定(答申)自体に瑕疵があるということはできないから、右諮問を経てなされた運輸大臣の本件処分を違法として取り消す理由とはならないものといわなければならない。
(ポイント)
① 諮問機関の新鋭・決定(答申)の過程に重大な法規違反があることにより、その決定自体に法が諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められる瑕疵があるときは、それに基づいてなされた行政処分は違法として取消しをまぬがれない。
② 一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関して諮問を受けた運輸審議会が開催した公聴会の審理手続で、申請計画の問題点につき申請者に主張・立証の機会を十分に与えなかった瑕疵がある場合でも、申請者が運輸審議会の認定判断を左右するに足りる資料。意見を提出し得る可能性があったと認め難い事情があるときは、諮問を経てされた大臣の免許拒否処分を取り消す自由とならない。
34.伊方原発訴訟(最判平4.10.29)
(事案)
A会社(四国電力株式会社)は、Y(内閣総理大臣)に対して「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)」23条の基づき、伊方発電所原子炉設置許可申請をし、Yがこれを許可した。そこで、Xら(愛媛県西宇和郡内に居住する33名)は、当該原子炉が設置されることにより生命・身体・財産等が侵害される危険が生じるとして、当該原子炉の安全性の審査に際して手続法上および実体法上の違法があることを理由に、当該原子炉の設置許可処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
原子炉設置許可処分の取消訴訟における審理・判断の方法をいかに解すべきか。
(判旨)
「右の技術的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は、当該原子炉施設そのものの工学的安全性、平常運転時における従業員、周辺住民及び周辺環境への放射線の影響、事故時における周辺地域への影響等を、原子炉設置予定地の地形、地質、気象等の自然的条件、人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の右技術的能力との関連において、多角的、総合的見地から検討するものであり、しかも、右審査の対象には、将来の予測に係る事項も
含まれているのであって、右審査においては、原子力工学はもとより、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであることが明らかである。そして、規制法24条2項が、内閣総理大臣は、原子炉設置の許可をする場合においては、同条1条3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び4号所定の基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければならないと定めているのは、右のような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し、右各号所定の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる趣旨にゆだねる趣旨と解するのが相当である。
以上の点を考慮すると、右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって現在の科学的技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前期のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることの主張、立証資料は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側がほじしていることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依頼した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべきである。」
(ポイント)
裁判所の審理・判断は、原子力委員会や原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議・判断をもとにしてなされた行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきで、現在の科学的水準に照らし、調査審議で用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、調査審議・判断の過程に看過し難い過誤・欠落があり、行政庁の判断がこれに依頼してされたと認められる場合には、当該判断には不合理な点があるとして、原子炉設置許可処分は違法となる。
35.第三次家永教科書検定訴訟
(事案)
日本史の研究者であるXが執筆した高校用教科書「新日本史」は、昭和28年以来検定済教科書として使用されてきたが、昭和53年の学習指導要領の改正に伴う全面改訂をした上で昭和55年9月に文部大臣(現文部科学大臣)に対して新規検定の申請をしたところ、教科用図書検定調査審議会は420か所にわたる修正意見・改善意見を付した上で、当該修正意見個所の修正を条件とする条件付合格を決定した。これに対し、Xは、改善意見については拒否理由書を提出して修正に応じないでいたが、修正意見についてはこれに従い修正したため本件教科書は合格となった。
そこで、Xは、文部大臣が昭和55年度に申請された本件教科書の原稿本の記述に対して修正意見および改善意見を付したこと、昭和58年度に申請された改訂検定の際に改訂原稿の記述に修正意見を付したこと、ならびに昭和57年に提出された正誤訂正申請を受理しなかったことにより精神的苦痛を受けたとして、国(Y)を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
① 文部大臣が行う高等学校の教科用図書の検定は、どのような場合に国家賠償法上の違法となるか。
② 教科用図書の検定にあたって文部大臣が改善意見・修正意見を付すことは、国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使にあたるか。
(判旨)
「文部大臣が検定審議会の答申に基づいて行う合否の判定、合格の判定に付する条件の有無及び内容物の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、中立、公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童生徒の心身の発達段階に適応しているか、などの様々な観点から多角的に行われるもので、学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣の合理的な裁量にゆだねられているものであるが、合否の判定、合格の判定に付する条件の有無及び内容等についての検定審議会の判断の過程に、原稿の記載内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況、教育状況についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となると解するのが相当である。そして、検定意見は、原稿の個々の記述に対して旧検定基準の各必要条件ごとに具体的理由を付して欠陥を指摘するものであるから、各検定意見ごとに、その根拠となるべき学説状況や教育状況等も異なるものである。例えば、正確性に関する検定意見は、申請図書の記述の学問的な正確性を問題にするものであって、検定当時の学会における客観的な学説状況を根拠とすべきものであるが、検定意見には、その実質において、原稿記述が誤りであるとして他説による記述を求めるものや、原稿記述が一面的、断定的であるとして両説併記を求めるものなどがある。そして、検定意見に看過し難い過誤があるか否かについては、右の場合は、検定意見の根拠となる学説が通説、定説として学界に広く受け入れられており、原稿記述が誤りと評価し得るかなどの観点から、右の場合は、学説においていまだ定説とされる学説がなく、原稿記述が一面的であると評価し得るかなどの観点から判断すべきである。また、内容の選択や内容の程度等に関する検定意見は、原稿記述の学問的な正確性ではなく、教育的な相当性を問題とするものであって、取り上げた内容が学習指導要領に規定する教科の目標等や児童、生徒の心身の発達段階等に照らして不適切であると評価し得るかなどの観点から判断すべきものである(前掲平成5年3月16日第三小法廷判決参照)。
ところで、原審の確定したところによると、本件検定当時のI教科用図書検定審査内規(昭和53年6月15日教科用図書検定調査審議会決定)は、検定審議会は原稿本を合格と判定した場合、これに訂正、削除または追加などの措置をしなければ教科書として不適切であると認められるこきは、これを修正意見として指摘し、必要な修正を加えることを合格の条件とすること、修正意見として指摘するには至らないが、訂正、削除または追加などの措置をした方が教科書としより良くなると認められるときは、これを改善意見として指摘することを定めており、これに従った運用がされていたことが認められる。そうすると、修正意見を付することは、申請者がこれに応じて訂正、削除または追加などの措置をしなければ教科書として不合格となるというものであるから、合格に条件を付するものであり、これが国家賠償法上違法となるかどうかについては前記のような判断を要する。これに対して、改善意見は、検定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有するものと考えられるから、教科書の執筆者又は出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情がない限り、その意見の当不当にかかわらず、原則として、違法の問題が生ずることはないというべきである。
原審認定の前記事実によると、七三一部隊に関しては、本件検定当時既に多数の文献、資料が公刊され、中には昭和43年に刊行された上告人の著作もあり、必ずしもすべてが本件検定の直前に公刊されたわけではないことが明らかである。そして、原審が、本件検定当時、七三一部隊の存在等を否定する見解があったことを認定していないことに照らせば、本件検定当時、これを否定する学説は存在しなかったか、少なくとも一般には知られていなかったものとみられる。そうすると、本件検定当時において、七三一部隊の実態を明らかにした公刊物の中には、作家やジャーナリストといった専門の歴史研究家以外のものが多く含まれており、また、七三一部隊の全容が必ずしも解明されていたとはいえない面があるにしても、関東軍の中に細菌戦を行うことをも目的とした『七三一部隊』と称する軍隊が存在し、生体実験をして多数の中国人等を殺害したとの大筋は、既に本件検定当時の学界において否定するものはないほどに定説化していたというべきであり、これに本件検定時までには終戦から既に38年も経過していることをも併せ考えれば、文部大臣が、七三一部隊に関する事柄を教科書に記述することは時期向早として、原稿記述を全部削除する必要がある旨の修正意見を付したことは、その判断の過程に、検定当時の学説状況の認識及び旧検定基準に違反するとの評価に看過し難い過誤があり、裁量権の範囲を逸脱した違法があるというべきである。」
(ポイント)
① 合否の判定時についての教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、原稿の記述内容についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、当該判断は、裁量権の範囲を逸脱して、国家賠償法上違法となる。
② 文部大臣の改善意見は、これに応ずることを合格の条件としておらず、助言・指導の性質を有するものにすぎないから、教科書の執筆者がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情がない限り、違法の問題は生じない。
36.行政行為の効力の発生時期(最判昭29.8.24)
(事案)
京都地方検察庁に勤務する検事Aは、昭和23年12月14日に衆議院議員総選挙に立候補するため辞職を願い出たため、同月24日付けで免官の発令がなされ、29日付けで官報で公示された。ただし、A自身が当該発令を了知したのは31日であった。
ところが、Aはその前に立候補を断念して辞表の撤回を申し出ており、その後も職務を継続したため、同月30日における本件刑事事件の公訴提起も担当した。その結果、当該事件の弁護人が、検察官の資格を有しない者による公訴提起は違法であり、判決で棄却するべき旨を主張した。
(争点)
公務員の任免に関する行政行為の効果の発生時期と官報による工事との関係をいかに解すべきか。
(判旨)
「そこで右胃がん免官による退職の効果の発生時期について考えてみると、特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時とするのが相当である。即ち、辞令書の交付その他公の通知によって、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知し得べき状態におかれた時と解すべきである(原判決がこの点について、退職令書の交付時に限ったことは妥当であい)。論旨は免官の発令が官報に掲載された日に退職の効果を生ずるものと主張すえうけれども、公務員の任免は法令の公布とは自らその性質を異にするばかりであく、官報による公示は特定の相手方に対する意思表示とは到底認めることができないのであって、所論は独自の見解に過ぎない。
ところで、原判決の確定したところによると、本件免官の発令は昭和23年12月24日附でなされ、同月29日附け官報にその旨を公示されたのであるけれども、A検事が免官の発令があったことを上司たる教徒地方の検察庁検事正から公に通知され、これを了知したのは昭和23年12月31日であり、更らに免官の辞令書の公布をうけたのは、それ以後のことであるというのであって、それ以前に免官の発令が同検事に到達したという事実は何ら認められていない。して見ると、本件につき公訴の提起があった同月30日には、同検事に対しては免官発令による退職の効果も未だ生じていなかったものと認めざるを得ない。従って同月30日A検事によってなされた本件公訴の提起は違法であって、これを無効とすべき理由はない。それ故所論旧刑訴410条6号違反並びに憲法31条違反の主張はその前提を欠き採用することができない。」
(ポイント)
特定の公務員の任免のような行政行為については、特別の規定がない限り、行政庁の意思表示が相手方に到達した時、すなわち辞令書の公布などにより相手方が現実にこれを了知し、または了知し得べき状態におかれた時にその効果が生ずる。法令の公布の場合のように官報により公示されたことによって効果が生ずるものではない。
37.内部的意思決定と異なる表示行為(最判昭29.9.28)
(事案)
Yは、その所有する農地をXに賃貸していたが、農地調整法9条3項に基づく賃貸借契約の解除の申入れについての許可を求める申請書を、昭和22年9月1日付けで北海道知事に提出した。
しかし、当該申請については、許可し難いことに審議がまとまったにもかかわらず、指令書の浄書係のミスから、「右申請許可する」との知事名義の指令書が知事の決済を受けて作成され、昭和23年2月27日にYがこれを受領した。
そのため、Yは、Xに対して当該賃貸借契約の解除を通知するとともに、本件土地の立入禁止を求める仮処分を申請し、昭和24年月5月13日および18日に仮処分決定を得た。
これに対して、Xは、Yの申請を許可するという知事の法律的効果意思は存在しないのであるから、当該申請を許可する旨の行政行為は存在せず、要式的行政行為ではない本件においては、当該指令書の交付はいわゆる事実行為にすぎないとして、仮処分の取消しを裁判所に請求した。
(争点)
行政機関の内部的意思決定と相違する書面が作成され交付された場合においても、当該書面に表示されているとおりの行政行為が成立するか。
(判旨)
「被上告人は北海道知事に対し本件賃貸借契約の解約につき農地調整法9条3項による許可を申請し、昭和23年2月27日附け知事の許可指令書を受け取ったのであるが、これよりさき北海道庁においては右申請を許可し難いことに審議がまとまったにもかかわらず、知事の決済の求めるいわゆる原議の指令案の『本申請許可する』との文句を抹消しないまま知事の指令案の『本申請許可する』との文句を抹消しないまま知事の決済を受けたので、これに基づいて『本申請許可する』との知事名義の指令書が作成され、これを被上告人が受領したものであるというのである。論旨は、この場合被上告人の申請を許可するという北海道知事の法律的効果意思は存在しないのであるから、許可の行政行為は存在せず、要式的行政行為でない本件においては指令書の交付は単に行政処分の行われた事実を通知するところの事実行為に過ぎないものであると主張する。しかし行政行為は表示行為によって成立するものであって、行政機関の内部で確定したものであっても外部に表示しない間は意思表示ではあり得ない。そうして当該行政行為が要式行為であると否とを問わず書面によって表示されたときは書面の作成によって行政行為は成立し、その書面の到達によって行政行為の効力を生ずるものである。この場合表示行為が当該行政機関の内部的意思決定と相違していても表示行為が正当の権限である者によってなされたものである限り、」この事実は原審の認定したところである)該書面に表示されているとおりの行政行為があったものと認めなければならない。そうだとすれば、原判決が右指令書の表示に従って本件賃貸借解約の申請を許可するという行政行為があったものと判示したのは正当であって、これを許可しないという意思は未だ外部に表示されていないにもかかわらず、不許可の行政行為があったと主張し、又は許可の処分がなかったと主張する論旨は理由がない。」
(ポイント)
行政行為が行政機関の内部的意思決定と相違していても、当該表示行為が正当の権限である者によってなされている限り、要式行為であると否とを問わず、書面の作成によって当該書面に表示されているとおりの行政行為が成立し、その書面の相手方への到達によって効力を生じる。つまり、錯誤により行政行為は、有効となる。
民法上は、錯誤による法律行為は原則として無効となる(同法95条)ので、結論の違いに注意が必要である。
{C}① 錯誤に基づく行為の効力(原則)
行政法・・・行政行為は→有効
民放・・・・法律行為は→無効
38.「明白な瑕疵」の意義(最判昭36.3.7)
(事案)
Aおよびその子Xは、Aの養子Bらとの間で山林等の所有権をめぐる紛争を抱えていたが、A側が当該山林等をBらに贈与する代わりにBらが800万円を支払うことで示談が成立し、その支払いのため、Bは当該山林にある立木を伐採・処分して示談金を支払った。しかし、山林所得税を免れるため、示談契約書800万円の金額を表示せず、立木の売買契約書にも登記名義人のAを売り主として表示した。そのため、税務署長YはAに対して山林所得金額および所得税額を決定・通知するとともに、無申告加算税を賦課した。
これに対して、当該処分直後にAを相続したXは、本件立木の売却により収入を得たのはBであってAではないため、Yによる処分には重大な瑕疵があり、しかも当該瑕疵が明白であるか否かは事実審の最終口頭弁論期日までに行われた証拠調べにより客観的に確定された事実から判断すべきであると主張して、Yによる処分が無効であることの確認を求めて提訴した。
(争点)
行政処分の瑕疵が明白であるか否かについては、いつの時点におけるどのような内容により決すべきか。
(判旨)
「行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵いというのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合』を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例である(昭和34年9月22日第三小法廷判決)。右判例の趣旨からすれば、瑕疵が名曰はくであるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指すものとっ解すべきである。もとより、処分成立の初めから重大かつ明白な瑕疵があったかどうかということ自体は、原審の口頭弁論終結時までにあらわれた証拠資料により判断すべきものであるが、所論のように、重大かつ明白な瑕疵があるかどうかを口頭弁論終結時までに現れた証拠及びこれにより認められる事実を基礎として判断すべきものであるということはできない。また、瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものであって、行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかは、処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどうかの判定に直接関係を有するものではなく、行政庁がその怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかにかかわらず、外形上、客観的に誤認が明白であると認められる場合には、明白な瑕疵があるというを妨げない。原審も、右と同旨の見解にでたものと解すべきであって、所論は、右に反する府独自の見解を前提とするものであり、すべて採用のかぎりでない。」
(ポイント)
行政処分の瑕疵の明白とは、処分庁の認定が誤認であることが、処分成立の当初から、外形上客観的に一見看取し得るものであったかそうかにより決すべきである。
つまり、「パッと見、明らか」か否かで!
39.課税処分と当然無効(最判昭48.4.26)
(事案)
Aは、自らが経営する会社の債権者による差押えを免れるため、自己所有の不動産を義妹夫婦であるXら名義にすることをXらに無断で行ったが、その後、借金の返済にあてるため、Xら名義の売買契約書等を偽造して当該不動産を第三者に売却した。そこで、税務署長Yは、Xらに当該不動産についての譲渡所得があったと認定して課税処分を行い、これに応じないXらに滞納処分を行った。
これに対して、Xらは、本件課税処分についての異議申し立てを行ったが、申立期間の徒過により不可争力が生じていることを理由に却下されたため、Xらは無効確認訴訟を提起した。しかし、第一審・第二審ともに、本件課税処分に重大な瑕疵があることは認めたが、明白な瑕疵ではないため無効とはいえないとして、Xらの請求を棄却した。
(争点)
行政処分が無効である旨を主張するためには、当該処分に存する瑕疵重大性が明白であることが、常に必要とされるか。
(判旨)
「一般に、課税処分が課税庁と非課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税処分の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効とならしめるものと解するのが相当である。
本件は、課税処分に対する通常の救済制度につき定められた不服申立期間の徒過による不可争的効果を理由として、なんら責むべき事情のない上告人らに前記処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情のある場合に該当し、前記の過誤による瑕疵は、本件課税処分を当然無効ならしめる。」
(ポイント)
課税処分が課税庁と被課税者との間のみのもので、処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないことから、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹に関わるものであって著しく不当と認められる例外的事情がある場合には、それだけで当該処分は当然無効となる。
つまり、例外として、重大性だけで(明白でなくても)無効となる。
40.瑕疵の治癒が認められた例(最判昭36.7.14)
尼崎地区農地委員会は、X所有の池沼を自作農創設特別措置法15条1項1号が規定する「農地の利用上必要な農業用施設」として買収するための買収計画を定めたが、Xは、これを不服として、兵庫県農地委員会に訴願を提起した。そのため、同法15条2項が準用する8条、9条に従い、当該訴願に対する裁決がなされるまでは買収計画をていしすべきところ、県農地委員会は、裁決をする前に、棄却裁決を得致死条件とする本件買収計画の承認を行い、これを受けて、兵庫県知事は買収令書をXに交付して本件池沼を買収した。そして、その10日後に、Xの訴願を棄却する旨の裁決がなされたが、Xは、当該棄却裁決に先立ってなされた買収処分は違法であること等を理由に、国(Y)を被告として、本件池沼の所有権に関する訴訟を提起した。
(争点)
農地買収計画についての訴願が提起されたにもかかわらず、その採決を経ないまま進行させた手続は有効といえるか。
(判旨)
「農地買収計画につき意義・訴願の提起があるにもかかわらず、これに対する決定・裁決を経ないで爾後の手続を進行させたという違法は、買収処分の無効原因となるものではなく、事後において決定・裁決があったときは、これにより買収処分の瑕疵は治癒されるものと解するのを相当とする(昭和34年9月22日第三小法廷判決参照)。
本件についてこれをみるのに、原審の確定した事実によれば、兵庫県農地委員会が本件買収計画を承認し、また兵庫県知事が被上告人に対する買収令書を発行した当時は、まだ同委員会による本件買収計画についての訴願裁決がなされていなかったとはいえ、右承認は訴願棄却の裁決があることを停止条件としてなされたものであり、訴願棄却の裁決もその穂行われたというのであるから、訴願棄却の裁決がなされる前に承認その他の買収手続をしいんこうさせてという瑕疵は、その後訴願棄却の裁決がなされたことによって治癒された、と解すべきである。」
(ポイント)
農地買収計画に対する訴願の提起があったにもかかわらず、その裁決を経ないまま都道府県のうち委員会訴願棄却裁決があることを停止条件として買収計画を承認し、それに基づき都道府県知事が土地所有者に買収令書を発行したという瑕疵は、その後に当該訴願に対する棄却裁決があったことにより治癒される。
→瑕疵の治癒を認めた判例である。
●瑕疵の治癒
行政行為に存在した瑕疵が、その後の事情により、実質的に違法要件を具備した結果、
違法行為を適法扱いすることをいう。
41.瑕疵の治癒が認められなかった例(最判昭48.4.26)
(事案)
清算手続中の法人Xが、事業年度所得ならびに清算所得についての法人税につき確定申告をしたところ、税務署長Yから増額厚生処分を受けたが、その更生通知書には、理由として加算項目についての金額が記載されているにすぎなかった。
そこで、これを不服とするXがA国税局長に審査請求をしたところ、同局長は、更正処分の一部を取り消した上で、その余の部分を維持すべき詳細な理由を裁決書に記載した。
しかし、Xは、本件更正処分の実態的違法性を主張するとともに、更正処分における理由付記を義務付けた法人税法旧38条にも違反する旨を主張して、本件更正処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
更正処分に対する審査請求において、裁決庁により詳細な理由が示された場合には、付記理由不備の違法性は治癒されるか。
(判旨)
「そこで、本件更正の附記理由をみるのに、その更生通知書の理由書に、係争事業年度所得の加算項目として、①営業譲渡補償金計上もれ1155万円、②認定利息(代表者)計上もれ1万9839円、清算所得の加算項目として、③残余財産価格の通算分4000円、④営業譲渡補償金905万円と記載されていることは、原判決の適法に確定するところである。所論は、右各項目のうち①⑤の記載は、『被上告会社は訴外日興証券株式会社に営業を譲渡した対価として250万円を清算所得に計上していたが、被上告会社代表者Aが右訴外会社から受領した借入金300万円、嘱託料290万円、手数料315万円、計905万円も右営業譲渡の対価であるのにこれが脱漏しており、営業譲渡の対価の総額は1155万円と評価されるので、これを加算すること』および『905万円は営業譲渡の対価の債券であること』を端的に要約したものであり、また、②④の記載は、『被上告会社の前記Aに対する仮払金と立替金についての認定利息が1万9839円であること』を端的に明らかにしたものであると主張する。しかし、③を除く前記格加算項目の記載から、右主張のごとき更正理由を理解することはとうてい不可能であり、その記載をもってしては、更正にかかる金額がいかにしてさんしゅつされたのか、それがなにゆえに被上告会社の課税所得とされるのか等の具体的根拠を知るに由ないものといわざるをえない。
してみると、処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分理由を相手方に知らせて不服申立の便宜を与えることを目的として更正に附記理由の記載を命じた前記法人税法の規定の趣旨にかんがみ、本件更正の附記理由には、不備の違法があるものというべきである。
しかし、更正に理由附記を命じた規定の趣旨が禅師のとおりであることに徴して考えるならば、処分庁と異なる機関の行為により附記理由不備の瑕疵が治癒されるとすることは、
処分そのものの慎重、合理性を確保する目的にそわないばかりでなく、処分の相手方としても、審査裁決によってはじめて具体的な処分根拠を知らされたのでは、それ以前の審査手続において十分な不服理由を主張することができないという不利益を免れない。そして、更正が附記理由不備のゆえに訴訟で取り消されるときは、更正期間の制限によりあらたな更正をする余地のないことがあるなど処分の相手方の利害に影響を及ぼすのであるから、審査裁決に理由が附記されたからといって、更正を取り消すことが所論のように無意味かつ不必要なこととなるものではない。
それゆえ、更正における附記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではないと解すべきである。」
(ポイント)
更正処分における理由付記の不備の瑕疵は、当該処分に対する審査請求についての裁決において処分理由が詳細に示された場合でも、治癒されない。
→瑕疵の治癒を認めなかった判例である。
42.違法行為の転換が認められなかった例(最判昭29.7.19)
(事案)
赤坂村農地委員会は、X所有の農地につき、小作人の請求がないのにかかわらず、これがあったものとして自作農創設特別措置法3条1項・附則2項ならべに同法施行令43条に基づき買取計画を求めた。そこで、Xは、広島県農地委員会(Y)に対して訴願を行ったが、Yは小作人の請求がないことを確認しながらも、農村地委員会の買収計画の手続的違法を是正することなく、同法施行令45条に基づき棄却裁決の取消しを求めて出訴した。
(争点)
自作農創設特別措置法施行令43条によって定められた農地買収計画を、訴願に対する採決によって、同令45条によるものとして維持することが認められるか。
(判旨)
「原判決は、『赤坂村農地委員会が、本件農地について小作人の請求がないのに拘らずその請求があったものとして改正前の地先農創設特別措置法附則2項、同法施行令43条により昭和20年11月23日現在の事実に基づいて買収計画を定めたこと、並びに、被控訴(被上告)委員会が同令45条を適用して本件買収を相当と認め控訴人(上告人)の訴願を容れない旨の裁決をしたものであること』を認定した上、『右のような事実関係においては、本件農地については右附則2項、同令43条の規定を適用すべきものではなく、従って、赤坂村農地委員会が、同法条により買収計画を定めた手続は違法であるから、被控訴委員会はこの点を是正して裁決すべきであったに拘らず、この点を釈明させない漫然改正前の同法施行令45条を適用して裁決したことは妥当でない』と判断しながら、しかも、行政事件特例法11条を適用して控訴人(上告人)の主張を排斤したことは所論のとおりである、しかし、改正前の自作農創設特別措置法附則2項によれば、3条1項の規定による農地の買収については、市町村農地委員会は相当と認めるときは、『命令』の定めるところにより、昭和20年11月23日現在における事実に基いて6条の規定による農地買収計画を定めることができるものである。そして、右『命令』である同法施行令43条は、右期日現在における小作農が農地買収計画を定めるべきことを請求したときは、市町村農地委員会は、当該小作地につき附則2項の規定により現在の事実に基いて農地買収計画を定めることの可否につき審議しなければならないと規定しているだけであるから、同令43条による場合と同令45条による場合とによって、市町村農地委員会が買収計画を相当と認める理由を異にするものとは認められない。従って原判決が同法43条により定めたと認定した赤坂村農地委員会の本件買収計画を被上告委員会が同令45条を適用して相当と認め上告人の訴願を容れない旨の裁決をしたことは違法であるとはいえない。されば、上告人の主張を排斤した原判決は、前記理由に依れば失当であるけれども、右の理由により結局正当に帰すから、論旨は採用できない。」
(ポイント)
行政行為とみればその法廷要件がする訴願についての裁決において、同令45条を適用することにより
相当なものとして維持することは違法ではない。
→違法行為の転換を認めた判例である。
●違法行為の転換
行政庁の意図した行政行為としては要件を満たさない違法であるが、他種の行政行為とみればその法廷要件が満たされており適法と考えられる場合に、その効力を維持する取扱いをいう。
43.事実上の公務員の理論(最大判昭35.12.7)
(事案)
奈良県内の村の村長であったXは、同村選挙管理委員会の名で行われた村長解職賛否投票の結果、過半数の同意があったものとして解職された。その結果、後任の村長が選出され、当該村長の関与につり、a村は奈良市に吸収合併された。これに対し、Xは、Xについての解職請求手続を管理執行した同村選挙管理委員会の構成が適法でないことを主張して、奈良県選挙管理委員会(Y)に訴願を行ったが、これが棄却されたため、当該棄却裁決の取消と解職賛否投票の無効確認を求めて出訴した。
(争点)
{C}① 村が吸収合併により消滅した後において、村長解職賛否投票の無効確認を求めることについて、訴えの利益は認められるか。
{C}② もし当該賛否投票の効力が失われた場合には、当該投票が有効であることを前提になされた後任の尊重による行政処分も無効となるか。
(判旨)
「上告人が村長であったa村は、本訴提起後の昭和32年8月27日、奈良県知事が関係自治団体の申請に基づいて同村を奈良市に吸収合併する旨決定し、同月30日内閣総理大臣からその旨告示されたことは、原判決の確定するところであるから、右市町村合併は地方自治法7条7項により右告示によって効力を生じ、a村は同日をもって廃止されたものである。
そして、本訴は前示委員会の裁決の取消、ならびに賛否投票の無効の宣言を求め、これによって上告人の村長たる地位を回復することを目的とする訴訟と解すべきであるから、a村が前記のごとく廃止され、たとえ上告人が本訴にいおいて勝訴して、右賛否投票の無効が宣言されても、既にその回復すべき地位の存在しないこととなった現在においては、かかる訴訟は訴訟の利益がなくなったものとして許すことのできないものであることは当裁判所の判例の趣旨に徴してあきらかである。(昭和35年3月9日大法廷判決参照)。
上告人は、本訴において賛否投票の無効が宣言されるときは、右判決の効力は既往に遡及し、後任村長が関与したa村の奈良市への合併の効力にも影響を及ぼす旨主張するけれども、たとえ賛否投票の効力が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提として、それまでの間になされた後任村長の行政処分は無効となるものではないと解すべきであるから、右上告人の主張は採用することができない。」
(ポイント)
{C}① 村が吸収合併により消滅した以後は、村長解職賛否投票の効力に関する訴えの利益はなくなる。
{C}② たとえ当該賛否投票の無効が宣言されても、当該投票が有効であることを前提としいてそれまでになされた後任の村長による行政処分は無効とならない。
→事実上の公務員の理論に言及した判例である。
●事実上の公務員の理論
公務員の欠格事由に該当する者が公務員に任命された場合などにおいて、その者が行った行為は原則として無効となるはずであるが、相手方の信頼を保護するために有効なものとして扱うことをいう。
44.旅券発給拒否における理由付記(最判昭60.1.22)
(事案)
Xが昭和52年1月8日に外務大臣(Y)に対し渡航先をサウディ・アラビアとする一般旅券の発給を申請したところ、Yは、同年2月16日付の書面に、「旅券法13条1項5号に該当する。」との理由を付して、当該申請に係る一般旅券を発給しない旨をXに通知した。
このため、Xは、Yに対して異議申立てを行ったが棄却されたため、Yを被告とする本件拒否処分の取消訴訟等を提起した。
(争点)
一般旅券発給拒否処分の通知書に、「旅券法13条1項5号に該当する。」とのみ理由に記載した本件拒否処分には、理由付記の不備による違法性があるのではないか。
(判旨)
「旅券法14条は、外務大臣が、同法13条の規定に基づき一般旅券の発給をしないと決定したときは、すみやかに、理由を付した書面をもって一般旅券の発給を申請した者にその旨を通知しなければならないことを規定している。い一般に、法律が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである(最高裁昭和38年5月31日第二小法廷判決)。旅券法が右のように一般旅券発給拒否通知書に拒否の理由を付記すべきものとしているのは、一般旅券の発給を拒否すれば、憲法22条2項で国民に保障された基本的人権である外国旅行の自由を制限することになるため、拒否事由の有無についての外務大臣の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきであり、このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは、それによって当該既定の適用の基礎となった事実関係をも当然知りうるような場合を別として、旅券法の要求する理由付記として十分でないといわなければならない。この見地に立って旅券法13条1項5号をみるに、同号は、『前各号に掲げる者を除く外、外務大臣において、著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者』という概括的、抽象的な規定であるため、一般旅券発給拒否通知書に同号に該当する旨付記されただけでは、申請者において発給拒否の基因となった事実関係をその記載自体から知ることはできないといわざるをえない。したがって、外務大臣において旅券法13条1項5号の規定を根拠に一般旅券の発給を拒否する場合には、申請者に対する通知書に同号に該当すると付記するのみでは足りず、いかなる事実関係を認定して申請者が同号に該当すると判断したかを具体的に記載することを要すると解するのが相当である。そうであるとすれば、単に『旅券法13条1項5号に該当する。』と付記されているにすぎない本件一般旅券発給拒否処分の通知書は、同法14条の定める理由付記の要件を欠くものというほかはなく、本件一般旅券発給処分に右違法があることを理由としてその取消しを求める上告人の本訴請求は、正当として認容すべきである。」
(ポイント)
一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者がその記載自体から了知し得るものでなければならず、本件拒否処分の通知書には旅券法14条が定める理由付記の要件を欠く違法があり、当該処分は取り消されるべきである。
45.違法性の承継が認められた例(最判昭25.9.15)
(事案)
X所有の農地につき、桃園村農地委員会が自作農創設特別措置法2条1項1号に該当する農地として買収計画を立てるため、Xは、当該農地が同法5条6号に該当するものとして買収計画から除外されるべき旨を主張して同委員会に異議を申し立て、さらに、三重県農地委員会に訴願をしたが、いずれも却下された(当該却下裁決についえた、Xは取消訴訟を提起していない。)。そのため、本件買収計画については県農地委員会の承認が与えられ、これに基づき三重県知事(Y)は、買収令書をXに交付して買収処分を行った。
これに対し、Xは、あらためて買収計画の違法性を主張して当該計画に基づく買収計画の取消しを求めて出訴した。
(争点)
買収計画についての出訴期間が経過した後に、当該買収計画の違法性を主張してその後になされた買収処分の取消しを主張することはできるか。
(判旨)
「法第5条はその各号の一に該当する農地については買収しないと規定しているのであるからこれに該当する農地を買収計画にいれることの違法であることは勿論これが買収処分の違法であることは言うまでもないところである。従って右の如き違法は買収計画と買収処分に共通するものであるから買収計画に対し異議訴訟の途を開きその違法を攻撃し得るからといって買収処分取消の訴えにおいて、その違法を攻撃し得ないと解すべきではない。法大7条が買収計画に対して異議訴訟を認めているのはただその違法の場合に行政庁に是正の機会をお与え所有者の権利保護の簡便な途を開いただけであって異議訴訟等の手続をとらなかったからと言って買収処分取消の訴訟においてその違法を攻撃する機会を失わせる趣旨であるとはかいせられない。買収計画に対し異議申立や訴願をせず又は訴訟採決に対する出訴期間を徒過したときは当事者はもはや買収計画に対しその取消を請求する権利を失うのであるからその意味では確定的効力があるのであるがその確定的効力は買収計画内容に存する違法を違法なしと確定する効力があるものではない。買収の計画は買収手続の一段階をなす市町村農地委員会の処分にすぎないので更に都道府県農地委員会の承認及び都道府県知事の買収令書の交付を経て買収手続は完結するのである。しかして買収計画の確定的効力は前記の如くその内容に存する違法を違法なしと確定する効力がないのであるから都道府県農地委員会の買収計画承認の権限は買収計画の内容の適否を審査する権限を包含するものと解すべく更に都道府県知事は買収計画の内容の適否を審査する権限を包含するものと解すべく更に都道府県知事は買収計画又はその承認の決議に対してこれを再議に付して是正させる権限を有するのである。(農地調整法第15条ノ28)故に都道府県農地委員会や知事が右権限の適正な行使を誤った結果内容の違法な買収計画にもとずいて買収処分が行われたならばかかる買収処分が違法であることは言うまでもないところで当事者は買収計画に対する不服を申し立てる権利を失ったとしても更に買収処分取消の訴においてその違法を攻撃し得るものといわなければならない。」
(ポイント)
自作農創設特別措置法5条に違反した買収計画に基づいて買収処分が行われたときは、被買収者は、買収計画に対する出訴期間経過後であっても、買収処分取消の訴えの中で買収計画の違法性を主張することができる。→違法性の承継を認めた判例である。
●違法性の承継
数個の行政行為が連続して行われる場合に、先行行為に瑕疵があったときに、その
瑕疵が後行行為にも承継されることをいう。
違法行為が承継される場合には、後行行為に対する取消しの訴えにおいて、先行行
為の違法性を主張することができる。
46.不可変更力に反してなされた採決の効力(最判昭30.12.26)
Xは、Y所有の農地についての賃借権の存在を主張してYと争いになったが、水戸地方裁判所における調停の成立により、X主張の賃借権は消滅した。しかし、その後、Xによる賃借権回復の裁定申請に対して緑岡村農地委員会がこれを認める裁定をしたため、Yはい茨城県農地委員会に訴願を申し立てたたが、昭和24年12月23日付けで棄却裁決がなされた。ところが、Yの申出に基づき県農地委員会が再議した結果、Yの主張を相当と認め、昭和26年6月29日付をもって前記棄却裁決を取り消した上で、Yの訴願を容認する裁決を行った。
そこで、Xは、Yを被告として、本件農地についての耕作権の確認と引渡しを求めて出訴した。
(争点)
訴願に対する採決を裁決庁自らがその後に取り消した場合は、当該取消しの採決は当然に無効となるか、それとも取消原因となるにとどまるか。
(判旨)
「本件において、茨城県農地委員会は、被上告人が緑岡村農地委員会のした裁定を不服として申立てた訴願につき、昭和24年12月23日附で訴願棄却の裁決をしながら、さらに被上告人の申出によって再議の結果、昭和26年6月29日附をもって先に棄却した被上告人の訴願における主張を相当と認め、前記訴願棄却の裁決を取り消した上改めて訴願の趣旨を認容するとの裁決をしたことは、原判決の確定したところである。そして、訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、原則としてゆすされないものと解するべきであるから(昭和29年1月21日第一小法廷判決参照)茨城県農地委員会が被上告人の申出により現判示の事情の下に先になした裁決を取り消してさらに訴願の趣旨を容認する裁決をしたことは違法であるといわねばならない。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するものと解すべきところ、茨城県農地委員会のなした前記訴願裁決取消の裁決は、いまだ取り消されないことは原判決の確定するところであって、しかもこれを当然無効のものと解することはできない。」
(ポイント)
訴願に対する裁決をした裁決庁が自ら当該採決を取り消すことは違法であるが、その違法は取消原因にとどまるものであって、後の裁決は当然に無効とならない。なぜなら、2度目の裁決も行政行為である以上、公定力を有するからである。
公定力とは、行政行為にたとえ瑕疵(重大かつ明白な瑕疵を除く)があっても、権限のある行政機関または裁判所が取り消すまでは、一応有効として扱われる効力をいう。
47.行政行為の撤回と損失補償(最判昭49.2.5)
(事案)
X社は、クラブ・レストラン・喫茶・料理等の事業を営むための建物所有を目的として、東京都(Y)が所有する中央卸売市場築地本場内の土地1044坪を、Yの使用許可を受け使用期間の定めなく借り受けていたが、実際にはその一部に建坪55坪の店舗1棟を建築したのみで、残りの部分は利用されないまま経過していた。そうするうちに卸売市場の混雑が進んできたことから、Yは960坪部分の使用指定を取り消す旨の通告をX社に対してなし、その上に存した前記建物につき、使用許可を取り消していない土地上に移転する行政代執行を行った。
これに対して、X社は、960坪部分ン位ついてなされた使用許可の取消しによって当該土地に関する使用権の喪失という積極的損害を受けており、これは憲法29条3項の特別の犠牲にあたるから、その補償がなされるべきであるにもかかわらず、これがなされていないことを理由に、Yを被告として本件土地の借地権の確認とそれに基づく土地の引渡しを求めて出訴した。
(争点)
行政財産たる土地についての使用許可の取消し(撤回)に当たっては、存実補償を要するか。
(判旨)
「本件取消を理由とする補償に関する法律および都条令についてみるに、本件取消がされた当時(昭和32年6月29日)の地方自治法および都条令にはこれに関する規定を見出すことができない。しかし、当時の国有財産法は、すでに、普通財産を貸し付けた場合における貸し付けた場合における貸付期間中の契約解除による損失補償の規定をもうけ(同法24条)、これを行政財産に準用していた(同法19条)ところ、国有であれ都有であれ、行政財産に差等はなく、公平の原則からしても国有財産法の右規定は都有行政財産の使用許可の場合にこれを類推適用すべきものと解するのが相当であって、これは憲法29条3項の趣旨にも合致するところである。そして、原判決の前記判示によれば、本件使用許可は期間を定めないものではあるが建物所有を目的とするというのであるから、前叙のところに従い右類推適用が肯定されるべきである。したがって、本件損失補償については、これを直接憲法29条3項にもとづいて論ずるまでもないのである。
本件のような都有行政財産たる土地につき使用許可によって与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきものであり、また、権利目的に右のような制約が内在しているものとして付与されているものとみるのが相当である。すなわち、当該行政財産に右の必要を生じたときに右使用権が消滅することを余儀なくされているのは、ひっきょう使用権自体に内在する前記のような制約に由来するものということができるから、右使用権者は、行政財産に右の必要を生じたときは、原則として、地方公共団体に対しもはや当該使用権を保有する実質的理由を失うに至るのであって、その例外は、使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払いをしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか、使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認められるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。」
(ポイント)
行政財産たる土地につき期間の定めなくなされた使用許可が、当該行政財産本来の用途・目的上の必要に基づいて撤回されたときは、特別の事情のない限り、使用権者は土地使用権の喪失についての補償を求めることはできない。
48,菊田医師赤ちゃんあっせん事件(最判昭63.6.17)
(事案)
上告人Xは、昭和25年に医師免許を付与され、昭和33年10月以降、宮城県石巻市にて産科・婦人科・肛門科の医院を開設していたが、その間んお昭和28年に、被上告人たる社団法人宮城県医師会(Y)から衛生保護法(現「母体保護法」)14条1項に基づく人工妊娠中絶を行いうる医師の指定を受けていた。
しかし、Xは、中絶の時機を逸しながらもその施術を求める女性を説得して出生をさせ、当該嬰児につき子どもを欲しがっている他の婦女が出産したとする虚偽の出生証明書を発行することにより、戸籍上も当該婦女の実子として登載させるという形で、当該嬰児をあっせんする、いわゆる実子あっせん行為を昭和52年10月20日までの間に220件繰り返した。
そのため、Yは、Xが昭和53年3月1日に仙台簡易裁判所から医師法違反ならびに公正証書原本不実記載・同行使罪により罰金20万に処する旨の略式命令を受け、刑が確定したことを受けて、「Xが指定医師として不適当と認められる」ことを理由に、昭和51年11月1日付けの指定医師の更新を取り消した(講学上の撤回)。
これに対し、Xは、当該指定取消処分と、その後の指定申請に対する却下処分の取消しを求めるとともに、Yと国に対する各3000万円の損害賠償の支払いを求めて提訴した(なお、Xは、昭和48年4月において、マスコミ等を通じてこの事実を社会に公表しており、その結果、このような実子あっせん行為が賛否両論を伴う社会問題となるとともに、昭和62年の民放改正による民放817条の2以下の特別養子縁組制度が創設される一つの契機となった。)。
民放817条の2
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
(争点)
優生保護法に基づく指定医師の指定といった授益的行政行為の撤回は、当該撤回を認める直接の明文規定がなくても許されるか。
(判旨)
「実子あっせん行為は、医師の作成する出生証明書の信用を損ない、戸籍制度の秩序を乱し、実子の親子関係の形成により、子の法的地位を不安定にし、未成年の子を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならない旨定めた民法798条の規定の趣旨を潜脱するばかりでなく、近親婚のおそれ等の弊害をもたらすものであり、また、将来子にとって親子関係の賛否が問題となる場合についての考慮がされておらず、子の福祉に対する配慮を欠くものといわなければならない。したがって、実子あっせん行為を行うことは、中絶施術を求める女性にそれを断念させる目的でなされるものであっても、法律上許されるものではないのみならず、
医師の職業倫理にも反するものというべきであり、本件取消処分の直接の理由となった当該実子あっせん行為についても、それが緊急避難ないしこれに準ずる行為に当たるとするべき事情は窺うことはできない。しかも、上告人は、右のような実子あっせん行為に伴う犯罪性、それによる弊害、その社会的影響を本当に軽視し、これを反復継続したものであって、その動機、目的が嬰児等の生命を守ろうとするに当たったこと等を考慮しても、上告人の行った実子あっせん行為に対する少なからぬ非難は免れないといわなければならない。
そうすると、被上告人医師会が昭和51年11月1日付の指定医師の指定をしたのちに、上告人が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、上告人が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、上告人に対する指定を存続させることが交易に適合しない状態が生じたというべきところ、実子あっせん行為のもつ右のような法的問題点、指定医師の指定の性質等に照らすと、指定医師の指定の撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回するべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるというべきである。」
(ポイント)
指定医師指定の撤回によって当該医師が被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性の高い場合には、指定権者は、法令上その撤回についての直接の明文がなくても、指定権限に基づき当該指定の撤回ができる。
49.宝塚市パチンコ条例事件(最判平17.7.9)
(事案)
兵庫県宝塚市(X)は、市内におけるパチンコ店等の主出店を規制するため、昭和58年に「宝塚市パチンコ店等ゲームセンターお及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」を制定し、パチンコ店等の建築等をしようとする者には市長の同意を得ることを義務づけ、同意なく建築をしようとする者には建築の中止・原状回復その他必要な措置を命じることができる旨が規定されていた。
ところが、平成4年11月にパチンコ店の出店を計画して市長の建築同意を申請したYに対し、市長が、建築予定地が条例の認める商業地域ではなく、準工業地域に属していることを理由に同意を拒否したところ、Yは、宝塚市建築審査会に対する審査請求により建築確認を認める裁決を得た上で、建築工事に着手した。
そのため、市長は平静6年3月15日に同条例に基づく建築工事中止命令を発したが、Yがこれを無視して工事を続けたことから、Xは、Yを相手方として、工事の続行禁止を求める仮処分決定を得るとともに、工事の続行禁止を求める民事訴訟を提起した。
(争点)
(地方公共団体が、条例に基づく行政上の義務の履行を求めて民事訴訟を提起することは認められるか。
(判旨)
「行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法3条1項にいう『法律上の争訟』、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる(最高裁昭和56年4月7日第三小法廷判決参照)。国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、法律上の争訟に当たるというべきであるが、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許されるものと解される。そして、行政代執行は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによるものと規定して(1条)、同法が行政上の義務の履行に関する一般法であることを明らかにした上で、その具体的な方法としては、同法2条の規定による代執行のみを認めている。また、行政事件訴訟法その他の法律にも、一般に国又は地方公共団体が国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟を提起することを認める特別の規定は存在しない。したがって、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当らず、これを認める特別の規定もないから、不適法というべきである。
本件訴えは、地方公共団体である上告人が本件条例8条に基づく行政上の義務の履行を求めて提起したものであり、原審が確定したところによると、当該義務が上告人の財産的権利に由来するものであるという事情も認められないから、法律上の争訟に当らず、不適法というほかはない。そうすると、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上によれば、第1審判決を取り消して、本件訴えを却下すべきである。
(ポイント)
地方公共団体が、行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟にあたらず、また、これを認める特別の規定も行政事件訴訟法その他の法律に存在しない以上、不適法である。つまり、認められない。
50.行政上の強制執行と民事上の強制執行(最判昭41.2.23)
(事案)
茨城県を区域をする農業共済組合連合会(X)は、その構成員たる下関市農業共済組合(A)に対して農業共済保険料や賦課金についての債権を有し、Aはその組合員たるYらに対して共済掛け金や賦課金・拠出金についての債権を有していた。そして、これらAの有する債権については、農業災害補償法87条の2およびこれを準用する農業共済組合法46条に基づき、滞納者に対する強制徴収が認められていたが、Xは、Aに代位して、共済掛金等を延滞しているYらに対して、その支払いを求めて民事訴訟を提起した。
(争点)
農業協同組合が、農作物等の共済掛金や賦課金・拠出金を滞納する組合員に対して、民事訴訟法の手続に従って徴収することは認められるか。
(判旨)
「農業災害補償法87条の2によれば、農業共済組合は、農作物共済若しくは蚕繭共済にかかる共済掛金又は賦課金を滞納する者がある場合には、督促状により繭共済にかかる共済掛金又は賦課金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促することを要し、その督促を受けた者が指定期限までにこれを完納しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができ、市町村は、右請求に応じて地方税の滞納処分の例によりこれを処分すべく、若し市町村が右請求に応じて地方税の滞納処分の例委によりこれを処分すべく、若し市町村が右請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、農業共済組合は、都道府県知事の許可を行けて、自ら地方税の滞納処分の例により処分することができることになっており、右徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされる等、その債権の実現について、特別の便宜が与えられている。また、拠出金の滞納についても、職業共済基金法46条により、前示す農業災害補償法87条の2の規定が準用され、右と同じ取扱いが認められている。かように、農業共済組合が組合員に対して有するこれら債権について、法が一般私法上の債権にみられない特別の取扱いを認めているのは、農業災害に関する共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上必要な財源を確保するあめには、農業共済組合が強制加入制のもとにこれに加入する多数の組合員から収納するこれらの金円につき、租税に準ずる簡易迅速な行政上の強制徴収の手段によらしめることが、もっとも適切かつ妥当であるとしたからにほかならない。
論旨は、農業災害補償法87条の2がこれら債権に行政上の強制徴収の手段を認めていることは、これら債権について、一般私法上の債権とひとしく、民訴法上の強制執行の手段をとることを排除する趣旨ではないと主張する。
しかし、農業共済組合が、法律上特にかような独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手段によってこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の機能行使の適性を欠くものとして、許されないところといわなければならない。」
(ポイント)
農業共済組合が構成員による農作物の共済掛金などの延滞に対して徴収を行うにあたっては、農業災害補償法が規定する強制徴収の手段によるべきであって、民事訴訟法に基づく強制徴収を行うことは許されず、その履行を裁判所に請求することも認められない。
51.豊中給水装置拒否事件(最判昭56.7.16)
(事案)
Xは、大阪府豊中市内に賃貸用共同住宅を所有していたが、当該共同住宅の増築工事をした上で、豊中市(Y)の建築主事に対して建築確認申請をしたところ、当該増築部分が建築基準法の定める建ぺい率に適合しないことを理由に確認が得られなかった。しかし、Xが続いてY水道局に対して給水装置新設工事の申し込みをしたため、Y水道局給水課長は、違反建築物に対する給水制限実施要領に基づき、当該申込の受理を拒絶して申込書を返戻するとともに、建築基準法違反状態を是正して建築確認を受けた後に再度申し込むようにYに勧告した。
このため、Xは、既存の給水装置から増築部分への私設水道装置の設置工事を行うとともに、Y水道局が当該申込みの受理を拒絶して1年半以上の間給水を停止したことは水道法15条に違反しており、Xの給を受けるべき権利を侵害したとして、Yを被告とする損害賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
違法建築物についての給水装置新設工事の申込の受理を市が事実上拒否することは、不法行為法上の損害賠償責任を構成するか。
(判旨)
「被上告人市の水道局給水課長が上告人の本件建物についての給水装置新設工事申込の受理を事実上拒絶し、申込書を返戻した措置は、右申込の受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、上告人に対し、右建物につき存する建築基準法違反も状態を是正して建築確認を受けたうえ申込をするよう一応の勧告をしたものにすぎないと認められるところ、これに対し上告人は、その後1年半余を経過したのち改めて右工事の申込をして受理されるまでの間右工事申込に関してなんらの措置も講じないままこれを放置していたのであるから、右の事実関係の下においては、前記被上告人市の水道局給水課長の当初の措置のみによっては、未だ、被上告人市の職員が上告人の給水装置工事申込の受理を違法に拒否したものとして、被上告人市において上告人に対し不法行為上の損害賠償の責任を負うものとするには当たらないと解するのが相当である。」
(ポイント)
市水道局給水課長が違法建築物の給水装置新設工事の申込みの受理を事実上拒絶し申込書を返戻した措置は、当該申込みの受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受けた上で申込をするよう勧告したものにすぎず、市は不法行為上の損害賠償責任を負わない。
52.川崎民商事件(最判昭47.11.22)
(事案)
川崎民主商工会会員であるYが提出した昭和37年分の所得税確定申告書について、過少申告の疑いをもった川崎税務署は、所得税の賦課徴収事務に従事する職員を派遣して、Yに対し、売上帳・仕入帳等の提示を求めたところ、Yがこれ拒否したため、Yは所得税法(旧)70条10号が規定する検査拒否罪に問われることとなった。
(争点)
{C}① 所得税法(旧)70条10号・63条は規定する税務職員による質問検査は、裁判所の判断を経ることなく行政庁の判断だけで行えるとしている点で、検索・押収には正当な理由に基づいて裁判所が発する令状が必要であるとする憲法35条に違反しないか。
{C}② 所得税法(旧)70条10号・12号・63条が規定する税務署職員による質問検査は、自己に不利益な供述の強要を禁止する憲法38条に違反しないか。
(判旨)
「所論のうち、憲法35条違反をいう点は、旧所得税法70条10号・63条の規定が裁判所の令状なくして強制的に検査することを認めているのは違憲である旨の主張である。たしかに、旧所得税法70条10号の規定する検査拒否に対する罰則は、同法63条所定の収税官史による当該帳簿等の検査の受忍をその相手方に対して強制する作用を伴うものであるが、同法63条所定の収税官史の検査は、もっぱら、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であって、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない。
また、右検査の結果過少申告の事実が明らかとなり、ひいては所得税逋脱の事実の発覚にもつながるという可能性がかんがえられないわけではないが、そうであるからといって、右検査が、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならない。けだし、この場合の検査の範囲は、前記の目的のため必要な所得税に関する事項にかぎられており、また、その検査は、同条各号に列挙されているように、所得税の賦課徴収手続上一定の関係にある者につき、その者の事業に関する帳簿その他の物件のみの範囲が定められているのであって、所得税の逋脱その他の刑事責任の嫌疑を基準に右の範囲が定められているのではないからである。
さらに、この場合の強制の態様は、収税官史の検査を正当な理由がなく拒む者に対し、同法70条所定の刑罰を加えることによって、間接的心理的に右検査の受忍を強制しようとすうるものであり、かつ、右の刑罰が行政上の義務違反に対する制裁通して必ずしも軽微なものとはいえないにしても、その作用する強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同旨すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである。国家財政の基本となる徴税権の適正な運用を確保し、所得税の公平確実な賦課徴収を図るという公益上の目的を実現するために収税官史による実効性のある検査制度が欠くべからざるものであることは、何人も否定しがたいものであるところ、その目的、必要性にかんがみれば、右の程度の強制は、実効性確保の手段として、あながち不均衡、不合理なものとはいえないのである。
憲法35条1項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、当該手続が刑事責任追及を目的とするものではないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら、前に述べた諸点を総合して判断すれば、旧所得税法70条10号、63条に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといって、これを憲法35条の法意に反するものとすることはできず、前記規定を違憲であるとする所論は、理由がない。
所論のうち、憲法38条違反という点は、旧所得税法70条10号、12号、63条の規定に基づく検査、質問の結果、所得税逋脱(旧所得税法69条)の事実が明らかになれば、税務職員は右の事実を告発できるのであり、右検査、質問は、刑事訴追をうけるおそれのある事項につき供述を要するもので意見である旨の主張である。
しかし、同法70条10号、63条に規定する検査が、もっぱら所得税の公平確実な賦課徴収を目的とする手続であって、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また、そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでないこと、および、このような検査制度に公益上の必要性と合理性の存することは、前示のとおりであり、これらの点について、同法70条12号、63条に規定する質問も同様であると解すべきである。そして、憲法38条1項の法意が、何人も自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであると解すべきことは、当裁判所大法廷の判例(昭和32年2月20日判決)とするところであるが、右規定による保障は、純然たる刑事手続であるばかりでなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶものと解するのを相当とする。しかし、旧所得税法70条10号、12号、63条の検査、質問の性質が上述のようなものである以上、右各規程そのものが憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」を強要するものとすることはできず、この点の所論も理由がない。」
憲法38条1項
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
(ポイント)
{C}① 刑事責任追及を目的としない手続において、一切の強制が憲法35条1項の保障の枠外にあると解すべきではないが、税務署職員による質問検査があらかじめ裁判官の発する令状によるべきことを一般的要件としていなくても、憲法35条1項に違反しない。
憲法35条1項
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
{C}② 憲法38条1項による保障は、純然たる刑事手続以外でも、それが実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶと解すべきであるが、税務署職員による質問検査は、そのような手続には当たらないので、自己に不利益な供述を強要するものではない。
53.鉄道公安職印の実力行使(最大判昭48.4.25)
(事案)
国鉄労働組合門司地方本部に所属するYらは、同労働組合が行った年度末手当要求に関する闘争に参加するため、国鉄久留米駅東てこ扱所2階の信号所に立ち入り、多数の労働組合員らによるいわゆるピケットを指導した。そして、久留米駅長の命を受けた同駅助役らの再三の退去要求に応じなかったため、現地対策本部から実力による排除の命を受けた鉄道公安職員らが退去強制を行おうとしたところ、2階からこれに水を浴びせかけるなどして抵抗したことから、住居侵入罪ならびに公務執行妨害罪により起訴された。
(争点)
鉄道公安職員が、鉄道営業法42条1項に基づき不法行為者を鉄道施設外に退去させるにあたって強制力を用いることは、憲法31条等との関係において認められるか。
憲法31条
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(判旨)
「まず、鉄道営業法42条1項は、旅客、公衆が停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入ったとき等同項各号に定める所為に及んだ場合、鉄道係員は、当該旅客、公衆を車外または鉄道地外に退去させうる旨を規定している。けだし、鉄道施設は、不特定多数の旅客および公衆が利用するものであり、また、性質上特別の危険性を蔵するものであるから、車内または鉄道地内における法規ないし秩序違反の行動は、これをすみやかに排除する必要があるためにほかならない。すなわち、同条項は、鉄道事業の公共性にかんがみ、事業の安全かつ確実な運営を可能ならしめるため、とくにかかる運営につき責任を負う鉄道事業者に直接にこの排除の係員が当該旅客、公衆を車外または鉄道地外に退去させるにあたっては、まず退去を促して自発的に退去させるのが相当であり、また、この方法をもって足りるのが通常であるが、自発的な退去に応じない場合、または危険は切迫する等やむをえない事情がある場合には、警察官の出動を要請するまでもなく、鉄道係員において当該具体的事情に応じて必要最小限度の強制力を用いるものであり、また、このように解しても、前述のような鉄道事業の公共性に基づく合理的な規定として、憲法31条に違反するものではないと解すべきである。
ところで、本件について考察するに、前記のとおり、久留米駅東てこ扱所2階の信号所に立ち入り、階段にすわり込んだ労働組合員らは、いずれもその勤務から離れ、久留米駅長等の当局側の警告を無視して、国鉄の業務運営上重要な施設を占拠し、その管理者の管理を事実上無視して、国鉄の業務運営上重要な施設を占拠し、その管理者を事実上排除したものであるから、このような場合は、鉄道営業法37条、42条1項3号にいう公衆が鉄道敷地内にみだりに立ち入った場合にあたるというを妨げず、これに対し、列車の正常かつ安全な運行に責任を有する国鉄当局が、同信号所の管理を回復するため、労働組合員らの退去を促し、さらにはその排除を図りうることは、当然の事理というべきである。
すなわち、このような場合、鉄道公安職員においては、前記『鉄道公安職員基本規定』所定の職務を行なう国鉄職員、すなわち、鉄道営業法42条1項所定の当該鉄道係員に属するものとして、すみやかに国鉄の業務運営上の障害を除去するため、前記信号所に立ち入りあるいは階段にすわり込んだ労働組合員らを退去させることができるものであり、その際には、前述のように、当該具体的事情に応じて必要最小限の強制力を用いることができるものと解すべきであって、検察官の所論引用の判例のうち仙台高等裁判所昭和36年5)第616号同38年3月29日判決および東京高等裁判所昭和39年5)第2487号同40年9月14日判決は、いずれもこの趣旨を判示したものである。そして、鉄道公安職員は、必要最小限度の強制力の行使として、信号所階段、その付近、同所内にいる労働組合員らに対し、拡声器等により自発的な退去を促し、もしこれに応じないときは、階段の手すりにしがみつき、あるいはたがいに腕を組む等して居すわっている者にい対し、手や腕を取ってこれをほどき、身体に手をかけて引き、あるいは押し、必要な場合にはこれをかかえ上げる等して、階段から引きおろし、これが実効を収めるために必要な限度で階段か下から適当な場所まで腕をとって連行する行為をもなしうるものと解すべきであり、また、このような行為がひつよ得最小限のものかどうかは、労働組合員らの抵抗の状況等の具体的な事情を考慮して決定すべきものである。」
(ポイント)
鉄道公安職員が、国鉄労働組合員を鉄道施設外に退去させるにあたって、本件のような行為をなすことは、必要最小限度の強制力の行使として許される。
54.刑罰と秩序罰の併科(最判昭39.6.5)
(事案)
Yらは、秋田地裁で行われた住居侵入罪に関する刑事裁判において、事件の証人として宣誓したにもかかわらず、裁判官による尋問に対して正当な理由なく証言を拒んだため、刑事訴訟法160条に基づき各5000円の過料に処せられたが、その後あらためて同法161条違反を理由に起訴された。
(争点)
同一の行為につき刑事訴訟法160条に基づく過料と同法161条に基づく罰金・拘留を併科することは、罰刑法定主義を定める憲法31条および二重処罰の禁止を定める同法39条後段に違反しないか。
(判旨)
「刑訴160条は訴訟手続上の秩序を維持するために秩序違反行為に対して当該手続を主宰する裁判所または裁判官により直接に科せられる秩序罰としての過料を規定したものであり、同161条は刑事司法に協力しない行為に対して通常の刑事訴訟手続により科せられる刑罰としての罰金、拘留を規定したものであって、両者は目的、要件及び実現の手続を異にし、必ずしも二社択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解するべきであり、右規定は憲法31条、同39条公団に違反しない。」
(ポイント)
同一の行為につき両者を併科するとは憲法31条9条後段に違反しない。併科も許される。
55.課外クラブ活動中の事故
(事案)
沖縄県金武町立金武中学校の2年生だったXは、友人らとともに体育館に行ったところ、体育館内においては課外クラブ活動であるバレーボール部とバスケットボール部とが両側に分かれて練習していたが、平素はバレーボール部の指導・監督をしている顧問の教諭は翌日の運動会の予行演習の準備のため運動場の方に行っておらず、また、他の教諭も体育館には居合わせていなかった。そこで、Xらは、トランポリンを倉庫から無断で持ち出し、バレーコートとバスケットコートの中間の壁側に設置してしばらく遊んでいたところ、バレーボール部員のAから練習の邪魔になるからトランポリン遊びを中止するように注意されたが、Xがこれに反発したため、AはXを倉庫に連れ込んだ上で鉄拳で2・3回Xの左顔面を殴打した。その結果、Xは1か月近くで左眼の視力を全く失うに至り、外傷性網膜全剥離と診断された。
このため、Xは、本件事故がバレーボール部の顧問の教諭が指導監督義務を怠ったために生じたものであるとして、金武町(Y)に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて出訴した。
国家賠償法1条1項
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
(争点)
公立中学校の生徒が課外クラブ活動中の他の生徒との喧嘩から左眼を失明した事故につき、当該クラブ活動に立ち会っていなかった顧問の教諭には過失があるといえるか。
(判旨)
「前記事実関係によれば、本件事故当時、体育館内においては、いずれも課外のクラブ活動であるバレーボール部とバスケットボール部とが両側に分かれて練習していたのであるが、本件記録によれば、課外のクラブ活動は、希望する生徒による自主的活動であったことが窺われる。もとより、課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育活動の一環として行われるものである以上、その実施について、顧問の教諭を始め学校側に、生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務があることを否定することはできない。しかしながら、課外のクラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべきものであることを鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問の教諭としては、個々の活動に常時立ち合い、監視指導すべき義務までを負うものではないと解するのが相当である。
ところで、本件事件は、体育館の使用をめぐる生徒間の紛争に起因するものであるところ、本件事故につきバレーボール部顧問の教諭が代わりの監督者を配置せずに体育館を不在にしていたことが同教諭の過失であるとするためには、本件のトランポリンの使用をめぐる喧嘩が同教諭にとって予見可能であったことを必要とするものというべきであり、もしこれが予見可能でなかったとすれば、本件事故の過失責任を問うことはできないといわなければならない。そして、右予見可能性を肯定するためには、従来からの金武中学校における課外クラブ活動中の体育館の使用方法とその範囲、トランポリンの管理等につき生徒に対して実施されていた指導の内容並びに体育館の使用方法等についての過去における生徒間の対立、紛争の有無及び生徒間における右対立、紛争の生じた場合に訴えることがないように教育、指導がされていたか否か等を更に総合検討して判断しなければならないものというべきである。」
(ポイント)
課外クラブ活動の顧問教諭には事故発生を未然に防止すべき一般的注意義務はあるが、個々の事故時にクラブ活動に立ち会っていなかったとしても、当該事故が発生する危険性を具体的に予見することができるような特段の事情がない限り、当該事故について過失はない。
なお、過失なしとしても、公立中学校の課外クラブ活動が、「公権力の行使」に当たることには注意。
56.スナック事件(最判昭57.1.19)
(事案)
暴行・傷害など前科23犯のAが、阪急淡路駅付近の「スナック舞子」および「スナックニュー阪急」において、泥酔の上、刃渡り7.5センチの飛び出しナイフを見せながら店員や客に「馬鹿野郎」「刺されたいか」などと怒鳴ったりしたため、「スナックニュー阪急」の支配人Xなどは、Aを淡路警察署に連れて行くとともに、途中でAから取り上げた本件ナイフを警察官に渡した。そこで、淡路警察署の警察官は、Aに本籍・氏名等を問うとともに身体検査を行い、大阪府警察本部にAの前科等を照会したが、当時、同本部には大阪府外の者の前科は登録されていなかったため、Aの前科は判明しなかった。その結果、淡路警察署員は、Aが相当酩酊しており、その供述態度も反抗的で信用できるものではなかったにもかかわらず、Aの行為は犯罪を構成せず、逮捕、保護または引取りを手配し、ナイフを領置・保管したりする必要はないと判断し、Aにナイフを持たせたまま帰宅させた。
そのため、Aは、警察署からの帰途に、本件ナイフでXの胸部や顔面を切りつけ、Xに左眼失明等の重傷を負わせた。
以上の経緯から、Xは、淡路警察署の警察官がAを逮捕せず、また、本件ナイフを領置することもなく帰宅させたことは、警察官としての職務に違背し違法であるとして、大阪府(Y)を被告として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
泥酔してナイフを出しながら客などを脅した者からナイフを提出させて一時保管の措置などをとることなく、これを帰宅させた警察の行為(不作為)は、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
(判旨)
「以上の事実関係からすれば、Aの本件ナイフの形態は鉄砲刀剣類等取締法22条の規定により禁止されている行為であることが明らかであり、かつ、同人の前記の行為が強迫罪にも該当するような危険なものであったのであるから、淡路警察署の警察官としては、飲酒酩酊したAの前記弁解をうのみにすることなく、同人を警察に連れてきたXらに対し質問するなどして「スナックニュー阪急」その他でのAの行動等について調べるべきであったといわざるをえない。そして、警察官が、右のような措置をとっていたとすれば、Aが警察に連れてこられた経緯や同人の異常な挙動等を容易に知ることができたはずであり、これらの事情から合理的に判断すると、同人に本件ナイフを携帯したまま帰宅することを許せば、帰宅途中ナイフで他人の生命又は身体に危害をお及ぼすおそれが著しい状況にあったというべきであるから、同人に帰宅を許す以上少なくとも同法24条の2第2項の規定により本件ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき義務があったものとっ解するのが相当であって、前記警察官が、かかる措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し違法であるというほかはない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、所論警察官の違法行為とXの受傷により被った損害との間に相当因果関係があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。
(ポイント)
他人の生命または身体に危害を及ぼす蓋然性の高い者がナイフを所持していた場合に、そのナイフについて一時保管措置を怠った警察官の不作為は、公権力の行使にあたる。
つまり、「公権力の行使」には作為だけでなく、不作為も含まれることに注意。
57.砲弾回収措置の不作為(最判昭59.2.23)
(事案)
東京都新島木村の前海岸付近では、第二次世界大戦後連合国軍の指令の下で大量に海中放棄された旧日本陸軍の砲弾類が風や波浪の影響により度々海岸に打ち上げられるようになり、陸上自衛隊や海上自衛隊が数次にわたってその回収作業を実施していた。しかし、それでも未回収の砲弾類が多く存在し、子ども達の中には、海岸で拾得した砲弾類の火薬を抜き取り、これに点火し花火のように遊ぶ者がいたり、大人達の中にも、海中に潜ってこれを拾い鉄屑として古物回収業者に売却する者や抜き取った火薬を焚火の火付けに使用している者などがいた。これにつき、新島警察署は、これを放置すれば人身事故等の発生する危険性があることを察知し、砲弾類回収の必要性を認めて、島民に対して砲弾類を発見した場合にはこれを警察に届け出るよう呼びかけるとともに、警視庁に対する正規の報告文書に前記事情を記載して報告し、砲弾類の処理を自衛隊に依頼するよう上申していたが、警視庁から自衛隊に対する依頼はなされていなかった。
そうするうちに、昭和44年6月29日午後3時40分ごろ、前浜海岸砂防堤付近において、Xら3名が他の中学生であるAなどから教えられた焚火で暖をとっていたところ、Aらがその焚火の中に投入していた砲弾が突然爆発し、この爆発によってXらのうち1名が死亡、1名が右眼球破裂、左網膜剥離等の障害を負うに至った。このため、負傷者および死亡者の遺族らが、東京都(Y)を相手取り、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて出訴した。
(争点)
海辺に打ち上げられた旧日本軍の砲弾により人身事故が発生した場合において、警察官がその回収等の措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
(判旨)
「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とするものであるから(警察法2条参照)、警察官は、人の人生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞れのある天災、事変、危険物の爆発等危険な事態があって特に急を要する場合においては、その危険物の管理者その他の関係者に対し、危険防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができるものとされている(警察官職務執行法4条1項参照)。もとより、これは、警察の前記のような責務を達成するために警察官に与えられた権限であると解されるが、島民が居住している地区からさほど遠からず、かつ、海水浴場として、一般大衆に利用されている海浜やその付近の海底に砲弾類が投棄されてたまま放置され、その海底にある砲弾類が毎年のように海浜に打ち上げられ、島民等が砲弾類の危険性についての知識の欠如から不用意に取り扱うことによってこれが爆発して人身事故等の発生する危険があり、しかも、このような危険は毎年のように海浜に打ち上げられることにより継続して存在し、島民等は絶えずかかる危険に曝されているが、島民等としてはこの危険を通常の手段では除去することはできないため、これを放置するときは、島民等の生命、身体の安全が確保されないことが相当の蓋然性をもって予測されうる状況のもとにおいて、かかる状況を警察官が容易に知りうる場合には、警察官において右権限を適切に行使し、自ら又はこれを処分する権限・能力を有する機関に要請するなどして積極的に砲弾類を回収するなどの措置を講じ、もって砲弾類の爆発による人身事故の発生を未然に防止することは、その職務上の義務でもあると解するのが相当である。
してみれば、原審の確定した前記一の事実関係のもとでは、新島警察署の警察官を含む警視庁の警察官は、遅くとも昭和41、42年ころ以降は、単に島民等に対して砲弾類の危険性についての警告や砲弾類を発見した場合における届け出の催告等の措置をとるだけでは足りず、更に進んで自ら又は他の機関に依頼して砲弾類を積極的に回収するなどの措置を講ずるべき職務上の義務があったものと解するのが相当であって、前記警察官が、かかる措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し、違法であるといわなければならあに。」
(ポイント)
旧日本陸軍の砲弾により人身事故が発生した場合、警察官がその回収等の措置をとらなかったことは、違法な公権力の行使に該当する。
58.水俣病の拡大と規制権限の不行使(最判昭59.2.23)
(事案)
水俣病は、水俣病またはその周辺海域の魚介類を多量に摂取したことによって起こる中毒性中枢神経疾患であり、症状が重篤な時は死亡するに至る病気であるが、昭和31年5月1日の「公式発見」当時は、その原因が不明であった。その後、昭和33年6月開催の参議院社会労働委員会において、厚生省環境衛生部長が原因物質は水俣市の肥料工場から流失したと推定される旨の発言をしたが、通産省軽工業局長は、同年9月頃、厚生省に対して、現段階では断定的な見解を述べることがないよう申し入れた。そして、昭和34年11月12日に至り、厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会は、水俣病の主因を成すものがある種の有機水銀化合物であるとの答申を厚生大臣に提出し、国や熊本県(Yら)は、遅くとも同年11月末頃には、原因物質の排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度の蓋然性をもって認識し得る状況となり、その頃までには同工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析技術も開発されていたと指摘した。
しかし、現実にチッソ株式会社が水俣工場のアセトアルデヒド製造を中止したのは昭和43年5月であり、国が水俣病の原因がチッソ水俣工場内で生成されたメチル水銀化合物である旨の政府見解を発表したのは同年9月、水俣湾およびその周辺海域を水質二法(公共用水域の水質の保全に関する法律、工場排水等の規制に関する法律)に基づく指定水域に指定したのは翌昭和44年であった(なお、水質二法は、昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止されている。)。
そこで、水俣病患者であると主張するXらは、Yらが水俣病の発生および被害拡大の防止のために規制制限を行使することを怠ったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて出訴した。
(争点)
国や熊本県が、それぞれ水質二法や県漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。
(判旨)
「昭和34年11月末の時点で、①昭和31年5月1日の水俣病の公式発見から起算しても既に3年半が経過しており、その間、水俣病はその周辺海域の魚介類を摂取する住民の命、健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続しいているのであって、上告人国は、現に多数の水俣病患者が発生し、死亡者も相当数に上がっていることを認識していたこと、②上告人国においては、水俣病のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと、③上告人にとって、チッソ水俣病工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析をすることは可能であったことといった事情を認めることができる。なお、チッソが昭和34年12月に整備した前記排水浄化装置が水銀の除去を目的としたものではなかったことを容易に知り得たことも、
前記認定のとおりである。そうすると、同年11月末の時点において、水俣病及びその周辺海域を指定水域に指定すること、当該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物が検出されないという水質基準を定めること、アセトアルデヒド製造施設を特定施設に定めることという上記規制権限を行使するために必要な水質二法所定の手続を直ちに執ることが可能であり、また、そうすべき状況にあったものといわなければならない。そして、この手続に要する期間を考慮に入れても、同年12月には、主務大臣として定められるべき通商産業大臣において、上記規制権限を行使して、チッソに対し水俣工場のアセトアルデヒド製造施設からの工場排水についての処理方法の改善、当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずることが可能であり、しかも、水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると、直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当である。また、この時点で上記規制権限が行使されていれば、それ以降の水俣病被害拡大を防ぐことができたこと、ところが、実際には、その行使がされなかったために、被害が拡大する結果となったことも明らかである。
本件における以上の諸事情を総合すると、昭和35年1月以降、水質二法に基づく上記規制権限を行使しなかったことは、上記規制権限を定めた水質二法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。
したがって、同項による上告人国の損害賠償責任を認めた原審の判断は、正当として是認することができる。この点に関する上告人国の論旨は採用することができない。
次に、上告人県の責任についてみると、以上説示したとこrによれば、前記事実関係の下において、熊本県知事は、水俣病にかかわる前記諸事情について上告人国と同様の認識を有し、又は有し得る状況にあったのであり、同知事には、昭和34年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使すべき作為義務があり、昭和35年1月以降、この権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くものとして、上告人県が国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は、同規制が、水俣動植物の繁殖保護等を直接の目的とするものではあるが、それを摂取する者の健康の保持等をもその究極の目的とするものであると解されることからすれば、是認することができる。」
(ポイント)
国は、昭和34年11月末の時点で、水俣病などを指定水域に指定する水質二法に基づく規制権限を行使することが可能であり、そうすべき状況にあった。また、熊本県知事も、同年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使するべき作為義務を負っていた。
したがって、昭和35年1月以降にこれら規制権限を行使しなかったことは、水質二法や県漁業調整規則の目的などに照らし、著しく合理性を欠くものといえ、国家賠償法上違法である。
59.宅配郷社に対する権限の不行使(最判平元.11.24)
(事案)
有限会社誠和住建は(A社)は、昭和47年10月に京都府知事から宅地建物取引業免許を付与され、昭和50年10月にその更新を受けた(この免許およびその更新は、宅建業法の定める免許基準に適合しないことが記録から窺われる。)が、その実質上の経営者Bは多額の負債を抱えており、A社の免許が更新される直前には最初の苦情が京都府(Y)に寄せられ、免許更新後の昭和51年頃にはA社の債務不履行が多くなっていた。そこで、Yの担当職員は、昭和51年7月8日にA社に対する立入検査を行い、新規契約の締結の禁止を指示したが、その後もA社に対する苦情が相次いだため、同年12月17日に宅建業法69条に基づく公開の聴聞を行い、翌年4月7日に京都府知事がA社の免許を取り消した。
一方で、この間に、Xは、A社が同社所有の建売住宅として売り出したのを信じて昭和51年9月3日にA社と本件土地建物の売買契約を締結したが、結局その所有権を取得できず、A社に支払った740万円相当の損害を被った。このため、Xは、A社の代表取締役Cに対して損害賠償請求訴訟を提起するとともに(この訴訟ではXの勝訴が確定)、Yに対して国家賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
{C}① 宅配業法所定の免許基準に達しない免許の付与ないし更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
{C}② {C}宅建業者に対する知事の監督処分権限の行使の遅れは、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
(判旨)
「右事実関係によれば、京都府知事が誠和住研に対し本件免許を付与し更にその後これを更新するまでの間、誠和住研の取引関係者からの担当職員に対する苦情申出は1件にすぎず、担当職員において双方から事情を聴取してこれを処理したというのであるから、本件免許の付与ないし更新それ自体は、法所定の免許基準に適合しないものであるとしても、その後に誠和住研と取引関係を持つに至った上告人に対する関係で直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為にあたるものではないというべきである。
また、本件免許の更新後は担当職員が誠和住研と被害者との交渉の経過を見守りながら被害者救済の可能性を模索しつつ行政指導を続けてきたなど前示事実関係の下においては、上告人が誠和住研に対し中間金390万円を支払った時点までに京都府知事において誠和住研に対する業務の停止ないし本件免許の取消をしなかったことが、監督処分権限の趣旨・目的に照らして著しく不合理であるということはできないから、右権限の不行使も国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。」
(ポイント)
{C}① 宅建業者に対する知事の免許の付与・更新が宅建業法所定の免許基準に適合しない場合でも、そのことが当該業者による不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係で、直ちに違法な行為には当たらない。
{C}② 宅建業者に対して知事が宅建業法に基づく業務停止処分・免許取消処分をしなかった場合でも、具体的事情の下で、当該処分権限が付与された趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り、当該業者による不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係で、違法な行為には当たらない。
60.クロロキン網膜症訴訟(最判平7.6.23)
(事案)
クロロキンは、昭和9年にドイツで合成に成功した化学物質であり、クロロキン製剤は、クロロキンの化合物を含有する製剤として、当初はマラリヤの治療薬として開発されたが、後には間接リュウマチ・エリテマトーテス・腎疾患・てんかんの治療にも使用されるようになり、わが国では、昭和30年3月から輸入販売が始まり、昭和35年12月から厚生大臣によって製造許可がなされるようになった。
しかし、このクロロキン製剤の服用によりクロロキン網膜症なる副作用が発生し、これによる患者には網膜障害が生じ、重症の場合には失明に至ることもまれではなく、そのような症例は、外国では昭和34年に初めて報告され、わが国では、昭和37年から昭和40年までの間に論文発表や症例報告がなされたが、その多くはクロロキン製剤の長期服用によりまれに生じるものとの位置づけであって、クロロキン製剤の有効性を否定するものではなかった。
その後、厚生大臣は、薬効問題懇談会の昭和46年7月7日の答申を受けて、日本薬局方に収載されている医薬品を含むすべての医薬品についての有効性および安全性の再評価作業に着手し、その結果、クロロキン製剤については、昭和51年7月に、マラリア・エリテストーテス・関節リウマチについては有効性・有用性が認められるものの、腎疾患については有効性と副作用を対比したとき副作用が上回る場合があるので有効性が認められず、てんかんについては有効と判定する根拠がないと公表された。
これに対し、昭和34年から昭和50年までの間に関節リウマチ・エリテマトーデス・腎疾患・てんかんのいずれかの治療のためにクロロキン製剤を服用して、クロロキン網膜症に罹患した被害者およびその相続人(Xら)は、厚生大臣がクロロキン製剤の製造承認等をした違法およびクロロキン網膜症の発生を防止するために適切な措置を執らなかった違法を主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
{C}① 厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認等の行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。
{C}② 厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。
(判旨)
「所論は、まず、厚生大臣が、リン酸クロロキン及びリン酸クロロキン錠を日本薬局方に収載し、キドラ及びCQCについて製造の許可又は承認及び効能追加の承認をしたことが違法であると主張するので、この点につき判断する。
前記の薬事法の目的に照らせば、厚生大臣は、特定の医薬品を日本薬局方に収載し、又はその製造の承認(承認事項の一部変更である効能追加の承認を含む。以下、同じ。)をするに当たって、当該医薬品の副作用を含めた安全性についても審査する権限を有する者であり、その時点における医学的、薬学的知見を前提として、当該医薬品の治療上の効能、効果と副作用を比較考量し、それが医薬品としての有用性を有するか否かを評価して、日本薬局方への収穫又は製造承認の可否を判断するものと解される。したがって、厚生大臣が特定の医薬品を日本薬局方に収載し、又はその製造の承認をした場合において、その時点における医学的、薬学的知見の下で、当該医薬品がその副作用を考慮してもなお有用性を肯定し得るときは、厚生大臣の薬局方収載等の行為は、国家賠償法1条1の適用上違法の評価を受けることはないというべきである。右の理は、製造の承認とその目的、性質を同じくする医薬品の製造の許可(旧薬事法26条3項)についても変わるところはないものと解される。
これを本件についてみると、前記の事実関係によれば、厚生大臣がクロロキン製剤について各行為をした昭和35年から昭和39年までの間においては、その副作用であるクロロキン網膜症に関する報告が内外の文献に現れ始めたばかりであって、報告内容も長期連用の場合のクロロキン網膜症の発症の危険性及び早期発見のための眼科的検査の必要性を指摘するにとどまり、クロロキン製剤の有用性を否定するものではなく、この間に我が国で報告された症例は合計17件であったというのであるから、これらの文献や症例報告に基づく当時の医学的知見の下においては、厚生大臣が、腎疾患及びてんかんを含めた前記各疾患に対するクロロキン製剤の有用性を肯定し得るものとして行った前記各行為に違法はないというべきである。
次に、所論は、厚生大臣がクロロキン製剤の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使して適切な措置を採らなかった違法を主張するので、この点につき判断する。
日本薬局方に収載され、又は製造の承認がされた医薬品が、その効能、効果を著しく上回る有害な副作用を有することが後に判明し、医薬品としての有用性がないと認められるに至った場合には、厚生大臣は、当該医薬品を日本薬局方から削除し、又はその製造の承認を取り消すことができると解するのが相当である。
薬事法は、厚生大臣は少なくとも10年ごとに日本薬局方の改定について中央薬事審議会に諮問しなければならないと規定する(41条3項)にとどまり、また、昭和54年法律第56号による改正後の薬事法74条の2のような製造の承認の取消しに関する明文の規定を欠くが、前記の薬事法の目的並びに医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認に当たっての厚生大臣の安全性に関する審査権限に照らすと、厚生大臣は、薬事法上右のような権限を有するものと解される。
厚生大臣の薬事法上の権限の行使についての右のような性質ないし特質を考慮すると、医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、厚生大臣が当該医薬品の副作用による被害の発生を防止するために前記の各権限を行使しなかったことが直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるものではbなく、副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、前記のような薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使は、副作用による被害を受けた者との関係において同項の適用上違法となるものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、前記の事実関係によれば、昭和37年以降我が国においても、文献等による症例の報告により、クロロキン製剤の副作用であるクロロキン網膜症に関する知見が次第に広まってきたものの、その内容はクロロキン製剤の有用性を否定するまでのものではなく、一方、クロロキン製剤のエリテマトーデス及び関節リウマチに対する有用性は国際的に承認され、昭和51年の再評価の結果の公表以前においては、クロロキン製剤は、根本的な治療法の発見されていない難病である腎疾患及びてんかんに対する有用性が認められ、臨床の現場において副作用であるクロロキン網膜症を考慮してもなお有用性を肯定し得るものとしてその使用が是認されていたというのであるから、当時のクロロキン網膜症に関する医学的、薬学的知見の下では、クロロキン製剤の有用性が否定されるまでには至っていなかったものということができる。したがって、クロロキン製剤の有用性が否定されるまでには至っていなかったものもということができる。したがって、クロロキン製剤について、厚生大臣が日本薬局方から削除や製造の承認の取消しの措置を採らなかったことが著しく合理性を欠くものとはいえない。」
(ポイント)
{C}① 本件において、厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載・製造の承認等の行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法とならない。
{C}② 本件において、厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とならない。
61.在宅投票事件(最判昭60.11.21)
(事案)
公職選挙法およびその委任による公職選挙法施行令は、疾病・負傷・妊娠・身体障害等のため歩行が困難である選挙人(「在宅選挙人」)について、投票所に行かずにその現在する場所において投票用紙に投票の記載をして投票することができる制度(「在宅投票制度」)を定めていたところ、昭和26年4月に行われた統一地方選でこの制度が悪用され、それによる選挙無効および当選無効の争訟が続出したことから、国会は、公職選挙法の一部を改正する法律を成立させて在宅投票制度を復活させるための立法を行わないでいた。
その結果、公職選挙法9条の規定による選挙権を有している小樽市在住のXは、担架等を用いなければ投票所に行くことができないため、昭和43年から47年までの間に実施された計8回の国政選挙ならびに地方選挙の投票をすることができなかったことから、在宅投票制度を廃止して復活しない本件立法不作為は、在宅選挙人の選挙権の行使を妨げ、憲法13条・14条・15条・44条・47条・93条の規定に違反する公権力の行使にあたるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を国(Y)に求めて提訴した。
憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
{C}③ 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
(争点)
国会議員による立法行為(立法の不作為を含む)は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使を構成するか。在宅投票制度を廃止し、これを復活させなかった行為は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使に該当するか。
(判旨)
「憲法51条が、『両議院の議員は、議院で行った演説、討議又は表決について、院外で責任を問はれない。』と規定し、国会議員の発言、表決につきその法的責任を免除しているのも、国会議員の立法過程における行動は政治的責任の対象とするにとどめるのが国民の代表者による政治の実現を期するという目的にかなうものである。との考慮によるのである。このように、国会議員の立法行為は、本質的に政治的なものであって、その性質上法的規制の対象になじまず、特定個人に対する損害賠償責任の有無という観点から、あるべき立法行為を措定して具体的立法行為の適否を評価するということは、原則的には許されないも尾いわざるを得ない。ある法律が個人の具体的権利利益を侵害するものであるという場合に、裁判所はその者の訴えに基づき当該法律の合憲性を判断するが、この判断は既に成立している法律の効力に関するものであり、法律の効力についての違憲審査がなされるからといって、当該法律の立法過程における国会議員の行動、すなわち立法行為が当然に法的評価に親しむものとすることはできないのである。
以上のとおりであるから、国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであって、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならない。
これを本件についてみると、前記のとおり、上告人は、在宅投票制度の設置は憲法の命ずるところであるとの前提に立って、本件立法行為の違法を主張するのであるが、憲法には在宅投票制度の設置を積極的に命ずる明文の規定が存しないばかりでなく、かえって、その47条は『選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。』と規定しているのであって、これが投票の方法その他選挙に関する事項の具体的決定を原則として立法的である国会の裁量的権限に任せる趣旨であることは、当裁判所の判例とするところである。そうすると、在宅投票制度を廃止しその後前記8回の選挙までにこれを復活しなかった本件立法行為につき、これが前示の例外的場合に当たると解すべき余地はなく、結局、本件立法行為につき、これが前示の例外的場合に当たると解すべき余地はなく、結局、本件立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないといわざるを得ない。」
(ポイント)
国会議員による立法行為につき、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うような例外的な場合でない限り、違法な評価は受けない。このように、極めて限定的にしか違法性を認めていない。その結果、在宅投票制度を廃止し、これを復活させない不作為は、違法な公権力の行使に該当しない。
62.在外邦人選挙権制限違憲事件(最判平17.9.14)
(事案)
改正前古色選挙法42条1項・2項は、選挙人名簿に登録されていない者および登録されることができない者は国政選挙の投票をすることができない旨を定めており、選挙人名簿への登録は、市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で、その者に係る当該市町村の住民票が作成された日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者についてのみ行われる(公職選挙法21条1項、住民基本台帳法15条1項)ため、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)は、選挙権を行使することができなかった。
その後、平成10年の公職選挙法の一部改正により、新たに在外選挙人名簿が調整されることとなり(同法30条の2以下)、それにより同法42条1項本文も「選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。」と定められたが、改正法附則8項により、当分の間は衆議院比例代表選出議員の選挙と参議院比例代表選出議員の選挙に限るとされていたため、その間、在外国民は週銀小選挙区の選挙と参議院選挙区選出議員の選挙についての選挙権を行使することができなかった。
そのため、在外国民であるXらが、国(Y)を相手取り、在外国民であることを理由に選挙権行使の機会を保障しないことが憲法14条1項、15条1項・3項、43条、44条ならびに市民的・政治的権利に関する国際規約(国際人権規約B規約)25条に違反することの確認と、平成8年10月20日に実施された衆議院議員総選挙の選挙権を行使できなかったことによる精神的苦痛に対する国家賠償を求めて出訴した。
(争点)
{C}① 在外国民が、平成10年改正前の公職選挙法により衆議院銀選挙・参議院議員選挙における選挙権を行使できなかったことが憲法・条約に違憲することの確認を求める訴訟を提起することは認められるか。また、平成10年改正後の公職選挙法附則8項により衆議院小選挙区選出議員の選挙と参議院選挙区選出銀の選挙についての選挙権ができなかったことが憲法・条約に違反することの確認を求める訴訟を提起することは認められるか。さらに、衆議小選挙区選出議員の選挙と参議院選挙区選出議員の選挙についての選挙権を有することの確認を求める訴訟を提起すること、認められるか。
{C}② 在外国民が平成8年10月20日に実施された衆議院銀総選挙において選挙権を行使できなかったことにつき、立法府である国会が公職選挙法の改正を怠っていたことは、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるか。
(判旨)
「〈確認の訴えについて〉
{C}① 本件の主位的確認請求に係る訴えのうち、本件改正前の公職選挙法が広告人らに衆議院
議員の選挙及び参議院議員の選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認を求める訴えは、選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認を求める訴えは、過去の法律関係の確認を求めるものであり、この確認を求めることが現に存する法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のために適切かつ必要な場合であるとはいえないから、確認の利益が認められず、不適法である。
{C}② また、本件の主位的確認請求に係る訴えのうち、本件改正後の公職選挙法が上告人らに衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認を求める訴えについては、他により適切な訴えによってその目的を達成することができる場合には、確認の利益を欠き不適法であるというべきところ、本件においては、後記3のとおり、予備的確認請求に係る訴えであるということができるから、上記の主位的確認請求に係る訴えは不適法であるといわざるを得ない。
{C}③ 本件の予備的確認請求に係る訴えは、公法上の当事者訴訟のうち公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、その内容をみると、公職選挙法附則8項につき所要の改正がされないと、在外国民である別紙当事者目録1記載の上告人らが、今後直近に実施されることになる衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において投票することができず、選挙権を行使する権利を侵害されることになるので、そのような事態になることを防止するために、同条上告人らが、同項が違憲無効であるとして当該各選挙につき選挙権を行使する権利を有することの確認をあらかじめ求める訴えであると解することができる。
選挙権は、これを行使することができなければ意味がないものといわざるを得なず、侵害を受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであるから、その権利の重要性にかんがみると、具体的な選挙につき選挙権を行使する権利の有無につき争いがある場合にこれを有することの確認の利益を肯定するべきものである。そして、本件の予備的確認請求に係る訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、上記の内容に照らし、確認の理胃液を肯定することができるものに当たるというべきである。なお、この訴えが法律上の争訟に当たることは論をまたない。
そうすると、本件の予備的確認請求に係る訴えについては、引き続き在外国民である同上告人らが、次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を請求する趣旨のものとして適法な訴えということができる。
{C}④ そこで、本件の予備的確認請求の当否について検討するに、前記のとおり、公職選挙法附則8項のうち、在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間同議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は、憲法15条1項及び3項、4条1項並びに44条ただし書きに違反するもので向こうであって、上告人らは、次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすすことができる地位にあるというべきであるというべきであるから、本件の予備的確認請求は理由があり、更に弁論をするまでもなく、これを認容すべきものである。
「〈国家賠償請求について〉国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。したがって、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって、当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるできであり、仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。しかしながら、立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国会議員の立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価をうけるものというべきである。最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁は、以上と異なる趣旨をいうものではない。
在外国民であった上告人らも国政選挙において投票する機会を与えられることを憲法上保障されていたのであり、この権利行使の機会を確保するためには、在外選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず、前記事実関係によれば、昭和59年に在外国民の投票を可能にするための法律案が閣議決定されて国会に提出されたものの、同法律案が廃案となった後、本件選挙の実施に至るまで10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったのであるから、このような著しい不作為は上記の例外的な場合に当たり、このような場合においては、過失の存在を否定することはできない。このような立法不作為の結果、上告人らは本件選挙において投票することはできない。このような立法不作為の結果、上告人らは本件選挙において投票することができず、これによる精神的苦痛を被ったものというべきである。したがって、本件においては、上記の違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求はこれを認容すべきである。」
(ポイント)
{C}① {C}平成8年10月20日実施の衆議院議員総選挙当時、公職選挙法が在外国民の選挙権行使を認めていなかったこと、また、平成10年改正後の公職選挙法附則8項の規定中、在外国民の選挙権を両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は、遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙の時点で、憲法15条1項などに違反するが、確認の利益を欠き不適法である。しかし、次回の衆議院小選挙区選出議員選挙・参議院選挙区選出議員選挙の選挙権を有する確認を求める訴えは、確認の利益が認められる。
{C}② 在外国民に国政選挙権行使の機会を保障するための立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず、10年以上の長きにわたって国会が立法措置を執らなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける著しい不作為にあたり、その過失も認められるため、国は在外住民に対して賠償義務を負う。
63.議員の免責特権と国家賠償責任(最判平9.9.9)
(事案)
昭和60年11月21日に開かれた衆議院社会委員会において、当時衆議院議員であり同委員会の医院であったYは、同日の議題であった医療法の一部を改正する法律案の審査に際し、地域医療計画における国の責任や医療圏・医療施設に関する都道府県の裁量権等の同法律案の問題点を指摘するとともに、札幌市の乙山病院の問題を取り上げて質疑し、同病院の院長Aが5名の女性患者に対して破廉恥な行為をしたことや、Aが薬物を常用するなど通常の精神状態にはないといったことを指摘して、現行の行政の中ではこのような医師をチェックすることができないのではないかと主張した。
この発言による指摘を受けたAが翌日自殺したことから、その妻であるXが、Yの発言によりAの名誉が毀損され、同人が自殺に追い込まれたとして、Yに対しては民放709条・710条に基づき、国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めて出訴した。
(争点)
国会議員が国会の質疑・演説・討論等の中でした個別の国民の名誉または信用を低下させる発言につき、国は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うか。
(判旨)
「所論は、特定の者を誹謗するにすぎない本件発言は、憲法51条が規定する『演説、討論又は表決』に該当しないのに、原審が上告人の被上告人Yに対する請求排斥したのは不当であるというものである。されたものであることが明ら
しかしながら、前記の事実関係の下においては、本件発言は国会議員である被上告人Yによって、国会議員としての職務を行なうにつきされたものであることが明らかである。そうすると、仮に本件発言が被上告人Yの故意又は過失による違法な行為であるとしても、被上告人国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である被上告人Y個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである。したがって、本件発言が憲法51条に規定する『演説、討論又は裁決』に該当するかどうかを論ずるまでもなく、上告人の被上告人に対する本訴請求は理由がない。
憲法51条は、『両議院の議員は、議院で行った演説、討議または表決について、院外で責任を問われない』と規定し、国会議員の発言、表決につきその法的責任を免除しているが、このことも、一面では国会議員の職務行為についての広い裁量の必要性を裏付けているということができる。もっとも、国会議員に右のような広範な裁量が認められるのは、その職権の行使を十全ならしめるという要請に基づくものであるうから、職務とは無関係に個別の国民の権利を侵害することを目的とするような行為が許されないことはもちろんであり、また、あえて虚偽の事実を摘示して個別の国民の名誉を毀損するような行為は、国会議員の裁量に属する正当な職務行為とはいえないというべきである。
以上によれば、国会議員が国会で行った質問等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
これを本件についてみるに、前示の事実関係によれば、本件発言が法律案の審議という
国会議員の職務に関係するものであったことは明らかであり、また、被上告人Yが本件発言をするについて同被上告人に違法又は不当な目的があったとは認められず、本件発言の内容が虚偽であるとも認められないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。したがって、被上告人国の国家賠償法上の責任を規定した原審の判断は、正当である。」
(ポイント)
国会議員が国会でした個別の発言につき、国家賠償法1条1項の違法な行為として国の損害賠償責任が肯定されるには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法・不当な目的をもって事実を摘示し、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを要する。
64.裁判行為と国家賠償法1条1項(最判昭57.3.12)
(事案)
ミシンの特注機械装置を製造販売していたXは,昭和42年12月に縫製業を営むA社から機械装置の注文を受け納入したが、A社は代金を支払わず、機械の調子が悪いことを理由に数か月使用した後これを返品した。一方で、Xは、昭和43年1月に同じA社からミシンの修理を依頼されたが、これを修理しないまま留置し、昭和44年11月に至って未修理のままこれをA社に返品した。
そこで、A社は、Xがミシンを修理しないまま1年10か月にわたって留置したことによる損害の賠償を求めて民事訴訟を提起したところ、Xは前記機械装置の使用による価値減少分についての損害賠償請求権を被担保債権とする留置権の成立を抗弁として提出したが、大阪地裁昭和47年1月21日判決は、Xの主張する被担保債権と留置権との間には牽連性が認められないことを理由にXの抗弁を否定し、A社の主張を認めたため、Xが控訴しないまま同判決が確定した。
ところが、その後になって、Xが、商人間における双方にとっての商行為から生じた債権を被担保債権とする場合については個別的牽連性がないものについても留置することを認める商法521条の規定を知るに及んで、前記の判決を行った裁判官が商法521条を適用しなかったままXを敗訴せしめたのは国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使にあたるとして、国(Y)に対して損害賠償を求める訴えを提起した。
(争点)
裁判官がした訴訟の裁判は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使を構成するか。
(判旨)
「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。したがって、本件において仮に前訴判決に所論のような法令の解釈・適用の誤りがあったとしても、それが上訴による是正の原因となるのは格別、それだけでは未だ右特別の事情がある場合にあたるものとすることはできない。」
(ポイント)
裁判官がした争訟の判決につき、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使があったとするためには、当該裁判官が違法・不当な目的をもって裁判をしたなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るようなs特別の事情があることが必要である。
65.「その職務を行うについて」の意味(最判昭31.11.30)
(事案)
警視庁に所属する巡査Aは、職務行為を装って金品を強奪する目的で、非番の日を選んで、制服制帽を着用の上、同僚から盗んだ拳銃を携帯して隣接する神奈川県川崎市に行き、川崎駅で本件被害者Bを不審尋問を装って呼び止めた。そして、Aは、駅事務室でBの所持品を取り調べ、その中にあった現金等が犯罪の証拠物に該当する疑いがあると主張してこれを受け取った上で、Bを本署に連行すると偽って連れ出したが、途中で自らが逃走しようとした際に声をたてられたので、前記拳銃を発射してBを死に至らせた。
そのため、Bの遺族(X)は、東京都(Y)を相手取り国家賠償を請求したが、Y側が本件Aの行為は国家賠償法1条1項に規定する「その職務を行なうについて」に該当しないと主張したため、出訴に及んだ。
(争点)
当初より職務執行の意思がなく、単に他人の金品を不法に領得する目的を有するに過ぎない公務員の行為も、国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」の要件を充たすか。
(判旨)
「原判決は、その理由において、国家賠償法1条の職務執行とは、その公務員が、その所為に出づる意図目的はともあれ、行為の外形において、職務執行を認め得べきものともって、この場合の職務執行なりとするほかないのであるとし、即ち、同条の適用を見るがためには、公務員が、主観的に権限行使の意思をもってした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限るとの解釈を排斥し、本件において、A巡査がもっぱら自己の利をはかる目的で「警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、その目的をとげた、判示のごとき職権乱用の所為をもって、同条にいわゆる職務執行について違法に他人に損害を加えたときに該当するものと解したのであるが同条に関する右の解釈は正当であるといわなければならない。けだし、同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる作為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の損益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。」
(ポイント)
国家賠償法1条1項が規定する。公務員が「その職務を行なうについて」違法に他人に損害を加えたとは、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限定せず、たとえ自己の利を図る目的をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれにより他人に損害を加えたときも、これに該当する。
外形、外見から判断するという外形説を採用している。
66.加害公務員の特定(最判昭57.4.1)
(事案)
大蔵事務官として林野税務署に勤務するXは、昭和27年6月に実施された定期健康診断において胸部エックス線間接撮影による検診を受けたところ、その撮影フィルムにはXが初期の肺結核に罹患していることを示す陰影があったにもかかわらず、税務署長からは特別の指示をうけなかった。そのため、Xは、従来どおり外勤の職務に従事した結果、翌28年6月の定期健康診断によりその事実が判明するまでの間に病状が悪化させ、長期療養を余儀なくされた。
そこで、Xは、国(Y)を相手に損害賠償を求める訴訟を提起したが、原審が認定した事実関係からは、レントゲン写真の読映にあたった医師が過失により陰影を看過したのか、それを報告する懈怠があったのか、あるいは林野税務署の職員が執るべき処置を執らなかったのか、さらには両者の中間にある職員が報告の伝達を怠ったのかが判明しなかった。
(争点)
公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合、具体的に加害行為を特定できなければ国または公共団体は損害賠償責任を負わないか。
(判旨)
「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じせしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものなのであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのであれば右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべきによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当であり、原審の見解は、右と趣旨を同じくする限りにおいて不当とはいえない。しかしながら、この法理が肯定されるのは、それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の行為に当たる場合に限られ、一部にこれに該当しない行為者が含まれている場合には、もとより右の法理は妥当しないのである。
本件における右検診等の行為が上告人の職員である医師によって行われたものであれば、同人の違法な検診行為につき上告人に対して民放715条の損害賠償責任を問疑すべき余地があり、ひいてはさきに述べた一般的法理に基づいて上告人の賠償責任を肯定しうる可能性もないではないが、仮に上告人の主張するように、右検診等の行為が林野税務署長の保健所への嘱託に基づき訴外岡山県の職員である同保健所勤務の医師によって行われたものであるとすれば、右医師の検診等の行為は右保健所の業務としてされたものというべきであって、たとえそれが林野税務署長の嘱託に基づいてされたものであるとしても、そのために右検診等の行為が上告人国の事務の処理とんり、右医師があたかも上告人国の機関ないしその補助者として検診等の行為をしたものと解さなければならない理由はないから、右医師の検診等の行為に不法行為を成立せしめるような行為があっても、そのために上告人が民放の前記法条による損害賠償責任を負わなければならない理由はないのである。」
(ポイント)
国・公共団体に属する数人の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせて場合、それが具体的にどの公務員のそのような違法行為によるものであるかと特定することができなくても、当該一連の行為によるものであるかをとくていすることができなくても、当該一連の行為のうちのいずれかに故意・過失による違法行為があったのでなければ被害が生ずることはなかったのであろうと認められるときは、国・公共団体は当該賠償責任を免れることはできない。つまり、加害行為者・加害行為を必ずしも特定できなくてもよい。
67.無罪の刑事判決と国家賠償(最判昭53.10.20)
(事案)
昭和27年に起きた国鉄根室本線の鉄道線路爆破事件で、列車往来危険罪・火薬類取締法違反の罪などに問われ、逮捕・勾留・起訴の後、控訴審において無罪判決を受けたXが、国と捜査にあたった警察官・控訴の提起・追行にあたった検察官を被告として、国家賠償を求めた。
(争点)
刑事裁判において無罪判決が確定した場合、当該事件における捜査や公訴の提起・追行は違法な公権力の行使にあたるか。
(判旨)
「刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留・公訴の提起・追行、起訴後の拘留が違法となることはない。けだし、逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないからであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである。」
(ポイント)
刑事事件において無罪判決が確定したというだけで、直ちに起訴前の逮捕・勾留・公訴の提起・追行、起訴後の拘留が違法とはならない。
68.パトカー追跡中の事故(最判昭61.12.27)
(事案)
富山警察署外勤課自動車警ら係所属の巡査Aらがパトカー富山11号に乗車して富山市内を機動警ら中、住吉警察官派出所前の交差点付近にさしかかったところ、国道8号線(現41号線)を走行中のB運転の普通乗用車が速度違反車であることを現認したため直ちに追尾し、速度38キロの速度超過を確認した後、赤色灯を点灯しサイレンを吹鳴して追跡を開始した。そのため、一旦は停止したBは、突如Uターンして時速約100キロで逃走し、富山市内の交差点に赤信号にもかかわらず進入したため、C運転の普通乗用車に衝突し、そのはずみでCの車両がX運転の普通乗用車に激突したため、Xやその同乗者が入院約1か月から4か月の重傷を負った。
そのため、Xらは、Aらのパトカーによる追跡の開始・継続ならびにその方法には過失があったとして、富山県(Y)に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて提訴した。
(争点)
警察官が運転するパトカーの追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した交通事故により第三者が損害を被った場合、当該追跡行為が国家賠償法上違法なものとして評価されるのはどのような場合か。
(判旨)
「およそ警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断してなんらかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者を停止させて質問し、また、現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙又は逮捕に当たる職責を負うものであって(警察法2条、65条、警察官職務執行法2条1項)右職責を遂行する目的のために被疑者を追跡することはもとよりなしうるところであるから、警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両を逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、右追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである。
以上の見地に立って本件をみると、原審の確定した前記事実によれば、Bは、速度違反行為を犯したのみならず、警察官の指示により一たん停止しながら、突如として高速度で逃走を企てたものであって、いわゆる挙動不審者として速度違反行為の他のなんらの犯罪に関係があるものと判断しうる状況にあったのであるから、本件パトカーに乗務する警察官は、Bを現行犯人として謙虚ないし逮捕するほか挙動不審者に対する職務質問をする必要もあったということができるところ、右警察官は逃走車両の車両番号は確認したうえ、県内各署に加害車両の車両番号、特徴、逃走方向等の無線手配を行い、追跡途中で『交通機動隊が検問開始』との無線交信を傍受したが、同車両の運転者の氏名等は確認できておらず、無線手配や検問があっても、逃走する車両に対しては究極的には追跡が必要になることを否定することができないから、当時本件パトカーが加害車両を追跡する必要があったものというべきであり、また、本件パトカーが加害車両を追跡していた道路は、その両側に商店や民家が立ち並んでいるうえ、交差する道路も多いものの、その他に格別危険な道路交通状況はなく、東山交差点からK町交差点までは4車線、その後は2車線で歩道を含めた歩道の幅員が約12メートル程度の市道であり、事故発生の時刻が午後11時頃であったというのであるから、逃走車両の運転の前示の態勢等に照らしても、本件パトカーの乗務員において当時追跡による第三者の被害発生の蓋然性のある具体的な危険性を予測しえたものということはできず、更に、本件パトカーの前記追跡方法自体にも特に危険を伴うものはなかったということができるから、右追跡行為が違法であるとすることはできないものというべきである。
警察法
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(現行犯人に関する職権行使)
第六十五条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
警察官職務執行法
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
(ポイント)
パトカーの追跡により第三者が損害を被った場合、当該追跡行為が国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使にあたるのは、当該追跡が現行犯逮捕や職務質問等の目的を遂行する上で不必要であるか、逃走車両の走行の態様や道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性に照らして、当該追跡の開始・継続・その方法が不相当であることを要する。いわゆるカーチェイスの事件である。
69.公務員個人の責任(最判昭30.4.19)
(事案)
農地調整法に基づくき実施された選挙により構成された熊本県球磨郡湯前町農地委員会は、委員半数ずつが同町の小作人組合の両組合系に分かれて対立し、それが激化したことから、熊本県知事(Y)は、熊本県農地委員会の請求により、昭和21年11月15日に同町農地委員会の解散処分を行った。そのため、これを不服とする同町農地委員会委員長Xらが、Yによる当該処分の無効確認とYおよびZ(県農地部長)に対して慰謝料の支払いを求めて出訴した。
(争点)
公権力の行使にあたる公務員の職務行為に基づく損害につき、当該公務員は被害者に対して直接に責任を負うか。
(判旨)
「農地調整法に基づく農地委員会は、農地委員会法(昭和26年3月31日法律第88号)の施行により、同法附則2項の経過的存続期間の終了とともに廃止されることとなり、市町村については昭和26年7月20日の選挙によりの農業委員会が成立すると、同時に農地委員会は消滅したことは、顕著な事実であるから、上告人等は、本件農地委員会についてもはや本訴により解散処分の無効確認の判決を求める利益を有しないのである。
次に上告人等の損害賠償等を請求する訴えについて考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すべきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。従って県知事を相手方とする訴えは不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。」
(ポイント)
公権力の行使にあたる公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責めに任じ、当該職務執行にあたった公務員は、行政機関としての地位においても、また個人としても、被害者に対して責任を負うものではない。
つまり、被害者は、加害公務員個人に対して、直接損害賠償を請求することはできない。
これに対し、民放715条の使用者責任の場合には、被害者は、被用者=加害者に対して、民放709条に基づいて直接損害賠償を請求することができる。
両者の違いに特に注意が必要である。
●加害者の個人責任
国家賠償法1条の場合 → なし
民法の使用者責任の場合 → あり
70.国家賠償請求訴訟と抗告訴訟の関係(最判昭45.8.20)
(事案)
矢掛町農地委員会(Y)の全身たる矢掛町農地委員会が、X所有の宅地につき自作農創設特別措置法15条に基づき買収計画を樹立・公告したため、Xがその無効を求めて出訴したところ、本件買収計画に関する買収申請人であったAらがいずれも当該買収申請を取り下げたため、Y委員会は本件買収計画を取り消し、その旨を公告した。そのため、第一審・第二審とも、本件買収計画がすでに失効している以上、その無効確認を求める訴訟は訴えの利益を欠くと判断したが、X側は、本件買収計画の無効確認を求めるのは、その後の国家賠償を求める目的によるものであるから、なお無効確認を求めるについての法律上の利益は失われていないと主張した。
(争点)
行政処分の無効確認訴訟が提起された後に当該処分が職権により取り消されても、国家賠償請求との関係で、なお無効確認を求めることについての訴えの利益は存するか。
(判旨)
「原判決の確定した事実によれば、被上告人矢掛町農業委員会の前身たる矢掛町農地委員会は昭和23年12月16日自作農創設特別措置法15条に基き本件買収計画を樹立・公告したが、買収令書の交付される前に買収計画の取下げがあったため、昭和27年5月28日本件買収計画を取り消す旨の決議をし、その頃これを公告したというのである。してみると、本件買収計画は、買収申請の取下により、初めに遡りその存在を失うに至ったものと解すべきであるから、上告人は、右計画の無効確認を求めるにつき法律上の利益を欠くに至ったものと解すべきである。
また、行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではないから、本訴が被上告人委員会の不法行為による国家賠償を求める目的に出たものということだけでは、本件買収計画の取消後においても、なおその無効確認を求めるにつき法律上の利益を有するということの理由をするに足りない。
(ポイント)
行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするにあたって、あらかじめ当該行政処分についての取消し、無効確認の判決を得なければならないものではない。
したがって、国家賠償を求める目的により提訴がなされているというだけでは、無効確認を求める法律上の利益は認められない。
71.高地落石事件(最判昭45.8.20)
(事案)
高知市方面と中村市方面を結ぶ一級国道たる国道56号線は、その途中の安和から海岸線に沿って長佐古トンネルに至る2000メートルの区間において、従来山側からしばしば落石があり、さらに崩土さえ何回かあったため、ここに侵入する人および車はたえず落石・崩土の危険におびやかされていた。
これに対して、道路管理者は、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切れを付けて立て、通行車に注意を促す等の処理を講じていた。そうする中、昭和38年6月13日に発生した崩土に伴う落石によりトラックの助手席に乗っていた16歳の青年が即死する事故が起きたことから、その両親(Xら)が、道路管理者たる国(Y)に対して国家賠償法2条1項に基づき、また管理費用の負担者たる高知県(Z)に対して国家賠償法3条1項に基づき、損害賠償を求めて提訴した。
(争点)
{C}① 国家賠償法2条1項における営造物の設置・管理の「瑕疵」の意味をいかに解すべきか、また、当該瑕疵を判断するにあたって、管理者における過失は必要とされるか。
{C}② 道路管理を充分に行うためには予算的に困難な状況が認められる場合は、国家賠償法2条1項および3条1項に基づく責任は免れられるか。
(判旨)
「国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(原判決の説示する安和より海岸線に沿い長佐古トンネルに至る2000メートルの区間)を含む国道56号線は、一級国道として高知市方面と中村市方面とを結ぶ陸上交通の上で極めて重要な道路であるところ、本件道路には従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかもしれず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれの
あるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったというべきである旨、本件道路における落石、崩土の発生する原因は道路の山側の地層に原因があったので、本件における道路管理の瑕疵の有無は、本件事故発生地点だけに局限せず、前記2000メートルの本件道路全般についての危険状況および管理状況等を考慮にいれて決するのが相当である旨、そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。してみれば、その余の点について判断するまでもなく、本件事故は道路管理に瑕疵があったため生じたものであり、上告人国は国家賠償法2条1項により、上告人県は管理費用負担者として同法3条1項により損害賠償の責に任ずべきことは明らかである。」
(ポイント)
{C}① 国家賠償法2条1項の営造物の設置・管理の「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国・公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない。
つまり、無過失責任である。
{C}② 道路管理を充分に行うために費用額が多額にのぼり、その予算措置に困難な状況が伴っても、それにより直ちに道路管理の瑕疵によって生じた損害の賠償責任を免れない。
つまり、予算不足という財政的な理由は、免責事由とならない。
72.大阪国際空港公害訴訟(最判昭56.12.16)
(事案)
昭和34年7月に空港警備法2条1項1号の第一種空港として指定された大阪国際空港は、国際航空路線および主要な国内航空路線の用に供されるわが国の代表的な国営空港の1つとして活用されてきたが、ジェット機の就航やB滑走路の増設などに伴い、それがもたらす騒音公害も深刻なおのとなってきた。そのため、昭和44年に至り、周辺住民300名余名(Xら)は、国(Y)を被告として、午後9時から翌朝7時までの本件空港の使用差止めと、過去および将来に係る損害賠償の支払いを求める民事訴訟を提起した。
(争点)
{C}① 民事上の請求として、一定の時間帯に航空機の離発着のためにされる国営空港の併用の差止めを求めることはできるか。
{C}② 営造物の物的欠陥以外の原因を理由として国家賠償法2条1項が規定する営造物の設置・管理の瑕疵を認定することは許されるか。
{C}③ 将来にわたって継続する不法行為を理由とする損害賠償請求は認められるか。
(判旨)
「〈差止請求に関す判断〉営造物管理権の本体をなすものは、公権力の行使をその本質的内容としない非権力的な権能であって、同種の私的施設の所有権に基づく管理権能とその本質において特に異なるところはない。国の営造物である本件空港の管理に関する事項のうちに、その目的の公共性に由来する多少の修正をみることがあるのは別として、私営の飛行場の場合における
と同じく、私法的規制に親しむものがあることは、否定しえないところである。しかしながら、本件空港の管理といっても、その作用の内容には種々のものがあり、その法律的性質が一律一様であると速断することはできない。のみならず、空港については、その運営に深いかかわりあいを持つ事象として、航空行政権、すなわち航空法その他航空行政に関する法令の規定に基づき運輸大臣に付与された航空行政上の権限で公権力の行使を本質的内容とするものの行使ないし作用の問題があり、これと空港ないし飛行場の管理権の行使ないし作用とが法律上そのような位置、関係に立つのかが更に検討されなければならない。そもそも法が一定の公共用飛行場についてこれを国営空港として運輸大臣みずから設置、管理すべきものとしたゆえんのものは、これによってその航空行政権の行使としての政策的決定を確実に実現し、国の航空行政を効果的に遂行することを可能とするにある、というべきである。すなわち、法は、航空機及びその運航、航空従事者、航空路、飛行場及び航空保安施設、航空運送事業並びに外国航空機等に関する広範な行政上の規制制限を運輸大臣付与し、運輸大臣をして、これらの権限の行使により、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運行して営む事業の秩序を確立し、社会、経済の発展、国際交流の活発化等により増大する航空運輸に対する需要と供給を調整し、他の諸政策分野と整合性のある航空行政制作を樹立して実施させることとしており、こてに関する公共施設として航空法の定める公共用飛行場を設けている。そして、そのうち、国際航空路線又は主要な国内航空路線に必要なものなど基幹となる公共用飛行場については、運輸大臣みずからが、又は法律により設立された運輸大臣の特別な指示ないし監督に服する特殊法人である新東京国際空港公団が、これを国営又は同公団営の空港として設置、管理し、公共の利益のためにその運営に当たるべきものとしている。それは、これら基幹となる公共用飛行場にあっては、その設置、管理のあり方がわが国の政治、外交、経済、文化等と深いかかわりを持ち、国民生活に及ぼす影響も大きく、したがって、どの地域にそおのような規模でこれを設置し、どのように管理するかについては航空行政の全般にわたる政策的判断を不可欠とするからにほかならないものと考えられる。右にみられるような空港国営化の趣旨、すなわち国営空港の特質を参酌して考えると、本件空港の管理に関する事項のう、少なくとも航空機の離着陸の規制そのもの等、本件空港の本来の機能の達成実現に直接にかかわる事項自体については、空港管理権に基づく管理と航空行政権に基づく規制とが、空港管理権者としての運輸大臣と航空行政権の主管者としての運輸大臣のそれぞれ別個の判断に基づいて分離独立的に行われ、両者の間に矛盾乖離を生じ、本件空港を国営空港とした本旨を没却し又はこれに支障を与える結果を生ずることがないよう、いわば両者が不即不離、不可分一体的に行使実現されているものと解するのが相当である。換言すれば、本件空港における航空機の離着陸び規制等は、これを法律的にみると、単に本件空港についての営造物管理権の行使という立場のみにおいてされるべきもの、そして現にされているものとみるべきではなく、航空行政権の行使という立場をお加えた、複合的観点に立った総合って気判断に基づいてされるべきもの、そして現にされているものとみるべきものである。前述のように、本件空港の離着陸のためにする供用は運輸大臣の有する空港管理権と航空行政権という二種の権限の、総合的判断に基づいた不可分一体的な行使の結果であるとみるべきであるから、右被上告人らの前記のような請求は、事理の当然として、不可避的に航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することとなるものといわなければならない。したがって、右被上告人らが行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして、上告人に対し、いわゆる通常の民事上の請求として前記のような私法上の給付請求権を有するとの主張の成立すべきいわれはないというほかはない。」
「(過去の損害の賠償請求に関する判断)国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如mすなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害をしょうぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によって危害を生ぜしめる危険性がある状態にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右製造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、したがって、右営造物の設置・管理者において、かかる危険があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生じせしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法2条1項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」
「〈将来の損害の賠償請求に関する判断〉民訴法226条はあらかじめ請求する必要があることを条件として将来の給付の訴えを許容しているが、同条は、およぞ将来に生ずる可能ではなく、主として、いわゆる期限制限付請求権や条件付請求権のように、既に権利発生の基礎をなす事実上及び法律上の関係が存在し、ただ、これに基づく具体的な給付義務の成立が将来におけるい一定の時期の到来や債権者において立証を必要としないか又は容易に立証しうる別の一定の事実の発生にかかっているにすぎず、将来具体的な給付義務が成立したときに改めて訴訟により右請求権成立のすべての要件の存在を立証することを必要としないを考えられるようなものについて、例外として将来の給付の訴えによる請求を可能ならしめたにすぎないものと解される。たとえ同一態様の行為が将来も継続されることが予測される場合であっても、それが現在と同様に不法行為を構成するか否か及び賠償すべき損害の範囲いかん等が流動性をもつ今後の複雑な事実関係の展開とそれらに対する法的評価に左右されるなど、損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず、具体的に請求権が成立したとされる時点においてははじめてこれを認定することができるとともに、その場合における権利の成立要件の具備については当然に債権者においてこれを立証すべく、事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考えられるようなものについては、前記の不動産の継続的不法占有の場合とはとうてい同一に論ずることはできず、かかる将来の損害賠償請求権については、冒頭に説示したとおり、本来例外的にのみ認められる将来の給付の訴えにおける請求書としての適格を有するものとすることはできないと解するのが相当である。」
民訴法226条
(文書送付の嘱託)
第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
(ポイント)
{C}① 行政訴訟の方法により請求をすることはともかく、通常の民事上の請求として、一定の時間帯についての国営空港の供用の差止めを求めることは認められない。
{C}② 営造物が通常有するべき安全性を欠いている状態には、営造物が供用目的によって利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合も含む。つまり、飛行機の離発着による騒音公害も含むということ。また、その危害は、当該営造物の利用者以外の第三者に対するそれを含む。つまり、周辺住民への被害を含むということ。
{C}③ 不法行為が将来も継続することが予想されても、損害賠償請求権の成否・額をあらかじめ一義的明確に認定されないなどの場合には、将来の給付の訴えとして損害賠償を求めることは認められない。
73.営造物の通常の用法に即しない行動(最判昭53.7.4)
(事案)神戸市内にある夢野合高等学校の校庭横を通る市道は、昭和35年頃には校庭から路面までの高さが約2メートルにすぎなかったが、その後の土砂の流入や道路舗装工事などの結果、次第に高くなって、約4メートルにも達するようになり、子どもの転落事故も数件発生したことから、神戸市(Y)は、昭和40年に防護柵を設置した。この防護柵は、2メートル間隔に立てられた高さ80センチのコンクリート柱に上下2本ン鉄パイプを通して手摺としており、路面から冗談手摺までの高さは65センチ、下段手摺までの高さは40センチであった(なお、当該鉄パイプは、この種の策に通常用いられる丸棒状のものでありが、幼児が遊び道具とするのに好適なものではない。)そして、本件道路付近は住宅地で、昼間車両の通行量が少なく、付近に適当な遊び場所がなかったことから、本件道路が子どもらの遊び場所となっていたところ、昭和44年8月4日の午後8時頃、防護柵の上段手摺に後ろ向きに腰掛けて遊んでいた当時6歳のXが、誤って約4メートル下の校庭に転落し、頭蓋骨陥没骨折の重傷を負った。
そのため、Xは、本件道路の設置・管理には瑕疵があったとして、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償をYに求めて出訴した。
(争点)
営造物の通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、当該営造物の設置・管理者は、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任を負うか。
(判旨)
「国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理に瑕疵があったとみられるかどうかは、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものであるところ、前記事実関係に照らすと、本件防護柵は、本件道路を通行する人や車が誤って転落するのを防止するために被上告人によって設置されたものであり、その材質、高さその他その構造に徴し、通行時における転落防止の目的からみればその安全性に欠けるところがないものというべく、上告人の転落事故は、同人が当時危険性の判断能力に乏しい6歳の幼児であったとしても、本件道路及び防護柵の設置管理者である被上告人において通常予測することができない行動に起因するものであったということができる。したがって、右営造物につき本来それが具有するべき安全性に欠けるところがあったとはいえず、上告人がしたような通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、被上告人はその設置管理者としての責任を負うべき理由はないものというべきである。」
(ポイント)
営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合に、当該行動が設置管理者において通常予測できないものであったときは、その事故は営造物の設置・管理の瑕疵によるものではない。
74.赤色灯事件(最判昭50.6.26)
(事案)
奈良県桜井市を通る県道天理・桜井線の初瀬橋北詰付近では、昭和41年9月6日当時、道路の中心線から西側、すなわち北進道路で掘削工事が行われており、その工事個所を表示するため、工事現場の南北各約2メートルの地点に、工事標識版と高さ約80センチ・幅約2メートルの黒黄まだらのバリケードが1つずつ設置され、当時バリケード間の道路中心線付近には高さ1メートルの赤色灯標柱が1つずつ設置されていた。しかし、同日の午後10時30分頃同所を北進した車により、前記工事現場の南側に設置されていた工事標識版・バリケード・赤色灯標柱がなぎ倒され、赤色灯点滅も消えた結果、その直後に同所を通過したA運転の乗用車がこれに気付いてあわててハンドルを切ったが、道路から3メートル下の田圃に同車は転落し、助手席に同乗していたBが死亡した。
このため、Bの遺族(X)が、奈良県(Y)に対し、本件県道には道路として通常有すべき安全性の欠如があったとして、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めて出訴した。
(争点)
他車により工事個所を示す工事標識版や赤色灯標柱などが倒され、赤色灯が消えた場合にも、その直後に同所を通過して事故に遭遇した者との関係では、道路管理者に管理の瑕疵があったこととなるか。
(判旨)
「本件事故発生当時、被上告人において設置した工事標識版、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性に欠陥があったといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によって惹起されたものであり、時間的に被上告人において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったというべく、このような状況のもとにおいては、被上告人の道路管理に瑕疵がなかったと認めるのが相当である。」
(ポイント)
夜間、工事個所を示す工事標識版や赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えていた場合でも、それが事故直前に通行した他の車両により惹起された時間的に道路管理者が遅滞なくこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であったときには、当該道路管理に瑕疵はない。
このように、国家賠償法2条の責任は、1条と異なり、無過失責任ではあるが、不可抗力による場合には免責されることに注意が必要である。
国家賠償法1条・2条
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
行政書士重要判例
Ⅲ 行政法
1. {C}浦安鉄抗撤去事件(最判平3.3.8)
(事案)
Aクラブは、二級河川である境川において、ヨットの保留施設とする目的で、鉄道レール約100本を全長850メートルにわたって、河川法の許可を受けないまま打ち込んだ。そのため、船舶の航行が困難となり、時に夜間や干潮時に航行する船舶にとっては非常に危険な状況が生じた。そこで、浦安町(当時)はAクラブ側に至急撤去を要請したが、撤去実施の様子が全く認められないため、町長(Y)がB建設との間で請負契約(代金130万円)を締結し、職員1名(時間外勤務手当4万8274円)とともに撤去にあたらせた。
以上の行為に対し、浦安町の住民(X)は、本件鉄杭の撤去は、何ら法律上の根拠に基づかない違法な行為であるから、その撤去に要した費用は違法な公益の支出にあたり、Yは合計額134万8274円についての損害を浦安町に与えたとして、地方自治法242条の2第1項に基づき、同額分を浦安市(昭和56年に市制施行)に変換するよう求めて住民訴訟を提起した。
(争点)
本件鉄抗撤去は違法な行為といえるか。請負代金の支出・時間外勤務手当の支給は違法か。
(判旨)
「本件判決は、右の設置場所、その規模等に照らし、浦安漁港の区域内の境川水域の利用に著しく阻害するものと認められ、同法39条1項の規定による設置許可の到底あり得ない。したがってその存置の許されないことの明白なものであるから、同法6項の規定の適用をまつまでもなく、漁港管理者の右管理権限に基づき漁港管理規定によって撤去することができるものと解すべきである。しかし、当時、浦安町においては漁港管理規定が制定されていなかったのであるから、上告人が浦安漁港の管理者たる司町の町長として本件撤去を強行したことは、漁港法の規定に違反しており、これにつき行政代執行法に基づく代執行としての適法性を肯定する余地はない。
浦安町は、浦安漁港の区域内の水域における障害を除去してその利用を確保し、さらに地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持する(地方自治法2条3項1号参照)という任務を負っているところ、同町の町長として右事務を処理すべき責任を有する上告人は、右のような状況下において、船舶航行の安全を図り、住民の危難を防止するため、その存置の許されないことが明白であって、撤去の強行によってもその財産的価値がほとんど損われないものと解される本件鉄杭をその責任において強行的に撤去したものであり、本件鉄杭撤去が強行されなかったとすれば、千葉県知事による除去が同月9日以降になされたとしても、それまでの間に本件鉄杭による航行船舶の事故及びそれによる住民の危難が生じた場合の不都合、損失を考慮すれば、むしろ上告人の本件鉄杭撤去の強硬はやむを得ない適切な措置であったと評価すべきである(原審が民法720条の規定が適用されない理由として指摘する諸般の事情は、航行船舶の安全及び住民の急迫の危難の防止のため本件鉄杭撤去がやむを得なかったものであることの認定を妨げるものとはいえない。)。
そうすると、上告人が浦安町の町長として本件鉄杭撤去を強行したことは、漁港法及び行政代執行法上適法と認めることのできないものであるが、右の緊急の事態に対処するためにとらえたやむを得ない措置であり、民法720条の法意に照らしても、浦安町としては、上告人が右撤去に直接要した費用を同町の経費として支出したことを容認すべきものであって、本件請負契約に基づく公金支出ついては、その違法性を肯認することはできず、上告人が浦安市に対し損害賠償責任を負うものとすることはできず、上告人が浦安町に対し、損害賠償責任を負うものとすることはできないといわなければならない。」
民法720条
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
(ポイント)
本件鉄杭撤去は、漁港法および行政代執行法上、適法性を肯定できないが、緊急の事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であり、民法720条(緊急避難)の法意に照らしても、当該費用を支出したことの違法性までは肯定できない。
どのような行政活動に法律の根拠を必要とするか(「法律の留保」の原則の適用範囲)が争われているが、判例は、本件のような根拠法がない行政活動について、ケースバイケースの対応をした。なお、学説上は、国民の権利自由を侵害したり、新たな義務を課すような侵害行政を行うには法律の根拠を必要とする、侵害留保説が通説である。
2. 自作農創設特別措置法と民法177条(最大判昭28.2.18)
Xは、戦前に本件農地をAより買い受け、代金を支払い、土地引渡しを済ませていたが、所有権移転登記については諸般の事情から行わないでいた。その上で、戦後の農地改革の際に、地区農地委員会は、本件農地の章勇者は登記簿上の名義人であるAであり、Aは不在地主であるといて、自作農特別措置法3条1項1号に基づき、本件農地の買収計画を定めた。そこで、Xは、異議申立てを経て、県農地委員会(Y)に訴願したが、認容されなかったため、Yのなした裁決の取消しを求めて出訴した。
(争点)
本件農地の所有権取得につき登記手続を完了していないXは、民法177条に基づき、第三者である地区農地委員会に対抗できないとするYの判断は適法か。
(判旨)
「自作農創設特別措置法(以下自作法と略称する)は、今次大戦の終結に伴い、我国農地制度の急速な民主化を図り、耕作者の地位の安定、農業生産力の発展を期して制定されたものであって、政府は、この目的達成のため、同法に基づいて、公権力を以て同法所定の要件に従い、所謂不在地主や大地主等の所有地を買収し、これを耕作者に売渡す権限を与えられているのである。即ち政府の同法に基く農地買収処分は、国家が権力的手段を以て農地の強制買上を行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とは、その本質を異にするものである。従って、かかる私経済上の取引の安全を保障するために設けられた民法177条の規定は、自作法による農地買収処分には、その適用を見ないものと解すべきである。されば、世府が同法に従って、農地の買収を行うには、単に登記簿の記載に依拠して、登記簿上の農地の所有者を相手方として買収処分を行うべきものではなく、真実の農地の所有者から、これを買収すべきものであると解する。」
民法177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(ポイント)
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家が権力的手段をもって農地の強制買上げを行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とはその本質を異にするので、民法177条を適用すべきでなく、政府は真実の農地所有者から農地を買収すべきである。
つまり、農地買収には民法177条は適用されない。
●民法177条の適用の可否
農地買収処分 ・・・✕
滞納処分の差押え・・・〇(「国税滞納処分と民法177条」参照)
3. 国税滞納処分と民法177条(最判昭31.4.24)
(事案)
Xは、A会社より本件土地を買い受け、代金も支払ったが、A会社の場合により所有権移転登記手続は未了であった(ただし、Xは、魚津税務署長に対し、本件土地を自己の所有とする財産税の申告をし、これを納入している。)。その後、魚津税務署長から事務の引継ぎを受けた所轄の富山税務署長(Y)は、A会社の租税の滞納を理由に本件土地を押さえ、その登記も経由した上で、翌年、Zを本件土地の買受人とする公売処分を執行して、Zへの移転登記手続も完了した。そこで、Xは、①Yに対する公売処分の無効確認と、②Zに対する本件土地の所有権移転登記手続を求めて出訴した。
(争点)
国税滞納処分による差押えに民法177条の適用はあるか。
(判旨)
「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押さえた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱いを受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても民法177条の運用があるものと解するのが相当である。
(ポイント)
国税滞納処分による差押えには民法177条が適用される。
民法177条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
4. 公営住宅の使用関係と信頼関係の法理(最判昭59.12.13)
(事案)
Yは、東京都(X)の所有にかかる本件公営住宅に入居していたが、Xの許可をうけずに同住宅の敷地上に建物を増築し、また、2年2か月にわたり割増賃料の支払いを滞納したため、公営住宅法22条1項(現行32条1項)に基づき、Yに対する使用許可を取り消すとともに、その明け渡しを求めて出訴した。
これに対し、Yは、本件無断増築が公営住宅法の定める引渡事由に該当するとしても、本件においては、XとYとの間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるとして、Xの明渡請求には効力がな旨の抗弁を行った。
公営住宅法32条1項
(公営住宅の明渡し)
第三十二条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。
一 入居者が不正の行為によつて入居したとき。
二 入居者が家賃を三月以上滞納したとき。
三 入居者が公営住宅又は共同施設を故意に毀き損したとき。
四 入居者が第二十七条第一項から第五項までの規定に違反したとき。
五 入居者が第四十八条の規定に基づく条例に違反したとき。
六 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(争点)
公営住宅の住居者が公営住宅法22条1項所定の明渡請求事由に該当する行為をした場合にも、信頼関係の法理は適用されるか。
公営住宅法22条1項
(入居者の募集方法)
第二十二条 事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。
(判旨)
「入居者が右使用許可を受けて事業主体とし入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあっても、事業主体と入居者の間の法律関係は、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異ることなく、このことは、法が賃貸(1条、2条)、家賃(1条、2条、12条、13条、14条)等私法上の賃貸借関係に通常用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかであるといわなければならない。したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法にして民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を決定するについては入居者を選択する事由を有しないものと解されるが、事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には信頼関係の基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情がある時には、事業主の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。
右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができ、右事実関係によれば、上告人の増築した本件建物は、構造上、現状回復が容易であり、かつ、本件住宅の保存にも適しているとはいいえず、また、被上告人が本件建物の増築を事後に許容したものとも認め難いところであるから、上告人の家庭に前記上告人の主張するような事情があるからといって、被上告人との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるということはできない。そうすると、被上告人の本訴明渡請求は、その余の点につて判断するまでもなく、理由があるものというべきである。」
(ポイント)
公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例に特別の定めがない限り、一般法である民法および借家法(現行「借地借家法」)の適用があり、その契約関係に規律するにつて、信頼関係の法理の適用がある。もっとも、本件におけるYの無断増築には、Xとの間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるということはできないので、Yは本件住宅を明け渡さなければならない。
5. 公営住宅の入居者の死亡と相続(最判平2.10.18)
(事案)
Yの祖父Aは、本件建物を東京都(X)から賃借していたが、その後死亡したため、Yが訴外Bらとともに、Aの地位を代襲相続した。一方、Xは、本件建物を含む都営住宅の老朽化が著しいことから、住人達に対し他の都営アパートへの移転斡旋を開始したが、本件建物につては、斡旋請求当時居住していたのは訴外Bらであったとして、Yに対し、所有権に基づく明渡しと不法占拠を理由とする不法行為に基づく損害賠償を請求した。
これに対し、Yは、都条例には使用権の譲渡・転貸を禁止した規定はあるが、入居者死亡の場合における使用権の継承の有無を定めた規定はなく、したがって、これについては一般法である民法の相続に関する規定が適用されるべきだと主張した。
(争点)
入居者死亡の場合における公営住宅の承継問題につき、民法の相続の規定は適用されるか。
(判旨)
「公営住宅法は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の推進に寄与することを目的とするmんであって(1条)、そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備するものに限定し(17条)、政令の定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、入居者を決定しなければならないものとした上(18条)、さらに入居者の収入が政令で定める基準を超えることになった場合には、その入居年数に応じて、入居者については、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない旨(21条の2第1項)、事業主体の長にちゅいては、当該公営住宅の明渡しを請求することができる旨(21条の3第1項)を規定しているのである。
以上のような公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を使用する権利を当然に承継すると解する余地はないというべきである。」
(ポイント)
公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はない。
6. 建築基準法65条と民法234条1項の関係
(事案)
Yは、自己の所有する土地上に、隣接する土地の所有者Xの了解を得ることなく、境界線に近接して鉄骨造3階建ての建物の建築を始めた。そこで、Xは、本件建築が、境界線から50センチメートル以上の距離を置くべきことを規定する民法234条1項に違反するとして、Yに対して、境界線から50センチメートル以内に建物部分の収去を求めて出訴した。
これに対し、Yは、本件建物の敷地は準防火地域内にあり、しかも本件建物の外壁は耐火構造のものであるから、建築基準法65条により、隣地境界線に接して建築することができると抗弁した。
民法234条1項
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
(争点)
建築基準法65条所定の建築物の建築に民法234条1項は適用されるか。
(判旨)
「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除推される旨を定めたものと解するのが相当である。けだし、建築基準法65条は、耐火構造の外壁を設けることが防火上望ましいという見地や、防火地域又は準防火地域における土地の合理的ないし効率的な利用を図るという見地に基づき、相隣関係を規律する趣旨で、右各地域内にある建物で外壁が耐火構造のものにつては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができることを規定したものと解すべきであって、このことは、次の点からしても明らかである。すなわち、第一に、同条の文言上、それ自体として、同法6条1項に基づく建築申請の審査に際しよるべき基準を定めたものと理解することはできないこと、第二に、建築基準法及びその他の法令において、右確認申請の審査基準として、防火地域又は準防火地域における建築物の外壁と隣地境界線との間の距離につき、直接規制している原則的な規定はない(建築基準法において、隣地境界線と建築物の外壁との間の距離につき、直接規制しているものとしては、第一種住居専用地域内における外壁の後退距離の限度を定めている54条の規定があるにとどまる。)から、建築基準法65条を、何らかの建築確認申請の審査基準を緩和する趣旨の例外規定と理解することはできないことからすると、同条は、建物を建築するには、境界線から50センチメートル以上の距離を置くべきものとしている民法234条1項の特則を定めたものと解して初めて、その規定の意味を見出しうるからである。
本件についてこれをみると、上告人所有地は準防火地域に指定され、上告人建物の外壁は耐火構造であるというのであるから、建築基準法65条により、上告人建物は、本件土地部分においても許容されるというべきである。
(ポイント)
建築基準法65条は、民法234条1項の特則を定めたものであり、同条所定の建築物の建築に限っては、民法234条1項の規定の適用が排除される。
つまり、建築基準法65条の方が優先するということ。
建築基準法65条>民法234条1項
7. 位置指定道路の通行妨害(最判平9.12.18)
(事案)
Yは、川崎市長から道路位置指定を受けた本件土地につき、その所有者から贈与を受けた者であるが、その後、本件土地近辺に居住する住民に対し、通行契約を締結しない車両等の通行を禁止する旨のビラをまいた上で、本件土地に簡易ゲートを設置し、さらに通行を不可能にする工事を施行する旨を自治会に通知した。
これに対し、居住者から自動車で公道に出るには、本件土地を通行することが不可欠な状態にある付近住民のXらが、Yに対し、本件土地について通行妨害行為の排除および将来の通行妨害行為の禁止を求めて提訴した。
(争点)
道路位置指定を受け開設されている道路を通行する講習の利益は、法律上の利益といえるか。当該道路の通行を敷地所有者に妨害されたよきには、公衆はその排除を求める権利を有するか。
(判旨)
「建築基準法42条1項5号の規定による位置の指定(以下、『道路位置指定』という。)を受け現実に開設されてる道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者から右通行を受任することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情がない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格的権利)を有するものというべきである。
けだし、道路位置指定を受け現実に開設されている道路を公衆が通行することができるのは、本来は道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害された者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則であるが、生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活に属するものであって、これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通についての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関する利益は私法上も保護に値するというべきであり、他方、道路位置指定に伴い建築基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、少なくとも道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、右の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私法上の通行受任義務をおうこととなってもやむを得ないものと考えられるからである。
(ポイント)
道路位置指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて、日常生活上不可欠の利益を有する者は、当該道路の通行を敷地所有者によって妨害され、妨害されるおそれがあるには、妨害行為の排除・将来の妨害行為の禁止を求める人格権的権利を有する。
8. 自衛隊内の事故と安全配慮義務(最判昭50.2.25)
(事案)
陸上自衛隊員のAは、八戸駐屯地内の武器車両整備工場内に勤務していた昭和40年7月に、他の隊員が運転する大型自動車に轢かれて死亡した。
遺族である原告(Xら)には、同月中に計807万4,000円の遺族補償金が国家公務員災害補償法に基づき支給されたが、その際に他の請求手段についてはヾ何の説明もなかったため、Xらは、一般の交通事故死と比較してあまりに低額であることに不満を抱きつつも、恩恵による遺族補償金の増割を期待する他ないと考えていた。
しかし、その後、他の請求手段があることを知り、昭和44年10月になって、国(Y)を被告とする自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償請求訴訟を提起したが、原審(東京高判昭48.1.31)は、民放724条前段が定める消滅時効(損害および加害者を知った時から3年)が成立しているとするとともに、Xらが主張した国の安全配慮義務違反に基づく債務不履行責任については、公務員と国との関係においては特別権力関係が成立することを理由に否定したため、Xらが上告した。
(争点)
① 国は国家公務員に対して安全配慮義務を負うか。
② 安全配慮義務を負うとした場合には、その債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、何年と解すべきか。
(判旨)
「思うに、国と国家公務員(以下、「公務員」という。)との間における主要な義務として、法は、公務員が職務に専念すべき義務(国家公務員法101条)1項前段、自衛隊法60条1項等」並びに法令及び上司の命令に従うべき義務(国家公務員法98条1項、自衛隊法56条、57条等)を負い、国がこれに対応して公務員に対し給与支払義務(国家公務員法52条、防衛庁職員給与法4条以下等)を負うことを定めているが、国の義務は右の給付義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきである。もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものであり、自衛隊員の場合にあっては、更に当該勤務が通常の作業時、訓練時、防衛出動時(自衛隊法76条)、治安出動時(同法78条以下)又は災害派遣時(同法83条)のいずれにおけるものであるか等によっても異なるべきものであるが、国が、不法行為規範のもとにおいて私人に対し、その生命、健康等を保護すべき義務を負っているほかは、いかなる場合においても公務員に対し安全配慮義務を負うものではないと解することはできない。けだし、右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として、一般的に認められるべきものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、公務員が前期の義務を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対し安全配慮義務を負いmこれを尽くすことが必要不可欠であり、また、国家公務員法93条ないし95条及びこれに基づく国家公務員法災害補償法並びに防衛庁職員給与法27条等の災害補償制度も国が公務員に対し安全配慮義務を負うことを当然の前提として、この義務が尽くされたとしてもなお発生すべき公務災害に対処するために設けられたものと解されるからである。
そして、会計法30条が金銭の給付を目的とする国の権利及び国に対する権利につき5年の消滅時効期間を定めたのは、国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜に考慮したことに基づくものであるから、同条の5年の消滅時効の定めは、右のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であって他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである。そして、国が、公務員に対する安全配慮義務を懈怠し違法に公務員の生命、健康等を侵害して損害を受けた公務員に対し損害賠償の義務を負う事態は、その発生が偶発的であって多発するものとはいえないから、右義務につき前記のような行政上の便宜を考慮する必要はなく、また、国が義務者であっても、被害者に損害を賠償すべき関係は、公平の理念に基づき被害者に生じた損害の公平な填補を目的とする点において、私人相互間における損害賠償の関係とその目的性質を異にするものではないから、国に対する右損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法30条所定の5年と解すべきではなく、民放167条1項により10年と解すべきである。
会計法30条
第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
民放167条1項
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
(ポイント)
① 国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所・施設・器具等の設置管理または公務員が国や上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命・健康等を危険から保護するように配慮すべき義務を負う。つまり、安全配慮義務を負う。
② 国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任については、主として行政上の便宜を考慮して5年の短期消滅時効を定める会計法30条は適用されるべきでなく、債権の一般的消滅時効を定める民放167条1項に基づき、10年の消滅時効が適用される。
9. 温泉審議会による諮問手続(最判昭46.1.22)
(事案)
島根県知事(Y)は、温泉業者Aによる温泉湧く出量を増加させるための動力装置の設置許可申請に対し、温泉法20条に基づく温泉審議会への諮問手続につき、持ち回りの方法による決議を経たのみで許可処分を行った。(なお、その後開かれた審議会において、当該許可処分を相当とする意見が事後的には表明されている。)
これに対し、他の温泉業者であるXは、この動力装置により、その所有する温泉の湧出量が激減する等の被害を被ったとして、当該処分の有効性をめぐり提訴した。
(争点)
① 持ち回りの方法による審議会の決議は有効か。
② 事後的になされた審議会による意見表明により、瑕疵は治癒されるか。
③ 法廷の諮問手続を経なかった瑕疵は、取消原因にとどまるか、それとも無効原因となるか。
(判旨)
「原判決の確定したところによれば、本件許可処分によれば、本件許可処分にあたり、温泉審議会は開かれず、知事による温泉審議会の意見聴取は持回り決議の方法によりされたものであるというのであり、また、温泉法19条、島根県温泉審議会条例(昭和25年同県条例第31号)6条等の規定に徴すれば、右審議会の意見は、適法有効なものということはできず、右処分後に開かれた審議会の意見によっても、右の瑕疵が補正されていないことは、原判決の判示判断の通りである。
ところで、温泉法20条によれば、知事が同法8条1項等所定の規定による処分をしようとするときは、温泉審議会の意見を聞かなけらばならないこととされていることは、所論のとおりであるが、同法19条は、都道府県知事の諮問に応じ温泉およびこれに関する行政に関し調査、審議させるため、都道府県に温泉審議会を置く、右審議会の組織、所掌事務、委員その他の職員については都道府県の条例で定める旨規定しており、その他、同法の目的を定める1条、許可不許可の基準を定める4条等の規定に徴すれば、前記20条が知事に対し、温泉審議会の意見を聞かなければならないこととしたのは、知事の処分の内容を適正ならしめるためであり、利害関係人の利益の保護を直接の目的としたものではなく、また、知事は右の意見に拘束されているものではないと解される。そして、これらの諸点を併せ考えれば、本件許可処分にあたり、知事のした温泉審議会の意見聴取は前記のようなものではあるが、取消の原因としてはともかく、本件許可処分を無効ならしめるもおということはできない。
(ポイント)
① 持ち回りの方法による審議会の決議は有効ではない。
② 処分がなされた後に開かれた審議会の意見表明によって、従前の瑕疵は治癒されない。
③ 温泉法20条に基づく知事による諮問手続は、利害関係人の利益保護を目的としたものではなく、知事の処分の内容を適正ならしめるためのものにすぎないため、取消原因としてはともかく、本件許可処分を当然に無効とするものではない。
10. 公共用財産の時効取得(最判昭51.12.24)
(事案)
Xは、自作農創設特別措置法により、国(Y)から本件田の売り渡しを受け、平穏・公然に耕作を継続していたが、その土地の一部は、公図上は水路として表示されている国有地であった。そこで、Xは、売渡日より10年経過した時点で、当該部分の所有権を時効取得したとして、所有権確認の訴えを提起した。
(争点)
明示の公用廃止がなされなくとも、公共用財産を時効取得することは可能か。再度
水路に復することが容易であっても、取得時効の成立を認めてよいか。
(判旨)
「公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての携帯、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されてものとして、これについて取得時効の成立を妨げないと解するのが相当である。
これを本件についてみるに、原審の確定するところによれば、1)本件係争地は、公図上水路として表示されている国有地であったが、古くから水田、あるいは畦畔に作りかえられ、本件田あるいはその畦畔の一部となり、水路としての外観を全く喪失し、本件係争地及び本件田は、被上告人の祖父が訴外Aから借り受けて小作していた当時から、幅60糎ないし75糎程度の細い畦畔によって合計45枚の水田に区分けされていた、2)被上告人は、昭和22年7月2日自作農創設特別措置法により上告人から本件田の売渡を受けたが、その当時の本件田と本件係争地の位置関係及び使用状況は、被上告人の祖父が耕作していた状態と全く同様であったため、被上告人は、本件田及び本件係争地を含んだ水田と畦畔全体を売り渡されたものと信じ、水田あるいは畦畔として平穏かつ公然に本件係争地の占有を続けたというのであり(この事実の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。)、右事実によれば、本件係争地は、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、被上告人の祖父の時代から引き続き、私人に占有されてきたが、そのために実際上公の目的が害されることもなく、もはやこれを公共用財産として維持すべき理由がなくなったことは明らかであるから、本件係争地は、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の対象となりうるものと解すべきである。これと同旨の見解に立って本件係争地に対する被上告人の取得時効の成立を肯定した原審の判決は、正当としてぜにんすることができる。
(ポイント)
公共用財産が、長年の事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態・機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続した場合には、当該公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を認めることができる。
つまり、黙示的に公用が廃止されば、取得時効が成立する。
11.予定公物の時効取得(最判昭44.5.22)
(事案)
Xの先代Aは、自作農創設特別措置法により国から本件土地の売渡しを受け、耕作を続けていたが、その後、旧都市計画法3条に基づき、建設大臣が都市計画上の公園として当該土地を京都市(Y)の市有地として決定した。
そこで、Aの相続人であるXが、当該決定後も耕作を継続したAには取得時効の成立が認められるとして、本件土地の所有権確認を求めて提訴した。
(争点)
建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地につき、取得時効の成立は認められるか。
(判旨)
「自作農創設特別措置法の規定に基づき、政府から売渡を受けて現に被上告人らの先代が耕作していた本件土地に対し、建設大臣が都市計画法上公園に決定したとしても、上告人行都市は右土地につき直ちに現実に外見上児童公園の形態を具備させたわけではなく(公用解し行為がないことは上告人も自認している)、したがって、それは現に公共用財産としてその使命をはたしているものではなく、依然としてこれにつき被上告人らの先代の耕作占有状態が継続されてきたというのであるから、かかる事実関係のもとにおいては、被上告人らの先代の本件土地に対する取得時効の進行が妨げられるものとは認められない。」
(ポイント)
予定公物であっても、取得時効が成立する。
12.村道の自由使用(最判昭39.1.16)
(事案)
Xらが生活および農業経営のため村道を利用していたところ、Yがその道路上に木を植えるとともに石材を堆積したため、Xを含む一般住民の通行が不可能となり、その上、Yが納屋を増築するに至って道路としての機能一切が消滅した。そこで、XらがYに対して通行妨害の排除を求めて提訴した。
(争点)
村民が村道を使用することについての法的権利性をどう解すべきか。その権利が侵害された場合に、妨害排除を求めることは可能か。
(判旨)
「地方公共団体の開設している村道に対しては村民各自は他の村民がその道路に対して有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行い得べきところの使用の自由権を有する。この通行の自由は公法関係から由来するものであるけれども、各自が日常生活上諸般の権利を行使するについて欠くことのできない要具であるから。これに対しては民放の保護を与うべきは当然の筋合である。故に一村民がこの権利を妨害されたときは民法上不法行為の問題の生ずるのは当然であり、この妨害が継続するときは、これが排除を求める権利を育てる。」
(ポイント)
村民は、村道を自己の生活のために使用する自由権を有するので、継続的な妨害がされた場合には、当該妨害の排除を請求できる。
13.幼年者との面会(最判平3.7.9)
(事案)
連続企業爆破犯として死刑判決を受け最高裁に上告中のXは、死刑廃止運動に関係するA女から援助を受け、その後A女の母親Bと養子縁組を結んだ。その上で、Xは、かねて文通により交流のあったA女の娘C(義理の姪、当時10歳)との面会の許可を拘置所長に求めたところ、拘置所長は、14歳未満との接見(面会)を原則として禁止する監獄法施行規則120条を理由に、許可しなかった。
そこで、Xは、規則120条が監獄法50条による委任の範囲を超えるものであって、憲法31条・13条・14条の保障する在監者と幼年者の面会権を制限するものとして違憲であること、仮に違憲でないとしても拘置所長の判断には裁量権を濫用した違法であることを理由に、本件不許可処分の取消しを求めるとともに、国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した。
憲法31条
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法13条
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法14条
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
(争点)
① 監獄法施行規則(旧)120条および(旧)124条は、憲法ならびに監獄法に違反しないか。
② 拘置所長が未決拘留者と14歳未満の者との接見を許さなかったことは、国家賠償法1条1項の適用を受ける違法行為といえるか。
(判旨)
「被拘留者には一般市民としての自由が保障されるので、法45条は、被拘留者と外部の者との接見は原則としてこれを許すものとし、例外的に、これを許すと支障を来す場合があることを考慮して、(ア)逃亡又は罪証隠滅のおそれが生ずる場合にはこれを防止するために必要かつ合理的な範囲において右の接見に制限を加えることができ、また、(イ)これを許すと監獄内の規律又は秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が認められる場合には、右の障害発生の防止のために必要な限度で右の接見に合理的な制限を加えることができる、としているにすぎないと解される。この理は、被拘留者との接見を求める者が幼年者であっても異なるところはない。
これを受けて、50条は、『接見ノ立会・・・其他接見・・・ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム』と規定し、命令(法務省令)をもって、面会の立会、場所、時間、回数等、面会の態様についてのみ必要な制限をすることができる旨を定めているが、もとより命令によって右の許可基準そのものを変更することは許されないもである。
ところが、規則120条は、規則121条ないし128条の接見の態様に関する規定と異なり、『14歳未満ノ者ニハ在監者ト接見ヲ為スコトヲ許サス』と規定し、規則124条は「所長ニ於テ処遇上其他必要アリト認ムルトキハ前4条ノ制限ニ依ラサルコトヲ得」と規定している。右によれば、規則120条が原則として被拘留者と幼年者との接見を許さないこととする一方で、規則124条がその例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととしていることが明らかである。しかし、これらの規定は、たとえ事物を弁別する能力の未発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても、それ自体、法律によらないで、被拘留者の接見の自由を著しく制限するものであって、法50条の委任の範囲を超えるものといわなければならない。
しかし、規則「20条(及び124条)は明治41年に公布されて以来長きにわたって施行されてきたものであって(もっとも、規則124条は、昭和6年私法省令第9号及び昭和41年法務省令第47号によって若干の改正が行われた。)、本件処分当時までの間これらの規定の有効性につき、実務上特に疑いを挟む解釈をされたことも裁判上とりたてて問題とされたこともなく、裁判上これが特に論議された本件においても第一、第二審がその有効性を肯定していることはさきにみたとおりである。そうだとすると、規則120条(及び124条)が右の限度において法50条の委任の範囲を超えることが当該法の執行者にとって容易に理解不能であったということはできないのであって、このことは国家公務員として法令に従ってその職務を遂行すべき義務を負う監獄の長にとっても同様であり、監獄の長が本件処分当時右のようなことを予見し、又は予見すべきであっいたということはできない。
本件の場合、原審の確定した事実関係によれば、所長は、規則120条に従い、本件処分をし、被上告人とCとの接見をきょかしなかったというのであるが、右に説示したところによれば、所長が右の接見を許可しなかったことにつき国家賠償法1条1項にいう『過失』があったということはできない。」
(ポイント)
① 監獄法施行規則(旧)120条および(旧)124条は、未決交流を14歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法50条の委任の限度を超え、無効である。
② しかし、拘置所長が行った不許可処分は、長きにわたって施行され、その有効性につき実務上特に疑いを差し挟む解釈がなされていなかった規定に基づいてなされたものであるため、国家賠償法1条1項にいう過失はない。
14.銃刀法14条に基づく委任の範囲(最判平2.2.11)
(事案)
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)14条は、一般的には所持が禁止されている銃砲刀剣類のうち、美術品もしくは骨董品として価値のある古式鉄砲または美術品として価値のある刀剣類に限り、文化庁長官の登録を受ければ例外的に所持・保管が許される旨の規定を定め、同条5項において登録の方法など登録に関し、必要な細目については文部省令で定めることが規定されていた。
これに対し、Xは、自己所有の外国製刀剣(サーベル)が「美術品として価値のある刀剣類」にあたり、例外的に所持が許される刀剣であることを主張して登録を申請したところ、文化庁長官から権限の委任を受けた都教育委員会(Y)から、登録に関わる鑑定基準の対象を規定する銃砲刀剣類登録規則(文部省令)4条2項には日本刀のみが規定されていることを理由に、申請を拒否された。
そこで、Xは、銃刀法14条が外国製刀剣を署外せずに登録の基準を文部省令に委任しているにもかかわらず、登録規制が登録に関わる鑑定基準の対象を日本刀に限定していることは、法の委任の趣旨を逸脱した違法なものであるとして、当該登録規制に基づくYの申請拒否処分の取消しを求めて出訴した。
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)14条
(登録)
第十四条 都道府県の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた都道府県にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。)は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 都道府県の教育委員会は、第一項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
(争点)
鑑定基準の対象を日本刀に限定する銃砲刀剣類登録規制(文部省令第2項は、銃刀法14条の委任の範囲を超えたものとして無効となるか。
(判旨)
「どのような銃刀類を我が国において文化財的価値を有するものとして登録の対象とするのか相当であるかの判断には、専門的知識経験を有する登録審査委員の鑑定に基づくことを要するものとともに、その鑑定の基準を認定すること自体も専門技術的な領域に属するものとしてこれを規則に委任したものというべきであり、したがって、規則においていかなる鑑定の基準を定めるかについては、法の委任の趣旨を逸脱しない範囲内において、所轄行政庁に専門技術的な観点からの一定の裁量権が認められているものと解するのが相当である。
要件が法の委任の趣旨を逸脱したものであるか否かをみるに、刀剣類の文化財的価値に©着目してその登録の途を開いている前記法の趣旨を勘案すると、いかなる刀剣類が美術品として価値があり、その登録を認めるべきかを決する場合にも、その刀剣類が我が国において有する文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、前記のとおり美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定め、この基準に合致するもののみを我が国において前記の価値を有するものとして登録の対象にすべきものとしたことは、法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱するものというべきではない。」
(ポイント)
登録規制4条2項が鑑定基準の対象を美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃刀法14条1項の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものであるから、法の委任の趣旨を逸脱する無効のものではできない。つまり、委任の範囲内である。
15.学習指導要領の法的性質(最判平2.1.18)
(事案)
福岡県伝習館高校の社会科教諭のXらが、学習指導要領の目標および内容うぃ逸脱した指導や教科書の不使用、考査の不実施などを理由に県教育委員会から懲戒免職処分を受けたため、当該処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
① 文部省告示たる高等学校学習指導要領に法規性は認められるか。
② 懲戒権者による裁量権の逸脱があるか。
(判旨)
「思うに、高等学校の教育は、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とするものであるが、中学校の教育の基礎の上に立って、所定の修業年限の間にその目的を達成しなければならず(学校教育法41条、46条参照)、また、高等学校においても、教師が依然生徒に対し相当な影響力、支配力を有しており、生徒の側には、いまだ教師の教育内容を批判する十分な能力は備わっておらず、教師を選択する余地も大きくないのである。これらの点からして、国が、教育の一定水準を維持しつつ、高等学校教育の目的達成に資するために、高等学校教育の内容及び方法について遵守すべき基準を定立する必要があり、特に法規によってそのような基準が定立されている事柄については、教育の具体的内容及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量にもおのずから制約が存在するのである。
本件における前記事実関係によれば、懲戒事由に該当する被上告人らの前記各行為は、高等学校における教育活動の中で枢要な部分を占める日常の教科の授業、考査ないし生徒の成績評価に関して行われたものであるところ、教育の具体的内容及び方法につき高等学校の教師に認められるべき裁量を前提としてもなお、明らかにその範囲を逸脱して、日常の教育の在り方を律する学校教育法の規定や学習指導要領の定め等に明白に違反するものである。
以上によれば、上告人が、所管に属する福岡県下の県立高等学校の教諭等職員の任免其の他の人事に関する事務を管理執行する立場において、懲戒事由に該当する被上告人らの態様、懲戒処分歴等の諸事情を考慮のうえ決定した本件各懲戒処分を、社会通念上著しく妥当を欠くものとまではいい難く、その裁量権の範囲を逸脱したものと判断することはできない。
(ポイント)
① 学校教育法とともに、文部省告示たる高等学校学習指導要領にも法規性は認められる。
② {C}Xらの行為には学校教育法・学習指導要領の定めに明白に違反する事実が認められるのため、懲戒権者たる福岡県教育委員会の処分に裁量権の範囲を逸脱していない。
16.通達に対する取消訴訟(最判昭43.12.24)
(事案)
本件通達は、昭和35年3月8日に厚生省公衆衛生環境衛生部長から各都道府県指定都市衛生主管部長にあてて発せられたものであるが、それは、当時、創価学会と他の既成宗教団体との間の対立から、創価学会員の家族の埋葬拒否事件が全国の墓地において頻発したため、これを是正すべく、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由として埋葬の求めを拒むことは墓地、舞相当に関する法律13条が認める「正当な理由」にはあたらないとの内閣法制局第一部長の趣旨に沿って今後の事務処理を行うよう求める内容のものであった。
そのため、墓地を経営する真言宗の一寺院であるXが、本件通達は、従来慣習法上認められていた異宗派を理由とする埋葬拒否権の内容を変更し、新たにXに対して一般第三者の埋葬請求を受忍すべき義務を負わせたものであって、この通達により、以後このような理由による埋葬拒否に対しては刑罰を科せられるおそれがあるとともに、現にこの通達が発せられてから多くの損害や不利益を被っているとして、本件通達の取消しを求める訴えを提起した。
(争点)
本件の通達は、行政事件訴訟法に基づく取消しの訴えの対象となりうるか。
(判旨)
「本件通達は、厚生省公衆衛生局環境衛生部長から都道府県指定都市衛生主管部局長にあてて発せられたので、その内容は、墓地、埋葬等に関する法律13条に関し、昭和24年8月22日付東京都衛生局長あて回答に示しオタ見解を改め、今後は内閣法制局第一部長の昭和35年2月15日付回答の趣旨にそって、解釈、運用することとしたことを明らかにすると同時に、諸機関において、この点に留意して埋葬等に関する事務処理をすると同時に、諸機関において、この点に留意して埋葬等に関する事務処理をするよう求めたものであり、行政組織および右法律の施行事務に関する関係法令を参酌すれば、本件通達は、被上告人がその権限にもとづき所掌事務について、知事を含めた関係行政機関に対し、法律の解釈、運用の方針を示して、その職務権限の行使を指揮したものと解せられる。
元来、通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員に対する行政機関内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に拘束されることはあっても、一般の国民は直接これに拘束されるものではなく、、このことに、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。
このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用あたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合いである。
このような通達一般の性質、前述した本件通達の形式、内容および原判決の引用する一審判決認定の事実(挙示の証拠に照らし背認することができる。)その他原審の違法に確定した事実ならびに墓地、埋葬等に関する法律の規定を併せて考えれば、本件通達は従来とらえられていた法律の解釈や取扱いを変更するものではあるが、それはもっぱら知事以下の行政機関を拘束するにとどまるもので、これらの機関は右通達に反する行為をすることはできないにしても、国民は直接これに拘束されることはなく、従って、右運動が直接に上告人の所論墓地経営権、管理権を侵害したり、新たに埋葬の受忍義務を課したりするものとはいえない。また、墓地等に関する法律21条違反の有無に関しても、裁判所は本件通達における法律解釈に拘束されるものではないのみならず、同法13条にいわゆる正当の理由の判断にあたっては、本件通達に示されている事情以外の事情をも考慮すべきものと解せられるから、本件通達が発せられたからといって直ちに上告において刑罰を科せられるおそれがあるともいえず、さらにまた、原審において上告人が主張するような損害、不利益は、原判示のように、直接本件通達によって被ったものということもできない。
そして、現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達中所轄の趣旨部分の取消しを求める本件訴は許されないものとして却下すべきものである。」
(ポイント)
通達は、原則として、法規の性質をもたず、上級行政機関が関係下級行政機関・職員に対しての職務権限の行使を指揮し、職務に対して命令するために発するものにすぎないので、一般の国民は直接これに拘束されない。行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になりうるのは、国民の権利義務や法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼす行政処分等でなければならない。したがって、通達の取消しを求める訴えは許さない。
つまり、通達は訴えの対象とならない。
17.みなし道路の一括指定(最判平14.1.17)
(事案)
Xは、奈良県御所市内の都市計画区域内に土地を所有していたところ、奈良県知事(Y)は、昭和37年12月28日付けの奈良県告示第327号により、「都市計画区域内において建築基準法施行の際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満1.8m以上の道については、建築基準法42条2項の規定により、同1項が規定する道路とみなすところの道路(みなし道路)に当たる」旨を指定した。
そのため、Xがその所有地上に建物の新築工事をするための建築確認申請に先立って、当該土地の一部である通路上の土地(本件通路部分)がこの「みなし道路(2項道路)」にあたるか否かを奈良県高田土木事務所に照合したところ、平成元年1月30日に建築主事から本件道路部分が「みなし道路(2項道路)」にあたる旨の回答がされた。
そこで、Xは、本件道路が建築基準法42条2項の要件をみたしておらず、本件通路部分についての指定部分は、存在しないことの確認を求める訴訟を提起したが、原審(大阪高判平10.6.17)は、Yによる当該告示は、包括的に一括して幅員4m未満1.8m以上の道を「みなし道路(2項道路)」とすることを定めたにとどまるものであって、本件通路部分といった特定の土地について個別具体的に指定したものではなく、不特定多数の者に対して一般的抽象的な基準を定立するものにすぎないから、これにより直ちに建築制限等の私権の制限を生じるものとして抗告訴訟の対象となる行政処分にあたると解することはできないとして、Xの訴えを却下した。そこで、Xが上告した。
(争点)
告示により一括して指定する方法でされた建築基準法42条2項所定のいわゆるみなし道路の指定は、抗告訴訟の対象となる処分に該当するか。
(判旨)
「本件告訴は、幅員4m未満1.8m以上の道を一括して2項道路として指定するものであるが、これによって、法第3章の規定が適用されるに至った時点において現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道のうち、本件告示の定める幅員1.8m以上の条件に合致するものすべてについて2項道路としての指定がされたこととなり、当該道につき指定の効果が生じるものと解される。原判決は、特定の土地について個別具体的に2項道路の指定をするものではない本件告示自体によって直ちに試験制限が生じるものではない旨をいう。しかしながら、それが、本件告示がされた時点では2項道路の指定の効果が生じていないとする趣旨であれば、結局、本件告示の定める条件に合致する道であっても、個別指定の方法による指定がない限り、特定行政庁により2項道路の指定がないことに帰することとなり、そのような見解は相当とはいえない。
そして、本件告示によって2項道路の指定の効果が生じるものと解する以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は2項道路とされ、その敷地所有権は当該道路につき道路内の建築物が制限され(法44条)、私道の変更又は廃止が制限される(法45条)等の具体的な試験の制限を受けることになるのである。そうすると、特定行政庁による2項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができる。
したがって、本件告示のような一括指定の方法による2項道路の指定も、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解すべきである。
そして、本件訴えは、本件通路部分について、本件告示による2項道路の指定の不存在確認を求めるもので、行政事件訴訟法3条4項にいう処分の存否のかくにんを求める抗告訴訟であり、同法36条の要件を満たすものということができる。
行政事件訴訟法3条4項
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法36条
(無効等確認の訴えの原告適格)
第三十六条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
(ポイント)
特定行政庁による2項道路の指定が一括指定の方法でされた場合でも、それにより指定の効果が及び道における敷地所有者は、当該道路内の建築物等が制限され、私道の変更・廃止が制限されるといった具体的な私権の制限を受けることになるので、そのような一括指定の方法による2項道路の指定も、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものであり、抗告訴訟の指定も。個人の権利義務に対して直接影響を与えるものであり、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
18.パチンコ球遊器事件(最判昭33.3.28)
(事案)
旧物品税法1条1項は、課税対象物品の一つとして「遊戯具」を挙げていたが、パチンコ球技器については同法にも同法施行規則にも明記がなく、約10年間にわたって物品税が賦課されない状態が続いていた。昭和26年3月2日の東京国税局長から管下税務署長に対する通達においてパチンコ球遊器が「遊戯具」にあたる旨が示され、これに従い、品川・大森・蒲田・墨田の各税務署長(Yら)に対し、物品税課税処分行った。
そこで、Xらは、被課税累計額計約238万円を納付した上で、本件処分の無効確認と納付金の返還を求めて出訴した。
(争点)
本件課税処分は、法律に基づかない「通達課税」であり、租税法律主義に反するのではないか。
(判旨)
「物品税は、物品税法が施行された当初(昭和4年4月1日)においては、消費税として出発したものではあるが、その後次第に生活必需品その他いわゆる資本的消費財も課税品目中に加えられ、現在の物品税法(昭和15年法律第40号)が制定された当時、すでに、一部生活必需品(たとえば隣寸)(第1条大3号)や「撞球台」(第1条第二種甲類1)」「乗用自動車」(第1条第二種甲類14)等の資本財もしくは資本財らり得べきものも課税品目として揚げられ、その後の改正においてさらにこの種の品目が数多く追加されたこと、いわゆる消費的消費財と生産的消費財との区別はもともと相対的なものであって、パチンコ球遊器も自家用消費財としての性格をまったく持っていたとはいい得ないこと、その他第一、第二判決の揚げるような理由にかんがみれば、社会通念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり、現判決も、もとより、所論のように、単に立法論としてパチンコ球遊器をぁ税品目に加えることの妥当性を論じたものではなく、現行法の解釈として「遊戯具」中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであって、右判決は正当である。
なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまたま所論通達を機縁として行われたものであったとしても、通達の内容が正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分と解するに妨げがなく、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであって、採用し得ない。」
(ポイント)
課税が通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上。その課税処分は法の解釈に基づくs誤聞であり、租税法律主義に反しない。
19,市街地再開発事業計画の決定・公告(最判平4.11.26)
(事案)
大阪市(Y)は、都市再開発法54条1項に基づき、阿部野地区における第二種市街地再開発事業の事業計画を決定し、その公告をしたが、当該地区内に不動産を所有するXは、本件事業計画決定の違法性を主張してその取消しを求めた。これに対し、第一審(大阪地判昭61.3.26)は事業計画決定の処分性を否定し、訴えを却下したが、第二審(大阪高判昭63.6.24)は事業計画決定の処分性を認め、本件を一審に差し戻したため、Yが上告した。
(争点)
都市再開発法に基づく第二種事業の事業計画決定は抗告訴訟の対象となるか。
(判旨)
「都市再開発法51条1項、54条1項は、市町村が、第二種市街地再開発事業を施行しようとするときは、設計の概要について都道府県知事の認可を受けて事業計画(以下「再開発事業計画」という。)を決定し、これを抗告しなければならないものとしている。そして、第二種市街地再開発事業については、土地収用法3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなして同法の規定を適用するものとし(都市再開発法6条1項、都市計画法69条)、都道府県知事がする設計の概要の許可をもって土地収用法20条の規定による事業の認定に代えるものとするとともに、再開発事業計画の決定の公告をもって同法26条1項の規定による事業の認定の告示とみなすものとしている(都市再開発法6条4項、同法施行令1条の6、都市計画法70条1項)。したがって、再開発事業計画の決定は、その広告の日から、土地収用法上の事業の認定と同一の法律効果を生ずるものであるから(同法26条4項)、市町村は、右決定の公告により、同法に基づく収用権限を取得するとともに、その結果として、施行地区の土地の所有者は、特段の事情のない限り、自己の所有地等が収用されるべき地位に立たされていることになる。しかも、この場合、都市再開発法上、施行地区内の宅地の所有者等は、契約又は収用により施行者(市町村)に取得される当該宅地等につき、公告があった日から起算して30日以内に、その対償の払渡しを受けることとするか又はこれに代えて建築施設の部分の譲受け希望の申出をするかの選択を余儀なくされるのである(同法118条の2第1項1号)。
そうであるとすると、公告された再開発事業計画の決定は、施行地区得内の土地の所有者等の法的地位を直接的な影響を及ぼすものであって、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解するのが相当である。」
(ポイント)
都市再開発法に基づき地方公共団体により定められ公告された第二種市街地再開発事業の事業計画の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
20.工場誘致計画の変更(最判昭56.1.27)
(事案)
沖縄県宜野座村(Y)の村議会は、X会社の工場を誘致するため、村所地を工場敷地の一部として譲渡する旨の決議を行った。そのため、X側も村有地の耕作者らに補償料を払い、整地工事等の行為も完了した。ところが、その後行われた村長選挙で本件工場進出反対の候補が当選し、Xが提出した工場の建築確認申請に不同意の旨の通知をした。
そこで、Xは、Yの協力拒否のために工場の建設・操業が不可能になり損害を被ったとして、損害賠償請求訴訟を提起した(元本額5574万5614円)。
(争点)
地方公共団体が一定の継続的な施策を計画・決定し、それに基づき特定の者に対して当該施策に適合する活動を個別具体的に勧告・誘致した後に当該施策を変更した場合、相手方に対して違法な加害行為を行ったものとして損害賠償責任を負うか。
(判旨)
「地方公共団体の施策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆる住民自治の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する見本原則であり、また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基礎として維持されるものと信頼し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右活動ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき審議衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかる信頼に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのではない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして前記住民自の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方を保護しないことが許されるものと解すべきではない。
(ポイント)
地方公共団体が計画・決定した施策に基づきなされた勧告・勧誘に動機づけられて活動に入った者が、その後の施策の変更により社会通念上看過することのできない程度の積極的損害を被った場合には、これにつき補償等の代償的措置を講じないまま施策を変更した当該地方公共団体は、やむを得ない客観的事情がない限り、損害賠償責任を免れない。
つまり、損害賠償責任を負う場合あり。
21.病院開設中止勧告に対する抗告訴訟(最判平17.7.15)
(事案)
Xは、富山県高岡市内にて病院の解説を計画し、富山県知事(Y)に対して医療法7条1項に基づく許可申請をしたところ、Yは、高岡医療圏における病院の病床数が富山県地域医療計画に定める必要病床数に達していることを理由に開設を中止するよう勧告した。これに対し、Xが、当該勧告を拒否するとともに、速やかに本件申請に対する許可をするよう文書で求めたため、Yは本件申請を許可する旨の処分をしたが、その際、富山県厚生部長名で「中止勧告にもかかわらず病院を開設した場合には、厚生省通知において、保険医療機関の指定の拒否をすることとされているので、念のため申し添える」との通告文書が送付された。
そこでXは、本件勧告は医療法30条の7に反するもので違法であり、また本件勧告とともになされた許可処分はいわば負担付きの許可であるとして、本件勧告の取消しまたは本件通告部分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
① 病院開設の中止勧告は、行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」といえるか。
② 本件の保険医療機関の指定の拒否があり得る旨の通告は、同法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」といえるか。
(判旨)
「富山県厚生部長名の本件通告部分をもって被上告人がした病院開設中止勧告と解することはできないから、その取消しを求める訴えを却下するべきものとした原審の判断を是認することができる。
しかし、医療法及び健康保険法の規定の内容やその運用の実情に照らすと、医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められているけれども、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当限度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。そして、いわゆる国民皆保険制度が採用されている我が国においては、健康保険、国民健康保険等を利用しないで病院で受診する者はほとんどなく、保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから、保険医療機関の指定を受けることができない場合には、実際上病院の開設自体をだんねんせざるを得ないことになる。このような医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果及び病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。後に保険医療機関の指定拒否処分の効力を抗告訴訟によって争うことができるとしても、そのことは上記の結論を左右するものではない。
したがって、本件勧告は、行政事件訴訟法3条2項の『行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為』に当たるというべきである。」
(ポイント)
① 医療法30条の7に規定に基づく病院開設中止の勧告は、行政指導として定められてはいるが、これに従わない場合には相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものであり、その効果・意義から、当該勧告は行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」にあたる。
行政指導は、事実行為であることから、原則として処分性が否定される。この判決は、行政指導である病院開設中止の勧告の処分性を肯定したものであり、要注意である。
●行政指導の処分性
原則・・・否定
例外・・・病院開設中止の勧告→肯定
② ただし、富山県厚生部長名でなされた通告は、富山県知事がした病院開設中止勧告と解することはできないから、同法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」ではない。
22.執拗な退職勧奨に対する慰謝料請求(最判昭55.7.10)
(事案)
下関市立商業高校に勤務するXら3人の教諭に対し、下関市教育委員会が長期・多数回にわたり退職勧奨(いわゆる「肩たたき」)を継続したため、当該一連の行為により精神的苦痛を受けたとして、Xらが下関市(Y)に対して国家賠償法に基づく慰謝料の支払いを求めて出訴した。
(争点)
執拗な退職勧奨は、国家賠償法に基づく慰謝料請求の対象となるか。
(判旨)
「被勧告者は何らの拘束なしに自由にその意思を決定しうるのはもとより、いかなる場合でも勧奨行為に応ずる義務もないと解するのが相当である。なお勧奨は一定の方法にしたがって行われる必要はなく、退職を求める人事行政上の事情や、被勧奨者の健康状態、勤務に対する適応性、家庭の事情その他被勧奨者の要望等具体的状況に応じて、退職の同意を得るために適切な種々の観点から説得方法を用いることができるが、いずれにしても、被勧奨者の任意の意思形成を妨げ、あるいは名誉感情を害するごとき言動が許されないことは言うまでもなく、そのような勧奨行為は違法な権利侵害として不法行為を構成する場合があることは当然である。」
(ポイント)
本来の目的である被鑑賞者の自発的な退職意思の形成を促す限度を超える心理的圧力を加えた場合には、違法な権利侵害として不法行為を構成する。
23.指導要綱に基づく開発負担金(最判平5.2.18)
(事案)
武蔵野市(Y)は、相次ぐマンション建設から市民の生活環境を守るため、一定規模以上の宅地開発または中高層建築物の建設を行おうとする事業主等に対する行政指導の内容を定める「武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱」を制定してきたが、その中には、事業主が「寄付願」を市長に提出して教育施設負担金を納付することも規定されていた
そこで、昭和52年に3階建てマンションの建築を計画し、教育施設負担金として1523万2000円の寄付を要請され、減免等の懇願も拒絶された結果、やむなく同額を納付したXが、当該寄付行為が強迫に基づくものであることを理由とした取消しと、武蔵野市による行政指導が違法な公権力の行使に当たることを理由とした国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を主張して出訴した。
(争点)
建設指導要綱に基づく寄付の要請は、国家賠償法1条1項に規定する違法な権力の行使にあたるか。
(判旨)
「行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、適法ということはできない。
被上告人がAに対し指導要領に基づいて教育施設の納付を求めた行為も、被上告人の担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、Aに対し、指導要綱所定の教育施設負担金をのうふしてなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって、マンションを建築しようとする以上右行政指導に従うことを余儀なくされるものであり、Aに教育施設負担金の納付を事実上強制しいようとしたものということができる。指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持をうけていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」
(ポイント)
本来の行政指導は、事業主の任意性を損なうことがない限り違法ではないが、事実上の強制にあたり、従うことを余儀なくされるものである場合、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使にあたる。
24.品川区マンション事件(最判昭60.7.16)
(事案)
Xは、昭和47年10月28日に本件マンションの建築確認申請を東京都(Y)にしたところ、付近住民からの反対運動を考慮したYが、Xに対して付近住民との話合いによる円満解決を指導し、Xもこれに応じて十数回の話合いを付近住民と行ったが、解決には至らなかった。
そうこうするうちに、Yは、昭和48年2月15日になって新高度地区案を発表し、その中で付近住民との紛争が解決しない事案については確認処分を行わない旨を定め、これに従い、Xに対しても、新高度地区案に沿った形での設計変更を求めるとともに、付近住民との話合いをさらに進めるよう勧告した。
そこで、Xは、確認処分留保を背景とするYの行政指導にはもはや服さない旨を表明し、同年3月1日に建築審査会に本件確認申請についての審査請求をしたが、結局、3月30日に至って金銭補償により住民との紛争を解決するとともに審査請求を取り下げたため、Yの建築主事も本件申請についての建築確認処分をした。しかし、Xは、当該確認申請に対する審査が終了しているにもかかわらず付近住民との話合いを強制的に指導し、その期間中確認処分を留保したYの行政処分は違法であるとして、確認留保期間中の請負代金の増加額と金利相当額の損害賠償をYに求める訴訟を提起した。
(争点)
建築主と付近住民との紛争につき建築主に行政指導が行われていることのみを理由として建築確認申請に対する処分を留保することは、国家賠償法1条1項に規定する違法な公権力の行使にたるか。
(判旨)
「建築基準法(以下「法」という。)6条3項及び4項によれば、建築主事は、同条1項所定の建築確認の申請書を受理した場合においては、その受理した日から21日(ただし、同条1項4号に揚げる建築物に係るものについては7日)以内に、申請に係る建築物の計画が当該建物の計画が当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは確認の通知を、適合しないと認めたときはその旨の通知(以下あわせて「確認処分」という。)を当該申請者に対して行わなければならないものとさだめられている。
しかしながら、建築主事の右義務は、いかなる場合にも例外を許さない絶対的な義務であるとまでは解することができないというべきであって、建築主事が確認処分の留保につき任意にしているものと認められる場合のほか、必ずしも右の同意のあることが明確であるとはいえない場合であっても、諸般の事情から直ちに確認処分をしないで応答を留保することが法の趣旨目的に照らし社会通念上合理的と認められるときは、その間確認申請に対する応答を留保することをもって、確認処分を違法に遅滞するものということはできないというべきである。
もっとも、右のような確認処分の留保は、建築主事の任意の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受任を強いることは許されない筋合いのものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導がおこなわれているとの理由だけで確認処分を留保することは、違法であると解するのが相当である。
したがって、いったん行政指導に応じて事業主と付近住民との間に話合いによる紛争解決をめざして協議が始められた場合でも、右協議の進行状況及び四囲の客観的状況により、建築主において建築主事に対し、確認処分を留保したままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、当該確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めているものと認められるときには、他に前記特段の事情が存在するものと認められない限り、当該行政処分を理由に建築主に対しっ確認処分の留保の措置を受忍せしめることの許されないことは前述のとおりであるから、それ以後の右行政指導を理由とする確認処分の留保は、違法となるものといわなければならない。
(ポイント)
建築主が確認申請に対する処分が留保されたままでの行政指導には協力できない旨の意思を真摯かつ明確に表明して申請に対する応答を求めたときには、特別の事情がない限り、行政指導が継続していることだけを理由とする確認処分の留保は国家賠償法1条1項に規定する違法な公権力の行使に該当する。
なお、平成6年10月から施行された行政手続法33条によって、本件のような場合を、明確に規制した。
25.営業許可を受けない食肉買入契約の効力(最判昭35.3.18)
(事案)
X社は、食品衛生法による許可を受けて食肉の販売を営んでいるA社に精肉を卸していたが、A社の支払いが滞りがちだったため取引を一時中止した。そのため、A社の代表取締役YがY個人として食肉を買い受けたい旨を懇請し、X社もこれを承諾して取引を再開したが、Yは内金を支払ったのみで残代金を支払わないことから、X社が残代金および遅延損害金の支払いを求めて出訴した、これに対して、Yは、Y個人が食品衛生法に基づく営業許可を受けていないことを理由に、本件契約が民放90条に違反し無効である旨を主張した。
民放90条
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(争点)
食品衛生法に基づく食肉販売業許可を受けない者との間でなした食肉の売買契約は、単なる取締法規違反か。
(判旨)
「本件売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食品販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定される理由はない。それ故右許可の有無は本件取引の私法上の効力に消長を及ぼすものではないとした原審の判断は結局正当であり、所論を採るを得ない。
(ポイント)
営業許可を受けない者がした食肉の買入契約は無効ではない。つまり、無許可の行為でも、その効力自体は有効である点に注意。
26.行政庁の承認を受けない農地賃借権移転(最判昭31.4.13)
(事案)
Aは、その所有する農地の賃借権をBからXに移転させていたころ、当該農地は政府に買収された上で、兵庫県知事(Y)により一部がCほか3名に、残部についてはXに売り渡す処分がなされた。これに対し、Xは、当該農地は全体について自作農創設特別措置法17条1項1号により自分に売り渡されるべきものであるとして、Cらに対する売渡処分の取消しを求めて出訴したが、Yは、BからXへの本件農地に関する賃借権の移転については、農地調整法に基づく村農地委員会の承認を受けていないことから無効であり、Cらへの売渡処分は自作農創設特別措置法施行令17条1項7号により正当である旨を主張した。
なお、本件農地に関する賃借権の移転については、AとXから耕作変更届が村農地委員会に提出されていたが、同委員会はこれを単なる陳情書として取り扱い、未承認のままになっていた経緯があり、この点につき、Yは、農地賃借権の移転に関する承認は合議制の行政庁たる農地委員会の自由裁量行為に属する旨を主張している。
(争点)
市町村農地委員会が(改正前の)農地調整法4条に基づいて行う農地賃借権の設定・移転に関する承認は、同委員会の自由裁量行為といえるか。
(判旨)
「論旨は、昭和24年法律第215号による農地調整法改正前の同法4条は、承認について何等客観的基準を設けておらず、従って承認は行政庁の自由裁量に属するに関わらず、原判決が改正後の規定を類推して羈束行為であるとしたのは、法律の解釈を誤った違法があるというのである。
しかし、農地に関する賃借権の設定移転は本来個人の自由契約に委ねられていた事項であって、法律が小作権保護の必要上これに制限を加え、その効力を承認にかからせているのは、結局個人の自由の制限であり、法律が承認について客観的な基準を定めていない場合でも、法律の目的で必要な限度においてのみ行政庁も承認を拒むことができるのであって、農地調整法の趣旨に反して承認を与えないのは違法であるといわなければならない。換言すれば、承認するかしないかは農地委員会の自由な裁量に委せられているのではない。
論旨は被上告人が提出したのは耕作変更届であって、法令に規定する承認申請所ではないというのである。しかし、かかる書面の趣旨が届出であるか承認申請であるかは、書面の文字によってのみ判断すべきものではない。農地調整法4条によって賃借権の設定、移転について承認、許可が必要である以上、当該行政機関としては耕作変更届と記載されていてもこれを承認許可を求める趣旨と解するか或は書面の訂正を求めるかすべきであって、届と記載してあるからといって、単なる陳述書として取り扱うことはゆるされないものと解すべきである。」
(ポイント)
農地賃借権の設定・移転に関する承認は、市町村農地委員会の自由裁量に委ねられていない。
自由裁量行為ではなく、羈束裁量行為である。
●羈束裁量行為と自由裁量行為
羈束裁量行為・・・裁判所が社会通念を基準に行政庁が行うべき行為の限界を判断す
ることができる裁量行為をいう。
自由裁量行為・・・どのような行為をするか、広く行政庁に委ねられている裁量行為
をいう。
27.マクリーン事件(最判昭53.10.4)
(事案)
アメリカ人であるXは、当時の出入国管理令に基づき、在留期間を1年とする許可を受けてわが国に滞在していたが、さらに1年間の在留期間の更新を法務大臣(Y)に申請したところ、在留期間中の無届転職と政治活動を理由に、出獄準備期間としての120日間の更新を許可されただけで、1年間の更新については、それを適当と認める足りる相当な理由があるとはいえないとして拒否された。そこで、Xは、当該不許可処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を認めるに足りる相当の理由の有無に関する判断について、法務大臣の裁量権はどの程度認められるものであり、それに対する裁判所の司法審査はどの範囲で及ぶのか。
(判旨)
「憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内にうけいれるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていること、その考えを同じくするものと解される。したがって、憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、所論のように在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解すべきである。そして、上述の憲法の趣旨を前提として、法律としての効力を有する出入国管理令は、外国人に対し、一定の期間を限り特定の資格によりわが国への上陸を許された外国人は、その在留期間が経過した場合には当然わが国から退去しなければならない。もっとも、出入国管理令は、当該外国人が在留期間の延長を希望するときには在留期間の更新を申請することができることとしているが(21条1項、2項)、その申請に対しては法務大臣が「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限りこれを許可することができるものと定めている(同条3項)のであるから出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものではないことは、明らかである。
右のように出入国管理令が原則として一定の期間を限って外国人の我が国への上陸及び在留を許しその期間の更新は法務大臣がこれを適当と道メルに足りる相当の理由があると判断した場合に限り許可することとしているのは、法務代位人に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨に出たものであり、そして、在留期間の更新事由が概括的に規定されその判断基準が特に定められていないのは、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨からであると解される。すなわち、法務大臣は、在留期間の更新の許否を決するにあたっては、外国人に対する出入国の管理及び在留の規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持、保険・衛生の確保、労働市場の安定などの国益の保持の見地に立って、申請者の申請事項の当否のみならず、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の政治・経済・社会等の諸事情、国際情勢、外交関係、国際礼穣など諸般の事情をしんさくし、時宣に応じた的確な判断をしなければならないのであるが、このような判断は、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければとうてい適切な結果を期待することができないものと考えられる。このような点にかんがみると、出入国管理令21条3項所定の『在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由』があるかどうかの判断における法務大臣の裁量権の範囲が広汎なものとされているのは当然のことであって、所論のように上陸拒否事由又は過去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることは許されないとかいすべきものではない。
したがって、裁判所は、法務大臣の右判断についてそれが違法となるかどうかを審理、判断するにあたっては、右判断が法務大臣の裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が社会通念に照らしい著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその濫用があったものとして違法であるとすることができるものと解するのが、相当である。」
(ポイント)
出入国管理令21条3項に基づく在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無の判断は、法務大臣の(自由)裁量に任されているものであり、裁判所はこの判断が裁量権の範囲を超えまたはその濫用があった場合にのみ、いほうとすることができる。
●自由裁量行為に対する司法審査
原則・・・否定
例外・・・逸脱または濫用→肯定
28.個室付浴場事件(最判昭53.6.16)
(事案)
被告Y社は個室付公衆浴場を開始したが、当該施設から134.6メメートルしか離れていないとことには山形県余目町立のA児童遊園があり、風俗営業等取締法4条の4(現行風俗営業法28条1項)では、児童福祉法7条に規定する児童福祉施設から200メートル以内で個室付公衆浴場を営むことは禁止されていることから、Y社は風俗営業等取締法違反に問われて国(X)から起訴された。
これに対して、Y社は、当該児童福祉施設の設置に係る山形県知事の認可処分は、もっぱらY社の営業を阻止する目的で余目町が申請したものに対してなされたものであり、行政圏の濫用に相当して違法であるとして、無罪を主張した。
(争点)
風俗営業等取締法4条の4に規定する児童福祉法7条に基づく児童福祉施設として、山形県知事がなした本件児童遊園設置の許可処分には、行政権の濫用に相当する違法性があるといえるか。
(判旨)
「本件の争点は、山形県知事のA児童遊園設置認可処分(以下「本件認可処分」という。)の違法性、有効性にある。すなわち、風俗営業等取締法は、学校、児童福祉施設などの特定施設と個室付浴場業の一定区域内における併存を例外なく全面的に禁止しているわけではない(同法4条の4第3項参照)ので、被告会社の営業に先立つ本件認可処分が行政権の濫用に相当する違法性を帯びているときには、A児童遊園の存在を被告会社の営業を規制する根拠にすることは許されないことになるからである。
ところで、原判決は、余目町が山形県の関係部局、同県警察本部と協議し、その示唆を受けて被告会社の営業の規制をさしあたっての主たる動機、目的として本件認可の申請をしたこと及び山形県知事もその経緯を知りつつ本件認可処分をしたことを認定しながら、A児童遊園を認可施設にする必要性、緊急性の有無については具体的な判断を示すことなく、公共の福祉による営業の自由の制限に依拠して本件認可処分の違法性、有効性を肯定している。また、記録を精査しても、本件当時余目町において、被告会社の営業の規制以外に、A児童遊園を無認可施設から認可施設に整備する必要性、緊急性があったことをうかがわせる事情は認められない。
本来、児童施設は、児童に健全な遊びを与えてその健康に増進し、情操をゆたかにすることを目的とする施設(児童福祉法40条参照)なのであるから、児童遊園設置の認可申請を容れた本件認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、被告会社の営業に対しこれを規制しうる効力を有しないといわざるをえない。
そうだとすれば、被告会社の本件営業については、これを規制しうる児童福祉法7条に規定する児童福祉施設の存在についての証明を欠くことになり、被告会社に無罪の言渡をすべきものである。したがって、原判決及び第一審判決は、犯罪構成要件に関連する行政処分の法的評価を誤って被告会社を有罪としたものにほかならず、右の違法は判決に影響を及ぼすもので、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
(ポイント)
個室付浴場業の規制を主たる動機・目的とする知事がした本件児童遊園設置認可処分は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。
29.公立大学の学生に対する懲戒処分(最判昭29.7.30)
(事案)
京都府立医科大学付属女子専門部の教授会は、同専門部に属するA教授の進退問題を審議するための会議を開こうとしたが、A教授の解雇反対を主張する学生達によって会議室は混乱し、教授会は流会となった。このため、京都府立医科大学学長Yは、専門部教授会における学生達の行為は学生の本分にもとり学内の秩序を乱すものであるとして、本科の学生5名(Xら)の放学処分を行った。
これに対して、Xらは、当該懲戒処分は学長としての裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとして、本件放学処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
公立大学の学生に対する懲戒処分は、学長の羈束裁量行為と解すべきか、それとも自由裁量行為と解すべきか。
(判旨)
「大学の学生に対する懲戒処分は、教育施設としての大学の内部規律を維持し教育目的を達成するために認められる自律的作用にほかならない。そして、懲戒権者たる学長が学生の行為に対し懲戒処分を発動するに当り、その行為が懲戒に値するものであるかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかを決するについては、当該行為の軽重のほか、本人の性格および平素の行状、右行為の他の学生に与える影響、懲戒処分の本人および他の学生におよぼす訓戒的効果等の諸般の要素を考量する必要があり、これらの点の判断は、学内の事情に通ぎょうし直接教育の衝に当るものの裁量に任すのでなければ、適切な結果を期することができないことは明らかである。それ故、学生の行為に対し、懲戒処分を発動するかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶかを決定することは、その決定が全く事実上の根拠に基づかないと認められる場合であるか、もしくは社会通念上著しく妥当を欠き懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えるものと認められる場合を除き、懲戒権者の裁量に任されているものと解するのが相当である。原審が上告人等に対する退学処分は懲戒権者たる学長の裁量権の範囲内の行為であると判断したことは正当であって、論旨は採用に値しない。」
(ポイント)
公立大学の学生の行為に対して懲戒処分を発動するかどうか、および懲戒処分のうちのいずれの処分を選ぶかを決定することは、その決定が全く事実上の根拠に基づかないと認められる場合であるか、または社会観念上著しく妥当を欠き懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものと認められる場合を除き、学長の裁量権に任される。つまり、学長の自由裁量行為である。
30.朝日訴訟(最判昭42.5.24)
(事案)
Xは、昭和17年から国立岡山療養所に単身の肺結核患者として入所し、厚生大臣(現厚生労働大臣)の設定した生活扶助基準で定められた最高金額たる付き600円の日用品費の生活扶助と現物による給食医療扶助とを受けていたが、昭和31年8月以降において実兄Cから毎月1500円の送金を受けるようになったため、津山社会福祉事務所長はこれを収入と認定し、月額600円の生活扶助を打ち切り、右送金額から日用品費を控除した残額900円を医療費の一部としてXに負担させる旨の保護変更を決定した。
これに対して、Xは、岡山県知事に対する不服申し立てを経て厚生大臣(Y)に不服を申し立てたが、昭和32年2月15日にこれを却下する旨の本件裁決を受けたため、600円の基準金額は生活保護法が規定する健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するに足りない違法なものであるとして、厚生大臣がなした本件却下裁決の取消しを求めて出訴した。
第一審東京地裁昭和35年10月19日判決はXの主張を認めて請求を任用したが、第二審の東京高等裁判昭和38年11月4日判決は請求を棄却したためXが上告したところ、Xが間もなく死亡した。そこで、その養子夫婦A・Bが生活保護受給権を相続したとして訴訟承継を主張した。
(争点)
① 被保護者が死亡しても、相続人により生活保護処分に関する採決取消訴訟は承認され得るか。
② 生活保護法8条に基づく厚生大臣の保護基準設定行為は、厚生大臣の自由裁量行為といえるか、また、いえるとしても本件基準につき裁量権の逸脱または濫用は認められないか。
(判旨)
「おもうに、生活保護法の規定に基づき要保護者または被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、法的権利であって、保護受給権とも称すべきものと解すべきである。しかし、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれをお譲渡し得ないし(59条参照)、相続の対象ともなり得ないというべきである。また、被保険者の生存中の扶助ですでに遅滞にあるものの給付を求める権利についても、医療扶助の場合はもちろんのこと、金銭給付を内容とする生活扶助の場合でも、それは当該被保険者の最低限度の生活の需要を満たすことを目的とするものであって、法の予定する目的以外に流用することを許されないものであるから、当該被保険者の死亡によって当然消滅し、相続の対象となり得ない、と解するのが相当である。また、所論不当利得返還請求権は、保護受給権を前提としてはじめて成立するものであり、その保護受給権が右に述べたように一身専属の権利である以上、相続の対象となり得ないと解するのが相当である。
されば、本件訴訟は、上告人ンお死亡と同時に終了し、同人の相続人A、同Bの両名においてこれを承継し得る余地はないもの、といわなければならない。
なお、念のために、本件生活扶助基準の適否に関する当裁判所の意見を付加する。
憲法25条1項は、『すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。』
と規定している。この規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みえるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない(昭和23年9月29日大法廷判決参照)。具体的権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するために制定された生活保護によって、はじめて与えられているというべきである。生活保護法は、『この法律の定める要件』を満たすものは、『この法律による保護』を受けることができると規定し(2条参照)、その保護は、厚生大臣の設定する基準に基づいて行うものとしているから(8条1項参照)、右の権利は、厚生大臣が最低限度の生活水準を維持するにたりると認めて設定した保護基準による保護を受け得ることにあると解すべきである。もとより、厚生大臣の定める保護基準は、法8条2項所定の事項を遵守したものであることを要し、結局には憲法の定める健康で文化的な最低限度の生活を維持するにたりるものでなければならない。しかし、健康で文化的な最低限度の生活なるものは、抽象的な相対的概念であり、その具体的内容は、文化の発達の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定的要素を総合考慮して初めて決定できるものである。したがって、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、いちおう、厚生大臣の合目的的な裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない。ただ、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬがれない。
原判決は、保護基準設定行為を行政処分たるかは、厚生大臣の羈束裁量行為であると解し、なにが健康で文化的な最低限度の生活であるかは、厚生大臣の専門技術的裁量に委されていると判示し、その判断の誤りは、法の趣旨・目的を逸脱しないかぎり、当不当の問題にすぎないものであるとした。羈束裁量行為といっても行政庁に全然裁量の余地が認められていないわけではないので、原判決が保護基準設定行為を羈束裁量行為と解しながら、そこに厚生大臣の専門技術的裁量の余地を認めたこと自体は、理由齟齬の違法をおかしたものではない。また、原判決が本件生活保護基準の適否を判断するにあたって考慮したいわゆる生活外的要素というのは、当時の国民所得ないしその反応である国の財政状態、国民の一般的生活水準、都市と農村における生活の格差、低所得者の生活程度とこの層に属する者の全人口において占める割合、生活保護を受けている者の生活が保護を受けていない多数貧困者の事情である。以上のような諸要素を考慮することは、保護基準の設定について厚生大臣の裁量のうちに属することであって、その判断については、法の趣旨・目的を逸脱しないかぎり、当不当の問題を生ずるにすぎないのであって、違法の問題を生ずることはない。」
(ポイント)
① 生活保護法の規定に基づき被保護者が国から生活保護を受けることを内容とする生活保護受給権は、当該個人に与えられた一身専属の権利であるため、相続の対象となり得ず、生活保護処分に関する裁決の取消訴訟は、被保険者の死亡により当然終了する。
② 何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられており、保護基準の設定に関する判断につては、法の趣旨・目的を逸脱しない限り当不当の問題が生ずるにすぎず、違法の問題は生じない。
31.公務員の懲戒処分と裁量権の範囲(最判昭52.12.20)
(事案)
神戸税関職員のXら(3名)は、同僚職員に対する懲戒処分についての抗議行動や各種の組合活動において指導的役割を果たして業務の処理を妨げたとして、国家公務員法(以下、国公法という。)に定める争議行為の禁止や職務専念義務および人事院規制に定める勤務時間中の総合活動の禁止に違反することを理由に、国公法82条に基づく懲戒免職処分を受けた。
そこで、Xらは、本件処分の無効確認ないし取消しを求めて出訴した。
(争点)
公務員に対する懲戒処分の適否について、裁判所の審査はどこまで及ぶか。
(判旨)
「公務員に対する懲戒処分は、当該公務員に職務上の義務違反、その他、単なる労使関係の見地においてではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することをその本質的な内容とする勤務関係の見地において、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認し、公務員関係の秩序を維持するため、科される制裁である。ところで、国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者がすべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択するべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかと決するについては、厚生であるべきこと(74条1項)を定め、平等取り扱いの原則(27条)及び不利益取扱いの禁止(98条3項)に違反してはならないことを定めている以外に、具体的基準を設けていない。したがって、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等・諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかふどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分にすべきか、を決定することができるものと考えられるのであるが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平磯から町内の事情に通暁し、都下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるものでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。もとより、右の裁量は、懇意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがって、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場にたって懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分と比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」 裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてなされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分をすべきであったかどうか、または、いかなる処分をせんたくすべきであったかについて判断し、その結果と実際になされた処分とを比較してその軽重を論じるべきではなく、それが社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合にのみ違法と判断すべきである。
●自由裁量行為の主な具体例(判例)
① 外国人の在留許可の更新
② 国公立大学の学生の処
③ 生活保護基準の設定
④公務員の懲戒処分
32 .個人タクシー事件(最判昭46.10.28)
(事案)
Xは、新規の個人タクシー営業免許を陸運局長(Y)に申請し、道路運送法(⑨)122条の2に基づく聴聞を受けたが、同法6条1項3号ないし5号の要件を満たさないとして、当該申請の却下処分を受けた。これに対し、Xは、陸運局長はあらかじめ審査基準を定めてその内容を申請人に告知することにより申請人に主張と証拠提出の機会与えるべきであるにもかかわらず、それがなされないままXの申請を却下したのは、職業選択の自由に関わるXの法的利益を侵害するものであり違法であると主張して、当該却下処分の取消しを求めて提訴した。
(争点)
個人タクシー事業の免許申請に対する審査として、いかなる手続公正ながものといえるか。
(判旨)
「聴聞担当官のうち前記基準の協議に関与した7,8名の係長以外のものは、被上告人の担当官を含め、前記基準事項の存在すら知らず、聴聞開始前に上司から聴聞書の項目および聴聞内容について証明をうけただけで、右基準事項については何らこれを知らされることなく、被上告人の聴聞担当官にあっても、被上告人の申請の却下事由となった他業関係(転業の難易)および運転歴(軍隊における運転経験を含む)に関しても格別の支持はなされず、したがって、右担当官は、被上告人が洋品店を廃業してタクシー業に専念する意思があるかどうか、軍隊における運転経験があるかどうか等の点について思いいたらず、これらの点を判断するについて必要な事実については何聴聞が行われなかった、というものである。
おもうに、道路運送法においては、個人タクシー事業の免許申請の諾否を決する手続について、同法122条の2の聴聞の規定のほか、審査、判定の手続、方法等に関する明文規定は存しえない。しかし、同法のよる個人タクシー事業の免許の諾否は個人の職業選択の自由にかかわりを有するものであり、このことと同法6条および前記122条の2の規定等とを併せて考えれば、本件におけるように、多数の者のうちから少数特定の者を、具体的個別的事実関係に基づき選択して免許の諾否を決しようとする行政庁としては、事実の認定につき行政庁の独断を疑うことが客観的にもっともと認められるような不公正な手続をとってはならないものと解せられる。すなわち、右6条は抽象的な免許基準を定めているにすぎないのであるから、内部的にせよ、さらに、その趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に適用すべく、とくに、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するようなものである等の場合には、右基準を適用するうえで必要とされる事項について、申請人に対し、その主張と証拠の提出の機会を与えなければならないというべきである。免許の申請人はこのような公正な手続によって免許の諾否につき判定を受くべき法的利益を有するものと解すべく、これに反する審査手続によって免許の申請の却下処分がされたときは、右利益を侵害するものとして、右処分の違法事由となるものというべきである。」
(ポイント)
道路運送法に定める個人タクシー事業免許にあたり、多数の申請人のうちから少数特定の者を選択するときは、同法の趣旨に沿う具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべきで、そのために適切な方法により申請人に対して主張と証拠提出の機会を与えることが必要であり、これに反する審査手続に基づく申請の却下処分は違法となる。
33.群馬中央バス事件(最判昭50.5.29)
(事案)
X会社は、運輸大臣(Y)に対して定期バス路線の延長を目的として道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の免許を申請したので、Yは、東京陸運局長に道路運送法(旧)122条の2に基づく聴聞を行わせた後、運輸審議会に諮問した。これを受けて、同審議会は、運輸省設置法16条に基づく公聴会を開催した後、利害関係人等の意見を聴取した上で、Yに対して本件申請を却下することが適当である旨を答申した。そこで、Yは、本件申請が道路交通法6条1項1号および5号に適合しないことを理由に却下し、その旨をX会社に通知した。
これに対して、X会社は、本件申請に対する審理は、陸運局長による簡単な聴聞がおこなわれただけで、現地調査その他十分な資料収集がされておらず、また、運輸審議会の審理手続において、独立公正な立場による独断のおそれのない手続によってなされたものではないことを主張して、本件却下処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
① 諮問を経て行政処分がされるべき場合における当該諮問機関の真理・決定(答申)の過程における違法性は、行政処分自体の違法性にいかなる影響を与えるか。
② 一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関して諮問を受けた運輸審議会が開催した公聴会の審理手続に瑕疵があった場合、この諮問を経てされた運輸大臣の免許許否処分は取消しの対象となるか。
(判旨)
「法は、運輸大臣が運輸審議会の決定を尊重すべきことを要求するにとどまり、その決定が運輸大臣を拘束するものとしていないから、運輸審議会は、ひっきょう、運輸大臣の諮問機関としての地位と権限を有するにすぎないものというべきであるが、しかしこのことはm運輸審議会の決定が全体として免許の許否の決定過程において有する意義と重要性、したがってまた、運輸審議会の審理手続のもつ意義と重要性を軽視すべき理由となるものではない。一般に、行政庁が行政処分をするにあたって、諮問機関に諮問し、その決定を尊重して処分をしなければならない旨を法が定めているのは、処分行政庁が、諮問機関の決定(答申)を慎重に検討し、これに十分な考慮を払い、特段の合理的な知友のないかぎりこれに反する処分をしないように要求することにより、当該行政処分客観的な適正妥当と公正を担保することを法が所期しているためであると考えられるから、かかる場合における諮問機関に対する諮問の理由は、極めて重大な意義を有するものとおいうべく、したがって、行政処分が諮問を経ないでなされた場合はもちろん、これを経た場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどにより、その決定(答申)自体に法が右諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、これを経てなされた処分も違法として取消をまぬがれないこととなるものと解するのが相当である。そして、この理は、運輸大臣による一般乗合旅客自動車運送事業の免許の許否についての運輸審議会への諮問の場合にも、当然に妥当するものといわなければならない。
ところで、一般乗合旅客自動車運送事業の免許の申請があった場合には、運輸大臣は原則として運輸審議会に諮問すべく、これを受けた運輸審議会は原則として公聴会を開いて審理したうえ決定をしなければならないことは、右に述べたとおりであるが、右の運輸審議会における審理及びこれに基づく決定の手続については、運輸省設置法及び運輸審議会一般規則にかなり詳細な定めが置かれている。しかし、これらの手続規定がいかなる趣旨、目的を有するものであり、したがってその手続の運用についていかなる配慮を施すべきものであるかは、これらの規定自体からはなく、専ら審理手続の意義と性格に照らしてこれを決すべきものであるところ、公聴会の審理を要求する趣旨が、前記のとおり、免許の許否に関する運輸審議会の客観性のある適正かつ公正な決定(答申)を保障するにあることにかんがみると、法は、運輸審議会の公聴会における審理を単なる資料の収集及び調査の一形式として定めたにとどまり、右規定に定められた形式を踏みさえすれば、その審理の具体的方法及び内容のいかんを問わず、これに基づく決定(答申)を適法なものとする趣旨であるとすることはできないのであって、これらの手続規定のもとにおける公聴会審理の方法及び内容自体が、実質的に前記のような要請を満たすようなものでなければならず、かつ、決定(答申)が、このような審理の結果に基づいてなされなければならないいと解するのが相当である。
右の見地に立って本件を見るに、上告人をして進んでこれらの点についての補充資料や釈明ないし反駁を提出させるための特段の措置はとられておらず、この点において、本件公聴会審理が上告人に主張立証の機械を与えるにつき必ずしも十分でないところがあったことは、これを否定することができない。しかしながら十分でないところがあったことは、これを否定することができない。しかしながら、仮に運輸審議会が、公聴会審理においてより具体的に上告人の申請系アックの問題点を指摘し、この点に関する意見及び資料の提出を促したとしても、上告人において、運輸審議会の認定判断を左右するに足る意見及び資料を追加提出しうる可能性があったと認め難いのである。してみると、右のような事情のもとにおいて、本件免許申請についての運輸審議会の審理手続における上記のごとき不備は、結局において、前記公聴会審理を要求する法の趣旨に違背する重大な違法とするには足りず、右審理の結果に基づく運輸審議会の決定(答申)自体に瑕疵があるということはできないから、右諮問を経てなされた運輸大臣の本件処分を違法として取り消す理由とはならないものといわなければならない。
(ポイント)
{C}① 諮問機関の新鋭・決定(答申)の過程に重大な法規違反があることにより、その決定自体に法が諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められる瑕疵があるときは、それに基づいてなされた行政処分は違法として取消しをまぬがれない。
{C}② 一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関して諮問を受けた運輸審議会が開催した公聴会の審理手続で、申請計画の問題点につき申請者に主張・立証の機会を十分に与えなかった瑕疵がある場合でも、申請者が運輸審議会の認定判断を左右するに足りる資料。意見を提出し得る可能性があったと認め難い事情があるときは、諮問を経てされた大臣の免許拒否処分を取り消す自由とならない。
34.伊方原発訴訟(最判平4.10.29)
(事案)
A会社(四国電力株式会社)は、Y(内閣総理大臣)に対して「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)」23条の基づき、伊方発電所原子炉設置許可申請をし、Yがこれを許可した。そこで、Xら(愛媛県西宇和郡内に居住する33名)は、当該原子炉が設置されることにより生命・身体・財産等が侵害される危険が生じるとして、当該原子炉の安全性の審査に際して手続法上および実体法上の違法があることを理由に、当該原子炉の設置許可処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
原子炉設置許可処分の取消訴訟における審理・判断の方法をいかに解すべきか。
(判旨)
「右の技術的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は、当該原子炉施設そのものの工学的安全性、平常運転時における従業員、周辺住民及び周辺環境への放射線の影響、事故時における周辺地域への影響等を、原子炉設置予定地の地形、地質、気象等の自然的条件、人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の右技術的能力との関連において、多角的、総合的見地から検討するものであり、しかも、右審査の対象には、将来の予測に係る事項も
含まれているのであって、右審査においては、原子力工学はもとより、多方面にわたる極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるものであることが明らかである。そして、規制法24条2項が、内閣総理大臣は、原子炉設置の許可をする場合においては、同条1条3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び4号所定の基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見を聴き、これを尊重してしなければならないと定めているのは、右のような原子炉施設の安全性に関する審査の特質を考慮し、右各号所定の基準の適合性については、各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる趣旨にゆだねる趣旨と解するのが相当である。
以上の点を考慮すると、右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって現在の科学的技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
原子炉設置許可処分についての右取消訴訟においては、右処分が前期のような性質を有することにかんがみると、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることの主張、立証資料は、本来、原告が負うべきものと解されるが、当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側がほじしていることなどの点を考慮すると、被告行政庁の側において、まず、その依頼した前記の具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認されるものというべきである。」
(ポイント)
裁判所の審理・判断は、原子力委員会や原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議・判断をもとにしてなされた行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきで、現在の科学的水準に照らし、調査審議で用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、調査審議・判断の過程に看過し難い過誤・欠落があり、行政庁の判断がこれに依頼してされたと認められる場合には、当該判断には不合理な点があるとして、原子炉設置許可処分は違法となる。
35.第三次家永教科書検定訴訟
(事案)
日本史の研究者であるXが執筆した高校用教科書「新日本史」は、昭和28年以来検定済教科書として使用されてきたが、昭和53年の学習指導要領の改正に伴う全面改訂をした上で昭和55年9月に文部大臣(現文部科学大臣)に対して新規検定の申請をしたところ、教科用図書検定調査審議会は420か所にわたる修正意見・改善意見を付した上で、当該修正意見個所の修正を条件とする条件付合格を決定した。これに対し、Xは、改善意見については拒否理由書を提出して修正に応じないでいたが、修正意見についてはこれに従い修正したため本件教科書は合格となった。
そこで、Xは、文部大臣が昭和55年度に申請された本件教科書の原稿本の記述に対して修正意見および改善意見を付したこと、昭和58年度に申請された改訂検定の際に改訂原稿の記述に修正意見を付したこと、ならびに昭和57年に提出された正誤訂正申請を受理しなかったことにより精神的苦痛を受けたとして、国(Y)を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
① 文部大臣が行う高等学校の教科用図書の検定は、どのような場合に国家賠償法上の違法となるか。
② 教科用図書の検定にあたって文部大臣が改善意見・修正意見を付すことは、国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使にあたるか。
(判旨)
「文部大臣が検定審議会の答申に基づいて行う合否の判定、合格の判定に付する条件の有無及び内容物の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、中立、公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童生徒の心身の発達段階に適応しているか、などの様々な観点から多角的に行われるもので、学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣の合理的な裁量にゆだねられているものであるが、合否の判定、合格の判定に付する条件の有無及び内容等についての検定審議会の判断の過程に、原稿の記載内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況、教育状況についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となると解するのが相当である。そして、検定意見は、原稿の個々の記述に対して旧検定基準の各必要条件ごとに具体的理由を付して欠陥を指摘するものであるから、各検定意見ごとに、その根拠となるべき学説状況や教育状況等も異なるものである。例えば、正確性に関する検定意見は、申請図書の記述の学問的な正確性を問題にするものであって、検定当時の学会における客観的な学説状況を根拠とすべきものであるが、検定意見には、その実質において、原稿記述が誤りであるとして他説による記述を求めるものや、原稿記述が一面的、断定的であるとして両説併記を求めるものなどがある。そして、検定意見に看過し難い過誤があるか否かについては、右の場合は、検定意見の根拠となる学説が通説、定説として学界に広く受け入れられており、原稿記述が誤りと評価し得るかなどの観点から、右の場合は、学説においていまだ定説とされる学説がなく、原稿記述が一面的であると評価し得るかなどの観点から判断すべきである。また、内容の選択や内容の程度等に関する検定意見は、原稿記述の学問的な正確性ではなく、教育的な相当性を問題とするものであって、取り上げた内容が学習指導要領に規定する教科の目標等や児童、生徒の心身の発達段階等に照らして不適切であると評価し得るかなどの観点から判断すべきものである(前掲平成5年3月16日第三小法廷判決参照)。
ところで、原審の確定したところによると、本件検定当時のI教科用図書検定審査内規(昭和53年6月15日教科用図書検定調査審議会決定)は、検定審議会は原稿本を合格と判定した場合、これに訂正、削除または追加などの措置をしなければ教科書として不適切であると認められるこきは、これを修正意見として指摘し、必要な修正を加えることを合格の条件とすること、修正意見として指摘するには至らないが、訂正、削除または追加などの措置をした方が教科書としより良くなると認められるときは、これを改善意見として指摘することを定めており、これに従った運用がされていたことが認められる。そうすると、修正意見を付することは、申請者がこれに応じて訂正、削除または追加などの措置をしなければ教科書として不合格となるというものであるから、合格に条件を付するものであり、これが国家賠償法上違法となるかどうかについては前記のような判断を要する。これに対して、改善意見は、検定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有するものと考えられるから、教科書の執筆者又は出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情がない限り、その意見の当不当にかかわらず、原則として、違法の問題が生ずることはないというべきである。
原審認定の前記事実によると、七三一部隊に関しては、本件検定当時既に多数の文献、資料が公刊され、中には昭和43年に刊行された上告人の著作もあり、必ずしもすべてが本件検定の直前に公刊されたわけではないことが明らかである。そして、原審が、本件検定当時、七三一部隊の存在等を否定する見解があったことを認定していないことに照らせば、本件検定当時、これを否定する学説は存在しなかったか、少なくとも一般には知られていなかったものとみられる。そうすると、本件検定当時において、七三一部隊の実態を明らかにした公刊物の中には、作家やジャーナリストといった専門の歴史研究家以外のものが多く含まれており、また、七三一部隊の全容が必ずしも解明されていたとはいえない面があるにしても、関東軍の中に細菌戦を行うことをも目的とした『七三一部隊』と称する軍隊が存在し、生体実験をして多数の中国人等を殺害したとの大筋は、既に本件検定当時の学界において否定するものはないほどに定説化していたというべきであり、これに本件検定時までには終戦から既に38年も経過していることをも併せ考えれば、文部大臣が、七三一部隊に関する事柄を教科書に記述することは時期向早として、原稿記述を全部削除する必要がある旨の修正意見を付したことは、その判断の過程に、検定当時の学説状況の認識及び旧検定基準に違反するとの評価に看過し難い過誤があり、裁量権の範囲を逸脱した違法があるというべきである。」
(ポイント)
① 合否の判定時についての教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、原稿の記述内容についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、当該判断は、裁量権の範囲を逸脱して、国家賠償法上違法となる。
② 文部大臣の改善意見は、これに応ずることを合格の条件としておらず、助言・指導の性質を有するものにすぎないから、教科書の執筆者がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情がない限り、違法の問題は生じない。
36.行政行為の効力の発生時期(最判昭29.8.24)
(事案)
京都地方検察庁に勤務する検事Aは、昭和23年12月14日に衆議院議員総選挙に立候補するため辞職を願い出たため、同月24日付けで免官の発令がなされ、29日付けで官報で公示された。ただし、A自身が当該発令を了知したのは31日であった。
ところが、Aはその前に立候補を断念して辞表の撤回を申し出ており、その後も職務を継続したため、同月30日における本件刑事事件の公訴提起も担当した。その結果、当該事件の弁護人が、検察官の資格を有しない者による公訴提起は違法であり、判決で棄却するべき旨を主張した。
(争点)
公務員の任免に関する行政行為の効果の発生時期と官報による工事との関係をいかに解すべきか。
(判旨)
「そこで右胃がん免官による退職の効果の発生時期について考えてみると、特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時とするのが相当である。即ち、辞令書の交付その他公の通知によって、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知し得べき状態におかれた時と解すべきである(原判決がこの点について、退職令書の交付時に限ったことは妥当であい)。論旨は免官の発令が官報に掲載された日に退職の効果を生ずるものと主張すえうけれども、公務員の任免は法令の公布とは自らその性質を異にするばかりであく、官報による公示は特定の相手方に対する意思表示とは到底認めることができないのであって、所論は独自の見解に過ぎない。
ところで、原判決の確定したところによると、本件免官の発令は昭和23年12月24日附でなされ、同月29日附け官報にその旨を公示されたのであるけれども、A検事が免官の発令があったことを上司たる教徒地方の検察庁検事正から公に通知され、これを了知したのは昭和23年12月31日であり、更らに免官の辞令書の公布をうけたのは、それ以後のことであるというのであって、それ以前に免官の発令が同検事に到達したという事実は何ら認められていない。して見ると、本件につき公訴の提起があった同月30日には、同検事に対しては免官発令による退職の効果も未だ生じていなかったものと認めざるを得ない。従って同月30日A検事によってなされた本件公訴の提起は違法であって、これを無効とすべき理由はない。それ故所論旧刑訴410条6号違反並びに憲法31条違反の主張はその前提を欠き採用することができない。」
(ポイント)
特定の公務員の任免のような行政行為については、特別の規定がない限り、行政庁の意思表示が相手方に到達した時、すなわち辞令書の公布などにより相手方が現実にこれを了知し、または了知し得べき状態におかれた時にその効果が生ずる。法令の公布の場合のように官報により公示されたことによって効果が生ずるものではない。
37.内部的意思決定と異なる表示行為(最判昭29.9.28)
(事案)
Yは、その所有する農地をXに賃貸していたが、農地調整法9条3項に基づく賃貸借契約の解除の申入れについての許可を求める申請書を、昭和22年9月1日付けで北海道知事に提出した。
しかし、当該申請については、許可し難いことに審議がまとまったにもかかわらず、指令書の浄書係のミスから、「右申請許可する」との知事名義の指令書が知事の決済を受けて作成され、昭和23年2月27日にYがこれを受領した。
そのため、Yは、Xに対して当該賃貸借契約の解除を通知するとともに、本件土地の立入禁止を求める仮処分を申請し、昭和24年月5月13日および18日に仮処分決定を得た。
これに対して、Xは、Yの申請を許可するという知事の法律的効果意思は存在しないのであるから、当該申請を許可する旨の行政行為は存在せず、要式的行政行為ではない本件においては、当該指令書の交付はいわゆる事実行為にすぎないとして、仮処分の取消しを裁判所に請求した。
(争点)
行政機関の内部的意思決定と相違する書面が作成され交付された場合においても、当該書面に表示されているとおりの行政行為が成立するか。
(判旨)
「被上告人は北海道知事に対し本件賃貸借契約の解約につき農地調整法9条3項による許可を申請し、昭和23年2月27日附け知事の許可指令書を受け取ったのであるが、これよりさき北海道庁においては右申請を許可し難いことに審議がまとまったにもかかわらず、知事の決済の求めるいわゆる原議の指令案の『本申請許可する』との文句を抹消しないまま知事の指令案の『本申請許可する』との文句を抹消しないまま知事の決済を受けたので、これに基づいて『本申請許可する』との知事名義の指令書が作成され、これを被上告人が受領したものであるというのである。論旨は、この場合被上告人の申請を許可するという北海道知事の法律的効果意思は存在しないのであるから、許可の行政行為は存在せず、要式的行政行為でない本件においては指令書の交付は単に行政処分の行われた事実を通知するところの事実行為に過ぎないものであると主張する。しかし行政行為は表示行為によって成立するものであって、行政機関の内部で確定したものであっても外部に表示しない間は意思表示ではあり得ない。そうして当該行政行為が要式行為であると否とを問わず書面によって表示されたときは書面の作成によって行政行為は成立し、その書面の到達によって行政行為の効力を生ずるものである。この場合表示行為が当該行政機関の内部的意思決定と相違していても表示行為が正当の権限である者によってなされたものである限り、」この事実は原審の認定したところである)該書面に表示されているとおりの行政行為があったものと認めなければならない。そうだとすれば、原判決が右指令書の表示に従って本件賃貸借解約の申請を許可するという行政行為があったものと判示したのは正当であって、これを許可しないという意思は未だ外部に表示されていないにもかかわらず、不許可の行政行為があったと主張し、又は許可の処分がなかったと主張する論旨は理由がない。」
(ポイント)
行政行為が行政機関の内部的意思決定と相違していても、当該表示行為が正当の権限である者によってなされている限り、要式行為であると否とを問わず、書面の作成によって当該書面に表示されているとおりの行政行為が成立し、その書面の相手方への到達によって効力を生じる。つまり、錯誤により行政行為は、有効となる。
民法上は、錯誤による法律行為は原則として無効となる(同法95条)ので、結論の違いに注意が必要である。
① 錯誤に基づく行為の効力(原則)
行政法・・・行政行為は→有効
民放・・・・法律行為は→無効
38.「明白な瑕疵」の意義(最判昭36.3.7)
(事案)
Aおよびその子Xは、Aの養子Bらとの間で山林等の所有権をめぐる紛争を抱えていたが、A側が当該山林等をBらに贈与する代わりにBらが800万円を支払うことで示談が成立し、その支払いのため、Bは当該山林にある立木を伐採・処分して示談金を支払った。しかし、山林所得税を免れるため、示談契約書800万円の金額を表示せず、立木の売買契約書にも登記名義人のAを売り主として表示した。そのため、税務署長YはAに対して山林所得金額および所得税額を決定・通知するとともに、無申告加算税を賦課した。
これに対して、当該処分直後にAを相続したXは、本件立木の売却により収入を得たのはBであってAではないため、Yによる処分には重大な瑕疵があり、しかも当該瑕疵が明白であるか否かは事実審の最終口頭弁論期日までに行われた証拠調べにより客観的に確定された事実から判断すべきであると主張して、Yによる処分が無効であることの確認を求めて提訴した。
(争点)
行政処分の瑕疵が明白であるか否かについては、いつの時点におけるどのような内容により決すべきか。
(判旨)
「行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵いというのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大・明白な瑕疵がある場合』を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例である(昭和34年9月22日第三小法廷判決)。右判例の趣旨からすれば、瑕疵が名曰はくであるというのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指すものとっ解すべきである。もとより、処分成立の初めから重大かつ明白な瑕疵があったかどうかということ自体は、原審の口頭弁論終結時までにあらわれた証拠資料により判断すべきものであるが、所論のように、重大かつ明白な瑕疵があるかどうかを口頭弁論終結時までに現れた証拠及びこれにより認められる事実を基礎として判断すべきものであるということはできない。また、瑕疵が明白であるかどうかは、処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうかにより決すべきものであって、行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかは、処分に外形上客観的に明白な瑕疵があるかどうかの判定に直接関係を有するものではなく、行政庁がその怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかにかかわらず、外形上、客観的に誤認が明白であると認められる場合には、明白な瑕疵があるというを妨げない。原審も、右と同旨の見解にでたものと解すべきであって、所論は、右に反する府独自の見解を前提とするものであり、すべて採用のかぎりでない。」
(ポイント)
行政処分の瑕疵の明白とは、処分庁の認定が誤認であることが、処分成立の当初から、外形上客観的に一見看取し得るものであったかそうかにより決すべきである。
つまり、「パッと見、明らか」か否かで!
39.課税処分と当然無効(最判昭48.4.26)
(事案)
Aは、自らが経営する会社の債権者による差押えを免れるため、自己所有の不動産を義妹夫婦であるXら名義にすることをXらに無断で行ったが、その後、借金の返済にあてるため、Xら名義の売買契約書等を偽造して当該不動産を第三者に売却した。そこで、税務署長Yは、Xらに当該不動産についての譲渡所得があったと認定して課税処分を行い、これに応じないXらに滞納処分を行った。
これに対して、Xらは、本件課税処分についての異議申し立てを行ったが、申立期間の徒過により不可争力が生じていることを理由に却下されたため、Xらは無効確認訴訟を提起した。しかし、第一審・第二審ともに、本件課税処分に重大な瑕疵があることは認めたが、明白な瑕疵ではないため無効とはいえないとして、Xらの請求を棄却した。
(争点)
行政処分が無効である旨を主張するためには、当該処分に存する瑕疵重大性が明白であることが、常に必要とされるか。
(判旨)
「一般に、課税処分が課税庁と非課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税処分の根幹についてのそれであって、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を当然無効とならしめるものと解するのが相当である。
本件は、課税処分に対する通常の救済制度につき定められた不服申立期間の徒過による不可争的効果を理由として、なんら責むべき事情のない上告人らに前記処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情のある場合に該当し、前記の過誤による瑕疵は、本件課税処分を当然無効ならしめる。」
(ポイント)
課税処分が課税庁と被課税者との間のみのもので、処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないことから、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹に関わるものであって著しく不当と認められる例外的事情がある場合には、それだけで当該処分は当然無効となる。
つまり、例外として、重大性だけで(明白でなくても)無効となる。
40.瑕疵の治癒が認められた例(最判昭36.7.14)
尼崎地区農地委員会は、X所有の池沼を自作農創設特別措置法15条1項1号が規定する「農地の利用上必要な農業用施設」として買収するための買収計画を定めたが、Xは、これを不服として、兵庫県農地委員会に訴願を提起した。そのため、同法15条2項が準用する8条、9条に従い、当該訴願に対する裁決がなされるまでは買収計画をていしすべきところ、県農地委員会は、裁決をする前に、棄却裁決を得致死条件とする本件買収計画の承認を行い、これを受けて、兵庫県知事は買収令書をXに交付して本件池沼を買収した。そして、その10日後に、Xの訴願を棄却する旨の裁決がなされたが、Xは、当該棄却裁決に先立ってなされた買収処分は違法であること等を理由に、国(Y)を被告として、本件池沼の所有権に関する訴訟を提起した。
(争点)
農地買収計画についての訴願が提起されたにもかかわらず、その採決を経ないまま進行させた手続は有効といえるか。
(判旨)
「農地買収計画につき意義・訴願の提起があるにもかかわらず、これに対する決定・裁決を経ないで爾後の手続を進行させたという違法は、買収処分の無効原因となるものではなく、事後において決定・裁決があったときは、これにより買収処分の瑕疵は治癒されるものと解するのを相当とする(昭和34年9月22日第三小法廷判決参照)。
本件についてこれをみるのに、原審の確定した事実によれば、兵庫県農地委員会が本件買収計画を承認し、また兵庫県知事が被上告人に対する買収令書を発行した当時は、まだ同委員会による本件買収計画についての訴願裁決がなされていなかったとはいえ、右承認は訴願棄却の裁決があることを停止条件としてなされたものであり、訴願棄却の裁決もその穂行われたというのであるから、訴願棄却の裁決がなされる前に承認その他の買収手続をしいんこうさせてという瑕疵は、その後訴願棄却の裁決がなされたことによって治癒された、と解すべきである。」
(ポイント)
農地買収計画に対する訴願の提起があったにもかかわらず、その裁決を経ないまま都道府県のうち委員会訴願棄却裁決があることを停止条件として買収計画を承認し、それに基づき都道府県知事が土地所有者に買収令書を発行したという瑕疵は、その後に当該訴願に対する棄却裁決があったことにより治癒される。
→瑕疵の治癒を認めた判例である。
●瑕疵の治癒
行政行為に存在した瑕疵が、その後の事情により、実質的に違法要件を具備した結果、
違法行為を適法扱いすることをいう。
41.瑕疵の治癒が認められなかった例(最判昭48.4.26)
(事案)
清算手続中の法人Xが、事業年度所得ならびに清算所得についての法人税につき確定申告をしたところ、税務署長Yから増額厚生処分を受けたが、その更生通知書には、理由として加算項目についての金額が記載されているにすぎなかった。
そこで、これを不服とするXがA国税局長に審査請求をしたところ、同局長は、更正処分の一部を取り消した上で、その余の部分を維持すべき詳細な理由を裁決書に記載した。
しかし、Xは、本件更正処分の実態的違法性を主張するとともに、更正処分における理由付記を義務付けた法人税法旧38条にも違反する旨を主張して、本件更正処分の取消しを求めて出訴した。
(争点)
更正処分に対する審査請求において、裁決庁により詳細な理由が示された場合には、付記理由不備の違法性は治癒されるか。
(判旨)
「そこで、本件更正の附記理由をみるのに、その更生通知書の理由書に、係争事業年度所得の加算項目として、①営業譲渡補償金計上もれ1155万円、②認定利息(代表者)計上もれ1万9839円、清算所得の加算項目として、③残余財産価格の通算分4000円、④営業譲渡補償金905万円と記載されていることは、原判決の適法に確定するところである。所論は、右各項目のうち①⑤の記載は、『被上告会社は訴外日興証券株式会社に営業を譲渡した対価として250万円を清算所得に計上していたが、被上告会社代表者Aが右訴外会社から受領した借入金300万円、嘱託料290万円、手数料315万円、計905万円も右営業譲渡の対価であるのにこれが脱漏しており、営業譲渡の対価の総額は1155万円と評価されるので、これを加算すること』および『905万円は営業譲渡の対価の債券であること』を端的に要約したものであり、また、②④の記載は、『被上告会社の前記Aに対する仮払金と立替金についての認定利息が1万9839円であること』を端的に明らかにしたものであると主張する。しかし、③を除く前記格加算項目の記載から、右主張のごとき更正理由を理解することはとうてい不可能であり、その記載をもってしては、更正にかかる金額がいかにしてさんしゅつされたのか、それがなにゆえに被上告会社の課税所得とされるのか等の具体的根拠を知るに由ないものといわざるをえない。
してみると、処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分理由を相手方に知らせて不服申立の便宜を与えることを目的として更正に附記理由の記載を命じた前記法人税法の規定の趣旨にかんがみ、本件更正の附記理由には、不備の違法があるものというべきである。
しかし、更正に理由附記を命じた規定の趣旨が禅師のとおりであることに徴して考えるならば、処分庁と異なる機関の行為により附記理由不備の瑕疵が治癒されるとすることは、
処分そのものの慎重、合理性を確保する目的にそわないばかりでなく、処分の相手方としても、審査裁決によってはじめて具体的な処分根拠を知らされたのでは、それ以前の審査手続において十分な不服理由を主張することができないという不利益を免れない。そして、更正が附記理由不備のゆえに訴訟で取り消されるときは、更正期間の制限によりあらたな更正をする余地のないことがあるなど処分の相手方の利害に影響を及ぼすのであるから、審査裁決に理由が附記されたからといって、更正を取り消すことが所論のように無意味かつ不必要なこととなるものではない。
それゆえ、更正における附記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではないと解すべきである。」
(ポイント)
更正処分における理由付記の不備の瑕疵は、当該処分に対する審査請求についての裁決において処分理由が詳細に示された場合でも、治癒されない。
→瑕疵の治癒を認めなかった判例である。
42.違法行為の転換が認められなかった例(最判昭29.7.19)
(事案)
赤坂村農地委員会は、X所有の農地につき、小作人の請求がないのにかかわらず、これがあったものとして自作農創設特別措置法3条1項・附則2項ならべに同法施行令43条に基づき買取計画を求めた。そこで、Xは、広島県農地委員会(Y)に対して訴願を行ったが、Yは小作人の請求がないことを確認しながらも、農村地委員会の買収計画の手続的違法を是正することなく、同法施行令45条に基づき棄却裁決の取消しを求めて出訴した。
(争点)
自作農創設特別措置法施行令43条によって定められた農地買収計画を、訴願に対する採決によって、同令45条によるものとして維持することが認められるか。
(判旨)
「原判決は、『赤坂村農地委員会が、本件農地について小作人の請求がないのに拘らずその請求があったものとして改正前の地先農創設特別措置法附則2項、同法施行令43条により昭和20年11月23日現在の事実に基づいて買収計画を定めたこと、並びに、被控訴(被上告)委員会が同令45条を適用して本件買収を相当と認め控訴人(上告人)の訴願を容れない旨の裁決をしたものであること』を認定した上、『右のような事実関係においては、本件農地については右附則2項、同令43条の規定を適用すべきものではなく、従って、赤坂村農地委員会が、同法条により買収計画を定めた手続は違法であるから、被控訴委員会はこの点を是正して裁決すべきであったに拘らず、この点を釈明させない漫然改正前の同法施行令45条を適用して裁決したことは妥当でない』と判断しながら、しかも、行政事件特例法11条を適用して控訴人(上告人)の主張を排斤したことは所論のとおりである、しかし、改正前の自作農創設特別措置法附則2項によれば、3条1項の規定による農地の買収については、市町村農地委員会は相当と認めるときは、『命令』の定めるところにより、昭和20年11月23日現在における事実に基いて6条の規定による農地買収計画を定めることができるものである。そして、右『命令』である同法施行令43条は、右期日現在における小作農が農地買収計画を定めるべきことを請求したときは、市町村農地委員会は、当該小作地につき附則2項の規定により現在の事実に基いて農地買収計画を定めることの可否につき審議しなければならないと規定しているだけであるから、同令43条による場合と同令45条による場合とによって、市町村農地委員会が買収計画を相当と認める理由を異にするものとは認められない。従って原判決が同法43条により定めたと認定した赤坂村農地委員会の本件買収計画を被上告委員会が同令45条を適用して相当と認め上告人の訴願を容れない旨の裁決をしたことは違法であるとはいえない。されば、上告人の主張を排斤した原判決は、前記理由に依れば失当であるけれども、右の理由により結局正当に帰すから、論旨は採用できない。」
(ポイント)
行政行為とみればその法廷要件がする訴願についての裁決において、同令45条を適用することにより
相当なものとして維持することは違法ではない。
→違法行為の転換を認めた判例である。
●違法行為の転換
行政庁の意図した行政行為としては要件を満たさない違法であるが、他種の行政行為とみればその法廷要件が満たされており適法と考えられる場合に、その効力を維持する取扱いをいう。
43.事実上の公務員の理論(最大判昭35.12.7)
(事案)
奈良県内の村の村長であったXは、同村選挙管理委員会の名で行われた村長解職賛否投票の結果、過半数の同意があったものとして解職された。その結果、後任の村長が選出され、当該村長の関与につり、a村は奈良市に吸収合併された。これに対し、Xは、Xについての解職請求手続を管理執行した同村選挙管理委員会の構成が適法でないことを主張して、奈良県選挙管理委員会(Y)に訴願を行ったが、これが棄却されたため、当該棄却裁決の取消と解職賛否投票の無効確認を求めて出訴した。
(争点)
① 村が吸収合併により消滅した後において、村長解職賛否投票の無効確認を求めることについて、訴えの利益は認められるか。
② もし当該賛否投票の効力が失われた場合には、当該投票が有効であることを前提になされた後任の尊重による行政処分も無効となるか。
(判旨)
「上告人が村長であったa村は、本訴提起後の昭和32年8月27日、奈良県知事が関係自治団体の申請に基づいて同村を奈良市に吸収合併する旨決定し、同月30日内閣総理大臣からその旨告示されたことは、原判決の確定するところであるから、右市町村合併は地方自治法7条7項により右告示によって効力を生じ、a村は同日をもって廃止されたものである。
そして、本訴は前示委員会の裁決の取消、ならびに賛否投票の無効の宣言を求め、これによって上告人の村長たる地位を回復することを目的とする訴訟と解すべきであるから、a村が前記のごとく廃止され、たとえ上告人が本訴にいおいて勝訴して、右賛否投票の無効が宣言されても、既にその回復すべき地位の存在しないこととなった現在においては、かかる訴訟は訴訟の利益がなくなったものとして許すことのできないものであることは当裁判所の判例の趣旨に徴してあきらかである。(昭和35年3月9日大法廷判決参照)。
上告人は、本訴において賛否投票の無効が宣言されるときは、右判決の効力は既往に遡及し、後任村長が関与したa村の奈良市への合併の効力にも影響を及ぼす旨主張するけれども、たとえ賛否投票の効力が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提として、それまでの間になされた後任村長の行政処分は無効となるものではないと解すべきであるから、右上告人の主張は採用することができない。」
(ポイント)
① 村が吸収合併により消滅した以後は、村長解職賛否投票の効力に関する訴えの利益はなくなる。
② たとえ当該賛否投票の無効が宣言されても、当該投票が有効であることを前提としいてそれまでになされた後任の村長による行政処分は無効とならない。
→事実上の公務員の理論に言及した判例である。
●事実上の公務員の理論
公務員の欠格事由に該当する者が公務員に任命された場合などにおいて、その者が行った行為は原則として無効となるはずであるが、相手方の信頼を保護するために有効なものとして扱うことをいう。
44.旅券発給拒否における理由付記(最判昭60.1.22)
(事案)
Xが昭和52年1月8日に外務大臣(Y)に対し渡航先をサウディ・アラビアとする一般旅券の発給を申請したところ、Yは、同年2月16日付の書面に、「旅券法13条1項5号に該当する。」との理由を付して、当該申請に係る一般旅券を発給しない旨をXに通知した。
このため、Xは、Yに対して異議申立てを行ったが棄却されたため、Yを被告とする本件拒否処分の取消訴訟等を提起した。
(争点)
一般旅券発給拒否処分の通知書に、「旅券法13条1項5号に該当する。」とのみ理由に記載した本件拒否処分には、理由付記の不備による違法性があるのではないか。
(判旨)
「旅券法14条は、外務大臣が、同法13条の規定に基づき一般旅券の発給をしないと決定したときは、すみやかに、理由を付した書面をもって一般旅券の発給を申請した者にその旨を通知しなければならないことを規定している。い一般に、法律が行政処分に理由を付記すべきものとしている場合に、どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである(最高裁昭和38年5月31日第二小法廷判決)。旅券法が右のように一般旅券発給拒否通知書に拒否の理由を付記すべきものとしているのは、一般旅券の発給を拒否すれば、憲法22条2項で国民に保障された基本的人権である外国旅行の自由を制限することになるため、拒否事由の有無についての外務大臣の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、拒否の理由を申請者に知らせることによって、その不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものというべきであり、このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは、それによって当該既定の適用の基礎となった事実関係をも当然知りうるような場合を別として、旅券法の要求する理由付記として十分でないといわなければならない。この見地に立って旅券法13条1項5号をみるに、同号は、『前各号に掲げる者を除く外、外務大臣において、著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者』という概括的、抽象的な規定であるため、一般旅券発給拒否通知書に同号に該当する旨付記されただけでは、申請者において発給拒否の基因となった事実関係をその記載自体から知ることはできないといわざるをえない。したがって、外務大臣において旅券法13条1項5号の規定を根拠に一般旅券の発給を拒否する場合には、申請者に対する通知書に同号に該当すると付記するのみでは足りず、いかなる事実関係を認定して申請者が同号に該当すると判断したかを具体的に記載することを要すると解するのが相当である。そうであるとすれば、単に『旅券法13条1項5号に該当する。』と付記されているにすぎない本件一般旅券発給拒否処分の通知書は、同法14条の定める理由付記の要件を欠くものというほかはなく、本件一般旅券発給処分に右違法があることを理由としてその取消しを求める上告人の本訴請求は、正当として認容すべきである。」
(ポイント)
一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由は、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者がその記載自体から了知し得るものでなければならず、本件拒否処分の通知書には旅券法14条が定める理由付記の要件を欠く違法があり、当該処分は取り消されるべきである。
45.違法性の承継が認められた例(最判昭25.9.15)
(事案)
X所有の農地につき、桃園村農地委員会が自作農創設特別措置法2条1項1号に該当する農地として買収計画を立てるため、Xは、当該農地が同法5条6号に該当するものとして買収計画から除外されるべき旨を主張して同委員会に異議を申し立て、さらに、三重県農地委員会に訴願をしたが、いずれも却下された(当該却下裁決についえた、Xは取消訴訟を提起していない。)。そのため、本件買収計画については県農地委員会の承認が与えられ、これに基づき三重県知事(Y)は、買収令書をXに交付して買収処分を行った。
これに対し、Xは、あらためて買収計画の違法性を主張して当該計画に基づく買収計画の取消しを求めて出訴した。
(争点)
買収計画についての出訴期間が経過した後に、当該買収計画の違法性を主張してその後になされた買収処分の取消しを主張することはできるか。
(判旨)
「法第5条はその各号の一に該当する農地については買収しないと規定しているのであるからこれに該当する農地を買収計画にいれることの違法であることは勿論これが買収処分の違法であることは言うまでもないところである。従って右の如き違法は買収計画と買収処分に共通するものであるから買収計画に対し異議訴訟の途を開きその違法を攻撃し得るからといって買収処分取消の訴えにおいて、その違法を攻撃し得ないと解すべきではない。法大7条が買収計画に対して異議訴訟を認めているのはただその違法の場合に行政庁に是正の機会をお与え所有者の権利保護の簡便な途を開いただけであって異議訴訟等の手続をとらなかったからと言って買収処分取消の訴訟においてその違法を攻撃する機会を失わせる趣旨であるとはかいせられない。買収計画に対し異議申立や訴願をせず又は訴訟採決に対する出訴期間を徒過したときは当事者はもはや買収計画に対しその取消を請求する権利を失うのであるからその意味では確定的効力があるのであるがその確定的効力は買収計画内容に存する違法を違法なしと確定する効力があるものではない。買収の計画は買収手続の一段階をなす市町村農地委員会の処分にすぎないので更に都道府県農地委員会の承認及び都道府県知事の買収令書の交付を経て買収手続は完結するのである。しかして買収計画の確定的効力は前記の如くその内容に存する違法を違法なしと確定する効力がないのであるから都道府県農地委員会の買収計画承認の権限は買収計画の内容の適否を審査する権限を包含するものと解すべく更に都道府県知事は買収計画の内容の適否を審査する権限を包含するものと解すべく更に都道府県知事は買収計画又はその承認の決議に対してこれを再議に付して是正させる権限を有するのである。(農地調整法第15条ノ28)故に都道府県農地委員会や知事が右権限の適正な行使を誤った結果内容の違法な買収計画にもとずいて買収処分が行われたならばかかる買収処分が違法であることは言うまでもないところで当事者は買収計画に対する不服を申し立てる権利を失ったとしても更に買収処分取消の訴においてその違法を攻撃し得るものといわなければならない。」
(ポイント)
自作農創設特別措置法5条に違反した買収計画に基づいて買収処分が行われたときは、被買収者は、買収計画に対する出訴期間経過後であっても、買収処分取消の訴えの中で買収計画の違法性を主張することができる。→違法性の承継を認めた判例である。
●違法性の承継
数個の行政行為が連続して行われる場合に、先行行為に瑕疵があったときに、その
瑕疵が後行行為にも承継されることをいう。
違法行為が承継される場合には、後行行為に対する取消しの訴えにおいて、先行行
為の違法性を主張することができる。
46.不可変更力に反してなされた採決の効力(最判昭30.12.26)
Xは、Y所有の農地についての賃借権の存在を主張してYと争いになったが、水戸地方裁判所における調停の成立により、X主張の賃借権は消滅した。しかし、その後、Xによる賃借権回復の裁定申請に対して緑岡村農地委員会がこれを認める裁定をしたため、Yはい茨城県農地委員会に訴願を申し立てたたが、昭和24年12月23日付けで棄却裁決がなされた。ところが、Yの申出に基づき県農地委員会が再議した結果、Yの主張を相当と認め、昭和26年6月29日付をもって前記棄却裁決を取り消した上で、Yの訴願を容認する裁決を行った。
そこで、Xは、Yを被告として、本件農地についての耕作権の確認と引渡しを求めて出訴した。
(争点)
訴願に対する採決を裁決庁自らがその後に取り消した場合は、当該取消しの採決は当然に無効となるか、それとも取消原因となるにとどまるか。
(判旨)
「本件において、茨城県農地委員会は、被上告人が緑岡村農地委員会のした裁定を不服として申立てた訴願につき、昭和24年12月23日附で訴願棄却の裁決をしながら、さらに被上告人の申出によって再議の結果、昭和26年6月29日附をもって先に棄却した被上告人の訴願における主張を相当と認め、前記訴願棄却の裁決を取り消した上改めて訴願の趣旨を認容するとの裁決をしたことは、原判決の確定したところである。そして、訴願裁決庁が一旦なした訴願裁決を自ら取り消すことは、原則としてゆすされないものと解するべきであるから(昭和29年1月21日第一小法廷判決参照)茨城県農地委員会が被上告人の申出により現判示の事情の下に先になした裁決を取り消してさらに訴願の趣旨を容認する裁決をしたことは違法であるといわねばならない。しかしながら、行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するものと解すべきところ、茨城県農地委員会のなした前記訴願裁決取消の裁決は、いまだ取り消されないことは原判決の確定するところであって、しかもこれを当然無効のものと解することはできない。」
(ポイント)
訴願に対する裁決をした裁決庁が自ら当該採決を取り消すことは違法であるが、その違法は取消原因にとどまるものであって、後の裁決は当然に無効とならない。なぜなら、2度目の裁決も行政行為である以上、公定力を有するからである。
公定力とは、行政行為にたとえ瑕疵(重大かつ明白な瑕疵を除く)があっても、権限のある行政機関または裁判所が取り消すまでは、一応有効として扱われる効力をいう。
47.行政行為の撤回と損失補償(最判昭49.2.5)
(事案)
X社は、クラブ・レストラン・喫茶・料理等の事業を営むための建物所有を目的として、東京都(Y)が所有する中央卸売市場築地本場内の土地1044坪を、Yの使用許可を受け使用期間の定めなく借り受けていたが、実際にはその一部に建坪55坪の店舗1棟を建築したのみで、残りの部分は利用されないまま経過していた。そうするうちに卸売市場の混雑が進んできたことから、Yは960坪部分の使用指定を取り消す旨の通告をX社に対してなし、その上に存した前記建物につき、使用許可を取り消していない土地上に移転する行政代執行を行った。
これに対して、X社は、960坪部分ン位ついてなされた使用許可の取消しによって当該土地に関する使用権の喪失という積極的損害を受けており、これは憲法29条3項の特別の犠牲にあたるから、その補償がなされるべきであるにもかかわらず、これがなされていないことを理由に、Yを被告として本件土地の借地権の確認とそれに基づく土地の引渡しを求めて出訴した。
(争点)
行政財産たる土地についての使用許可の取消し(撤回)に当たっては、存実補償を要するか。
(判旨)
「本件取消を理由とする補償に関する法律および都条令についてみるに、本件取消がされた当時(昭和32年6月29日)の地方自治法および都条令にはこれに関する規定を見出すことができない。しかし、当時の国有財産法は、すでに、普通財産を貸し付けた場合における貸し付けた場合における貸付期間中の契約解除による損失補償の規定をもうけ(同法24条)、これを行政財産に準用していた(同法19条)ところ、国有であれ都有であれ、行政財産に差等はなく、公平の原則からしても国有財産法の右規定は都有行政財産の使用許可の場合にこれを類推適用すべきものと解するのが相当であって、これは憲法29条3項の趣旨にも合致するところである。そして、原判決の前記判示によれば、本件使用許可は期間を定めないものではあるが建物所有を目的とするというのであるから、前叙のところに従い右類推適用が肯定されるべきである。したがって、本件損失補償については、これを直接憲法29条3項にもとづいて論ずるまでもないのである。
本件のような都有行政財産たる土地につき使用許可によって与えられた使用権は、それが期間の定めのない場合であれば、当該行政財産本来の用途または目的上の必要を生じたときはその時点において原則として消滅すべきものであり、また、権利目的に右のような制約が内在しているものとして付与されているものとみるのが相当である。すなわち、当該行政財産に右の必要を生じたときに右使用権が消滅することを余儀なくされているのは、ひっきょう使用権自体に内在する前記のような制約に由来するものということができるから、右使用権者は、行政財産に右の必要を生じたときは、原則として、地方公共団体に対しもはや当該使用権を保有する実質的理由を失うに至るのであって、その例外は、使用権者が使用許可を受けるに当たりその対価の支払いをしているが当該行政財産の使用収益により右対価を償却するに足りないと認められる期間内に当該行政財産に右の必要を生じたとか、使用許可に際し別段の定めがされている等により、行政財産についての右の必要にかかわらず使用権者がなお当該使用権を保有する実質的理由を有すると認められるに足りる特別の事情が存する場合に限られるというべきである。」
(ポイント)
行政財産たる土地につき期間の定めなくなされた使用許可が、当該行政財産本来の用途・目的上の必要に基づいて撤回されたときは、特別の事情のない限り、使用権者は土地使用権の喪失についての補償を求めることはできない。
48,菊田医師赤ちゃんあっせん事件(最判昭63.6.17)
(事案)
上告人Xは、昭和25年に医師免許を付与され、昭和33年10月以降、宮城県石巻市にて産科・婦人科・肛門科の医院を開設していたが、その間んお昭和28年に、被上告人たる社団法人宮城県医師会(Y)から衛生保護法(現「母体保護法」)14条1項に基づく人工妊娠中絶を行いうる医師の指定を受けていた。
しかし、Xは、中絶の時機を逸しながらもその施術を求める女性を説得して出生をさせ、当該嬰児につき子どもを欲しがっている他の婦女が出産したとする虚偽の出生証明書を発行することにより、戸籍上も当該婦女の実子として登載させるという形で、当該嬰児をあっせんする、いわゆる実子あっせん行為を昭和52年10月20日までの間に220件繰り返した。
そのため、Yは、Xが昭和53年3月1日に仙台簡易裁判所から医師法違反ならびに公正証書原本不実記載・同行使罪により罰金20万に処する旨の略式命令を受け、刑が確定したことを受けて、「Xが指定医師として不適当と認められる」ことを理由に、昭和51年11月1日付けの指定医師の更新を取り消した(講学上の撤回)。
これに対し、Xは、当該指定取消処分と、その後の指定申請に対する却下処分の取消しを求めるとともに、Yと国に対する各3000万円の損害賠償の支払いを求めて提訴した(なお、Xは、昭和48年4月において、マスコミ等を通じてこの事実を社会に公表しており、その結果、このような実子あっせん行為が賛否両論を伴う社会問題となるとともに、昭和62年の民放改正による民放817条の2以下の特別養子縁組制度が創設される一つの契機となった。)。
民放817条の2
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
(争点)
優生保護法に基づく指定医師の指定といった授益的行政行為の撤回は、当該撤回を認める直接の明文規定がなくても許されるか。
(判旨)
「実子あっせん行為は、医師の作成する出生証明書の信用を損ない、戸籍制度の秩序を乱し、実子の親子関係の形成により、子の法的地位を不安定にし、未成年の子を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならない旨定めた民法798条の規定の趣旨を潜脱するばかりでなく、近親婚のおそれ等の弊害をもたらすものであり、また、将来子にとって親子関係の賛否が問題となる場合についての考慮がされておらず、子の福祉に対する配慮を欠くものといわなければならない。したがって、実子あっせん行為を行うことは、中絶施術を求める女性にそれを断念させる目的でなされるものであっても、法律上許されるものではないのみならず、
医師の職業倫理にも反するものというべきであり、本件取消処分の直接の理由となった当該実子あっせん行為についても、それが緊急避難ないしこれに準ずる行為に当たるとするべき事情は窺うことはできない。しかも、上告人は、右のような実子あっせん行為に伴う犯罪性、それによる弊害、その社会的影響を本当に軽視し、これを反復継続したものであって、その動機、目的が嬰児等の生命を守ろうとするに当たったこと等を考慮しても、上告人の行った実子あっせん行為に対する少なからぬ非難は免れないといわなければならない。
そうすると、被上告人医師会が昭和51年11月1日付の指定医師の指定をしたのちに、上告人が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、上告人が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、上告人に対する指定を存続させることが交易に適合しない状態が生じたというべきところ、実子あっせん行為のもつ右のような法的問題点、指定医師の指定の性質等に照らすと、指定医師の指定の撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回するべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるというべきである。」
(ポイント)
指定医師指定の撤回によって当該医師が被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性の高い場合には、指定権者は、法令上その撤回についての直接の明文がなくても、指定権限に基づき当該指定の撤回ができる。
49.宝塚市パチンコ条例事件(最判平17.7.9)
(事案)
兵庫県宝塚市(X)は、市内におけるパチンコ店等の主出店を規制するため、昭和58年に「宝塚市パチンコ店等ゲームセンターお及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」を制定し、パチンコ店等の建築等をしようとする者には市長の同意を得ることを義務づけ、同意なく建築をしようとする者には建築の中止・原状回復その他必要な措置を命じることができる旨が規定されていた。
ところが、平成4年11月にパチンコ店の出店を計画して市長の建築同意を申請したYに対し、市長が、建築予定地が条例の認める商業地域ではなく、準工業地域に属していることを理由に同意を拒否したところ、Yは、宝塚市建築審査会に対する審査請求により建築確認を認める裁決を得た上で、建築工事に着手した。
そのため、市長は平静6年3月15日に同条例に基づく建築工事中止命令を発したが、Yがこれを無視して工事を続けたことから、Xは、Yを相手方として、工事の続行禁止を求める仮処分決定を得るとともに、工事の続行禁止を求める民事訴訟を提起した。
(争点)
(地方公共団体が、条例に基づく行政上の義務の履行を求めて民事訴訟を提起することは認められるか。
(判旨)
「行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法3条1項にいう『法律上の争訟』、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる(最高裁昭和56年4月7日第三小法廷判決参照)。国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、法律上の争訟に当たるというべきであるが、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許されるものと解される。そして、行政代執行は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによるものと規定して(1条)、同法が行政上の義務の履行に関する一般法であることを明らかにした上で、その具体的な方法としては、同法2条の規定による代執行のみを認めている。また、行政事件訴訟法その他の法律にも、一般に国又は地方公共団体が国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟を提起することを認める特別の規定は存在しない。したがって、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当らず、これを認める特別の規定もないから、不適法というべきである。
本件訴えは、地方公共団体である上告人が本件条例8条に基づく行政上の義務の履行を求めて提起したものであり、原審が確定したところによると、当該義務が上告人の財産的権利に由来するものであるという事情も認められないから、法律上の争訟に当らず、不適法というほかはない。そうすると、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上によれば、第1審判決を取り消して、本件訴えを却下すべきである。
(ポイント)
地方公共団体が、行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟にあたらず、また、これを認める特別の規定も行政事件訴訟法その他の法律に存在しない以上、不適法である。つまり、認められない。
50.行政上の強制執行と民事上の強制執行(最判昭41.2.23)
(事案)
茨城県を区域をする農業共済組合連合会(X)は、その構成員たる下関市農業共済組合(A)に対して農業共済保険料や賦課金についての債権を有し、Aはその組合員たるYらに対して共済掛け金や賦課金・拠出金についての債権を有していた。そして、これらAの有する債権については、農業災害補償法87条の2およびこれを準用する農業共済組合法46条に基づき、滞納者に対する強制徴収が認められていたが、Xは、Aに代位して、共済掛金等を延滞しているYらに対して、その支払いを求めて民事訴訟を提起した。
(争点)
農業協同組合が、農作物等の共済掛金や賦課金・拠出金を滞納する組合員に対して、民事訴訟法の手続に従って徴収することは認められるか。
(判旨)
「農業災害補償法87条の2によれば、農業共済組合は、農作物共済若しくは蚕繭共済にかかる共済掛金又は賦課金を滞納する者がある場合には、督促状により繭共済にかかる共済掛金又は賦課金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促することを要し、その督促を受けた者が指定期限までにこれを完納しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができ、市町村は、右請求に応じて地方税の滞納処分の例によりこれを処分すべく、若し市町村が右請求に応じて地方税の滞納処分の例委によりこれを処分すべく、若し市町村が右請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、農業共済組合は、都道府県知事の許可を行けて、自ら地方税の滞納処分の例により処分することができることになっており、右徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされる等、その債権の実現について、特別の便宜が与えられている。また、拠出金の滞納についても、職業共済基金法46条により、前示す農業災害補償法87条の2の規定が準用され、右と同じ取扱いが認められている。かように、農業共済組合が組合員に対して有するこれら債権について、法が一般私法上の債権にみられない特別の取扱いを認めているのは、農業災害に関する共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上必要な財源を確保するあめには、農業共済組合が強制加入制のもとにこれに加入する多数の組合員から収納するこれらの金円につき、租税に準ずる簡易迅速な行政上の強制徴収の手段によらしめることが、もっとも適切かつ妥当であるとしたからにほかならない。
論旨は、農業災害補償法87条の2がこれら債権に行政上の強制徴収の手段を認めていることは、これら債権について、一般私法上の債権とひとしく、民訴法上の強制執行の手段をとることを排除する趣旨ではないと主張する。
しかし、農業共済組合が、法律上特にかような独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手段によってこれら債権の実現を図ることは、前示立法の趣旨に反し、公共性の強い農業共済組合の機能行使の適性を欠くものとして、許されないところといわなければならない。」
(ポイント)
農業共済組合が構成員による農作物の共済掛金などの延滞に対して徴収を行うにあたっては、農業災害補償法が規定する強制徴収の手段によるべきであって、民事訴訟法に基づく強制徴収を行うことは許されず、その履行を裁判所に請求することも認められない。
51.豊中給水装置拒否事件(最判昭56.7.16)
(事案)
Xは、大阪府豊中市内に賃貸用共同住宅を所有していたが、当該共同住宅の増築工事をした上で、豊中市(Y)の建築主事に対して建築確認申請をしたところ、当該増築部分が建築基準法の定める建ぺい率に適合しないことを理由に確認が得られなかった。しかし、Xが続いてY水道局に対して給水装置新設工事の申し込みをしたため、Y水道局給水課長は、違反建築物に対する給水制限実施要領に基づき、当該申込の受理を拒絶して申込書を返戻するとともに、建築基準法違反状態を是正して建築確認を受けた後に再度申し込むようにYに勧告した。
このため、Xは、既存の給水装置から増築部分への私設水道装置の設置工事を行うとともに、Y水道局が当該申込みの受理を拒絶して1年半以上の間給水を停止したことは水道法15条に違反しており、Xの給を受けるべき権利を侵害したとして、Yを被告とする損害賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
違法建築物についての給水装置新設工事の申込の受理を市が事実上拒否することは、不法行為法上の損害賠償責任を構成するか。
(判旨)
「被上告人市の水道局給水課長が上告人の本件建物についての給水装置新設工事申込の受理を事実上拒絶し、申込書を返戻した措置は、右申込の受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、上告人に対し、右建物につき存する建築基準法違反も状態を是正して建築確認を受けたうえ申込をするよう一応の勧告をしたものにすぎないと認められるところ、これに対し上告人は、その後1年半余を経過したのち改めて右工事の申込をして受理されるまでの間右工事申込に関してなんらの措置も講じないままこれを放置していたのであるから、右の事実関係の下においては、前記被上告人市の水道局給水課長の当初の措置のみによっては、未だ、被上告人市の職員が上告人の給水装置工事申込の受理を違法に拒否したものとして、被上告人市において上告人に対し不法行為上の損害賠償の責任を負うものとするには当たらないと解するのが相当である。」
(ポイント)
市水道局給水課長が違法建築物の給水装置新設工事の申込みの受理を事実上拒絶し申込書を返戻した措置は、当該申込みの受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受けた上で申込をするよう勧告したものにすぎず、市は不法行為上の損害賠償責任を負わない。
52.川崎民商事件(最判昭47.11.22)
(事案)
川崎民主商工会会員であるYが提出した昭和37年分の所得税確定申告書について、過少申告の疑いをもった川崎税務署は、所得税の賦課徴収事務に従事する職員を派遣して、Yに対し、売上帳・仕入帳等の提示を求めたところ、Yがこれ拒否したため、Yは所得税法(旧)70条10号が規定する検査拒否罪に問われることとなった。
(争点)
① 所得税法(旧)70条10号・63条は規定する税務職員による質問検査は、裁判所の判断を経ることなく行政庁の判断だけで行えるとしている点で、検索・押収には正当な理由に基づいて裁判所が発する令状が必要であるとする憲法35条に違反しないか。
② 所得税法(旧)70条10号・12号・63条が規定する税務署職員による質問検査は、自己に不利益な供述の強要を禁止する憲法38条に違反しないか。
(判旨)
「所論のうち、憲法35条違反をいう点は、旧所得税法70条10号・63条の規定が裁判所の令状なくして強制的に検査することを認めているのは違憲である旨の主張である。たしかに、旧所得税法70条10号の規定する検査拒否に対する罰則は、同法63条所定の収税官史による当該帳簿等の検査の受忍をその相手方に対して強制する作用を伴うものであるが、同法63条所定の収税官史の検査は、もっぱら、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であって、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない。
また、右検査の結果過少申告の事実が明らかとなり、ひいては所得税逋脱の事実の発覚にもつながるという可能性がかんがえられないわけではないが、そうであるからといって、右検査が、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならない。けだし、この場合の検査の範囲は、前記の目的のため必要な所得税に関する事項にかぎられており、また、その検査は、同条各号に列挙されているように、所得税の賦課徴収手続上一定の関係にある者につき、その者の事業に関する帳簿その他の物件のみの範囲が定められているのであって、所得税の逋脱その他の刑事責任の嫌疑を基準に右の範囲が定められているのではないからである。
さらに、この場合の強制の態様は、収税官史の検査を正当な理由がなく拒む者に対し、同法70条所定の刑罰を加えることによって、間接的心理的に右検査の受忍を強制しようとすうるものであり、かつ、右の刑罰が行政上の義務違反に対する制裁通して必ずしも軽微なものとはいえないにしても、その作用する強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同旨すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである。国家財政の基本となる徴税権の適正な運用を確保し、所得税の公平確実な賦課徴収を図るという公益上の目的を実現するために収税官史による実効性のある検査制度が欠くべからざるものであることは、何人も否定しがたいものであるところ、その目的、必要性にかんがみれば、右の程度の強制は、実効性確保の手段として、あながち不均衡、不合理なものとはいえないのである。
憲法35条1項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、当該手続が刑事責任追及を目的とするものではないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。しかしながら、前に述べた諸点を総合して判断すれば、旧所得税法70条10号、63条に規定する検査は、あらかじめ裁判官の発する令状によることをその一般的要件としないからといって、これを憲法35条の法意に反するものとすることはできず、前記規定を違憲であるとする所論は、理由がない。
所論のうち、憲法38条違反という点は、旧所得税法70条10号、12号、63条の規定に基づく検査、質問の結果、所得税逋脱(旧所得税法69条)の事実が明らかになれば、税務職員は右の事実を告発できるのであり、右検査、質問は、刑事訴追をうけるおそれのある事項につき供述を要するもので意見である旨の主張である。
しかし、同法70条10号、63条に規定する検査が、もっぱら所得税の公平確実な賦課徴収を目的とする手続であって、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、また、そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでないこと、および、このような検査制度に公益上の必要性と合理性の存することは、前示のとおりであり、これらの点について、同法70条12号、63条に規定する質問も同様であると解すべきである。そして、憲法38条1項の法意が、何人も自己の刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであると解すべきことは、当裁判所大法廷の判例(昭和32年2月20日判決)とするところであるが、右規定による保障は、純然たる刑事手続であるばかりでなく、それ以外の手続においても、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶものと解するのを相当とする。しかし、旧所得税法70条10号、12号、63条の検査、質問の性質が上述のようなものである以上、右各規程そのものが憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」を強要するものとすることはできず、この点の所論も理由がない。」
憲法38条1項
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
(ポイント)
① 刑事責任追及を目的としない手続において、一切の強制が憲法35条1項の保障の枠外にあると解すべきではないが、税務署職員による質問検査があらかじめ裁判官の発する令状によるべきことを一般的要件としていなくても、憲法35条1項に違反しない。
憲法35条1項
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 憲法38条1項による保障は、純然たる刑事手続以外でも、それが実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続にはひとしく及ぶと解すべきであるが、税務署職員による質問検査は、そのような手続には当たらないので、自己に不利益な供述を強要するものではない。
53.鉄道公安職印の実力行使(最大判昭48.4.25)
(事案)
国鉄労働組合門司地方本部に所属するYらは、同労働組合が行った年度末手当要求に関する闘争に参加するため、国鉄久留米駅東てこ扱所2階の信号所に立ち入り、多数の労働組合員らによるいわゆるピケットを指導した。そして、久留米駅長の命を受けた同駅助役らの再三の退去要求に応じなかったため、現地対策本部から実力による排除の命を受けた鉄道公安職員らが退去強制を行おうとしたところ、2階からこれに水を浴びせかけるなどして抵抗したことから、住居侵入罪ならびに公務執行妨害罪により起訴された。
(争点)
鉄道公安職員が、鉄道営業法42条1項に基づき不法行為者を鉄道施設外に退去させるにあたって強制力を用いることは、憲法31条等との関係において認められるか。
憲法31条
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
(判旨)
「まず、鉄道営業法42条1項は、旅客、公衆が停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入ったとき等同項各号に定める所為に及んだ場合、鉄道係員は、当該旅客、公衆を車外または鉄道地外に退去させうる旨を規定している。けだし、鉄道施設は、不特定多数の旅客および公衆が利用するものであり、また、性質上特別の危険性を蔵するものであるから、車内または鉄道地内における法規ないし秩序違反の行動は、これをすみやかに排除する必要があるためにほかならない。すなわち、同条項は、鉄道事業の公共性にかんがみ、事業の安全かつ確実な運営を可能ならしめるため、とくにかかる運営につき責任を負う鉄道事業者に直接にこの排除の係員が当該旅客、公衆を車外または鉄道地外に退去させるにあたっては、まず退去を促して自発的に退去させるのが相当であり、また、この方法をもって足りるのが通常であるが、自発的な退去に応じない場合、または危険は切迫する等やむをえない事情がある場合には、警察官の出動を要請するまでもなく、鉄道係員において当該具体的事情に応じて必要最小限度の強制力を用いるものであり、また、このように解しても、前述のような鉄道事業の公共性に基づく合理的な規定として、憲法31条に違反するものではないと解すべきである。
ところで、本件について考察するに、前記のとおり、久留米駅東てこ扱所2階の信号所に立ち入り、階段にすわり込んだ労働組合員らは、いずれもその勤務から離れ、久留米駅長等の当局側の警告を無視して、国鉄の業務運営上重要な施設を占拠し、その管理者の管理を事実上無視して、国鉄の業務運営上重要な施設を占拠し、その管理者を事実上排除したものであるから、このような場合は、鉄道営業法37条、42条1項3号にいう公衆が鉄道敷地内にみだりに立ち入った場合にあたるというを妨げず、これに対し、列車の正常かつ安全な運行に責任を有する国鉄当局が、同信号所の管理を回復するため、労働組合員らの退去を促し、さらにはその排除を図りうることは、当然の事理というべきである。
すなわち、このような場合、鉄道公安職員においては、前記『鉄道公安職員基本規定』所定の職務を行なう国鉄職員、すなわち、鉄道営業法42条1項所定の当該鉄道係員に属するものとして、すみやかに国鉄の業務運営上の障害を除去するため、前記信号所に立ち入りあるいは階段にすわり込んだ労働組合員らを退去させることができるものであり、その際には、前述のように、当該具体的事情に応じて必要最小限の強制力を用いることができるものと解すべきであって、検察官の所論引用の判例のうち仙台高等裁判所昭和36年5)第616号同38年3月29日判決および東京高等裁判所昭和39年5)第2487号同40年9月14日判決は、いずれもこの趣旨を判示したものである。そして、鉄道公安職員は、必要最小限度の強制力の行使として、信号所階段、その付近、同所内にいる労働組合員らに対し、拡声器等により自発的な退去を促し、もしこれに応じないときは、階段の手すりにしがみつき、あるいはたがいに腕を組む等して居すわっている者にい対し、手や腕を取ってこれをほどき、身体に手をかけて引き、あるいは押し、必要な場合にはこれをかかえ上げる等して、階段から引きおろし、これが実効を収めるために必要な限度で階段か下から適当な場所まで腕をとって連行する行為をもなしうるものと解すべきであり、また、このような行為がひつよ得最小限のものかどうかは、労働組合員らの抵抗の状況等の具体的な事情を考慮して決定すべきものである。」
(ポイント)
鉄道公安職員が、国鉄労働組合員を鉄道施設外に退去させるにあたって、本件のような行為をなすことは、必要最小限度の強制力の行使として許される。
54.刑罰と秩序罰の併科(最判昭39.6.5)
(事案)
Yらは、秋田地裁で行われた住居侵入罪に関する刑事裁判において、事件の証人として宣誓したにもかかわらず、裁判官による尋問に対して正当な理由なく証言を拒んだため、刑事訴訟法160条に基づき各5000円の過料に処せられたが、その後あらためて同法161条違反を理由に起訴された。
(争点)
同一の行為につき刑事訴訟法160条に基づく過料と同法161条に基づく罰金・拘留を併科することは、罰刑法定主義を定める憲法31条および二重処罰の禁止を定める同法39条後段に違反しないか。
(判旨)
「刑訴160条は訴訟手続上の秩序を維持するために秩序違反行為に対して当該手続を主宰する裁判所または裁判官により直接に科せられる秩序罰としての過料を規定したものであり、同161条は刑事司法に協力しない行為に対して通常の刑事訴訟手続により科せられる刑罰としての罰金、拘留を規定したものであって、両者は目的、要件及び実現の手続を異にし、必ずしも二社択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解するべきであり、右規定は憲法31条、同39条公団に違反しない。」
(ポイント)
同一の行為につき両者を併科するとは憲法31条9条後段に違反しない。併科も許される。
55.課外クラブ活動中の事故
(事案)
沖縄県金武町立金武中学校の2年生だったXは、友人らとともに体育館に行ったところ、体育館内においては課外クラブ活動であるバレーボール部とバスケットボール部とが両側に分かれて練習していたが、平素はバレーボール部の指導・監督をしている顧問の教諭は翌日の運動会の予行演習の準備のため運動場の方に行っておらず、また、他の教諭も体育館には居合わせていなかった。そこで、Xらは、トランポリンを倉庫から無断で持ち出し、バレーコートとバスケットコートの中間の壁側に設置してしばらく遊んでいたところ、バレーボール部員のAから練習の邪魔になるからトランポリン遊びを中止するように注意されたが、Xがこれに反発したため、AはXを倉庫に連れ込んだ上で鉄拳で2・3回Xの左顔面を殴打した。その結果、Xは1か月近くで左眼の視力を全く失うに至り、外傷性網膜全剥離と診断された。
このため、Xは、本件事故がバレーボール部の顧問の教諭が指導監督義務を怠ったために生じたものであるとして、金武町(Y)に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて出訴した。
国家賠償法1条1項
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
(争点)
公立中学校の生徒が課外クラブ活動中の他の生徒との喧嘩から左眼を失明した事故につき、当該クラブ活動に立ち会っていなかった顧問の教諭には過失があるといえるか。
(判旨)
「前記事実関係によれば、本件事故当時、体育館内においては、いずれも課外のクラブ活動であるバレーボール部とバスケットボール部とが両側に分かれて練習していたのであるが、本件記録によれば、課外のクラブ活動は、希望する生徒による自主的活動であったことが窺われる。もとより、課外のクラブ活動であっても、それが学校の教育活動の一環として行われるものである以上、その実施について、顧問の教諭を始め学校側に、生徒を指導監督し事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務があることを否定することはできない。しかしながら、課外のクラブ活動が本来生徒の自主性を尊重すべきものであることを鑑みれば、何らかの事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のある場合は格別、そうでない限り、顧問の教諭としては、個々の活動に常時立ち合い、監視指導すべき義務までを負うものではないと解するのが相当である。
ところで、本件事件は、体育館の使用をめぐる生徒間の紛争に起因するものであるところ、本件事故につきバレーボール部顧問の教諭が代わりの監督者を配置せずに体育館を不在にしていたことが同教諭の過失であるとするためには、本件のトランポリンの使用をめぐる喧嘩が同教諭にとって予見可能であったことを必要とするものというべきであり、もしこれが予見可能でなかったとすれば、本件事故の過失責任を問うことはできないといわなければならない。そして、右予見可能性を肯定するためには、従来からの金武中学校における課外クラブ活動中の体育館の使用方法とその範囲、トランポリンの管理等につき生徒に対して実施されていた指導の内容並びに体育館の使用方法等についての過去における生徒間の対立、紛争の有無及び生徒間における右対立、紛争の生じた場合に訴えることがないように教育、指導がされていたか否か等を更に総合検討して判断しなければならないものというべきである。」
(ポイント)
課外クラブ活動の顧問教諭には事故発生を未然に防止すべき一般的注意義務はあるが、個々の事故時にクラブ活動に立ち会っていなかったとしても、当該事故が発生する危険性を具体的に予見することができるような特段の事情がない限り、当該事故について過失はない。
なお、過失なしとしても、公立中学校の課外クラブ活動が、「公権力の行使」に当たることには注意。
56.スナック事件(最判昭57.1.19)
(事案)
暴行・傷害など前科23犯のAが、阪急淡路駅付近の「スナック舞子」および「スナックニュー阪急」において、泥酔の上、刃渡り7.5センチの飛び出しナイフを見せながら店員や客に「馬鹿野郎」「刺されたいか」などと怒鳴ったりしたため、「スナックニュー阪急」の支配人Xなどは、Aを淡路警察署に連れて行くとともに、途中でAから取り上げた本件ナイフを警察官に渡した。そこで、淡路警察署の警察官は、Aに本籍・氏名等を問うとともに身体検査を行い、大阪府警察本部にAの前科等を照会したが、当時、同本部には大阪府外の者の前科は登録されていなかったため、Aの前科は判明しなかった。その結果、淡路警察署員は、Aが相当酩酊しており、その供述態度も反抗的で信用できるものではなかったにもかかわらず、Aの行為は犯罪を構成せず、逮捕、保護または引取りを手配し、ナイフを領置・保管したりする必要はないと判断し、Aにナイフを持たせたまま帰宅させた。
そのため、Aは、警察署からの帰途に、本件ナイフでXの胸部や顔面を切りつけ、Xに左眼失明等の重傷を負わせた。
以上の経緯から、Xは、淡路警察署の警察官がAを逮捕せず、また、本件ナイフを領置することもなく帰宅させたことは、警察官としての職務に違背し違法であるとして、大阪府(Y)を被告として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
泥酔してナイフを出しながら客などを脅した者からナイフを提出させて一時保管の措置などをとることなく、これを帰宅させた警察の行為(不作為)は、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
(判旨)
「以上の事実関係からすれば、Aの本件ナイフの形態は鉄砲刀剣類等取締法22条の規定により禁止されている行為であることが明らかであり、かつ、同人の前記の行為が強迫罪にも該当するような危険なものであったのであるから、淡路警察署の警察官としては、飲酒酩酊したAの前記弁解をうのみにすることなく、同人を警察に連れてきたXらに対し質問するなどして「スナックニュー阪急」その他でのAの行動等について調べるべきであったといわざるをえない。そして、警察官が、右のような措置をとっていたとすれば、Aが警察に連れてこられた経緯や同人の異常な挙動等を容易に知ることができたはずであり、これらの事情から合理的に判断すると、同人に本件ナイフを携帯したまま帰宅することを許せば、帰宅途中ナイフで他人の生命又は身体に危害をお及ぼすおそれが著しい状況にあったというべきであるから、同人に帰宅を許す以上少なくとも同法24条の2第2項の規定により本件ナイフを提出させて一時保管の措置をとるべき義務があったものとっ解するのが相当であって、前記警察官が、かかる措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し違法であるというほかはない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいて、所論警察官の違法行為とXの受傷により被った損害との間に相当因果関係があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。
(ポイント)
他人の生命または身体に危害を及ぼす蓋然性の高い者がナイフを所持していた場合に、そのナイフについて一時保管措置を怠った警察官の不作為は、公権力の行使にあたる。
つまり、「公権力の行使」には作為だけでなく、不作為も含まれることに注意。
57.砲弾回収措置の不作為(最判昭59.2.23)
(事案)
東京都新島木村の前海岸付近では、第二次世界大戦後連合国軍の指令の下で大量に海中放棄された旧日本陸軍の砲弾類が風や波浪の影響により度々海岸に打ち上げられるようになり、陸上自衛隊や海上自衛隊が数次にわたってその回収作業を実施していた。しかし、それでも未回収の砲弾類が多く存在し、子ども達の中には、海岸で拾得した砲弾類の火薬を抜き取り、これに点火し花火のように遊ぶ者がいたり、大人達の中にも、海中に潜ってこれを拾い鉄屑として古物回収業者に売却する者や抜き取った火薬を焚火の火付けに使用している者などがいた。これにつき、新島警察署は、これを放置すれば人身事故等の発生する危険性があることを察知し、砲弾類回収の必要性を認めて、島民に対して砲弾類を発見した場合にはこれを警察に届け出るよう呼びかけるとともに、警視庁に対する正規の報告文書に前記事情を記載して報告し、砲弾類の処理を自衛隊に依頼するよう上申していたが、警視庁から自衛隊に対する依頼はなされていなかった。
そうするうちに、昭和44年6月29日午後3時40分ごろ、前浜海岸砂防堤付近において、Xら3名が他の中学生であるAなどから教えられた焚火で暖をとっていたところ、Aらがその焚火の中に投入していた砲弾が突然爆発し、この爆発によってXらのうち1名が死亡、1名が右眼球破裂、左網膜剥離等の障害を負うに至った。このため、負傷者および死亡者の遺族らが、東京都(Y)を相手取り、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて出訴した。
(争点)
海辺に打ち上げられた旧日本軍の砲弾により人身事故が発生した場合において、警察官がその回収等の措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
(判旨)
「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもってその責務とするものであるから(警察法2条参照)、警察官は、人の人生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞れのある天災、事変、危険物の爆発等危険な事態があって特に急を要する場合においては、その危険物の管理者その他の関係者に対し、危険防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができるものとされている(警察官職務執行法4条1項参照)。もとより、これは、警察の前記のような責務を達成するために警察官に与えられた権限であると解されるが、島民が居住している地区からさほど遠からず、かつ、海水浴場として、一般大衆に利用されている海浜やその付近の海底に砲弾類が投棄されてたまま放置され、その海底にある砲弾類が毎年のように海浜に打ち上げられ、島民等が砲弾類の危険性についての知識の欠如から不用意に取り扱うことによってこれが爆発して人身事故等の発生する危険があり、しかも、このような危険は毎年のように海浜に打ち上げられることにより継続して存在し、島民等は絶えずかかる危険に曝されているが、島民等としてはこの危険を通常の手段では除去することはできないため、これを放置するときは、島民等の生命、身体の安全が確保されないことが相当の蓋然性をもって予測されうる状況のもとにおいて、かかる状況を警察官が容易に知りうる場合には、警察官において右権限を適切に行使し、自ら又はこれを処分する権限・能力を有する機関に要請するなどして積極的に砲弾類を回収するなどの措置を講じ、もって砲弾類の爆発による人身事故の発生を未然に防止することは、その職務上の義務でもあると解するのが相当である。
してみれば、原審の確定した前記一の事実関係のもとでは、新島警察署の警察官を含む警視庁の警察官は、遅くとも昭和41、42年ころ以降は、単に島民等に対して砲弾類の危険性についての警告や砲弾類を発見した場合における届け出の催告等の措置をとるだけでは足りず、更に進んで自ら又は他の機関に依頼して砲弾類を積極的に回収するなどの措置を講ずるべき職務上の義務があったものと解するのが相当であって、前記警察官が、かかる措置をとらなかったことは、その職務上の義務に違背し、違法であるといわなければならあに。」
(ポイント)
旧日本陸軍の砲弾により人身事故が発生した場合、警察官がその回収等の措置をとらなかったことは、違法な公権力の行使に該当する。
58.水俣病の拡大と規制権限の不行使(最判昭59.2.23)
(事案)
水俣病は、水俣病またはその周辺海域の魚介類を多量に摂取したことによって起こる中毒性中枢神経疾患であり、症状が重篤な時は死亡するに至る病気であるが、昭和31年5月1日の「公式発見」当時は、その原因が不明であった。その後、昭和33年6月開催の参議院社会労働委員会において、厚生省環境衛生部長が原因物質は水俣市の肥料工場から流失したと推定される旨の発言をしたが、通産省軽工業局長は、同年9月頃、厚生省に対して、現段階では断定的な見解を述べることがないよう申し入れた。そして、昭和34年11月12日に至り、厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会は、水俣病の主因を成すものがある種の有機水銀化合物であるとの答申を厚生大臣に提出し、国や熊本県(Yら)は、遅くとも同年11月末頃には、原因物質の排出源がチッソ水俣工場のアセトアルデヒド製造施設であることを高度の蓋然性をもって認識し得る状況となり、その頃までには同工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析技術も開発されていたと指摘した。
しかし、現実にチッソ株式会社が水俣工場のアセトアルデヒド製造を中止したのは昭和43年5月であり、国が水俣病の原因がチッソ水俣工場内で生成されたメチル水銀化合物である旨の政府見解を発表したのは同年9月、水俣湾およびその周辺海域を水質二法(公共用水域の水質の保全に関する法律、工場排水等の規制に関する法律)に基づく指定水域に指定したのは翌昭和44年であった(なお、水質二法は、昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止されている。)。
そこで、水俣病患者であると主張するXらは、Yらが水俣病の発生および被害拡大の防止のために規制制限を行使することを怠ったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて出訴した。
(争点)
国や熊本県が、それぞれ水質二法や県漁業調整規則に基づく規制権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。
(判旨)
「昭和34年11月末の時点で、①昭和31年5月1日の水俣病の公式発見から起算しても既に3年半が経過しており、その間、水俣病はその周辺海域の魚介類を摂取する住民の命、健康等に対する深刻かつ重大な被害が生じ得る状況が継続しいているのであって、上告人国は、現に多数の水俣病患者が発生し、死亡者も相当数に上がっていることを認識していたこと、②上告人国においては、水俣病のアセトアルデヒド製造施設であることを高度のがい然性をもって認識し得る状況にあったこと、③上告人にとって、チッソ水俣病工場の排水に微量の水銀が含まれていることについての定量分析をすることは可能であったことといった事情を認めることができる。なお、チッソが昭和34年12月に整備した前記排水浄化装置が水銀の除去を目的としたものではなかったことを容易に知り得たことも、
前記認定のとおりである。そうすると、同年11月末の時点において、水俣病及びその周辺海域を指定水域に指定すること、当該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物が検出されないという水質基準を定めること、アセトアルデヒド製造施設を特定施設に定めることという上記規制権限を行使するために必要な水質二法所定の手続を直ちに執ることが可能であり、また、そうすべき状況にあったものといわなければならない。そして、この手続に要する期間を考慮に入れても、同年12月には、主務大臣として定められるべき通商産業大臣において、上記規制権限を行使して、チッソに対し水俣工場のアセトアルデヒド製造施設からの工場排水についての処理方法の改善、当該施設の使用の一時停止その他必要な措置を執ることを命ずることが可能であり、しかも、水俣病による健康被害の深刻さにかんがみると、直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと認めるのが相当である。また、この時点で上記規制権限が行使されていれば、それ以降の水俣病被害拡大を防ぐことができたこと、ところが、実際には、その行使がされなかったために、被害が拡大する結果となったことも明らかである。
本件における以上の諸事情を総合すると、昭和35年1月以降、水質二法に基づく上記規制権限を行使しなかったことは、上記規制権限を定めた水質二法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。
したがって、同項による上告人国の損害賠償責任を認めた原審の判断は、正当として是認することができる。この点に関する上告人国の論旨は採用することができない。
次に、上告人県の責任についてみると、以上説示したとこrによれば、前記事実関係の下において、熊本県知事は、水俣病にかかわる前記諸事情について上告人国と同様の認識を有し、又は有し得る状況にあったのであり、同知事には、昭和34年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使すべき作為義務があり、昭和35年1月以降、この権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くものとして、上告人県が国家賠償法1条1項による損害賠償責任を負うとした原審の判断は、同規制が、水俣動植物の繁殖保護等を直接の目的とするものではあるが、それを摂取する者の健康の保持等をもその究極の目的とするものであると解されることからすれば、是認することができる。」
(ポイント)
国は、昭和34年11月末の時点で、水俣病などを指定水域に指定する水質二法に基づく規制権限を行使することが可能であり、そうすべき状況にあった。また、熊本県知事も、同年12月末までに県漁業調整規則32条に基づく規制権限を行使するべき作為義務を負っていた。
したがって、昭和35年1月以降にこれら規制権限を行使しなかったことは、水質二法や県漁業調整規則の目的などに照らし、著しく合理性を欠くものといえ、国家賠償法上違法である。
59.宅配郷社に対する権限の不行使(最判平元.11.24)
(事案)
有限会社誠和住建は(A社)は、昭和47年10月に京都府知事から宅地建物取引業免許を付与され、昭和50年10月にその更新を受けた(この免許およびその更新は、宅建業法の定める免許基準に適合しないことが記録から窺われる。)が、その実質上の経営者Bは多額の負債を抱えており、A社の免許が更新される直前には最初の苦情が京都府(Y)に寄せられ、免許更新後の昭和51年頃にはA社の債務不履行が多くなっていた。そこで、Yの担当職員は、昭和51年7月8日にA社に対する立入検査を行い、新規契約の締結の禁止を指示したが、その後もA社に対する苦情が相次いだため、同年12月17日に宅建業法69条に基づく公開の聴聞を行い、翌年4月7日に京都府知事がA社の免許を取り消した。
一方で、この間に、Xは、A社が同社所有の建売住宅として売り出したのを信じて昭和51年9月3日にA社と本件土地建物の売買契約を締結したが、結局その所有権を取得できず、A社に支払った740万円相当の損害を被った。このため、Xは、A社の代表取締役Cに対して損害賠償請求訴訟を提起するとともに(この訴訟ではXの勝訴が確定)、Yに対して国家賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
① 宅配業法所定の免許基準に達しない免許の付与ないし更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
② {C}宅建業者に対する知事の監督処分権限の行使の遅れは、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使に該当するか。
(判旨)
「右事実関係によれば、京都府知事が誠和住研に対し本件免許を付与し更にその後これを更新するまでの間、誠和住研の取引関係者からの担当職員に対する苦情申出は1件にすぎず、担当職員において双方から事情を聴取してこれを処理したというのであるから、本件免許の付与ないし更新それ自体は、法所定の免許基準に適合しないものであるとしても、その後に誠和住研と取引関係を持つに至った上告人に対する関係で直ちに国家賠償法1条1項にいう違法な行為にあたるものではないというべきである。
また、本件免許の更新後は担当職員が誠和住研と被害者との交渉の経過を見守りながら被害者救済の可能性を模索しつつ行政指導を続けてきたなど前示事実関係の下においては、上告人が誠和住研に対し中間金390万円を支払った時点までに京都府知事において誠和住研に対する業務の停止ないし本件免許の取消をしなかったことが、監督処分権限の趣旨・目的に照らして著しく不合理であるということはできないから、右権限の不行使も国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきである。」
(ポイント)
① 宅建業者に対する知事の免許の付与・更新が宅建業法所定の免許基準に適合しない場合でも、そのことが当該業者による不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係で、直ちに違法な行為には当たらない。
② 宅建業者に対して知事が宅建業法に基づく業務停止処分・免許取消処分をしなかった場合でも、具体的事情の下で、当該処分権限が付与された趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り、当該業者による不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係で、違法な行為には当たらない。
60.クロロキン網膜症訴訟(最判平7.6.23)
(事案)
クロロキンは、昭和9年にドイツで合成に成功した化学物質であり、クロロキン製剤は、クロロキンの化合物を含有する製剤として、当初はマラリヤの治療薬として開発されたが、後には間接リュウマチ・エリテマトーテス・腎疾患・てんかんの治療にも使用されるようになり、わが国では、昭和30年3月から輸入販売が始まり、昭和35年12月から厚生大臣によって製造許可がなされるようになった。
しかし、このクロロキン製剤の服用によりクロロキン網膜症なる副作用が発生し、これによる患者には網膜障害が生じ、重症の場合には失明に至ることもまれではなく、そのような症例は、外国では昭和34年に初めて報告され、わが国では、昭和37年から昭和40年までの間に論文発表や症例報告がなされたが、その多くはクロロキン製剤の長期服用によりまれに生じるものとの位置づけであって、クロロキン製剤の有効性を否定するものではなかった。
その後、厚生大臣は、薬効問題懇談会の昭和46年7月7日の答申を受けて、日本薬局方に収載されている医薬品を含むすべての医薬品についての有効性および安全性の再評価作業に着手し、その結果、クロロキン製剤については、昭和51年7月に、マラリア・エリテストーテス・関節リウマチについては有効性・有用性が認められるものの、腎疾患については有効性と副作用を対比したとき副作用が上回る場合があるので有効性が認められず、てんかんについては有効と判定する根拠がないと公表された。
これに対し、昭和34年から昭和50年までの間に関節リウマチ・エリテマトーデス・腎疾患・てんかんのいずれかの治療のためにクロロキン製剤を服用して、クロロキン網膜症に罹患した被害者およびその相続人(Xら)は、厚生大臣がクロロキン製剤の製造承認等をした違法およびクロロキン網膜症の発生を防止するために適切な措置を執らなかった違法を主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
(争点)
① 厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載および製造の承認等の行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。
② 厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法となるか。
(判旨)
「所論は、まず、厚生大臣が、リン酸クロロキン及びリン酸クロロキン錠を日本薬局方に収載し、キドラ及びCQCについて製造の許可又は承認及び効能追加の承認をしたことが違法であると主張するので、この点につき判断する。
前記の薬事法の目的に照らせば、厚生大臣は、特定の医薬品を日本薬局方に収載し、又はその製造の承認(承認事項の一部変更である効能追加の承認を含む。以下、同じ。)をするに当たって、当該医薬品の副作用を含めた安全性についても審査する権限を有する者であり、その時点における医学的、薬学的知見を前提として、当該医薬品の治療上の効能、効果と副作用を比較考量し、それが医薬品としての有用性を有するか否かを評価して、日本薬局方への収穫又は製造承認の可否を判断するものと解される。したがって、厚生大臣が特定の医薬品を日本薬局方に収載し、又はその製造の承認をした場合において、その時点における医学的、薬学的知見の下で、当該医薬品がその副作用を考慮してもなお有用性を肯定し得るときは、厚生大臣の薬局方収載等の行為は、国家賠償法1条1の適用上違法の評価を受けることはないというべきである。右の理は、製造の承認とその目的、性質を同じくする医薬品の製造の許可(旧薬事法26条3項)についても変わるところはないものと解される。
これを本件についてみると、前記の事実関係によれば、厚生大臣がクロロキン製剤について各行為をした昭和35年から昭和39年までの間においては、その副作用であるクロロキン網膜症に関する報告が内外の文献に現れ始めたばかりであって、報告内容も長期連用の場合のクロロキン網膜症の発症の危険性及び早期発見のための眼科的検査の必要性を指摘するにとどまり、クロロキン製剤の有用性を否定するものではなく、この間に我が国で報告された症例は合計17件であったというのであるから、これらの文献や症例報告に基づく当時の医学的知見の下においては、厚生大臣が、腎疾患及びてんかんを含めた前記各疾患に対するクロロキン製剤の有用性を肯定し得るものとして行った前記各行為に違法はないというべきである。
次に、所論は、厚生大臣がクロロキン製剤の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使して適切な措置を採らなかった違法を主張するので、この点につき判断する。
日本薬局方に収載され、又は製造の承認がされた医薬品が、その効能、効果を著しく上回る有害な副作用を有することが後に判明し、医薬品としての有用性がないと認められるに至った場合には、厚生大臣は、当該医薬品を日本薬局方から削除し、又はその製造の承認を取り消すことができると解するのが相当である。
薬事法は、厚生大臣は少なくとも10年ごとに日本薬局方の改定について中央薬事審議会に諮問しなければならないと規定する(41条3項)にとどまり、また、昭和54年法律第56号による改正後の薬事法74条の2のような製造の承認の取消しに関する明文の規定を欠くが、前記の薬事法の目的並びに医薬品の日本薬局方への収載及び製造の承認に当たっての厚生大臣の安全性に関する審査権限に照らすと、厚生大臣は、薬事法上右のような権限を有するものと解される。
厚生大臣の薬事法上の権限の行使についての右のような性質ないし特質を考慮すると、医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、厚生大臣が当該医薬品の副作用による被害の発生を防止するために前記の各権限を行使しなかったことが直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法と評価されるものではbなく、副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、前記のような薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使は、副作用による被害を受けた者との関係において同項の適用上違法となるものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、前記の事実関係によれば、昭和37年以降我が国においても、文献等による症例の報告により、クロロキン製剤の副作用であるクロロキン網膜症に関する知見が次第に広まってきたものの、その内容はクロロキン製剤の有用性を否定するまでのものではなく、一方、クロロキン製剤のエリテマトーデス及び関節リウマチに対する有用性は国際的に承認され、昭和51年の再評価の結果の公表以前においては、クロロキン製剤は、根本的な治療法の発見されていない難病である腎疾患及びてんかんに対する有用性が認められ、臨床の現場において副作用であるクロロキン網膜症を考慮してもなお有用性を肯定し得るものとしてその使用が是認されていたというのであるから、当時のクロロキン網膜症に関する医学的、薬学的知見の下では、クロロキン製剤の有用性が否定されるまでには至っていなかったものということができる。したがって、クロロキン製剤の有用性が否定されるまでには至っていなかったものもということができる。したがって、クロロキン製剤について、厚生大臣が日本薬局方から削除や製造の承認の取消しの措置を採らなかったことが著しく合理性を欠くものとはいえない。」
(ポイント)
① 本件において、厚生大臣による医薬品の日本薬局方への収載・製造の承認等の行為は、国家賠償法1条1項の適用上違法とならない。
② 本件において、厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とならない。
61.在宅投票事件(最判昭60.11.21)
(事案)
公職選挙法およびその委任による公職選挙法施行令は、疾病・負傷・妊娠・身体障害等のため歩行が困難である選挙人(「在宅選挙人」)について、投票所に行かずにその現在する場所において投票用紙に投票の記載をして投票することができる制度(「在宅投票制度」)を定めていたところ、昭和26年4月に行われた統一地方選でこの制度が悪用され、それによる選挙無効および当選無効の争訟が続出したことから、国会は、公職選挙法の一部を改正する法律を成立させて在宅投票制度を復活させるための立法を行わないでいた。
その結果、公職選挙法9条の規定による選挙権を有している小樽市在住のXは、担架等を用いなければ投票所に行くことができないため、昭和43年から47年までの間に実施された計8回の国政選挙ならびに地方選挙の投票をすることができなかったことから、在宅投票制度を廃止して復活しない本件立法不作為は、在宅選挙人の選挙権の行使を妨げ、憲法13条・14条・15条・44条・47条・93条の規定に違反する公権力の行使にあたるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を国(Y)に求めて提訴した。
憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
③ 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
(争点)
国会議員による立法行為(立法の不作為を含む)は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使を構成するか。在宅投票制度を廃止し、これを復活させなかった行為は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使に該当するか。
(判旨)
「憲法51条が、『両議院の議員は、議院で行った演説、討議又は表決について、院外で責任を問はれない。』と規定し、国会議員の発言、表決につきその法的責任を免除しているのも、国会議員の立法過程における行動は政治的責任の対象とするにとどめるのが国民の代表者による政治の実現を期するという目的にかなうものである。との考慮によるのである。このように、国会議員の立法行為は、本質的に政治的なものであって、その性質上法的規制の対象になじまず、特定個人に対する損害賠償責任の有無という観点から、あるべき立法行為を措定して具体的立法行為の適否を評価するということは、原則的には許されないも尾いわざるを得ない。ある法律が個人の具体的権利利益を侵害するものであるという場合に、裁判所はその者の訴えに基づき当該法律の合憲性を判断するが、この判断は既に成立している法律の効力に関するものであり、法律の効力についての違憲審査がなされるからといって、当該法律の立法過程における国会議員の行動、すなわち立法行為が当然に法的評価に親しむものとすることはできないのである。
以上のとおりであるから、国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではないというべきであって、国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けないものといわなければならない。
これを本件についてみると、前記のとおり、上告人は、在宅投票制度の設置は憲法の命ずるところであるとの前提に立って、本件立法行為の違法を主張するのであるが、憲法には在宅投票制度の設置を積極的に命ずる明文の規定が存しないばかりでなく、かえって、その47条は『選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。』と規定しているのであって、これが投票の方法その他選挙に関する事項の具体的決定を原則として立法的である国会の裁量的権限に任せる趣旨であることは、当裁判所の判例とするところである。そうすると、在宅投票制度を廃止しその後前記8回の選挙までにこれを復活しなかった本件立法行為につき、これが前示の例外的場合に当たると解すべき余地はなく、結局、本件立法行為につき、これが前示の例外的場合に当たると解すべき余地はなく、結局、本件立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないといわざるを得ない。」
(ポイント)
国会議員による立法行為につき、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うような例外的な場合でない限り、違法な評価は受けない。このように、極めて限定的にしか違法性を認めていない。その結果、在宅投票制度を廃止し、これを復活させない不作為は、違法な公権力の行使に該当しない。
62.在外邦人選挙権制限違憲事件(最判平17.9.14)
(事案)
改正前古色選挙法42条1項・2項は、選挙人名簿に登録されていない者および登録されることができない者は国政選挙の投票をすることができない旨を定めており、選挙人名簿への登録は、市町村の区域内に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で、その者に係る当該市町村の住民票が作成された日から引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者についてのみ行われる(公職選挙法21条1項、住民基本台帳法15条1項)ため、国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民(在外国民)は、選挙権を行使することができなかった。
その後、平成10年の公職選挙法の一部改正により、新たに在外選挙人名簿が調整されることとなり(同法30条の2以下)、それにより同法42条1項本文も「選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。」と定められたが、改正法附則8項により、当分の間は衆議院比例代表選出議員の選挙と参議院比例代表選出議員の選挙に限るとされていたため、その間、在外国民は週銀小選挙区の選挙と参議院選挙区選出議員の選挙についての選挙権を行使することができなかった。
そのため、在外国民であるXらが、国(Y)を相手取り、在外国民であることを理由に選挙権行使の機会を保障しないことが憲法14条1項、15条1項・3項、43条、44条ならびに市民的・政治的権利に関する国際規約(国際人権規約B規約)25条に違反することの確認と、平成8年10月20日に実施された衆議院議員総選挙の選挙権を行使できなかったことによる精神的苦痛に対する国家賠償を求めて出訴した。
(争点)
{C}① 在外国民が、平成10年改正前の公職選挙法により衆議院銀選挙・参議院議員選挙における選挙権を行使できなかったことが憲法・条約に違憲することの確認を求める訴訟を提起することは認められるか。また、平成10年改正後の公職選挙法附則8項により衆議院小選挙区選出議員の選挙と参議院選挙区選出銀の選挙についての選挙権ができなかったことが憲法・条約に違反することの確認を求める訴訟を提起することは認められるか。さらに、衆議小選挙区選出議員の選挙と参議院選挙区選出議員の選挙についての選挙権を有することの確認を求める訴訟を提起すること、認められるか。
{C}② 在外国民が平成8年10月20日に実施された衆議院銀総選挙において選挙権を行使できなかったことにつき、立法府である国会が公職選挙法の改正を怠っていたことは、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるか。
(判旨)
「〈確認の訴えについて〉
{C}① 本件の主位的確認請求に係る訴えのうち、本件改正前の公職選挙法が広告人らに衆議院
議員の選挙及び参議院議員の選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認を求める訴えは、選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認を求める訴えは、過去の法律関係の確認を求めるものであり、この確認を求めることが現に存する法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のために適切かつ必要な場合であるとはいえないから、確認の利益が認められず、不適法である。
{C}② また、本件の主位的確認請求に係る訴えのうち、本件改正後の公職選挙法が上告人らに衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認を求める訴えについては、他により適切な訴えによってその目的を達成することができる場合には、確認の利益を欠き不適法であるというべきところ、本件においては、後記3のとおり、予備的確認請求に係る訴えであるということができるから、上記の主位的確認請求に係る訴えは不適法であるといわざるを得ない。
{C}③ 本件の予備的確認請求に係る訴えは、公法上の当事者訴訟のうち公法上の法律関係に関する確認の訴えと解することができるところ、その内容をみると、公職選挙法附則8項につき所要の改正がされないと、在外国民である別紙当事者目録1記載の上告人らが、今後直近に実施されることになる衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において投票することができず、選挙権を行使する権利を侵害されることになるので、そのような事態になることを防止するために、同条上告人らが、同項が違憲無効であるとして当該各選挙につき選挙権を行使する権利を有することの確認をあらかじめ求める訴えであると解することができる。
選挙権は、これを行使することができなければ意味がないものといわざるを得なず、侵害を受けた後に争うことによっては権利行使の実質を回復することができない性質のものであるから、その権利の重要性にかんがみると、具体的な選挙につき選挙権を行使する権利の有無につき争いがある場合にこれを有することの確認の利益を肯定するべきものである。そして、本件の予備的確認請求に係る訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、上記の内容に照らし、確認の理胃液を肯定することができるものに当たるというべきである。なお、この訴えが法律上の争訟に当たることは論をまたない。
そうすると、本件の予備的確認請求に係る訴えについては、引き続き在外国民である同上告人らが、次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を請求する趣旨のものとして適法な訴えということができる。
{C}④ そこで、本件の予備的確認請求の当否について検討するに、前記のとおり、公職選挙法附則8項のうち、在外選挙制度の対象となる選挙を当分の間同議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は、憲法15条1項及び3項、4条1項並びに44条ただし書きに違反するもので向こうであって、上告人らは、次回の衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすすことができる地位にあるというべきであるというべきであるから、本件の予備的確認請求は理由があり、更に弁論をするまでもなく、これを認容すべきものである。
「〈国家賠償請求について〉国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。したがって、国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって、当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるできであり、仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても、そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。しかしながら、立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国会議員の立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価をうけるものというべきである。最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁は、以上と異なる趣旨をいうものではない。
在外国民であった上告人らも国政選挙において投票する機会を与えられることを憲法上保障されていたのであり、この権利行使の機会を確保するためには、在外選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず、前記事実関係によれば、昭和59年に在外国民の投票を可能にするための法律案が閣議決定されて国会に提出されたものの、同法律案が廃案となった後、本件選挙の実施に至るまで10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったのであるから、このような著しい不作為は上記の例外的な場合に当たり、このような場合においては、過失の存在を否定することはできない。このような立法不作為の結果、上告人らは本件選挙において投票することはできない。このような立法不作為の結果、上告人らは本件選挙において投票することができず、これによる精神的苦痛を被ったものというべきである。したがって、本件においては、上記の違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求はこれを認容すべきである。」
(ポイント)
{C}① {C}平成8年10月20日実施の衆議院議員総選挙当時、公職選挙法が在外国民の選挙権行使を認めていなかったこと、また、平成10年改正後の公職選挙法附則8項の規定中、在外国民の選挙権を両議院の比例代表選出議員の選挙に限定する部分は、遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙の時点で、憲法15条1項などに違反するが、確認の利益を欠き不適法である。しかし、次回の衆議院小選挙区選出議員選挙・参議院選挙区選出議員選挙の選挙権を有する確認を求める訴えは、確認の利益が認められる。
{C}② 在外国民に国政選挙権行使の機会を保障するための立法措置を執ることが必要不可欠であったにもかかわらず、10年以上の長きにわたって国会が立法措置を執らなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける著しい不作為にあたり、その過失も認められるため、国は在外住民に対して賠償義務を負う。
63.議員の免責特権と国家賠償責任(最判平9.9.9)
(事案)
昭和60年11月21日に開かれた衆議院社会委員会において、当時衆議院議員であり同委員会の医院であったYは、同日の議題であった医療法の一部を改正する法律案の審査に際し、地域医療計画における国の責任や医療圏・医療施設に関する都道府県の裁量権等の同法律案の問題点を指摘するとともに、札幌市の乙山病院の問題を取り上げて質疑し、同病院の院長Aが5名の女性患者に対して破廉恥な行為をしたことや、Aが薬物を常用するなど通常の精神状態にはないといったことを指摘して、現行の行政の中ではこのような医師をチェックすることができないのではないかと主張した。
この発言による指摘を受けたAが翌日自殺したことから、その妻であるXが、Yの発言によりAの名誉が毀損され、同人が自殺に追い込まれたとして、Yに対しては民放709条・710条に基づき、国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償を求めて出訴した。
(争点)
国会議員が国会の質疑・演説・討論等の中でした個別の国民の名誉または信用を低下させる発言につき、国は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うか。
(判旨)
「所論は、特定の者を誹謗するにすぎない本件発言は、憲法51条が規定する『演説、討論又は表決』に該当しないのに、原審が上告人の被上告人Yに対する請求排斥したのは不当であるというものである。されたものであることが明ら
しかしながら、前記の事実関係の下においては、本件発言は国会議員である被上告人Yによって、国会議員としての職務を行なうにつきされたものであることが明らかである。そうすると、仮に本件発言が被上告人Yの故意又は過失による違法な行為であるとしても、被上告人国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である被上告人Y個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである。したがって、本件発言が憲法51条に規定する『演説、討論又は裁決』に該当するかどうかを論ずるまでもなく、上告人の被上告人に対する本訴請求は理由がない。
憲法51条は、『両議院の議員は、議院で行った演説、討議または表決について、院外で責任を問われない』と規定し、国会議員の発言、表決につきその法的責任を免除しているが、このことも、一面では国会議員の職務行為についての広い裁量の必要性を裏付けているということができる。もっとも、国会議員に右のような広範な裁量が認められるのは、その職権の行使を十全ならしめるという要請に基づくものであるうから、職務とは無関係に個別の国民の権利を侵害することを目的とするような行為が許されないことはもちろんであり、また、あえて虚偽の事実を摘示して個別の国民の名誉を毀損するような行為は、国会議員の裁量に属する正当な職務行為とはいえないというべきである。
以上によれば、国会議員が国会で行った質問等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
これを本件についてみるに、前示の事実関係によれば、本件発言が法律案の審議という
国会議員の職務に関係するものであったことは明らかであり、また、被上告人Yが本件発言をするについて同被上告人に違法又は不当な目的があったとは認められず、本件発言の内容が虚偽であるとも認められないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。したがって、被上告人国の国家賠償法上の責任を規定した原審の判断は、正当である。」
(ポイント)
国会議員が国会でした個別の発言につき、国家賠償法1条1項の違法な行為として国の損害賠償責任が肯定されるには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法・不当な目的をもって事実を摘示し、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを要する。
64.裁判行為と国家賠償法1条1項(最判昭57.3.12)
(事案)
ミシンの特注機械装置を製造販売していたXは,昭和42年12月に縫製業を営むA社から機械装置の注文を受け納入したが、A社は代金を支払わず、機械の調子が悪いことを理由に数か月使用した後これを返品した。一方で、Xは、昭和43年1月に同じA社からミシンの修理を依頼されたが、これを修理しないまま留置し、昭和44年11月に至って未修理のままこれをA社に返品した。
そこで、A社は、Xがミシンを修理しないまま1年10か月にわたって留置したことによる損害の賠償を求めて民事訴訟を提起したところ、Xは前記機械装置の使用による価値減少分についての損害賠償請求権を被担保債権とする留置権の成立を抗弁として提出したが、大阪地裁昭和47年1月21日判決は、Xの主張する被担保債権と留置権との間には牽連性が認められないことを理由にXの抗弁を否定し、A社の主張を認めたため、Xが控訴しないまま同判決が確定した。
ところが、その後になって、Xが、商人間における双方にとっての商行為から生じた債権を被担保債権とする場合については個別的牽連性がないものについても留置することを認める商法521条の規定を知るに及んで、前記の判決を行った裁判官が商法521条を適用しなかったままXを敗訴せしめたのは国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使にあたるとして、国(Y)に対して損害賠償を求める訴えを提起した。
(争点)
裁判官がした訴訟の裁判は、国家賠償法1条1項の規定する違法な公権力の行使を構成するか。
(判旨)
「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。したがって、本件において仮に前訴判決に所論のような法令の解釈・適用の誤りがあったとしても、それが上訴による是正の原因となるのは格別、それだけでは未だ右特別の事情がある場合にあたるものとすることはできない。」
(ポイント)
裁判官がした争訟の判決につき、国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使があったとするためには、当該裁判官が違法・不当な目的をもって裁判をしたなど、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るようなs特別の事情があることが必要である。
65.「その職務を行うについて」の意味(最判昭31.11.30)
(事案)
警視庁に所属する巡査Aは、職務行為を装って金品を強奪する目的で、非番の日を選んで、制服制帽を着用の上、同僚から盗んだ拳銃を携帯して隣接する神奈川県川崎市に行き、川崎駅で本件被害者Bを不審尋問を装って呼び止めた。そして、Aは、駅事務室でBの所持品を取り調べ、その中にあった現金等が犯罪の証拠物に該当する疑いがあると主張してこれを受け取った上で、Bを本署に連行すると偽って連れ出したが、途中で自らが逃走しようとした際に声をたてられたので、前記拳銃を発射してBを死に至らせた。
そのため、Bの遺族(X)は、東京都(Y)を相手取り国家賠償を請求したが、Y側が本件Aの行為は国家賠償法1条1項に規定する「その職務を行なうについて」に該当しないと主張したため、出訴に及んだ。
(争点)
当初より職務執行の意思がなく、単に他人の金品を不法に領得する目的を有するに過ぎない公務員の行為も、国家賠償法1条1項の「その職務を行うについて」の要件を充たすか。
(判旨)
「原判決は、その理由において、国家賠償法1条の職務執行とは、その公務員が、その所為に出づる意図目的はともあれ、行為の外形において、職務執行を認め得べきものともって、この場合の職務執行なりとするほかないのであるとし、即ち、同条の適用を見るがためには、公務員が、主観的に権限行使の意思をもってした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限るとの解釈を排斥し、本件において、A巡査がもっぱら自己の利をはかる目的で「警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、その目的をとげた、判示のごとき職権乱用の所為をもって、同条にいわゆる職務執行について違法に他人に損害を加えたときに該当するものと解したのであるが同条に関する右の解釈は正当であるといわなければならない。けだし、同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず自己の利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる作為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の損益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。」
(ポイント)
国家賠償法1条1項が規定する。公務員が「その職務を行なうについて」違法に他人に損害を加えたとは、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限定せず、たとえ自己の利を図る目的をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれにより他人に損害を加えたときも、これに該当する。
外形、外見から判断するという外形説を採用している。
66.加害公務員の特定(最判昭57.4.1)
(事案)
大蔵事務官として林野税務署に勤務するXは、昭和27年6月に実施された定期健康診断において胸部エックス線間接撮影による検診を受けたところ、その撮影フィルムにはXが初期の肺結核に罹患していることを示す陰影があったにもかかわらず、税務署長からは特別の指示をうけなかった。そのため、Xは、従来どおり外勤の職務に従事した結果、翌28年6月の定期健康診断によりその事実が判明するまでの間に病状が悪化させ、長期療養を余儀なくされた。
そこで、Xは、国(Y)を相手に損害賠償を求める訴訟を提起したが、原審が認定した事実関係からは、レントゲン写真の読映にあたった医師が過失により陰影を看過したのか、それを報告する懈怠があったのか、あるいは林野税務署の職員が執るべき処置を執らなかったのか、さらには両者の中間にある職員が報告の伝達を怠ったのかが判明しなかった。
(争点)
公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合、具体的に加害行為を特定できなければ国または公共団体は損害賠償責任を負わないか。
(判旨)
「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じせしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものなのであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのであれば右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべきによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当であり、原審の見解は、右と趣旨を同じくする限りにおいて不当とはいえない。しかしながら、この法理が肯定されるのは、それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の行為に当たる場合に限られ、一部にこれに該当しない行為者が含まれている場合には、もとより右の法理は妥当しないのである。
本件における右検診等の行為が上告人の職員である医師によって行われたものであれば、同人の違法な検診行為につき上告人に対して民放715条の損害賠償責任を問疑すべき余地があり、ひいてはさきに述べた一般的法理に基づいて上告人の賠償責任を肯定しうる可能性もないではないが、仮に上告人の主張するように、右検診等の行為が林野税務署長の保健所への嘱託に基づき訴外岡山県の職員である同保健所勤務の医師によって行われたものであるとすれば、右医師の検診等の行為は右保健所の業務としてされたものというべきであって、たとえそれが林野税務署長の嘱託に基づいてされたものであるとしても、そのために右検診等の行為が上告人国の事務の処理とんり、右医師があたかも上告人国の機関ないしその補助者として検診等の行為をしたものと解さなければならない理由はないから、右医師の検診等の行為に不法行為を成立せしめるような行為があっても、そのために上告人が民放の前記法条による損害賠償責任を負わなければならない理由はないのである。」
(ポイント)
国・公共団体に属する数人の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせて場合、それが具体的にどの公務員のそのような違法行為によるものであるかと特定することができなくても、当該一連の行為によるものであるかをとくていすることができなくても、当該一連の行為のうちのいずれかに故意・過失による違法行為があったのでなければ被害が生ずることはなかったのであろうと認められるときは、国・公共団体は当該賠償責任を免れることはできない。つまり、加害行為者・加害行為を必ずしも特定できなくてもよい。
67.無罪の刑事判決と国家賠償(最判昭53.10.20)
(事案)
昭和27年に起きた国鉄根室本線の鉄道線路爆破事件で、列車往来危険罪・火薬類取締法違反の罪などに問われ、逮捕・勾留・起訴の後、控訴審において無罪判決を受けたXが、国と捜査にあたった警察官・控訴の提起・追行にあたった検察官を被告として、国家賠償を求めた。
(争点)
刑事裁判において無罪判決が確定した場合、当該事件における捜査や公訴の提起・追行は違法な公権力の行使にあたるか。
(判旨)
「刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留・公訴の提起・追行、起訴後の拘留が違法となることはない。けだし、逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないからであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである。」
(ポイント)
刑事事件において無罪判決が確定したというだけで、直ちに起訴前の逮捕・勾留・公訴の提起・追行、起訴後の拘留が違法とはならない。
68.パトカー追跡中の事故(最判昭61.12.27)
(事案)
富山警察署外勤課自動車警ら係所属の巡査Aらがパトカー富山11号に乗車して富山市内を機動警ら中、住吉警察官派出所前の交差点付近にさしかかったところ、国道8号線(現41号線)を走行中のB運転の普通乗用車が速度違反車であることを現認したため直ちに追尾し、速度38キロの速度超過を確認した後、赤色灯を点灯しサイレンを吹鳴して追跡を開始した。そのため、一旦は停止したBは、突如Uターンして時速約100キロで逃走し、富山市内の交差点に赤信号にもかかわらず進入したため、C運転の普通乗用車に衝突し、そのはずみでCの車両がX運転の普通乗用車に激突したため、Xやその同乗者が入院約1か月から4か月の重傷を負った。
そのため、Xらは、Aらのパトカーによる追跡の開始・継続ならびにその方法には過失があったとして、富山県(Y)に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて提訴した。
(争点)
警察官が運転するパトカーの追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した交通事故により第三者が損害を被った場合、当該追跡行為が国家賠償法上違法なものとして評価されるのはどのような場合か。
(判旨)
「およそ警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断してなんらかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある者を停止させて質問し、また、現行犯人を現認した場合には速やかにその検挙又は逮捕に当たる職責を負うものであって(警察法2条、65条、警察官職務執行法2条1項)右職責を遂行する目的のために被疑者を追跡することはもとよりなしうるところであるから、警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して車両を逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、右追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである。
以上の見地に立って本件をみると、原審の確定した前記事実によれば、Bは、速度違反行為を犯したのみならず、警察官の指示により一たん停止しながら、突如として高速度で逃走を企てたものであって、いわゆる挙動不審者として速度違反行為の他のなんらの犯罪に関係があるものと判断しうる状況にあったのであるから、本件パトカーに乗務する警察官は、Bを現行犯人として謙虚ないし逮捕するほか挙動不審者に対する職務質問をする必要もあったということができるところ、右警察官は逃走車両の車両番号は確認したうえ、県内各署に加害車両の車両番号、特徴、逃走方向等の無線手配を行い、追跡途中で『交通機動隊が検問開始』との無線交信を傍受したが、同車両の運転者の氏名等は確認できておらず、無線手配や検問があっても、逃走する車両に対しては究極的には追跡が必要になることを否定することができないから、当時本件パトカーが加害車両を追跡する必要があったものというべきであり、また、本件パトカーが加害車両を追跡していた道路は、その両側に商店や民家が立ち並んでいるうえ、交差する道路も多いものの、その他に格別危険な道路交通状況はなく、東山交差点からK町交差点までは4車線、その後は2車線で歩道を含めた歩道の幅員が約12メートル程度の市道であり、事故発生の時刻が午後11時頃であったというのであるから、逃走車両の運転の前示の態勢等に照らしても、本件パトカーの乗務員において当時追跡による第三者の被害発生の蓋然性のある具体的な危険性を予測しえたものということはできず、更に、本件パトカーの前記追跡方法自体にも特に危険を伴うものはなかったということができるから、右追跡行為が違法であるとすることはできないものというべきである。
警察法
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(現行犯人に関する職権行使)
第六十五条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
警察官職務執行法
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
(ポイント)
パトカーの追跡により第三者が損害を被った場合、当該追跡行為が国家賠償法1条1項の違法な公権力の行使にあたるのは、当該追跡が現行犯逮捕や職務質問等の目的を遂行する上で不必要であるか、逃走車両の走行の態様や道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性に照らして、当該追跡の開始・継続・その方法が不相当であることを要する。いわゆるカーチェイスの事件である。
69.公務員個人の責任(最判昭30.4.19)
(事案)
農地調整法に基づくき実施された選挙により構成された熊本県球磨郡湯前町農地委員会は、委員半数ずつが同町の小作人組合の両組合系に分かれて対立し、それが激化したことから、熊本県知事(Y)は、熊本県農地委員会の請求により、昭和21年11月15日に同町農地委員会の解散処分を行った。そのため、これを不服とする同町農地委員会委員長Xらが、Yによる当該処分の無効確認とYおよびZ(県農地部長)に対して慰謝料の支払いを求めて出訴した。
(争点)
公権力の行使にあたる公務員の職務行為に基づく損害につき、当該公務員は被害者に対して直接に責任を負うか。
(判旨)
「農地調整法に基づく農地委員会は、農地委員会法(昭和26年3月31日法律第88号)の施行により、同法附則2項の経過的存続期間の終了とともに廃止されることとなり、市町村については昭和26年7月20日の選挙によりの農業委員会が成立すると、同時に農地委員会は消滅したことは、顕著な事実であるから、上告人等は、本件農地委員会についてもはや本訴により解散処分の無効確認の判決を求める利益を有しないのである。
次に上告人等の損害賠償等を請求する訴えについて考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すべきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。従って県知事を相手方とする訴えは不適法であり、また県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。」
(ポイント)
公権力の行使にあたる公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責めに任じ、当該職務執行にあたった公務員は、行政機関としての地位においても、また個人としても、被害者に対して責任を負うものではない。
つまり、被害者は、加害公務員個人に対して、直接損害賠償を請求することはできない。
これに対し、民放715条の使用者責任の場合には、被害者は、被用者=加害者に対して、民放709条に基づいて直接損害賠償を請求することができる。
両者の違いに特に注意が必要である。
●加害者の個人責任
国家賠償法1条の場合 → なし
民法の使用者責任の場合 → あり
70.国家賠償請求訴訟と抗告訴訟の関係(最判昭45.8.20)
(事案)
矢掛町農地委員会(Y)の全身たる矢掛町農地委員会が、X所有の宅地につき自作農創設特別措置法15条に基づき買収計画を樹立・公告したため、Xがその無効を求めて出訴したところ、本件買収計画に関する買収申請人であったAらがいずれも当該買収申請を取り下げたため、Y委員会は本件買収計画を取り消し、その旨を公告した。そのため、第一審・第二審とも、本件買収計画がすでに失効している以上、その無効確認を求める訴訟は訴えの利益を欠くと判断したが、X側は、本件買収計画の無効確認を求めるのは、その後の国家賠償を求める目的によるものであるから、なお無効確認を求めるについての法律上の利益は失われていないと主張した。
(争点)
行政処分の無効確認訴訟が提起された後に当該処分が職権により取り消されても、国家賠償請求との関係で、なお無効確認を求めることについての訴えの利益は存するか。
(判旨)
「原判決の確定した事実によれば、被上告人矢掛町農業委員会の前身たる矢掛町農地委員会は昭和23年12月16日自作農創設特別措置法15条に基き本件買収計画を樹立・公告したが、買収令書の交付される前に買収計画の取下げがあったため、昭和27年5月28日本件買収計画を取り消す旨の決議をし、その頃これを公告したというのである。してみると、本件買収計画は、買収申請の取下により、初めに遡りその存在を失うに至ったものと解すべきであるから、上告人は、右計画の無効確認を求めるにつき法律上の利益を欠くに至ったものと解すべきである。
また、行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではないから、本訴が被上告人委員会の不法行為による国家賠償を求める目的に出たものということだけでは、本件買収計画の取消後においても、なおその無効確認を求めるにつき法律上の利益を有するということの理由をするに足りない。
(ポイント)
行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするにあたって、あらかじめ当該行政処分についての取消し、無効確認の判決を得なければならないものではない。
したがって、国家賠償を求める目的により提訴がなされているというだけでは、無効確認を求める法律上の利益は認められない。
71.高地落石事件(最判昭45.8.20)
(事案)
高知市方面と中村市方面を結ぶ一級国道たる国道56号線は、その途中の安和から海岸線に沿って長佐古トンネルに至る2000メートルの区間において、従来山側からしばしば落石があり、さらに崩土さえ何回かあったため、ここに侵入する人および車はたえず落石・崩土の危険におびやかされていた。
これに対して、道路管理者は、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切れを付けて立て、通行車に注意を促す等の処理を講じていた。そうする中、昭和38年6月13日に発生した崩土に伴う落石によりトラックの助手席に乗っていた16歳の青年が即死する事故が起きたことから、その両親(Xら)が、道路管理者たる国(Y)に対して国家賠償法2条1項に基づき、また管理費用の負担者たる高知県(Z)に対して国家賠償法3条1項に基づき、損害賠償を求めて提訴した。
(争点)
① 国家賠償法2条1項における営造物の設置・管理の「瑕疵」の意味をいかに解すべきか、また、当該瑕疵を判断するにあたって、管理者における過失は必要とされるか。
② 道路管理を充分に行うためには予算的に困難な状況が認められる場合は、国家賠償法2条1項および3条1項に基づく責任は免れられるか。
(判旨)
「国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(原判決の説示する安和より海岸線に沿い長佐古トンネルに至る2000メートルの区間)を含む国道56号線は、一級国道として高知市方面と中村市方面とを結ぶ陸上交通の上で極めて重要な道路であるところ、本件道路には従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかもしれず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれの
あるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったというべきである旨、本件道路における落石、崩土の発生する原因は道路の山側の地層に原因があったので、本件における道路管理の瑕疵の有無は、本件事故発生地点だけに局限せず、前記2000メートルの本件道路全般についての危険状況および管理状況等を考慮にいれて決するのが相当である旨、そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし回避可能性のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。してみれば、その余の点について判断するまでもなく、本件事故は道路管理に瑕疵があったため生じたものであり、上告人国は国家賠償法2条1項により、上告人県は管理費用負担者として同法3条1項により損害賠償の責に任ずべきことは明らかである。」
(ポイント)
{C}① 国家賠償法2条1項の営造物の設置・管理の「瑕疵」とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国・公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としない。
つまり、無過失責任である。
{C}② 道路管理を充分に行うために費用額が多額にのぼり、その予算措置に困難な状況が伴っても、それにより直ちに道路管理の瑕疵によって生じた損害の賠償責任を免れない。
つまり、予算不足という財政的な理由は、免責事由とならない。
72.大阪国際空港公害訴訟(最判昭56.12.16)
(事案)
昭和34年7月に空港警備法2条1項1号の第一種空港として指定された大阪国際空港は、国際航空路線および主要な国内航空路線の用に供されるわが国の代表的な国営空港の1つとして活用されてきたが、ジェット機の就航やB滑走路の増設などに伴い、それがもたらす騒音公害も深刻なおのとなってきた。そのため、昭和44年に至り、周辺住民300名余名(Xら)は、国(Y)を被告として、午後9時から翌朝7時までの本件空港の使用差止めと、過去および将来に係る損害賠償の支払いを求める民事訴訟を提起した。
(争点)
{C}① 民事上の請求として、一定の時間帯に航空機の離発着のためにされる国営空港の併用の差止めを求めることはできるか。
{C}② 営造物の物的欠陥以外の原因を理由として国家賠償法2条1項が規定する営造物の設置・管理の瑕疵を認定することは許されるか。
{C}③ 将来にわたって継続する不法行為を理由とする損害賠償請求は認められるか。
(判旨)
「〈差止請求に関す判断〉営造物管理権の本体をなすものは、公権力の行使をその本質的内容としない非権力的な権能であって、同種の私的施設の所有権に基づく管理権能とその本質において特に異なるところはない。国の営造物である本件空港の管理に関する事項のうちに、その目的の公共性に由来する多少の修正をみることがあるのは別として、私営の飛行場の場合における
と同じく、私法的規制に親しむものがあることは、否定しえないところである。しかしながら、本件空港の管理といっても、その作用の内容には種々のものがあり、その法律的性質が一律一様であると速断することはできない。のみならず、空港については、その運営に深いかかわりあいを持つ事象として、航空行政権、すなわち航空法その他航空行政に関する法令の規定に基づき運輸大臣に付与された航空行政上の権限で公権力の行使を本質的内容とするものの行使ないし作用の問題があり、これと空港ないし飛行場の管理権の行使ないし作用とが法律上そのような位置、関係に立つのかが更に検討されなければならない。そもそも法が一定の公共用飛行場についてこれを国営空港として運輸大臣みずから設置、管理すべきものとしたゆえんのものは、これによってその航空行政権の行使としての政策的決定を確実に実現し、国の航空行政を効果的に遂行することを可能とするにある、というべきである。すなわち、法は、航空機及びその運航、航空従事者、航空路、飛行場及び航空保安施設、航空運送事業並びに外国航空機等に関する広範な行政上の規制制限を運輸大臣付与し、運輸大臣をして、これらの権限の行使により、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運行して営む事業の秩序を確立し、社会、経済の発展、国際交流の活発化等により増大する航空運輸に対する需要と供給を調整し、他の諸政策分野と整合性のある航空行政制作を樹立して実施させることとしており、こてに関する公共施設として航空法の定める公共用飛行場を設けている。そして、そのうち、国際航空路線又は主要な国内航空路線に必要なものなど基幹となる公共用飛行場については、運輸大臣みずからが、又は法律により設立された運輸大臣の特別な指示ないし監督に服する特殊法人である新東京国際空港公団が、これを国営又は同公団営の空港として設置、管理し、公共の利益のためにその運営に当たるべきものとしている。それは、これら基幹となる公共用飛行場にあっては、その設置、管理のあり方がわが国の政治、外交、経済、文化等と深いかかわりを持ち、国民生活に及ぼす影響も大きく、したがって、どの地域にそおのような規模でこれを設置し、どのように管理するかについては航空行政の全般にわたる政策的判断を不可欠とするからにほかならないものと考えられる。右にみられるような空港国営化の趣旨、すなわち国営空港の特質を参酌して考えると、本件空港の管理に関する事項のう、少なくとも航空機の離着陸の規制そのもの等、本件空港の本来の機能の達成実現に直接にかかわる事項自体については、空港管理権に基づく管理と航空行政権に基づく規制とが、空港管理権者としての運輸大臣と航空行政権の主管者としての運輸大臣のそれぞれ別個の判断に基づいて分離独立的に行われ、両者の間に矛盾乖離を生じ、本件空港を国営空港とした本旨を没却し又はこれに支障を与える結果を生ずることがないよう、いわば両者が不即不離、不可分一体的に行使実現されているものと解するのが相当である。換言すれば、本件空港における航空機の離着陸び規制等は、これを法律的にみると、単に本件空港についての営造物管理権の行使という立場のみにおいてされるべきもの、そして現にされているものとみるべきではなく、航空行政権の行使という立場をお加えた、複合的観点に立った総合って気判断に基づいてされるべきもの、そして現にされているものとみるべきものである。前述のように、本件空港の離着陸のためにする供用は運輸大臣の有する空港管理権と航空行政権という二種の権限の、総合的判断に基づいた不可分一体的な行使の結果であるとみるべきであるから、右被上告人らの前記のような請求は、事理の当然として、不可避的に航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することとなるものといわなければならない。したがって、右被上告人らが行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして、上告人に対し、いわゆる通常の民事上の請求として前記のような私法上の給付請求権を有するとの主張の成立すべきいわれはないというほかはない。」
「(過去の損害の賠償請求に関する判断)国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如mすなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害をしょうぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によって危害を生ぜしめる危険性がある状態にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右製造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、したがって、右営造物の設置・管理者において、かかる危険があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生じせしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法2条1項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」
「〈将来の損害の賠償請求に関する判断〉民訴法226条はあらかじめ請求する必要があることを条件として将来の給付の訴えを許容しているが、同条は、およぞ将来に生ずる可能ではなく、主として、いわゆる期限制限付請求権や条件付請求権のように、既に権利発生の基礎をなす事実上及び法律上の関係が存在し、ただ、これに基づく具体的な給付義務の成立が将来におけるい一定の時期の到来や債権者において立証を必要としないか又は容易に立証しうる別の一定の事実の発生にかかっているにすぎず、将来具体的な給付義務が成立したときに改めて訴訟により右請求権成立のすべての要件の存在を立証することを必要としないを考えられるようなものについて、例外として将来の給付の訴えによる請求を可能ならしめたにすぎないものと解される。たとえ同一態様の行為が将来も継続されることが予測される場合であっても、それが現在と同様に不法行為を構成するか否か及び賠償すべき損害の範囲いかん等が流動性をもつ今後の複雑な事実関係の展開とそれらに対する法的評価に左右されるなど、損害賠償請求権の成否及びその額をあらかじめ一義的に明確に認定することができず、具体的に請求権が成立したとされる時点においてははじめてこれを認定することができるとともに、その場合における権利の成立要件の具備については当然に債権者においてこれを立証すべく、事情の変動を専ら債務者の立証すべき新たな権利成立阻却事由の発生としてとらえてその負担を債務者に課するのは不当であると考えられるようなものについては、前記の不動産の継続的不法占有の場合とはとうてい同一に論ずることはできず、かかる将来の損害賠償請求権については、冒頭に説示したとおり、本来例外的にのみ認められる将来の給付の訴えにおける請求書としての適格を有するものとすることはできないと解するのが相当である。」
民訴法226条
(文書送付の嘱託)
第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
(ポイント)
① 行政訴訟の方法により請求をすることはともかく、通常の民事上の請求として、一定の時間帯についての国営空港の供用の差止めを求めることは認められない。
② 営造物が通常有するべき安全性を欠いている状態には、営造物が供用目的によって利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合も含む。つまり、飛行機の離発着による騒音公害も含むということ。また、その危害は、当該営造物の利用者以外の第三者に対するそれを含む。つまり、周辺住民への被害を含むということ。
③ 不法行為が将来も継続することが予想されても、損害賠償請求権の成否・額をあらかじめ一義的明確に認定されないなどの場合には、将来の給付の訴えとして損害賠償を求めることは認められない。
73.営造物の通常の用法に即しない行動(最判昭53.7.4)
(事案)神戸市内にある夢野合高等学校の校庭横を通る市道は、昭和35年頃には校庭から路面までの高さが約2メートルにすぎなかったが、その後の土砂の流入や道路舗装工事などの結果、次第に高くなって、約4メートルにも達するようになり、子どもの転落事故も数件発生したことから、神戸市(Y)は、昭和40年に防護柵を設置した。この防護柵は、2メートル間隔に立てられた高さ80センチのコンクリート柱に上下2本ン鉄パイプを通して手摺としており、路面から冗談手摺までの高さは65センチ、下段手摺までの高さは40センチであった(なお、当該鉄パイプは、この種の策に通常用いられる丸棒状のものでありが、幼児が遊び道具とするのに好適なものではない。)そして、本件道路付近は住宅地で、昼間車両の通行量が少なく、付近に適当な遊び場所がなかったことから、本件道路が子どもらの遊び場所となっていたところ、昭和44年8月4日の午後8時頃、防護柵の上段手摺に後ろ向きに腰掛けて遊んでいた当時6歳のXが、誤って約4メートル下の校庭に転落し、頭蓋骨陥没骨折の重傷を負った。
そのため、Xは、本件道路の設置・管理には瑕疵があったとして、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償をYに求めて出訴した。
(争点)
営造物の通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、当該営造物の設置・管理者は、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任を負うか。
(判旨)
「国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理に瑕疵があったとみられるかどうかは、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものであるところ、前記事実関係に照らすと、本件防護柵は、本件道路を通行する人や車が誤って転落するのを防止するために被上告人によって設置されたものであり、その材質、高さその他その構造に徴し、通行時における転落防止の目的からみればその安全性に欠けるところがないものというべく、上告人の転落事故は、同人が当時危険性の判断能力に乏しい6歳の幼児であったとしても、本件道路及び防護柵の設置管理者である被上告人において通常予測することができない行動に起因するものであったということができる。したがって、右営造物につき本来それが具有するべき安全性に欠けるところがあったとはいえず、上告人がしたような通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、被上告人はその設置管理者としての責任を負うべき理由はないものというべきである。」
(ポイント)
営造物の通常の用法に即しない行動の結果事故が生じた場合に、当該行動が設置管理者において通常予測できないものであったときは、その事故は営造物の設置・管理の瑕疵によるものではない。
74.赤色灯事件(最判昭50.6.26)
(事案)
奈良県桜井市を通る県道天理・桜井線の初瀬橋北詰付近では、昭和41年9月6日当時、道路の中心線から西側、すなわち北進道路で掘削工事が行われており、その工事個所を表示するため、工事現場の南北各約2メートルの地点に、工事標識版と高さ約80センチ・幅約2メートルの黒黄まだらのバリケードが1つずつ設置され、当時バリケード間の道路中心線付近には高さ1メートルの赤色灯標柱が1つずつ設置されていた。しかし、同日の午後10時30分頃同所を北進した車により、前記工事現場の南側に設置されていた工事標識版・バリケード・赤色灯標柱がなぎ倒され、赤色灯点滅も消えた結果、その直後に同所を通過したA運転の乗用車がこれに気付いてあわててハンドルを切ったが、道路から3メートル下の田圃に同車は転落し、助手席に同乗していたBが死亡した。
このため、Bの遺族(X)が、奈良県(Y)に対し、本件県道には道路として通常有すべき安全性の欠如があったとして、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めて出訴した。
(争点)
他車により工事個所を示す工事標識版や赤色灯標柱などが倒され、赤色灯が消えた場合にも、その直後に同所を通過して事故に遭遇した者との関係では、道路管理者に管理の瑕疵があったこととなるか。
(判旨)
「本件事故発生当時、被上告人において設置した工事標識版、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性に欠陥があったといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によって惹起されたものであり、時間的に被上告人において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったというべく、このような状況のもとにおいては、被上告人の道路管理に瑕疵がなかったと認めるのが相当である。」
(ポイント)
夜間、工事個所を示す工事標識版や赤色灯標柱などが倒れ赤色灯が消えていた場合でも、それが事故直前に通行した他の車両により惹起された時間的に道路管理者が遅滞なくこれを原状に復し道路の安全を保持することが不可能であったときには、当該道路管理に瑕疵はない。
このように、国家賠償法2条の責任は、1条と異なり、無過失責任ではあるが、不可抗力による場合には免責されることに注意が必要である。
国家賠償法1条・2条
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
75.87時間事件(最判昭50.7.25)
(事案)
Aは、大型貨物自動車を運転中に、和歌山県橋本市内の国道170号線で事故を起こし、右車輪やハンドル等に故障が生じたため、同車を同国道の菱田産業石油倉庫前まで移動させ、道路中央線より左方に右前輪が53センチ、右後輪が16センチ寄った位置の道路と並行でない形に駐車してこれを放置した。そして、同国道の和歌山件部分の管理については、和歌山県知事が国から委任されているところ、その管理事務所を担当する同県橋本土木出張所には当時パトロール車の配置がなく、常時巡視はしていなかったことから、本件事実を認識していなかった。その結果、事故車の放置から約87時間後の昭和40年10月21日の午前66時過ぎに、Bの運転する原動機付自転車が時速約60キロで当該事故車の荷台右後部に激突し、Bは頭蓋骨骨折により即死した(なお、管轄する警察署は、少なくとも同月19日には当該事故車を認識していたようである。)
このため、Bの両親(Xら)が、和歌山県(Y)を被告としてっ国家賠償法2条1項および3条1項に基づく損害賠償を求めて提起したところ、Yは、子の請求を認めた原審(大阪高判昭47.3.28)には道路交通法51条に基づく警察署の措置の不手際の問題と道路管理者たる県知事の道路管理の不手際の問題との混同が認められるとして、最高裁に上告した。
(争点)
国道上に故障した大型貨物自動車が約87時間にわたって放置されたことは、国道の管理の瑕疵といえるか。
(判旨)
「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うところ(道交法42条)、前記事実関係に照らすと、同国道の本件事故現場付近は、幅員7.5メートルの道路中央線付近に故障した大型貨物自動車が87時間にわたって放置され、道路の安全性を著しく欠如する状態であったにもかかわらず、当時その管理事務を担当する橋本土木出張所は、道路を常時巡視して応急の事態に対処しうる看視体制をとっていなかったために、本件事故が発生するまで右故障車が道路上に長時間放置されていることすら知らず、まして故障車のあることを知らせるためのバリケードを設けるとか、道路の片側部分を一時通行止めにするなど、道路の安全性を保持するために必要とされる措置を全く講じていなかったことは明らかであるから、このような状況のもとにおいては、本件事件発生当時、同出張所の道路管理に瑕疵があったというほかなく、してみると、本件道路の管理費用を負担すべき上告人は、国家賠償法2条及び3条の規定に基づき、本件事故によって被上告人らの被った損害を賠償する責に任ずべきであり、上告人は、道路交通法上、警察官が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資するために、違法駐車に対して駐車の方法の変更・場所の移動などの規制を行うべきものとされていること(道路交通法1条、51条)」を理由に、前記損害賠償を免れることはできない者と解するのが、相当である。」
(ポイント)
国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が「約87時間」にわたって放置されたにもかかわらず、道路管理者がこれに気付かず道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかったことは、国道としての道路管理に瑕疵がある。
76.大東水害訴訟(最判昭59.1.26)
(事案)
一級河川の指定を受けている谷田川を支川の1つとする寝屋川の流域は、低湿地が多いところであったが、戦後は急速な市街化が進行したため、流域の全体において浸水被害が発生するようになった。そこで、これに対応する治水対策として、昭和45年には本川の改修工事がほぼ完成したため、同46年以降は支川の改修が着手されたが、同程度の規模の水系に対する投資額としては全国一の費用が投下されたにもかかわらず、その全域の改修は完成に至っていなかった。そして、谷田川について昭和51年を目標に改修工事が行われていたが、国鉄野崎駅前付近については29戸の立退きと用地取得の手続を要し、それが進められていた昭和47年7月における豪雨により谷田川の溢水が生じ、同地域に居住するXらの家屋に床上浸水が発生した。
そこで、Xらは、谷田川の管理者たる国と、その管理費用の負担者たる大阪府、さらに近接する3本の排水路の管理者たる大東市(以上Yら)を被告として、国家賠償法2条1項および3条1項に基づく損害賠償訴訟を提起した。
(争点)
① 河川管理についての瑕疵の有無は、そのような基準ではんだんすべきか。
② 改修計画に基づいて改修中の河川における管理の瑕疵はどのように考えるべきか。
(判旨)
「我が国における治水事業の進展等により前示のような河川管理の特質に由来する財政的、技術的及び社会的諸制約が解消しただんかいにおいてはともかく、これらの諸制約によっていまだ通常予測される災害に対応する安全性を備えるに至っていない現段階においては、当該河川の管理にyついての瑕疵の有無は、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、前記諸制約のもとでの同種・同規模尾の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認しうる安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであると解するのが相当である。
そして、既に改修計画が定められ、これに基づいて現に改修中である河川については、右計画が全体として右の見地からみて格別不合理なものと認められないときは、その後の事情の変動により当該河川の未改修部分につき水害発生の危険性が特に顕著となり、当初の計画の時期を練り上げ、又は工事の順序を変更するなどして早期の改修工事を施行しなければならないと認めるべき特段の事由が生じない限り、右部分につき改修がいまだ行われていないとの一事をもって河川管理の瑕疵があるとすることはできないと解すべきである。そして、右の理は、人口密集地域を流域とするいわゆる都市河川の管理についても、前記の特質及び諸制約が存すること自体には異なるところがないのであるから、一般的にはひとしく妥当するものというべきである。」
(ポイント)
① 河川管理の瑕疵の有無は、諸般の事情を総合的に考慮し、河川管理における財政的・技術的・社会的諸制約の下での河川の管理の一般水準、社会通念に照らして是認しうる安全性、つまり過渡的安全性を備えていたか否かによって判断すべきである。
したがって、道路の場合と異なり、財政的な理由が免責事由となりうることに特に注意が必要となる。
●財政的理由と免責
道路(人工公物)→免責されない
河川(自然公物)→免責されうる
② 改修計画に基づき現に改修中の河川は、当該計画が過渡的安全性からみて格別不合理なものと認められないときは、後の事情変動により未改修部分につき特に改修工事を施行しなければならない特段の事由がない限り、当該河川管理に瑕疵はない。
77.多摩川水害訴訟(最判平2.12.13)
(事案)
多摩川は、昭和41年に河川法4条に基づき一級河川に指定され、同年7月に建設大臣が策定した「多摩川水系工事実施基本計画」に従い改修工事が順次実施されたが、狛江市猪方地区付近については、当該基本計画においても「改修工事完成区間」とされ、新規の改修計画はなかった。
ところが、昭和49年8月30日夜から降り続いた雨により、9月1日の昼頃には宿河原堰左岸の一部が破壊され、同日深夜から3日午後3時までの間に住宅面積約300平方メートル宇賀流失し、Xらの住宅19棟が失われる災害が発生した。ただし、この時の洪水の規模は、明治43年および昭和22年に発生した洪水とほぼ同程度のものであり、本件基本計画が定めた猪方地区付近の計画高水流量の毎秒4170平方メートルを下回るものであったことから、Xらは、多摩川の管理者である国(Y)に対し、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求める訴訟を提起した。
(争点)
河川の改修整備がなされた後に水害発生の危険の予測が可能になっていた場合には、それについての河川管理の瑕疵はそのように考えるできか。
(判旨)
「国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいい、このような瑕疵の存在については、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的、個別的に判断すべきものである。ところで、河川は、当初から通常有すべき安全性を有するものとして管理がかいしされるものではなく、治水事業を経て、逐次その安全性をたかめてゆくことが予定されているもんおであるから、河川が通常予測し、かつ、回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるに至っていないとしても、直ちに河川管理にかしがあるとすることはできず、河川の備えるべき安全性とおしては、一般的に施行されてきた治水事業の過程における河川の改修、整備の段階に対応する安全性をもって足りるものとした水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、河川管理における財政的、技術的及び社会的諸制約のもとで同種・同規模の河川の管理と一般的水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断するべきであると解するのが相当である。
ところで、本件河川部分は、基本計画策定後本件災害時までの間において、基本計画に定める事項に照らして新規の改修、整備の必要がないものとされていたところから、工事実施基本計画に準拠して改修、整備がされた河川と同視されるものであり、本件は、このような河川部分について、管理の瑕疵が問題となる事実である。
工事実施基本計画が策定され、右計画に準拠して改修、整備がされ、あるいは右計画に準拠して新規の改修、整備の必要がないものとされた河川の改修、整備の段階に対応する安全性とは、同計画に定める規模の洪水における流水の通常の作用から予測される災害の発生を防止するに足りる安全性をいうものと解すべきである。けだし、前記判断基準に示された河川管理の特質から考えれば、改修、整備がされた河川は、その改修、整備がされた段階において想定された洪水から、当時の防災技術の水準に照らして通常予測し、かつ、回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるべきものであるというべきであり、水害が発生した場合においても、当該河川の改修、整備がされた段階において想定された規模の洪水から当該水害の発生の危険を通常予測することができなかった場合には、河川管理の瑕疵を問うことができないからである。
また、水害発生当時においてその発生の危険を通常予測することができたとしても、右危険が改修、整備された段階においては予測することができなかったものであって、当該改修、整備の後に生じた河川及び流域の環境の変化、河川工学の知見の拡大又は防災技術の向上することはできない。けだし、右危険を除去し、又は減殺するための措置を講ずることについては、前記判断基準の示す河川管理に関する諸制約が存在し、右措置を講ずるためには相応の期間を必要とするものであるから、右判断基準が示されている諸事情及び諸制約を当該事実に即して考慮した上、右危険の予測が可能になった時点から当該水域発生当時までに、予測し得た危険に対する対策を講じなかったことが河川管理の瑕疵に該当するかどうかを判断すべきものであると考えられるからである。
(ポイント)
改修整備後に水害発生の危険が可能となった場合の河川管理の瑕疵は、(大東水害訴訟で示された)過去に発生した水害の規模や頻度の自然的条件、土地の利用状況その他の社会的条件、改修を要する緊急性の有無その程度といった諸般の事情、河川管理における財政的・技術的・社会的諸制約を考慮した上で、当該危険の予測が可能となった時点から現実の水害発生時までの間にその危険に対する対策を講じるべきであったか否かによって判断すべきである。
78.法定外公共用物の瑕疵(最判昭59.11.29)
(事案)
京都市の南西部を南北に流れる天神川の西側にある堤防兼用道のさらに西側を流れる溝渠は、元は農業用水路であって、河川法の適用も準用もないいわゆる普通河川であるが、その敷地はすべて国または京都府が所有していた。そして、京都府が昭和14年頃に天神川改修工事をした際に、その附帯工事として本件溝渠の整備をした結果、都市排水路としての機能を果たすようになったため、その後の人口の増加に伴う水量の増加に勾配があまりないことが加わり、本件溝渠の底にはかなりのヘドロがたまってしばしば溢水が生じるようになったので、住民の要望を受けた京都市(Y)が、京都府の担当部局と相談の上、昭和47年3月から本件溝渠の七条通りから八条通りまでの間の改修工事を順次進めていた。
ところが、同年の8月19日、すでに工事が終了している地点において、Xらの長男が本件溝渠を理由とする国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を請求したところ、Yは、京都府にはこのような普通河川の管理に関する条例がさだめられているが、市にはそのような条例がないため、本件溝渠の管理者にあたらないと主張した。
(争点)
国家賠償法2条1項が定める「公の営造物の設置又は管理」を解釈するにあたっては、当該営造物の所有の有無や管理についての法律的根拠をそのような考えるべきか。
(判旨)
「地方自治法2条3項2号は、河川、運河、溜池、用排水路、堤防等を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制することを地方公共団体の事務として掲げているのであるが、右の規定は地方公共団体の事務を提示しているにすぎず、右の規定から直ちに地方公共団体がその区域内の普通河川を法律上管理することとなるわけのものではなく、普通河川の管理に関する条例を定めていない上告人を普通河川である本件溝渠の法律上の管理者であるとすることはできない。しかしながら、国家賠償法2条にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物についいて法律上の管理権ないしは所有者、賃貸権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も同条にいう管理者に含まれるものと解するのを相当とするところ、地方公共団体の右規定が河川、運河、溜池、用排水路、堤防等の設置、管理等を地方公共団体の事務として掲げたのは、これらの施設の利用、管理が地域住民の生活と密接な関係を有することにかんがよってみ、当該地域住民に最も近い関係にある地方公共団体の事務とすることが適当であるとの考慮にでたものと解され、なかでも市街地にある普通河川は、都市排水路としての機能ばかりでなく、都市空間の確保等の機能の面においても住民の生活に密着した都市施設としての性格が極めて強いのであって、本件の場合においても、前示事実関係のもとにおいては、上告人は、地域住民の要望に答えて都市施設である排水路としての機能の維持、都市水害の防止という地方公共の目的を達成すべく、本件改修工事を行い、そえによって本件溝渠について事実上の管理をすることになったものというべきであって、本件溝渠について事実上の管理をすることになったものというべきであって、本件溝渠の管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国家賠償法2条に基づいてその損害を賠償する義務を負うものといわなければならない。そして、このことは、国又は京都府が本件溝渠について法律上の管理権をもつかどうかによって左右されるものではない。
(ポイント)
市内を流れる普通河川について、市がその所有者や法律上の管理権を持たない場合でも、地域住民の要望にこたえて地方公共団体の目的を達するためその改修工事を行い、事実上管理することになったときは、市は国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体にあたる。
79.補助金の交付と国家賠償法3条の費用負担者(最判昭50.11.28)
(事案)
三重県熊野市にある観光地の「鬼ヶ城」は吉野熊野国立公園の一部にあたり、三重県が自然公園法14条2項に基づく厚生大臣の承認を受けてそこを散策するための周回路を設置していた。会社の慰安旅行でこの鬼ヶ城を訪れたXが、周回路を散策中、途中にあるかけ橋から転落して下半身麻痺の大けがを負ったことから、Xが、当該周回路の設置・管理に瑕疵があったとして、国(Y)、三重県、熊野市に対して国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めて提訴したところ、第二審(大阪高判昭48.5.30)が、Yの責任を、同法2条1項の設置・管理としてではなく、3条1項に基づく費用負担者として設定したため、Yが上告した。
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条 前二条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
(争点)
地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対して国が補助金を交付している場合、国は、国家賠償法3条1項に規定する「国の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者」に該当するか。
(判旨)
ところで、自然公園法25条によれば、地方公共団体が国立公園事業を執行する場合、その執行費用は、この地方公共団体が負担すべきものとされているが、同法14条1項及び2項によれば、上告人が国立公園事業を執行すべきものとされ、地方公共団体は、上告人から承認を受けているその一部の執行をなしうるに止まり、また、同法26条によれば、国が地方公共団体に対し執行費用の一部を補助することができる旨定められているのである。そして、この補助金交付の趣旨・目的は、上告人が、執行すべきものとされている国立公園事業につき、一般的に地方公共団体に対しその一部の執行を勧奨し、自然公園法の見地から助成の目的たりうると認められる国立公園事業の一部につき、その執行を予定し又は執行している地方公共団体と補助金の交付契約を締結し、之を通じて右地方公共団体に対し、その執行を義務づけ、かつ、その執行が国立公園事業としての一定水準に適合するべきものであることの義務を課するとともに、当該事業の実施によって地方公共団体が被る財政的な負担の軽減をはかることにあるのであり、右の国立公園事業としての一定の水準には、国立公園事業としての一定の水準には、国立公園事業が国民の利用する道路、施設等に関するものであるときは、その利用者の事故防止に資するに足りるものであることが含まれるべきであることは明らかである。そして、原審が適法に確定したところによれば、上告人は、同法14条2項により三重県に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として本件かけ橋を含む本件周回路の設置を承認し、その際設置費用の半額に相当する補助金を交付し、その後の改修にも度々相当の補助金の交付を続け、上告人の本件周回路に関する設置費用の負担の割合は2分の1近くにも達しているのであるから、上告人は、国家賠償法3条1項の適用に関しては、本件周回路の設置費用の負担者というべきである。」
(ポイント)
国家賠償法3条1項の設置費用の負担者には、当該営造物の設置費用につき法律上の負担義務を負う者のほか、この者と同等かこれに近い設置費用を負担し、実質的には当該営造物による事業を共同執行していると認められる者で、当該営造物の瑕疵による危険を効果的に抑止しうる者も含まれる。
したがって、国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際当該設置費用の半額相当の補助金を交付し、その後の補修においても補助金を交付して周回路に関する設置費用の2分の1近くを負担しているときには、国は、国家賠償法3条1項が規定する公の営造物の設置費用の負担者に該当する。
80.郵便法違憲事件(最大判平14.9.11)
(事案)
Xは、Aに対する別件の損害賠償請求訴訟において勝訴したことから。債権差押命令の申立てを行い、これを受け、裁判所が発した債権差押命令の正本が書留郵便物の一種である特別送達郵便物の形式でAの預金があったB銀行C支店に送付されたところ、郵便業務従事者がこれを直接C支店に送達せず、C支店の私書箱に投函したため、当該送達がすくなくとも1日は遅れ、その間にAが当該差押えの対象になるべき預金を全額引き出してしまった。
そのため、Xは、当該送達の遅れによる損害の賠償を国家賠償法1条1項に基づき国(Y)に求めたが、Yは、郵便法68条が書留郵便物の亡失・き損などに限り一定の金額の範囲内の損害賠償を認めているにすぎないこと、および同法73条が損害賠償請求権者を当該郵便物の差出人またはその承諾を得た受取人に限定しエチルことを理由に、Xの請求を拒絶した。
(争点)
① 郵便法68条および73条のうと、書留郵便物について国の損害賠償責任を免除または制限している部分は、憲法17条に違反しないか。
② 郵便法68条および73条のうち、特別送達郵便物についての国の損害賠償責任を免除または制限している部分は、憲法17条に違反しないか。
(判旨)
「郵便物は、『郵便の役務をなるべき安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進すること』を目的として制定されたものであり(法1条)、法68条、73条が規定する免責又は責任制限もこの目的を達成するために設けられたものであると解される。すなわち、郵便官署は、限られた人員と費用の制約の中で、日々大量に取り扱う郵便物を、送達距離の長短、交通手段の地域差にかかわらず、円滑迅速に、しかも、なるべく安い料金で、あまねく、公平に処理することが要請されているのである。仮に、その処理の過程で郵便物に生じ得る事故について、すべて民法や国家賠償法の定める原則に従って損害賠償をしなければならないとすれば、それによる金銭負担が多額となる可能性があるだけでなく、千差万別の事故態様、損害について、損害が生じたと主張する者らに個々に対応し、債務不履行又は不法行為に該当する事実や損害額を確定するために、多くの労力と費用を要することになるから、その結果、料金の値上げにつながり、上記目的の達成が害されるおそれがある。したがって、上記目的の下に運営される郵便制度が極めて重要な社会基盤の一つであることを考慮すると、法68条、73条が郵便物に関する損害賠償の対象及び範囲に限定を加えた目的は、正当なものであるということができる。上記のような記録をすることが定められている書留郵便については、通常の職務規範に従って業務執行がされている限り、書留郵便物の亡失、配達遅延等の事故発生の多くは、防止できるであろう。
しかし、書留郵便物も大量であり、限られた人員と費用の制約の中で処理されなければならないものであるから、郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づく損害の発生は避けることのできない事柄である。限られた人員と費用の制約の中で日々大量の郵便物をなるべき安い料金で、あまねく、公平に処理しなければならないという郵便事業の特質は、書留郵便物についても異なるものではないから、法1条に定める目的を達成するため、郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じたにとどまる場合には、法68条、73条に基づき国の損害賠償責任を免除し、又は制限することは、やむを得ないものであり、憲法17条に違反するものではないということができる。
しかしながら、上記のような記録をすることが定められている書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為に基づき損害が生ずるようなことは、通常の職務規範に従って業務執行がされている限り、ごく例外的な場合にとどまるはずであって、このような事態は、書留の制度に対する信頼を著しく損なうものといわなければならない。そうすると、このような例外的な場合にまで国の損害賠償責任を免除し、又は制限しなければ法1条に定める目的を達成することができないとは到底考えられず、郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為についてまで免責又は責任制度を認める規定に合理性があるとは認め難い。以上によれば、法68条、73条の規定のうち、書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条が立法府に付与した裁量の範囲を逸脱したものといわざるを得ず、同条に違反し、無効であるというべきである。
特別送達は、民訴法第1篇第5章第3節に定める訴訟法上の送達の実施方法であり(民訴法99条)、国民の権利を実現する手続の進行に不可欠なものであるから、特別送達郵便については、適正な手続に従い確実に受送達者に送達されることが特に強く要請される。そして、特別送達郵便物は、書留優郵便物全体のうちのごく一部にとどまることが窺われるよう上に、書留料金に加えた特別の料金が必要とされている。また、裁判関係の書類についてい
えば、特別送達郵便物の差出人は送達事務取扱者である裁判所書記官であり(同法98条2項)、その適正かつ確実な送達に直接の利害関係を有する訴訟当事者等は自らがかかえあることのできる他の送付の手段を全く有していないという特殊性がある。さらに、特別送達の対象となる書類については、裁判所書記官(同法100条)、執行官(同法99条1項)、廷史(裁判所法63条3項)等が送達を実施することもあるが、その際に過誤が生じ、関係者に損害が生じたものであっても、被害者は、国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求し得ることになる。そうすると法68条、73条の規定のうち、特別送達郵便について、郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じる場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条に違反し、無効であるというべきである。」
(ポイント)
① 書留郵便物について、郵便業務従事者の故意・重過失により損害が生じた場合にも不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除・制限している郵便法68条と73条は、その範囲で憲法17条に違反し無効である。
② 特別送達郵便物について、郵便業務従事者の故意・過失により損害が生じた場合にも不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除・制限している郵便法68条と73条は、その範囲で憲法17条に違反し無効である。
憲法17条
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
郵便法68条、73条
(郵便約款)
第六十八条 会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
イ この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
ロ 郵便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項
ハ 郵便に関する料金の収受に関する事項
ニ その他会社の責任に関する事項
二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(審議会等への諮問)
第七十三条 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
一 第六十七条第三項、第六十八条第一項又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二 第六十七条第二項第三号又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
三 第七十一条の規定による命令をしようとするとき。
81.消防職員の過失と失火責任法(最判昭53.7.17)
(事案)
名古屋市内の店舗付住宅の2階貸室で火災が発生しているとの通報を受けて、同視(Y)の消防署職員が出勤したが、現場に到達した時にはすでに隣人により鎮火していたため、同職員は出火原因の調査と残り火の点検だけを行って引き上げたところ、およそ7時間半後に第一次出火の際の残り火が押入れから再燃して本件建物は全焼した。
そのため、本件建物の1階で喫茶店を営むXが、前記消防署職員には残り火の点検・出再火の危険回避を怠った過失があるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償をYに対して請求したところ、Yは同職員が約1時間にわたって点検・検証を行ったことを理由に、同職員には重過失はなく、国家賠償法4条に基づき失火責任法が準用されるため免責される旨を主張した。
(争点)
公権力の行使にあたる公務員の失火には、「失火ノ責任ニ関スル法律」が適用されるか。
※失火責任法は、「民放709条の規定は、失火の場合はこれを適用せず、但し、失火者に重大なる過失ありたるときは、この限りにあらず」と規定する。
(判旨)
「国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、同法1条1項の規定が適用される場合においても、民放の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民放709条の特則を規定したものであるから、国家賠償法4条の「民法」に含まれると解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の適用を排除すべき合理的理由も存しない。したがって、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法4条により失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失があることを必要とするものといわなければならない。
(ポイント)
失火責任法は、失火者の責任条件について民法09条の特則をきていしたものであるから、国家賠償法4条にいう「民法」に該当し、公権力の行使にあたる公務員の失火による国・公共団体の損害賠償責任にも適用される。
82.河川附近地制限令事件(最判昭43.11.27)
(事案)
Yは、名取川の堤外民有地の各所有者に対して賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたあところ、昭和34年12月11日付の宮城県告示により同地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けなければ砂利を搾取することができなくなった。しかし、Yは、知事に対する許可申請の拒否処分を受けた後も砂利採取等を続けたため、同令4条2号違反を理由とする同令10条に基づき罰金刑に処せられるべく、国(X)から起訴された。
これに対して、Yは、賃借料を支払い、労務者を雇い入れるなどの相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるという相当の損失を被るのであるから、同令4条2号による制限は特定の人に対して特別の財産上の犠牲を強いるものであり、当該制限にあたっては正当な補償がなされるべきであるにもかかわらず、それに対する補償を規定しておらず、かえって同令10条がこの制限違反者に対する罰則のみを定めていることは、憲法29条3項に違反するものであり、無効である旨などを理由に無罪を主張した。
憲法29条3項
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(争点)
損失補償に関する規定を定めていない河川附近地制限令4条2号およびその制限違反についての罰則を定める同令10条は、憲法29条3項に違反するか。
(判旨)
「河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍するべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがって、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。
もっとも、本件記録に現れたところによれば、被告人は、名取川の堤外民有地の各所有者
に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地令により、知事の許可を受けることなくして砂利を採取することができなくなり、従来、労務者を雇い入れ、相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合いであるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものだとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきとされる制限の範囲をこえ特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条及び5条による規制について同令7条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。しかし、同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆるばあいについて一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた」同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規程を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。
したがって、右各規程の違憲無効を口実にして、同令4条2号の制限を無視し、所定の許可を受けることなく砂利を採取した被告人に、同令10条の定める刑責を肯定した原判決の結論は、正当としてこれを指示することができる。」
(ポイント)
特別の犠牲を課した場合には、損失補償に関する規定が個別法令になくても、直接憲法29条3項を根拠にして補償請求が認められる余地がないわけではないので、補償規定を持たなくても、河川附近地制限令は直ちに違憲無効ではない。
83.奈良県ため池条例事件(最判昭38.6.26)
(事案)
代々ため池の堤とうで耕作を行ってきた者(Y)が、県の条例によりため池の堤とうの耕作を禁止された後も耕作を続けたため、起訴された。
(争点)
災害防止のために財産権を制限した場合、憲法29条3項の保障は必要か。
(判旨)
「ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも民法でも違法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民放が保障する財産権の行使の埒外にあるものというべく、従って、これらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。
本条例は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局すれは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上已むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、憲法29条3項の損失補償はこれを必要としない。」
憲法29条3項
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
(ポイント)
災害防止のための財産権の制限は、財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務だから、憲法29条3項の損失補償は必要ない。
84.収用目的の消滅と返還の是非(最判昭46.1.20)
(事案)
Xらの所有に属していた本件各土地は、昭和22年12月に自作農創設特別措置法3条に基づき国に買収されたが、その後売渡処分がなされないままの状態が続き、同28年12月に至って京都農政局長の認許により稲沢土地区画管理地区に編入されたため、愛知県知事(Y)が同36年11月2日に農地法36条に基づきAらにこれを売り渡した。
そこで、Xらは、当該売渡処分の取消しを求めて農林大臣(Z)に訴願を提起したが、却下されたため、Yを被告とする当該売渡処分の取消訴訟とZを被告とする裁決取消訴訟ならびに本件各土地についてのXらの売渡義務確認訴訟を提起した。
(争点)
① 農地法80条1項が、当該農地につき自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする旨の農林大臣の認定があったときは、これを売り払いまたは所管換・所属替をすることができるとした上で、同条2項が一定の要件に該当する場合にはこれを旧所有者に売り払わなければならない旨をさだめているにもかかわらず、農地法施行令16条4号が、この法80条1項による農林大臣の認定を、買収後新たに生じた公用等の目的に供すべき緊急の必要があり、かつその用に供されることが確実な土地に限定しているのは、法律による委任の範囲をこえて、法いるのではないか。
② 買収農地の旧所有者は、買収農地を自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、農林大臣に対して当該農地の売払いを求めることができないか。
(判旨)
「都道府県知事が自創法3条により買収した農地については法80条の適用があり(自創法3条、46条、農地法施行法5条、法9条、78条1項参照)、法80条1項は、農林大臣において買収農地が政令の定めるところにより自作農の創設または土地の農業上の利用の増進の目的と認めたときは、これを売り払い、またはその所管換もしくは所管替をすることができる旨を定め、同条2項は、右の場合には農林大臣は当該土地を旧所有者に売り払わなければならない旨を定め、しかも、農地法施行令(以下、令という。)16条4号は、買収農地が公用、公共用または国民生活の安定上必要な施設の用に供する(以下、公用等の奥的に供するという。)緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地であるときにかぎり農林大臣において法80条1項の認定をすることができる旨を定めている。
私有財産の収用が正当な補償のもとに行われた場合においてその後にいたり収容目的が消滅したとしても、法律上当然に、これを被収容者に返還しなければならないものではない。しかし、収容が行われた後当該収用物件につき収容目的となった公共の用に供しないことを相当とする事実が生じた場合には、なお、国がこれを保有させ、その処置を原則として国の裁量にまかせるべきであるとする合理的理由はない。したがって、このような場合には、被収容者にこれを回復する権利を保障する措置をとることが立法政策上当を得たものというべく、法80条の買収農地売払制度も右の趣旨で設けられたものと解すべきである。
ところで、令16条4号が、前記のように、買収農地のうち法80条1項の認定の対象となるべき土地を買収後新たに生じた公用等の目的に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実なものに制限していることは、その規定上明らかである。その趣旨は、買収の目的に優先する公用等の目的に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な場合にかぎり売り払うべきこととしたものと考えられる。同項は、その規定の体裁からみて、売払いの対象を定める基準を政令に委任しているものと解されるか、委任の範囲にはおのずから限度があり、明らかに法が売払いの対象として予定しているものを除外することは、前記法80条に基づく売払制度の趣旨に照らし、許されないところであるといわなければならない。農地改革のための臨時立法であった自創法とは異なり、法は、恒久立法であるから、同条による売払いの要件も当然、長期にわたる社会、経済状況の変化にも対処できるものとして規定されているはずのものである。したがって、農地買収の目的に優先する公用等の目的に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実であるという場合ではなくても、当該買収農地自体、社会的、経済的にみて、すでにその農地としてではなくても、当該買収計画自体、社会的、経済的にみて、すでにその農地としての現況を将来にわたって維持すき意義を失い、近く農地以外のものとすることを相当とするもの(法7条1項4号参照)として、買収の目的である自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする状況にあるといいうるものが生ずるであろうことは、当然に予測されるところであり、法80条は、もとよりこのような買収農地についても旧所有への売払いを義務付けているものと解されなければならんあいのである。したがって、同条の認定をすることができる場合につき、令16条が、自創法3条による買収農地については令16条4号の場合にかぎることとし、それ以外の前記のような場合につき法80条の認定をすることができないとしたことは、法の委任の範囲を超えた無効のものというほかはない。
これを要するに、旧所有者は、買収農地を自作農の目的に供しないことを相当する事実が生じた場合には、法80条1項の農林大臣の認定の有無にかかわらず、直接、農林大臣に対し当該土地の売払いをすべきこと、すなわち買受けの申込みに応じその承諾をすべきことを求めることができ、農林大臣がこれに応じないときは、民事訴訟法手続により農林大臣に対し右義務の履行を求めることができるものというべきである。したがって、このような場合に都道府県知事が右土地につき売渡処分をしたときは、旧所有者は、行政訴訟手続により右処分の取消しを求めることができるものといわなければならない。」
(ポイント)
① 農地法施行令が農地法に基づく認定ができる場合を限定し、明らかに農地法が売払いの対象として予定している土地につて認定できないようにしいることは、法の委任を超え。向こうである。
② 私有財産の収用が正当な補償の下に行われた場合には、一般には、その後に至って収容目的が消滅したとしても、法律上当然にこれを被収容者に返還しなければならないものではない。つまり、収容目的が消滅した後、返還しなくてもよい。
85.自作農創設特別措置法事件(最大判昭28.12.23)
(事案)
農地改革によって農地を買収されたXが、自作農創設特別措置法の買収価格の算定が著しく低額であるとして、増額を請求した。
(争点)
憲法29条3項の「正当な補償」とは、いかなる補償をいうか。
(判旨)
「憲法29条3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常にかかる価格完全に一致することを要するものではないと解するのを相当とする。」
(ポイント)
憲法29条3項の「正当な補償」は、相当な補償である。
86.土地収用法事件(最判昭48.10.18)
(事案)
Xらが所有する本件土地は、倉吉都市計画街路用地にあたっており、昭和39年1月14日において、起業者たる鳥取県知事Yから土地収用法旧33条に基づく鳥取県告示7号をもって、土地細目の公告がなされた。その上で、YとXらとの間での協議が調わないため、同年3月23日に都市計画法旧20条に基づき建設大臣による土地収用の制定がなされ、同年6月22日にその損失補償額についての鳥取県収用委員会の裁定が下された。
これに対して、Xらは当該損失補償額は近傍類地の取引の実例からして低すぎると主張して提訴した。
(争点)
土地収用法に基づき収用された土地の「補償」は、いかなる補償か。
(判旨)
「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な擬制の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収容者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要するものである。
(ポイント)
土地収用法における損失の補償は、完全な補償である。
87.ガソリンタンク事件(最判昭58.2.18)
(事案)
高松市内の国道沿いでガソリンスタンドを営むY(モービル石油)は、消防法に基づく市長の許可を得てガソリンタンク5基を地下に埋設していたところ、X(国)がその付近で地下道を設置したため、4基のタンクが当該地下道から水平距離にして10メートル以内のところに所在することとなり、消防法10条、12条ならびに危険物の規制に関する政令13条、危険物の規制に関する規則23条に違反する状態となった。そのため、当該地下貯蔵タンクの移設工事を余儀なくされたYは、道路法70条1項に基づく損失補償を求めて香川収用委員会に裁決の申請をなし、同委員会は907万円余の損失補償を認める旨の裁決を行った。
これに対して、Xは、当該裁決の取消しと損失補償支払債務の不存在の確認を求めて提訴した。
(争点)
道路工事の施行の結果、危険物の移転を余儀なくされたことによる損失は、道路法70条1項の定める損失補償の対象となるか。
(判旨)
「道路法70条1項の規定は、道路の新設又は改築のための工事の施行によって当該道路とその隣接地との間に高低差が生ずるなど土地の形状の変更が生じた結果として、隣接地の用益又は管理に障害を来し、従前の用法に従ってその用益又は管理を維持、継続していくためには、用益上の利便又は境界の保全等の管理の必要上当該道路の従前の形状に応じて設置されていた通路、みぞ、かき、さくその他これに類する工作物を増築、修繕若しくは移転し、これらの工作物を新たに設置し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合において、道路管理者は、これに要する費用の全部又は一部を補償しなけらばならないものとしたものであって、その補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するために已むを得ない必要があってした前記工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られると解するのが相当である。したがって、警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めている場合において、道路工事の施行の結果、警察違反の状態が生じ、危険物保有者が損失を被ったとしても、それは道路工事の施行によって警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至ったものにすぎず、このような尊実は、道路法70条1項の定める補償の対象に属しないものというべきである。」
(ポイント)
道路法70条1項の定める損失補償の対象は、一定の場合に限られるので、道路工事施行の結果、危険物保有者が基準に適合するように工作物の移転を余儀なくされても、警察規制に基づく損失がたまたま現実化するに至ったにすぎず、補償対象には含まれない。
つまり、本件では保障されないということ。
88.損失補償の支払時期(最大判昭24.7.13)
(事案)
昭和22年3月31日を政府に対する産米の割当供出の期限とされたYが、その期日までに割当量の一部を政府に売り渡さなかったため、食糧管理法違反を理由に懲役8か月の判決を受けたことから、Yは、それを不服として最高裁に再上告(『日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急手的措置に関する法律』により当時特別に認められていた手続)したが、その際、Yは、政府からの代金の支払いが約2か月後の5月20日であり、これは売買の目的物と代金の支払いが約2か月後の5月20日であり、これは売買の目的物と代金の支払いを同時期と推定する民法573条や双務契約における両債務についての同時履行の抗弁権を定める民放533条に違反するものであって、本件割当供出は違憲である旨を主張した。
(争点)
政府が食糧管理法に基づき個人の産米を買い上げるにあたっては、産米の供出と同時にその代金を支払わなければ、「正当な補償」の下に私有財産権を公共のために用いることを規定する憲法29条3項に違反することになるか。
(判旨)
「憲法第29条は、財産権の不可侵を規定すると共に『私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる』と定めている。従って、国家が私人の財産を公共の用に供するにはこれによって私人の被るべき損害を填補するに足りるだけの相当な賠償をしなければならないことは言うまでもない。しかしながら、憲法は『正当な補償』と規定しているだけであって、補償の時期についてはすこしも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことについては、憲法の保障するところではないといわなければならない。なければならない。もっとも、補償が財産の供与より甚しく遅れた場合には、遅延による損害をも填補する問題を生ずるであろうがだからといって、憲法は補償の同時履行までをも保障したものと解することはできない。
食糧管理法による、いわゆる供出米については、政府から買入代金の支払として正当な補償がなされることは公知の事実であり、再上告もまた、その受領を認めている。たゞ本件の買入代金の支払いは供出金後に行われたにすぎないのである。それが憲法違反でないことは前記の説明によって明らかであろう。されば、政府が食糧管理法に基き個人の産米を買上げるには供出と同時に代金を支払わなければ憲法第39条に違反するとの論旨は理由がない。」
(ポイント)
憲法は「正当な補償」と規定しているだけで、補償の時期については言明していないから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されることは、憲法は補償していない。つまり、同時履行でなくてよい。
89.予防接種事故(最判平3.4.19)
(事案)
X1(当時正誤6か月)は、小樽市保健所において(旧)予防接種法に基づく痘そうの予防接種を受けたところ、9日後に脊髄炎を発症し、その後下半身麻痺による運動障害および知能障害の重篤な後遺障害を残すに至った。
そのため、X1およびその両親(X2,X3)は、小樽市保健所予防課長が十分な予診を尽くさず、保健所長も十分な予診を行うことができるように措置しなかったとして、予防接種の小樽巣市長に委任した国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、また、小樽保健所予防課長および保健所長の給与負担者である小樽市に対しては国家賠償法3条1項に基づき損害賠償を請求するとともに、原審(札幌高判昭61.7.31)において憲法29条3項、25条等に基づく損失補償請求を予備的請求として追加した。
(争点)
痘そうの予防接種によって重篤な後遺障害が発生したばあいにおいて、(旧)予防接種実施規則(厚生省令)4条が規定する禁忌者に該当していたか否かの判断はいかに解すべきであるか。
(判旨)
「原審の理由とするところは、要するに、本件接種によって上告人X1の本件被害よりもが生じたものであるが、本件接種前の同上告人の症状は咽頭炎であり、遅くとも同月6日には解熱していたから、右咽頭炎は治癒していたものであり、本件接種当日、である同月8日に発熱がなかったから、本件接種当時において同上告人は禁忌者に該当せず、したがって、予診に不十分な点があったとしても、本件接種の実施は正当であったとするものである。
しかしながら、予防接種によって重篤な後遺障害が発生する原因としては、被接種者が禁記者に該当していたこと又は被接種者が後遺障害を発生しやすい個人的要因を有していたことが考えられるところ、禁忌者として掲げた事由は一般通常人なり得る病的状態、比較的多くみられる疾患又はアレルギー体質等であり、ある個人が禁忌者に該当する可能性は右の個人的要因を有する可能性よりもはるかに大きいものというべきであるから、予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、当該被接種者が禁忌者に該当していたことによって右後遺障害が発生した高度の蓋然性があると考えられる。したがって、予防接種によって右後遺障害が発生した場合には、禁忌者を識別するために必要される予診が尽くされたが禁忌者に該当すると認められる事由を発見することができなかったこと、被接種者は禁忌者に該当していたと推定するのが相当である。
この点を本件についてみるに、前記事実関係によれば、上告人X1が現在呈している後遺障害は、その全体にわたり、本件接種に起因するおのと認められるというのであるが、原審は必要な予診を尽くしたかどうかを審理せず、上告人X1が前記個人的素因を有していたと認定するものでもない。そして、咽頭炎とは咽頭部に炎症を生じているという状態を示す症状名でであって、咽頭炎が治癒したとは咽頭部の炎症が消滅したことをいうにすぎず、その原因となった疾患の治癒を示すものでもなければ、他の疾患にり患していないことを意味するものでもなく、原審が咽頭炎の治癒を認定した根拠は、要するに、上告人X1の解熱の経過にすぎず、また、記録によれば、本件接種当日において同上告人に発熱がなかったとの事実認定の基礎にされた上告人X2の供述も検温の結果に基づくものではなく、同上告人の観察に基づく判断にすぎないのである。そうであるとすると、原審認定事実によっては、いまだ同上告人が禁忌者に該当していなかったと断定することはできない。」
(ポイント)
痘そうの予防接種によって重篤な後遺障害が発生した場合には、禁忌者を識別するために必要とされる予診が尽くされたが禁忌者に該当する事由を発見することができなかったこと、被接種者が後遺障害を発生しやすい個人的素因を有していたこと等の特段のじじょうが認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたものと推定すべきである。
90.長野県勤務評定事件(最判昭47.11.30)
(事案)
長野県教育委員会教育長は、昭和34年に公布施行された「長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則」を実施するため、「長野県立学校職員の勤務評定実施要領」と「勤務評定書の様式および使用区分ならびに取扱要領」(いわゆる長野方式)を定めて、これを県立の各学校長宛に通達した。それによれば、当該勤務評定表書は評定者である学校長が記入する第二表Bの自己観察ならびに希望事項欄の記載方法としては、自己評価に基づき、「学校の指導計画が的確に実施されるように工夫しているか」「熱意をもって仕事にうちこんであるか」といったことが具体例に記入されることが求められていた。
これに対して、長野県立高校の教諭であるXら32名は、もし本件通達の定める自己観察表示義務の履行を強制されることになれば、自己自身の価値観の表示を義務付けられることになり、憲法によって保障された思想・良心・表現の自由等が害されることとなるが、他方で、当該表示義務を履行しなければ、懲戒その他の不利益処分を受けるおそれがあるとして、この法律上の地位の不安定を除去するため、当該表示義務の不存在確認を求めて出訴した。
(争点)
勤務評定にかかわる自己観察表示義務の不存在確認といった公法上の義務の不存在確認訴訟は、行政事件訴訟法上認められるか。
(判旨)
「所論の表示義務なるものは、それ自体その履行を直接強制されるような義務ではなく、その違反が懲戒その他の不利益処分の原因となるにすぎないものであるから、本訴の趣旨とするところを実質的に考察すれば、上告人らの過去もしくは将来における右義務の不履行に対し懲戒その他の不利益処分が行われるのを防止するために、その前提である上告人らの義務の不存在をあらかじめ確定しておくことにあるものと解される。ところで、具体的・現実的な争訟の解決を目的とする現行訴訟制度のもとにおいては、義務違反の結果として将来なんらかの不利益処分を受けるおそれがあるというだけで、その処分の発動を差し止めるため、事前に右義務の成否の確定を求めることが当然許されるわけではなく、当該義務の履行によって侵害を受ける権利の性質およびその侵害の程度、違反に対する制度としての不利益処分の確実性およびその内容または性質等に照らし、右処分を受けてからこれに関する訴訟のなかで事後的に義務の存否を争ったのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等、事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情がある場合は格別、そうではないかぎり、あらかじめ右のような義務の存否の確定を求める法律上の利益を認めることはできないものと解すべきである。
本件において原審の確定するところによれば、本件通達は、第二表Bの自己観察ならびに希望事項欄の記載方法として、自己評価に基づき、たとえば『学校の指導計画が的確に実施されるようにくふうしているか』、『分掌した校務を積極的に処理しているか』、『熱意をもって仕事にうちこんでいるか』というような第二表Aの観察内容やBの各項目等を参考にして、つとめた具体的に記入することと定めているにすぎない、というのであって(通達別冊第2項(25)、その文言自体、これを最大限に拡大して解釈するのでなければ、記入者の有する制会館、人生観、教育観等の表明を命じたものと解することはできない。してみれば、本件通達によって記載を求められる事項が、上告人らの主張するような内心的自由等に重大なかかわりを有するものと認めるべき義お売り的根拠はなく、上告人からこれを表示しなかったとしても、ただちに義務違反の責めを問われることが確実であるとは認められず、その他、上告人らにおいて不利益処分をまって義務の存否を争ったのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等の特段の事情の存在は、いまだこれを見出すことができないのである。所論は、行政事件訴訟法36条の規定をひいて、権利侵害のおそれさえあればその予防のための訴訟を広く認めるべきあると主張するが、前記説示に照らして採用することができない。
以上により、上告人らは、将来における不利益処分を防止するために、あらかじめほんけん通達の定める自己観察の結果の表示を義務を負わないことのっ確認を求める法律上の利益を有しないものというほかなく、本訴はこの点において不適合たるを免れない。」
(ポイント)
具体的な結論として、判例は、特段の事情がない限り、義務違反の結果として将来何らかの不利益処分を受けるおそれがあるというだけで、当該処分の発動を差し止めるため事前に義務の不存在の確認を求める訴えを提起することは、法律上の利益を欠き不適法である。とした。
ただし、判例は、結果的に認めてはいないが、公法上の義務の不存在確認訴訟が認められる余地を示唆していることに特に注意が必要である。
すなわち、行政事件訴訟は、法定の6つの累計に抗告訴訟を限定する趣旨ではなく、法定抗告訴訟以外の無名抗告訴訟(=法定外抗告訴訟)が認められる余地はあるとしているのである。
●抗告訴訟の類型
・法定抗告訴訟(3条)
① 処分の取消しの訴え(2項)
② 裁決の取消しの訴え(3項)
③ 無効等確認の訴え(4項)
④ 不作為違法確認の訴え(5項)
⑤ 義務付けの訴え(6項)
{C}⑥ 差止めの訴え(7項)
・無名抗告訴訟
●取消訴訟の主な訴訟要件
① 処分性
② 原告適格
③ 狭義の訴えの利益
④ 被告適格
⑤ 裁判管轄
⑥ 出訴期間
91.土地区画整理事業の事業計画決定(最判平20.9.10)
(事案)
浜松市(Y)は、遠州鉄道が線路の高架化を行なうのに合わせて、遠州上島駅周辺の約5.7ヘクタールの土地の再整備を計画し、平成15年11月17日に静岡県知事から土地区画調整法52条1項の規定に基づく事業計画の設計概要についての許可を受けた。そこで、Yは、同月25日に本件土地区画整理事業の事業計画の決定をし、その公告をしたところ、その施行地区内に土地を所有しているXらが、本件事業計画は無駄な投資であり周辺住民に悪影響を耐えるものであって、公共施設の整備改善および宅地の利用増進という法所定の事業目的を欠くとともに、その計画決定は地権者に相談なく一方的に決められたものだとして、本件事業計画の決定の取消しを求めて出訴した。
これに対し、原審(東京高判平17.9.28)は、最高裁昭和41年2月23日大法廷判決に従い、土地区画整理事業の事業計画は、当該土地区画整理事業の基礎的事項を一般的・抽象的に決定するものであって、いわば当該土地区画整理事業の青写真としての性質を有するにすぎず、これによって利害関係者の権利にどのような変動を及ぼすかが必ずしも具体的に確定されるわけではないから、それが広告された段階においても抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらず、したがって本件事業計画の決定の取消しを求める訴えは不適法なものであるとして却下した。これに対し、Xらが上告した。
(争点)
余地区画整理法に基づく土地区画整理事業の事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか。
(判旨)
「市町村は、土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規定及び事業計画を定めなければならず(法52条1項)、事業計画が定められた場合においては、市町村長は、遅滞なく、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない(法55条9項)。そして、この公告がされると、換地処分の公告がある日まで、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更若しくは建築場その他の工作物の新築、改築もしくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならず(法76条1項)、これに違反した者がある場合には、都道府県知事は、当該違反者又はその承継者に対し、当該土地の原状回復等を命ずることができ(同条4条)、この命令に違反した者に対しては刑罰が科される(法140条)。このほか、施行地区内の宅地についての所有者以外の権利で登記のないものを有し又は有することとなった者は、書面をもってその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならず(法85条1項)、施行者は、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、仮換地の指定や換地処分等をすることができることとされている(同条5項)
また、土地区画整理事業の事業計画は、施行地区(施行地区を工区に分ける場合には施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画という当該土地区画整理事業の基礎的事項を一般的に定めるものでるが(法54条、6条1項)、事業計画において定める設計の概要については、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならず、このうち、設計説明書には、事業施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の事業施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合が記載され(これにより、施行地区全体でどの程度の減歩がされるのが分かる。)設計図(縮尺1200分の1以上のもの)には、事業施行後における施行地区内の公共施設等の位置及び形状が、事業施行により新設され又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示されることから(平成17年国土交通省令第102号による改正前の土地区画整理法施行規則6条)、事業計画が決定されると、当該土地区画整理事業の施行によって施行地区内の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能になるのである。そして、土地区画整理事業の事業計画については、いったんその決定がされると、特段の事情がない限り、その事業計画に定められたところに従って具体的な事業がそのまま進められ、その後の手続きとして、施行地区内の宅地について換地処分が当然に行われることになる。前記の建築行為等の制限は、このような事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障害になるおそれのある事態が生ずるごとき防ぐために法的強制力を伴って設けられているのであり、しかも、施行地区内の宅地所有者等は、換地処分の公告がある日まで、その制限を継続的に課され続けるのである。
そうすると、施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がされることによって、前記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされるものということができ、その意味で、その法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはできない。
もとより、換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所有者等は、当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができるが、換地処分等がされた段階では、実際上、既に工事等も進捗し、換地計画も具体的に定められるなどしており、その時点で事業計画の違法を理由として当該換地処分等を取り消した場合には、事業全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない。それゆえ、換地処分等の取消訴訟において、宅地所有者が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、当該換地処分等を取り消すことは公共の福祉に適合しないとして事情判決(行政事件訴訟法31条1項)がされる可能性が相当程度あるのであり、換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴訟を提起することができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済が十分に果たされるとはいい難い。そうすると、事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性があるというべきである。
以上によれば、市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点からみても、これを対象とした抗告訴訟の「提起を認めるのが合理的である。したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。
これと異なる趣旨をいう最高裁昭和37年(オ)第122号同41年2月23日大法廷判決・民集20巻2号271頁及び最高裁平成3年(行ツ)第208号同4年10月6日第三小法廷判決・裁判集民事166号41ページは、いずれも変更すべきである。」
(ポイント)
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果が有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。
したがって、事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たる。
このように判例は、土地区画整理事業計画の決定について、従来の判例を変更して、処分性を肯定した。つまり、行政計画に処分性があり、とした。
92.輸入禁制品当該通知の処分性(最判昭54.12.25)
(事案)
輸入業者であるX社が女性ヌード写真集「サン・ワームド・ヌード」392冊について輸入申告をしたところ、横浜税関長(Y)は、昭和44年5月31日、Xの対し、当該写真集が関税定率法21条1項3号が定める「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」に該当する輸入禁制品であるとの同条3項に基づく通知をした。
これに対し、Xが同条4項の規定による異議の申出をしたところ、Yは、同年8月25日において、同条5項に基づきこの異議の申出を棄却する旨の決定をし、これをXに通知した。
そこで、Xは、関税法67条の規定に基づく税関長による検査が憲法21条2項が禁止する「検閲」に該当するとともに、当該写真集は風俗を害すべき書籍にもあたらないものとして、Yによる通知・決定の取消しを求めて出訴したが、原審(東京高判昭48.4.26)は、関税定率法21条3項に基づく通知自体は税関長による単なる観念の通知にとどまり、当該書籍、図画等についての輸入の禁止もしくは不許可の効果を生ぜしめるものではなく、これによって輸入申告者の権利・義務に何らの影響を及ぼすものではないから、Yによる通知・決定は抗告訴訟の対象たるべき処分に該当しないと判示して、Xの訴えを却下した、このため、Xは、当該通知が行政法学上の準法律的行政行為としての「通知」にあたるとして上告した。
(争点)
関税定率法21条3項に基づく通知、同条5項に基づく決定およびその通知は、抗告訴訟の対象である処分に該当するか。
(判旨)
「右3項の規定による通知並びに右5項の規定による決定及びその通知が行政庁のいわゆる観念の通知とみるべきものであることは、原判決の判示するとおりである。
しかしながら、輸入禁制品について税関長がその輸入を許可するものでないことは、関税違法67条、70条、71条、73条関税定率法21条等の規定に徴しあきらかである。そして、税関長において、輸入申告者に対し、関税定率法21条3項の規定による通知をし、又は、更に、輸入申告者からの異議の申出にかかわらず先の通知に示された判断を変更することなく維持し、同条5項の規定による決定及びその通知をした場合においては、当該貨物につき輸入の許可の得られるべくもないことがあきらかとなったものということができると同時に、関税定率法21条の規定の趣旨からみて、税関長において同条1項3号に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物について、税関長が同条3項及び5項に定める措置をとる以外に当該輸入申告に対し何らかの応答的行政処分をすることは、およそ期待され得ないところであり、他方、輸入申告者は輸入の許可を受けないで貨物を輸入することを法律上禁止されている(関税法111条参照)のであるから、輸入申告者は、当該貨物を適法に輸入する道を閉ざされるに至ったものといわなければならない。そして、輸入申告者の被るこのような制約は、輸入申告に対する税関長の応答的行政処分が未了である場合に輸入申告者がその間申告にかかる貨物を適法に輸入することができないという、行政事務処理手続に伴う一般的・経過的な状態化におけるものとは異なり、関税定率法21条3項の規定による通知又は同条5項の規定による決定及びその通知(以下、『関税定率法による通知等』という。)によって生ずるに至った法律上の効果である、とみるのが相当である(なお、前記のとおり税関長の判断の結果の表明である関税定率法による通知等により、輸入申告者が、それまで関税法67条の規定により負っていた義務、すなわち、貨物の輸入については税関長の許可を受けなければならないという一般的な義務を免れ、許可なしで当該貨物を輸入することができることとなると解しうるべき合理的根拠は、これを見出し難い。また、税関長において関税法138条ないし140条の規定によって通告及び措置を採ったとしても、これにつき刑事手続が必ず開始されるとは断定し得ず、ひいて当該貨物が輸入禁制品に該当するかどうかが右刑事手続おいて確定されるという保障はないのであるから、このことをもって原審の判示するように関税定率法による通知等の処分性を否定する一根拠とすることもできない。)。
そうすると、被上告人の関税定率法による通知等は、その法律上の性質において被上告人の判断の結果の表明、すなわち観念の通知であるとはいうものの、もともと法律の規定に準拠してされたものであり、かつ、これにより上告人に対し深刻にかかる本件貨物を輸入することができなくなるという法律上の効果を及ぼすというべきものであるから、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するもの、と解するのが相当である。」
(ポイント)
税関長が県税定率法21条3項に基づき輸入禁制品に該当する旨の通知をし、これに対する異議の申出につき同条5項に基づく棄却決定をして通知をした場合には、当該貨物を適法に輸入する道を閉ざされるのであるから、当該通知等が観念の通知といえ、その法律上の効果からみて、「処分」に該当する。
93.交通反則金の納付通告と取消し訴訟(最判昭57.7.15)
(事案)
大阪府警の警察官から駐車違反の事実を指摘されたXは、それが自己の行為によるものではないことを主張したため、現行犯逮捕された身柄を拘束された。そのため、Xは、早期釈放を願って翌日に反則金を仮納付し釈放されたが、後日、大阪府警察本部から仮納付を法納付とみなす効果をもつ反則金納付通告を受けた。
そこで、Xは、駐車違反者につき事実誤認があることを理由として、当該反則金納付通告の取消しを求めて出訴した。
(争点)
道路交通法127条1項の規定に基づく反則金の納付通告は、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象となるか。
(判旨)
「交通反則通告制度は、車両等の運転手がした道路交通法違反行為のうち、比較手軽微であって、警察官が現認する明白で定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警察本部長が低額の納付を通告し、その通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続が進行するということを骨子とするものであり、これによって、大量に発生する車両等の運転者の道路交通法違反事件について、事案の軽重に応じた合理的な処理方法をとるとともに、その処理の迅速化を図ろうとしたものである。
右のような交通反則通告制度の趣旨とこれを具体化した道路交通法の諸規定に徴すると、反則行為は本来犯罪を構成する行為であり、したがってその成否も刑事手続において審判されるべきものであるが、前記のような大量の違反事件処理の迅速化の目的から行政手続としての交通反則通告制度を設け、反則者がこれによる処理に服する途を選んだときは、刑事手続によらないで事案の終結を図ることとしたものと考えられる。道路交通127条1項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告(以下「通告」という。)があっても、これによる「通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意に右反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり、納付しないときは、検察官の公訴の提起によって刑事手続が開始され、その手続において通告の理由となった反則行為となるべき事実の有無等がしんぱんされることとなるものとされているが、これは上記の趣旨を示すものにほかならない。してみると、道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となった反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によってその効果の覆減滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求めて途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である。もしそうでなく、右のような抗告訴訟が許されるものとすると、本来刑事手続における審判対象として予定されている事項を行政訴訟手続で審判することになり、また、刑事手続と行政訴訟手続との関係について複雑困難な問題を生ずるのであって、同法がこのような結果を予想し、これを容認しているものとは到底考えられない。
右の次第であるから、通告に対する行政事件訴訟法による取消訴訟は不適法というべきであり、これと趣旨を同じくする原審の判断は正当である。」
(ポイント)
交通反則通告制度は、反則金の納付の通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは刑事訴追を行わないが、一定期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続を進行させることとする制度である。通告を受けた者がその自由意志により通告に係る反則金を納付したときは、抗告訴訟によってその効果を履滅することは許されず、当該通告の理由となった反則行為の不成立を主張したいのであれば、反則金を納付しないまま、後日の公訴提起を待って刑事訴訟手続の中で争うべきである。
したがって、当該通告に対して行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することは、不適法である。
94.主婦連ジュース事件(最判昭53.3.14)
(事案)
公正取引委員会(Y)は、昭和46年3月5日に、社団法人日本果汁協会ほか3名の申請に基づいて、飲料等の表示に関する厚生競争規約を認定したが、その内容において、果汁含有率5パーセント未満または果汁を含まない飲料については、その旨の表示に代えて、「合成着飲料」や「香料使用」などによる表示方法を認めていたことから、主婦連合会とその会長(Xら)が、それでは一般消費者に誤りなく伝えておらず、適正な表示とはいえないとして、不当景品類及び不当表示防止法10条6項に基づく不服申立てをYにしたところ、Yは、昭和48年3月14日に、Xらには不服申立適格がないとする旨の却下審決を行った。そこで、Xらは、この審決の取消しを求める訴訟を提起した。
(争点)
一般消費者は、不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項の規定による校正取引委員会の処分について不服があるもの」に含まれるか。
(判旨)
「不当景品類及び不当表示防止法(以下『景表法』という。)10条1項により公正取引委員会がした公正競争規約の認定に対する行政上の不服申し立ては、これにつき行政不服審査法(以下『行審法』という。)の適用を排除され(景表法11条)、専ら景表法10条6項の定める不服申立手続によるべきこととされている(行審法1条2項)が、行政上の不服申立の一種にほかならないのであるから、景表法の右条項にいう『第1項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの』とは、一般の行政処分についての不服申立の場合と同様に、当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利者若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、と解すべきである。
この点を公正競争規約の認定に対する不服申立についてみると、景表法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下『独禁法』という。)が禁止する不公正な取引方法の一類型である不当顧客誘引行為のうち不当な景品及び表示によるものを適切かつ迅速に規制するために、独禁法に定める規制手続の特例を定めた法律であって、景表法1条は、『一般消費者の利益を保護すること』をその目的として掲げている。ところが、まず、独禁法は、『公正且つ自由な競争を促進し一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。』と規定し(1条)、公正な競争秩序の維持、すなわち公共の利益の実現を目的としているものであることが明らかである。したがって、その特例を定める景表法も、本来、同様の目的をもつものと解するのが相当である。更に、景表法の規定を通覧すれば、同法は、3条において公正取引委員会は景品類の提供に関する事項を制限し又は景品類の提供を禁止することができることを、4条において事業者に対し自己の供給する商品又は役務の取引について不当な表示をしてはならないことを定めるとともに、6条において公正取引委員会は3条の規定による制限若しくは禁止又は4条の規定に違反する行為があるときは事業者に対し排除命令を発することができることを、9条1項、独禁法90条3項において排除命令の違反に対しては、罰則の適用をもってのぞむことを、 それぞれ定め、また、景表法10条1項において事業者又は事業者団体が公正取引委員会の認定を受けて公正競争規約を締結し又は設定することができることを定め、同条2項において公正取引委員会が公正競争規約の認定をする場合の制約について定めている。これらは、同法が、事業者又は事業団体の権利ないし自由を制限する規定を設け、しかも、その実効性は公正取引委員会による右規定の適正な運用によって確保されるべきであるとの見地から公正取引委員会に前記のような権限を与えるとともにその権限行使の要件を定める規定を設け、これにより公益の実現を図ろうとしていることを示すものと解しべきであって、このように、景表法の目的を¥とするところは交易の実現にあり、同法1条にいう一般消費者の利益の保護もそれが直接的な木庭であるか間接的であるかは別にして、公益保護の一環としてのそれであるというべきである。してみると、同法の規定にいう一般消費者も国民を消費者としての側面からとらえたものであるというべきであり、景表法の規定により一般消費者が受ける利益は、公正取引委員会による同法の適正な運用によって実現されるべき公益の保護を通じ国民一般が共通してもつにいたる抽象的、平均的、一般的な利益、換言すれば、同法の規定の目的である公益の保護の結果として生ずる反射的な利益
ないし事実上の利益であって、本来私人等権利主体の個人的な利益を保護することを目的とする法規により保障される法律上の利益とはいえないものである。もとより、一般消費者といっても、個々の消費者を離れて存在するものではないが、景表法上かかる個々の消費者の利益は、同法の規定が目的とする公益の保護を通じてその結果として保護されるべきもの、換言すれば、公益に完全に包摂されるような性質の者にすぎないと解すべきである。したがって、仮に、公正取引委員会による公正競争規約の認定が正当にされなかったとしても、一般消費者としては、景表法の規定の適正な運用によって得られるべき反射的な利益ないし事実上の利益が得られなかったにとどまり、その本来有する法律上の地位には、なんら消長はないといわなければならない。そこで、単に一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定につき景表法10条6項による不服申立をする法律上の利益をもつ者であるということはできないのであり、これを更に、『果汁等を飲用するという点において、他の一般の消費者と区別された特定範囲の者』と限定してみても。それは、単に反射的な利益をもつにすぎない一般消費者の範囲を一部相対的に限定したにとどまり、反射的な利益をもつにすぎない者であるという点において何ら変わりないのであるから、これをももって不服申立をする法律上の利益をもつ者と認めることはできないものといわなければならない。」
(ポイント)
不当景品類及び不当表示防止法の規定により一般消費者が受ける利益は、公正取引委員会による同法の適正な運用によって実現されるべき公益の保護の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上の利益であって、公正取引委員会による公正競争規約の認定につき不当景品類及び不当表示防止法10条6項による不服申立てをする法律上の利益とはいえない。
つまり、一般消費者は原告適格なり、ということになる。
●原告適格の有無
法律上の利益 →あり
反射的利益・事実上の利益 →なし
95.公衆浴場業距離制限規定事件(最判昭37.1.19)
(事案)
公衆浴場法2条が規定する公衆浴場の配置の適正基準につき、京都府公衆浴場法施行条例1条は、各公衆浴場との最短距離を250メートル間隔とする旨を定めていた。それにもかかわらず、京都府知事(Y)が、既設業者であるXの経営する浴場から208メートルしか離れていない所でのAの新規開業に対して許可を与えたことから、XらがこのYのAに対する営業許可の無効確認を求めて出訴したが、第一審、第二審ともに、新規業者に対する営業許可により既設業者が被る不利益は、単なる反射的利益にずぎず、法的に保護された利益とは認められないとして、Xらの原告適格を否定した。
(争点)
都道府県知事が第三者に対してなした公衆浴場許可処分について、既設業者は無効確認を求める原告適格を有するか。
(判旨)
「公衆浴場法は、公衆浴場の経営につき許可制を採用し、第2条において、『設置の場所が配置の適正を欠く』と認められるときは許可を拒み得る旨を定めているが、その立法趣旨は、『公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くべからざる、多分に公共性を伴う厚生施設である。そして、若しその設立を業者の自由に委せて、何等その偏在及び濫立を防止する等その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、その偏在により、多数の国民が日常容易に公衆浴場を利用しようとする場合に不便を来すおそれを保し難くmまた、その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を経済的に不合理ならしめ、ひいて浴場の衛生設備の低下等好ましからざる影響を来たすおそれなきを保し難い。このようなことは、上記公衆浴場の性質に鑑み、国民保険及び環境衛生の上から、出来る限り防止することが望ましいことであり、従って、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在乃至濫立を来たすに至るがごときは、公共の福祉に反するものであって、この理由により公衆浴場の経営の許可を与えないことができる旨の規定を設け』たのであることは当裁判所大法廷判決の判示するところである(昭和30年1月26日判決)。そして、同条はその3項に右設置場所の配置の基準については都道府県条例の定めるところに委任し、京都府公衆浴場法施行条例は各公衆浴場との最短距離は250米間隔とする旨を規定している。
これらの規定の趣旨から考えると公衆浴場法が許可制を採用し前述のような規定を設けたのは、主として『国民保健及び環境衛生』という公共の福祉の見地から出たものであることはむろんであるが、他面、同時に、無用の競争により経営が不合理化することのなきように濫立を防止することが公共の福祉のため必要であるとの見地から、被許可者を濫立による経営の不合理から守ろうとする意図をも有するものであることは否定しえないところであって、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によって保護せられる法的利益と解するを相当とする。」
(ポイント)
公衆浴場法は、被許可者を濫立による経営の不合理から守ろうとする意図をも有するので、行さhの営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益にとどまらず、公衆浴場法いよって保護される法的利益と解すべきである。つまり、公衆浴場の既設郷社には原告適格がある。
なお、一般的には、既設業者の営業上の利器は、反射的利益にすぎず、原告適格なしとされる場合が多いことに注意(例えば、質屋営業など)。
96.小田急高架化訴訟(最判平17.12.7)
(事案)
当時の建設大臣(現国土交通大臣)Yは、平成6年5月19日付けで、都市計画法59条2項に基づき、東京都に対し、小田急小田急線の喜多見駅付近から梅ヶ丘付近までの区間(「本件区間」)の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の認可(「本件鉄道事業許可」)をするとともに、本件区間の街路事業認可」)を行い、ともに同年6月3日付でこれを告示した。
これに対し、本件鉄道事業地内の不動産につき権利を有さないがその周辺地域に居住しているXら(その一部は本件各付属街路事業の事業地内の不動産については権利を有している。)が、本件鉄道事業による騒音や振動により健康や生活環境に著しい被害が生じるおそれがあるとして、本件都市計画事業認可の取り消しを求める訴えを提起した。
しかし、原審(東京高判平15。12.18)は、本件鉄道事業の事業地内に不動産を有しない者には原告適格が認められず、付属街路事業の事業地内に不動産上の権利を有する者の原告適格も、当該付属街路事業認可の取消しを求める限度でのみ認められるにすぎないと判示した。
(争点)
鉄道事業許可の取消しを求める原告適格は、当該鉄道事業地内に不動産上の権利を有する者に限られ、付属街路事業の事業地内に不動産上の権利を有する者を含めて、周辺地域に居住する者には一切認められないか。
(判旨)
「行政事件訴訟法9条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき『法律上の利益を有する者』とは、当該処分のより自己の権利若しくは法律上の利益若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消されるにとどめず、それが、帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解されるばあいには、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
そして、処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し、この場合において当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令の目的を共通にする慣例法令があるちきはその趣旨及び目的をも参酌し、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分がっその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するべきものである(同条2項参照)。
上記の見地に立って、まず、上告人れが本件鉄道事業認可の取消しを求める原告適格を有するか否かについて検討すると、都市計画事業の認可は、都市計画に事業の内容が適合することを基準としているものであるところ、前記アのような都市計画に関する都市計画法の規定に加えて、前記イの公害対策基本法等の規定の趣旨及び目的をも参酌し、併せて、都市計画法66条が、認可の告示があったときは、施行者が、事業の概要について事業地およびその付近地の住民に説明し、意見を聴取する等の措置を講ずることにより、事業の施行についてこれらの者の協力が得られるように努めなければならないと規定していることも考慮すれば、都市計画事業の認可に関する同法の規定は、事業に伴う騒音、振動等によって、事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境の被害が発生することを防止し、もって健康で文化的な都市生活を確保し、良好な生活環境を保全することも、その趣旨及び目的とするものと解される。都市計画法は又はその関係法令に違反した違法な都市計画の決定又は変更を基礎として都市計画事業の認可がされた場合に、そのような事業に起因する騒音、振動等による被害を直接的に受けるのは、事業地の周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ、その被害の程度は、居住地が事業地に接近するにつれて増大するものと考えられる。また、このような事業に係る事業地の周辺地域に居住する住民が、当該地域に居住し続けることにより上記の被害を反復、継続して受けた場合、その被害は、これらの住民の健康や生活環境に係る著しい被害にも至りかねないものである。そして、都市計画事業の認可に関する同法の規定は、その趣旨及び目的にかんがみれば、事業地の周辺地域に居住する住民に対し、違法な事業にい起因する騒音、振動等によってこのような健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体井的な利益を保護しようとするものと解されているところ、前記のような被害の内容、性質、程度等に照らせば、この具体的な利益は、一般的功績の中に吸収解消されることが困難なものといわざるを得ない。
以上のような都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定の趣旨及び目的、これらの規定が都市計画事業の認可の制度を通して保護しようとしている利益の内容及び性質等を考慮すれば、同法は、これらの規定を通じて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るなどの公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相応である。したがって、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するものといわなければならない。
(ポイント)
都市計画事業の事業地周辺に居住する住民のうち、当該事業が実施されたことで騒音、振動等による健康、生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、原告適格を有する。
97.原子炉もんじゅ事件(最判平4.9.22)
(事案)
動力炉・核燃料開発事業団(現独立行政法人日本原子力研究開発機構)が福井県敦賀市に建設・運転を計画した高速増殖炉「もんじゅ」について、昭和58年5月27日に宮沢喜一内閣総理大臣(Y)が行った「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」23条、24条に基づく原子炉設置許可処分に対し、周辺地域に居住する住民がその無効確認を求めて出訴した。これに対し、原審(名古屋高金沢支判平元7.19)は、無効確認訴訟の訴えの利益は認めたものの、原子炉から半径20キロメートルの範囲内に居住する住民にのみ原告適格を認めるにとどまった。そおこで、一部敗訴となった住民(Xら)と内閣総理大臣(Y)の双方が上告に及んだ。
(争点)
設置許可申請に係る原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし約58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき行政事件訴訟法36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当するか。
(判旨)
「行政事件訴訟法9条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条にいう当該処分の取消しを求めるにつき、『法律上の利益を有する者』とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである(最高裁昭和53年3月14日第三小法廷判決、最高裁昭和57年9月9日第一小法廷判決、最高裁平成元年2月17日第二小法廷判決参照)・そして、当該行政法規が、不特定多数の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の内容・性質等考慮して判断すべきである。行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えの原告適格について規定するが、同条にいう当該処分の無効等の確認を求めるにつき、『法律上の利益を有する者』の意義についても、右の取消訴訟の原告適格の場合と同義に解するのが相当である。
規制等は、原子力基本法の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、精錬、加工、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行うなどを目的として制定されたものである(1条)。規制法23条1項に基づく原子炉の設置申請は、同項各号所定の原子炉の区分に応じ、主務大臣に対して行われるが、主務大臣は、右許可申請が同法24条1項各号に適合していると認められるときでなければ許可をしてはならず、また、右許可をする場合においては、あらかじめ、同項1号、2号及び3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び4号に規定する基準の適用については、核燃料物質及び原子炉に関する安全の確保のための規制等を所管事項とする原子力安全委員会の意見を聞き、これを充分に尊重してしなければならないものとされている(24条)。そして、同法24条1項3号所定の技術的能力の有無及び4号所定の安全性に関する各調査に過誤、欠落があった場合には重大な原子力事故が起こる可能性があり、事故が起こったときは、原子炉施設に近い住民ほど被害を受ける蓋然性が高く、しかも、その被害の程度はより直接的かつ重大なものとなるのであって、特に、原子炉施設の近くに居住する者はその生活、身体等に直接的かつ重大な被害を受けるものと想定されるものであり、右各号はこのような原子炉の事故等がもたらす災害による被害の性質を考慮した上で、右技術的能力及び安全性に関する基準を定めているものと解される。右の3号(技術的能力に係る部分に限る。)及び4号の設けられた趣旨、右各号が考慮している被害の性質等にかんがみると、右各号は、単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、原子炉施設周辺に居住し、右事故等がもたらず災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護するものとする趣旨を含むと解するのが相当である。
上告人らは本件原子炉から約29キロメートルないし58キロメートルの範囲内の地域に居住していること、本件原子炉は研究開発段階にある原子炉である高速増殖炉であり(規制法23条1項4号、同法施行令6条の2第1項1号、動力炉・核燃料開発事業団法2条1項参照)、その電気出力は28万キロワットであって、炉心の燃料としてはウランとプルトニウムの混合酸化物が用いられ、炉心内において毒性の強いプルトニウムの増殖が行われるものであることが記録上明らかであって、かかる事実に照らすと、上告人らは、いずれも本件原子炉の設計許可の際に行われる規制法24条1項3号所定の技術的能力の有無及び4号所定の安全性に関する各審査に過誤、欠落がある場合に起こり得る事故等のより直接的かつ重大な被害を受けるものと規定される地域内に居住する者というべきであるから、本件設置許可処分の無効確認を求める本訴請求において、行政事件訴訟法36条所定の『法律上の利益を有する者』に該当するものと認めるのが相当である。
行政事件訴訟法36条によれば、処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えにうおって目的を達することができないものに限り、提起することができると定められている。処分の無効確認訴訟を提起し得るための要件の一つである。右の当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、当該処分に基づいて生ずる法律関係に関し、処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のために被っている不利益を排除することができない場合はもとより、当該処分に起因する紛争を解決するための争訟形態として、当該処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分の無効確認を求める訴えのほうがより直載的で適切な形態であるとみるべき場合をも意味するものと解するのが相当である(最高裁昭和45年11月6日第二小法廷判決、最高裁昭和63年4月17日第二小法廷判決参照)。」
(ポイント)
設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法36条にいう、「法律上の利益を有する者」に該当する。そして、設置許可申請に係る電力出力28万キロワットの原子炉(高速増殖炉)から約29キロメートルないし58キロメートルの範囲内の地域に居住している住民は、当該『法律上の利益を有する者』に該当する。
98.選挙の立候補と免職処分の取消し訴訟(最大判昭40.4.28)
(事案)
名古屋郵便局管内の白子郵便局に勤務していたXは、昭和24年8月12日に、行政機関職員定員法附則3則および国家公務員法78条4号の規定に基づき、名古屋郵便局長(Y)により免職された。そこで、これを不服とするXは、本件処分の取消訴訟を提起したが、当該訴訟の係属中の昭和26年4月に鈴鹿市議会議員選挙に立候補して当選した。そのため、Y側は、公務員が公職の選挙に立候補したときは公職選挙法90条の規定によりその届出の日に当該公務員の職を辞したものとみなされる以上、仮に本件免職処分が取り消されてもXは郵政省の職員たる地位を回復できないのであるから、Xには訴えの利益が消滅している旨を主張した。
(争点)
免職された公務員が当該免職処分の取消訴訟の係争中に公職の立候補者として届出た場合において、行政事件訴訟法9条の訴えの利益をどのように考えるべきか。
(判旨)
「行政事件訴訟法9条は、『処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。』と規定している。
しかして、原判決の認定にかかる前示事実に照らせば、本件免職処分が取り消されたとしても、上告人は市議会銀に立候補したことにより郵政省の職員たる地位を回復するに由ないこと。まさに、原判決説示のとおりである。しかし、公務員免職の行政処分は、それが取り消されない限り、免職処分の効力を保有し、当該公務員は、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから、本件免職処分の効力を排除する判決を求めることは、右の権利、利益を回復するための必要な手続であると認められる。そして、法9条が、たとえ注意的にもしろ、括弧内において前記のような規定を設けたことに思いを致せば、同法の下においては、広く利益を認めるべきであって、上告人が郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなって現在においても、特段の事情の認められない本件において、上告人の叙上のごとき権利、利益が害されたままになっているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人は、なおかつ、本件訴訟を進行する利益を有するものと認める。
(ポイント)
公務員免職処分は、それが取り消されない限り、公務員として有するはずであった給料請求権などについて裁判所の救済を求めることができないから、たとえ以前の地位を回復できなくなっても、当該訴訟を追行する利益を有する。つまり、訴えの利益は消滅しない。
●訴えの利益の有無(狭義の)
処分・裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分・裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する場合を含む。
99.会議の公開の瑕疵と原告の死亡(最判昭49.12.10)
(事案)
京都市立旭ヶ丘中学校教諭であったAら3名は、転勤命令に従わなかったため、地方公務員法29条1項1号および2号所定の懲戒事由に該当するとして、昭和29年5月に京都市教育委員会(Y)から懲戒免職処分を受けた。しかし、旧教育委員会法37条1項本文が会議公開の原則を定めた上で、非公開にする場合は出席委員の3分の2以上の多数で議決を要すると規定していた(同条項但書)にもかかわらず、当該処分を決した同委員会の臨時会おいては、非公開のまま委員長により開会が宣言され、その1,2分後に出席委員5名の全員一致で会議を秘密とする旨の議決がなされるという手続がとられていた。
そこで、Aらが、当該懲戒免職処分を決した本件会議には手続上の瑕疵があるとして、処分取消の訴えを提起したところ、訴訟係属中の昭和40年10月23日に原告の1人であるAが死亡したため、その相続人であるXが訴訟継承の申立てをしたが、大阪高等裁判所は、昭和43年11月19日の判決において、取消訴訟の訴訟追行権は一身専属のものであり、Xが本訴を承継することはできないとして、Aに関する訴訟が終了した旨を宣言した。
(争点)
免職された公務員が当該免職処分の取消訴訟の継続中に死亡した場合、その相続人には訴訟承継が認められるか。
(判旨)
「本件免職処分は、被上告委員会の出席委員5名全員一致により秘密会で審議することとされた会議において、議決されたものであるが、右秘密会で審議する旨の議決そのものに公開違反の瑕疵があり、その瑕疵がひいて右免職処分の議決をも違法ならしめるものであると主張されているのである。しかし、原審の認定するところによれば、被上告委員会においては、従来人事に関する案件はすべて秘密会で審議されているものであって、各委員ともこれを了知しており、さればこそ上告人らについての人事に関する本件処分案件も出席委員全員の賛成により秘密会で審議することとされていたというのであるから、右秘密会で審議する旨の議決自体はいわば予定されていたとところともいえるのであって、これを公開の会議で行うことは、その議決の公正を確保する面からは実質的にさして重要な意義を有するものではなかったということができる。また、原審確定の事実に徴すれば、被上告委員会において、本件処分案件を秘密会で審議する旨の議決を全面的に非公開で行うこととする積極的な措置をとったものとまでは認められず、むしろ、上告人ら旭ヶ丘関係者だけが傍聴することができない状況のもとで会議が開かれたため、会議の完全な公開がその限度でされなかったことにとどまり、右秘密会で審議する旨の議決が全く秘密裡にされたものであるということもできないのである。以上の点をあわせて考えるときは、本件免職処分の議決には、その審議を秘密会でする旨の議決が完全な公開のもとにない会議で行われたという点において形式上公開違反の瑕疵があるとはいえ、右処分案件の議事手続全体との関係から見れば、その違反の程度及び態様は実質的に前記公開原則の趣旨目的に反するというに値いしないほど軽微であり、これをもって右免職処分の議決そのものを取り消すべき事由とするには当たらないものと解するのが、相当である。
Aは、本訴係属中に死亡したことにより、もはや将来にわたって公務員としての地位を回復するに由ないこととなったことは明らかであるが、本件免職処分後死亡に至るまでの間に公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利を主張することができなかったという法律状態は依然として存続しており、その排除、是正のためには遡って右処分の取消しを必要とするのであるから、将来における公務員の地位の回復が不可能になったというだけでは、右処分の取消しを求める法律上の利益ないし適格が失われるものではない(行政事件訴訟法9条、当裁判所昭和40年4月28日大法廷判決参照)。そして、右の場合、原告である当該公務員が訴訟係属中に死亡したとしても、免職処分の取消しによって回復される右給料請求権等が一身専属的な権利ではなく、相続の対象となりうる性質のものである以上、その訴訟は、原告の死亡により訴訟追行の必要が絶対的に消滅したものとして当然終了するものではなく、相続人において引き続きこれを追行することができるものと解すべきである。けだし、免職処分の取り消す判決によって給料請求権を回復しうる関係は、右取消しに付随する単なる法律要件的効果ないし反射的効果ではなく、取消訴訟の実質的目的をなすものであって、その訴訟の原告適格を基礎づける法律上の利益とみるべきことは前記のとおりであるから、右利益が相続によって承継されるものであるときは、これに伴い原告適格も相続人に承継されると解するのを相当とするからである。そして、この結論は、免職処分の取消訴訟が右給料請求権等を直接的訴訟物とするものでないことによって、なんら左右されるものではない。それゆえ、Aの提起した本件訴訟は、同人の死亡によって当然終了するものではなく、相続人たる上告人Xにおいてこれを承継するものである。」
(ポイント)
免職された公務員が訴訟係属中に死亡しても、免職処分取消しによって回復される給料請求権が一身専属的な権利ではなく、相続の対象となるものだから、それに伴い原告適格も相続人に承継される。
100.工事の完了と訴えの利益(最判昭59.10.26)
(事案)
Aらが仙台市の建築主事(Y)に対して共同住宅2棟についての建築確認を建築基準法6条1項に基づき申請したところ、Yはそれらについての確認処分を行った。これに対して、陳地に居住するXが、当該建築物の敷地に隣接する通路は建築基準法43条が定める接道義務の対象となる同法42条の道路の要件を充たしていないなどの点で違法であり、また、当該建築物の建築により保健衛生上影響を受けるとともに火災等の危険にさらされるおそれがあると主張して、仙台市建築審査会に対して本件確認処分の取消しを求める審査請求をなしたが、棄却裁決を受けた。
そこで、Xは、Yを被告とする本件確認処分の取消訴訟を提起したが、すでにその時点では当該建築物の建築工事は完了していた。
(争点)
建築確認を受けて着手していた建築工事が完了した場合には、確認処分の取消しを求める訴えの利益は消滅するか。
(判旨)
「建築基準法によれば、建築西は、同法6条1項の建築物の建築等の工事をしようとする場合においては、右工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下『建築関係規定』という。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならず(6条1項。以下この確認を『建築確認』という。)建築確認を受けない右建築物の建築等の工事は、することができないものとされ(6条5項)、また、建築主は、右工事を完了した場合においては、その旨を建築主事に届け出なけれならず(7条1項)、建築主事が右届出を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の史員は、届出に係る建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを検査し(7条2項)、適合していることを認めたときは、建築主に対し検査済証を交付しなければならないものとされている(7条3項)。そして、特定行政庁は、建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、建築主等に対し、当該建築物の除去その他これらの規定に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる(9条1項。以下この命令を『違反是正命令』という。)、とされている。これらの一連の規定に照らせば、建築確認は、建築基準法6条1項の建築物の建築等の工事が着手される前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合していることを公権的に判断する行為であって、それをうけなければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということができる。しかしながら、右工事が完了した後における建築主事等の検査は、当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを基準とし、同じく特定行政庁の違反是正命令は、当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基準とするものでない以上、違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量にゆだねられているから、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発する上において法的障害となるものではなく、また、たとえ建築確認が違法であるとして判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるものではない。
したがって、建築確認証は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」
(ポイント)
建築確認は、それを受けなければ当該工事ができないという法的効果を付与されているにすぎないものであるから、当該工事がっ完了した場合には、それにより建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。
101.皇居前広場事件(最大判昭28.12.23)
(事案)
日本労働組合評議会(X)は、昭和26年11月10日付で、昭和27年5月1日のメーデーのために皇居外苑の使用許可を求める申請を管理者たる厚生大臣(現厚生労働大臣)Yになしたが、Yは、国民公園管理規則4条に基づき、昭和27年3月13日にこれを不許可とした。このため、Xは、当該処分が表現の自由を保障する憲法21条や勤労者の団結権を保障する憲法28条に違反しているとして、その取消を求めて出訴したが、その訴訟の係属中に本件申請に係る同年5月1日が経過したことから、第二審の東京高等裁判所は、それにより原告が処分の取消しを求める権利保護の利益がなくなったとして請求を棄却したため、Xが上告した。
(争点)
公園使用についての不許可処分の取消しを求める訴えについては、使用すべき日が経過することにより判決を求める法律上の利益が失われることとなるか。
(判旨)
「上告人の原審における本訴請求の趣旨は、上告人の昭和26年11月10日附『昭和27年5月1日メーデーのための皇居外苑使用許可申請』に対して被上告人が同年3月13日になした不許可処分は違法であるから、これが取消を求めるというのである。そして、実体法が訴訟上行使しなければならないものとして認めた形成権に基づくいわゆる狭義の形成訴訟の場合にあっては、法律がかかる形成権を認めるに際して当然訴訟上保護の利益があるようその内容を規定しているのであるから、抽象的には所論のごとくその権利発生の法廷要件を充たす限り一応その訴は保護の利益あるものといい得るであろう。しかし、狭義の形成訴訟の場合においても、形成権発生後の事情の変動により具体的に保護の利益なきに至ることあるいは多言を要しないところである。(例えば離婚の訴提起後協議離婚の成立した場合の如きである。)また、被上告人は同年5月1日における皇居外苑の使用を許可しなかっただけで、上告人に対して将来に亘り使用を禁じたものでないことも明白である。されば、上告人の本訴請求は、同日の経過により判決を求める法律上の利益を喪失したものといわなければならない。そして、原判決は、上告人の本訴請求を権利保護の利益なきものとして棄却の裁判をしたのもであって、裁判そのものを拒否したものではなく、憲法32条に違反したものとはいえない。また、原判決は、本訴のごとき訴は、所期の日時までに確定判決を受けることも不可能ではないと判断したものであるから、憲法76条2項の保障に反したものともいえない。」
(ポイント)
特定の期日における公園の使用を求める申請に対する不許可処分の取消訴訟は、当該期日の経過により判決を求める法律上の利益が失われる。本件では、「5月1日」が過ぎれば、訴えの利益がなくなるということになる。
102.運転免許停止処分と訴えの利益(最判昭55.11.25)
(事案)
Xは、道路交通法33条が定める列車踏切での一旦停止義務を怠ったとして義務違反点数を加算された結果、それまで累積点数と合わせて、福井県公安委員会(Y)指導下の福井県警察本部長から自動車運転免許の効力を30日間停止する処分を昭和48年12月17日に受けた(ただし、Xが、同日、法定講習を受けたため、29日間の短縮を受け、翌18日までの停止処分となる。)しかし、Xはこれを不服としてYに審査請求をしたが、昭和49年4月12日に棄却裁決を受けた。
そこで、Xは、原処分ならびに当該棄却裁決の取消しを求めて出訴したところ、Y側は、原処分の日から無違反・無処分で1年が経過すれば、その翌日からは当該処分を理由にXが道路交通法上不利益を受けるおそれはなくなり、他にも当該処分を理由にXが不利益に取り扱われることを認める法令の規定はないのであるから、当該機関の経過によりXには原処分および裁決の取消しにより回復すべき法律上の利益はなくなっていると主張した。これに対し、原審(名古屋高判52.12.14)は、Xには原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に当該処分が存した事実を覚知され、名誉・感情・信用等を損なう可能性が常時継続する以上、それを排除することは法の保護に値する利益であると解した。そこで、Y側が上告した。
(争点)
自動車運転免許の効力停止処分後無違反・無処分で1年を経過した場合には、当該処分の取消しを求める訴えの利益は消滅するか。
(判旨)
「原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は、昭和48年12月17日被上告人に対し自動車運転免許の効力を30日間停止する旨の処分(以下『本件原処分』という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を29日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から万年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件処分の効果は右処分の日1日の期間の経過によりなくなったものであり、また、本件原処分の日から1年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなったことはもとより、他に本件処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法9条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。
この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもって被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当であり。」
(ポイント)
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、当該処分の日から無違反・無処分で1年を経過すれば、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しない。当該記載のある免許証により警察官に処分があった事実を知られ、名誉・感情等を損なうとしても、それは事実上の効果にすぎないからである。
103.審査決定における附記理由の不満(最判昭37.12.26)
(事案)
X株式会社の青色申告承認を取り消す旨の処分を芝税務署長(Y)が行ったため、X社はこれを不服として東京国税所長(Z)に審査請求をしたところ、Zはこれを棄却したが、その際、審査決定の通知書には「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行った青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません。」とのみ決定理由が示されていた。
そのため、X社は、Yを被告とする青色申告書提出承認の取消処分の取消訴訟とともに、Zがした棄却決定には審査決定の書面に理由を附記すべきものとした法人税法35条5項に違反する瑕疵があるとして、Zを被告とする審査請求決定の取消訴訟を提起した。
(争点)
{C}① 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行った青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません。」とのみ決定理由を記載することは、当該審査決定の取消事由になるか。
{C}② 原処分とそれを維持した審査決定の取消しを同時に求める訴えにおいて、原処分の取消請求を棄却すべき場合にも、審査決定の理由附記に不備があれば、当該決定は取り消さなければならないか。
(判旨)
法人税法35条5項(昭和37年法律67号による解除前)が、審査決定の書面に理由を附記すべきものとしているのは、訴願法や行政不服審査法による裁決の理由附記と同様に、決定機関の判断を慎重ならしめるとともに、審査決定が審査機関の恣意に流れることのないように、その公正を保障するためと解されるから、その理由としては、請求人の不服の事由に対応してその結論に到達した過程を明らかにしなかればならない。ことに本件のように、当初税務署長がした処分に理由の附記がない場合に、請求人の請求を排斥するについては、審査請求書記載の不服の事由が簡単であっても、同処分を正当とする理由を明らかにしなければならない。このように考えるならば、前記、本件審査決定の理由は、理由として不備であることが明白であって、この点に関する原判示は正当である。このことは、請求人が棄却の理由を推知できる場合であると否とにかかわりのないものと解すべきである。
「法律が審査決定に理由を附記すべき旨を規定しているのは、行政機関として、その結論に到達した理由を相手方国民に知らしめることを義務づけているのであって、これを反面からいえば、国民は自己の主張に対する行政機関の判断とその理由とを要求する権利を持つともいえるのである。従って、原判決のいうように、審査決定に対する不服の訴訟において、当事者が、審査請求に際しての主張事実、決定に際しての認定事実等に拘束されないという一事をもって、理由附記に不満のある決定を取り消すことがゆるされないということはできない。換言すれば、理由にならないような理由を附記するに止まる決定は、審査決定手続に違法がある場合と同様に、判決による取消を免れないと解すべきである。
しかし、本件の場合は、上告人は芝税務署長がした原処分の取消をも訴求しており、その理由がないことは、原判示のとおりであり、上告人も本件上告において取消処分の内容については何等の不服も述べていないのである。審査請求も、結局は、上告人に対する青色申告書提出承認の取消処分の取消を求める趣旨である以上、上述のような理由附記の不備を理由に、本件審査決定を取り消すことは全く意味がないことというべきであろう。けだし、本件決定を取り消し、東京国税局長が、あらためて理由を附記した決定をしても、すでに青色申告提出承認の原取消処分の違法でないことが本判決で確定している以上、決定の取消を求める訴においても、裁判所はこれと異なる判断をすることはできないからである。」
(ポイント)
① 本件審査決定の理由附記に不備があることは明白であり、当該決定の取消事由となり得る。
② 原処分の取消しを求める趣旨で審査請求がなされている以上、原処分自体に違法性がない限り、理由附記の不備を理由に本件審査決定を取り消すことは意味がなく、当該決定の取消請求も棄却すべき。
104.条例違反者に対する罰則(最大判昭37.5.30)
(事案)
Yは、売春を行う目的で大阪市内において通行人を勧誘したことから、「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」(昭和25年12月1日公布施行にかかる大阪市条例)の2条1項に違反したとして起訴されたが、Y側は、本件条例違反者に対する罰則の根拠となる地方自治法14条1項および5項(現3項)は、条例に対する授権の範囲が不特定かつ抽象的であり、その結果、一般に条例でいかなる事項についても罰則を付することが可能となるから、罰刑法定主義を定めた憲法31条に違反するものであるとして、無罪を主張した。
(争点)
法令に特別な定めがあるものと除くほかは、地方公共団体がその条例中に条例違反者に対して一定範囲の刑罰を科する旨の規定を設けることができると定める地方自治法14条およびそれに基づく本件条例は、憲法31条に違反しないか。
(判旨)
「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基づき(同92条)、直接憲法94条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法にほかならない。従って条例を制定する権能もその効力も法律の認める範囲を超えることはできないけれども、法律の範囲内にあるかぎり、条例はその効力を有するものといわなければならない(昭和29年11月24日大法廷判決参照)。
論旨は、右地方自治法14条1項、5項が法令に特別の定めがあるものを除く外、その条例中に条例違反者に対し前示の如き刑を科する旨の規定を設けることができるとしたのは、その授権の範囲が不特定かつ抽象的で具体的に特定されていいない結果一般に条例でいかなる事項についても罰則を付することが可能となり罰刑法定主義を定めた憲法31条に違反する。と主張する。
しかし、憲法31条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきで、このことは憲法73条6号但書によっても明らかである。ただ、法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならないことは、いうまでもない。ところで、地方自治法2条に規定された事項のうちで、本件に関係のあるのは3項7号及び1号に挙げられた事項であるが、これらの事項は相当に具体的な内容のものであるし、同法14条5項による罰則の範囲も限定されている。しかも、条例は、法律以下の法令といっても上述のように、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されてあればたりると解するのが正当である。そうしてみれば、地方自治法2条3項7号及び1号のように相当に具体的な内容の事項につき、同法14条5項のように限定された刑罰の範囲内において、条例をもって罰則を定めることができるとしたのは、憲法31条の意味において法律の定める手続によって刑罰を科するものということができるのであって、所論のように同条に違反するとはいえない。従って地方自治法14条5項に基づく本件条例の右条項も憲法同条に違反するものということができない。」
(ポイント)
条例で刑罰を定める場合は、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りる。
地方自治法14条3項のように、限定された刑罰の範囲内で条例をもって罰則を定めることができるとしたのは、憲法31条の法律の定める手続によって刑罰を科するもので、同条に違反しない。
105.売春条例事件(最大判昭33.10.15)
(事案)
Yは、東京都内で料亭を経営していたが、同料亭内において営利を目的として複数の従業員に不特定の相手方との売春を行わせていたとして、東京都売春等取締条例(昭和24年東京都条令第58号)違反により起訴された。Y側は、地方公共団体が売春の取締りについて格別に制定する結果、地域によってその取扱いに差別が生ずることは憲法14条が保障する法の下の平等に違反するとして、無罪を主張した。
(争点)
地方公共団体が各別に制定する売春の取締りに関する条例は。憲法14条に違反しないか。
(判旨)
「社会生活の法的規律は通常、全国にわたり劃一的な効力をもつ法律によってなされているけれども、中には各地方の特殊性に応じその実績に即して規律するためにこれを各地方公共団体の自治に委ねる方が一層合目的的なものもあり、また、ときにはいずれかの方法によって規律しても差支えないものもある。これすなわち憲法94条が、地方公共団体は『法律の範囲内で条例を制定することができる』と定めている所以である。地方自治法は、憲法のこの規定に基き、普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、その事務に関し、条例を制定することができる旨を規定し(同法14条1項)、その事例として、『地方公共団の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること』(同法2条3項1号)や『風俗又は清潔を汚す行為の制限その他の保健衛生、風俗のじゅん化に関する事項を処理すること』(同条同項7号)等を例示している。そして条例中には、法令に特別の定めがあるものを除く外、『条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、10万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる』(同法14条5項)としているのである。本件東京都売春等取締条例は前記憲法94条並びに地方自治法の諸条項に基いて制定されたものである。(同条例は、昭和31年法律118号売春防止法附則4項、1項但書により昭和23年4月1日効力を失ったが、同法附則5項により、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の規定によることとなっている。
論旨は、売春取締に関する罰則を条例で定めては、地域によって取扱に差別を生ずるが故に、憲法の掲げる平等の原則に反するとの趣旨を主張するものと解される。しかし憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところである。それ故、地方公共団体が売春の取締について各別に条例を制定する結果、その取扱に差別を生ずることがあっても、所論のように地域差の故をもって違憲ということはできない。
(ポイント)
憲法自体が各地方公共団体に条例制定権を認めている以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されるのであるから、そのような差別は憲法自らが容認している。
106.徳島市公安条例事件(最大判昭50.9.10)
(事案)
Yは、昭和43年12月10日に、徳島県反戦青年委員会主催の「B52、松茂・和田島基地撤去、騒乱罪粉砕、安保推進内閣打倒」を表明する集団示唆行動に青年・学生約300人とともに参加したが、当該集団行進の先頭集団が徳島市内の藍場浜公園入口から新町橋西側車道上を経て豊栄堂小間物店前付近に至る車道上においてだ行進を行い、交通秩序の維持に反する行為をした際に、自らもだ行進をしたり、所携の笛を吹きあるいは両手を使って集団行進者にだ行進をさせるよう刺激を与え、もって集団行進者が交通秩序の維持に反する行為をするように扇動し、かつ、所轄警察署長の与えた道路使用許可の条件に違反する行為をなしたとして、道路交通法77条3項、119条1項13号nあらびに「集団行進及び集団示唆運動に関する条例」(昭和27年1月24日徳島市条例第3号)3条3号、5条違反を理由に起訴された。
(争点)
道路交通法77条1項4号・3項、119条1項13号と、昭和27年徳島市条例第3号(いわゆる徳島市公安条例)3条3号、5号、5条との関係をどのように考えるべきか。国法と条例との関係が問題となる。
(判旨)
「道路交通法は道路交通秩序の維持を目的とするのに対し、本条例は道路交通秩序の維持にとどまらず、地方公共の安寧と秩序の維持という、より広はん、かつ、総合的な目的を有するのであるから、両者はその規制の目的を全く同じくするものとはいえないのである。
もっとも、地方公共の案寧と秩序の維持という概念は広いものであり、道路交通法の目的である道路交通秩序の維持をも内包するものであるから、未条例3条3号の遵守事項が単純な交通秩序違反行為をも対象としているものとすれば、それは道路交通法77条3項による警察署長の道路使用許可条件と部分的には共通する点がありうる。しかし、そのことから直ちに、本条3条3号の規定が国の法令である道路交通法に違反するという結論を導くことはできない。
すなわち、地方自治法14条1項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法2条2項の事務に関し条例を制定することができる。と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者と別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例の間にはなんらの矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。
これを道路交通法77条及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則と本条例についてみると、徳島市内の道路における集団行動等について、道路交通秩序維持のための行為規制を施している部分に関する限りは、両者の規律が併存競合していることは、これを否定することはできない。しかしながら、道路交通法77条1項4号は、同号に定める通行の形態又は方法による道路の特別使用行為等を警察署長の許可によって個別的に解除されるべき一般的禁止事項とするかどうかにつき、各公安委員会が当該普通公共団体における道路又は交通の状況に応じてその裁量により決定するところにゆだね、これを全国的に一律に定めることを避けているのであって、このような態度から推すときは、右規定は、その対象となる道路の特別使用行為につき、各普通地方公共団体が、条例により地方公共団体の安寧と秩序の維持のための規制を施すにあたり、その一環として、これらの行為に対し、
道路交通法による根拠とは別個に。交通秩序の維持の見地から一定の規制を施すこと自体を排斥する趣旨まで含むものとは考えられず、各公安委員会は、このような規制を施した条例が存在する場合には、これを勘案して、右の行為に対し道路交通法の前記規定に基づく規制を施すかどうか、また、いかなる内容の規制を施すかを決定することができるものと解するが、相当である。そうすると、道路における集団行動等に対する道路交通秩序維持のための具体的規制が、道路交通法77条及びこれに基づく公安委員会規制と条例の双方において重複して施されている場合においても、両者の内容に矛盾抵触するところがなく、条例における重複規制がそれ自体としての特別の意義と効果を有し、かつ、その合理性が肯定される場合には、道路交通法による規制は、このような条例による規制を否定、排除する趣旨ではなく、条例の規制の及ばない範囲にいおいてのみ適用される趣旨のものと解するのが相当である、したがって、右条例をもって道路交通法に違反するものとすることはできない。」
(ポイント)
条例が国法に違反するか否かは、両者が対象事項、規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容、効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるか否かによって決する。
例えば、①ある事項について国法中にこれを規律する明文の規定がない場合(いわゆる「横出し条例」)でも、当該法令全体絡みて規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置するべきとする趣旨であるときは、これについて規律を設ける条例は国法に違反することとなる。
逆に、特定事項についてこれを規律する国法と条例とが併存する場合でも、②条例が国法とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって国法の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときは、国法と条例との間には何ら矛盾抵触はなく、条例は国法に違反しない。
す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体においてその地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であるときは、国法と条例との間には何ら矛盾抵触はなく、条例は国法に違反しない。
結局、条例と国法との関係は、趣旨などで判断する!
107.普通河川管理条例と河川法(最判昭53.12.21)
(事案)
Xは、Xが居住する高知市内の土地と普通河川(河川法の適用も準用もない河川)との間に存するX占有の土地(本土土地)を通行する者が増えたため、これを防ぐための木の塀を本件土地の両側に設置した。しかし、Y(高知市長)は、このような工作物は高知市普通河川等管理条例に違反する無許可の工作物であるとして、その除却をXに命じた。そのため、Xは当該除却命令の無効確認を求めて出訴したが、原審(高松高判昭52.12.21)は、本件土地が当該普通河川の護岸にあたり、「河川管理施設」に含まれるため、たとえ民有地であっても、その者の同意の有無を問わずYによる河川管理の対象になるとして、Yの除却命令を適法とした。
そこで、Xは、河川法3条が、河川管理者以外の者が設置した施設については、私権を保護するため、その者の同意を得た場合に限って河川管理者が河川管理施設となし得る旨を規定しているのであるから、河川法の適用・準用のない普通河川について、法が定める以上の規制を条例で定めることは憲法94条に違反するものであり、原審が何らの理由も示さないまま本件土地が河川管理施設にあたると判断したことは許されないとして上告した。
(争点)
普通河川の管理について定める普通地方公共団体の条例と河川法との関係はいかに解すべきか。
(判旨)
「河川の管理について一般的な定めをした法律としては河川法があり、同法は河川を。その公共性の強弱の度合いに応じて、同法の適用がある一級河川及び二級河川(いわゆる適用河川)、同法の準用があるいわゆる準用河川並びに同法の適用も準用もないいわゆる普通河川に区分している。一級河川とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川で建設大臣が指定したものをいい(同法4条1項)、二級河川とは、右政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいい(同法5条1項)、準用河川とは、一級河川又は二級河川以外の河川で市町村長が指定したものをいい(同法100条)、普通河川とは、これらの指定を受けていない河川をいうのであるが、普通河川であっても、これを河川法の適用又は準用の対象とすることを必要とする事情が生じた場合には、いつでも適用河川又は準用河川として指定することにより同法の適用又は準用の対象とすることができる仕組みになっている。このように、河川の管理について一般的な定めをした法律として河川法が存在すること、しかも、同法の適用も準用もない普通河川であっても、同法の定めがあるところと同程度の河川管理を行う必要が生じたときは、いつでも適用河川又は準用河川として指定することにより同法の適用又は準用の対象とする途が開かれているいろことにかんがみると、河川法は、普通河川については、適用河川又は準用河川に対する管理以上に強力な河川管理は施されない趣旨であると解されるから、普通地方公共団体が条例をもって普通河川の管理に関する定めをするについても、河川法が適用河川等について定めるところ以上に強力な河川管理の定めをすることは、同法に違反し、許されないものといわなければならない。
ところで、河川法3条は、同法による河川管理の対象となる『河川』に含まれる堤防、護岸等の『河川管理施設』は、それが河川管理者以外の者に設置したものであるときは、当該施設を管理する者の同意を得たものに限るものとしている。これは、河川管理者以外の者が設置した施設をそれが『河川管理施設』としての実体を備えているということだけで直ちに一方的に河川管理権に服せしめ、右施設を権原に基づき管理している者の権利を制限することは、財産権を保障した憲法29条との関係で問題があることを考慮したことによるものと解される。このような河川法の規定及び趣旨に照らして考えれば、普通地方公共団体が、条例により、普通河川につき河川管理者以外の者が設置した堤防、護岸等の施設をその設置者等権原に基づき当該施設を管理する者の同意の有無にかかわらず河川管理権に服せしめることは、同法に違反し、許されない。」
(ポイント)
河川法の適用(準用)のない普通河川について、条例で同法の定める以上に強力な河川管理の定めを普通河川に施すことは、同法に違反し許されない。徳島県公安条例事件で示した基準により、国法に違反するとしたものである。
新着情報・お知らせ
井上久社会保険労務士・行政書士事務所
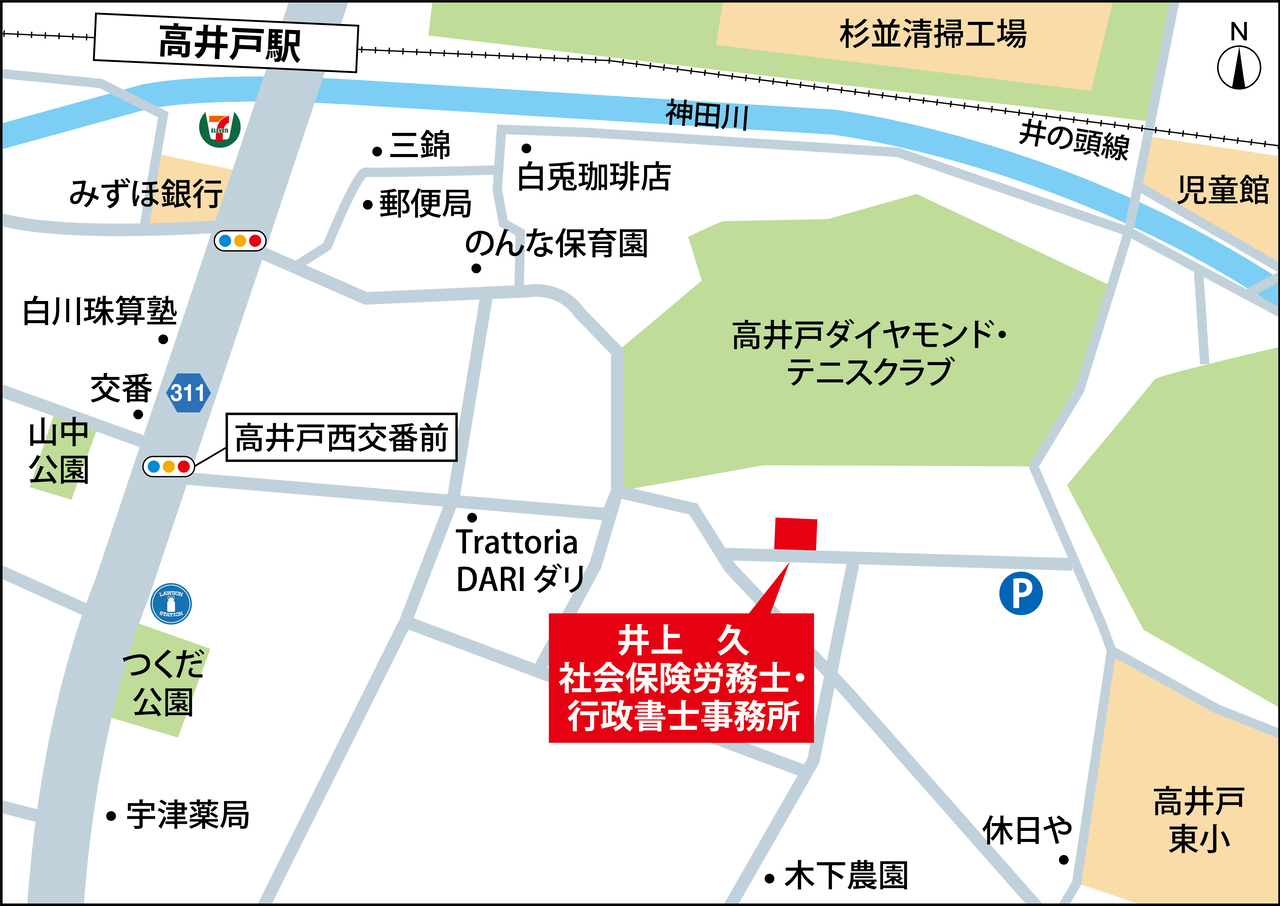
住所
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
アクセス
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

