101 事業場外労働のみなし労働時間制一阪急トラベルサポート(第2)事件
最2小判平成26年1月24日(平成24年(受)1475号)
要旨
旅客添乗員の業務は、「労働時間を算定し難いとき」に該当せず、みなし労働時間を適用できないと例
事実
Xが、A会社が企画する海外ツアーごとに、派遣会社Yに雇用され、A会社に派遣されて添乗業務にじゅうじしていた。添乗業務の具体的内容は、A会社がツアーの開始前に、添乗員に対しツアーの内容や手順を示し、添乗員用のマニュアルにより、具体的な業務の指示をし、ツアーの実施中は、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れて、旅行日程の変更が必要となる場合には、A会社の指示を受けることを求め、ツアー終了時は、添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めていた。
Xには、日当として、16000円が支払われていたが、時間外や休日の割増賃金の未払金があるとして、その支払いを求めて、訴えを提起した。Y会社は、Xには、労基法38条の2の事業場外労働におけるみなし労働時間制が適用されると主張した。
1審は、「労働時間を算定し難いとき」に該当するが、「業務の遂行に通常必要とされる時間」は
11時間であったとして、その時間分に相当する時間外割増賃金等の請求を認めた。双方が控訴したが、原審は、「労働時間を算定し難いとき」に該当しないとして、実労働時間を認定して、Xの請求を一部認容した。そこでnY会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求の一部認容)。
Ⅰ 「本件添乗業務は、旅行日程が・・・・その日時や目的地等を明らかにして定められることによって、業務の内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲およびその決定に係わる選択の幅は限られているものということができる」。
Ⅱ「本件添乗業務について、A会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程の途中で相応の変更を要する事態が生じた場合には、その時点で、個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の状況等につき詳細な報告をうけるものとされているということができる」。
Ⅲ 「以上のような業務の性質、内容やその他遂行の態様、状況等、A会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、こてに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の21項にいう「労働時間を算定し難いとき」にあたるとはいえない」。
解説
労基法は、勤務時間の全部または一部について、事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなすとし、このみなし時間と実態との乖離が著しくなることを防ぐために、その業務を遂行するためには、所定労働時間を超えて労働することが通常必要になる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとされるとし、この業務の遂行に通常必要とされる時間は過半数代表との労使協定によって定めることもできる、としている(労基法38条の2)。
本判決は、添乗業務の内容が具体的に確定され、添乗員にとっての裁量が小さいこと(判旨Ⅰ)、また、添乗員が具体的な指揮監督下で労務に従事していたこと(判旨Ⅱ)を、みなし労働時間制を否定する根拠としている。
行政解釈によると、
①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理するものがいる場合、
②事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合、
③事業場において、訪問先、帰社時刻等、当日の業務に従事し、その後事業場に戻る場合には、「労働時間を算定し難いとき」に該当しないとしている(昭和63年1月1日基発1号。裁判例として、ほるぶ事件ー東京地判平成9年8月1日等)。
昨今では、携帯電話の普及など、事業場外での労働でも、具体的な指揮監督が用意であることが多く、②に該当する場合がほとんどであろう。本件は、③に近い類型といえる。
今後は、テレワークなどの在宅型や移動型の勤務形態における労働時間管理が、この規程との関係で問題となろう(平成20年7月28日期発0728002号も参照)。
なお、Y会社では、国内ツアーの添乗員、海外と国内の両方の添乗員についても、同様の訴訟が提起されており、いずれも「労働時間を算定し難いとき」には該当しないとする判断で確定している。
労基法38条の2〔事業場外労働〕
第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
② 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
102 時間外労働命令の有効要件(1)一日立製作所武蔵工場事件
最1小判平成3年11月28日(昭和61年(オ)840号)(民集45巻8号1270頁)
要旨
使用者は、就業規則の規定に基づき、時間外労働を命じることが認められるか。
事実
Xは、Y会社のA工場においてトランジスターの品質および歩留の向上を管理する係として、勤務していた。昭和42年9月6日、9月の選別実績歩留がXの算出した推定値を下回ったため、B主任が問いただしたところ、Xはその作業に手抜きがあったことを認めた。そこで、BはXに対し、残業して原因の究明と歩留推定のやり直しを命じたところ、Xはこれを拒否して、翌日に実施した。このため、Y会社は、この残業拒否を理由にXに対して出勤停止14日間の懲戒処分を言い渡すとともに、始末書を提出するよう命じた。Xは、当該処分後に出勤した際、残業は労働者の権利であり、就業規則に違反した覚えはないとして始末書の提出を拒否したが、管理者らの説得により始末書を提出したところ、反省の態度がみられないとして、受領を拒否されたため、かえって挑発的な発言をするようになった。そこで、Y会社は、Xの態度は過去4回の処分歴と相まって、就業規則所定の懲戒事由に該当するとして、懲戒解雇とした。Xは、この懲戒解雇は無効であると主張して訴えを提起した。
なお、就業規則には「業務上の都合のよりやむを得ない場合には、組合との協定により1日8時間、1週48時間の実労働時間を延長(早出、残業または呼出)することがある」という規定がもうけられていた。
1審は、組合との協定(三六協定)で定める時間外労働事由は、具体性に欠けるので残業命令は無効であり、懲戒解雇も有効であると判断した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)
労基法32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、いわゆる三六協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、「使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めていりときは、当該就業規則の規程の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右集合規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする」。
解説
1 使用者は、法定労働時間を超える労働(時間外労働)をさせる場合には、労基法36条に基づき三六協定を締結し、それを労働基準監督署長へ届け出なければならない。さらに、割増賃金の支払いも必要となる(労基法37条)。割増賃金を支払っても、三六協定の締結・届出義務は免除されない。
他方、三六協定の締結・届出がなされている場合でも、労働者は使用者からの時間外労働命令に当然に服さなければならないわけではなく、、時間外労働命令の拘束力が認められるためには、そのような命令の労働契約上の根拠が必要となる。三六協定は、労基法32条に違反するという状態を解消する(すなわち、同条違反による罰則の適用を免れたり、法定労働時間を超えて働かせる定めを有効としたりする)という効力(免罰的効力)をもつにとどまるからである。
時間外労働命令に関する労働契約上の最も明確な根拠となるのは、個々の労働者の具体的同意である。さらに、本判決は、就業規則上の合理的な規定も根拠となるとする。労契法の施行後は、同法7条により、当該条項が周知と合理性の要件を満たしていれば、労働契約の内容となる、と法律構成されることになろう。
本件では、就業規則上、労働組合との協定(三六協定)により、時間外労働を命じることがある。と定められていたので、就業規則の内容の合理性は、この三六協定の内容の合理性になった。本件の三六協定で定めている時間外労働事由について、最高裁は、その合理性を肯定している。
2 三六協定で定めることのできる時間外労働の上限については、現在では、労基法36条2項に基づき制定されて基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準))によろ定められている。また、この上限を超えて時間外労働を定めることも、特別条項付き協定が締結されていれば可能となる。
三六協定の締結当事者は、三六協定の内容が、この基準に「適用したものとなるようにしなければならに」(労基法36条3項)。限度基準を超える時間外労働が定められた場合には、行政官庁は助言や指導をすることができる(同4項)が、限度基準を超える三六協定の条項が無効となるとまでは解されていない。ただし、現在(2017年12月)、限度基準を罰則付きの規制とし、また、特別の条項付き協定が締結されている場合の時間外労働の上限を新たに導入しようとする法改正が進められている。
なお、限度基準を遵守した三六協定が締結され、労働契約上の根拠がある場合であっても、時間外労働命令が、生活上の不利益が大きく、業務上の必要性が十分でない場合には、権利濫用となりうる。
なお、三六協定の締結・届出と割増賃金の支払義務は、休日労働をさせる場合にもあてはまる(なお、休日労働とは、法定休日[労基法35条]に労働をさせる場合を指すのであり、法定外休日については、こうした義務は課されない)。
労基法32条(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労基法35条(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労基法36条(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
労基法36条2項
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
労基法36条3項
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
労基法36条4項
④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
労基法37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労契法7条
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
103 時間外労働命令の有効要件(2)一トーコロ事件
東京高判平成9年11月17日(平成6年(ネ)4745号)
要旨
三六協定の締結主体としての過半数代表者は、どのように選ばれなければならないのか。
事実
Xは、Y会社の従業員であり、電算写植機のオペレーターとして、住所録作成(組版)の業務に従事していた。平成3年9月末ころ、組版業務の部署において、午後7時まで残業をする申し合わせがなされて、Xも同年10月初旬ころから、毎日30分ないし1時間45分程度残業するようになった。Y会社は、繁忙時期にはいり、上司がXに何度か、残業時間を延長するよう求めたが、Xがこれに従わないとみると、同月31日に、営業部長が本件、残業命令を発した。Xは、同年2月4日、Xが眼精疲労であるとする医師の診断書を提出しら。その後は、Xは、住所録の組版の残りや登録外文字作成の業務に従事し、定時の午後5時半になると帰宅していた。
Y会社の社長は、Xに対し、自己都合退職をするよう勧告し、Xがこれを拒否すると、解雇を通告した。そこで、Xは、この解雇は無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認などを求めて、訴えを提起した。1審は、Xの請求をほぼ認容した(ただし、慰謝料請求は認められなかった)。そこで、Y会社は控訴した。なお、本判決に対しては、Y会社は上告したが、最高裁は、本判決の判断は、正当として是認できるとして、上告を棄却している(最2小判平成13年6月22日)。
判旨 控訴棄却(Xの請求の一部認容、一部棄却)
本件の三六協定は、平成3年4月6日に所轄の労度基準監督署に届け出られたものであるが、協定の当事者は、Y会社と「労働者の過半数を代表する者」としての「営業部A]であり、協定の当事者の選出方法については、「全員の話し合いによる選出」とされていた。
「「労働者の過半数を代表する者」は当該事業場の労働者により過去に選出されなければならないが、適法な選出といえるためには、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して三六協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持しているを認められる民主的な手続がとられていることが必要というべきである(昭和63年1月1日基発第1号参照)」。
Aは「友の会」の代表者であるが、「友の会」は役員を含めたY会社の全従業員によって構成されており、会員相互の親睦等を図り、融和団結の実をあげることは明らかであり、したがって、Aが「友の会」の代表者として、自動的に本件、三六協定を締結したにすぎないときには、Aは労働組合の代表者でもなく、「労働者の過半数を代表する者」でもないから、本件、三六協定は無効というべきである。
また、本件、三六協定の締結に際して、労働者のその事実を知らせ、締結の可否を判断させる趣旨のための社内報が配布されたり、集会が開催されたりした形跡はなく、Aが「労働者の過半数を代表する者」として民主的に選出されたことを認めるに足りる証拠はない。
解説
過半数代表とは、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合(過半数組合)か、当該事業場の労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を指す。過半数代表には、現行法上、就業規則の作成・変更の際に意見聴取を受ける権限(労基法90条)や、さまざまなタイプの労使協定の締結権限など重要な権限が与えられている(労基法36条1項、24条1項ただし書、39条4項、6項および7項等。労基法以外にも、育児介護休業法6条1項等)。
過半数代表者については、その選出方法が法律上定められておらず、使用者が一方的に指定するなど、その選出方法に問題がある例があるといわれてきた。現在では、本判決でも引用されている通達を明文化した労規則6条の2において、
①管理監督者(労基法41条2号)の地位にないこと、
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかに4して実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること、という要件が定められている(そのほか、過半数代表者に対する不利益取扱いの禁止も定められている)。
本件では、「友の会」は労働組合ではなく(したがって、過半数組合に該当しない)、また、その代表者であるAが自動的に過半数代表者となるのは民主的な選出という手続的ルールに反するので、Aの締結した労使協定(三六協定)は無効とされ、Xに対する残業命令は無効(それゆえ、解雇も無効)と判断された。
労基法90条 (作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
労基法36条1項 (時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
労基法24条1項 (賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労基法39条4項
④使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項
労基法39条6項
⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
労基法39条7項
⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
労基法41条2号
第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
育児介護休業法6条1項(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
第6条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
労規則6条の2
第六条の二 法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三第一項、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
104 割増賃金一医療法人康心会事件
最2小判平成29年7月7日(平成28年(受)222号)
要旨
病院医師の割増賃金の基本級組入れ合意の有効性。
事実
Xは、医療法人Yとの間で、雇用契約を締結していたが、看護師への不適切な指導等を理由として、解雇された。そこで、労働契約の地位確認および時間外労働に対する未払いの割増賃金等の支払いを求めていった絵を提起した。
XとY法人との雇用契約によると、賃金は、本給、諸手当、賞与により構成される年棒制で、その額は1700万円であった。また、Y法人の時間外労働に関する規定では、時間外手当の対象となるのは、勤務日の午後9時から翌日の午前8時30分までと休日に発生する緊急業務に要した時間とされ、当直・日直の当番医師には、別途手当を支給することが定められており、それ以外の割増賃金は、年棒に含まれることが包囲されていた(本件合意)が、年棒のうち割増賃金にあたる部分は明らかにされていなかった。
Y法人は、Xに対し、年棒以外に、時間外手当と当直手当を支払っていたが、時間外手当は、深夜割増分だけで、時間外労働分の割増は支払われていなかった。
1審では、時間外労働者が月60時間を超えた場合の割増金と深夜労働が月60時間を超えた場合の割増賃金と深夜労働に対する割増賃金は、年棒に含めて支払われたとはいえないとして、不足分の支払いを命じた。双方が控訴したところ、原審は、本件合意は、Xの医師としての業務の特質に照らして合理性があるとして、原判決を一部取り消して、Xの請求を棄却した(なお、1審も控訴審も、解雇は有効としている)。そこで、Xは上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し。
Ⅰ 労基法37条はの定める使用者の割増賃金支払義務は、それによって時間外労働等を抑制し、労働義務は、それによって時間外労働等を抑制し、労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への補償を行おうとする趣旨によるものである。
Ⅱ (1)割増賃金の算定方法は、同条その他の関係規程に具体的に定められているところ、同条は、同条等に定められた方法により、算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され、労働者に支払われる基本給や諸手当にあらかじめ含めることにより割増賃金に支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではない。
(2)使用者が同条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、同条等に定められた方法により、算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ、同条の上記趣旨によれば、割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては、労働契約における基本給等の定めにつき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別できることが必要であり、割増賃金に当たる部分の金額が、同条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。
解説
労基法37条は、使用者に対して、時間が労働、休日労働、深夜労働をさせた場合における割増賃金の支払いを義務付けている。割増賃金の算定方法は、通常の労働時間または労働日の賃金(労基法19条を参照)に対して所定の割増率を乗じるというものである(割増賃金令によると、割増率は、時間外労働と深夜労働については25%以上、休日労働については35%以上である。なお、時間外労働が1か月に60時間を超えた場合には、割増率は50%に引き上げられるが、その引上げ分は、休暇で代替させることができる(労基法37条3項)。通常の労働時間に対する賃金から除かれるもの(除外賃金)は、法令で定められている(労基法37条5項、労規則21条)。
割増賃金の算定は、法令の定める方法に従って行う必要があると解されておらず、使用者が独自の算定式に基づき支払った割増賃金が、法令の定める方法によって算定された割増賃金を上回っていれば、適法な取扱いとなる(判旨Ⅱ(1))。また、下回っていても、その定めが無効となるのではなく、差額の支払い請求することができると解すべきである(労基法13条。判旨Ⅱ(2)も同旨か)。
割増賃金を基本給に組み入れる旨の合意がある場合も、基本的には、この考え方が当てはまる。ただし、この場合でも、通常の労働時間の賃金にあたる部分と時間外の割増賃金にあたる部分とが判別できることが時間外の割増賃金にあたる部分とが判別でることが必要である(判旨Ⅱ(2))。同旨の判例として、高知県観光事件ー最2小判平成6年6月13日、テックジャパン事件ー最1小判平成24年3月8日)。判別可能性がない場合には、割増賃金の組入れ合意は無効とされ、基本給全体が割増賃金の算定基礎となる。
なお、本件については、高給を支払われる医師は、交渉力の格差はなく、その合意を有効とみる余地はないかというデロケーションの論点もありうる(→【92】日新製鋼事件)。
労基法37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労基法37条3項
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
労基法37条5項
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
労規則19条
第十九条 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異る場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
② 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。
労規則21条
第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
105 休日の振替一三菱重工横浜造船所事件
横浜地判昭和55年3月28日(昭和50年(ワ)868号)
要旨
休日の振替は、どのような場合に認められるか。
事実
Y会社は、大規模な交通ゼネストがあることが予定された昭和49年4月11日と12日を休日に振り替えて、休日であった同月13日(土曜日)と14日(日曜日)を勤務日にした。Y会社の就業規制には、業務上必要がある場合は休日を他の日に振り替えることがある、とする規定があった。ところが、Y会社の従業員であるXらは勤務日とされた13日と14日に」出金しなかったため、Y会社はXらを欠勤扱いにし、賃金を控除した。そこで、控除された賃金相当額の支払いを求めて訴えを提起した。
判旨 請求棄却
Y会社の就業規則の規定によれば、「一定の条件のもとに就業規則所定の休日を他に振替えることができることになっているのであるから、所定の休日は振替のありうることが予定されたうえで特定されているものというべきであり、右の定めは就業規則によるものであることから、その性質上、労働契約の内容をなしているものと解されるので、使用者は、前記の条件が満たされるかぎり、特定された休日を振替えることができるものというべく、たとえ、個々の振替の際に労働者の同意、了解がなくとも、そのことの故に直ちに休日振替が違法、無効となるいわれはないものと解するほかはない。そして、本件において、4月13日、14日の休日を同月11日、12日に振替えたのみであるから、・・・・労基法35条1項、2項違反の生ずる余地はないので、したがって、本件措置が同条に違反して休日を剥奪したことにならないことは明らかである」。
解説
労基法35条は、使用者に対して、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」(変形休日制)を労働者に与えることを義務付けている。休日の特定は、できるだけとくていさせるよう指導する方針になっている(昭和63年3月14日基発150号)。
突発的な業務の都合で、事前に特定された休日が労働日とされ、別の労働日が休日に振替えられるという措置がとられることがある。これを休日の振替という。休日の振替には、ある労働者を休日(振替休日)としたうえで、本来の休日を労働日とする「事前の振替」と、ある休日に労働をさせた後に、別の労働日を休日とする(つまり代休を与える)「事後の振替」とがある。
本件では「事前の振替」が問題となっており、判旨は、就業規則上の規定があれば、労働者の同意なしにこうした振替を行うことができると判断している(厳密にいえば、合理性の審査がもとめられよう。労契法7条)。
なお、振替を行った結果、1週1日(変形休日制の場合には4週4日)の休日の要件を満たさなくなる場合には、労基法違反となる。逆に、この要件を満たしているかぎりは、法定休日の変更は許されることになり、当該日に労働をさせても休日労働とならず、三六協定の締結・届出(労基法36条)や割増賃金の支払い(同法37条)はもとめられないことになる(ただし、振替の 結果、、1週間の労働時間が40時間を超すことになる場合には、やはり三六協定の締結・届出と割増賃金の支払いが必要となる)。
以上に対して、「事後の振替」の場合は、その日の労働は法的には休日労働とされることになる。すなわち、三六協定の結果・届出を割増賃金の支払いが必要となる。事後に代休を付与したとしても、休日労働が行われた事実が消えるわけではないので、使用者は割増賃金の支払いを免れることはできないし、三六協定に基づかない休日労働を行わせたという違法性の瑕疵は治癒しないので、使用者は就業規則や労働協約でまどで定めを置いていない限り、代休を与える必要はないし、代休を付与する場合でも、労基法上の休日に関する規制は他起用されない。
「事後の振替」の場合は、休日労働をさせていることになるので、以上の労基法上の規制以外に、時間外労働と同様、労働契約上の根拠が必要となる(→【102】日立製作所武蔵工場ジケン)。
労基法35条(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労基法37条
労契法7条
労基法36条1項、2項(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
労基法37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
労契法7条
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
労契法7条
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
106 管理監督者一日本マクドナルド事件
東京地判平成20年1月28日(平成17年(ワ)26903号)
要旨
ファーストフードの店長は管理監督者に該当するか。
事実
Xは、ハンバーガー等の販売等を目的とするY会社に昭和62年2月に採用され、その直営店の店長に平成11年10月に昇格している。Y会社では、店長以上の職位の従業員が労基法41条2号の管理監督者として扱われ、法定労働時間(労基法32条)を超える時間外労働について割増賃金(同法37条)が支払われていなかった。Xは、店長職は管理監督者には該当しないとして、未払いの割増賃金の支払いを求めて訴えを提起した。
判旨 一部却下、一部認容、一部棄却
「管理監督者については労働基準法の労働時間等に関する規定は、適用されないが(同法41条2号)、これは、管理監督者は、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇やその勤務態度において、他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので、労働時間等に関する規定の適用を除外されても、上記の基本原則(筆者注:法定労働時間や法定休日の規制の枠を超えて労働させる場合に、割増賃金を支払うべきことに反するような事態が避けられ、当該労働者の保護に欠けるところのないという趣旨によるものと解される。
したがって、Xが管理監督者にあたるといえるためには、店長の名称だけでなく、実質的に以上の法の趣旨を充足するような立場にあると認められるおのでなければならず、具体的には、①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、
②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、
③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
などの諸点から、判断すべきであるといえる」。
Xは、①から③のいずれの点も満たさないので、管理監督者には該当しない。
解説
労基法41条は、労基法上の労働時間に関する規定について、農業、畜産・水産業に従事する者(1号)、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」(3号)の適用除外を定めている。さらに、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)と「機密の事務を取り扱う者」の適用除外が定められている(2号)。文言上、適用除外とされるのは、「労働時間、休憩及び休日に関する規程」で、年次有給休暇は外されている(労基法第4章の見出しと比較せよ)。深夜労働も適用除外されない(ことぶき事件ー最2小判平成21年12月18日)。
管理監督者は、3号の監視・断続的労働に従事する者とは異なり、適用除外を受けるにおいて、行政官庁(労働基準監督署長)の事前の許可の必要がないため、使用者側が、当該労働者の役職だけ管理職にし、割増賃金の支払義務を免れようとする「名ばかり管理職」が社会問題となってきた(本判決も、その観点から話題になった)。
管理監督者の定義は法令上は明確にされていないが、従来、行政会解釈により、ある程度、明らかにされていた(昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号)。それによると、重要な職務と責任を有していること、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にあること、賃金等の待遇面において、一般労働者に比し、優遇措置が講じられていること、が判断基準となる。
本判決も、この行政解釈とほぼ同様の基準により、半判旨①から③の要素を考慮して管理監督者の該当性の判断をすべきものとしている(先例として、神代学園ミューズ音楽院事件ー東京高判平成17年3月30日)。もっとも、管理監督者に該当するためには、これまでも、判旨が言及しているような(経営者との一体性)が求められると解されており、これは、かなり厳格な判断基準である。従来の裁判例においても、管理監督者性が肯定された事例はきわめて少ない(最近の肯定例として、ことぶき事件ー前掲(美容・理容店の店長)・日本ファースト証券事件ー大阪地判平成20年2月8日(証券会社の支店長)、セントラルスポーツ事件ー京都地判平成24年4月17日「スポーツクラブ運営会社のエリアディレクター」等)。
「名ばかり管理職」が生まれる背景には、日本に、上級のホワイトカラーに対する適用除外制度(ホワイトカラー・エグゼンブショウン)がないという事情がある。
そうしたこともあり、現在(2017年12月)、「高度プロフェッショナル制度」という、新たな適用除外の制度を設けようとする法改正が進められている。
労基法41条2項第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
労基法32条(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労基法37条
第37条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
107 年次有給休暇権の発生要件(1)一林野庁白石営林署事件
最2小判昭和48年3月2日(昭和41年(オ)848号)(民集27巻2号191頁)
要旨
年休の取得には使用者の承認は必要か。
事実
Xは、A営林署の職員であり、B労働組合の組合員でもある。組合員が勤務時間内に許可なく職場大会を開いた等の理由で処分を受けたため、これに抗議する闘争を行うこととし、C分会はその拠点の1つとされた。Xは、Cの闘争に参加するために、昭和33年12月9日に翌日と翌々日(10日、11日)の2日間の年次有給休暇(年休)を請求し、この2日間出勤しなかった。当局はこの年休請求を不承認として2日分の給料をカット分の支払いを求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、Xの請求を認容したので、Y(国)は上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求認容)。
Ⅰ 年休の権利は、労基法39条1項・2項の要件が充足されることによって、法律上当然に労働者に生ずる権利でって、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではなく、また、同条5条にいう「請請求」とは、休暇の時季にのみかかる文書であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならない。
労基法は、有給休暇を「与える」といっているが、休暇の付与義務者たる使用者に要求されるのは、労働者がその権利として有する有給休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本的内容とする義務にほかならない。
Ⅱ 「年次休暇の利用目的は、労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である」。
Ⅲ 「いわゆる一斉休暇闘争とは、これを、労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として、全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄・離脱するものと解するときは、その実質は、年次休暇に名を藉りた同盟罷業にほかならない。したがって、その形式のいかんにかかわらず、本来の年次休暇の行使ではないのであるから、これに対する使用者の時季変更権の行使もありえず、一斉休暇の下に同盟罷業に入った労働者の全部について、賃金請求権が発生しないことになるのである」。
Ⅳ しかし、「他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは、なんら当該年次有給休暇の成否に英きぃおうすることろはない」。けだし、労働者が、違法に時季指定をしたときは、使用者による適法な時季変更権の行使がない限り、指定された時季に年休が成立するものであり、時季指定の成立要件である「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断は、当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきものであるからである。
解説
年休は、労基法39条1項および2項(短時間労働者は3項)の要件を満たした労働者が請求した時季に使用者は付与しなければならない(5項)。法律の文言上、労働者に時季の指定権があるのは明らかであるが、年休権の法的資質については、議論があった。
本判決は、労基法39条1項および2項所定の要件がそろえば、使用者の対応(承認の有無など)に関係なさく、労働者には年休権が当然に発生するとし、それとは別に労働者には時季指定権があるとする二分説の立場を採択することを明示した(判旨Ⅰ)。ただし、使用者には「事業の正常な運営を妨げる場合」には、時季変更権の行使が認められているので、その意味で、時季指定権の効果は解除条件付きである。
年休を争議目的で取得することができるかという点も、本判決では、論点となっている。
本判決は、年休の自由利用の原則を認めたうえで(判旨Ⅱ)、ただ、労働者が、その所属する事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として、全員一斉に休暇を取得するという一斉休暇闘争は、使用者の時季変更権を前提とするという一斉休暇闘争は、使用者の時季変更権を前提としないもので、年休に名を藉りた争議行為にすぎないとしている(判旨Ⅲ)。他方、他の事業場における争議行為に参加するために年休を取得することは年休自由利用の原則の範疇内のことであり(判旨Ⅳ)、本件はこのケースに該当するので、Xの年休取得は有効とされた。
なお、その後、ある労働者が、すでに請求していた年休日に、その所属する労働組合の争議行為が前倒しで行われることになり、そのため、年休を維持したまま当該事業場における正常な業務の運営を阻害する目的で職場を離脱したという事案において、最高裁は、「労働基準法の適用される事業場において業務を運営するための正常な勤務体制が存在することを前提としてその枠内で休暇を認めるという年次有給休暇制度の趣旨に反する」ので、年休は成立しないとした(津田沼電車事件ー最3小判平成3年11月19日)。
労基法39条1項第(年次有給休暇)
39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労基法39条2項
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
一年 一労働日
二年 二労働日
三年 四労働日
四年 六労働日
五年 八労働日
六年以上 十労働日労基法39条3項
③ 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
労基法39条4項
④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項
労基法39条5項
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
108 年次有給休暇権の発生要件(2)一八千代交通事件
最1小判平成25年6月6日(平成23年(受)2183号)(民集67巻5号1187頁)
要因
無効な解雇による不就労期間は、年休の出勤率要件の算定において出勤日扱いとなるか。
事実
一般乗用旅客自動車等を営むY会社は、タクシー乗務員として雇用していたXを、平成19年5月16日に解雇する旨の意思表示をし、同日以降のXの就労を拒んだ。Xは、この解雇は無効であると主張して提訴し勝訴し、平成21年9月4日、職場に復帰した。
Xは、同月13日から同月15日まで、平成22年1月13日および同年2月15日の合計5日の労働日につき、年休の時季指定をし、就労しなかった。しかし、Y会社は、Xは前年度において労基法39条2項所定の年休の成立要件を満たしていないとして、Xが就労しなかった5日間を欠勤として扱い、賃金を支払わなかった。そこで、Xは、未払い分の賃金を支払わなかった。そこで、Xは、未払い分の賃金などの支払い求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、Xの年休権は適法に成立していると判断して、その請求を(一部)認容した。そこで、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求の一部認容)。
労基法[39条1項及び2項における前年度の全労働日に係わる出勤率が8割以上であることという年次有給休暇の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規程の趣旨に照らすと、前年度の総歴日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から、出勤日数に算入するのが相当でなく、全就労日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労度日にふくまれるものと解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このうような日は、使用者の責に帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から、出勤日に算入するのが相当でなく、全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項および2項における出勤率の算定にあたっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものというべきである」。
解説
年次有給休暇が発生するためには、前期に全労働日の8割以上出勤していることが要件となる(労基法39条1項および2項)。通常の欠勤は、全労働日に含めたうえで、出勤扱いとならないことに異論はまいが、欠勤の種類によっては、全労働日から除外すること、あるいは、全労働日に算入して、出勤扱いとすることも考えられる。後者の出勤扱いとされる場合の例としては、業務上の負傷・疾病による療養のための休業、育児休業、介護休業、産前産後の休業が法律で明記されている(同法39条8項)。
従来の行政解釈では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の日」と「正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日」は全労働日に含まれないとされてきた。しかし、学説上は、全労働日に含めたうえで、出勤扱いにすべきとする見解も有力に主張されていた。
このようななか、本判決は、全労働日を「就業規則や労働協約等に定められた休日以外の日」とする解釈を前提としたうえで、無効な解雇による不就労期間について、「労働者の責めに帰すべき事由」の存否に着目して、これに該当しない場合には、出勤扱いとするという解釈を示した。「労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者」を年休取得対象者から除外するという出勤率要件の趣旨をふまえたものである。
ただし、「労働者の責めに帰すべき事由」がない場合であっても、衡平等の観点から、「不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等」は全労働日には含めないとしている。「使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業」は、労基法26条の使用者の帰責事由には該当し、休業手当の請求権を発生させる(→【168】ノース・ウエスト航空事件が、年休の出勤率要件との関係では出勤扱いとはされていない。
本判決後、行政解釈は修正されている(平成25年7月10日基発0710第3号)。
労基法39条1項第(年次有給休暇)
39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労基法39条2項
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
一年 一労働日
二年 二労働日労基法39条1項
三年 四労働日
四年 六労働日
五年 八労働日
六年以上 十労働日労基法39条3項
③ 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
労基法39条3項
③ 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
労基法39条8項
⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
109 時季変更権の有効性(1)一電電公社弘前電報電話局事件
最2小判昭和62年7月10日(昭和59年(オ)618号)(民集41巻5号1229頁)
要因
交替制で働く労働者の年休の時季指定について、使用者が状況に応じた配慮をせず勤務割の変更をしなかった場合の時季変更権の行使は有効か。
事実
Xは、Y公社のA施設部機械課に勤務し、6輪番交替服務の勤務体制に組み入れられていた。Xは、勤務制において、日勤勤務にあたっていた昭和53年9月17日(日曜)に年休の時季指定をした。機械課では、労使間の協議により、日曜の日勤勤務の場合に必要な最低配置人員は2名と定められていた。B課長は、Xが同日に予定されている成田空港反対現地集会に参加して違法行為に及び恐れがある者と考え、参加を阻止するため、Xの代替勤務を申し出ていた職員を説得してその申出を撤回させたうえ、同日にXが出勤しなければ必要な最低配置人員を欠くことになるとして時季変更権を行使した。Xは、同日出勤せず、成田空港反対現地集会に参加した。Y会社は、Xに対して欠勤を理由として戒告処分にし、賃金を1日分カットした。そこで、Xは、戒告処分の無効と、未払賃金と付加金、および慰謝料の支払いを求めて訴えを提起した。
1審は、Xの請求をほぼ認容したが、原審は、Y公社の時季変更権の行使は適法であるとして、Xの請求を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 原判決一部破棄、一部差戻し(時季変更権の行使は無効と判断した)。
Ⅰ「労働者の年次休暇の時季指定に対応する使用者の義務の内容は、労働者がその権利としての休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本とするものにほかならないのではあるが、年次休暇は労基法が労働者に特に認めた権利であり、その実務を確保するために附加金及び刑事罰の制度が設けられていること(同法114条、119条1項)、及び、休暇の時季の選択権が第1次的に労働者に与えられていることにかんがみると、同法の趣旨は、使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請しているものとみることができる」。
Ⅱ 労基法39条5項ただし書の「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断において、「代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるべきというべきであるが、特に勤務制による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである、したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して、代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者が」そのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人数を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次休暇の利用目的は、労基法の関知しないところである・・・・から、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況であるにもかかわらず、休暇の利用目的のいあkんによって、そのための配慮をせずに年次休暇を与えないことに等しく、許されない者であり、右時季変更権緒の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない」。
解説
判例は、年休に対応する使用者の義務は、労働者の年休権の京樹を妨げてはならないという不作為を基本とすると述べている(→【107】林野庁白石営林署事件の判旨Ⅰ)が、本判決は、これに加えて、労基法は、「労働者が指定した時季に休暇をとれるよう状況に応じた配慮をすることを要請している」とした(判旨Ⅰ)。そこでいう配慮の典型例は、代替勤務者の配置である。とりわけ本件のように最低配置人員が設定されて、その人数しかはいちされていないような場合には、年休を取得すれば直ちに「事業の正常な運営を妨げる」として、時季変更権の行使が認められる可能性があるので、使用者に代替勤務者確保のための配慮が求められるのは当然のことといえよう。
この際に使用者に求められるのは、「状況に応じた」、「通常な配慮」である。その後の判例は、「通常の配慮をすれば代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況にあったか否かについては、当該事業場において、年次休暇の時季指定に伴う勤務割の変更が、どのような方法により、どの程度、行われていたか、年次休暇の時季指定に対し、使用者が従前どのような対応の仕方をしてきたか、当該労働者の作業の内容、性質、欠務補充要員の作業の繁閑などからみて、他の者による代替勤務が可能であったか、また、当該年次休暇の時季指定が、使用者が代替勤務者を確保しうるだけの」時間的余裕のある時期にされたものであるか、更には、当該事業所において週休制がどのように運用されてきたかなどの諸点を考慮して判断されるべきである」、としている(電電公社関東電気通信局事件ー最3小判平成元年7月4日)。
本件では、使用者側は、代替勤務は、代替勤務を申し出ていた者に翻意させるなど配慮とは逆の行動をしており、また、その行動の目的は、成田空港反対闘争への参加を阻止するところにあり、年休自由利用の原則にも反するものであったので、時季変更権の行使を認めないとする本判決の結論は妥当である。
労基法114条(付加金の支払)
第114条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
労基法119条1項
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
労基法39条5項
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
110 時季変更権の有効性(2)一電電公社此花電報電話局事件
最1小判昭和57年3月18日(昭和53年(オ)558号)(民集36巻3号366頁)
要因
年休の取得後に行使された時季変更権は有効か。
事実
X1およびX2は、Y公社に勤務する職員である。昭和44年8月18日、午前8時40分ころに、理由を述べずその日の1日分の年休を請求し、午前9時からの勤務に就かなかった。これに対して、所属長であるA課長は、事務に支障が生ずる恐れがあると判断したが、休暇を必要とする事情によっては休暇を認めるのを妥当とする場合があると考え、Xから休暇を必要とする事情を聴取するため、連絡をするように電報を打った。しかし、午後3時ころ出社したX1が、理由を明らかにすることを拒んだため、ただちに年休の請求を不承認とする意思表示をした。(X2も類似の事案)。なお、Y公社の就業規則には、Xらのような交替服務の職員の年休については、前々日までに所属長の承認を得なければならないと定めていた。Y公社は、いずれの場合についても、Xらを欠勤扱いとし、賃金を控除したため、Xらは、未払い賃金と付加金の支払を求めて訴えを提起した。
1審はXらの請求を認容したが、原審は、時季指定権の行使は、有効であるとして、原判決の一部を取り消した。そこで、Xらは上告した。
判旨 上告棄却
Ⅰ「使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し、又は、経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく、客観的に右時季変更権を行使しうる事由が存し、かつ、その行使が遅滞なくされたものである場合には、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。
Ⅱ 原判決は、Xらの本件各年休の請求が就業規則等の定めに反し、前々日の勤務終了時までにされなかったため、Y公社において代行者を配置することが困難となり、事業の正常な運営に支障を生じるおそれがあったところ、Xらが就業規則の規程どおりに請求しえなかった事情を説明するため休暇を必要とする事情をも明らかにするならば、時季変更権の行使を差し控えることもありうるところであったのに、Xらはその事由すらいっさい明らかにしなかったのであるから、時季変更権を行使されたのは、やむえないことであると判断したものであって、使用者が時季変更権を行使するか否かを判断するため労働者に対し、休暇の利用目的を問いただすことや、休暇の利用目的を明らかにしないこと、または、その明らかにした利用目的が相当でないことを時季変更権行使の理由としうることを一般的に認めたものではない。
解説
1 本件では、就業規則の規定に違反して、休暇の取得の直前に時季指定をした労働者に対し、事後的に行使された時季変更権の有効性が争われている。
まず、時季指定権の行使をいつまでにすべきかについては、法律上の規定がなく、就業規則上の合理的な制限の範囲内のものであれば適法と解されている。本判決では、交交替制勤務の労働者について、前々日までという制限が合理的であることは当然の前提となっている。期間制限が労働者に厳しすぎる(1か月前までの指定など)と、そのような規定は合理映を欠くと判断される可能性はあろう(労契法7条)。
本判決は、時季変更権の事後的な行使について、時季指定が休暇の始期にきわめて近接した時期に行われ、時季変更権の行使の判断の時間的余裕がなかった場合には、その行使が遅滞なく行われれば、適法であると判断している(判旨Ⅰ)。時季指定をした日が休暇の取得日に近接すればするほど、事後的な時季変更権の行使が許される可能性が高まるということであろう(なお、時季変更権の要件を満たしていない場合であっても、時季指定権の濫用が認められる場合はあろう)。
2 年休については自由利用の原則があり、使用者が休暇目的を考慮して時季変更権を行使するかどうかを決めることは許されない(→【107】林野庁白石営林署事件、【109】電電公社弘前電報電話局事件)。しかし、本判決によると、客観的に時季変更権の要件が備わっている場合に、その行使を差し控えるかどうかを判断するために、休暇目的を問うことは許される(判旨Ⅱ)。
時季変更権をめぐっては、非代替的業務に従事する労働者の年休について、事業の正常な運営を妨げる可能性が高いため問題となりやすい。判例上は、高校の期末試験の当日の出題担当教師の年休や職場の技能改善のための訓練への参加に従事するよう命じられていた従業員の年休については時季変更権の行使が有効とされている(それぞれ、道立夕張南高校事件ー最1小判昭和62年1月29日、NTT事件ー最2小判平成12年3月31日)。非代替的で時期的に限定されている業務の場合には、時季変更権の行使は有効とされやすいだろう。
労契法7条
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
111 時季変更権の有効性(3)一時事通信社事件
最3小判平成4年6月23日(平成元年(オ)399号)(民集46巻4号306頁)
要因
長期連続休暇に対する時季変更権の行使は有効か。
事実
Y会社の記者であるXは、科学技術庁(当時)の科学技術記者クラブに1人だけ配置されていた。Xは、昭和55年当時において、前年度の繰り越し分を含めて40日間の年休日数を有していたところ、同年6月30日、休暇および欠勤届を提出し(8月20日から9月20日まで)、年休の時季指定をした(所定の休日等を除いた年休日は24日)。
これに対し、Xの所属する社会部の部長は、Xが1か月も不在になれば、取材活動に支障をきたすおそれがあり、代替記者を配置する人員の余裕もないとの理由をあげて、Xに対し、2週間ずつ2回に分けて休暇を取ってほしいと回答した上で、後半の2週間の時季指定については業務の正常な運営を妨げるものとして、時季変更権を行使した。しかし、Xは、8月22日から9月20日までの間、欠勤した。
そこで、Y会社は、時季変更権を行使した9月6日から20日までの間の勤務を要する10日間について業務命令に反して就業しなかったことを理由にXを譴責処分に処し、賞与も減額支給した。Xはこの時季変更権の行使は違法であるとして、譴責処分の無効確認と賞与の減額分の支給を求めて、訴えを提起した。1審は、時季変更権の行使を有効としたが、原審は、Xの請求をほぼ認容した。そこで、Y会社は上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し。
Ⅰ 「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務設計、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。しかも、使用者にとっては、労働者が時季指定をした時点において、その長期休暇期間中の当該労働者の所属する事業場において予想される業務量の程度、代替勤務者確保の可能性の有無、同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業活動の正常な運営の確保にかかわる諸般の事情について、これを正確に予測することは困難であり、当該労働者の休暇の取得がもたらす事業運営への支障の有無、程度につき、蓋然性に基づく判断をせざるを得ないことを考えると、労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない」。
Ⅱ 「もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右裁量的判断は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右裁量的判断が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、・・・・時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである」。
解説
本判決は、労働者が長期連続の年休の時季指定をした場合には、使用者との事前の調整が必要であるとし、そのような調整を経ない時季指定に対しては、時季変更権の行使において、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるをえないとする(判旨Ⅰ)
もっとも、この使用者の裁量的判断は、年休権を保障している趣旨に沿う合理的なものでなければならない(判旨Ⅱ)
本判決は、Xの担当していた業務は専門的知識を要するもので、代替要員の確保が困難であったこと、記者クラブへの単独配置は企業経営上やむをえないものであったこと、Xが時期や期間についてY会社との間で十分な調整を行わずに、長期連続休暇の時期指定をしていること、Y会社は部長から理由をあげて2回に分けて休暇を取得するよう回答し、実際に後半部分のみ時季変更権を行使するなど、相当な配慮をしえいることを考慮して、最終的には、時季変更権の行使を有効と判断した(判旨外)。
長期連続の年休は、労働者の休息や余暇の保障という点では、望ましいものであるが、本判決によると、使用者との十分な事前調整が必要であるし、そのような調整がなされなければ、時季変更権の行使が有効とされやすくなるなど、労働者にとってその取得は容易ではない。なお、長期連続休暇とは逆に、1日未満の細切れの年休取得については、使用者が任意に応じれば有効と解されてきたが、平成20年の労基法改正により、過半数代表との労使協定に基づき、5日以内であれば、時間年休を取得できるいおうになった(39条4項)。
労働基準法39条 (年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
一年 一労働日
二年 二労働日
三年 四労働日
四年 六労働日
五年 八労働日
六年以上 十労働日
③ 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。
⑨ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
112 計画年休一三菱重工長崎造船所事件
福岡高判平成6年3月24日(平成4年(ネ)306号)
要因
労基法上の計画年休協定の定める年休日は、労働者に対して拘束力をもつか。
事実
船舶等の製造・修理を業とするY会社のA造船所では、昭和59年以来、夏季の連続休暇を実施する一環として有給休暇の一斉付与措置を行っていた。しかし、これに反対する少数労働組合Bの組合員に対しては、そのような措置はとっていなかった。昭和62年に労基法が改正され、協定による計画的年休付与が定められていたことから、Y会社は、反対するB組合にも、計画年休措置をとることができると考えた。そこで、昭和63年10月、B組合と計画年休措置について団体交渉を行ったが、合意には至らなかった。他方、Y会社は、A造船所の従業員の98%で組織するC労働組合との間で、平成元年7月25日、26日の2日間を年休日とする計画年休協定(本件協定)を締結し、その協定に従い、本件計画年休を実施した。
B組合の組合員であるXは、同月27日、28日に年休を取得するとして、欠勤した。Y会社は、計画年休付与措置によって、Xの年休残日数が1日になっているため、27日は年休となるが、28日は欠勤となるとして、28日分の賃金を控除した。Xは、残存保有有給休暇日数の確認と控除分の賃金の支払をい等を求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求を棄却したので、Xは控訴した。
判旨 控訴棄却(Xの請求棄却)
Y会社のA造船所における本件計画年休は、労基法39条6項の趣旨に則り、年休の取得を促進するため、平成元年から、C組合との間の書面による協定に基づいて実施されたものである。本件協定の締結にあたっては、昭和63年10月以降、3つの労働組合との団体交渉を通じて、制度導入の提案、趣旨説明、意見聴取等適正な手続を経由したことが認められる。そして、本件計画年休は、その内容においても、事業所全体の休業による一斉付与方式を採用し、計画的付与の対象日数を2日に絞るとともに、これを夏季に集中させることによって大多数の労働者が希望する10日程度の夏季連続休暇の実現を図るという法の趣旨に則ったものであり、現時点において、年休取得率の向上に寄与する結果が得られていると否とを問わず、Xについて、適用を除外すべき特別の事情があるとは認められない以上、これに反対するXに対しても、その効力を有するものというべきである。
解説
計画年休制度は、昭和62年の労基法改正の際に、年休の取得の向上を目的として導入されたものである(労基法39条6項)。これは、過半数代表と使用者との間の書面協定により、年休の時季を定めた場合には、労働者の時季指定権と使用者の時季変更権がともに消滅し、協定が定めた時季に年休日が特定されるというものである(ただし、この効果は、労働者の年休の5日分を超える部分だけである)。計画的付与の方法としては、本件のような一斉付与方式があるほか、班別の交代付与方式、付与計画表による個人別付与方式等がある(昭和63年1月1日基発1号を参照)。
計画年休協定に私法上の効力が認められるかについては議論がある。労使協定の代表例である三六協定については、免罰的効力しかなく、三六協定の内容に則して使用者が時間外労働を命じるためには、別途に労働契約上の根拠が必要と解されている(→【102】日立製作所武蔵工場事件)。
ただ、時間外労働については、そもそも労働時間の長さが労働契約により、きめられるものであり、三六協定は労基法によるその規制を解除するという効果しかないとかいされるのに対して、年休は労基法に根拠をもつ権利であり、計画年休協定は、その年休の付与方法に関する特別なルールを定める者なので、その協定に法的な拘束力を認めるのは、むしろ、当然といえるであろう。本判決も、このような立場に立っている。
もっとも、本件のように少数組合が計画年休に反対している場合に、少数組合の組合員にまで、労使協定の効力を及ぼすのには問題があるという考え方もあろう。本判決は、そのような点もふまえて、協定が適正な他続を経由して締結されたことに言及し、それを考慮にいれて、協定の拘束力を認めているように思われる。しかし、解釈論としては、労使協定が過半数組合との間で、書面により締結されるという形式要件を満たしていえrば、その協定は、当該事業所の全労働者に拘束力が及びと解さざるを得ないし、そう解するほうが、計画年休制度導入の立法趣旨にも沿うであろう。
また、判旨は、一般論として、協定の適用を除外すべき特別の事情がある場合には、協定の効力を否定する趣旨のようにも読める。どのような場合には、協定の効力を否定する趣旨のようにも読める。どのような場合に、特別の事情が認められるかははっきりしないが、行政当局は、特別の事情により年休の付与をあらかじめ定めることが適当でない労働者については、計画的付与の対償から除外することなどを、労使関係者が考慮するよう指導することとしている(昭和63年1月1日基発1号)。
労基法39条6項
⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
113 年次有給休暇の取得と不利益取扱一沼津交通事件
最2小判平成5年6月25日(平成4年(オ)1078号)(民集47巻6号4585頁)
要因
年休による欠勤日を皆勤手当ての算定において欠勤扱いすることは適法か。
事実
Xは、タクシー業を営むY会社の乗務員である。Y会社では、乗務員の出勤率を高めるため、ほぼ交番表(月ごとの稼働予定表)どおり出勤した者に対して、報奨として皆勤手当を支給することとしていた。Y会社は、その従業員で組織する労働組合(Xも加入)との間で締結された労働協約において、交番表に定められた労働日数および労働時間を勤務した乗務員に対し、昭和63年度は1か月3100円、平成元年度は1か月4100円、の解禁手当を支給していた。
Xは、昭和62年8月から平成3年2月までの43か月間に42日の年休を取得していた。労働協約では、皆勤手当は、欠勤が1日のときは半額とし、欠勤が2日以上のときは不支給とされていたが、この欠勤には、年休を含むものとして運用されてきた(A組合もこのことは了承していた)。しかし、その後、労働基準監督署の指導があり、A組合との交渉で、年休を欠勤扱いとしないことにし、他方これまでの減額・不支給分については組合としては、請求しないこととした。
Xは、A組合の方針に反して、皆勤手当の過去の減額・不支給分の支払いを求めて訴えを提起した。なお、Xの現実の給与支給月額の中で、皆勤手当の額の占める割合は、最大でも1.85%にすぎなかった。
1審はXの請求を認容したが、原審は原判決を取消し、Xの請求を棄却した。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却
労基法136条が、「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定していることからすれば、使用者が、従業員の出勤率の低下を防止する等の観点から、年次有給休暇の取得を何らかの経済的不利益と結びつける措置を採ることは、その経営上の合理性を是認できる場合であっても、できるだけ避けるべきであることはいうまでもないが、右の規程は、それ自体としては、使用者の努力義務を定めたものであって、労働者の年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱いの私法上の効果を否定するまでの努力を有するものと解されない。また、右のような措置は、年次有給休暇を保障した労働基準法39条の精神に沿わない面を有することは否定できないものであるが、その効力については、その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等、諸般の事情を総合して、年次有給休暇を取得する権利の行使を抑制し、ひいては、同法が労働者に右権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる者でない限り、公序に反して、無効となるとすることはできないと解するのが相当である」。
解説
労基法136条は、年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない、と定めている。本判決は、文言に忠実に、同条は努力義務を定めたものであり、私法上の効力はもたないとした(学説上は、この判旨に批判的な見解もある)。その一方で、労基法等に基づく権利の行使を抑制し、その権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められれば、公序良俗として、無効となるという判例法理(エヌ・ビー・シー工業事件ー最3小判昭和60年7月16日、日本シュ―リング事件ー最1小判平成元年12月14日、【133】東朋学園事件を参照)は適用されるとしている。
本判決は、Y会社は、交番表が作成された後に乗務員が年休を取得した場合には、代替要員の手配が困難となり、自動車の実働率が低下するという事態が生じるので、このような形で年休を取得することを避ける配慮をした乗務員には皆勤手当を支給するとしたものであって、この措置は、年休の取得を一般的に抑制する趣旨に年休を取得したことにより控除される皆勤手当の額が、年休を取得したことにより、控除される皆勤手当の額が相対的に大きいものではないことなどから、結論としては、公序良俗にはならないとしている(判旨外)。
なお、判例には、年休の所得日を、その属するきかんに対応する賞与の計算上欠勤として扱うことはできないとしたものである(エス・ウント・エー事件ー最3小判平成4年2月18日)。
労基法136条
第136条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
労基法39条
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
一年 一労働日
二年 二労働日
三年 四労働日
四年 六労働日
五年 八労働日
六年以上 十労働日
③ 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)
三 その他厚生労働省令で定める事項
114 業務上の負傷・死亡一行橋労基署長(テイクロ九州)事件
最2小判平成28年7月8日(平成26年(行ヒ)494号)
要因
歓送迎会に参加後の事故と業務遂行性
事実
A会社では、その親会社の中国での子会社から受け入れていた中国人研修生のために、社長業務を代行していたB部長の発案で、親睦を深めるために本件歓送迎会(費用はA会社負担)が開かれることとなった。A会社で勤務するCも、B部長から参加を勧められた。Cは、いったんは期限が迫っている資料作成の仕事があることを理由に断ったものの、最終的にはこれに応じることとし、当日は、資料作成業務を一時中断して、遅れて参加した。歓送迎会後は、B部長が中国研修生をその居住するアパートまで送るはずであったが、結局、Cが送ることになり、Cはその途中で交通事故に遭い死亡した。
Cの妻のXは、Y労働基準監督署長に対し、労災保険法に基づく遺族補償給付、および、葬祭料の支給を請求したが、YはCの死亡が業務上の事由によるものにあたらないことを理由に不支給決定をした。そこでXは、取消訴訟を提起したが、1審や、本件歓送迎会は、従業員有志によって開催された私的な会合であり、Cが任意に行った運転行為が、A会社の支配下にある状態でされたものとは認められないとして、Cの死亡は業務上の事由によるものとはいえないと判断して、請求を棄却した。原審も、この判断を支持した。そこで、Xは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xの請求認容)。
Ⅰ 労働者の負傷、疾病、死亡等が労災保険法に基づく業務災害に関する保険給付の対象となるには、「それが業務上に関する保険給付の対象となるには、「それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の1つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である」。
Ⅱ 「Cは、A会社により、その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、本件工場における自己の業務を一時中断して、これに途中参加することとなり、本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため、本件車両を運転して、本件、工場に戻るに当たり、併せてB部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていった際に4本件事故に遭ったものということができるから、本件歓送迎会が事業場外で開催され、アルコール飲料も供されたものであり、本件研修生らを本件アパートまで送ることがB部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても、Cは、本件事故の際、なお本件会社の支配下にあったというべきである。また、本件事故によりCの死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである」。
解説
1 労災保険制度における保険給付の対象となる「業務災害」とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」である(労災保険法7条1項1号)。「業務上」かどうかの判断は、行政解釈によると、災害が業務に起因するものでなければならず(業務起因性)、そのためには、災害が業務の遂行中にすなわち労働者が事業主の支配ないし管理下にある状態で発生したものであること(業務遂行性)が必要とされている。判例は、このうち業務遂行性については、「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態」かどうかを判断基準としている(十和田労基署長(白山タイル)事件ー最3小判昭和59年5月29日(自家用車による通勤途上の事故について、結論としては業務遂行性を否定)。判旨Ⅰも同旨)。
2 一般に「業務遂行性」が認められるケースとしては、、
①事業主の支配下にあり、かつ、その管理下にあって、業務の従事している場合、
②事業主の支配下にあり、かつその管理下にあるが、業務には従事していない場合、
③事業主の支配下にあるが、その管理を離れて、業務に従事している場合がある。
歓送迎会や忘年会などへの参加は、③に該当するかが問題となり、これを否定した例もある(福井労基署長(足羽道路企業)事件ー名古屋高金沢支判昭和58年9月21日等)が本判決の事案では、歓送迎会が会社の事業活動に密接に関連するものであり、それへの参加が事実上強制されていたことや、事故が、社長業務を代行していた部長が行う予定あったことを、Cが代わって遂行中に起きたということが重視された、業務遂行中に肯定された(判旨Ⅱ)
3 業務遂行中が認められても、業務起因性が否定されれば、「業務上」の災害とはならない。たとえば、上記①の場合でも、それが自然現象やけんかなどの被災者の私的な逸脱行為などによる場合(仕事上の注意に端を発した大工のけんんかについて、業務起因性を否定した判例として、倉敷労基署長事件ー最1小判昭和49年9月2日)、上記②の場合でも、事業場施設やその管理の不備・欠陥によるものでない場合(出張中の飲酒とともなう死亡事故について、業務起因性を肯定した裁判例として、大分労基署長(大分放送)事件ー福岡高判平成5年4月28日)には、業務起因性が否定される。
労災保険法7条1項1号
〔保険給付の種類等〕
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
115 業務上の疾病一横浜南00労基署長(東京海上横浜支店)事件
最1小判平成12年7月17日(平成7年(行ツ)156号)
要因
過労により発症した脳疾患について、業務起因性が認められるか。
事実
Xは、A海上火災保険株式会社の横浜支店で支店長付の運転手の業務に従事していた。Xの昭和58年1月から昭和59年5月11日までの時間外労働時間は、1か月平均150時間、走行距離は1か月平均約3500キロメートルであり、特に同58年12月以降の1日平均の時間外労働時間は7時間を上回り、(深夜労働時間も含まれる)、同月以降の各月の走行距離もかなり多かった。
昭和59年5月10日、Xは、午前5時50分に車庫を出発し、午後7時30分頃、車庫に帰ったが、午後7時50分ころエンジンオイルの漏れを発見し、午後11時ころまでかかって修理し、午前1時頃に就寝した。
Xは、同月11日、午前4時30分頃起床し、午前5時少し前に車庫に行き、支店長を迎えに行くため自動車を運転して車庫を出たが、その後、間もなく、本件くも膜下出血を発症した。
Xは、昭和56年10月と同57年10月の各健康診断では、血圧が正常と高血圧の境界領域にあり、高血圧症が進行していたが、治療の必要のない程度のものであった。Xには、酒、たばこ等健康に悪影響を及ぼすと認められる嗜好はなかった。
Xは、本件くも膜下出血の発症により休業したため、Y労基署長に対して、休業補償の請求をしたところ、Yは不支給処分とした。そこで、Xはこの処分の取消しを求めて訴えを提起した。1審はXの請求を認容したが、原審は1審判決を取り消した。そこで、Xは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xの請求認容)。
Xの業務は、精神的緊張を伴うものであったうえ、支店長の業務の都合に合わせて行われる不規則なものであり、拘束時間がきわめて長く、また、その労働密度は決して低くはない。Xは、本件、くも膜下出血の発症に至るまで相当長期間にわたりこのような業務に従事してきたのであり、このような勤務の継続がXにとって精神的、身体的にかなりの負荷となり慢性的な疲労をもたらしたことは否定し難い。Xの発症前日にかけての業務は、Xの従前の業務を比較して、決して負担の軽いものであったとはいえず、それまでの長時間にわたる過重な業務の継続と相まって、Xにかなりの精神的、身体的負担を与えたものとみるべきである。
「Xの基礎疾患の内容、程度、Xが本件くも膜下出血発症前に従事していた業務の内容、態様、遂行状況等に加えて、脳動脈りゅうの血管病変は慢性の高血圧症、動脈硬化により増悪するものと考えられており、慢性の疲労や過度のストレスの持続が慢性の高血圧症、動脈硬化の原因の1つとなり得るものであることを併せて考えれば、Xの右基礎疾患が右発症当時その自然の経過によって一過性の血圧上昇があれば直ちに破裂を来す程度にまで増悪していたとみることは困難というべきであり、他に確たる憎悪要因を見いだせない本件においては、Xが右発症前に従事した業務による過重な精神的、身体的負荷がXの右基礎疾患をその自然の経過を超えて憎悪させ、右発症に至ったものとみるのが相当であって、その間に相当因果関係の存在を肯定することがせきる」。
解説
「業務上の疾病」の範囲については、労基法75条2項に基づき、同法施行規則35条、別表第1の2において列挙されている。また、そこに具体的に列挙されていない疾病であっても、「その他業務に起因することの明らかな疾病」であれば「業務上の疾病」と認められる(別表第1の2第11号)。本件において問題となったくも膜下出血のような過労を原因とする脳心臓疾患は、以前は別表第1の2に列挙されていなかったが、平成22年5月の改正により、心理的負荷等による精神的障害と並び、列挙されることになった(8号。精神障害は9号)。
脳心臓疾患の業務上認定について、行政による認定基準が定められていた(昭和62年10月26日基発620号、平成7年2月」1日基発38号)が、厳しすぎるとの批判があった。特に長期間の就労による疲労やストレスの蓄積に起因する脳心臓疾患については、従来の認定基準では、業務起因性を認めることが困難であった。
そのようななか、本判決は、発症直前の業務が特に過重であるという事情がないにもかかわらず(ただし、「決して負担の軽いものではなかった」と認定されている)、基礎疾患の程度や内容(治療を要するほどの高血圧ではなかったこと)、業務の内容(精神的緊張をともなうもので、労働密度も低いとはいえなかったこと)に加え、「他に確たる憎悪要因をみいだせない」こと(本件では、健康に悪影響を及ぼす嗜好がなかったことが重要である)から、業務上の負荷との間の相当因果関係を肯定した(つまり、業務起因性を肯定した)。
新たな認定基準を設け(平成13年12月12日基発1063号)、「長期間の過重業務」による発症の過重性も考慮されるようになった。とくに発症前1か月の時間外労働が100時間を超える場合、または、発症前2か月間ないし6か月間の1か月平均の時間外労働がおおむね80時間を超える場合には、業務と発症の関連性が高いとしている)。
労基法75条2項(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
労基法施行規則35条、
第三十五条 法第七十五条第二項の規定による業務上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする。
労基法施行規則35条、別表第1の2第11号
労働基準法施行規則別表第一の二
十一その他業務に起因することの明らかな疾病
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
別表第一の二
一業務上の負傷に起因する疾病
二物理的因子による次に掲げる疾病
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の
造血器障害、骨壊死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務による熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊え死
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
三身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
3 さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢循環障害、末梢神経障害又は
運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務による後頭部、頚部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
四化学物質等による次に掲げる疾病
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの
2 弗素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
4 蛋たん白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘ぜん息等の呼吸器
疾患
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
別表第1の2第8号
八長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止
(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
別表第1の2第9号
九人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
別表第1の2第11号
十一その他業務に起因することの明らかな疾病
116 治療機会の喪失一地公災基金愛知県支部長(瑞鳳小学校)事件
最3小判平成8年3月5日(平成4年(行ツ)70号)
要因
発症には、業務起因性がない場合でも、その後の業務の遂行により、治療機会が奪われたために症状が悪化した場合には、業務起因性が認められるか。
事実
Aは、市立B小学校の教諭として勤務していたところ、ポートボールの練習試合の審判として球技指導中、ハーフタイムに気分が悪いといって倒れ、意識不明をなって入院した。入院先で、Aは特発性脳内出血と診断され、緊急手術を受けて一時意識状態が好転したが、その後死亡した。
Aは、意識不明となった当日は、午前7時40分過ぎころ出勤し、直ちにポートボールの練習指導を行い、続いて朝の会に参加した後、時間割表通りに授業を行い、午前11時35分から50分まで清掃指導をした。その後、C小学校で練習試合があり、他校の試合で審判もすることになっていたため、午後1時ころ自家用車に児童を同乗させて市内のC小学校へ出発した。
Aは、当日出勤後間もないころから頭痛等の身体的不調を訴え、普通の健康状態にあるとは考えにくい行動をとり、また、体調が悪いことから、昼ころとポートボールの試合の審判の開始前の2回にわたり、同僚の教諭らに審判の交代を頼んだが、聞き入れられず、やむなく午後2時ころに始まった他校の試合に審判として臨んだものであった。
Aの妻子であるXらは、地方公務員災害補償法に基づき、地公災基金支部長(Y)に遺族補償と葬祭料の支給を請求したところ、公務外認定処分を受け支給が認められなかった。Xらは、この不支給処分について、所定の機関に、審査請求、再審査請求をしたが、いずれも棄却された。そこで、Xら公務外認定処分の取消しを求めて訴えを提起した。1審は、Xらの請求を認容したが、原審は1審判決を取り消し、Xらの請求を棄却した。そこで、Xらは上告した。なお、差戻し後の控訴審は、再びXらの請求を棄却し(名古屋高判平成10年3月31日)、その上告は棄却された(最2小判平成12年4月21日)。
判旨 原判決破棄、差戻し。
本件では、出血開始後の公務の遂行がその後の症状の自然的経過を超える憎悪の原因になったことにより、またはその間の治療の機会が奪われたことにより死亡の原因となった重篤な血腫が形成されたたという可能性を否定し去ることは許されない。
仮にこの可能性が肯定されるならば、Aの特発性脳内出血が後の死亡の原因となる重篤な症状に至ったのは、午前中に脳内出血が開始し、体調不調を自覚したにもかかわらず、直ちに安静を保ち診察治療を受けることが困難であって、引き続き公務に従事せざるをえなかったという。公務に内在する危険が現実化したことにようるものとみることができる。
解説
本件では、Aが特発性脳内出血を発症したこと自体については、公務起因性(民間の労災保険における業務起因性に相当する)が認められていない。しかし、本判決は、そのような場合でも、発症後の公務の遂行がその後の症状の自然的経過を超える憎悪の原因になったり、あるいは、その間の治療の機会が奪われたことにより重篤化をもたらした場合には、公務起因性が認められるという判断枠組みを示している(ただし、差戻し後の上告審は、「発症当日に行った公務が脳内出血の拡大に影響を及ぼしたことは認められず、また、発症後直ちに医師の診察を受けたとしても脳内出血の拡大を防ぐことができたとは認められない」とした差戻し控訴審の判断を受け入れて、公務外認定処分を適法としている)。
また、最高裁は、発症後、入院して適切な治療と安静を必要としていたにもかかわらず公務に戻り、その後、死亡したという事案で「直ちに安静を保つことが困難で、引き続き公務に従事せざるを得なかったという、公務に内在する危険が現実化した」として公務起因性を認めている(地公災基金東京都支部長(町田高校)事件ー最3小判平成8年1月23日)。
これは、公務災害の事案であるが、民間労働者の労災事案においても、同様の判断が示されている(中央労基署長(永井製本)事件ー東京高判平成12年8月9日、尼崎労基署長(森永製菓塚口工場)事件ー大阪高判平成12年11月21日)。
117 過労自殺と労災一豊田労基署長(トヨタ自動車)事件
名古屋高判平成15年7月8日(平成13年(行コ)28号)
要因
過労によりうつ病に罹患して自殺した場合に、業務起因性が認められるか。
事実
Aは、B自動車会社の設計課に所属していた従業員である(35歳)。Aは、当時係長の職に就いており、中間管理職として、一般職員よりもストレスが強い業務に従事していた。Aは、昭和63年2月以降、業務量が格段に増加する一方で、Aの残業時間数は、設定されていた目標残業時間数にほぼ合致しており、それだけAの労務密度は、たかいものになっていた。
昭和63年7月は、Aの部署で設計作業の締切が迫るなど、業務が過重になり、同月の時間外労働時間は68.5時間であった。この頃、Aは所属する労働時間から強い要請により、職場委員長に就任している。
就任は9月からの予定であったが、Aは業務に支障をしたすことを懸念し、不安や焦燥感を相当感じることとなった。さらにAは、同年8月20日に、16日間の海外出張を命じられた(出張は6か月先)が、Aは自分の部署の作業遅延を期にかけ、出張によって、設計作業の締切が遵守できなくなると悩んでいた。
Aは、同年8月25日に、ビルから飛び降り自殺した。Aの妻Xは、Aの自殺は、業務に起因するうつ病によるものであるとして、Y労基署長に対し、労災保険に基づく遺族補償年金と葬祭料の申請を行ったが、Yは不支給処分をした。Xは、この不支給処分の取消しを求めて、訴えを提起した。1審は、Xの請求を認容したので、Yが控訴した。
判旨 控訴棄却(Xの請求認容)。
業務と精神疾患の発症・憎悪との間に相当因果関係が肯定されるためには、単に業務が他の原因と共働して精神疾患を発症もしくは憎悪させて原因であると認められるだけでは足りず、当該業務自体が、社会通念上、当該精神疾患を発症もしくは、憎悪させる一定程度以上の危険性を内在または、随伴していることが必要である。
うつ病発症のメカニズムは十分解明されていないが、現在の医学的知見によれば、「ストレスー脆弱性」理論が合理的であると認められる。もっとも、「ストレスー脆弱性」理論においても、ストレスと個体側の脆弱性の関係は、医学的に解明されているわけではない。したがって、業務とうつ病の発症・憎悪との間の相当因果関係の存否の判断は、うつ病に関する医学的知見を踏まえて、発症前の業務内容および生活状況ならびにこれらが労働者に与えた心身的負荷の程度、さらには当該労働者の基礎疾患等の身体的要因や、うつ病に親和的な性格等の個体側の要因等を具体的かつ総合的に検討し、社会通念に照らして判断するのが相当である。
Aは、過重、過密な業務および職場委員長への就任内定による心理的負荷とAのうつ病親和的な性格傾向が相乗的な影響し合って、昭和63年7月下旬ないし、8月上旬頃にうつ病を発症し、さらにその後の作業日程調整および本件主張命令によって、うつ病が急激に悪化し、うつ病による希死念慮の下に発作的に自殺したと認められる。
「上記の過重、過密な業務等による心身的負荷は、Aに対し、社会通念上、うつ病の発症だけでなく、憎悪においても、一定程度以上の危険性を有するものであったと認められるから、業務と本件うつ病の発症との間には、相当因果関係を肯定することができ、本件自殺は、本件うつ病の症状として発現したものであるから、労災保険法12条の2の2第1項の「故意」には該当しないものである」。
解説
労働者の自殺は、「故意による死亡」として、労災保険給付の支給対象とならないのが原則である(労災保険法12条2の2第1項)。かつての通達では、自殺が業務上の死亡と認定されるためには、労働者の自殺が心神喪失状態において行われることを要するとされていた。しかし、その後の通達により、業務による心理的負担によって、精神障害が発症したと認められる者が自殺を図った場合には、業務起因性を認めることとされ、(平成11年9月14日基発544号。さらに平成23年12月26日に新しい認定基準が出された[基発1226号第1号])、また、故意との関係でも、「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は、自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で、自殺が行われた場合には、故意には該当しない」と扱われることになった(平成11年9月14日基発545号)。本判決も、故意に該当しないと判断し、業務起因性を肯定している(→【118】静岡労基署長(日研化学)事件)。
労働者が業務による心理的負担から、うつ病等の精神障害となり、自殺したケースで問題となるのは、業務による心理的負荷の過重性の判断について、誰を基準とするのかとである。裁判例には、通常想定される範囲の同種労働者の中で、最も脆弱な者を基準とするという立場と、当該当事者と同種の業務に従事し遂行することが許容できる程度の心身の健康状態を有する労働者を基準とするという立場があり、本判判決は、前者の立場である(判旨外。後者の立場のものとして、三田労基署長(ローレルバンクマシン)事件ー東京地判平成15年2月12日等)。
労災保険法12条の2の2第1項
〔支給制限〕
第12条の2の2 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
118 いじめ自殺と労災一静岡労基署長(日研化学)事件
東京地判平成19年10月15日(平成18年(行ウ)143号)
要因
現場でのいじめによる自殺について、業務起因性が認められるか。
事実
A(昭和42年生まれ)は、大学卒業後の平成2年4月にB会社に入社し、同9年4月からC営業所C2係に所属して、医療情報担当者(MR)として勤務していた。同14年4月、C2係に係長Dが配属され、同係はD係長、Aと他1名の3人体制となった。C係長は大きな声で、一方的に、相手の性格や言い方等に気を配らずに傍若無人な話し方をする性格であり、Aに対しても、「存在が目障り」「車のガソリン代がもったいない」「何処へ飛ばされようと、Aは仕事をしない奴だと言いふらしたたる」「給料泥棒」「お前は対人恐怖症やろ」「肩にフケが付いている。お前、病気とちがうか」、などと発言していた。
Aは、平成15年3月、家族や上司を名宛人とする8通の遺書を残し、公園で自殺した。Aの妻であるXは、Y署長に対し、公園で自殺した。Aの妻であるXは、Y労基署長に対し、Aの死亡は、業務に起因するものであるとして、労災保険法に基づく遺族補償年金と葬祭料の支給を請求したが、Yは不支給処分をした。そこで、Xは、その処分の取消しを求めて訴えを提起した。
判旨 請求認容。
Ⅰ「精神障害の発症については、環境由来のストレスと、個体側の反応性、脆弱性との関係で、精神的破綻が生じるかどうかが決まるという「ストレス―脆弱性」理論が、現在広く受け入れられていると認められること・・・・からすれば、業務と精神障害の発症との間の相当因果関係が認められるためには、ストレスと・・・・個体側の反応性、脆弱性を総合考慮し、業務による心理的負荷が、社会通念上。客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であるといえる」場合に、業務に内在又は随伴する危険が現実化したものとして、当該精神障害の業務起因性を肯定するのが相当である」。
Ⅱ 「労働者の自殺についての業務起因性が問題となる場合、通常は、当該労働者が死の結果を認識し認容したものと考えられるが、少なくとも、当該労働者が業務に起因する精神障害を発症した結果、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺に至った場合には、当該労働者が死亡という結果を意図したとまではいうことができず、労災保険法12条の2の2第1項にいう「故意」による死亡には該当しないというべきである」。
Ⅲ「一般に、企業等の労働者が、上司との間で意見の相違等により、軋れつを生じる場合があることは・・・避け難いものである。・・・・上司とのトラブルに伴う心理的負荷が、企業等において、一般的に生じ得る程度のものである限り、社会通念上客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であるとは認められないものである。しかしながら、そのトラブルの内容が、上記の通常予定されるような範疇を超えるものである場合には、従業員に精神障害を発症させる程度に過重であると評価されるのは当然である」。
本件では、「D係長のAに対する態度によるAの心理的負荷は、人生においてまれに経験することもある程度に強度のものということができ、一般人を基本として。社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重なものと評価するのが相当である」。
解説
本判決は、いわゆるパワーハラスメント(パワハラ)をうけたことを原因とする自殺について、業務起因性を肯定したものである(パワハラの類型については、厚生労働省の「職場のいじめ、嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ」の報告書を参照)。
本判決は、多くの裁判例と同様(→【117】豊田労基署長(トヨタ自動車)事件)、精神障害の発症について、「ストレスー脆弱性」理論に基づき、ストレスと個体側の反応性・脆弱性を総合考慮し、業務による心理的負荷が、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であるといえる場合に、業務に内在または随伴する危険が現実化したものとして業務起因性を肯定するという判断枠組みを採用している(判旨Ⅰ)。自殺について、一定の場合に故意に否定するのも、近年の裁判例のとりである(判旨Ⅱ)。
本件では、D係長のパワハラにより、Aの受けた心理的負荷は、一般人を基準として、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重なものであったと判断されている(判旨Ⅲを参照)。擬態的には、本判決があげた事実は、
①D係長がAに対して発した言葉自体の内容が過度に厳しいこと、
②D係長のAに対する態度にAに対する嫌悪の感情の側面があること、
③D係長のAに対する極めて直截なものの言い方をしていたと認められること、
④C2係の勤務形態が、上司とのトラブルを円滑に解決することが困難な環境にあること、である(判旨外)。
民事損害賠償(安全配慮義務違反)の事件では、本判決以前に、職場でのいじめが原因となって自殺した事案で使用者に損害賠償責任が認められた例があるが(川崎市水道局事件ー東京訪販平成15年3月25日[ただし、本人の心理的要因も考慮して、7割の減額]、誠昇会北本共済病院事件ーさいたま地判平成16年9月24日[過失相殺なし]。このほか、自殺事件ではないが、暴言が過重な心理的負荷を与えたことなどを理由に慰謝労請求を認めた裁判例として、日本ファンド事件ー東京地判平成22年7月27日)。
118 いじめ自殺と労災一静岡労基署長(日研化学)事件
東京地判平成19年10月15日(平成18年(行ウ)143号)
要因
現場でのいじめによる自殺について、業務起因性が認められるか。
事実
A(昭和42年生まれ)は、大学卒業後の平成2年4月にB会社に入社し、同9年4月からC営業所C2係に所属して、医療情報担当者(MR)として勤務していた。同14年4月、C2係に係長Dが配属され、同係はD係長、Aと他1名の3人体制となった。C係長は大きな声で、一方的に、相手の性格や言い方等に気を配らずに傍若無人な話し方をする性格であり、Aに対しても、「存在が目障り」「車のガソリン代がもったいない」「何処へ飛ばされようと、Aは仕事をしない奴だと言いふらしたたる」「給料泥棒」「お前は対人恐怖症やろ」「肩にフケが付いている。お前、病気とちがうか」、などと発言していた。Aは、平成15年3月、家族や上司を名宛人とする8通の遺書を残し、公園で自殺した。Aの妻であるXは、Y署長に対し、公園で自殺した。Aの妻であるXは、Y労基署長に対し、Aの死亡は、業務に起因するものであるとして、労災保険法に基づく遺族補償年金と葬祭料の支給を請求したが、Yは不支給処分をした。そこで、Xは、その処分の取消しを求めて訴えを提起した。
判旨 請求認容。
Ⅰ「精神障害の発症については、環境由来のストレスと、個体側の反応性、脆弱性との関係で、精神的破綻が生じるかどうかが決まるという「ストレス―脆弱性」理論が、現在広く受け入れられていると認められること・・・・からすれば、業務と精神障害の発症との間の相当因果関係が認められるためには、ストレスと・・・・個体側の反応性、脆弱性を総合考慮し、業務による心理的負荷が、社会通念上。客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であるといえる」場合に、業務に内在又は随伴する危険が現実化したものとして、当該精神障害の業務起因性を肯定するのが相当である」。
Ⅱ 「労働者の自殺についての業務起因性が問題となる場合、通常は、当該労働者が死の結果を認識し認容したものと考えられるが、少なくとも、当該労働者が業務に起因する精神障害を発症した結果、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺に至った場合には、当該労働者が死亡という結果を意図したとまではいうことができず、労災保険法12条の2の2第1項にいう「故意」による死亡には該当しないというべきである」。
Ⅲ「一般に、企業等の労働者が、上司との間で意見の相違等により、軋れつを生じる場合があることは・・・避け難いものである。・・・・上司とのトラブルに伴う心理的負荷が、企業等において、一般的に生じ得る程度のものである限り、社会通念上客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であるとは認められないものである。しかしながら、そのトラブルの内容が、上記の通常予定されるような範疇を超えるものである場合には、従業員に精神障害を発症させる程度に過重であると評価されるのは当然である」。
本件では、「D係長のAに対する態度によるAの心理的負荷は、人生においてまれに経験することもある程度に強度のものということができ、一般人を基本として。社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重なものと評価するのが相当である」。
解説
本判決は、いわゆるパワーハラスメント(パワハラ)をうけたことを原因とする自殺について、業務起因性を肯定したものである(パワハラの類型については、厚生労働省の「職場のいじめ、嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ」の報告書を参照)。
本判決は、多くの裁判例と同様(→【117】豊田労基署長(トヨタ自動車)事件)、精神障害の発症について、「ストレスー脆弱性」理論に基づき、ストレスと個体側の反応性・脆弱性を総合考慮し、業務による心理的負荷が、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重であるといえる場合に、業務に内在または随伴する危険が現実化したものとして業務起因性を肯定するという判断枠組みを採用している(判旨Ⅰ)。自殺について、一定の場合に故意に否定するのも、近年の裁判例のとりである(判旨Ⅱ)。
本件では、D係長のパワハラにより、Aの受けた心理的負荷は、一般人を基準として、社会通念上、客観的にみて、精神障害を発症させる程度に過重なものであったと判断されている(判旨Ⅲを参照)。擬態的には、本判決があげた事実は、
①D係長がAに対して発した言葉自体の内容が過度に厳しいこと、
②D係長のAに対する態度にAに対する嫌悪の感情の側面があること、
③D係長のAに対する極めて直截なものの言い方をしていたと認められること、
④C2係の勤務形態が、上司とのトラブルを円滑に解決することが困難な環境にあること、である(判旨外)。
民事損害賠償(安全配慮義務違反)の事件では、本判決以前に、職場でのいじめが原因となって自殺した事案で使用者に損害賠償責任が認められた例があるが(川崎市水道局事件ー東京訪販平成15年3月25日[ただし、本人の心理的要因も考慮して、7割の減額]、誠昇会北本共済病院事件ーさいたま地判平成16年9月24日[過失相殺なし]。このほか、自殺事件ではないが、暴言が過重な心理的負荷を与えたことなどを理由に慰謝労請求を認めた裁判例として、日本ファンド事件ー東京地判平成22年7月27日)。
119 安全配慮義務(1)-陸上自衛隊八戸整備工場事件
最3小判昭和50年2月25日(昭和48年(オ)383号)(民集29巻2号143頁)
要因
安全配慮義務とは何か。
事実
Aは昭和40年7月13日に陸上自衛隊八戸駐屯地に車両整備工場において車両を整備していたところ、後進していた大型自動車の後車輪で、頭部を轢かれて即死した。Aの両親であるXらは、昭和44年10月6日に、Y(国)に対して、損害賠償を請求したが、Xらの請求を棄却した。そこでXらは、上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し。
Ⅰ「国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設、もしくは、器具等の設置管理又は、公務員が国もしくは、上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するべき義務(以下、「安全配慮義務」という。)を負っているものと解すべきである」。
Ⅱ「もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、公務員の職種、地位、及び安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等違によって、異なるべきものである。」
Ⅲ「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として、当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として、一般的に認められるものであって、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はない。」
解説
1 労災が発生したとき、被災労働者(死亡の事故の場合にはその遺族)は、シフから労災保険給付が支給されるが、さらに使用者に対して損害賠償を請求することも可能である(労災保険給付と民事損害賠償との調整については、→【125】三共自動車事件等)。その際の損害賠償請求の根拠となるのが、使用者の安全配慮義務である。
使用者(またはその従業員)の過失または故意にょり労災が発生したときに、使用者が、民法709条、715条等により不法行為に基づく損害賠償責任を負うことについては異論がない(本件では、自動車損害賠償責任保険法3条による責任も問題となっている)。
問題は、労働者側が。使用者の安全配慮義務違反を理由として、債務不履行による損害賠償請求(民法415条)ができるかである。こうした債務不履行構成と、前述の不法行為構成とでは、時効の点で重要な違いがでてくる。本件では、事故から約4年3か月経過後に提訴がなされているが、自動車損害賠償の請求権(時効については、民法の不法行為による規定が適用される)は、3年で時効消滅してしまう(民法724条)ので、加害者が時効を援用すると、労働者側の請求は認められないことになる。これに対し、債務不履行による損害賠償請求権が認められると、時効は10年となる。
(民法167条1項、改正民法の施行後は、166条1項[1号適用の場合は時効は5年])ので、本件のような事案でも請求がおまられることになる。この点について、本判決は、公務員の事案であったが、使用者に安全配慮義務を認めた最初の最高裁判決であり(判旨Ⅰ)、時効期間も10年となることを認めた(判旨外)
しかも、「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」と述べており(判旨Ⅲ)、この判示部分から、安全配慮義務は、国と公務員との関係だけでなく、民間労働者にも広く適用しうるものと解することができた。実際、その後の判例は、民間労働者と使用者との関係にぽいても、安全配慮義務を認めている→【120】川義事件)。
その後は、労契法において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるいおう、必要な配慮をするものとする」と規程され(5条)、使用者の安全配慮義務は明文の根拠をもつものとなっている。
2 前述のように、時効との関係で、安全配慮義務が認められたことの意味は大きい。さらに、不法行為構成の場合には、労働者側は使用者の過去を証明しなければならず、その立証は必ずしも容易ではないのに対して、債務不履行責任の場合には、使用者が帰責事由のないことを立証しなければならない(航空自衛隊事件ー最2小判昭和56年2月16日)という点でも、債務不履行責任構成のほうが、労働者側に有利である。ただし、安全配慮義務の具体的な違反は、労働者側で主張立証しなければならないので、実際上の労働者側の負担は、債務不履行構成であっても必ずしも軽いおものではない。
一方、債務不履行構成の場合はには、不法行為構成の場合(民法711条)とは異なり、遺族に固有の慰謝料の請求は認められていない(大石塗装・鹿島建設事件ー最1小判昭和55年12月18日)。また、損害賠償の履行が遅滞したことに対する遅延損害金の発生については、不応行為構成の場合には、事故の日からであるのに対して、債務不履行構成の場合には、履行の請求時の翌日からとなる(民法412需要3項を参照。前掲・大石塗装・鹿島建設事件)。これらの点では、不法行為構成のほうが、労働者側に有利となる。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法715条(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
自動車損害賠償責任保険法3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
民法415条(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
民法167条(債権等の消滅時効)
第167条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
労契法5条 (労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
民法710条(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法166条(消滅時効の進行等)
第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
民法412条3項(履行期と履行遅滞)
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
120 安全配慮義務(2)-川義事件
最3小判昭和59年4月10日(昭和58年(オ)152号)(民集38巻6号557頁)
要因
宿直中の従業員が強盗により殺害された場合において、使用者に安産配慮義務違反は認められるか。
事実
Y会社の従業員であるAは、宿直勤務中、Y会社に侵入して商品を盗もうとした同社の下従業員Bに殺害された。Aの両親のXらは、Y会社の安全配慮義務違反を理由に、損害賠償の請求をした。1審は。Xらの請求を一部認容した(Aの過失を3割5分と認定して過失相殺している)。原審も、Xらの請求を一部認容した(Aの過失を2割5分として過失相殺している)。そこで、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求の一部認容、一部棄却)。
Ⅰ 「雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるから、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは、器具等を使用すし又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負っているものっと解するのが相当である」。
Ⅱ 「もとより、使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって、異なるべきものであることはいうまでもないが、これを本件の場合に即してみれば、Y会社は、A1人に対し・・・24時間の宿直勤務を命じ、宿直勤務の場所を本件社屋内、就寝場所を同社屋1階商品陳列場と指示したのであるから、宿直勤務の場所である本社社屋内に、宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入できないような物的設備を施し、かつ、万一盗賊が侵入した場合は、盗賊から加えられるかも知れない危害を免れることができるような物的施設を設けるとともに、これら物的施設等を十分に整備することが困難であるときは、宿直員を増員するとか宿直員に対する安全教育を十分に行うなどし、もって、右物的施設等と相まって、労働者たるAの生命、身体等に危険が及ばないように配慮する義務があったものと解すべきである」。
Ⅲ 本件では、Aに対する安全配慮義務の不履行があり、それにより、本件事故が発生したものということができるので、Y会社は、この事故によって被害を被った者に対し、その損害を賠償するべき義務がある。
解説
本件は、民間労働者につい使用者の安全配慮義務を認めた、最初の最高裁判決である(公務員については→、【119】陸上自衛隊八戸車両整備工場事件)。使用者には、労働契約上、安全配慮義務がある(現在は労契法5条)が、本判決は、これを、「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」と定義している(判旨Ⅰ)。
安全配慮義務の愚弟的内容は、「労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務となる当該具体的状況等によって異なるべきもの」とされており(判旨Ⅱ)、ケース・バイ・ケースの判断となる。
安全配慮義務の内容として、まず、あげられるのは、労働者の利用する施設、機械、器具等についての安全を確保する義務である。これは、設備等の物的な面での安全確保だけでなく、適正な人員配置といった人的な面からの安全確保も含まれる。本判決は、本件では使用者には、安全を確保できるよう物的施設等を十分に整備し、それが困難であるときは、宿直員を増員するとか宿直員に対する安全教育を十分に行うなどの義務があったと判断している(判旨Ⅱ)。
近年では、安全配慮義務の内容に、労働者の健康に配慮する義務も含まれるようになっている(労契法5条の「生命、身体の安全」には「健康」も含まれると解すべきである)。たとえば、労働者が過労により、脳出血で死亡したという事案(いわゆる過労死の事案)において、使用者は「労働時間、休憩時間、休日、休憩場所について適正な労働条件を確保し、さらに、健康診断を実施した上、労働者の年齢、健康状態に応じて従事する作業時間及び内容の軽減、就労場所の変更等適切な措置を採るべき義務を負う」という一般論を述べ、高血圧症の労働者に対して、業務の軽減措置等を講じなかったことに安全配慮義務違反があるとした裁判例がある(システムコンサルタント事件ー東京高判平成11年7月28日)。
さらに、最高裁は、過労死自殺の事案で、使用者に健康配慮義務を認め、その違反を理由とする損害賠償責任を肯定している(→【121】電通事件。ただし、不法故意の事案である)。
121 過労自殺と使用者の安全配慮義務責任-電通事件
最2小判平成12年3月24日(平成10年(オ)217号・218号)(民集54巻3号1155頁)
要因
労働者の過労による自殺について、使用者の安全配慮義務違反は認められるか。
事実
Aは、平成2年4月にY会社に入社し、同年6月にラジオ推進部に」配属された。Aは、同年8月ころから、翌日の1時ないし2時ころにきたくすることが多くなり、同年11月末ことまでは、出勤した翌日の午前4時ないし、5時ころに帰宅していたが、このころ以降、帰宅しない日があるようになった。
ラジオ推進部には、平成3年7月に至るまで、新入社員の補充はなく、このころ、Aは、帰宅しない日がおおくなった。Aは、心身ともに疲労困憊した状態になっていて、Aの上司もそれに気付いていた。
Aは、平成3年8月27日、自宅で自殺した。Aの両親であるXらは、Y会社に対して、民法415条ないし709条に基づき、Aの死亡による損害を請求した。1審は、Xの請求をほぼ全面的に認容したが、原審は、過失相殺の規程(民法722条)の類推適用により、発生した損害の7割のみをY会社に負担させるのを相当とする判断を行った。そこで、XらとY会社の双方が上告した。
判旨 Xらの敗訴部分について原判決破棄、差戻し。
Ⅰ 「労働者が労働日に長時間にわたり、業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険があることは、周知のところである。・・・・使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに関し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し、業務上の始期監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。
Ⅱ 「身体に対する加害行為を原因とする被害者の損害賠償請求において、裁判所は、加害者の賠償すべき額を決定するに当たり、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、民法722条2項の過失相殺の規程を類推適用して、損害の発生又は、拡大に寄与した被害者の性格等の心理的要因を一定の限度で、しんしゃくすることができる・・・・。この趣旨は、労働者の業務の負担が、過重であることを原因とする損害賠償請求においても、基本的に同様に解すべきものである。
しかしながら、企業等に雇用される労働者の性格が多様のものであることはいうまでもないところ、ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして、通常想定される範囲を外れるものでない限り、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が業務の過重負担に起因して当該労働者に生じた損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような事態は使用者として予想すべきということができる。しかも、使用者又はこれに代わって、労働者に対し業務上の指揮監督を行う者は、・・・・その配置先、遂行すべき業務の内容等を定める・・・・際に、各労働者の性格をも考慮することができるのである。したがって、労働者の性格が前記の範囲を外れるものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において、使用者の賠償すべき額を決定すべき額を決定するに当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を、心理的要因として、しんしゃくすることはできない」。
解説
使用者の安全配慮義務は、物理的な安全配慮面への配慮だけでなく、労働者の健康(精神的な健康も含む)の面への配慮も含められる(→【120】川義事件[解説]).
本判決は、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を負う」と述べている(判旨Ⅰ)。これは、不法行為における注意義務の内容として述べられているが、安全配慮義務(健康配慮義務)の内容としても、そのままあてはまると解すべきである。
自殺の場合には、本人が自ら起こしたことなので、そもそも相当因果関係があるのか、という論点もある。しかし、判例は、うつ病に罹患すると自殺に至る確率が、正常な場合よりも格段に高まる点を考慮して、過労によってうつ病に罹患すると自殺に至るまでの因果関係も肯定する傾向にある。その一方で、労働者の性格等の心理的要因は過失相殺の規定の類推適用により、損害額の減額理由となるものとする。ただし、労働者の性格は多様なので、「ある業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでないかぎりものでないかぎり」、その性格等を心理的要因として斟酌してはならない、と述べている(判旨Ⅱ)。
また、最近の判例は、労働者が自らの精神的健康についての情報を申告しなかったことをもって、過失相殺をすることは許されないとしている(東芝事件ー最2小判平成26年3月24日)。
民法415条(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
第722条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
122 労働災害と取締役の損害賠償責任-大庄ほか事件
大阪高判平成23年5月25日(平成22年(ネ)1907号)
要因
労働者が長時間労働により死亡した場合において、取締役も損害賠償を負うか。
事実
Aは、平成19年3月に大学卒業後、同年4月1日にY1会社に入社し、Y1会社の運営する店舗で調理関係の業務に従事していたが、同年8月11日未明に急性左心機能不全により死亡した。Aの労働時間は、死亡前の1か月間では、総労働時間約237時間34分、時間外労働時間数95時間58分、2か月目では、それぞれ、273時間41分、105時間41分、3か月目では、302時間11分、129時間6分、4か月目では、251時間6分、78時間12となっており、Aは、恒常的に長時間労働を行っていた(なお、本件は労災認定もされている)。
Y1会社は、新卒者の賃金は最低支給額19万4500円とされていたが、その内訳は、基本給が12万3200円、役割給が7万1300円で、役割給は80時間分の時間外労働を前提としたものであった。また、三六協定では、1か月100時間、1年間に6回、750時間を限度として延長できるものとされていて、実際、Aの勤務するB店でも月の労働時間が300時間を超えることが常態化していた。
Aの両親のX1・X2は、Y1会社には不法行為または債務不履行に基づき、また、代表取締役社長Y2およびその他の取締役Y3~Y5には、不法行為または、会社法429条1項に基づき、損害賠償請求した。1審は、Xらの請求を一部認容した。そこで、Yらは、控訴した。本判決に対して、Yらは、上告したが、上告棄却、不受理となっている。
判旨 控訴棄却(以下では、Y2~Y5に関する判示部分のみとりあげる)。
Ⅰ「取締役は、会社に対する善管注意義務として、会社が使用者としての安全配慮義務に反して、労働者の生命・健康を損なう事態をまねくことのないよう注意する義務を負い、これを懈怠して労働者に損害を与えた場合には、会社法429条1項の責任を負うと解するのが相当である」。
Ⅱ 人事管理部の上部組織である管理本部長Y5、店舗本部長Y3、店舗本部の下部組織である第一支社長Y4は。また、、店舗本部の下部組織である第一支社長Y4は、B店の労働状況を把握しうる組織上の役職者であって、現実の労働状況を認識することが十分に容易な立場にあり、その認識をもとに、担当業務を執行し、また、取締役会を構成する一員として取締役会の議論を通して、労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務を負っていた。また、Y2も代表取締役として、同様の義務を負っていた。しかるに、Y2らが、Y1会社をして、労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築させ、長時間勤務による過重労働を抑制させる措置をとらせていたとは認められない。
Ⅲ Y1会社では、基本給の中に時間外労働80時間分を組み込む給与体系の下で恒常的に時間外労働が1か月80時間を超える者が多数出現しがちであった。また、三六協定の特別延長事項に記載されていた臨時の特別の事情とは無関係に、恒常的に三六協定に定める時間外労働を超える時間外労働がなされていた。こうした恒常的に長時間労働は、B店だけでなく、他店でも惹起していたものと推認される。このような全社的な従業員の長時間労働について、Y2らは、認識していたか、極めて容易に認識できたと考えられる。
Ⅳ 「Y2らは、悪意又は重大な過失により、会社が行うべき労働者の生命・健康を損なうことがないような体制の構築と長時間労働の是正方策の実行に関して任務懈怠があったことは明らかであり、その結果Aの死亡という結果を招いたのであるから、会社法429条1項に基づく責任を負うというべきである」。
解説
会社法429条は、取締役らの、悪意、あたは重過失による任意懈怠により、第三者(労働者も含む)に損害が生じた場合の賠償責任を定めている。本件では、任意懈怠の有無、悪意または重過失の有無が問題となるが、本判決はまず、取締役は、会社に対する善管注意義務として、会社が安全配慮義務(労契法5条)にいはんしないよう注意する義務をおうとし(判旨Ⅰ)、本件では、Y2らに「労働者の生命・健康を損なうことがないような体制を構築すべき義務」があったとする(判旨Ⅱ)。しかし、Y1は会社では、長時間労働を前提とするような勤務体制がとられ、実際に長時間労働が恒常的に行われ、Y2らは、少なくともこれを極めて容易に認識可能であった(判旨Ⅲ)にもかかわらず、前記の義務に違反したとして、結論として、Y2らの悪意または重過失による任意懈怠を肯定した(判旨Ⅳ)。
本判決は、労働法令の遵守について、取締役も、一定の責任を負う可能性があることを示したものだが、その結論は、本件の給与体系や三六協定の内容から、いわば、制度的に長時間労働を認識しやすかったという事案の特殊性があることはそれほど多くないであろう(小規模会社で、代表取締役の責任を肯定した裁判例として、おかざき事件ー大阪高判平成19年1月18日、サン・チャレンジほか事件ー東京地判平成26年11月4日)。
会社法429条1項(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
一 取締役及び執行役 次に掲げる行為
イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ハ 虚偽の登記
ニ 虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 監査役及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
労契法5条(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
123 直接的な雇用関係がない者に対する安全配慮義務-三菱重工神戸造船所事件
最1小判平成3年4月11日(平成3年4月11日(平成元年(オ)516号・1495号)
要因
下請会社の4従業員の、作業場での騒音を原因とする聴力障害について、元請け会社に安全配慮義務違反が認められるか。
事実
Xら(18名)は、Y会社のいくつかの下請企業に在籍し、Y会社のA造船所において就労してきたが、聴力障碍に罹患した。Xら社外工は、その就労期間中、A造船所の敷地内で作業をし、Y会社の本工と一緒に同一の作業をすることもあった。Xら社外工に対する作業上の指揮監督については、直接的には各下請企業の責任者が行っていたが、それは、Y会社の職制から受けた指示に基づくものであった。
Xらは、聴力障碍は、A造船所における騒音によるものであるとして、Y会社に対して、安全配慮義務違反および不法行為を理由として、損害賠償(慰謝料)の請求を一部認容した。原審は、1審を一部変更したが、Xらの請求を一部認容した(なお、Xらの中には、消滅時効等を理由に請求を棄却された者もいる)。そこで、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xらの請求の一部認容)。
「Y会社の下請企業の労働者がY会社のA造船所で労務の提供をするに当たっては、いわゆる社外工として、Y会社の管理する設備、工具等を用い、事実上Y会社の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容もY会社の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、Y会社は、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し、安全配慮義務を負うものであるとした原審の判断は、正当として是認することができる」。
解説
安全配慮義務は、使用者が、労働契約関係にあたる労働者に対して、信義則上、負う義務がある。労契法においても、労働契約にともなう義務と規定されるている(5条)。では、労働契約関係にない者との間で、安全配慮義務が認められる余地はないのであろうか。本件は、元請会社が、下請会社の従業員に対して、安全配慮義務を負うことがあるかどうかが問われだ事件である。
安全配慮義務を最初に認めた最高裁判決は、この義務を「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において」認められるものとしており(→【129】陸上自衛隊八戸車両整備工場事件)、労働契約関係の存在がこの義務を前提になるとは考えられてはいない。実際、その後の最高裁判決においても、元請け企業が下請企業の従業員との関係で、「雇用契約ないしこれに準ずる法律関係の当事者」であるとして、安全配慮義務を負うことも認めるものがあった(大石塗装・鹿島建設事件ー最1小判昭和55年12月18日)。
本判決も、これらの判例を踏襲し、元請企業の安全配慮義務を認めた原審判断を支持している。実際上、問題となるのは、どのような事実関係がそろえば、「特別な社会的接触の関係に入った」と判断してよいのかである。本判決は、下請企業の労働者が、
①元請会社の事業場で労務の提供をしていること、
②元請会社の管理する設備、工場等を用いていること、
③事実上、元請会社の指揮・監督を受けて稼働していること、
④作業内容が元請会社の従業員(本工)とほとんど同じであったこと、という事実に言及している。
安全配慮義務は、不樗木な意味での指揮命令関係(労働契約に根拠づけられた指揮命令関係)がなくても、事実上、その指揮や監督が及んでづいる場合には、広く認められるべきであり、判例の傾向は、妥当といえるであろう(最近の否定例として、東京電力ほか3社事件ー静岡地判平成26年12月25日)。
なお、労働法の制定後においても、こうした判例は、実質的に維持されると解するべきである。同法5条の文言との関係では、そこでいう「労働契約」4を、実質的な意味での指揮監督が及んでいる関係を含むという解釈をとることも考えられるが、本件のようなケースが労契法の施行後に起きた場合には、労契法は直接適用できないものの、その類推適用をするという方法で処理するのが妥当であろう(労契法5条は、安全配慮義務を成文化したが、それは、安全配慮義務の成立範囲を労働契約に伴うものに限定するという趣旨と解すべきでない。
この場合、いかなる要件がそろえば、類推適用が認められるのかについては、本判決を含めた従来の判例を参考にして判断されていくことになろう。
労契法5条(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
124 労災保険給付と労働基準法上の災害補償責任-神奈川都市交通事件
最1小判平成20年1月24日(平成18年(受)1154号)
要因
業務災害により、休業中であった労働者が、症状固定により労災保険法上の休業補償給付を打ち切られた場合、労基法上の休業補償の支給を請求することが認められるか。
事実
Xは、Yタクシー会社の乗務員である。Xは、平成7年9月27日、タクシーに乗務中、第三者の運転する普通乗用自動車に衝突され、頸椎捻挫等の傷害を負った。Xは、本件は、本件事故の後、休業し、労災保険法に基づく休業補償給付を受けていたが、平成11年11月2日付けで、A労基署長から、Xの傷害につき、同年8月31日に症状が固定したとして、
①同年9月1日以降の療養、休業補償給付は、全部不支給とする、
②同年7月16日から同年8月31日までの休業補償給付は、実際に通院した日のみを療養のため、休業する日と認め、その余は、不支給とする旨の決定を受けた。
Xは、本件事故後、休職していたが、平成12年4月16日、タクシー乗務員として復職した。
Xは、Y会社に対し、平成11年7月16日から同12年4月15日までの期間について、主位的に、雇用契約または労働協約に基づく賃金の支払を求め、予備的に、労基法26条に基づく休業手当または、同法76条1項に基づく休業補償の支払いを求めた。1審は、Xの請求を棄却したが、労基法76条1項に基づく休業補償については、労災保険法の支給を受けた以外の残額は、使用者に支払い義務があるとした。そこで、Y会社は上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xの請求棄却)。
「労働者が、労働基準法76条に定める休業補償と同一の事由について、労働者災害補償給付12条の8第1項2号、14条所定の休業補償給付を受けるべき場合においては、使用者は、労働基準法84条1項により、同法76条に基づく休業補償義務を免れると解するのが相当である」。
「労働者災害補償保険法の適用事業に使用されている労働者に関しては、同法14条1項に基づき休業補償給付が支給されないこととされている休業の最初の3日間に係わる分を除き、使用者は、およそ、労働基準法76条に基づく休業補償義務を免責されることになる」。
本件については、「Xが労働者災害補償保険法の適用事業に使用されている労働者であり、Xの労働基準法76条1項に基づく休業補償請求の範囲が本件事故を原因とする休業の最初の3日間に係る分を含まないことは明らかであるから、Y会社は、同法84条1項により、同法76条に基づく休業補償義務を免れる」。
解説
使用者は、業務上の負傷や疾病に対しては、所定の災害補償責任を負う(労基法76条以下)が、この災害補償責任は労災保険法に基づく給付が行われるべきときは、免れることができる(同法84条1項)。労災保険法は、労基法上の災害補償責任の責任保険として創設されたものだぁらである。このように、労災保険制度があるため、労基法上の災害補償責任は、実際上は、意味のないものとなっている(ただし、労災保険法上の休業補償給付は、休業の4日目から支給されるので、最初の3日間は、使用者に休業補償義務が生じる)。
本件では、業務災害により休業中であった労働者の、休業補償給付の打切りがなされた後の処遇が問題となっている。症状固定(治癒)になっても、それは完治を意味するものではなく、ただちに復職が認められるわけではないので、本件のように休職期間中であるにもかかわらず、労災保険給付も認められないという事態が生じうる。
そこで、このようなときに労基法上の休業補償が認められるかどうかが問題となるが、本判決は、労基法84条1項は、労災保険の給付を労基法上の災害補償責任とが相互に併存していて両者が調整されるという趣旨のものではなく(同条2項の災害補償責任と民事損害賠償責任については、そのような調整が行われる関係にある)、使用者は、労災保険制度の適用対象者に対しては、保険給付が実際に支給されたかどうかに関係なく、災害補償責任は(最初の3日間の休業補償給付を除き)一切免れるという判断を示した。なお、休業手当におついても、本判決は、平成12年4月15日まで服飾を認めなかったことについては正当な理由があり、その間、使用者にはXの行った事務職として終了申入れを受け入れる義務はなかったとし、Xの休業は使用者の責に帰すべき事由によるものではないとして、その請求を認めなかった(判旨外)。
労基法26条(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
労基法76条1項(休業補償)
第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
労基法84条1項(他の法律との関係)
第84条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
労災保険法12条の8第1項2号
〔業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由〕
第12条の8 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 傷病補償年金
七 介護補償給付
労災保険法14条1項〔休業補償給付〕
第14条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
125 労災保険給付と民事損害賠償との調整(1)-三共自動車事件
最3小判昭和52年10月25日(昭和50年(オ)621号)(民集31巻6号836頁)
要因
民事損害賠償額から、労災保険の将来給付分を控除することが認められるか。
事実
Y会社は、特殊自動車等の分解整備を業とする会社である。Xは、Y会社の整備士として雇用され、本社付設工場において就業しており、本件事故当時は20歳であった。Xは、トラクターショベル車の点検修理作業に従事中に、ワイヤーロープの切断によりバケットが頭上に落下して脳挫傷、頸椎骨折等の重傷を負った。そこでXは、民法717条および715条に基づいてY会社に対して損害賠償を請求した。
1審および原審ともに、Xの損害賠償請求額を一部認容した。原審は、損害額については、労災保険から支給を受けた休業補償給付金と長期傷病補償給付金(現工法では、傷病補償年金)、ならびに厚生年金保険から支給を受けた障害年金を逸失利益から控除するだけでなく、将来において給付される長期傷病補償給付金および障害年金についても現存価値を算出したうえ、逸失利益から控除した。そこで、Xは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xの請求の一部認容。原判決および1審判決を一部変更して損害額を増額)。
Ⅰ「労働者災害補償保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式でおこなうものであって、厚生年金保険法に基づく保険給付と同様、受給権者に対する損害の填補の性質をも有するから、事故が使用者の行為によって、生じた場合において、受給権者に対し、政府が労働者災害補償保険法に基づく保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の規定を類推適用し、また、政府が厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは、衡平の理念に照らし、使用者は、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責に免れると解するのが、相当である」。
Ⅱ「右のように政府が保険給付をしたことによって、受給権者の使用者に対する損害賠償請求権が失われるのは、右保険給付が損害の填補がの性質をも有する以上、政府が現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり、継続して給付されたことがかくていしていても、受給権者は使用者に対し、損害賠償の請求するにあたり、このような将来の給付額を損害賠償請求額から控除することを要しないと解するのが、相当であえう」。
解説
1 労働災害に遭った労働者(死亡事故の場合は、その遺族)は、労災保険の申請をして、保険給付を受給することができるし、同時に、安全配慮義務違反等を理由に、使用者に損害賠償を請求することもできる(民法415条、709条等。→【119】陸上自衛隊八戸車両整備工場事件)。もっとも、労働者が労災保険給付と民事損害賠償ろなるし、また、使用者が強制保険として労災保険に加入していることの利益(保険利益)が損なわれることになる。
そこで、判旨Ⅰは、労基法84条2項を類推適用し、政府が労災保険の給付をしたときは、保険者は、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れるを述べた。
2 労災保険給付が年金給付等の形で行われる場合、将来における保険給付分について、あらかじめ損害賠償額から、控除できるかにちゅいては、学説の立場は、対立してきた。
控除を認めると、労働者は、その将来の保険給付分に相当する損害額については、民事訴訟で一括して補償を受けることができず、労災保険による年金給付(つまり、分割支給)を受け入れることを強制したりすると、結局は、損害の填補がなされないままに終わる可能性がある一方、控除をしなければ、労働者は民事損害賠償と労災保険給付により二重の損害填補を受けてしまう可能性があるし、使用者としても、保険利益がなくなるという問題がでてくる。こうしたなか、本判決は、控除をしないとする非控除説の立場を明らかにした(判旨Ⅱ。すでに、最高裁判所は、第三者行為災害において、同旨の判断をしていた[仁田原・中村事件ー最3小判昭和52年5月27日])。
ただ、非控除説には、前述のような問題があったため、本判決後、昭和55年に法改正がなされ、使用者は、将来の保険給付分のうち、前払い一時金の限度で、損害賠償に支払いが猶予され、その間に、年金給付または、前払い一時金の支給がなされた場合には、その限度で損害賠償責任が免除されることになった(労働保険法64条1項)。前払い一時金の範囲を超える部分については、労働者や遺族が損害賠償を受けたときはには、その価額の限度で保険給付のほうが支給停止される(同条2項)。
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
民法715条(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
労働基準法84条2項(他の法律との関係)
第84条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
② 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
民法415条(債務不履行による損害賠償)
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
労災保険法64条1項・2項〔損害賠償との調整に関する暫定措置〕
第64条 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。
一 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
② 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。
一 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)
126 労災保険給付と民事損害賠償との調整(2)-コック食品事件
最2小判平成8年2月23日(平成6年(オ)992号)(民集50巻2号249頁)
要因
特別支給金を、民事損害賠償の損害額から控除することが認められるか。
事実
給食弁当等の製造販売を行うY会社において、弁当調理補助作業にパートタイマーとして、従事していたXは、Y会社の工場での作業中に、弁当箱洗浄機に右手を巻き込まれて負傷し、入通院して加療を受けた。その後、症状が固定したが、後遺障害が残り、労災保険の障害等級10級に該当すると認定された。
Xは、Y会社に対して、安全配慮義務違反を理由に、入院雑費、休業損害、後遺障害による逸失利益等の賠償を求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、Xの請求を一部認容した。1審および原審ともに、Xの請求を一部認容した。賠償額の算定にあたり、1審・原審はいずれも、Xの労災保険から受給した休業補償給付を傷害補償給付は逸失利益から控除したものの休業特別支給金と障害特別支給金は控除しなかった。そこで、Y会社は、特別支給金についても控除するべきであるとして上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求の一部認容、一部棄却)。
1 労災保険法による保険給付は、使用者の労基法上の災害補償義務を政府が労災保険によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害または通勤災害による労働者の損害を填補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労基法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償めを免れると解されるし、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定も設けられている。
Ⅱ「保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について、損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている」(労災保険法12条の4)
Ⅲ 他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業補償支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給するが、特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活に援護等により、その福祉の増進を図るために行われるものであり、使用者または、第三者の損害賠償義務の履行と特別支給金との関係において、保険給付の場合における前記各規定と同趣旨の定めはない。
Ⅳ「このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである」。
解説
労災保険給付と民事損害賠償とは、「同一の理由」の範囲で調整がなされ(→【125】三共自動車事件)、「同一の事由」とは、保険給付の対象になる損害と民事損害賠償の対象となる損害とが同性質で、保険給付と民事損害賠償が相互補完性を有する関係にあるものとされている(青木鉛鉄事件ー最2小判昭和62年7月10日)。具体的には、労災保険の補償給付とこようような関係にあるのは、財産的損害のうちの消極的損害(逸失利益)だけであるとされ、したがって、たとえば慰謝料は、調整対象とならず全額支給される(同判決)。
では、労災保険から支給されるものの、保険給付としてではなく、社旗復帰促進等事業(労災保険法29条1項2号を参照)は、民事損害賠償との調整対象となるのだろうか。特別支給金が、実質的には保険給付の上乗せとしての意味があるため、保険給付と同じように民事損害賠償と調整可能かが問題となる。
この点について、本判決は、労災保険給付については、民事損害賠償との明文の調整規定(労基法84条2項は類推適用)がある(判旨Ⅰ、Ⅱ)のに対して、特別支給金については、このような調整規定はなく、さらに特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護などにより、その福祉の増進を図るために支給されるものである、保険給付のように損害おwてん補する性質をゆうしていないことから、損害賠償から控除することはできないとした(判旨Ⅲ、Ⅳ。なお、本判決と同旨の判例として、(→【137】改新進社事件)。
しかし、この判例に対しては、特別支給金は本体の保険給付と支給事由も手続も同じであり、保険給付との一体性があることから、特別支給金の支給が社会復帰促進等事業の枠内でおこなわれていることや、明文の調整規定がないという形式的な理由だけで控除をみとめないのは妥当ではないという批判もある。
労基法84条2項(他の法律との関係)
第84条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
② 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
労災保険法12条の4〔第三者の行為による事故〕
第12条の4 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
② 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
労災保険法29条1項2号
第29条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
127 労災保険給付と民事損害賠償との調整(3)-フォーカスシステムズ事件
最大判平成27年3月4日(平成24年(受)1478号)(民集69巻2号178頁)
要因
遺族補償年金と調整対象となるのは、逸失利益の元本部分だけか、遅延損害金を含むのか。遺族補償年金の支給により、損害がてん補されたと評価される時点はいつか。
事実
ソフトウエアの開発等を業とするY会社に雇用されていたAは、長時間の時間外労働や配置転換にともなう業務内容の変化等の業務に起因する心理的負荷の蓄積により、精神障害を発症し、病的な心理状態の下で、さいたま市の自宅を出た後、無断欠勤して京都市に行き、河川敷のベンチでウイスキー等を過度に摂取する行動に及び、翌日、午前10時頃、死亡した。そこで、Aの両親のXらは、Y会社に業務軽減措置などをとらなかった安全配慮義務違反ないし、不法行為法上の注意義務違反があったとして、損害賠償およびこれに対する遅延損害金を請求した。
1審は、Y会社の責任を肯定した(Aの過失は、2割)うえで、Xらに支給されていた労災保険給付(遺族補償年金、葬祭料)との損益相殺については、遅延損害金から充当した。これに対し、原審は、Aの過失を3割としたうえで、損益相殺については、遅延損害金とは行わず、また遺族補償年金は、不法行為の時点で損害が填補されたものとして損益相殺を行うべきとした(東京高判平成24年3月22日)。Xは上告した。
判旨 上告棄却
Ⅰ 被害者が不法行為によって死亡した場合において、 その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、また、支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、遺族補償年金につき、その填補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。
Ⅱ 被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、または支給を受けることが確定したときは、制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り、その填補の対象となる損害は、不法行為の時に填補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当である。
解説
労災保険と損害賠償との調整について、判例は、両者の「同性異質」と「相互補完性」がある範囲でおこなうものとしている(青木建設事件ー最2小判昭和62年7月10日)。労災保険の遺族補償年金は、「労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失をてん補することを目的とするものであって・・・・、その填補の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される」(判旨外)ので、損益相殺の対象となる(判旨Ⅰを参照)。
本件で問題となったのは、この損益相殺が、損害賠償に対する遅延損害金も対象となるのか、さらに労災保険給付によって損害が填補されるのはどの時点と判断して損益相殺すべきなのかである。
前者の点について、従来の判例は、本件と同様の死亡事案において、遺族補償年金は、まず、遅延損害金から充当する(民法491条1項を参照)、という立場であり(最2小判平成16年12月20日)、本件1審もこれに従った。ところが、最高裁は、交通事故により後遺障害が残った事案で、各種労災保険等ろの調整について、これとは異なり、本件の原審と同じ立場を示していた(最1小判平成22年9月13日等)。本判決も、平成22年判決に従った原審を維持し、そのかぎりで平成16年判決の判例変更が行われた。
遺族補償年金の支給確定分が、遅延損害金に充当されないのは、遅延損害金は、あくまで債務者の履行遅滞を理由とする債券であり、遺族補償年金の目的と明らかに異なり、「同性質性」と「相互補完性」がないからとされる(判旨外)。
また、後者の点に関して、不法行為に損害が填補されたとする判旨Ⅱは、遺族補償年金の支給日までの遅延損害金が発生しなくなるという点では、被害者に不利となるが、そもそも不法行為の損害の算定そのものに、将来予測や擬制の下に行わざるをえないところがあること、加えて遺族補償年金は、一定の額が定期的に支給されるものであり、「これは、遺族の被扶養利益の喪失が現実化する都度ないし、現実化するのに対応して、その支給を行うことを制度上予定しているものと解されるのであって、制度の趣旨に沿った支給がされる限り、その支給分については、当該遺族に被扶養利益の喪失が生じなかったとみることが相当である」ことなどを、その判断の根拠としている。
民法491条1項(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
(旧民法)第491条
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
128 労災保険給付と民事損害賠償との調整(4)-高田建設事件
最3小判平成元年4月11日(昭和63年(オ)462号)(民集43巻4号209頁)
要因
民事損害賠償の額について、被災労働者の過失分の減額は、労災保険給付を控除する前に行うべきか、控除した後におこなうべきか。
事実
Xは、普通貨物自動車を運転中に、Y1運転の乗用車と衝突して、負傷した。そこで、Xは、Y1とY1運転の乗用車の所有者であるY2に対して、損害賠償を請求した。Xは、この事故により、治療費、通院費、入院付添費、入院雑費、休業損害、入通院慰謝料、弁護士費用等の損害を被った。他方、自賠責保険から治療費が、労災保険から休業補償給付金が支払われ、また、Y2から150万円のしはらいがなされている。
1審は、損害額全体から労災保険給付を控除した後、Xの過失分7割を減額した額の賠償を認めた。そこで、Xは控訴した。原審は、Xの過失分は6割であるとし、
Xの過失分をまず、減額したところ、休業損害は799万706円、その他の損害は、156万5385円となり、休業損害は、労災保険により、全額補償され、その他の損害も、自賠責保険とY2の支払いによって、全額補償されているという理由で、Xの請求を棄却すべきとした(一部認容した1審判決は相当ではないが、控訴したのがXだけであり、1審判決を不利益に変更することは許されないので、控訴棄却となった)。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却。
Ⅰ「労働者災害補償保険法(以下「法」という。)に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により、被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつき、これを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額から、過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である」。
Ⅱ 「法12条の4は、・・・・受給権者に対する第三者の損害賠償義務とが相互補完の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしているのであって、政府が保険給付をしたときは、右保険給付の原因となった事件と同一の事由については、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、右給付の価額の限度において、国に移転する結果減縮すると解されるところ・・・・、損害賠償額を定めるにつき、労働者の過失を斟酌すべき場合には、受給権者は第三者に対し、右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので、同条1項により国に移転するとされる損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味すると解するのが、文理上自然であり、右規程の趣旨にそうものといえる」。
解説
労災事件における民事損害賠償において、労働者側にも過失がある場合には、過失相殺が行われて、損害賠償額の減額が行われる(民法722条2項、418条)。労災給付の支給があった場合、その額は、損害賠償額から控除される(→【125】三共自動車事件)が、過失相殺による減額は、労災保険給付の控除の前に行うべきか、後に行うべきかについては議論がある。
前者の控除前葬祭説によると、労災保険給付の支給分は、使用者の過失相殺分に充当されることになるが。本判決は、この立場である(判旨Ⅰ)。労災保険給付は、使用者の損害陪h層責任に対する保険であるということを考慮に入れると、この立場が、労災保険制度の趣旨に合致するといえるであろう(ただし、判旨Ⅱにおける理由付けは、第三者行為災害に関する労災保険法12条の4の文理解釈を決め手としており、これが十分に説得的なものといえるかには疑問も残る[後述の伊藤正巳裁判官の少数意見も同旨]。なお、控除前相殺説は、使用者行為災害の場合にも妥当するものであり、先例がある[大石塗装・鹿島建設事件ー最1小判昭和55年12月18日])。
他方、控除後相殺説によると、労災保険給付は、使用者過失分と労働者過失分の按分され、それぞれが労使双方の負担すべき損害分に充当されていくこととなる。使用者にとっては、損害損害賠償額から控除される割合が減ることになり、労働者にとっては、有利な考え方となる。本件の第1審判決は、この立場であり、本判決の伊藤正巳裁判官の少数意見も同じである。
伊藤裁判は、控除後相殺説をとる理由として、「労災保険制度が社会保障的性格を有し、できるだけ労働者の損害を保障しようとしていることは、法・・・・の解釈にも反映させてしかるべきである」と述べる。
労災保険給付があったからといって、賠償額が増えるのはおかしいという批判に対しては、「労災保険が純然たる責任保険と異なることは前記のとおりであるから、労災保険が給付される場合とこれが給付されない場合とで、受給権者の受領することのできる金額に差が生ずるのは当然のことである」と反論している。
労災保険法12条の4〔第三者の行為による事故〕
第12条の4 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
② 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
民法722条2項(損害賠償の方法及び過失相殺)
第722条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法418条(過失相殺)
第418条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
129 第三者行為災害と示談-小野運送事件
最3小判昭和38年6月4日(昭和37年(オ)711号)(民集17巻5号716頁)
要因
第三者行為災害について、加害者と被害者との間で、示談が成立した場合、それは、労災保険給付の支給額に影響するか。
事実
Y会社の従業員であったAは、Y会社の自動車を運転中に、B会社の従業員であるCと接触し、Cに骨折等の傷害を与えた、これにより、Cは、Aの使用者であるY会社に対し、約46万円の損害賠償請求権を得ることになった(民法715条)。
その後、Y会社とCの間で示談が成立した。その内容は、自動車損害賠償責任保険に基づく給付金10万円と慰謝料・治療費2万円をY会社から受け取り、その他の損害賠償請求権をいっさい放棄するというものであった。
X(国)は、Cからの労災保険給付の申請の際、この示談の事を聞き、Cに対し、労災保険法に基づき給付される保険給付金約42万円のうち、12万円を差し引いた約30万円をしはらった。
Xは、労災保険法12条の4に基づき、この給付金をY会社に対し求償した。Y会社は、Cが示談によって損害賠償請求を放棄した以上、XがCに対し、補償給付をしたとしても、XがCに代位して請求できる金銭債権はないとして、その支払いを拒否した。
1審は、Xの請求を認容した。Y会社が控訴したところ、原審は、1審判決を取り消し、Y会社の主張を認めた(XのCへの不当利得返還請求の可能性は示唆している)。そこで、Xは上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求棄却)。
Ⅰ 「労働者が第三者の行為により損害を被った場合には、その第三者に対して、取得する損害賠償請求権は、通常の不法行為上の債権であり、その災害につき労働者災害補償保険法による保険が付せられているからといって、その性質を異にするものとは解されない。しかたがって、他に別段の規定がないかぎり、被災労働者らは、私法自治の原則上、第三者が自己に対し、負担する損害賠償債務の全部又は一部を免除する自由を有する。
Ⅱ 労災保険法20条(現在の12条の4)1項は、政府は、補償の原因である事故が、第三者の行為によって生じた場合に、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する旨を規定するとともに、同条2項は、前項の場合において、補償をうけるべきものが、当該第三者より同一の申出につき損害賠償をうけたときは、政府は、その価額の限度で災害補償の義務を免れる旨を規定している。
この2項は、単に、被災労働者から第三者から現実に損害賠償を受けた場合には、政府もまた、その限度において、保険給付をする義務を免れる旨を規定しているだけであるが、労災保険制度は、もともと、被災労働者らの被った損害を補償することを目的とするものであるから、被災労働者が、第三者の自己に対する損害賠償請求債務の全部または一部を免除し、その限度はにおいて損害賠償請求権を喪失した場合、政府は、その限度において、保険給付をする義務を免れる。
解説
第三者行為災害とは、政府、事業主、被災労働者以外の第三者の行為により、業務上の災害に遭遭う場合をいう。この場合にも、労災保険給付はなされるが、政府は、労災保険給付をした場合には、被災労働者が加害者である第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得し、その第三社に対して法定代位権を行使することができる‘搭載保険法12条の4)
本件で問題となったのは、被災労働者が、加害者との間で示談をした場合、労災保険の給付額に影響するかである。労災保険法の条文上は、被災労働者が第三者から損害賠償を受けた場合、には、政府はその価額の限度で保険給付を免れるが、示談のように被災労働者が加害者の債務の免除をした場合にも、同様に解してよいのかが問題となるのである。
まず、そもそも、こうした債務免除が許されるのかどうかが問題となりえるが、判旨Ⅰは、労災保険の対象となる損害賠償債権であっても、普通の不法行為債権とかわりはないのであり、私的自治の原則に基づき、被災労働者には、免除をする自由があるとする。
次に、この場合、政府の行う労災保険給付も縮減するかであるが、判旨Ⅱはこれも肯定する。その理由は、労災保険制度は、被災労働者らの被った損害を補償することを目的とするものであり、被災労働者が、加害者の損害賠償請求権は喪失するので、政府はその限度おいて、保険給付えおする義務を免れるという店にある(そのため、政府は、被害者が免除した分については、加害者に法定代位権を行使することはできない)。
このような結論は、被災労働者が不用意な示談や真意に沿わない示談をしたっ場合に酷な結果が生じたおそれもあるが、この点については、本判決は、
①労災保険制度に対する労働者の認識を深めること、
②保険給付が迅速におこなわれること、
③損害賠償債務の免除が被災労働者らの真意に出たものかどうかに関する認定を厳格におこなうこと(錯誤または詐欺等も問題とされるべきである)
によって、防止しうると述べている(判旨外)。
民法715条(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
労災保険法12条の4〔第三者の行為による事故〕
第12条の4 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
② 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
130 通勤災害-羽曳野労基署事件
大阪高判平成19年4月18日(平成18年(行コ)46号)
要因
介護目的での通勤経路からの逸脱後の災害は、通勤災害に該当するか。
事実
Xは、平成13年2月26日、勤務終了後、両足が不自由な義父Aの介護のために、A宅に寄り、約1時間40分程度、Aの身の回りの世話をした後、A宅を出た。Xは、帰宅途中、原付バイクと接触し、頭蓋骨折、脳挫傷等のけがを負った。A宅は、Xの通勤経路から外れていたが、本件事故は、A宅から帰る途中、コンビニエンスストアに寄った後、通常の通勤経路(復路)に入る直前の交差点(道路幅3.9メートル)を横断しているところ(復路まで0.9メートルの地点)で遭ったものであった。
Xは、通勤災害であるとして労災保険法に基づき、Y労基署長に対して、休業給付の申請をしたが、Yは不支給処分を行った。そこで、Xは、Yの不支給処分の取消しを求め、訴えを提起した。1審は、Xの請求を認容したため、Yは控訴した。
判旨 控訴棄却(Xの請求認容)。
Ⅰ Aは当時85歳の高齢であり、両下肢機能全廃のため、食事の世話、入浴の介助、簡易トイレにおける排泄物の処理といった日常生活全般について、介護が不可欠な状態であった。X夫婦は、A宅の近隣に居住しており、独身で帰宅の遅い義兄と同居しているAの介護を行うことができる親族は他にいなかったので、Xは週4日間程度、これらの介護を行い、Xの妻もほぼ毎日、父Aのために食事の世話やリハビリの送迎をしてきた。
このような事情の下では、XのAに対する介護は、「労働者本人又はその家族の衣、食、保健、衛生など、家庭生活を営むうえでの必要な行為」というべきであるから、労災保険法施行規則8条1号所定の「日用品の購入、その他これに準ずる行為」にあたる。
Ⅱ「合理的な経路とは、事業場と自宅との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路をいい、必ずしも、最短距離の唯一の経路を指すものでないから、この合理的な経路も。1人の労働者にととって、1つとは限らず、そのうちどれを労働者が選択しようが地涌であると解されている。また、徒歩で通勤する場合に、この合理的な経路である限り、労働者が道路のいずれの側を通行するかは、問わないと解するのが相当である。
解説
通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」である(労災保険法7条1項2号を参照)。通勤災害に対しても、業務災害とほぼ同じ保険給付が行われる。ここでいう「通勤」とは、労働者が、就業に関し、合理的な経路と方法により、
①住居と就業の場所との間の往復、
②就業の場所から他の就業の場所への移動(たとえば、兼業先への移動)、
③①に掲げる往復に先行し、または、後続する住居間の移動(たとえば、単身赴任の労働者が週末に帰省先と往復すること)を行うことをいう(7条2項)。
就業に関しない移動は、ここでの「通勤」には含まれない。勤務時間後の任意参加の会合への参加は、業務性があれば「就業」に含まれる(否定例として、中央労基署長事件ー東京高判平成20年6月25日等)。
①から③の経路を逸脱し、または、移動を中断した場合、その逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」には含まれない(7条3項)。ただし、この逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむ得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除き、「通勤」として取り扱われる(同項、ただし書き)。
ここでいう「厚生労働省令で定めるもの」とは、労働保険法施行規則8条に規定があり、日用品の購入、職業能力開発のための受講、選挙権の行使、病院での診療があげられている。
本件は、義父の介護のために義父宅に立ち寄った後に災害に遭ったケースである。これが通勤災害と認められるためには、事故が起きた場所が、合理的な経路の範囲内であるか、また、そうであるとしても、合理的な経路からいったん逸脱した理由が、労災保険法7条3項ただし書の要件を充たすかが問題となる。
本判決は、まず後者の点について、介護は労災保険法施行規則8条には列挙されていないものの、同条1号の「日用品の購入そのたこれに準ずる行為」に該当するという解釈を示した(判旨Ⅰ)。文言上は、かなり無理な解釈であるが、その後、同条に新たに5号が設けられ、家族の介護という理由が追加されたため、立法的に解決された。
本判決は、合理的な経路について、かなり緩やかな解釈を行っている(判旨Ⅱ)。一方、同種の事例について厳格な解釈をした裁判例(札幌中央労基署長事件ー札幌高判平成元年5月8日)もある。
労災保険法施行規則8条1号
第八条 法第七条第三項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
労災保険法7条1項2号〔保険給付の種類等〕
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
三 二次健康診断等給付
労災保険法7条2項
② 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
労災保険法7条3項
③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
131 間接差別-三陽物産事件
東京地判平成6年6月16日(平成3年(ワ)5511号・平成4年(ワ)14509号)
要因
勤務地限定勤務の女性従業員の賃金を勤務地非限定勤務の男性従業員よりも低くすることが、女性であることを理由とする賃金差別に該当するか。
事実
Y会社は、年功的要素を加味した職能資格を基準とした賃金制度を導入していたが、その給与規定には、非世帯主および独身の世帯主には、所定の本人給を支払わないという条項があった(世帯主基準)。Y会社では、男性従業員は、実年齢に応じた本人給と一時金が支払われたが、女性社員の多くは、世帯主基準ンの適応により、25歳の年齢を想定した賃金設定で本人給が据え置かれることになった。
Y会社は、労働基準監督署から、世帯主基準の運用に際して、男女同一賃金に違反する疑いがないように措置すべきとの指導を受けたため、給与規定に勤務地域基準を導入した。この基準は、本人の意思で勤務地域を限定して勤務している従業員に対して、26歳相当の本人給で据え置くというものであった。
Xらは、世帯主基準および勤務地域基準の適用によって本人給に差をつけることは、労基法4条違反であるとし、債務不履行ないし、不法行為を理由として、実年齢に対応した本人給および一時金と既払いの賃金との差額ならびに慰謝料の支払い等を求めて訴えを提起した。
判旨 一部認容。
Ⅰ Y会社は、住民票上、女性の大多数が非世帯主または独身の世帯主に該当するという社会的現実およびY会社の従業員構成を意識しながら、世帯主基準の適用の結果、生じる効果が女性従業員に一方的に著しい不利益になることを容認して上記基準を制定したものに据え置かれる女性従業員に対し、女性であることを理由に賃金を差別したものというべきである。本件、世帯主基準は、労基法4条の男女同一賃金の原則に反し、無効である。
Ⅱ 一般論として、広域配置転換の存否により、賃金に差異を設けることは、それなりの合理性が認められるから、本件において、勤務地域基準の制定および運用が男女差別といえるものでないかぎり、何ら違法とすべき理由はない。
しかし、Y会社は、女性従業員は、すべて営業職に従事しておらず、過去現在とも広域配転を経験したじょとがないこと、そして、女性従業員が一般に広域配転を希望しないことを認識していた。Y会社は、労働基準監督署の指導を受け、給与規定の取扱いを正当化するため、勤務地域基準の適用の結果、生じる効果が、女性従業員に一方的に著しい不利益となることを容認しつつ、この基準を新たに制定したものとすいにんされるのである。この基準は、女性であることを理由に賃金を差別したものであるというべきであり、労基法4条の男女同一賃金の原則に反し、無効である。
解説
労働基準法4条は、女性であることを理由とする賃金差別を禁止している(→【184】兼松事件「解説」)。
本件では、直接的には、女性に対する不利益な本人給が定められているわけではない。当初は、世帯主基準、その後は、勤務地域基準を用いた結果、賃金に格差が生じたにすぎないともいえる。労基法は3条に定める事由(国籍、信条又は社会的身分)と4条の場合以外の事由による賃金格差を禁止してはいない(その他の法律では、短時間労働者法9条、労組法7条1号などがある)ため、本件のような格差は当然には違法とはいえない。
ただ、本件では、世帯主基準については、女性従業員の大多数が、非世帯主であることと認識し、女性従業員に一方的に著しい不利益となることを容認して設けられたものであるとして、労基法4条違反としている(判旨Ⅰ。」なお、家族手当を世帯主に支給するという条項を有効とした裁判例として、日産自動車事件ー東京地判平成元年1月26日)、無効とした裁判例として、岩手銀行事件ー仙台高判平成4年1月10日)。
さらに、勤務地域基準については、一般的にはその合理性は認められるものの、本件では、従来の格差を正当化するために、この基準が女性従業員に一方的に著しい利益となることを容認しつつ制定されたものであるとして、やはり労基法4条違反となるとしている(判旨Ⅱ)
本件は、中立的な基準を用いながら、その結果として、実質的に差別をもたらすという間接差別の事例のようにもみえる、間接差別が、明文の規定なしに、禁止される差別に含まれるかどうかについては解釈上の争いがありうるところである。ただ、本件では、使用者が用いた基準は、まったく形だけのものであって、男女の格差を容認しており、実質的には、直接的な女性差別があったとみるべき事案であろう。なお、男女雇用機会均等法の平成19年改正により、募集・採用・昇進における一定の措置について、性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男女比率の事情を換算して実質的に性別を理由とするさべつになるおそれがあるもので、合理的理由のないものは間接差別として禁止されることになった(7条)。間接差別の成立範囲は限定されている(同法施行規則2条)。
労基法4条 (男女同一賃金の原則)
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労基法3条 (均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
短時間労働者法9条(通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止)
第9条 事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。
労組法7条1号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
男女雇用機会均等法7条(性別以外の事由を要件とする措置)
第7条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
男女雇用機会均等法施行規則2条
第二条 法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの
三 労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの
132 セクシャル・ハラスメント-福岡セクシャル・ハラスメント事件
福岡地判平成4年4月16日(平成元年(ワ)1872号)
要因
同僚従業員のセクシャル・ハラスメントについて、使用者は損害賠償責任を負うか。
事実
Xは、情報誌の編集発行等を行うY1会社の女性従業員であり、Y2は、同社の発行雑誌の編集長であった。Xは、過去に雑誌等の経験があったため、入社後すぐに、Y1会社の発行する雑誌の編集を、Y2に代わって担当するようになり、その後も、記事の執筆等を含めた社内の重要な業務を担当するようになった。そして、Y2が病気で入院した後は、Y2の補充として出向してきたA係長とXが、Y1会社の業務方針を決定するようになった。そのため、Y2は、業務に復帰後、社内の重要業務にかかわれないという疎外感をもち、Xに対してライバル心を抱くようになった。
このようななか、Y2は、Y1会社の従業員や社外の関係者らに対し、Xの異性関係が乱れている等の発言を繰り返し、また、Aに代わって入社したB専務に対して、取引先からの依頼が途絶えたのは、取引先の支店長とXの不倫関係が終了したことが原因であると、事実関係を十分に確認することなく、報告するなどした。
Y2とXの確執によって、職場環境に悪影響が生じ始めたため、B専務は、XとY2に対して、話し合いにより問題を解決するように指示したが、両者の関係は修復しなかった。そこで、B専務は、まずXに、関係が修復できなければ退職してもらうと述べたところ、Xは、退職の意思を示した。他方、Y2は、3日間の自宅謹慎と賞与の減額処分を受けた。
Xは、Y2に対して、民法709条に基づき、Y1会社に対して、民法715条に基づき、損害賠償の支払いを求めて訴えを提起した。
判旨 一部認容、一部棄却(慰謝料は150万円)
Ⅰ「Y2が、Y1会社の職場又はY1会社の社外ではあるが、職場に関連する場において、X又は職場の関係者に対し、Xの個人的な性生活や性向を窺わせる事項について発言を行い、その結果、Xを職場に居づらくさせる状況を作り出し、しかも、右状況の出現について意図していたか、又は、少なくともよけんしていた場合には、それは、Xの人格を損なっておsの感情を害し、Xにとって働きやすい職場環境のなかで働く利益を害するものであるから、Y2はXに対して民法709条の不法行為責任を負う」。
Ⅱ「使用者は、被用者との関係において、社会通念上伴う義務として、被用者が労務に服する過程で生命及び健康を害しないよう職場環境等につき、配慮すべき注意義務を負うが、そのほかにも、労務遂行に関連して被用者の人格的尊厳を侵し、その労務提供に重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ、又は、これに適切に対処して、職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務もあるとかいされるところ、被用者を選任監督する立場にある者に被用者に対する不法行為が成立することがあり、使用者も民法715条により、不法行為責任を負うことがあると解するべきである」。
解説
セクシャル・ハラスメントについては、事業主に対して、雇用管理上必要な措置を講じる義務が課されている(男女雇用機会均等法11条。詳細は、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」「平成18年度厚生労働省告示615号。その後改正あり]を参照)。そこで、あげられている職場のセクシャル・ハラスメントには、対価型(性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき、不利益を受けること)と環境型(性的な言動により、当該労働者の職場環境が害されること)とがある(女性から男性に対するものや同性間のものも含まれる)。本件は、環境型のケースである。
セクシャル・ハラスメントは、加害者だけでなく、その使用者に対しても損害賠償責任が認められる可能性がある。本判決では、加害者であるY2の行為は、Xにとって働きやすい職場環境で働く利益を害するとして不法行為であるとする(民法709条)(判旨Ⅰ)。さらに、使用者にも、「職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務」があり、被用者を船員監督する立場にある者がこの義務に違反した場合には、不法行為が成立し損害賠償責任(民法715条)を負うことがあるとし、(判旨Ⅱ)、本件では、B専務らが、職場環境を調整するよう配慮する義務を怠っていたことから、Y1会社は使用者責任を負うと判断している(判旨外)。
本件では、不法行為責任が問われているが、その後の裁判例には、労働契約上の付随義務として、使用者には、労働契約上の付随義務として、使用者には、「労務の提供に関して、良好な職場環境の維持確保に配慮すべき義務」があると述べ、セクシャル・ハラスメントに対して適切な対処をしないことについて、この義務に違反すると認めたものがある(仙台セクシャル・ハラスメント(自動車販売会社)事件ー仙台地判平成13年3月26日)。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法715条(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
男女雇用機会均等法11条
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
133 産前産後の休業と賞与の出勤要件-東朋学園事件
最1小判平成15年12月4日(平成13年(受)1066号)
要因
法律によって保障されている休業期間は、賞与の支給要件との関係で欠勤扱いにしてよいか。
事実
学校法人Y学園において、期間の定めのない労働契約に基づき事務職として働くXは、平成6年7月8日に出産し、翌9日から同年9月2日までの8週間、産後休業を取得した。その後、Xは、Y学園の育児休業規定に基づいて勤務時間の短縮を請求し、同年10月6日から翌年7月8日までの間、1日につき1時間15分の勤務時間短縮措置を受けた。
Xは、平成6年度の夏期賞与および期末賞与について、賞与の支給に関する回覧文書に基づき、産前産後の休業期間が欠勤と扱われたため、給与規定(就業規則)において賞与の支給について、90%以上の出勤を要件とする条項(本件90%条項)に基づき、支給がなされなかった。また、平成7年度の夏期給与についても、勤務時間短縮措置に基づく短縮時間分が欠勤日数に加算されて90%の出勤率要件を満たさないことから、支給されなかった。回覧文書は、給与規定に基づき作成されたもので、そこには、賞与の算定方法として欠勤日数に応じた減額が定められていると同時に、欠勤日数の算定方法についても定められていた。
Xは、産後休業の日数や勤務時間短縮措置による短縮時間短縮措置による短縮時間分を欠勤に算入することは、労基法や育児介護休業法の趣旨に反し、違法であるとして、賞与の支給を求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求を認め、原審も1審の判断を支持した。そこで、Y学園は上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し
Ⅰ「産前産後休業を取得し、または、勤務時間の短縮措置を受けた労働者は、その間、就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねてられているというべきである」。
Ⅱ 従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないいこととするのは、一応の経済的合理性を有するものである。本件90%条項は、産前産後休業(労基法65条)や育児休業法10条(現在の育児会議休業法23条)を受けて定められた勤務時間の短縮措置を請求しうる法的利益に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、これらの法規定の趣旨に照らすと、これにより、上記権利等の行使を抑制し、ひいては労基法等が権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合にかぎり、公序に反するものとして無効となる。
本件90%条項は、これらの権利等の行使に対する事実上の抑止力は相当強いとみるもが相当である。そううすると、本件90%条項のうち、出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し、出勤した日数に産前産後休業の日数および勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないとものとしている部分は、公平に反し、無効であるというべきである。
Ⅲ 賞与の計算式の適用にあたっては、産前産後休業の日数および勤務時間短縮措置による短縮時間分は、回覧文書の定めるところに従って欠勤として減額の対象となっているというべきである。
解説
賞与の支給要件に、一定の出勤要件を科すことは、基本的には、使用者の自由にまかされている。ただ、本判決は、労基法等の法律上の休暇・休業の権利を行使した場合に、それを欠勤扱いとすることは、法律が権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合には、公序違反でむこうとなる(民法90条)と判断している(判旨Ⅱ)。このような考え方は、判例上すでに確立していたものである(エヌ・ピー・シー工業事件ー最3小判昭和60年7月16日、日本シェーリング事件ー最1小判平成元年12月14日、→【113】沼津交通事件)。なお、現在では、産前、産後休業(労基法65条)の取得や育児・介護休業の取得、3歳未満の子を養育中の労働者による所定労働時間の短縮請求等を理由とする解雇その他不利益取扱いを明文で禁止する規定がある(男女雇用機会均等法9条3項、育児介護休業10条、16条、23条の2)。
本判決は、産前産後の休業等は、賞与の支給要件としての出勤率には影響させてはならないが、賞与の算定額には影響させてよい(欠勤日数分だけ控除してよい)と判断した(判旨Ⅲ)。原判決は、これら休業を欠勤扱いすることをも違法としていた。しかし、休業期間や欠勤期間を無給とする合意は可能であり(判旨Ⅰ参照。ノーワーク・ノーペイの原則)、本判決は、この考え方を賞与の算定の場合にもあてはめたものである。
労基法65条 (産前産後)
第65条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
育児休業法10条(現在の育児介護休業法23条)(不利益取扱いの禁止)
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
民法90条(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
男女雇用機会均等法9条3項 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならな
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
育児介護休業法10条 (不利益取扱いの禁止)
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児介護休業法16条(準用)
第16条 第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。
育児介護休業法23条の2
第23条の2 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
134 妊娠中の軽易業務への転換と不利益取扱い-広島中央保健生活協同組事件
最1小判平成26年10月23日(平成24年(受)2231号)(民集68巻1270頁)
要因
妊娠中の女性の請求による軽易業務への転換にともなう降格が、男女雇用機会均等法9条3項の禁止する不利益取扱いに該当するか。
事実
消費生活協同組合Yの組織するA病院に理学療法士として勤務するXは、労基法65条3項に基づいて軽易作業への転換を請求した。この異動により、これまでの副主任の役職を免ぜられた(本件措置1)。その後、Xは、産前休業および産後休業を取得し、引き続き育児休業を取得した。休業あけの職場復帰後のポストでは、すでに別の副主任がいただめ、Xは副主任に任ぜられなかった(本件措置2)。
Xは、本件措置1は、男女雇用機会均等法9条3項に違反する無効なものであり、また、本件措置2は、育児介護休業法10条に違反する無効なものであると主張し、副主任手当の支払い、および、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を求めて訴えを提起した。1審も原審も、Xの請求を認めなかった。そこで、Xは上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し。
Ⅰ 女性労働者を妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させることは、原則として、男女雇用機会均等法9条3項の禁止する取扱いにあたるものと解されるが、「当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は、事業主において、当該労働者につき降格の措置を執ることなく、軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から、支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度に照らして、上記措置につき、同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である。
Ⅱ「上記の承諾に係る合理的な理由に関しては、上記の有利又は不利な影響の内容や程度の評価に当たって、上記措置の前後における職務内容の実質、業務上の負担の内容や提訴、労働条件の内容等を勘案し、当該労働者が上記措置による影響につき、事業主から適切な説明を受けて十分に理解した上で、その諾否を決定し得たか否かという観点から、その存否を判断しべきものと解される。また、上記特段の事情に関しては、上記の業務上の必要性の有無及びその内容や程度の評価に当たって、当該労働者の転換後の業務の性質や内容、転換後の職場の組織や業務態勢及び人員配置の状況、当該労働者の知識や経験の等を勘案するとともに、上記の有利な影響の内容や程度の評価にあたって、上記措置に係る経緯や当該労働者の意向等を勘案して、その存否を判断すべきものと解される。
解説
男女雇用機会均等法は、女性労働者の妊娠、出産、労基法65条による産前休業と産後休業の取得などを理由とした不利益な取扱いを禁止している(9条3項)。この禁止には、妊娠中の軽易業務への転換に対する不利益取扱いも含まれる(男女雇用機会等均等法施行規則2条の2第6号)。
不利益取扱いのうち解雇は、妊娠中か出産後1年を経過しないでなされると、それが禁止されている理由によるものでないことを事業主が証明しない限り、無効となる(男女雇用機会等均等法9条4項)。降格については、こうした規定はないものの、本判決は、男女雇用機会等9条3項を強行規定と解し(判旨外)、軽易業務への転換請求を契機としてなされた降格は、原則として、同項に違反するとしたうえで、例外として、自由な意思による承諾がある場合と、降格させないと業務上の支障があるなどの特段の事情がある場合をあげた(判旨Ⅰ)。前者は、強行規定違反の例外として、自由意思による同意がある場合を認めた判例を念頭に置いたものであろう(→【92】日新製鋼事件)。そこでは、適切な説明を受けて十分に理解した上での承諾であるかに着目している点が注目される。
本件は、妊娠を理由とした降格ではなく、軽易業務への転換を契機とした降格である。役職や職位の降格についいぇは、使用者の広い裁量が認められているものの(→【44】東京都自動車整備振興会事件)、本判決は、妊娠中の女性に対しては、その裁量は厳しく制限されると判断したことになる。
なお、平成28年の男女雇用機会均等法の改正により、マタニティ・ハラスメントに対する使用者の雇用管理上必要な措置を講じる義務が追加されている(11条の2)
労基法65条3項 (産前産後)
第65条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
男女雇用機会等均等法9条3項(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第9条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
育児介護休業法10条(不利益取扱いの禁止)
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
男女雇用機会均等法施行規則2条の2第6号
第二条の二 法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
六 労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
男女雇用機会等均等法11条の2(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条の2 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
135 育児休業の取得と不利益取扱い-医療法人稲門会[いわくら]事件
大阪高判平成26年7月18日(平成25年(ネ)3095号)
要因
3か月以上の育児休業を取得した労働者に翌年度の昇給を行わなかったことが、育児介護休業法10条に反するか。
事実
Xは、平成10年4月、医療法人Yに採用され、平成15年4月からY法人のA病院で看護師として勤務してきた(平成25年1月末に退職)。Y法人の就業規則によると、A病院で勤務する者の基本給は、保人給、職務給、および、経験年数と能力により定まる職能給で構成されている。Y法人の育児介護休業規定には、育児休業中は本人給のもの昇給とする旨の規定があった。Y法人は、この規定は、従来からの運用を確認したものであり、育児休業として3か月以上の欠勤があった者は、他の私傷病と同様、職能給の昇給を行わない趣旨のものと解していた(労働組合も同様の認識さあった)。また、Y法人の賃金制度と密接に関係している人材育成評価制度のマニュアルでは、育児休業などにより、評価期間中における勤務期間中における勤務期間が3か月に満たない場合は、評価不能として取り扱う旨の定めがあった。
Xは、平成22年9月4日から、同年12月3日まで育児休暇を取得したところ、Y法人は、Xの3か月間の不就労を理由として、平成23年度の職能給を昇給させなかった。また、Xは平成23年度の終了により、同24年度の昇格試験の受験資格が認められていたはずが、経性22年度が受験資格に必要な標準年数に算入されなかったために、受験資格が認められなかった。Xは、これらの取扱いが、育児介護休業法10条に定める不利益取扱いに該当し、公序良俗(民法90条)に反する違法行為すぁると主張して、Y法人に対し、不法行為に基づき、昇給、昇格していた場合の給与等の支払いを求めて訴えを提起した。
1審は、職能給の不昇給を公序良俗違反ではないとしたが、受験機会の不給付は、不法行為に該当するとした(京都地判平成25年9月24日)。そこで、Xは控訴した。
判旨 原審の一部取消し(Xの請求を認容)。
Ⅰ 育児介護休業法10条の禁止する不利益な取扱いは、同法が労働者に保障した同法上の育児休業取得の権利を抑制し、ひいては同法が労働者に前記権利を保障した趣旨を実質的に失わせる場合は、公序に反し、不法行為法上も違法になるものと解するのが相当である。
Ⅱ 本件不昇給規定は、1年の4分の1にすぎない3か月の育児休業により、他の9か月は、その就労状況いかんにかかわらず職能給昇給の審査対象から除外し、休業期間中の不就労の限度を超えて育児休業者に職能給を昇給させないという不利益を課すものであり、育児休業を私傷病以外の他の欠勤、休暇、休業の取扱い(不就労日に含めない取扱い)よりも合理的理由なく不利益に取り扱うものである。
このような取扱いは、Y法人の人事評価制度の在り方に照らしても合理性を欠くし、育児休業を取得する者に無視できない経済的不利益を与えるものであって、育児休業の取得を抑制する働きをするものであるから、育児介護休業法10条に禁止する不利益取扱いに当たり、かつ、同法が労働者に保障した育児休業取得の権利を抑制し、ひいては同法が労働者に保障した趣旨を実質的に失わせるものであるといわざるを得ず、公序に反し、無効である。したがって、平成23年度にXを昇給させなかったY法人の行為は、不法行為法上違法というべきである。
解説
育児介護休業法10条は、育児休業の申請や取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止する規定である(介護休業等にも同様の規定がある)。この規定に違反した措置の私法上の効力は、明確ではないが、本判決は、同条に該当することを理由にただちに無効とするのではなく、同法などで権利を保障した趣旨を実質的に失わせる効果をもつ場合には、公序良俗違反とする判例(→【133】東朋学園事件等)を適用し、不法行為上の違法性を判断を行った(判旨Ⅰ)。
ただ、同条と同種の規定である男女雇用機会等均等法9条3項は、強行規定とされていること(→【134】広島中央保健生活協同組合事件)からすると、育児介護休業法10条も強行規定と解するのが自然である(同最高裁判決の櫻井瀧子裁判官の補足意見も参照)。この判例と整合的に判旨Ⅰを解すならば、同条の「不利益な取扱い」に該当するかの判断において、「不利益な取扱い」に該当するかの判断において、「権利を保障した趣旨を実質的に失わせる」かどうかという基準が適用されると解すべきことになろう(育児短時間勤務が適用されたことを理由とする昇給抑制措置を同法23条の2に反して無効とし、損害賠償請求を認めた裁判例として、社会福祉法人全国重症心身障碍児(者)を守る会事件ー東京地判平成27年10月2日)。
なお、平成28年の育児介護休業法の改正により、育児休業や介護休業等の取得等に対するハラスメントに対する使用者の雇用管理上必要な措置を講じる義務が追加されている(25条)
育児介護休業法10条(不利益取扱いの禁止)
第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児介護休業法23条の2
第23条の2 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
育児介護休業法25条
(職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第25条 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
民法90条(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
136 国際労働契約における準拠法の選択-ルフトハンザ事件
東京地判平成9年10月1日(平成5年(ワ)12180号・19557号)
要因
外国法人で働く日本人労働者に対しては、どの国の法律が適用されるか。
事実
Xら3人(日本人)は、ドイツに本店を置く航空会社Yに雇用され、エアホステスとして勤務していた。Y会社では、基本給のほかに、インフレ手当の意味をもつ付加手当に関しては、書面において、「Y会社は付加手当を撤回または削除する権利を留保する」という本件留保条項が挿入されていた。
Y会社は、Xらの給与所得に対する課税所得の変更により、Xらの給与の手取額が増加することとなったため、付加手当を支給する理由が失われたとして、本件留保条項に基づき付加手当を撤回することとした。
Xらの月例給与総額に占める付加手当の割合は、約10ないし13%であった。Xらは、付加手当の撤回は無効であるとして、その支払いを求めて訴えを提起した。
判旨 請求棄却。
Ⅰ「雇用契約の準拠法については、法例7条の規定に従いこれを定めるべきであるが、当事者間に明示の合意がない場合においても、当事者自治の原則を定めた同条1項に則り、契約の内容等具体的事情を総合的に考慮して当事者の黙示の意思を推定すべきである」。
Ⅱ 本件各雇用契約においては、Y会社とXらとの間で、Xらの権利義務についてはY会社の乗務員に関する労働協約によると合意されていること、この労働協約により、XらY会社の乗務員の基本的な労働条件全般が定められていること、この労働協約ドイツ労働法に独特の規定に基づいていること、この労働協約の適用を受ける労働条件の交渉は、本社の従業員代表を通じてなされていること、付加手当等の労働協約の適用を受けない個別的な労働条件についても、Xらは本社(在ドイツ)の客室乗務員人事部と交渉してきたこと、Xらに対する具体的労務管理と指揮命令は客室乗務員人事部が行っていたこと、Xらの給与は雇用契約上ドイツマルクで合意され、Y会社の給与算定部(在ドイツ)でドイツマルクにより、ドイツの社会保険制度や税制に則して算定され、その後、東京営業所において、国外所得として税務処理などをした後にXらに日本円で、送金されていつこと、Xらに対する募集および面接試験は日本で行われたが、本社の客室乗務員人事部が東京ベースのエアホステスの募集を決定し、同人事部の担当者が来日して、面接試験を行い、採用決定をしたものであること、X2およびX3はドイツにおいて雇用契約書に署名しているが、署名した雇用契約書は東京営業所を通じて、本社の客室乗務員人事部に返送しており、Xらの雇用契約はいずれもY会社の本社の担当者との間で締結されていることが認められる。
以上の諸事実を総合すれば、本件各雇用契約を締結した際、本件、各雇用契約の準拠法はドイツ法であるとの黙示の合意が成立していたものでと推定することができる。
解説
国際的な労働契約が締結された場合、どの国の法律が適用されるのかという準拠法の問題については、かつては、法例7条1項により、当事者自治の原則に基づき決定するものとされていた。当事者の合意が明確でない場合には、同条2項により、行為地法を適用するのではなく、当事者の黙示の意思を探求するという手法がとられてきた(判旨Ⅰを参照)。
その後、平成18年に「法の適用に関する通則法」(以下、通則法)が制定された。法例では、労働契約についての準拠法選択について、労働者の保護のための特別な規定は存在していなかったが、通則法では、当事者自治の原則を引き続き採用したうえで(7条)、労働契約のついての特則が定められた(12条)。
それによると、まず、「当該労働契約に最も密接な関係がある地の法」(最密接関係地方)以外の地の法が選択された場合において、
第1に、労働者が、最密接関係地法の中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、その強行規定が適用される(1項)。
第2に、最密接関係地法は、当該労働者において、労務を提供すべき地の法と推定する。労務を提供すべき地を特定できない場合には、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法と推定する(以上、2項)。
次に、当事者による準拠法の選択がなされたなかった場合には、通則法8条1項により、最密接関係地方法が準拠法となる。このときも当該労働契約において労務を提供すべき地の法が、この最密接関係地方と推定される(12条3項、8条2項は適用されない)。仮に、本件のような事案で、黙示の合意を探求するのではなく、準拠法選択がなされていなかったと認定された場合、現在の通則法を適用すると、XらとY会社との労働契約の最密接関係地方は、Xらは東京ベースの勤務であり、勤務地が日本であるので日本法と推定されるが、判例Ⅱで認定されたような事情があれば、この推定が覆されて、ドイツ法が準拠王を判断される可能性はあるであろう。 本判決は、ドイツ法を適用し、本件の付加手当の撤回が、ドイツ民法典315条の「公正な裁量」に基ずくと認められるかどうかについて検討して、これを肯定している。 なお、国際裁判管轄については、平成24年の民事訴訟法改正により、労働関係における特則(3条の4第2項・3項、3条の7第6項)が設けられている。
法の適用に関する通則法7条(当事者による準拠法の選択)
第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
法の適用に関する通則法12条(労働契約の特例)
第十二条 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
2 前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
3 労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
法の適用に関する通則法8条(当事者による準拠法の選択がない場合)
第八条 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
民事訴訟法3条の4第2項・3項(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
第3条の4 消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
2 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
3 消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない。
民事訴訟法3条の7第6項(管轄権に関する合意)
第3条の7 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる。
6 将来において生ずる個別労働関係民事紛争を対象とする第1項の合意は、次に掲げる場合に限り、その効力を有する。
一 労働契約の終了の時にされた合意であって、その時における労務の提供の地がある国の裁判所に訴えを提起することができる旨を定めたもの(その国の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意については、次号に掲げる場合を除き、その国以外の国の裁判所にも訴えを提起することを妨げない旨の合意とみなす。)であるとき。
二 労働者が当該合意に基づき合意された国の裁判所に訴えを提起したとき、又は事業主が日本若しくは外国の裁判所に訴えを提起した場合において、労働者が当該合意を援用したとき。
137 外国人労働者の逸失利益-改進社事件
最3小判平成9年1月28日(平成5年(オ)2132号)(民集51巻1号78頁)
要因
オ-バーステイの外国人労働者が労災に遭った場合の逸失利益は、どのように算定されるか。
事実
Xは、パキスタン回教共和国の国籍を有する者であり、昭和63年11月28日、日本で就労する意図の下に、短期滞在(観光目的)の在留資格で入国し、翌日からY1会社に雇用され、在留資格経過後も不法に残留し、継続してY1会社において製本等の業務に従事していたところ、平成2年3月30日に指の一部を切断するという、本件事故に被災して後遺障害を残す負傷をした。Xは、Y1会社および同社の代表取締役Y2に対して、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求をした。1審は、Xの後遺障害による逸失利益利益については、Xが本件事故後、別のA会社で働くようになり、そこを退社した日の翌日から、3年間は日本においてY1会社から受けていた実収入額と同額の収入を、その後、67歳までの39年間は来日前に母国で得ていた収入を日本円に換算して1か月当たり3万円程度をそれぞれ得ることができたものと認めるのが相当であるとして、Xの請求を棄却した。そこで、Xは上告した(yらも附帯上告)。
判旨 上告棄却(Xの請求の一部認容、一部棄却)(以下は、逸失利益に関する判示部分のみとりあげる)。
Ⅰ「財産上の損害としての逸失利益は、事故がなかったら、存していたであろう利益の喪失分として、評価算定されるものであり、その性質上、種々の証拠資料に基づき相当程度の蓋然性をもって、推定される当該被害者の将来の収入等の状況を基礎として、算定せざるを得ない。損害の填補、すなわち、あるべき状態への回復という損害賠償の目的からして、右算定は、被害者個々人の具体的事情を考慮して行うのが相当である。こうした逸失利益算定の方法については、被害者が日本人であると否とによって、異なるべき理由はない。
Ⅱ「したがって、一時的に我が国に滞在し、将来出国が予定されている外国人の逸失利益を算定するも当たっては、当該外国人がいつまで我が国に居住して慰労するか、その後はどこの国に出国してどこに生活の本拠を置いて就労することになるか、などの点を証拠資料に基づき相当程度の蓋然性が認められる程度に予測し、将来のあり得べき収入状況を推定すべきことになる。
そうすると、予測される我が国での就労可能性ないし、滞在可能期間内は、我が国での収入等を基礎として、逸失利益を算定するのが合理的ということができる。そして、我が国における就労可能期間は、来日目的、事故の時点における本人の意思、在留資格の有無、在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、就労資格の有無、就労の態様等の事実的及び規範的な諸要素を考慮して、これを認定するのが相当である。
Ⅲ 在留期間を超えて不法に我が国に残留し就労する不法残留外国人は、最終的にはわが国からの退去を強制されるものであり、わが国における滞在および就労は不安定なものであり、わが国における滞在および就労は不安定なものといわざるをえない。そうすると、在留特別許可等により、その滞在および就労が合法的なものとなる具体的な蓋然性が認められる場合はともかく、不法残留外国人のわが国における就労可能期間を長期にわたるものと認めることはできないものというべきである。
解説
外国人が日本に在留するためには、在留資格のいずれかに該当しなければならない。在留資格の中には、就労が認められているものもあるが、その在留資格に応じた就労活動をしなければならず、また、在留期間は、許可された範囲となっている(出入国管理及び難民認定法2条の2、別表1を参照)。就労が認められていない在留資格で就労している場合、認められた就労活動をしている場合、在留期間を超えて在留して就労している場合などは、不法就労となす。
不法就労の場合であっても、実際に労働関係が展開している場合には、労働保護法規の適用はある。その典型例が、労災保険の適用である。さらに本判決は、安全配慮義務違反による損害賠償請求も認めている(なお、平成21年の外国人研修制度の改正前に雇用関係にない研修期間中も使用従属関係があったとして、労働保護法規の適用を認めた裁判例は少なくない(三和サービス事件ー名古屋高判平成22年3月25日等」)。
本件の主たる争点は、不法残留中の外国人の逸失利益安定方法である。本判決は、逸失利益の算定は、「種々の証拠資料に基づき相当程度の蓋然性をもって推定される当該被害者の将来の収入等の状況を基礎として算定せざるを得ない」とし、このことは日本人と外国人とで区別する理由はないとする(判旨Ⅰ)。しかし、一時的にしか日本に滞在しない外国人の特殊性もあるのであり、そうした外国人については、予測される日本での就労可能期間ないし滞在可能期間内は日本での収入等を基礎とし、その後は想定される出入国先(多くは母国)での収入等を基礎として逸失利益を算定するのが合理的とする(判旨Ⅱ)。そして不法残留の場合には、強制退去の可能性もあることから、日本での就労可能期間を長期にわたると認めることはできないとし(判旨Ⅲ)、結論として、日本での滞在期間を3年とした原審の判断を相当としている。
出入国管理及び難民認定法2条の2
(在留資格及び在留期間)
第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
138 労働組合法上の労働者性-INAXメンテナンス事件
最3小判平成9年1月28日(平成5年(オ)2132号)(民集51巻1号78頁)
要因
業務委託契約を締結しているカスタマーエンジニアは、労組法上の労働者か。
事実
X会社は、親会社であるA会社の製造した住宅設備機器の修理を業とする会社である。X会社のカスタマーエンジニア(以下、CE)は、一般労働組合BのC支部の下にD分会を結成し、B組合、C支部、D分会(以下、まとめて組合)は連名で、X会社に団体交渉を申し入れた。これに対し、X会社は、CEは、個人事業主であり、労組法上の労働者ではないので、団体交渉に応じる義務はないと回答した。
X会社は、CEとの間で、業務委託契約を締結しているが、個別の業務は、X会社が、発注した顧客の所在場所を担当するCEに依頼し、CEがそれに応諾した上で行われていた。CEが応諾しなくても、X会社は、業務委託契約の債務不履行と判断していなかったが、実際には、応諾拒否の割合は、1%弱であった。
CEは業務の際、A会社の子会社の作業であることを示すため、X会社の制服着用や名刺携行をし、業務終了時にはX会社に報告書を提出していた。業務委託手数料は、顧客への請求金額に、CEの級に応じた一定率を乗じて算出されていた。CEの作業時間は、1件平均70分、1日平均3.7時間で、X会社からの平均依頼件数は、月113件。4平均休日取得日数は月5.8日であった。
B組合とC支部は、E労働組合に対して、X会社の断行拒否は不当労働行為(労組法7条2号)に該当するとして、救済を申し立てたところ、Eは団交応諾と文書手交を内容とする救済命令を発した。X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査申立てをしたが、Yはこれを棄却する命令を発した。そこで、X会社は、Yの命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審はX会社の請求を棄却したため、X会社が控訴したところ、原審はCEの労働者性を否定して、Yの命令を取り消した。
そこで、Yは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(X会社の請求棄却)。
CEは、X会社の主たる事業であるA会社の住宅設備機器の修理補修業務の遂行に不可欠な労働力として、X会社の組織に組み入れられていた。また、CEとX会社の間の業務委託契約の内容は、X会社の定めた「業務委託に関する覚書」によって、規律されており、個別の修理補修等の依頼内容をCE側で変更する余地がなかったことも明らかであるから、X会社とCEとの間の契約内容を一方的に決定していたものというべきである。さらに、CEの報酬は、X会社が商品や修理内容に従ってあらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に、当該CEにつき、X会社が決定した級ごとに定められた一定率を乗じ、これに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で、支払われていたのであるから、労務の提供の対価としての性質を有するものということができる。
加えて、X会社からの修理補修等の依頼について、たとえ、CEが承諾拒否を理由に債務不履行責任を追及されることがなかったとしても、各当事者の認識や契約の実際の運用においては、CEは基本的にX会社のよる個別の修理補修等の依頼に応ずるべき関係にあったものとみるのが相当である。しかも、CEは、X会社の指定する業務遂行方法に従い、その指揮監督に下に労務の提供を行っており、かつ、その業務について場所的にも一定の拘束を受けていたもものということができる。以上の諸事情を総合考慮すれば、CEは、X会社との関係において労組法上の労働者に当たると解するのが相当である。
解説
労組法上の労働者概念(3条)は、労基法(9条)や労契法(2条1項)の労働者概念(→【87】横浜南労基署長(旭総業)事件)と比べても、「使用される」という要件がないなど、文言上、より広いものとなっている(たとえば、失業者は、労組法上の労働者ではあるが、労基法上の労働者ではない)。このことは、労組法上の労働者に該当するためには、労働契約関係の存在は、必ずしも必要とされないということを意味している。
ただ、その一般的な判断枠組みは明確ではなく、本判決もこれをめいじしたはいない。本判決は、CEが、
①業務の遂行に不可欠な労働力として組織に組み入れられていること、
②契約内容が一方的に決定されていること、
③報酬が労務提供の対価としての性質を有すること、
④実質的に諾否の事由がなかったこと、
⑤業務遂行において指揮監督下にあり、場所的拘束性と時間的拘束性もあったこと
に言及して、労組法上の労働者性を肯定している(同様の基準で、合唱団員の労組法上の労働者性を肯定した判例として、新国立劇場運営財団事件ー最3小判平成23年4月12日)。その後の判例では、
⑥独立の事業者としての実態を備えていないこと
を判断要素として追加している(ビクターサービスエンジニアリング時間ー最3小判平成24年2月21日)。以上のように実態に着目した判断をするアプローチは、これまでの判例も同様であった(CBC管弦楽団労組時間ー最1小判昭和51年5月6日)。
最近の判例や労働委員会の命令では、個人事業主のように、使用従属性が希薄な者であっても、団体交渉により労働条件の維持改善を図るのに適していると解される場合には、労組法上の労働者に含める傾向にある(バイシンクメッセンジャーの労組法上の労働者性を肯定した最近の裁判例として、ソクハイ事件ー東京地判平成24年11月15日。また、フランチャイザーとフランチャイズ契約を結ぶフランチャイジー[加盟店のオーナー]に労働者性を肯定する労委命令も登場している)。
労働組合法7条2項(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
労働組合法3条(労働者)
第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
労基法9条 (定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労契法2条1項(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
139 管理職組合の労働者性-ゼメダイン事件
東京高判平成12年2月29日(平成11年(行コ)157号)
要因
管理職だけで組織された労働組合からの団体交渉を、会社が拒否することは認められるか。
事実
X会社は、接着剤等の製造販売を業とする株式会社である。X会社の課長であったA、担当職(担当次長)であったBらは、管理職定年制の実施を契機に管理職の権利・雇用・地位を守るため、C労働組合を結成し、X会社側にその通告をした。その後、C組合は、X会社に対し、定年延長にともなう担当職に対する資格手当減額措置の廃止や、スタッフ管理職手当の親切等を交渉事項とする団体交渉の申入れをしたが、X会社はこれに応じなかった。
そこで、C組合は、X会社の団交拒否について、不当労働行為の救済申し立てをしたところ、D労働委員会は申立てを認容する命令を発した。X会社は、Y(中央労働委員会)に再審査申立てをしたが、Yはこれを棄却する命令を発した。そこで、X会社は、Yの命令の取消しを求めて、訴えを提起した。1審は、X会社の請求を棄却したため、X会社は控訴した。なお、最高裁は、本判決に対する上告を棄却している。
判旨 控訴棄却(X会社の請求棄却)。
労組法7条2号は、2条において定義された「労働組合」の文言を用いず、「労働者の代表者」という文言を用いて、労働者の団結の形態を問わない旨、明らかにしていること、憲法の規定上「勤労者」すなわち労働者であるかぎりにおいては、利益代表者といえども、労働三権を保障されているものと解されること、それにもかかわらず、労組法が、2条ただし書き1号のような規定を置いたのは、同号掲記の労働者の参加を許せば、組合の自主性が損なわれるおそれがあるとの見地から、一種の後見的配慮に基づくものと考えられるが、本来、組合員の範囲は、組合自身が決定すべきことであり、このような後見的配慮を働かせる場合には、おのずから、限度があるといわざるを得ないこと、以上のことにかんがみれば、利益代表者の参加を許す労働組合であっても、使用者と対等関係に立ち、自主的に結成された統一的な団体であれば、労組法7条2号の「労働者の代表者」に含まれるものであって、ただ、このような労働組合は、使用者から団交を拒否された場合でも、労働委員会による救済手続を享受することはできないものと解するのが相当である。
解説
労組法2条は、労働組合を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」と定義しているが、役員、雇入、解雇、昇進または移動に関して直接の健全を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者、その他、使用者の利益代表者の参加を許す団体は、定義から除外している(たdし書1号)。
実際には、組合規約や労働協約上、課長になれば非組合員扱いとされる例が多いといわれているが、利益代表者かどうかの判断は、本来、その労働者の権限や職務内容等からみて、その加入によって、労働組合の自主性が失われる蓋然性が高いかという観点から、行われるべきであり、労組法上の利益代表の範囲はかなり限定的であることには注意を要する(本件では、C組合には利益代表者は加入していないと判断された)。
利益代表者が加入しているため、労組法上の労働組合の定義に該当しない団体は、同法5条1項により、労働委員会における資格審査において、法定号組合とは認められず、そうなると、「この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない」。したがって、不当労働行為の救済申し立てをすることもできなくなる(判旨参照)。
なお、労組法上の労働組合の定義を満たす場合でも、同法5条2項の定める規約を具備していなければ、やはり、法適合組合とはならない(同条1項)。
このような労組法上の法適合組合でない場合には、労組法上の保護や救済を受けることはできないが、その場合でも、憲法上の団体としての保障を受けることはできないが、その場合でも、憲法上の団結としての保障を受ける余地はあるし、いずれにせよ、現行法上違法な団体となるわけではないので、たとえば、断行拒否に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条を参照)等が認められることはある。なお、判旨は、7条2号が「労働組合」という文言を用いていないことから、2条の定義に合致しない労働組合であっても、使用者は、団体交渉に応じなければならないとするが、労組法7条は不当労働行為に関する規定なので、労働委員会での救済申し立てが認められない労働組合との関係で、同条(2号)違反があったとするのは、適切でなく、この点で判旨Ⅱは疑問がある。
労組法7条2項(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
労組法2条 (労働組合)
第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
労組法5条(労働組合として設立されたものの取扱)
第5条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在地
三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
民法709条(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
140 混合組合の労働組合性-大阪教育合同労組事件
東京高判平成26年3月18日(平成25年(行コ)395号)
要因
地方公務員法の適用を受ける職員と労組法の適用を受ける職員とが混在する混合組合に、不当労働行為救済における申立人不適が認められるか。
事実
Aは、地方自治体Xに属する教職員等を中心に結成された団体で、地方公務員法(地公法)が適用される組合員(地公法適用組合員)と労組法が適用される組合員(労組法適用組合員)により、更生される混合組合である。
A組合は、Xの公立学校の常勤講師や非常勤講師等の任用の保障(雇用の継続)を交渉自工とする団体交渉を申し入れたところ、B教育委員会はこれを拒否した。そこで、A組合はC労働委員会に救済申し立てをしたが、Cは却下および棄却をした。そこで、A組合はY(中央労働委員会)に再審査を申し立てたところ、Yは労働法適用組合員(非常勤講師)の任用の保障を求める団体交渉拒否についてはCの棄却命令を取り消し、Bに文書手交を命じた。
そこで、Xは、Yの命令が違法であるとして、その取り消しを求めて訴えを提起した。1審は、Xの請求を棄却した。そこで、Xは控訴した。なお、本判決に対して、Xは上告したが、上告棄却・不受理となっている。
判旨 控訴棄却(Xの請求棄却。以下は、本判決が引用する1審判決の内容である)。
「地公法は、登録された職員団体となる場合を除き、職員団体の構成員を地公法が適用される一般職の地方公務員に限定する旨の規定を置いておらず、地公法及び労組法は、一般職の地方公務員が労働団体に加入することを制限する旨の規定を置いていないことからすれば、現行法は、混合組合の存在を許容しているものと解することができる。
そして、混合組合が地公法適用組合員と労組法適用組合員とにより構成されているとの組織実績があることを鑑みれば、混合組合は、代表される組合員に対し、適用される法律の区別に従い、地公法の職員団体及び労組法上の労働組合としての複合的な法的性格を有すると解するのが自然かつ合理的である(複合性格説・二元適用論)」。
混合組合であるA組合は、「労組法適用組合員に関する問題については、労働組合として、労組法上の権利を行使することができると言うべきであるから、労組法7条各号の別を問わず、救済命令の申立人適格を有するものと解するのが相当である。
解説
特別職の地方公務員(地公法3条3項)は、地公法が適用されず(同法4条2項)、労組法の適用を受ける。本件の非常勤講師は、特別職の地方公務員である(同法3条3項3号)。他方、本件の常勤講師のような一般職の地方公務員(同法3条2項)は、労組法は適用されず(同法58条1項)、その結成する職員団体は、地公法による特別な規制を受ける(同法52条以下。争議行為も禁止されている。同37条)。そこで、こうした地公法の規制を受ける一般職の職員と労組法の適用を受ける職員が混在する「混在組合」が、労組法の適用を受ける職員との関係で、労組法上の労働組合と認められるのか(特に、不当労働行為救済の申立人適格がsるのか)という点が問題となってきた。
従来の裁判例は、不利益取扱いの事案について、労組法の適用される労働者(単純労務職員等)にとって、救済される手段が奪われることは適切でないとして、混合組合にも申立人適格を認めてきた(北海道立釧路療養所事件ー札幌高判昭和56年9月29日等)。中労委の実務でも、そのような取扱いがなされてきた。
もっとも、裁判例の中には、単一性格説・一元適用論にたつものもあり、そのうえで、労組法7条1号および4号との関係でのみ、混合組合の申立人適格を判定するものであった(大阪教育合同労組事件ー大阪高判平成14年1月22日)。しかし、単一性格説、一元適用論では、混合組合の法的性格が、組合員の労的割合や役員構成という容易に変動しうる要素によって判断されることとなり、判断基準が不安定となるし、また不当労働行為制度は労組法7条の各号を相互補完的に活用することが期待されていることから、1号と4号のみに限定して、申立人適格を認める必然性がないとして、本判決は、中労委と同様、複合性格説・二元適用論を支持した(大阪高裁も、現在では、本判決と同じ立場である。(大阪教育合同労組事件ー大阪高判平成27年1月29日)。
なお、本判決は、非常勤講師の任用の実態が、繰り返しの任用によって、実質的に勤務が継続する中での任用条件の変更または前年度の継続であったとして、A組合の要求した団交事項は、義務的団交事項であると判断している(判旨外)。
労組法7条(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
地公法3条3項・地公法3条3項3号・地公法3条2項
第三条 地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
一の二 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
二 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
二の二 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
三 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
四 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
五 非常勤の消防団員及び水防団員の職
六 特定地方独立行政法人の役員
地公法4条2項(この法律の適用を受ける地方公務員)
第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
地公法58条1項(他の法律の適用除外等)
第五十八条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
地公法52条(職員団体)
第五十二条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
4 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
5 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
地公法37条(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
141 組合加入拒否の違法性-全ダイエー労組事件
横浜地判平成元年9月26日(昭和63年(ワ)710号)
要因
労働組合は、会社の上級職制に対して組合員資格を否定することが認められるか。
事実
Xは、昭和44年にA会社に入社し、同58年以降、A会社の資格制度上副主事の地位にある。Y労働組合では、A会社との間で締結した労働協約において、副主事以上の者をY組合の組合員の判旨から除外する旨を定め、組合規約においても、同趣旨の規定を置いている。Xは、同63年、Y組合への加入を申し込んだが、Y組合は、Xが組合員資格を有しないことを有しないことを理由に、Xの加入を申込みを承認しなかった。
Xは、Y組合の加入拒否により、組合員であれば支給されたであろう昇給額と実際の昇給額の差額等の損害を被ったとして、その賠償を求めて訴えを提起した。
判旨 請求棄却
Ⅰ「労働者と労働組合の法律関係は、労働者が組合に加入申し込みをし、組合がこれに対する承諾をすることによって、初めて発生する者であり、組合が特定企業の従業員で組織され、労働者が当該企業の従業員であるからといって、そのことから当然に労働者と組合間に何らかの法律関係が生じるというものではない。この意味では、労働組合の加入は、申込と承諾という2つの意思表示から成る契約の締結であって、労働者から加入の申込があった場合、これを拒否することが違法と評価され、損害賠償義務を負うか否かはともかくとして、労働組合には、承諾義務はないと解するのが一般である。このことは、労働組合と特定企業の間にユニオンショップ協定が締結されている場合においても、異別に解すべき理由はなく、労働者は、組合に対して組合加入の承認を求めうるべき私法上の請求権を有しないというべきである」。
Ⅱ「労働組合は、労働者が自己の利益を擁護するため自主的に結成する任意団体であるから、組合員資格をどのような定めるかについては、労働組合法上労働組合に与えられている特別の機能、しなわち、団体交渉によって組合員をはじめとする労働者の労働条件を規定する機能とこれを法的に強化するための諸々の保護との関係で、一定の制約を受けるほか、原則として、組合の自治に委ねると解するのが相当である。殊に、従業員の職種、地位、職位、資格その他の種類等労働者の利害関係の相違を基準として、加入資格を制限することは、いかなる範囲の労働者を結集することが労働運動上効果的であるかという組織構成の決定の問題であって、組合自治の領域に属するものというべきであるから、Y組合が、A会社の資格制度上副主事以上の者を組合員の除外資格とする組合規約に基づき、Xの加入を承認しなかったことは、何ら違法を招来するものでない。・・・・
労働組合法2条も、企業別組合に対し、但書1号所定の労働者以外のすべての従業員に組合員資格を付与すべきことを規定するものではない。従って、Y組合の組合員資格がこれらの規定又はその精神に反し無効であるということはできないし、他に、これを無効とすべき理由も見出し得ない」。
解説
労働者が、労働組合への加入を拒否された場合、労働者はそのことを法的に争うことができるのであろうか。組合加入の拒否の事例には、組合員資格がないことをりゆうとする場合と、組合員資格があったとしても、その労働者の加入は認めないという場合がある。本件は前者の場合である。
本判決は、労働組合への加入は、契約の締結であり、「労働者は、組合に対して、組合加入の承認を求めうべき私法上の請求権を有しない」と述べる(判旨Ⅰ)。この判断は、本件とは異なり、組合員資格があるにもかかわらず、加入を拒否された場合にもあてはまるものと解すべきであろう。もっとも、判旨Ⅰは、加入拒否により、拒否された労働者に損害賠償請求権が発生する可能性は否定していない。
本件では、Y組合が組合員資格から副主事以上の労働者を排除したことの適法性が問題となっている。この点につき、本判決は、原則として、これは組合自治の問題であると述べている。
ただし、「労働組合法上、労働組合に与えられている特別の権能、すなわち、団体交渉によって組合員をはじめとする労働者の労働条件を規定する権能とこれを法的に強化するための諸々の保護との関係で、一定の制約を受ける」とも述べている(判旨Ⅱ)。
その具体的な意味は必ずしも明確ではないが、労組法が、人種、宗教、性別、門地、身分によって組合員資格を奪われないことを規約の必要記載事項として定めていることを考慮にいれると(5条2項4号)、そこで、列挙された理由によって、組合加入が拒否された場合には、違法と評価されて損害賠償請求が認められる可能性はあろう。
もっとも、本判決は、本件のように、一定の職制以上の者を組合員資格から除外することについては、やはり、組合自治の問題であり、Y組合の加入拒否は違法ではないとしている(判旨Ⅱ)。なお、使用者の利益代表者の組合加入を認めれば、その組合は、法適合組合ではない(2条ただし書1号→【139】セメダイン事件)が、だからといって、使用者の利益代表者の組合加入を認めたはならないというわけではない。法適合組合でない形態での活動を選択する余地はあるからである。
労組法2条(労働組合)
第2条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
三 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
労組法5条2項4号(労働組合として設立されたものの取扱)
第5条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在地
三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
142 労働組合からの脱退の制限-東芝労働組合小向支部・東芝事件
最2小判平成19年2月2日(平成16年(受)1787号)(民集61巻1号86頁)
要因
労働組合からの脱退を制限する合意を組合員と使用者がした場合、その合意は有効か。
事実
Xは、Y2会社に雇用され、同社の従業員で構成されているY1労働組合に加入した。Y1組合とY2会社とが締結した労働協約には、ユニオン・ショップ協定とチェックオフ協定の条項がある。これに基づき、Y2会社は、Y1組合の組合費のチェックオフをしている。
Xは、割増賃金についての運用等に不満があり、それに関するY1組合の対応にも不満をもったことから、A全国一般労働組合B地連に加入した上で、Y1組合に対し、脱退届を送付したが、Y1組合は、その受理を留保した。XおよびB地連は、Y2会社に対し、XがB地連に加入したことを通知するとともに、団体交渉を申し入れたが、Y2会社は、Y1組合が脱退届の受理を留保していることを英雄に団体交渉に応じなかった。
XとB地連は、これが不当労働行為にあたるとして、C労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てたところ、和解が成立した。和解の際には、Y1組合に所属し続けることをXに義務付けることなどを内容とする本件付随合意がなされた。
その後、Xは、工場内での配置転換等について不満を抱き、Y1組合に支援を求めても不十分な対応しかされなかったとして、再び、Y1組合に不満をもち、脱退の意思を表示し、Y2会社に対して、チェック・オフの中止を申し入れた。
Y2会社がこれに応じなかったため、Xは、Y1組合に対して、Xが組合員としての地位を有しないことの確認およびチェック・オフされた金額の返還等を求めて、また、Y2会社にはY1組合の組合費を控除しない金額の賃金をXに支払う義務を負うことの確認を求めて、訴えを提起した。1審は、Xの請求を認容したが、原審は。Xの脱退の効力を否定し、1審判決のうち、脱退の有効性を前提とした部分を取り消した。そこで、Xは上告した。
判旨 原判決破棄、自判(Xの請求認容)。
Ⅰ 一般に労働組合の組合員は、脱退の自由すなわち、その意思により組合員としての地位を離れる事由を有するものと解される。そうすると、本件、付随合意は、脱退の自由を制限し、XがY1組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを、Y2会社に対して、約したものであることとなる。
Ⅱ 本件、付随合意は、XとY2会社との間で成立したものであるから、その効力は、原則として、Xが本件付随合意に違反して、Y1組合から脱退する権利を行使しても、Y2会社との間で、債務不履行の責任等の問題を生ずるにとどまる。
Ⅲ 労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として、はじめて、容認されることである。そうすると、本件付随合意のうち、Y1組合から脱退する権利をおよそ行使しないことをXに義務づけて、脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し、無効であるというべきである。
解説
労働組合からの脱退は、原則として、自由である。脱退を制限するような定めは、無効となる。(脱退には、組合の機関の承認を要するとする組合規約を無効とした裁判例として、日本鋼管鶴見製作所事件→東京高判昭和61年12月17日)。さらに、本判決は「労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合費はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれているものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として、初めて容認される」、と述べている(判旨Ⅲ。なお、ユニオン・ショップのように、組合からの脱退を事実上制約するものにとどまる制度は、判例上、原則として有効とされている。→【143】三井倉庫港運事件)。
本件付随合意は、XがY1組合から脱退しないことを義務づけたものであり、Xの脱退の自由を制限する内容をもつものといえる(判旨Ⅰ)。ただ、こうした合意がY1組合とに間で結ばれたという点に、本件の特徴がある。
Y1組合との間で結ばれていれば、判旨Ⅲのロジックにより、端的に無効ということになろうが、Y2会社との関係では、この合意が、当然に無効となるのではない。また、この合意はX・B地連とY2会社との和解にともなって結ばれたもので(Y2会社は和解金として、250万円をB地連側に支払っている)、一方的にXが押し付けられたという事情があるわけではない。
最高裁は、本件付合意は、Xの脱退の効力を否定するとぴう部分は無効である(判旨Ⅲ)が、債務不履行責任の問題が生じる余地はあるとする(判旨Ⅱ)。脱退しない義務を課すこと自体は、有効であり、それに違反したときに、損害賠償という金銭解決のみ認める趣旨なのであろう。ただ、実際にXに債務不履行責任が認められるのは、Y2会社が何も問題がある行為をとっていないにもかかわらず、Y1組合がXのために十分な対応をしないという理由により、脱退したような場合に限られるであろう。
143 ユニオン・ショップ-三井倉庫港運事件
最1小判平成元年12月14日(昭和60年(オ)386号)(民集43巻12号2051頁)
要因
ユニオン・ショップ協定締結組合から脱退し、別組合に加入した労働者への解雇は有効か。
事実
Y会社の海上コンテナトレーラー運転手であるXらには、昭和58年2月21日午前8時半ころ、A労働組合に対して、脱退届を提出して、同組合を脱退し、即刻、B労働組合C支部に加入し、その旨を同日午前9時10分頃、Y会社に通告した。Y会社は、A組合との間で、「Y会社は、Y会社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、A組合に加入しない者及びA組合を除名された者を解雇する」という内容のユニオン・ショップ協定を締結していた。
A組合らは、Xについて、脱退届を提出したその日に、Y会社に対し、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇をするよう要求し、Y会社は、同日、午後6時頃、Xらを解雇した。そこで、Xらは、この解雇は、解雇権濫用で無効であるとして、従業員たる地位にあるとの確認を求めて、訴えを提起した。1審および原審ともに、Xの請求を認容した。そこで、Y会社は、上告した。
判旨 上告棄却
「ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という)の団結権と同様、同協定うぃ締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであることから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には、許されないものというべきである。
したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合に加入している者及び締結組合から脱退した又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について、使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の協定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用とて無効るといわざるを得ない。
解説
ユニオン・ショップとは、その会社の従業員が全員、当該労働組合の組合員でなければならないということであり、使用者と労働組合との間で、ユニオン・ショップ協定が結ばれれば、使用者は、その労働組合に加入しない労働者や、脱退したり、除名されたりした労働者を解雇する義務を負うとされているのが通常である。こうしたユニオン・ショップ協定に基づく解雇については、解雇権濫用法理(現在では、労契法16条)の適用下においても有効となるというのが確定判例である(→【46】日本食塩製造事件)。
ところで、本判決は、この確定判決の射程を限定したという点で重要な意味をもつ。すなわち、労働組合から脱退した労働者であっても、別の労働組合に加入している場合には、ユニオン・ショップ協定における使用者の解雇義務は及ばないと判断したのである(同旨の判例として、日本鋼管鶴見製作所事件ー最1小判平成」元年12月21日)。その理由として、判旨は、次の点をあげている。
①労働者は、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があること、
②ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであること、である。
すなわち、労働者の組合選択の自由と他の労働組合の団結権の保障という観点から、ユニオン・ショップ協定の効力範囲は限定されるのである。
この判決によって、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇が認められるのは、労働組合を脱退した後、あるいは、労働組合から除名された後、その労働組合にも加入していないか、新たな労働組合を結成していないという場合に限られることになる(このほか、採用後、その労働組合にも加入していない労働者にもユニオン・ショップ解雇は認められる)。これにより、ユニオン・ショップ協定の効力は、大幅に減殺されることになった。
なお、ユニオン・ショップ協定の有効性については、これに疑問を提起する学説もある。従来、憲法28条の保障する団結権は、同21条の保障する結社の自由とは異なり、団結しない事由を認めないとかいされてきた(消極的団結権の否定)。しかし、近年、労働組合に加入するかどうかは、労働者の自由な決定にゆだねられるべきであり、ユニオン・ショップ協定のは、そのような労働者の自由を侵害するとして無常と解すべきであるという説や少なくとも解雇権の濫用と解すべきとする説が有力となりつつある(その根拠としては、消極的団結権の肯定や憲法13条の自己決定権の尊重等があげられている)。
民法90条(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法21条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
憲法13条〔個人の尊重〕
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
労契法16条(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
144 労働組合の統制権-三井美唄労組事件
最大判昭和43年12月4日(昭和38年(あ)974号)(民集22巻13号1425頁)
要因
労働組合の方針に反して、地方議会議員選挙に独自に立候補して当選した労働者に対して課された権利停止の統制処分は有効か。
事実
A労働組合は、地方議会選挙においては、労働組合から統一候補を推薦して、選挙運動を進めることにしていた。昭和34年のB市の市議会議員選挙の際にも統一候補を選んだが、組合員の統一候補に選ばれなかったにもかかわらず、独自に立候補しようとした。そこで、YらA組合の役員は、Cに立候補を断念するように説得したが、結局、Cは立候補し当選した。Yらは、これらの行為が公職選挙法225条3項(選挙の候補者や当選人等を威迫する罪)に該当するとして起訴された。1審は、Yらを有罪とし、原審は、無罪とした。そこで、検察官は上告した。
判旨 原判決破棄、差戻し(一部分のみ上告棄却)。
Ⅰ「労働者がその労働条件を適正に維持し、改善しようとしても、個々にその使用者たる企業者に対しでいたのでは、一般に企業者の有する経済的実力に圧倒され、対等の立場においてその利益を主張し、これを貫徹することは、困難である。そこで、労働者は、多数団結して、労働組合等を結成し、その団結の力を利用して必要かつ妥当な団体行動をすることによって、適正な労働条件の維持改善を図っていく必要がある。憲法28条は、この趣旨において、企業者対労働者、すなわち、使用者対使用者という関係に立つ間において、経済上の弱者である労働者のために、団結権、団体交渉および団体行動権(いわゆり労働基本権)をほしょうしたものである。
Ⅱ「労働基本権を保障する憲法28条は、さらに、これを具体化した労働組合法も、直接には、労働者対使用者の関係を規制することを目的としたものであり、労働者の使用者に対する労働基本権を保障するものにほかならない。
ただ、労働者が憲法28条の保障する団結権に基づき労働組合を結成した場合において、その労働組合が正当な団体行動を行うにあたり、労働組合の統一と一体化を図り、その団結力の強化を期するためには、その組合員たる個々の労働者の行動についても、組合として、合理的な範囲において、これに規制を加えることが許されなければならない(以下、これを組合の統制権とよぶ)。およそ、組織的団体においては、一般に、その構成員に対し、その目的に則して、合理的な範囲内での統制権を有するのが通例であるが、憲法上、団結権を保障されている労働組合においては、その組合員に対する組合の統制権は、一般の組織的団体のそれと異なり、労働組合の団結権を確保するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、労働者の団結権保障の一環として、憲法28条の精神に由来するもおということができる」。
解説
労働組合は、通常、組合員に対して、組合内部の秩序の維持のための規制を行い、それに違反する場合に制裁を課すという定めを置いている。この制裁を統制処分という。統制処分としては、譴責、戒告、制裁金(罰金)、権利停止、除名が定められていつことが多い。なかでも、除名処分は、ユニオン・ショップ協定が、締結されている場合には、使用者からの解雇と結びつくことになるので(→【143】三井倉庫港運事件)、組合員に、大きな影響を及ぼすものとなる。
最高裁は、「労働組合の統一と一体化を図り、その団結力の強化を期するためには、その組合員たる個々の労働者の行動についても、組合として、合理的な範囲において、これに規制を加えることが許されないことが許されなければならない」とし、これを統制権と呼んでいる(判旨Ⅱ)。そして、これを統制権は、組織的団体が、一般に合理的な範囲内で、有するのが通例だが、労働組合については、憲法上、団結権が保障されているという点で、特別な法的性格をもつとしている。
すなわち、憲法28条は、適正労働条件の維持改善を図るために、対使用者において経済的な弱者である労働者の維持改善を図るために、対使用者において、経済的な弱者である労働者が団結権その他の労働基本権を享受することを保障しているのであり(判旨Ⅰ)、そのような団結権に基づいて結成されているのである(判旨Ⅱ)。
もっとも、統制権を具体的に行使する場合には、労働組合はその規約に基づく必要があり、憲法28条のみを根拠として、具体的な統制権を行使できるわけではない。
また、本判決は、判旨Ⅱに引き続いて、「労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内において、その組合員に対する統制権を有するものと解するべきでる」と述べており、(判旨外)、統制権には、こうした一般的な制約がかかっている。労働組合の4世紀の決定に違反する行為をした組合員が統制処分の対象となるのが原則であるが、本件のように、組合員の政治的自由と抵触する可能性がある場合には、当然に労働組合の統制権が及ぶわけではない(詳細は、→【145】中里鉱業所事件[解説])。
公職選挙法225条3号(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ 又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き 棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
145 組合員の政治活動の制限-中里鉱業所事件
最2小判昭和44年5月2日(昭和40年(オ)823号)
要因
国政選挙において、労働組合の決めた候補者以外の候補を応援する活動をした組合員に対する除名処分は有効か。
事実
Y労働組合は、昭和37年に、定期大会において、参議院銀選挙に政党Aの公認候補を推薦すること、宗教団体Bの信者の組合員が大会決議に故意に違反して、反組合的行動をとった場合には、統制違反として処分されるべきことを決議した。ところが、Y組合の組合員であるXは、選挙期間中に、その入会しているBの政治組織であるC政治連盟の推薦候補者の選挙ポスターY組合は、Xのこの行為は、組合大会決議に反するとして、臨時組合大会において、Xを除名する旨の決議をした。なお、Y組合は、会社との間で、ユニオン・ショップ協定を締結していた。
Xは、この除名処分の無効確認を求めて訴えを提起した。1審および原審ともに、Xの請求を認容した。そこで、Y組合は、上告した。
判旨 上告棄却(Xの請求認容)。
Ⅰ「労働組合は、憲法28条による労働者の団結件保障の効果として、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲内においては、その組合員に対する統制権を有するが、他方、公職の選挙に立候補する自由は、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権の1つと解すべきであって、労働組合が、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙運動を推進している場合に、統一候補の選にもれた組合員が、組合の方針に反して立候補しようとするときは、これを断念するよう勧告または説得することは許さないが、その域を超えて、立候補をとりやめることを要求し、これに従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界をこえるものとして許されない」。
Ⅱ「この理は、・・・・立候補した者のためにする組合員の政治活動の自由との関係についても妥当とする」。
Ⅲ「Y組合の大会決議は、組合の推薦する特定候補以外の立候補者を支持する組合員の政治活動(選挙運動)を一般的・包括的に制限禁止し、これに違反する行動を行った組合員は、。
統制違反として、処分されるべき旨を決議したものであって、・・・・組合の統制権の限界を超えるものとして無効と解すべきである。
解説
判旨Ⅰは、三井美唄労組事件(→【144】)の最高裁の判旨を受け継いだものである。同事件で、最高裁は、労働組合が、その目的を達成するために必要な政治活動等を行うことを妨げられるものではないので、地方議会議員の選挙にあたり、いわゆる統一候補を決定し、組合を挙げて選挙活動を推進することとし、統一候補の選にもれたが、なお立候補を思いとどまるように勧告または説得することも、その限度においては、組合の政治活動の一環として、許されるところと考えてよく、その範囲で、統制権をもつと述べている。
他方で、同判決は、「公職選挙における立候補の自由は、憲法15条1項の趣旨に照らし、基本的人権の1つとして、憲法の保障する重要な権利であるから、これに対する制約は、特に慎重でなければならず、組合の団結を維持するための統制権の行使に基づく制約であっても、その必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量して、その許否を決すべきであり、その際、政治活動に対する組合の統制権のもつ・・・・性格と立候補の自由の重要性とを十分考慮する必要がある」とも述べている。そして、この事件では、結論として、労働組合の決定に反して、立候補して当選した組合員に対する統制処分を適法とする原判決は破棄を免れないとした。
すなわち、労働組合として組合員に対しておこなうことができるのは、組合の方針に反する政治活動を断念することまでであり、その域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に津政権違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるものである(判旨Ⅰも同旨)。そして、本判決は、この理は、立候補した他人のためにする組合員の政治活動についても、あてはまるとした(判旨Ⅱ)。
なお、判旨Ⅲは、除名処分の無効だけでなく、当初の大会決議そのものを無効としている。そうすると、Y組合の行為が仮に勧告や説得の域にとどまっていたとしても、それが違法と評価される可能性があったことになる。判旨Ⅲの大会決議まで無効としたのは、組合員の政治活動を一般的・包括的に制限し、それに違反した者に対して統制処分をするという、組合員の政治的自由に対する強度の制限がおこなわれていたからであろう。
憲法28条〔勤労者の団結権〕
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法15条1項〔公務員の選定及び罷免の権利、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障〕
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
146 組合員の協力義務-国労広島地本事件
最3小判昭和50年11月28日(昭和48年(オ)499号)(民集29巻10号1698頁)
要因
労働組合の政治活動に関わる費用について、組合員は臨時組合費の納入義務を負うか。
事実
Xは、旧国鉄の職員によって結成された労働組合であり、Yらはいずれも旧国鉄の職員で、X組合の組合員であった。X組合は、YらがX組合を脱退した後に、組合費の支払を怠っていたとして、その支払いを求めて、訴えを提起した。1審は、一般組合員については、請求を認容したが、臨時組合費のうち、炭労資金、安保訴金、政治意識昂揚資金等は、Yらに納入義務はないとした。原審も1審の判断を維持した。そこで、X組合は、上告したが(なお、Yらも、敗訴部分について上告したが棄却されたいる)。
判旨 原判決一部破棄、自判(Xの請求の一部認容、一部棄却)。
Ⅰ「思うに、労働組合の組合員は、組合の構成員として、留まる限り、組合が正規の手続に従って決定した活動に参加し、また、組合の活動を妨害するような行為を避止する義務を負うとともに、右活動の経済的基礎をなす組合費を納付する義務を負うものであるが、これらの義務(以下、「協力義務」という。)は、もとより、無制限のものではない、労働組合は、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体であって、組合員はかかる目的のための活動に参加する者としてこれに加入するのであるから、その協力義務も当然に右目的達成のために必要な団体活動の範囲に限られている」。
Ⅱ「労働組合の活動の範囲が広く、かつ、弾力的でるとしても、そのことから、労働組合がその目的の範囲内においてするすべての活動につき、当然、かつ、一様に組合員に対して、統制力を及ぼし、組合員の協力を強制できるものと速断することは、できない。労働組合の活動が、組合員の一般的要請にこたえて、拡大されるものであり、組合員としてある程度まではこれを予想して組合に加入するのであるから、組合からの脱退の自由が確保されている限り、たとえ、個々の場合に組合の決定した活動に反対の組合員であっても、原則的にはこれに対する協力義務を免れないというべきであるが、労働組合の活動が、前記のように多様化するにつれて、組合による統制の範囲も拡大し、組合員が1個の市民又は人間として有する自由や権利と矛盾衝突する場合が、増大し、しかも今日の社会的条件のもとでは、組合に加入していることが労働者にとって、重要な利益で、組合脱退の自由も事実上大きな制約を受けていることを考えると、労働組合の活動として許されたものであるというだけで、そのことから直ちにこれに対する組合員の協力義務を無条件で肯定することは、相当でないというべきである」。
Ⅲ「それゆえ、・・・・問題点とされている具体的な組合活動の内容・性質、これについて組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較衡量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である」。
解説
組合員には、労働組合の手続で決まったことには従うという協力義務がある。組合費の納入義務も、その協力義務の1つであり、これに違反した場合には、通常は、除名処分となる。本件では、臨時組合費の中に、組合の政治的な活動に関わるものがあったため、協力義務を課すことが組合員の政治的な自由と抵触しないかが問題となった。
本判決は、一般論として、組合員の協力義務も無制限なものでなく、労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図るという目的の達成のために必要な団体活動の範囲に限られるとする(判旨Ⅰ)。組合員には、脱退の自由がることからすると、ある程度、広い統制力を組合に認めてもよいといえそうだが、本判決は、組合脱退の自由が事実上大きく制約されていることも考慮すべきとする(判旨Ⅱ)。そして、具体的な組合活動の内容、程度、態様等を比較考量し、「多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から」、組合の統制力と組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要であるとする(判旨Ⅲ)。
具体的に見ていくと、本判決は、他組合の闘争に対する支援基金については、組合の目的に合致するとして協力義務を肯定し、特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金については、どの政党を支持するかは、組合員各人が自主的に決定すべき事柄であつとして協力義務を否定した。
他方、安保反対闘争に参加して処分を受けた組合員を救援するための資金は、結論として、組合員個人の政治的思想に関係する程度はきわめて軽微であるとして、協力義務を肯定している。なお、一般論としては、「労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動のごとき」は、組合員に協力義務を認めてもよいが、安保運動反対そのものは、「個人的かつ自主的な思想、見解、判断等に基づいて決定すべきことであるから」協力義務は、認められないとしている。
147 チェック・オフ-エッソ石油事件
最1小判平成5年3月25日(平成3年(オ)928号)
要因
組合員から組合費のチェック・オフの中止の申し出があった場合には、使用者はチェック・オフを継続してはならないか。
事実
Xらは、Y会社の従業員であり、A労働組合の組合員であったが、闘争方針の相違から、執行部と激しく対立するようになり、昭和57年9月にB労働組合を結成した。その後、B組合に属する支部・分会連合会は、Y会社に対して、Xらの同月以降のチェック・オフにかかるA組合に交付せず、この支部・分会連合会に支払うよう申し入れた。それにもかかわらず、Y会社は、同年10月から翌年3月までのXらの毎月の賃金等から、A組合の組合費をチェック・オフし、A組合に交付した。そこで、Xらは、Y会社にこの行為は、不法行為に該当するとして、チェック・オフされた組合費に相当する損害額の賠償を求めて、訴えを提起した。1審は、Xらの請求を認容し、原審もXらの請求をほぼ認容した・そこで、Y会社は上告した。
判旨 上告棄却(Xらの請求の一部認容、一部棄却)。
Ⅰ「労働基準法・・・・24条1項ただし書の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は、これにより、右協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法120条1号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎないものであって、それが、労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである」。
Ⅱ「使用者と労働組合との間に右協定(労働協約)が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定の他に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき、委任を受けることが必要であって、右委任が存しないときには、使用者は、当該組合員の賃金からチェック・オフをすることはできないものと解するのが相当である。そうすると、チェック・オフ開始後においても、組合員は、使用者に対し、いつでもチェック・オフの中止を申し入れることができ、右中止を申し入れがされたときには、使用者は当該組合員に対するチェック・オフを中止すべきものである。
解説
チェック・オフとは、労働組合の組合費を、使用者が組合員に支払う賃金から天引きし、それを労働組合に引き渡すことである。チェック・オフは、労働組合と使用者との間のチェック・オフ協定に基づき行われるが、その協定が労働協約の形式で締結されたときには(労組法14条を参照)規範的効力が生じ(同条16条)、組合員がチェック・オフによる組合費の徴収を義務付けられるのかが、問題となる。この点について、本判決は、労働協約の形式で締結されたものであっても、組合員が「チェック・オフを受忍すべき義務を負うものではない」。として規範的効力を否定していうる(判旨Ⅰ)。
また、チェック・オフは、賃金の一部を控除するという面で、賃金全額払いの原則(労基法24条1項)に反することになる(→【172】済生会中央病院事件[判旨外])ため、チェック・オフが有効に行われるためには、使用者と過半数代表との間で書面による労使協定が締結されていなけらばならない(同項ただし書)。過半数組合であれば、自動的に過半数代表となるので、書面でチェック・オフが協定が締結されていれば、それが、労基法24条1項ただし4書の労使協定になるし、また、労働協約ともなりうる(過半数組合でない労働組合は、自力では、チェック・オフがを合法化できない)。
本判決は、労使協定の効力は、免罰的効力にすぎず(→【102】日立製作所武蔵工場事件)、この協定により、使用者がチェック・オフを行う権限や組合員がチェック・オフを受忍する義務を負うわけではないとする(判旨Ⅰ)。
そして、本判決は、使用者がチェック・オフを行うためには、組合員からの支払委任が必要であるとする(判旨Ⅱ)。この見解によると、使用者は、労働組合とのチェック・オフ協定と組合員の支払委任とに基づき、組合費を組合に支払うことが義務づけられ、チェック・オフは、その費用についての組合費への償還請求権(民法650条)と、組合員への賃金支払債務の一部との相殺という法律構成となる。
支払委任説をとることの重要な法的帰結は、組合員は、いつでも支払委任を撤回できるということである(民法651条を参照)。支払委任の撤回があれば、使用者はチェック・オフはできなくなる(判旨Ⅱ)。実際には、組合員からの支払委任の撤回はほとんど考えられない(てっかいをすると統制処分の対象となろう)が、本件のような組合移籍にともない、どの組合に所属するかが明確でなくなったときには、支払委任の撤回(チェック・オフ中止の申入れ)の有無により、チェック・オフの継続の適法性の判断をするという本判決の処理は、実務上も重要な意味がある。
労基法24条1項(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労基法120条1号
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
労組法14条(労働協約の効力の発生)
第14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
労組法16条(基準の効力)
第16条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
民法650条(受任者による費用等の償還請求等)
第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
民法651条(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
148 労働組合の分裂-名古屋ダイハツ労組事件
最1小判昭和49年9月30日(昭和44年(オ)438号)
要因
労働組合からの集団脱退により新たな労働組合が結成された場合に、組合財産の分割は認められるか。
事実
Aは、B会社に従業員で結成された労働組合である。A組合はCの下部組織として活動してきたが、組合内部において、Cの傘下をを離れたほうがよいという意見が生じて、大多数はこれに賛成した。しかし、組合内部には、Cの下部組織としての立場を頑強に維持しようとする少数派があった。そのようななか、A組合の委員長Dは、独断で臨時組合大会を開催し、解散動議を出して、解散決議を強行した。A組合の規約には、解散決議は組合大会で、組合員の直接Dが無記名投票により採決することを要する旨、」規定されたいたが、この解散決議は、起立の方法によって採決された。
その後、A組合の組合員224名は、A組合は解散の決議により、消滅したとして、Y組合を結成し、Dを執行委員長に選任した。その際、A組合の会計係がY組合に加入しており、Y組合の結成に参加した人員が解散に反対した人員に比し、圧倒的に多数であった事情等もあって、A組合の財産は、Y組合の財産として、Dが保管するに至った。他方、A組合の解散決議に反対したA組合の組合員約40名は、執行委員長を新たに補充したのみで、他の組合員役員および組合規約並びに組合の名称については、何ら変更を加えることなく、X組合(すなわち、A組合)として、現在に至っている。
X組合は、DがA組合の財産をY組合の財産として独占保有し損害を与えたとして、Y組合に対してその賠償を求めて訴えを提起した。1審は、A組合の解散決議はむこうであるし、組合分裂があったものとも認められないとして、X組合の請求を認容した。Y組合は控訴したが、原審は、控訴を棄却した。そこで、Y組合は上告した。
判旨 上告棄却(X組合の請求認容)。
Ⅰ「労働組合の規約中に解散決議の採択方法につき、直接無記名投票による旨の定めがある場合において、それ以外の採用方法によってされた組合解散決議は、あらかじめ決議に参加する者全員がその採決方法によることを同意していたと認められるときのほかは、客観的にみて、その採決方法によらざるをえないと認めるに足りるだけの特段の事情が存しないかぎり、無効である解するのが相当である」。
本件では、起立の方法によることにつき、担ぎ参加者全員の同意を得ていなかったのであり、そのような方法によらざるえないと認めるに足りるだけの特段の事情があったといい難い。
Ⅱ「労働組合において、その内部に相拮抗する異質集団が成立し、その対立抗争が甚だしく、そのため、組合が統一的組織体として存在し活動することが事実上困難となり、遂に、ある異質集団に属する組合員が組合(以下、旧組合という。)から集団的に離脱して新たな組合(以下、新組合という。)を結成し、ここに新組合と旧組合の残留組合員による組合(以下、残存組合という。)とが対峙するに至るというような事態が生じた場合には」、「旧組合は、組織的同一性を損なうことなく、残存組合として存続し、新組合は、旧組合とは組織上全く別個の存在であるとみられるのが通常であって、ただ、旧組合の内部対立により、その統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難をなり、その結果旧組合員の集団的離脱及びそれに続く新組合の結成という事態が生じた場合に、はじめて、組合の分裂という特別の法理の導入の可否につき、検討する余地を生ずるものと解されるのである。
解説
労働組合の財産は、判例上、組合員全員の総有とされており、組合員全員の同一性による、総有廃止などの財産処分に関する定めがない限り、組合員は当然には持分権や分割請求権をもつものではない(品川白瓦事件ー最1小判昭和32年11月14日。国労大分地本事件ー最1小判昭和49年9月30日も参照)、労働組合の内部において、深刻な対立が生じて、多数の組合員が集団的には、脱退したという場合でも、これを単なる脱退と評価すれば、組合員には、組合財産のの分割請求権が原則としてない以上、組合財産は、残存組合が独占的に保有することができる。しかし、このような場合、「組合の分裂」という概念を認めて、組合財産の分裂を認めるほうが公平であるという考え方もある。
本判決は、「旧組合の内部対立により、その統一的な存続・活動が極めて高度かつ、永続的に困難となり、その結果、旧組合員の集団的離脱及びそれに続く新組合の結成という事態が生じた場合」に、はじめて「組合の分裂」という概念を認める余地があるとしている(判旨Ⅱ)。ただ、この基準は、かなり厳格なもので、本件でも、「A組合は、到底機能喪失により自己分解したとは評価しえない」とされ、このような場合に該当しないとされた(判旨外)。
なお、本判決は、本件の解散決議を無効としている(判旨Ⅰ)が、仮に解散決議が有効であった場合、残余財産の帰属については、法人格のある労働組合の場合(労組法13条を参照)に準じた処理をすべきとする見解も有力である。
労組法13条の10 (残余財産の帰属)
第13条の10 解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
149 複数組合の共同交渉-旭ダイヤモンド工業事件
東京高判昭和57年10月13日(昭和54年(行コ)115号・116号)
要因
企業内における複数の労働組合からの共同交渉の申込みに、使用者は応じなければならないか。
事実
X会社には、それぞれ別の工場の従業員を組織しているA労働組合とB労働組合がある。両組合は、年末一時金に」ついて、X会社に共を同交渉を申し入れた。しかし、X会社は、共同交渉が回答促進を目的とするものであるなら、従来から両組合に同時回答をしているので共同交渉の必要がないこと、両組合の組織形態が基本的に異なっていること、要求事項に違いがあることを理由にこれを拒否した。その後、両組合は「統一交渉団」を結成し、交渉権限の委任状を添えて、X会社に団体交渉を申し込んだが、X会社はこれも拒否した。なお、X会社では、これまでA、B両組合による共同交渉に応じたこともあった。
A、B両組合は、X会社の前記の団交拒否は、不当労働行為であるとして、Y労働委員会に救済申立てをしたところ、Yは不当労働行為と認定して救済命令を発した。そこで、X会社は、この救済命令の取消しを求めて訴えを提起した。1審は、控訴審引用の判断を示して、最高裁(最2小判昭和60年12月13日)は、原審の認定判断を正当として是認するとして、上告を棄却している。
判旨 控訴棄却(X会社の請求認容。以下は、控訴審の引用する1審判決の内容である)。
Ⅰ「団体交渉権を保障されている労働者の団結は、まずなによりも、団結力を保持するものでなければならないのであり、この団結力を保持する団体であるということができるためには、構成員に対し統制力をもちそこに統一的な団体意思が形成されていることが必要であると解される。・・・・統制力を欠き、統一団体意思の形成されていない単なる労働者の集団は、使用者との団体交渉能力をもたず、このような団結からの団体交渉申入れに対しては、使用者がこれを拒否しても正当な理由があるものとして不当労働行為にはならないものと解されるのであるが、このことは、その間に統制力を欠き、統一団体意思の形成されていない単なる労働組合の集団からの団体交渉の申し入れについてもまた、同様である。
Ⅱ「同一企業内に複数の労働組合が併存する場合であっても、その交渉の形態(ないし方式)は、各労働組合と使用者との個別交渉の形態によるのが原則である。このような各労働組合の個別交渉の原則のわくをこえて複数の労働組合が共同して使用者に対し、団体交渉を求めることは、各労働組合の闘争力、交渉力を強化するとともに複数の労働組合の組合員相互に共通する具体的要求事項を統一的ないし画一的に解決することを」目的とし、その点意義があるものと考えられるのであるが、使用者に対する関係で、このような共同交渉の形態による団体交渉を求めることができるためには、複数の労働組合相互間において統一された意思決定のもとに統一した行動をとることができる団結の条件すなわち統一意思と統制力が確立されていることが必要であると解するのが相当である」。
Ⅲ「もっとも、・・・・使用者が労働組合と労働協約又は協定等により、共同交渉の形態による団体交渉を行うことを約している場合、共同交渉の形態による団体交渉を行うことが確立した労使慣行となっている場合、その他使用者が共同交渉の申し入れに応ずることが合理的かつ相当であると認められる特段の事情がある場合には、使用者が共同交渉を申し入れを拒否することは許されないものというべきであるが、右のような例外的な場合を除いては、・・・・共同交渉の形態による団体交渉の申し入れであることを理由にこれを拒否しても、正当な理由があるものとして、不当労働行為にはならないものというべきである」。
解説
日本では、アメリカのように排他的交渉代表性は、さいようされていないので、同一企業内で複数の労働組合が併存する場合には、使用者はいずれの労働組合からの団体交渉申込みにも応じなければならない。では、企業内における複数の労働組合が共同交渉や、統一交渉団との団体交渉を申し込んできた場合にも、使用者はそれに応じなければならないのであろうか。
本判決は、まず、統制力を欠き、統一団体意思が形成されていない単なる労働者の集団は、団体交渉能力をもたないとし、同じことは、労働組合の集団でもあてはまるとする(判旨Ⅰ)。そして、複数の労働組合が併存する場合には、個別交渉が原則であり、共同交渉を申し込むためには、「複数の労働組合相互間において、統一された意思表示のもとに統一した行動をとることができる団体の条件」、すなわち、統一意思と統制力が確立されていることが必要とする(判旨Ⅱ)。
150 誠実交渉義務-カール・ツァイス事件
東京地判平成元年9月22日(昭和62年(行ウ)130号)
要因
使用者は、どのような場合に誠実交渉義務をはたしたといえるか。
事実
A労働組合は、X会社の従業員150名により、昭和59年5月9日に結成された。A組合は、同月10日、X会社に対して、結成通知書を提出するとともに、ユニオン・ショップ協定の締結、組合役員の配転についての組合の同意、団体交渉時の賃金保障、チェック・オフ、組合事務所、掲示板の設置、貸与、組合の日常は、すでに活動における便宜供与という基本要求事項についての団体交渉を申し込んだ。第1回目の団体交渉は、同年9月12日に行われ、昇給と特別賞与については妥結して協定が結ばれたが、基本要求事項は、継続審議となった。
同60年の春闘の際は、X会社は、A組合の要求に対して、昇給事項についての回答書を手交し、協定に調印した。同61年、A組合は、継続審議となっていた基本要求事項や、組合員の人事異動について、X会社に団体交渉を申し入れた。しかし、X会社は、基本要求事項についてはすでに解決済であるとし、人事異動については労働条件変更の具体的申入れに該当しないとして、団体交渉を拒否した。そこで、A組合は、Y労働委員会に不当労働行為の救済申立てをした。Yは、誠実交渉義務違反の不当労働行為と認め、救済命令を発した。そこで、X会社は、その取消しを求めて、訴えを提起した。
判旨 請求棄却
Ⅰ「労働組合法7条2号は、使用者が団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止しているが、使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意をもって団体交渉に当たったとは認められないような場合も、右規程により、団体交渉の拒否として不当労働行為となると解するのが相当である。このように、使用者には、誠実に団体交渉にあたる義務があり、したがって、使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならなず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また、結局において労働組合の要求に対し、譲歩することができないとしても、その論拠を示して反論するなどの努力をすべき義務があるのであって、合意を求める労働組合の努力に対しては、右のような誠実な対応を通じて、合意達成の可能性を模索する義務があるものと解すべきである」。
Ⅱ「なるほど、使用者の団交応諾義務は、労働組合の要求に対し、これに応じたり譲歩したりする義務まで含むものではないが、・・・・右要求に応じられないのであれば、その理由を十分説明し納得が得られるよう努力すべきであり、また、使用者は、労働組合に対し、その活動のためにする企業の物的施設の利用その他の便宜供与を受忍しなければならない義務を負うものではないが、ここれについては、義務的団体交渉事項と解するのが相当であるから、労働者から右のような事項について団体交渉の申し入れがあれば、使用者は、その要求をよく検討し、要求に応じられないもであれば、その理由を十分説明するなどして納得が得られるよう努力すべきである。
解説
労組法7条2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むことを不当労働行為として定めている。この団体交渉には、労組法の明文の規定はないものの、労働組合からの団体交渉に誠意をもって応じないという誠実交渉義務違反も含むと解されている(判旨Ⅰ)。問題は、どのような場合であれば、誠実交渉義務を果たしたといえるかである。本判決は、一般論として、使用者には、合意を求める労働組合の努力に対して、使用者には、合意を求める労働組合の努力に対して、誠実な対応を通じて合意達成の可能性を模索する義務がある。とする(判旨Ⅰ)。その誠実性の判断要素としては、
①労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料をていじすること、
②労働組合の要求に応じないときでも、その論拠を示して反論するなども努力をすること、
などが例示されtいる(判旨Ⅰ)。
また、使用者には譲歩の義務はないので、労働組合の要求に応じる必要はないものの、その場合でも、労働組合の要求に対して、その理由を十分説明し、納得が得られるように努力しなければならない(判旨Ⅱ)。
本件におけるX会社の態度は、以上の点について誠実性が認められず、不当労働行為と判断された。過去の裁判例を見ると、たとえば、文書による回答に固執し、会見して協議するようとしない場合、合意達成の意思がない事を明言して交渉に臨む場合、実質的に交渉権限のない者を交渉に出席させて実のある交渉を阻害している場合、交渉をいたずらに引き延ばそうとする場合等に、誠実交渉義務違反が認められている。
なお、交渉において双方の主張が出尽くし、いずれかの譲歩により、交渉が進展する見込みがなくデッドロック(行き詰まり)に陥った場合には、使用者は、団体交渉を拒否して正当な理由があるとされる(池田電器事件ー最2小判平成4年2月14日)。ただし、いったんデッドロックに陥っても、その後に事情の変更があれば、使用者に再び誠実交渉義務が生じる可能性はある(寿建築研究所事件ー東京高判昭和52年6月29日も参照)。
労働組合法7条2号(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
本資料の作成につきましては、私が尊敬申し上げております大内 伸哉一先生の「最新重要判例200労働法第5版」を参考に、私のお客さまへのプレゼン資料として、作成させていただきましたので、その旨、記載させていただきます。
新着情報・お知らせ
井上久社会保険労務士・行政書士事務所
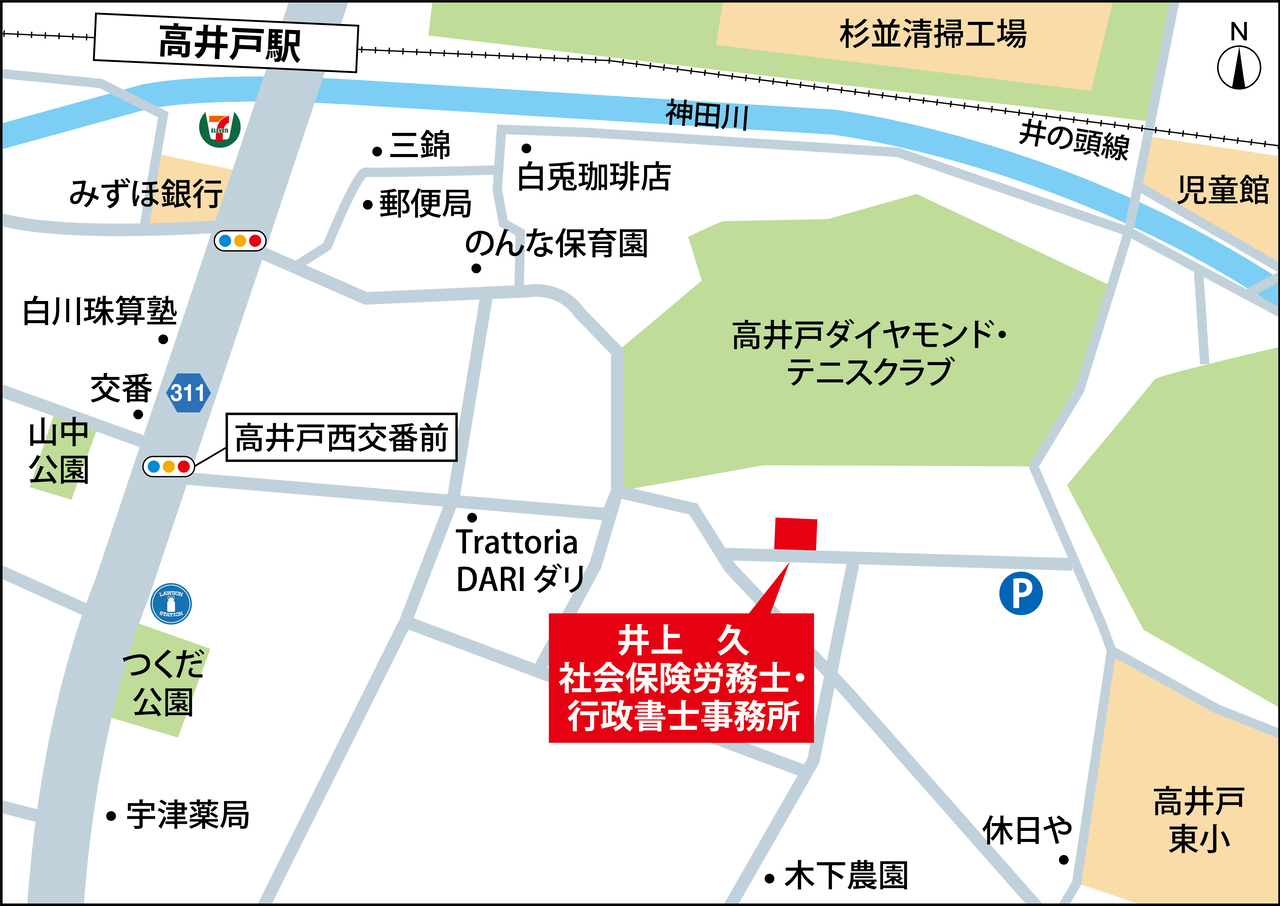
住所
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
アクセス
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

