新日本保険新聞掲載 「新米社労士イノキュウの現場からの本音の報告」
第1回掲載分(2024年4月8日(月)
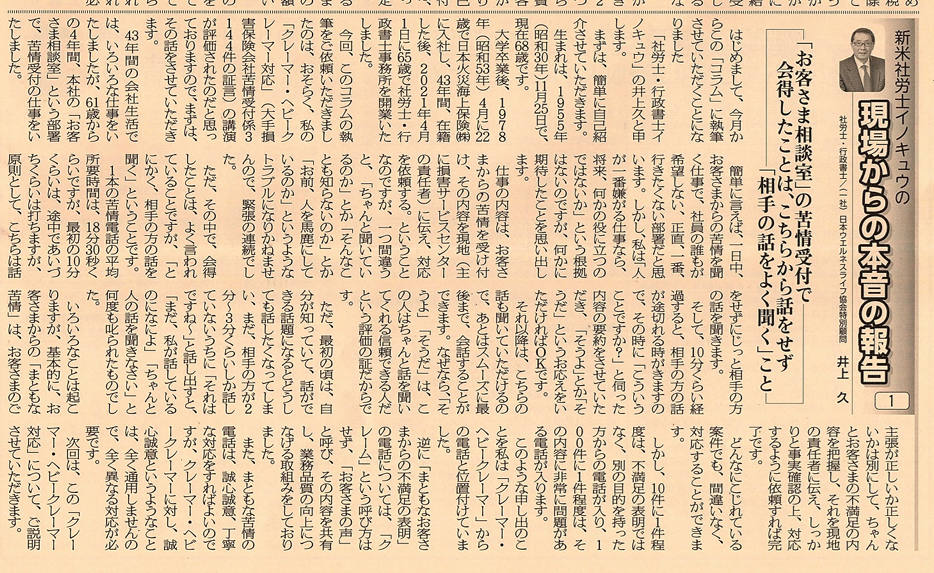
はじめまして、今月からこの「コラム」に執筆させていただくことになりました「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久と申します。
まずは、簡単に自己紹介させていただきます。生まれは、1955年(昭和30年)11月25日で、現在68歳です。大学卒業後、1978年(昭和53年)4月に22歳で日本火災海上保険(株)に入社し、43年間、在籍した後、2021年4月1日に65歳で社労士・行政書士事務所を開業いたしました。
今回、このコラムの執筆をご依頼いただきましたのは、おそらく、私の「クレーマー・ヘビークレーマー対応」(大手損害保険会社苦情受付係3,144件の証言)の講演が評価されたのだと思っておりますので、まずは、その話をさせていただきます。
43年間の会社生活では、いろいろな仕事をいたしましたが、61歳からの4年間、本社の「お客さま相談室」という部署で、苦情受付の仕事をいたしました。
簡単に言えば、一日中、お客様からの苦情を聞く仕事で、社員の誰もが希望しない、正直、一番、行きたくない部署だと思います。しかし、私は「人が一番いやがる仕事なら、将来、何かの役に立つのではないか」という根拠はないのですが、何かに期待したことを思い出します。
仕事の内容は、お客さまからの苦情を受け付け、その内容を現地(主に損害サービスセンターの責任者)に伝え、対応を依頼する。ということなのですが、一つ間違うと、
「ちゃんと聞いているのか」とか「そんなことも知らないのか」とか「お前、人を馬鹿にしているのか」というようなトラブルになりかねませんので、緊張の連続でした。
ただ、その中で、会得したことは、よく言われていることですが、「とにかく、相手の方の話を聞く」ということです。
1本の苦情電話の平均所要時間は、18分30秒くらいですが、最初の10分くらいは、途中であいづちくらいは打ちますが、原則として、こちらは話をせずにじっと相手の方の話を聞きます。そして、10分くらい経過すると、相手の方の話が途切れる時がきますので、その時に「こういうことですか?」と伺った内容の要約をさせていただき、「そうよ」とか「そうだ」というお応えをいただければOKです。それ以降は、こちらの話も聞いていただけるので、あとはスムーズに最後まで、会話することができます。なぜなら、「そうよ」「そうだ」は、この人はちゃんと話を聞いてくれる信頼できる人だという評価の証だからです。
ただ、最初の頃は、自分が知っていて、話ができる話題になるとどうしても話したくなってしまい、まだ、相手の方が2分~3分くらいしか話していないうちに「それはですね~」と話し出すと「まだ、私が話しているのになによ」「ちゃんと人の話を聞きなさい」と何度も叱られたものでした。
いろいろなことは起こりますが、基本的に、お客さまからの「まともな苦情」は、お客様のご主張が正しいか正しくないかは別にして、ちゃんとお客さまの不満足の内容を把握し、それを現地の責任者に伝え、しっかりと事実確認の上、対応するように依頼すれば完了です。
どんなにこじれている案件でも、間違いなく、対応することができます。
しかし、10件に1件程度は、不満足の表明ではなく、別の目的をもった方からの電話が入り、100件に1件程度は、その内容にひじょうに問題がある電話が入ります。
このような申し出のことを私は「クレーマー・ヘビークレーマー」からの電話と位置付けていました。逆に「まともなお客さまからの不満足の表明」の電話については、「クレーム」という呼び方はせず、「お客さまの声」と呼び、その内容を共有し、業務品質の向上につなげる取り組みをしておりました。
また、まともな苦情の電話は、誠心誠意、丁寧な対応をすればよいのですが、クレーマー・ヘビークレーマーに対し、誠心誠意というようなことは、全く通用しませんので、全く、異なる対応が必要です。次回は、この「クレーマー・ヘビークレー対応」について、ご説明させていただきます。
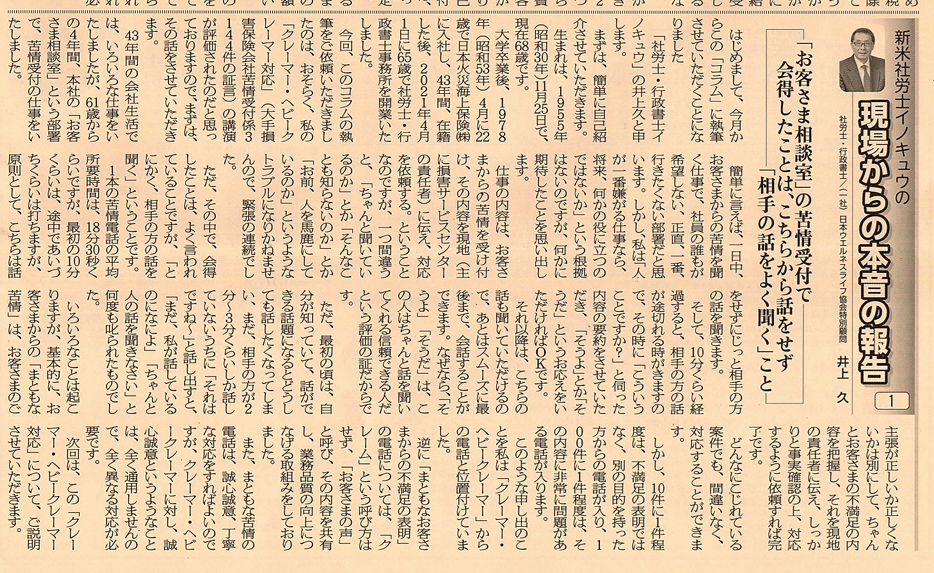
2024年4月4日(月)掲載分 クレーマー・ヘビークレーマー対応①
第2回掲載分(2024年5月13日(月))
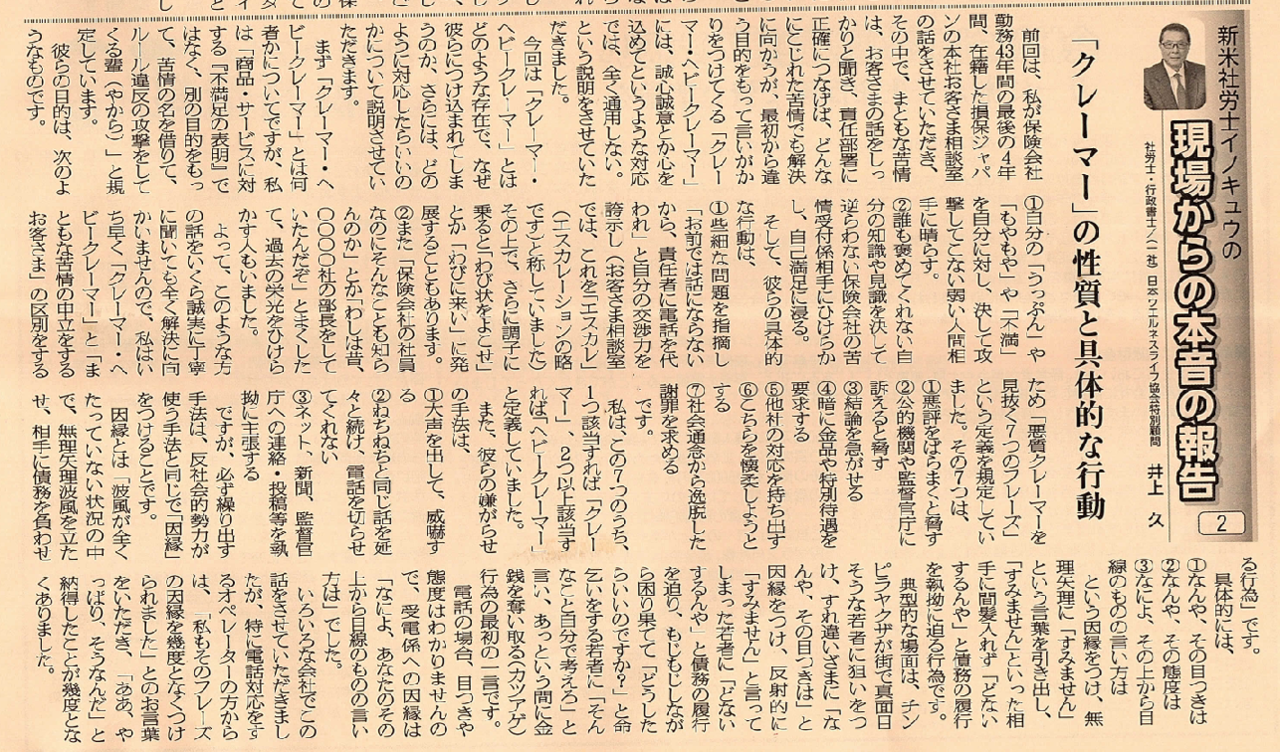
2024年5月13日(月)
こんにちは、「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久です。
前回は、私が保険会社勤務43年間の最後の4年間、在籍した損保ジャパンの本社お客さま相談室の話をさせていただき、その中で、まともな苦情は、お客さまの話をしっかりと聞き、
責任部署に正確につなげば、どんなにこじれた苦情でも解決に向かうが、最初から違う目的をもって言いがかりをつけてくる「クレーマー・ヘビークレーマー」には、誠心誠意とか心を込めてというような対応では、全く、通用しない。という説明をさせていただきました。
今回は、「クレーマー・ヘビークレーマー」とはどのような存在で、なぜ、彼らにつけ込まれてしまうのか、更には、どのように対応したらいいのかについて説明させていただきます。
まず、「クレーマー・ヘビークレーマー」とは何者かについてですが、
私は「商品・サービスに対する「不満足の表明」ではなく、別の目的をもって、苦情の名を借りて、ルール違反の攻撃をしてくる輩(やから)」と規定しています。
彼らの目的は一言では言えませんが、次のようなものです。
① 自分の「うっぷん」や「もやもや」や「不満」を自分に対し、決して攻撃してこない弱い人間相手に晴らす。
② 誰も褒めてくれない自分の知識や見識を決して逆らわない保険会社の「苦情受付係」
相手にひけらかし、自己満足に浸る。
そして、彼らの具体的な行動は
① ささいな問題を指摘し、「お前では、話にならないから、責任者に電話を代われ。」と自分の交渉力を誇示し、(お客さま相談室では、これを「エスカレ」(エスカレーションの略です。)と称していました。)その上で、さらに調子に乗ると、「わび状をよこせ。」とか「詫びに来い。」に発展することもあります。
② また、「保険会社の社員なのにそんなことも知らんのか。」とか 「わしは、昔、〇〇〇〇社の部長をしていたんだぞ。」とまくしたて、自らの過去の栄光をひけらかす人もいました。
よって、このような方の話をいくら誠実に丁寧に聞いても全く解決に向かいませんので、
私はいち早く、「クレーマー・ヘビークレーマー」と「まともな苦情の申立をするお客さま」の区別をするため「悪質クレーマーを見抜く7つのフレーズ」という定義を規定していました。
その7つは
①悪評をばらまくと脅す
②公的機関や監督官庁に訴えると脅す
③結論を急がせる
④暗に金品や特別待遇を要求する
⑤他社の対応を持ち出す
⑥こちらを懐柔しようとする
⑦社会通念から逸脱した謝罪を求める
です。
私は、この7つのフレーズの内、
1つ該当すれば「クレーマー―」
2つ以上該当すれば「ヘビークレーマー」と定義していました。
また、彼らの嫌がらせの手法は
①大声を出して、威嚇する。
②ねちねちと同じ話を延々と続け、電話を切らせてくれない。
③ ネット、新聞、監督官庁への連絡・投稿等を執拗に主張する。
ですが、
必ず繰り出す手法は、反社会的勢力が使う手法と同じで「因縁」をつけることです。
因縁とは、「波風が全くたっていない状況の中で、無理矢理波風を立たせ、相手に債務を負わせる行為」です。
具体的には、
① なんや、その目つきは、
② なんや、その態度は、
③ なによ、その上から目線のものの言い方は、
という因縁をつけて、無理矢理に「すみません」という言葉を引き出し、
「すみません」といった相手に間髪入れず、「どないするんや」と債務の履行を執拗に迫る行為です。
典型的な場面は、チンピラヤクザが街で真面目そうな若者に狙いをつけ、すれ違いざまに
「なんや、その目つきは」と因縁をつけ、反射的に「すみません。」と言ってしまった若者に「どないするんや」と債務の履行を迫り、もじもじしながら困り果てて「どうしたらいいのですか?」と命乞いをする若者に「そんなこと自分で考えろ」と言い、あっという間に金銭を奪い取る(カツアゲ)行為の最初の一言です。
電話の場合、目つきや態度はわかりませんので、受電係への因縁は
「なによ、あなたのその上から目電のものの言い方は」でした。
いろいろな会社でこの話をさせていただきましたが、特に電話対応をするオペレーターの方からは、「私もそのフレーズの因縁を幾度となくつけられました。」とのお言葉をいただき、「ああ、やっぱり、そうなんだ」と納得したことが幾度となくありました。
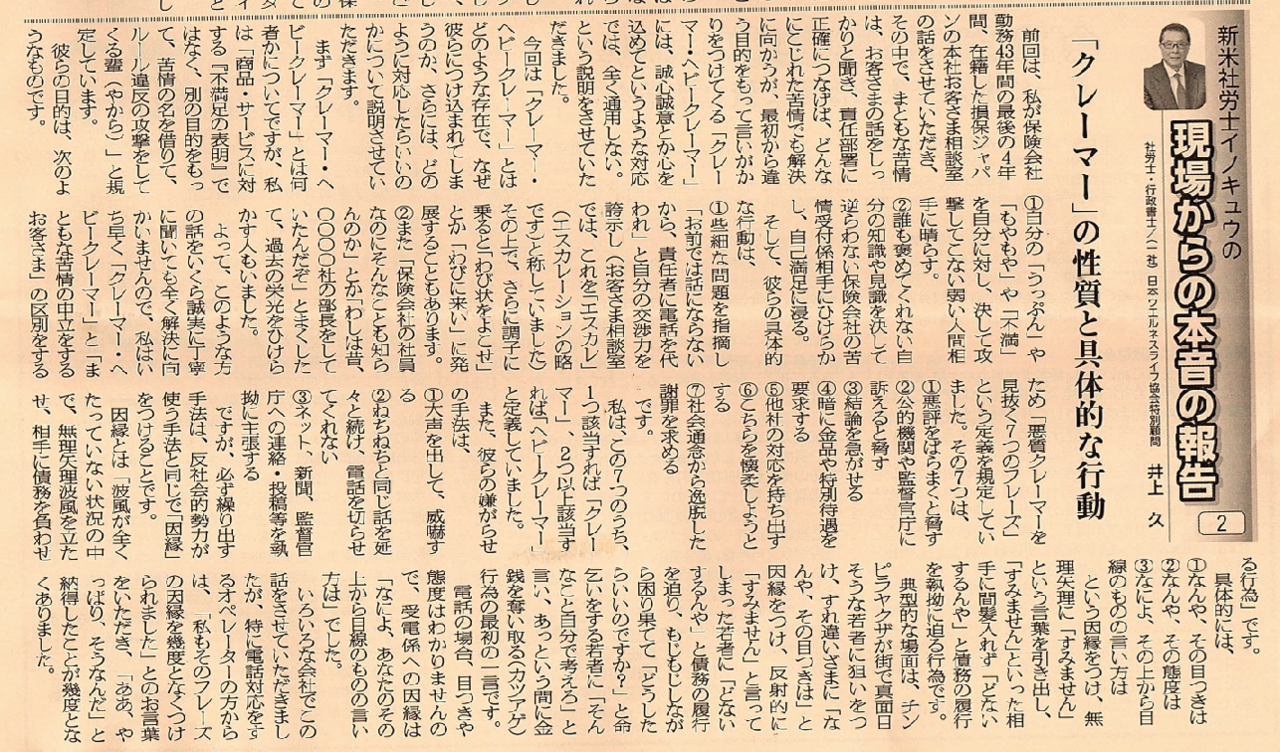
2024年5月13日(月)掲載 クレーマー・ヘビークレーマー対応②
第3回掲載分(2024年6月10日(月))
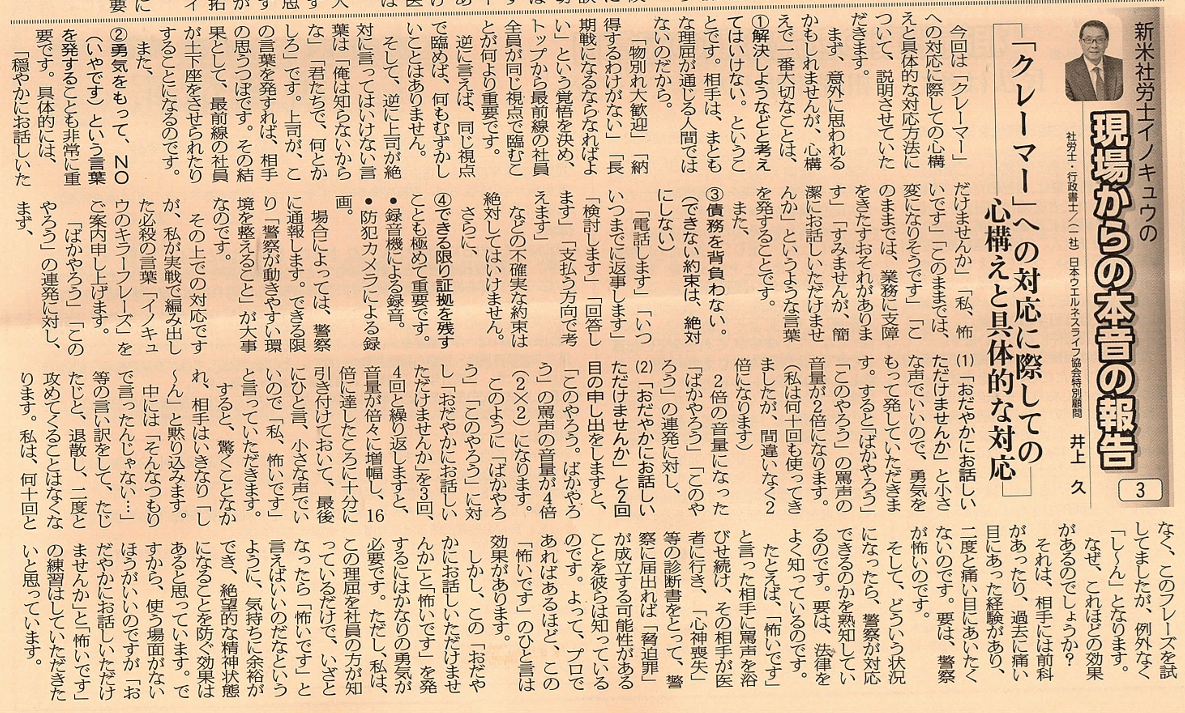
2024年6月10日(月)掲載分
こんにちは、「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久です。
前回と前々回で、私が保険会社勤務43年間の最後の4年間、在籍した損保ジャパンの本社お客さま相談室の話と、まともな苦情ではなく、別の目的をもって、苦情の名を借りて、ルール違反の攻撃をしてくる輩(やから)である「クレーマー・ヘビークレーマー」の使う手法までの説明をさせていただきました。
今回は、対応に際しての心構えと具体的な対応方法について、説明させていただきます。
まず、意外に思われかもしれませんが、心構えで一番大切なことは
① 解決しようなどと考えてはいけない。
ということです。
相手は、まともな理屈が通じる人間ではないのだから。
・物別れ大歓迎。
・納得する訳がない。
・長期戦になるならなればよい。
という覚悟を決め、
トップから最前線の社員全員が同じ視点で臨むことが何より重要です。
逆に言えば、同じ視点で臨めば、何もむずかしいことはありません。
そして、逆に上司が絶対に言ってはいけない言葉は
「俺は知らないからな。」「君たちで、何とかしろ。」です。
上司が、この言葉を発すれば、相手の思う壺です。
その結果として、最前線の社員が土下座をさせられたりすることになるのです。
また、
② 勇気をもって、NO(いやです。)という言葉を発することもひじょうに重要です。
具体的には
・穏やかにお話しいただけませんか。
・私、怖いです。
・このままでは、変になりそうです。
・このままでは、業務に支障をきたすおそれがあります。
・すみませんが、簡潔にお話しいただけませんか。
というような言葉を発することです。
また、
③債務を背負わない。(出来ない約束は、絶対にしない。)
・電話します。
・いついつまでに返事します。
・検討します。
・回答します。
・支払う方向で考えます。
等の不確実な約束は絶対してはいけません。
さらに、
④できる限り、証拠を残すことも極めて重要です。
・録音機による録音。
・防犯カメラによる録画。
場合によっては、警察に通報します。
出来る限り、「警察が動きやすい環境を整えること」が大事なのです。
その上での対応ですが、
私が実戦で編み出した必殺の言葉「イノキュウのキラーフレーズ」をご案内申し上げます。
「ばかやろう」「このやろう」の連発に対し、まず、
① 「おだやかにお話しいただけませんか」と小さな声でいいので、勇気をもって発していただきます。すると、「ばかやろう。」「このやろう」の罵声の音量が2倍になります。(私は何十回も使ってきましたが、間違いなく2倍になります。)
2倍の音量になった「ばかやろう」「このやろう」の連発に対し、
② 「おだやかにお話しいただけませんか」と2回目の申し出をしますと、
「このやろう。ばかやろう。」の罵声の音量が4倍(2×2)になります。
このように「ばかやろう」「このやろう」に対し、「おだやかにお話いただけませんか」を
3回、4回と繰り返しますと、音量が倍々に増幅し、16倍に達したころに
十分に引き付けておいて、最後に一言、ちいさな声でいいので、
「私、怖いです。」と言っていただきます。
すると、驚くことなかれ、相手はいきなりし~ん。と黙り込みます。
中には、「そんなつもりで言ったんじゃない・・・・・」等の言い訳をして、
たじたじと、退散し、二度と攻めてくることはなくなります。
私は、何十回となく、このフレーズを試してましたが、例外なく、し~んとなります。
では、なぜ、これほどの効果があるのでしょうか?
それは、彼ら、彼女らには、前科があったり、過去に痛い目にあった経験があり、
二度と痛い目にあいたくないのです。要は、警察が怖いのです。
そして、どういう状況になったら、警察が対応できるのかを熟知しているのです。
要は、法律をよく知っているのです。
たとえば、「怖いです。」と言った相手に罵声を浴びせ続け、その相手が医者に行き、
「心神喪失」等の診断書をとって、警察に届出れば、「脅迫罪」が成立する可能性があることを彼らは知っているのです。よって、プロであればあるほど、この「怖いです。」の一言は効果があります。
しかし、この「おだやかにお話いただけませんか」と「怖いです」を発するにはかなりの勇気がいります。ただし、私は、この理屈を社員の方が知っているだけで、いざとなったら、「怖いです。」と言えばいいのだなというように、気持ちに余裕ができ、絶望的な精神状態になることを防ぐ効果はあると思っています。ですから、使う場面がない方がいいのですが、できれば、「おだやかにお話いただけませんか」と「怖いです」の練習は、していただきたいと思っています。
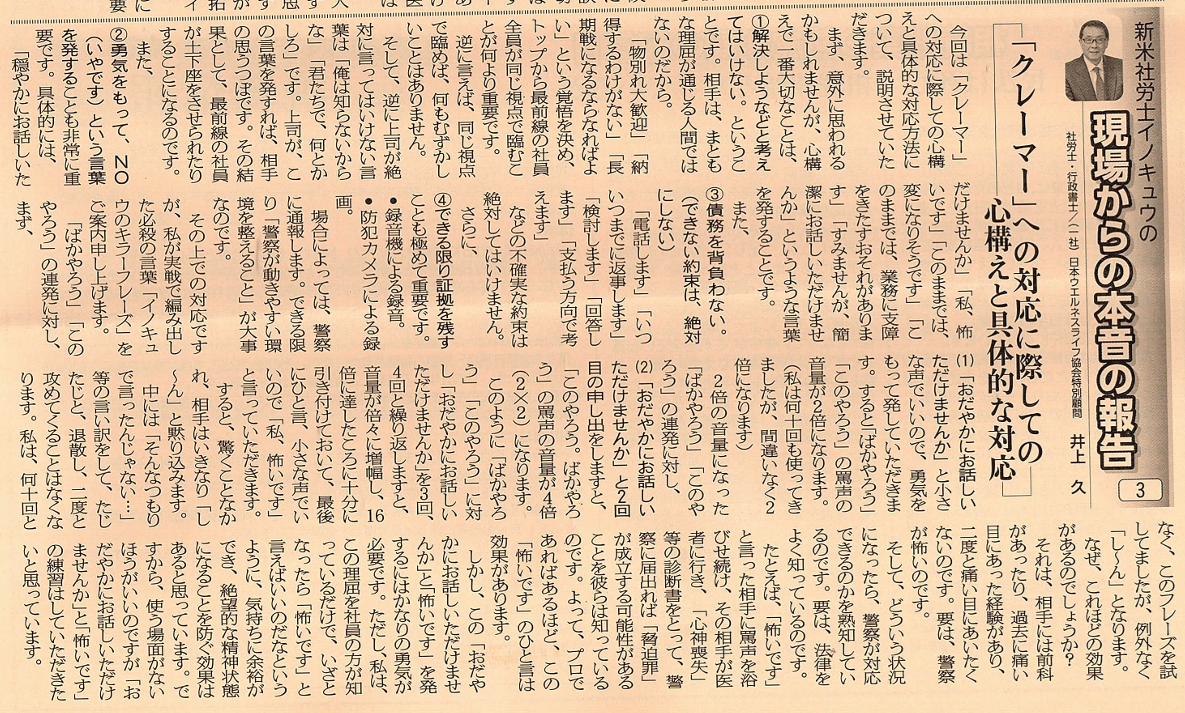
2024年6月10日(月)掲載分 クレーマー・ヘビークレーマー対応③
第4回掲載分(2024年7月8日(月))
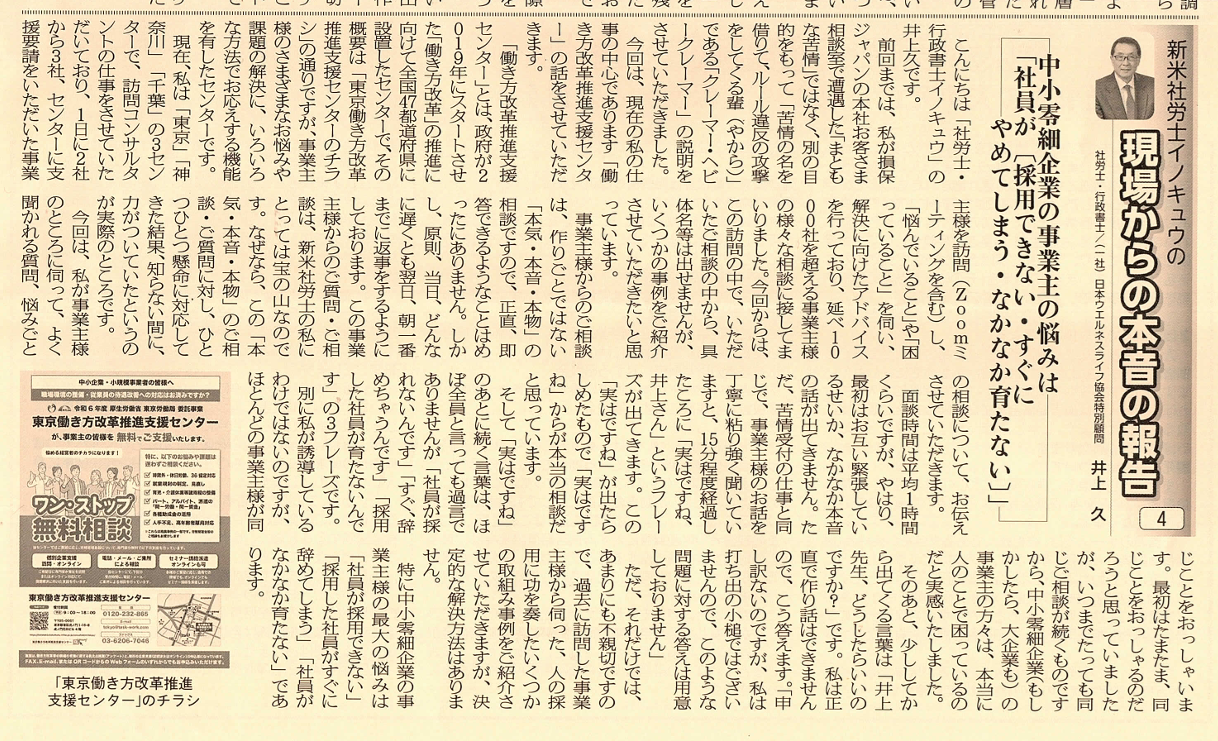
2024年7月8日(月)掲載分
こんにちは「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久です。
前回までは、私が損保ジャパンの本社お客さま相談室で遭遇した「まともな苦情」ではなく、別の目的をもって、「苦情の名を借りて、ルール違反の攻撃をしてくる輩(やから)」である「クレーマー・ヘビークレーマー」の説明をさせていただきました。
今回は、現在の私の仕事の中心であります「働き方改革推進支援センター」の話をさせていただきます。
「働き方改革推進支援センター」とは、政府が2019年にスタートさせた「働き方改革」の推進に向けて全国47都道府県設置したセンターで、その概要は、「東京働き方改革推進支援センターのチラシ」の通りですが、事業主様のさまざまなお悩みや課題の解決に、いろいろな方法でお応えする機能を有したセンターです。
現在、私は、「東京」、「神奈川」、「千葉」、の3センターで、訪問コンサルタントの仕事をさせていただいており、1日に2社から3社、センターに支援要請をいただいた事業主様を訪問(Zoomミーティングを含む)し、「悩んでいること」や「困っていること」を伺い、解決に向けたアドバイスを行っており、延べ1,000社を超える事業主様の様々な相談に接してまいりました。今回からは、この訪問の中で、いただいたご相談の中から、具体名等は出せませんが、いくつかの事例をご紹介させていただきたいと思っています。
事業主様からのご相談は、作り事ではない「本気・本音・本物」の相談ですので、正直、即答できるようなことはめったにありません。しかし、原則、当日、どんなに遅くとも翌日、朝一番までに返事をするようにしております。この事業主様からのご質問・ご相談は、新米社労士の私にとっては宝の山なのです。なぜなら、この「本気・本音・本物」のご相談・ご質問に対し、ひとつひとつ懸命に対応してきた結果、知らない間に、力がついていたというのが実際のところです。
今回は、私が事業主様のところに伺って一番、よく聞かれる質問、悩みごとの相談について、お伝えさせていただきます。
面談時間は平均1時間くらいですが、やはり、最初はお互い緊張しているせいか、なかなか本音の話がでてきません。ただ、苦情受付の仕事と同じで、事業主様のお話を丁寧に粘り強く聞いていますと、だいたい、15分経過したころに「実はですね、井上さん。」というフレーズが出てきます。この「実はですね」がでたらしめたもので、「実はですね」からが本当の相談だと思っています。
そして、「実はですね」のあとに続く言葉は、ほぼ、全員と言っても過言でありませんが、「社員が採れないんです。」「すぐ、辞めちゃうんです。」「採用した社員が育たないんです。」の3フレーズです。別に私が誘導している訳ではないのですが、ほとんどの事業主様が同じことをおっしゃいます。最初はたまたま、同じことをおっしゃるのだろうと思っていましたが、いつまでたっても同じご相談が続くものですから、中小零細企業(もしかしたら、大企業も・・・)の事業主の方々は、本当に人のことで困っているのだ。と実感いたしました。
そして、そのあと、少ししてから出てくる言葉は「井上先生、どうしたらいいのですか?」です。 私は正直で作り話はできませんので、いつも、こう答えます。「申し訳ないのですが、私は打ち出の小槌ではございませんので、このような問題に対する答えは用意しておりません。」
ただ、それだけでは、あまりにも不親切ですので、過去に訪問した事業主様から伺った、人の採用に功を奏したいくつかの取り組み事例をご紹介させていただきますが、決定的な解決方法はありません。
特に中小零細企業の事業主様の最大の悩みは「社員が採用できない。」「採用した社員がすぐに辞めてしまう。」「社員がなかなか育たない。」であります。
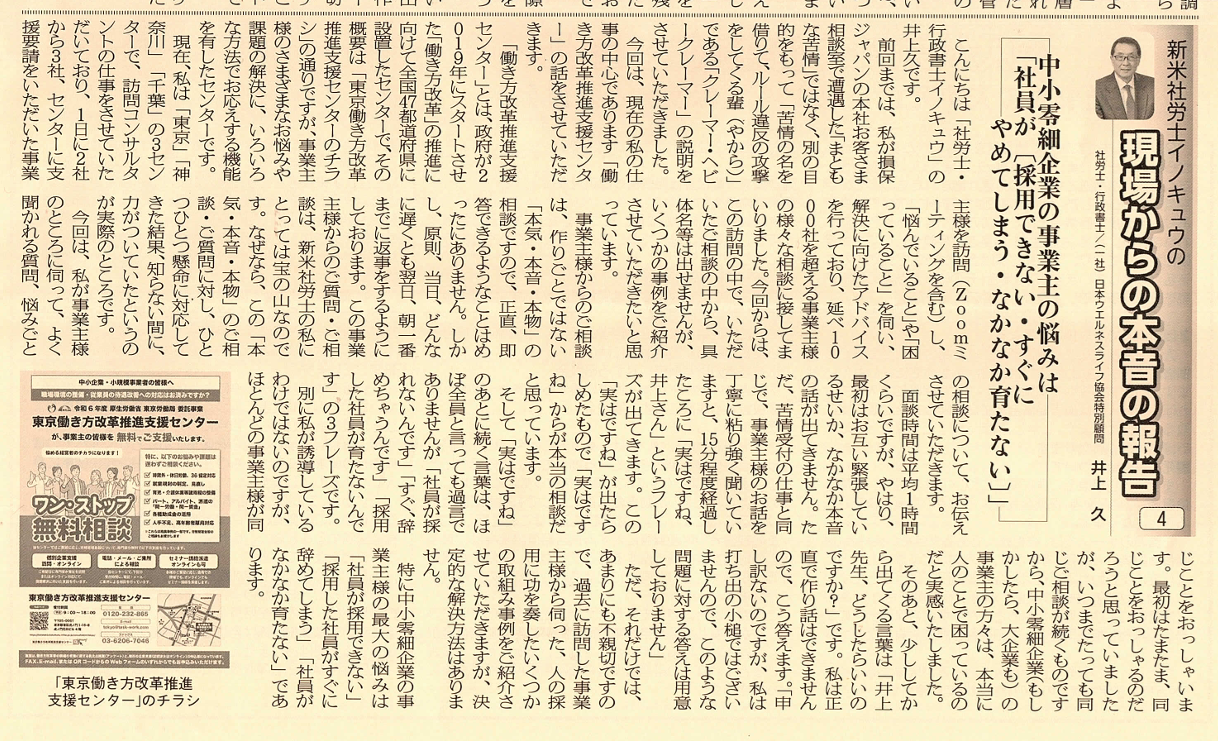
2024年7月8日(月)掲載分 問題社員・クレーマー社員対応①
第5回掲載分(2024年8月12日(月))
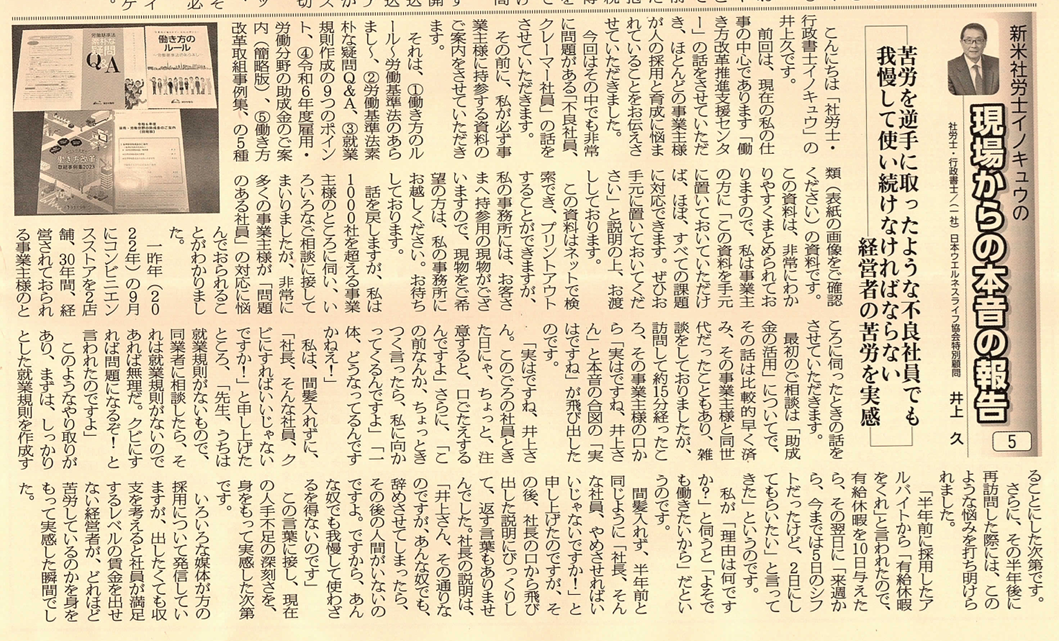
2024年8月12日(月)掲載分
こんにちは「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久です。
前回は、現在の私の仕事の中心であります「働き方改革推進支援センター」の話をさせていただき、ほとんどの事業主様が人の採用と育成に悩まれていることをお伝えさせていただきました。
今回は、その中でも、ひじょうに問題がある「不良社員」「クレーマー社員」の話をさせていただきます。
その前に、私が必ず事業主様に持参する資料のご案内をさせていただきます。
それは、①働き方のルール~労働基準法のあらまし~、②労働基準法素朴な疑問Q&A、③就業規則作成の9つのポイント、④令和6年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)、⑤働き方改革取組事例集、の5種類(表紙の画像をご確認ください)の資料です。この資料は、ひじょうにわかりやすくまとめられておりますので、私は事業主の方に「この資料を手元に置いておいていただけば、ほぼ、すべての課題に対応できます。是非、お手元に置いておいてください。」と説明の上、お渡ししております。
この資料はネットで検索でき、プリントアウトすることができますが、私の事務所には、お客さまへ持参用の現物がございますので、現物をご希望の方は、私の事務所にお越しください。お待ちしております。
話を戻しますが、私は1000社を超える事業主様のところに伺い、いろいろなご相談に接していりましたが、ひじょうに多くの事業主様が、「問題のある社員」の対応に悩んでおられることがわかりました。
一昨年(2022年)の9月にコンビニエンスストアを2店舗、30年間、経営されておられる事業主様のところに伺ったときの話をさせていただきます。
最初のご相談は、「助成金の活用」についてで、その話は比較的、早く済み、その事業主様と同世代だったこともあり、雑談をしておりましたが、訪問して約15分経ったころ、その事業主様の口から、
「実はですね、井上さん」と本音の合図の「実はですね、」が飛び出したのです。
「実はですね、井上さん」「このごろの社員ときた日にゃ、ちょっと、注意すると、口ごたえするんですよ。」さらに、「この前なんか、ちょっときつく言ったら、私に向かってくるんですよ。」「一体、どうなってるんですかねえ!」
私は、間髪入れずに、「社長、そんな社員、くびにすればいいじゃないですか!」
と申し上げたところ、「だけど、先生、うちは就業規則がないもので、同業者に相談したら、「それは就業規則がないのであれば、無理だ、くびにすれば、問題になるぞ!」と言われたのですよ。」 このようなやり取りがあり、まずは、しっかりとした就業規則を作成することにした次第です。
さらに、その半年後に再訪問した際には、このような悩みを打ち明けられました。
「半年前に採用したアルバイトから、「有給休暇をくれ。」と言われたので、有給休暇を10日与えたら、その翌日に、「来週から、今までは5日のシフトだったけど、2日にしてもらいたい。」と言ってきた。」と言うのです。
私が、「理由は何ですか?」と伺うと「よそでも働きたいから」だというのです。
間髪入れず、半年前と同じように「社長、そんな社員、やめさせればいいじゃないですか!」と申し上げたのですが、その後、社長の口から飛び出した説明にびっくりして、返す言葉もありませんでした。社長の説明は、「井上さん、その通りなのですが、あんな奴でも、辞めさせてしまったら、その後の人間がいないのですよ。ですから、あんな奴でも我慢して使わざるを得ないのです。」
この言葉に接し、現在の人手不足の深刻さを、身をもって実感した次第です。
いろいろな媒体が方の採用について発信していますが、出したくても収支を考えると社員が満足するレベルの賃金を出せない経営者が、どれほど、苦労しているのかを身をもって実感した瞬間でした。
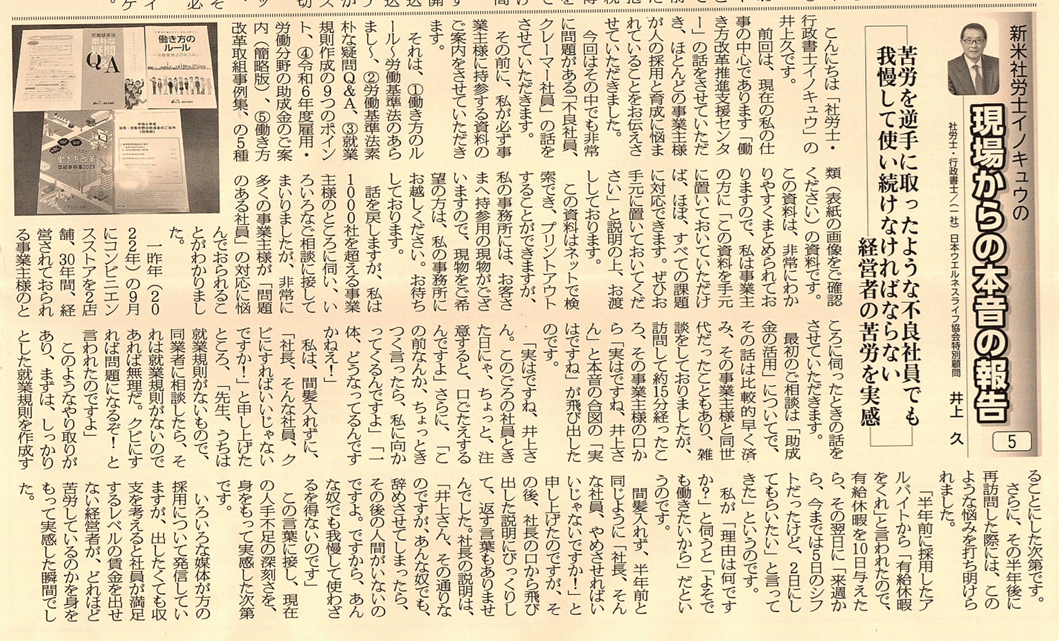
2024年8月12日(月)掲載 問題社員・クレーマー社員対応②
第6回掲載分(2024年9月9日(月))
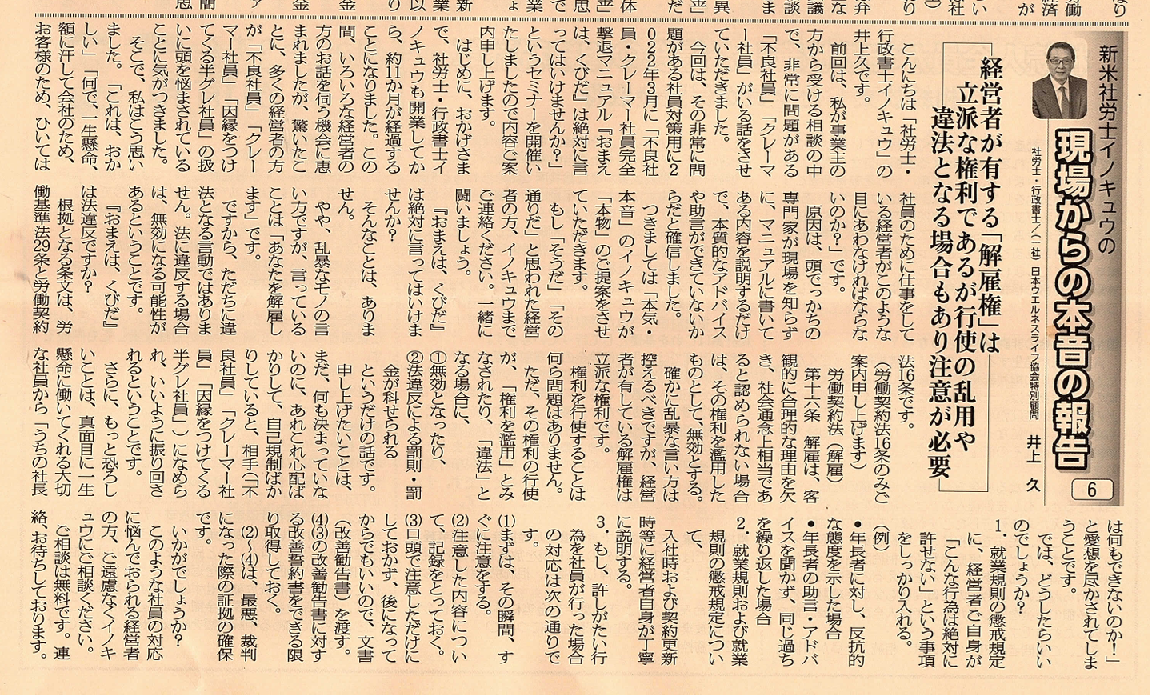
新日本保険新聞連載執筆原稿⑥(2024年9月掲載予定原稿)
こんにちは「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久です。
前回は、私が事業主の方から受ける相談の中で、ひじょうに問題がある「不良社員」「クレーマー社員」がいる話をさせていたました。
今回は、そのひじょうに問題がある社員対策用に2022年3月に「不良社員・クレーマー社員完全撃退マニュアル「おまえは、くびだ。」は絶対に言ってはいけませんか?」というセミナーを開催いたしましたので、その内容ご案内申し上げます。
はじめに
おかげさまで、社労士・行政書士イノキュウも開業してから、約11カ月が経過することになりました。この間、いろいろな経営者の方のお話を伺う機会に恵まれましたが、驚いたことにひじょうに多くの経営者の方が「不良社員」「クレーマー社員」「因縁をつけてくる半ぐれ社員」の扱いに頭を悩まされていることに気がつきました。
そこで、私はこう思いました。「これは、おかしい。」「何で、一生懸命、額に汗して会社のため、お客様のため、ひいては社員のために仕事をしている経営者がこのような目にあわなければならないのか?」です。
原因は、頭でっかちの専門家が現場を知らずに、マニュアルに書いてある内容を説明するだけで、本質的なアドバイスや助言ができていないからだと確信いたしました。
つきましては、「本気・本音」のイノキュウが「本物」のご提案をさせていただきます。もし、「そうだ。」「その通りだ。」と思われた経営者の方、イノキュウまでご連絡ください。
いっしょに闘いましょう。
「おまえは、くびだ。」は絶対に言ってはいけませんか?
そんなことは、ありません。
「おまえは、くびだ。」はやや、乱暴な物の言い方ですが、
言っていることは、⇒「あなたを解雇します。」です。
ですから、ただちに違法となる言動ではありません。
法に違反する場合は、無効になる可能性があるということです。
「おまえは、くびだ。」は法違反ですか?
根拠となる条文は、労働基準法29条と労働契約法16条です。
(労働契約法16条のみご案内申し上げます。)
労働契約法(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
確かに乱暴な言い方は控えるべきですが、経営者が有している解雇権は立派な権利です。
権利を行使することは、何ら問題はありません。
ただ、その権利の行使が、「権利を濫用」とみなされたり、「違法」となる場合に
①無効となったり、
②法違反による罰則・罰金が科せられるというだけの話です。
申し上げたいことは、まだ、何も決まっていないのに、あれこれ心配ばかりして、自己規制ばかりしていると、相手(「不良社員」「クレーマー社員」「因縁をつけてくる半ぐれ社員」)になめられ、いいように振り回されるということです。
さらに、もっと恐ろしいことは、真面目に一生懸命に働いてくれる大切な社員から、
「な~んだ、所詮、うちの社長は何もでないのか!」と愛想を尽かされてしまうことです。
では、どうしたらいいのでしょうか?
①就業規則の懲戒規定に、経営者ご自身が「こんな行為は絶対に許せない。」という事項をしっかり入れる。
(例)
・年長者に対し、反抗的な態度を示した場合
・年長者の助言・アドバイスを聞かず、同じ過ちを繰り返した場合
②就業規則および就業規則の懲戒規定について、
入社時および契約更新時等に経営者自身が丁寧に説明する。
③もし、許しがたい行為を社員が行った場合の対応は次の通りです。
1.まずは、その瞬間、すぐに注意をする。
2.注意した内容について、記録をとっておく。
3.口頭で注意しただけにしておかないで、後になってからでもいいので、
文書(改善勧告書)を渡す。
4.3の改善勧告書に対する改善誓約書をできる限り取得しておく。
2~4は、最悪、裁判になった際の証拠の確保です。
いかがでしょうか?
このような社員の対応に悩んでおられる経営者の方、ご遠慮なくイノキュウにご相談ください。ご相談は無料です。連絡、お待ちしております。
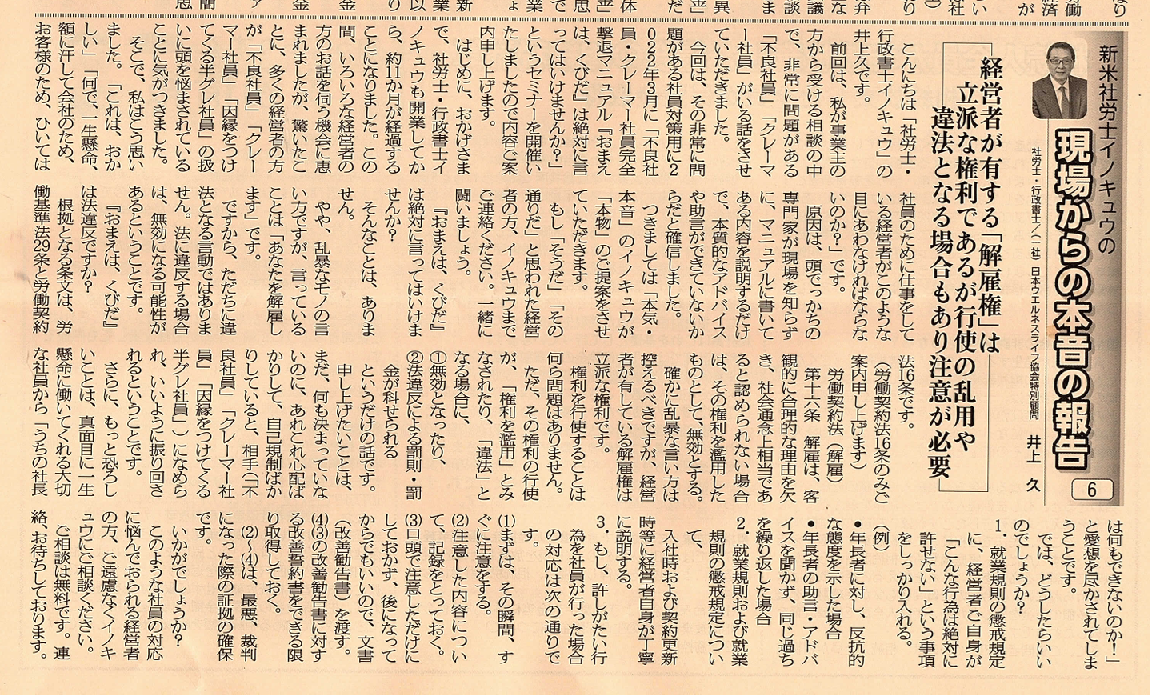
2024年9月9日(月)第6回掲載分 問題社員・クレーマー社員対応③
第7回掲載分(2024年10月14日(月))
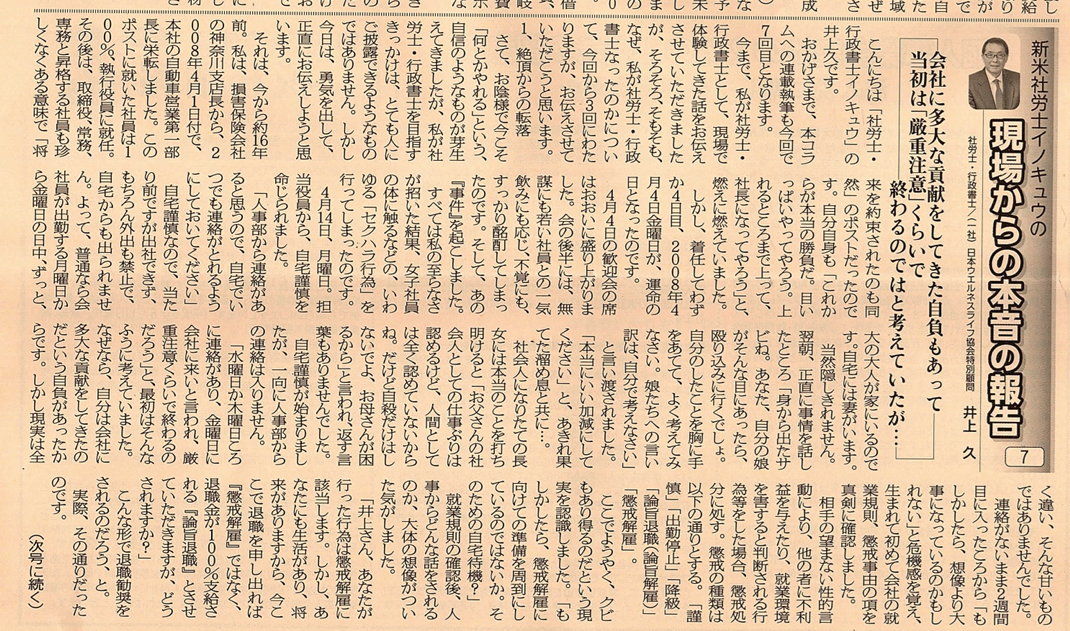
こんにちは「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久です。
おかげさまで、本コラムへの連載執筆も今回で7回目となります。
今まで、私が社労士・行政書士として、現場で体験してきた話をお伝えさせていただきましたが、そろそろ、そもそも、なぜ、私が社労士・行政書士なったのかについて、今回から3回にわたりますが、お伝えさせていただこうと思います。
1.絶頂からの転落
さて、お陰様で今こそ「何とかやれる」という、自信..のようなものが芽生えてきましたが、私が社労士・行政書士を目指すきっかけは、とても人にご披露できるようなものではありませんでした。しかし今日は、勇気を出して、正直にお伝えしようと思います。
それは、今から約16年前。私は、損害保険会社の神奈川支店長から、2008年4月1日付で、本社の自動車営業第一部長に栄転しました。当時はまだ、運転手付きの車や、数千万円の高級ゴルフクラブ会員権の付与など、給与外の待遇も非常によかった時代で、正に、人生の絶頂期にありました。おまけに、このポストに就いた社員は100%、執行役員に就任。その後は、取締役、常務、専務と昇格する社員も珍しくなく、ある意味で、「将来を約束されたのも同然」のポストだったのです。
周囲の社員や取引先からは、「井上大部長!」とか、「よっ、将来の社長!」とか、ありとあらゆる賛辞や煽ての言葉が降り注ぎました。自分自身も「これからが本当の勝負だ。目いっぱい、やってやろう。登れるところまで登って、社長になってやろう」と、燃えに燃えていました。
しかし、着任してわずか4日目、2008年4月4日金曜日が、運命の日となったのです。
前述の通り、社員からも持ち上げられた私は、すっかりいい気になっていたのでしょう。
4月4日の歓迎会の席はおおいに盛り上がりました。会の後半には、無謀にも若い社員との一気飲みにも応じ、不覚にも、すっかり酩酊してしまったのです。そして、あの“事件”を起こしました。
すべては私の至らなさが招いた結果です。女子社員の体に触るなどの、いわゆる「セクハラ行為」を行ってしまったのです(お恥ずかしいことに泥酔しすぎて記憶がありませんが、目撃者が多数おりました)。
4月14日、月曜日。担当役員から、自宅謹慎を命じられました。
「いずれ、人事部から連絡があると思うので、自宅でいつでも連絡がとれるようにしておいてください」自宅謹慎なので、当たり前ですが出社できず、勿論、外出も禁止で、自宅からも出られません。よって、普通なら会社員が出勤する月曜日から金曜日の日中、ず~っと、大の大人が家にいるのです。自宅には、妻がいます。当然隠しきれません。翌朝、正直に事情を話したところ、
「身から出たサビね。あなた、自分の娘がそんな目にあったら、殴り込みにいくでしょ。自分のしたことを胸に手をあてて、よく考えてみなさい。娘たちへの言い訳は、自分で考えなさい」
と言い渡されました。「本当にもう、いい加減にしてください」と、あきれ果てた溜め息と共に……。
社会人になりたての長女には本当のことを打ち分けると、
「お父さんの社会人としての仕事ぶりは認めるけど、人間としては全く、認めていないからね。だけど、自殺だけはしないでよ、お母さんが困るから」と言われ、返す言葉もありませんでした。
こうして自宅謹慎が始まりましたが、一向に人事部からの連絡は入りません。
「水曜日か木曜日ころに連絡があり、金曜日に会社に来いといわれ、厳重注意くらいで終わるのだろう」と、最初はそんな風に考えていました。なぜなら、自分は会社に多大な貢献をしてきたのだという自負があったからです。
しかし現実は全く、そんな甘いものではありませんでした。
連絡がないまま1週間が経過し、2週間目に入ったころから、「もしかしたら、想像より大事になっているのかもしれない」と危機感を覚え始めます。生まれて初めて会社の就業規則――懲戒事由の項――を真剣に確認しました。
相手の望まない性的言動により、他の者に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行為等をした場合、懲戒処分に処す。懲戒の種類は以下の通りとする。「謹慎」「出勤停止」「降級」「論旨退職(論旨解雇)」「懲戒解雇」……。
懲戒解雇。ここでようやく、クビもありうるのだという現実を認識しました。
「……もしかしたら、懲戒解雇に向けての準備を周到にしているのではないか。そのための自宅待機?」
就業規則の確認後、人事からどんな話をされるのか、大体の想像がついた気がしました。
「井上さん、あなたが行った行為は懲戒解雇に該当します。しかし、あなたにも生活があり、将来がありますから、今ここで退職を申し出れば、『懲戒解雇』ではなく、退職金が100%支給される『論旨退職』とさせて頂きますが、どうされますか?」
こんな形で退職勧奨をされるのだろう、と(実際、その通りだったのです)。
(次号に続く)
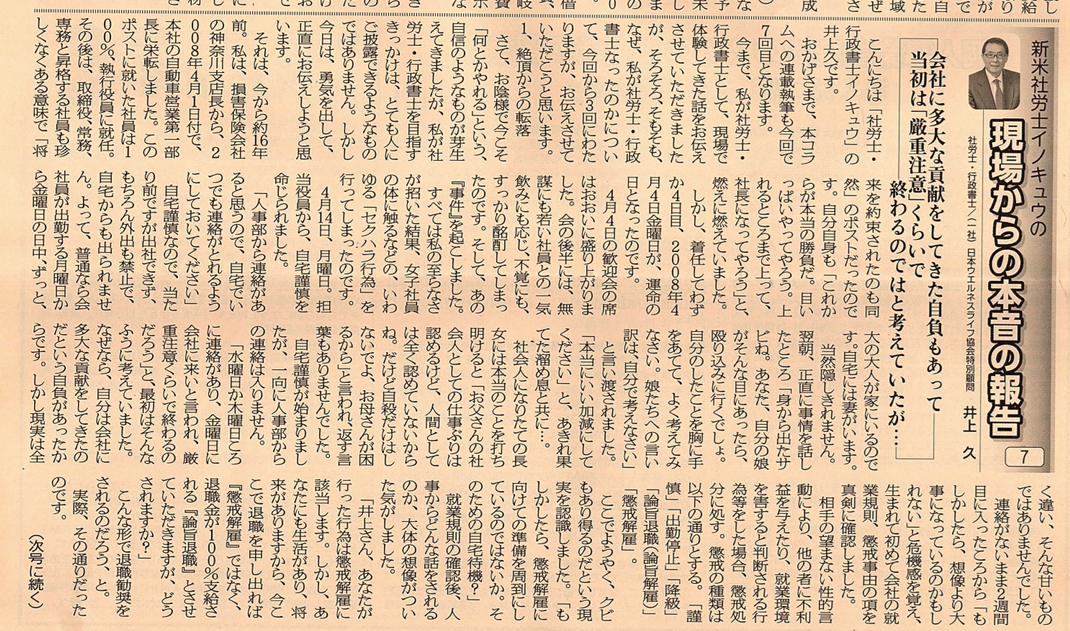
2024年10月14日(月)第7回掲載分 セキララ体験談「どん底からの生還」①
第8回掲載分(2024年11月11日(月))
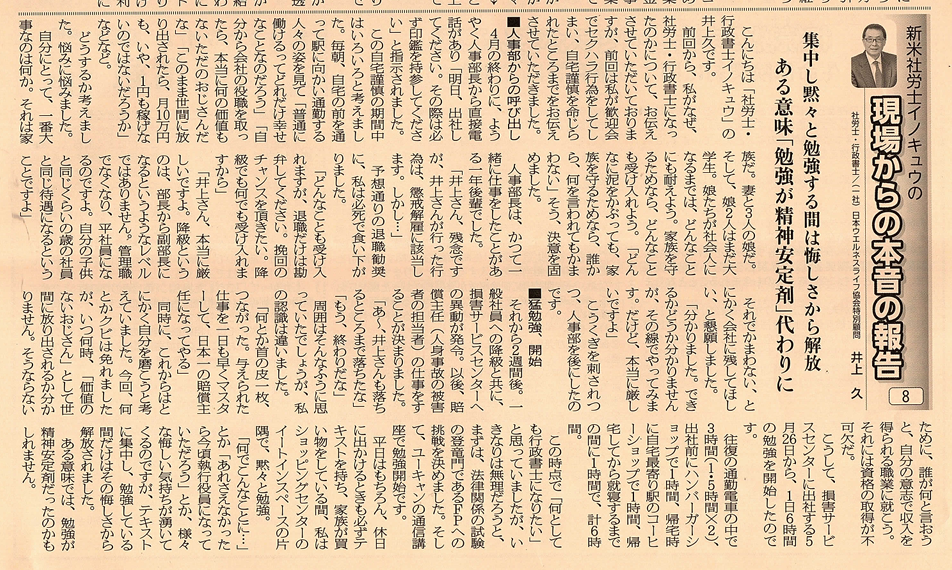
こんにちは「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久です。
前回から、私が何故、社労士・行政書士になったのかについて、お伝えさせていただいておりますが、前回は、私が歓迎会でセクハラ行為をしてしまい、自宅謹慎を命じられたところまでをお伝えさせていただきました。
2.人事部からの呼び出し
4月の終わりに、ようやく人事部長から直接電話があり、「明日、出社してください。その際は必ず印鑑を持参してください」と指示されました。
この自宅謹慎の期間中は 、色々と考えました。毎朝、自宅の前を通って駅に向か う 、通 勤する人々の姿を見ては、
「あ~、普通に働けるってどれだけ幸せなことなのだろう」
「自分から会社の役職を取ったら、本当に何の価値もないただのおじさんだな」
「このまま世間に放り出されたら、月10万円も、いや、1円も稼げないのではないだろうか」等々。
人事部に出頭してどうするか、考えました。悩みに悩みました。
自分にとって、一番大事なのは何か。それは家族だ。妻と3人の娘だ。そして、娘2人はまだ大学生。娘たちが社会人になるまでは、どんなことにも耐えよう。家族を守るためなら、どんなことも受け入れよう。
「どんなに泥を被っても、家族を守るためなら、誰から、何を言われてもかまわない」
そう、決意を固めました。
人事部長は、かつて一緒に仕事をしたことがある一年後輩でした。
「井上さん、残念ですが、井上さんが行った行為は、懲戒解雇に該当します。しかし……」
予想通りの退職勧奨に、私は必死で食い下がりました。
「どんなことも受け入れますが、退職だけは勘弁してください。挽回のチャンスを頂きたい。降級でもなんでも受け入れますから」
「井上さん、本当に厳しいですよ。降級というのは、部長から副部長になるというようなレベルではありません。管理職でなくなり、平社員になるのですよ。自分の子供と同じくらいの歳の社員と同じ待遇になるということですよ」
それで構わない、とにかく会社に残してほしい、と懇願しました。
「……分かりました。できるかどうか分かりませんが、その線でやってみます。だけど、本当に厳しいですよ」こう釘を刺されつつ、人事部を後にしたのです。
3.猛勉強、開始
それから2週間後。一般社員への降級と共に、損害サービスセンターへの異動が発令。以後、賠償主任(人身事故の被害者の担当者)の仕事をすることが決まりました。
「あ~、井上さんも落ちるところまで落ちたな」「もう、終わりだな」
周囲はそんな風に思っていたでしょうが、私の認識は違いました。
「何とか首の皮一枚、繋がった。与えられた仕事を一
日も早くマスターして、日本一の賠償主任になってやる」
同時に、これからはとにかく自分を磨こうと考えていました。今回、なんとかクビは免れましたが、いつ何時、「価値のないおじさん」として世間に放り出されるか分かりません。そうならないために、誰が何と言おうと、自分の意志で収入を得られる職業に就こう。そ
れには資格の取得が不可欠だ。
こうして、損害サービスセンターに出社する 5月26日から、1日6時間の勉強を開始したのです。
往復の通勤電車の中で3時間(1.5時間×2)、出社前にハンバーガーショップで1時間、帰宅時に自宅最寄り駅のコーヒーショップで1時間、帰宅してから就寝するまでの間に1時間で、計6時間。
この時点で、「何としても行政書士になりたい」と思っていましたが、いきなりは無理だろうと、まずは、法律関係の試験の登竜門であるFPへの挑戦を決めました。そして、ユーキャンの通信講座で勉強開始です。
平日は勿論、休日に出かけるときも必ずテキストを持ち、家族が買い物をしている間、私はショッピングセンターのイートインスペースの片隅で、黙々と勉強。
「何でこんなことに……」とか、「あれさえなかったら今頃執行役員になっていただろう」とか、様々な悔しい気持ちが湧いてくるのですが、テキストに集中し、勉強している間だけはその悔しさから解放されました。ある意味では、勉強が精神安定剤だったのかもしれません。
(次回に続く)
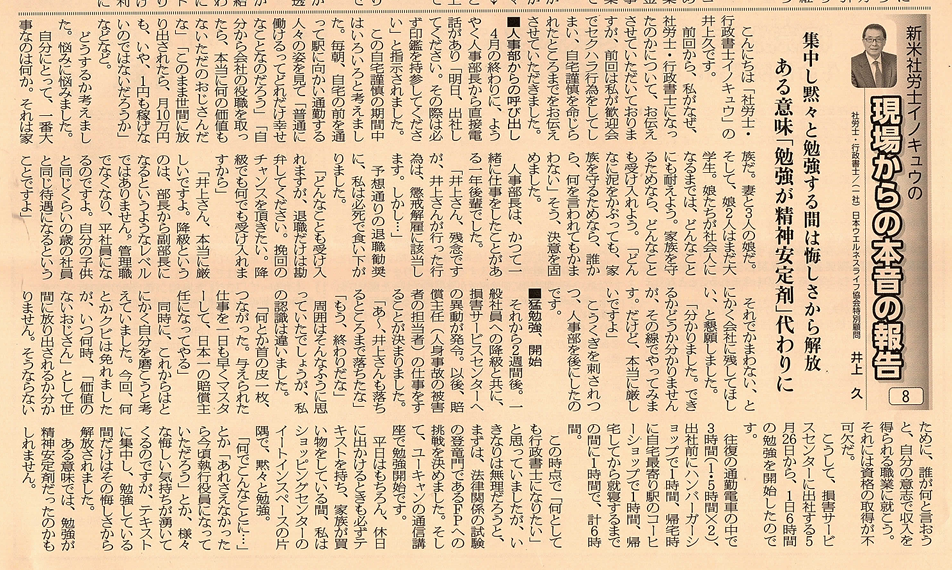
2024年11月11日(月)掲載 セキララ体験談「どん底からの生還」②
第9回掲載分(2024年12月9日(月))
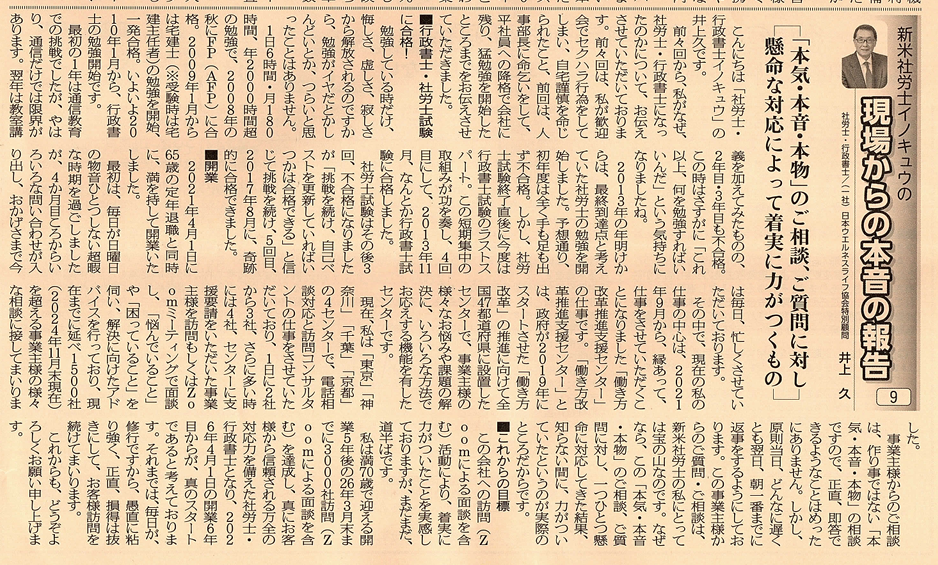
2024年12月9日(月)第9回掲載分
こんにちは「社労士・行政書士イノキュウ」の井上久です。
前々回から、私が何故、社労士・行政書士になったのかについて、お伝えさせていただきます。前々回は、私が歓迎会でセクハラ行為をしてしまい、自宅謹慎を命じられたこと、前回は、人事部長に命乞いをして、平社員への降格で会社に残り、猛勉強を開始したところまでをお伝えさせていただきました。
(3)行政書士・社労士試験に合格!
勉強している時だけ、悔しさ、虚しさ、寂しさから解放されるのですから、勉強がイヤだとかしんどいとか、辛いと思ったことはありません。
1日6時間・月180時間、年2,000時間超の勉強で、2008年の秋に FP(AFP)に合格。2009年1月からは宅建士(※受験時は宅建主任者)の勉強を開始、一発合格。いよいよ2010年1月から、行政書士の勉強開始です。
最初の1年は通信教育での挑戦でしたが、やはり、通信だけでは限界があります。翌年は教室講義を加えてみたものの、2年目・3年目も不合格。この時はさすがに、「これ以上、何を勉強すればいいんだ」という気持ちになりましたね。
2013年の年明けからは、最終到達点と考えていた社労士の勉強を開始しました。予想通り? 初年度は全く手も足も出ず不合格。しかし、社労士試験終了直後に、今度は行政書士試験のラストスパート。
この短期集中の取り組みが功を奏し、4回目にして、2013年11月、なんとか行政書士試験に合格しました。
社労士試験はその後3回、不合格になりましたが、「挑戦を続け、自己ベストを更新していれば、いずれ、いつかは合格できる」と信じて挑戦を続け、5回目、2017年8月に、奇跡的に合格できました。
(4)定年退職と同時に開業、そして、今後も目標
2021年4月1日に65歳の定年退職と同時に開業いたしました。
最初は、毎日が日曜日の物音ひとつしない超暇な軸を過ごしましたが、4ヵ月目頃から、
いろいろな仕事が入り出し、おかげさまで、今は、毎日、忙しくさせていただいております。
その中で、現在の私の仕事の中心は、2021年9月から、縁あって、その仕事をさせていただくことになりました「働き方改革推進支援センター」の仕事です。「働き方改革推進支援センター」とは、政府が2019年にスタートさせた「働き方改革」の推進に向けて全国47都道府県設置したセンターで、事業主様のさまざまなお悩みや課題の解決に、いろいろな方法でお応えする機能を有したセンターです。
現在、私は、「東京」、「神奈川」、「千葉」、「京都」の4センターで、電話相談対応と訪問コンサルタントの仕事をさせていただいており、1日に2社から3社、さらに多い時には4社、センターに支援要請をいただいた事業主様を訪問もしくはZoomミーティングで面談し、「悩んでいること」や「困っていること」を伺い、解決に向けたアドバイスを行っており、現在までに延べ1,250社(2024年8月末現在)を超える事業主様の様々な相談に接してまいりました。
事業主様からのご相談は、作り事ではない「本気・本音・本物」の相談ですので、正直、即答できるようなことはめったにありません。しかし、原則、当日、どんなに遅くとも翌日、朝一番までに返事をするようにしております。この事業主様からのご質問・ご相談は、新米社労士の私にとっては宝の山なのです。なぜなら、この「本気・本音・本物」のご相談・ご質問に対し、ひとつひとつ懸命に対応してきた結果、知らない間に、力がついていたというのが実際のところだからです。
この会社への訪問(Z00mによる面談を含む)活動により、着実に力がついたことを実感しておりますが、まだまだ、道半ばです。
私は満70才で迎える開業5年後の26年3月末までに3,000社訪問(Zoomによる面談を含む)を達成し、真にお客さまから信頼される万全の対応力を有した社労士・行政書士となり、2026年4月1日の開業6年目からが、真のスタートであると考えております。それまでは、毎日が、修行ですから、愚直に粘り強く、正直、損得は抜きにして、お客さま訪問を続けてまいります。これからも、よろしくお願い申し上げます。
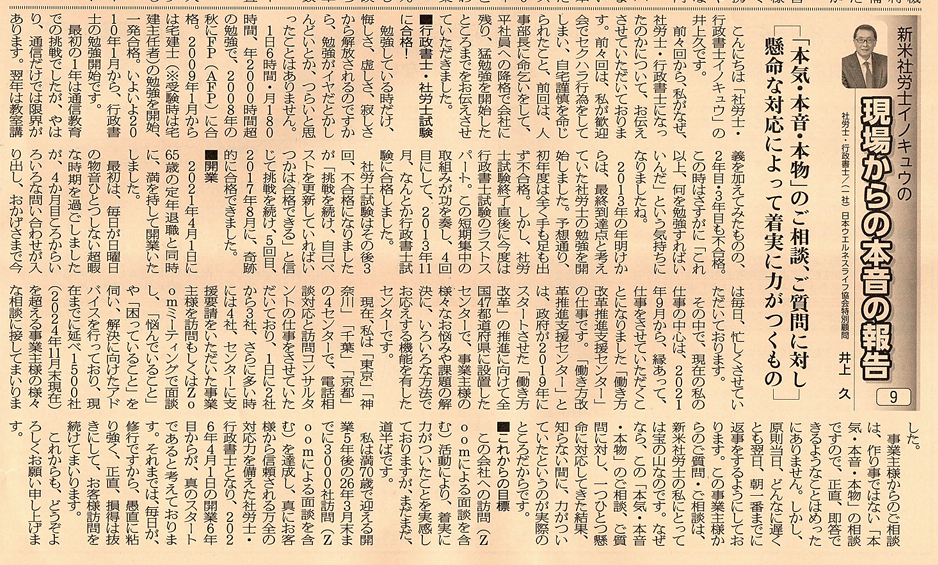
2024年12月9日(月)第9回掲載分 セキララ体験談「どん底からの生還」②
第10回掲載分(2025年1月13日(月)掲載分
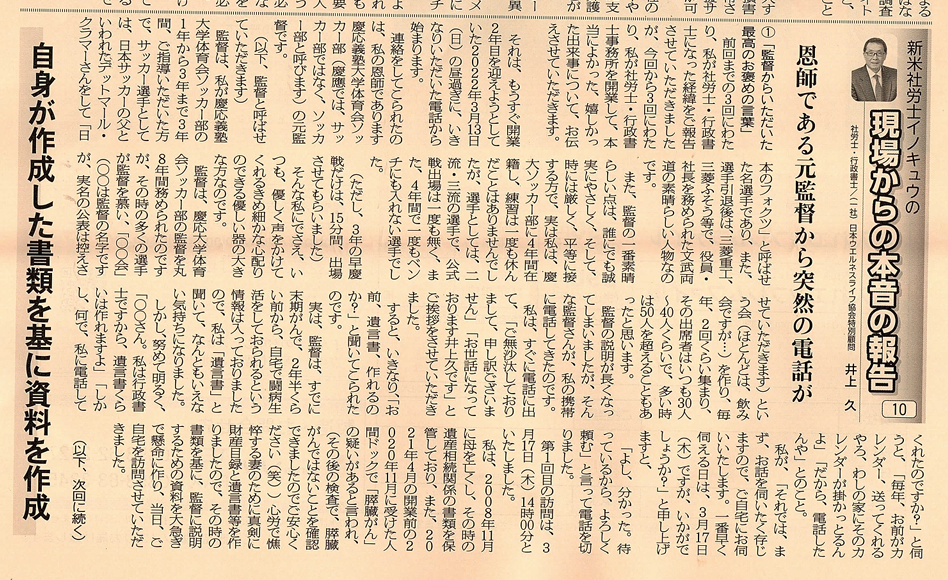
2025年1月13日(月)掲載分 新米社労士イノキュウの現場からの本音の報告(10)
新日本保険新聞 寄稿原稿2025年1月分
① 「監督からいただいた最高のお褒めの言葉」
前回までの3回にわたり、私が社労士・行政書士になった経緯をご報告させていただきましたが、
今回から3回にわたり、私が社労士・行政書士事務所を開業して、本当によかった、嬉しかった出来事について、お伝えさせていただきます。
それは、もうすぐ開業2年目を迎えようとしていた2022年3月13日(日)の昼過ぎに、いきなりいただいた電話からはじまります。連絡をしてこられたのは、私の恩師であります慶応義塾大学体育会ソッカー部の元監督です。(以下、監督と呼ばせていただきます。)
監督は、私が慶応義塾大学体育会ソッカー部(慶應では、サッカー部ではなく、ソッカー部と呼びます。)の1年から3年まで3年間、ご指導いただいた方で、サッカー選手としては、日本サッカーの父といわれたデッドマルクラーマーさんをして「日本のフォクツ」と呼ばせた名選手であり、また、選手引退後は、三菱重工、三菱ふそう、等で、役員・社長を務められた文武両道の素晴らしい人物なのです。
また、監督の一番素晴らしい点は、誰にでも誠実にやさしく、そして、時には厳しく、平等に接する方で、実は私は、慶大ソッカー部に4年間在籍し、練習は1度も休んだことはありませんでしたが、
選手としては、二流・三流の選手で、公式戦出場は1度も無く、また、4年間で一度もベンチにも入れない選手でした。(ただし、3年の早慶戦だけは、15分間、出場させてもらいました。) そんな私にでさえ、いつも、優しく声をかけてくれるきめ細かな心配りのできる優しい器の大きな方なのです。
監督は、慶応大学体育会ソッカー部の監督を丸8年間務められたのですが、その時の多くの選手が
監督を慕い、「○○会」(○○は監督の名字ですが、実名の公表は控えさせていただきます。)という会(ほとんどは、飲み会ですが・・)を作り、毎年、2回くらい集まり、その出席者はいつも30人~40人くらいで、多い時は50人を超えることもあったと思います。
監督の説明が長くなってしまいましたが、そんな監督さんが、私の携帯に電話してきたのです。
私は、すぐに電話に出て、「ご無沙汰しておりまして、申し訳ございません。」「お世話になっております井上久です。」とご挨拶をさせていただきました。すると、いきなり、「お前、遺言書、作れるのか?」と聞いてくるのです。実は、監督は、すでに末期がんで、2年半くらい前から、自宅で闘病生活をしておられるという情報は入っておりましたので、私は、「遺言書」と聞いて、なんともいえない気持ちになりました。しかし、努めて明るく、「○○さん。私は行政書士ですから、遺言書くらいは作れますよ。」「しかし、何で、私に電話してくれたのですか?」と伺うと、「毎年、お前がカレンダー、送ってくれるやろ、わしの家にそのカレンダーが掛かっとるんよ。」「だから、電話したんや」とのこと、
わたしは、こう申し上げました「それでは、まず、お話を伺いたく存じますので、ご自宅に伺いいたします。一番、早く、伺える日は、3月17日(木)ですが、いかがでしょうか?」と申し上げますと、
「よし、わかった。待っているから、よろしく頼む。」と言って電話を切りました。
第1回目の訪問は、3月17日(木)14時00分といたしました。
私は、2008年11月に母を亡くし、その時の遺産相続関係の書類を保管しており、
また、2021年4月の開業前の2020年11月に受けた人間ドックで「膵臓がん」の疑いがあると言われ、(その後の検査で、膵臓がんではないことを確認できましたのでご安心ください(笑))心労で憔悴する妻のために真剣に財産目録と遺言書等を作りましたので、その時の書類を基に、監督に説明するための資料を大急ぎで懸命に作り、当日、ご自宅を訪問させていただきました。
(以下、次回に続く)
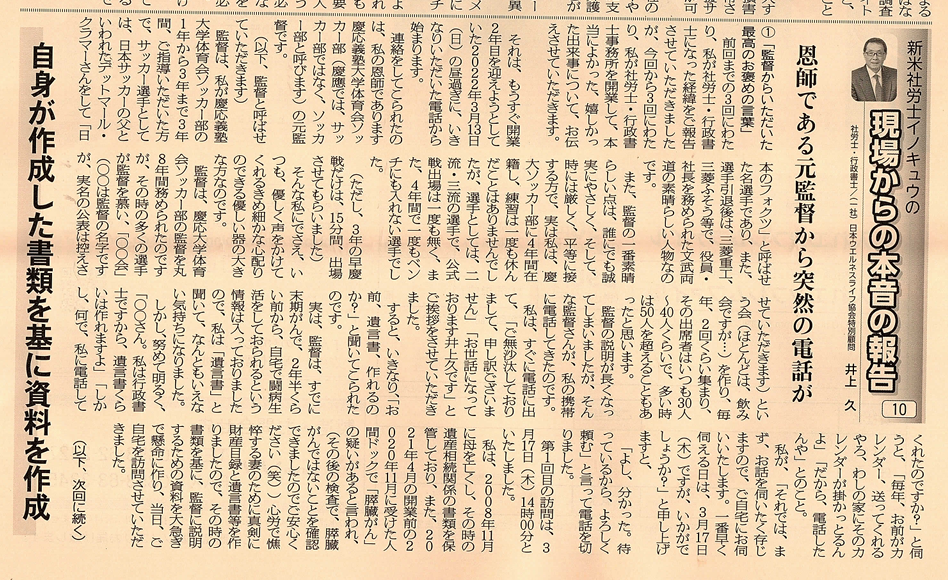
2025年1月13日(月)掲載分 セキララ体験談「恩師からの最高のほめ言葉」①
第11回掲載分(2025年2月10日(月)掲載分)
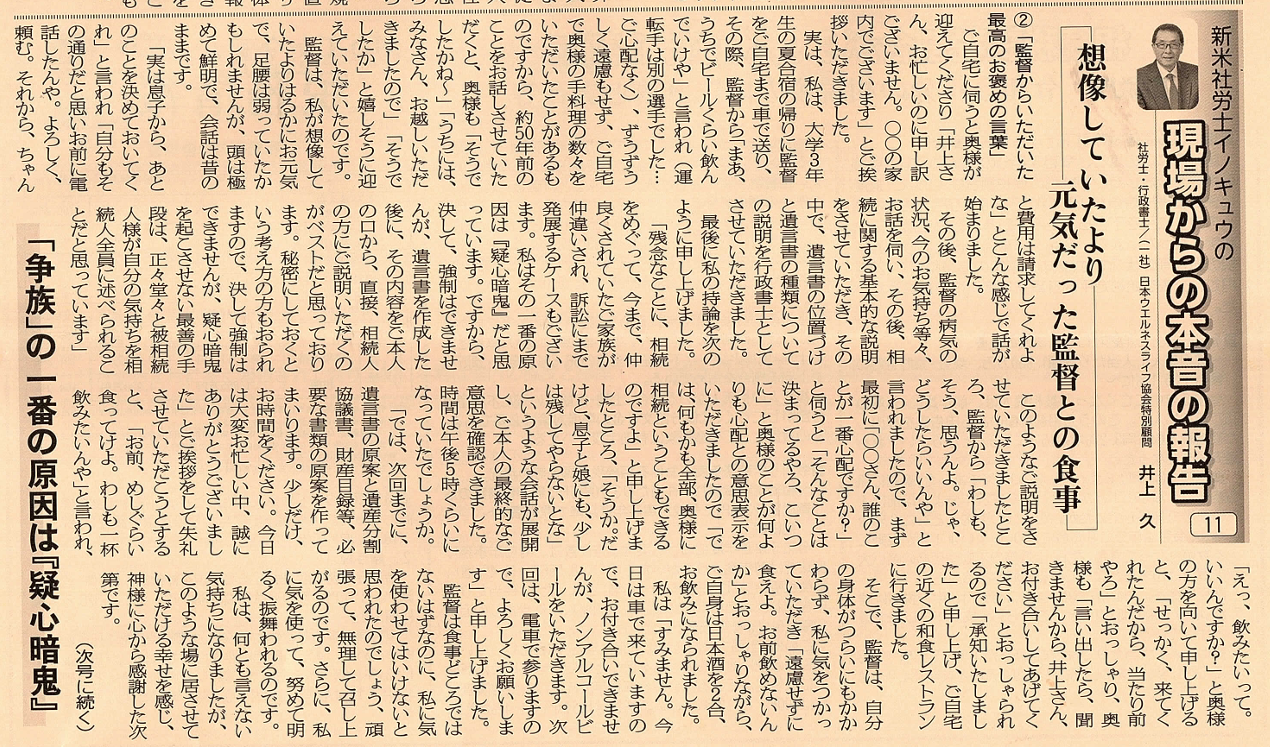
2025年2月10日(月)第11回掲載
②「監督からいただいた最高のお褒めの言葉」(2025年2月掲載予定分)
ご自宅にうかがうと奥様がお迎えいただき、「井上さん、お忙しいのに申し訳ございません。」「○○の家内でございます。」とご挨拶いただきました。
実は、私は、大学3年生の夏合宿の帰りに監督をご自宅まで車で送り、その際、監督から「まあ、うちでビールくらい飲んでいけや」と言われ(運転手は別の選手でした・・・ご心配なく)、ずうずうしく、遠慮もせず、ご自宅で奥様の手料理の数々をいただいたことがあるものですから、約50年前のことをお話させていただくと奥様も「そうでしたかね~」「うちには、みなさん、お越ししいただきましたので」「そうでしたか」と嬉しそうにお迎えいただいたのです。
監督は、私が想像していたよりはるかにお元気で、足腰は弱っていたかもしれませんが、頭は極めて鮮明で、会話は昔のままです。
「実は、息子から、あとのことを決めておいてくれ。」と言われ、「自分もその通りだと思い、お前に電話したんや」「よろしく、頼む」「それから、ちゃんと費用は請求してくれよな」とこんな感じで話が始まりました。
その後、監督の病気の状況、今のお気持ち、等々、お話を伺い、その後、相続に関する基本的な説明をさせていただき、その中で、遺言書の位置づけと遺言書の種類についての説明を行政書士としてさせていただきました。
最後に、私の持論を次のように申し上げました。
「残念なことに、相続をめぐって、いままで、仲良くされていたご家族が仲たがいされ、中には、訴訟にまで発展するケースもございます。私はその一番の原因は「疑心暗鬼」だと思っています。」
「ですから、決して、強制はできませんが、遺言書を作成した後に、その内容をご本人の口から、直接、相続人の方にご説明いただくのがベストだと思っております。「秘密にしておく。」という考え方の方もおられますので、決して強制はできませんが、疑心暗鬼を起こさせない最善の手段は、正々堂々と被相続人様が自分の気持ちを相続人全員に述べられることだと思っています。」
このようなご説明をさせていただきましたところ、監督から
「わしも、そう、思うんよ。」「じゃ、どうしたらいいんや」と言われましたので、
まず最初に、「○○さん、誰のことが一番、心配ですか?」と伺うと
「そんなことは決まってるやろ、こいつに」と奥様のことが何よりも心配との意思表示をいただきましたので、「では、何かも全部、奥様に相続ということもできるのですよ。」と申し上げましたところ、
「そうか、だけど、息子と娘にも、少しは残してやらないとな。」というような会話が展開し、ご本人の最終的なご意思を確認できました。
もう、時間は、午後5時くらいになっていたでしょうか、
「では、次回までに、遺言書の原案と遺産分割協議書、財産目録等、必要な書類の原案を作ってまいります。少しだけ、お時間をください。今日は、たいへん、お忙しい中、誠にありがとうございました。」
とご挨拶をして、失礼させていただこうとすると、
「お前、めしぐらいくってけよ。」「わしも一杯飲みたいんや。」と言われ、
「えっ、飲みたいって、いいんですか?」と奥様の方を向いて申し上げると
「せっかく、来てくれたんだから、当たりまえやろ」とおっしゃり、奥様も
「言い出したら、聞きませんから、井上さん、お付き合いしてあげてください。」とおっしゃられるので
「承知いたしました。」と申し上げ、ご自宅の近くの和食レストランに行きました。
そこで、監督は、自分の身体がしんどいにもかかわらず、私に気をつかっていただき
「遠慮せずに食えよ。お前、飲めないんか」とおっしゃりながら、ご自身は日本酒を2合、お飲みになられました。
私は、「すみません。今日は、車で、来ていますので、お付き合いできませんが、ノンアルコールビールをいただきます。」「次回は、電車で参りますので、よろしくお願いします。」と申し上げました。
さらに、自分はおそらく、食事どころではないはずなのに、私に気を使わせてはいけないと思われたのでしょう、頑張って、無理して、召し上がるのです。さらに、私に気を使って、努めて明るく振舞われるのです。私は、何とも言えない気持ちになりましたが、このような場に居させていただける幸せを感じ、神様に心から感謝した次第です。
(以下、次号に続く)
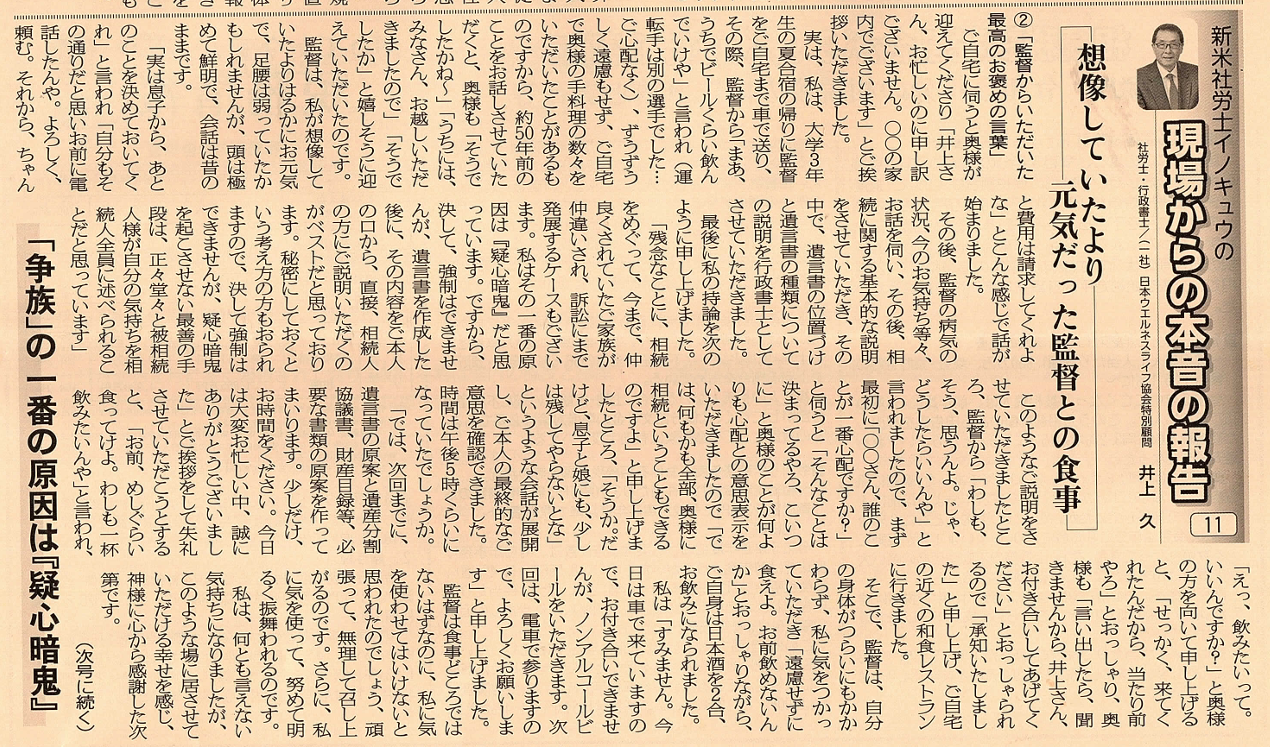
2025年2月10日(月)第11回掲載分 セキララ体験談「恩師からの最高のほめ言葉」②
第12回掲載分(2025年3月10日(月)
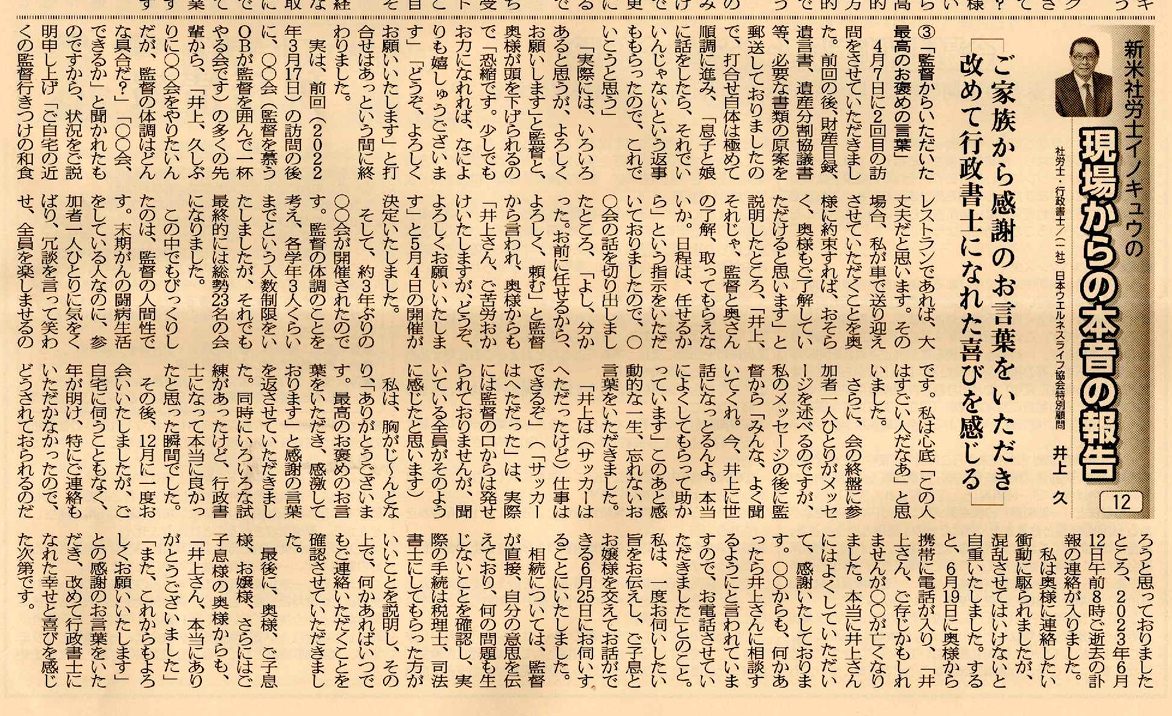
2025年3月10日(月)掲載分
③「監督からいただいた最高のお褒めの言葉」
4月7日(木)の13時30分に2回目の訪問をさせていただきました。前回の後、財産目録、遺言書、遺産分割協議書等、必要な書類の原案を郵送しておりましたので、打合せ自体は極めて順調に進み、「息子と娘に話をしたら、「それで、いいんじゃない。」という返事ももらったので、これでいこうと思う。」
「実際には、いろいろ、あると思うが、よろしくお願いします。」と監督と、奥様が頭を下げられるので、「恐縮です。」「少しでもお力になれれば、なによりも嬉しゅうございます。」「どうぞ、よろしくお願いいたします。」と打合せはあっという間に、終りました。
実は、前回(2022年3月17日(木))の訪問の後に、○○会(監督を慕うOBが監督を囲んで一杯やる会です)の多くの先輩から、「井上、久しぶりに○○会をやりたいんだが、監督の体調はどんな具合だ?」「○○会、出来るか」と聞かれたものですから、3月17日(木)の状況をご説明申し上げ、「ご自宅の近くの監督行きつけの和食レストランであれば、大丈夫だと思います。その場合、私が車で送り迎えさせていただくことを奥様に約束すれば、おそらく、奥様もご了解していただけると思います。」と説明したところ、「井上、それじゃ、監督と奥さんの了解、取ってもらえないか?」「日程は、任せるから」という指示をいただいておりましたので、○○会の話を切り出しましたところ、
「よし、わかった。」「お前に任せるから、よろしく、頼む。」と監督から言われ、奥様からも「井上さん、ご苦労おかけいたしますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。」と言われ、5月4日(水)12時30分~の開催が決定いたしました。
そして、5月4日(水)に約3年ぶりの○○会が開催されたのです。監督の体調のことを考え、各学年、3人くらいまでという人数制限をいたしましたが、それでも最終的には総勢23名の会になりました。
この中でもびっくりしたのは、監督の人間性です。末期がんの闘病生活をしている人なのに
参加者一人一人に気をくばり、冗談を言って笑わせ、全員を楽しませるのです。私は、心底、「この人はすごい人だなあ」と思いました。
さらに、会の終盤に参加者一人一人がメッセージを述べるのですが、私のメッセージの後に
監督から「みんな、よく聞いてくれ。今、井上に世話になっとるんよ。」「本当に良くしてもらって助かっています。」このあと感動的な一生、忘れないお言葉をいただいたのです。
「井上は(サッカーはへただったけど)、仕事はできるぞ。」(「サッカーはへただった。」は、実際には監督の口からは発せられておりませんが、聞いている全員がそのように感じたと思います。)
私は、胸がじ~んとなり、「ありがとうございます。」「最高のお褒めのお言葉をいただき、感激しております。」と感謝の言葉を返させていただきました。
同時に、いろいろな試練があったけど、行政書士になって本当に良かったと思った瞬間でした。
その後は、12月に一度、お会いいたしましたが、ご自宅にうかがうこともなく、年が明け、とくにご連絡もいただかなかったので、どうされておられるのだろうと思っておりましたところ、
2023年6月12日(月)午前8時00分ご逝去の訃報が慶応義塾大学体育会ソッカー部からメールで入りました。
私は、奥様に連絡したい衝動に駆られましたが、混乱させてはいけないと自重いたしました。
すると、6月19日(月)に奥様から携帯に電話が入り、「井上さん、ご存じかもしれませんが○○が亡くなりました。」「本当に井上さんには、よくしていただいて、感謝いたしております。」「○○からも、何かあったら、井上さんに相談するようにと言われていますので、お電話させいただきました。」とのこと、私は、一度、お伺いしたい旨、お伝えし、ご子息とお嬢様を交えてお話ができる6月25日(日)にお伺いすることにいたしました。
6月25日(日)に奥様、ご子息様、お嬢様とお会いいたしましたが、相続については、監督が、直接、自分の意思を伝えており、何の問題も生じないことを確認し、実際の手続は税理士、司法書士にしてもらった方がいいことを説明し、その上で、何かあれば、いつでもご連絡いただくことを確認させていただきました。
最後に、奥様、ご子息様、お嬢様、さらには、ご子息様の奥様からも
「井上さん、本当にありがとうございました。」「また、これからも、よろしくお願いいたします。」との感謝のお言葉をいただき、改めて、行政書士になれた幸せと喜びを感じた次第です。
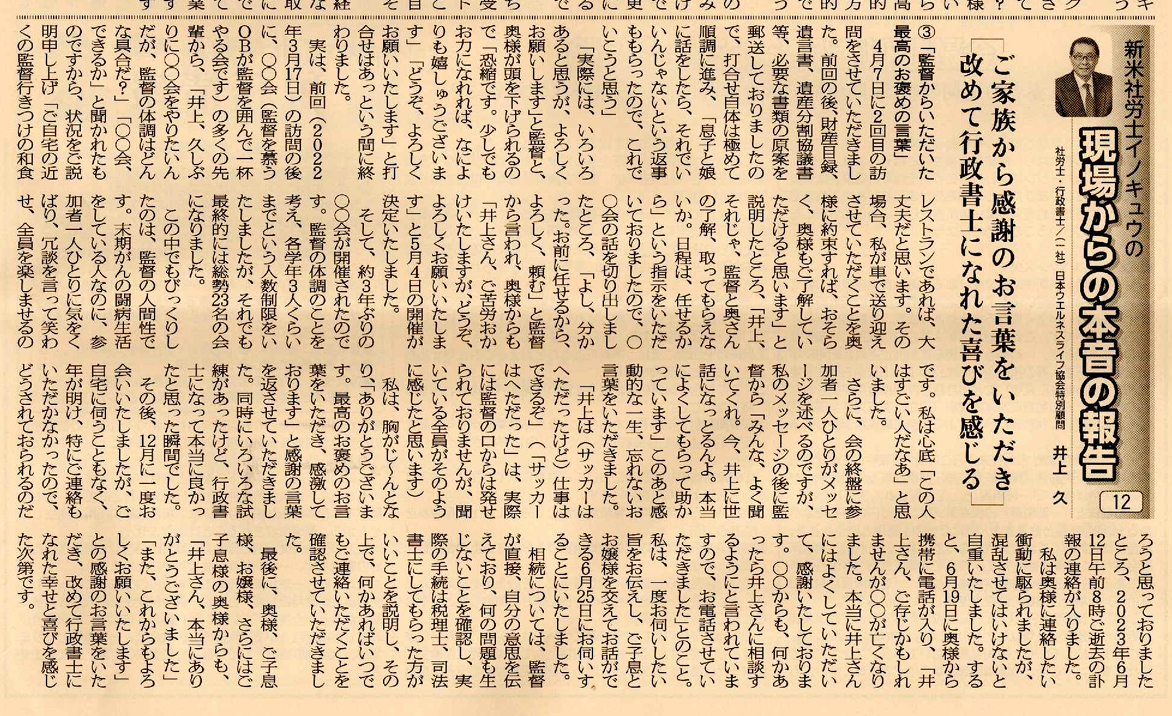
2025年3月10日(月)第12回掲載分 セキララ体験談「恩師からの最高のほめ言葉」③
第13回掲載分(2025年4月14日(月)
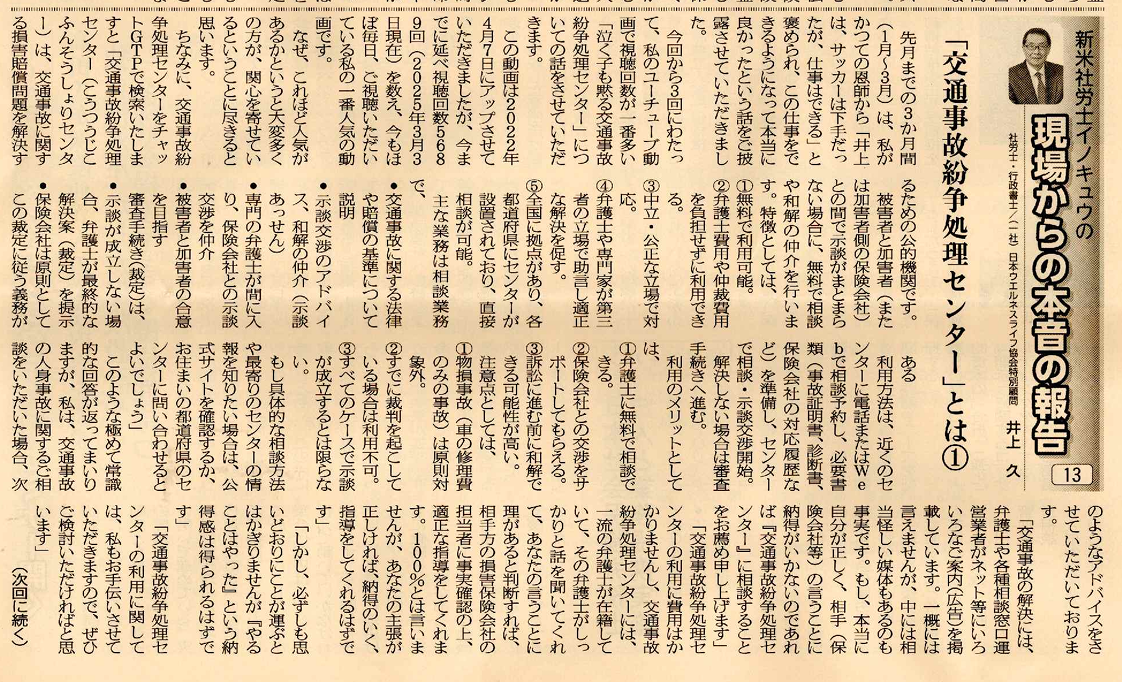
2025年4月14日(月)掲載分
泣く子も黙る「交通事故紛争処理センター」とは
先月までの3か月間(1月~3月)は、私がかつての恩師から「井上は、サッカーは下手だったが、仕事はできる。」と褒められ、この仕事をできるようになって本当に良かったという話をご披露させていただきましたが、今月から3か月間は、私のユーチューブ動画で
視聴回数が一番多い、「泣く子も黙る交通事故紛争処理センター」についての話をさせていただきます。この動画は2022年4月7日(木)にアップさせていただきましたが、今までに延視聴回数5,689回(2025年3月3日(月)現在)を数え、今も、ほぼ、毎日、ご視聴いただいている私の一番人気の動画です。
なぜ、これほど、人気があるかというとたいへん多くの方が、関心を寄せているということに尽きると思います。
ちなみに、交通事故紛争処理センターをチャットGTPで検索いたしますと
「交通事故紛争処理センター(こうつうじこふんそうしょりセンター)は、交通事故に関する損害賠償問題を解決するための公的機関です。被害者と加害者(または加害者側の保険会社)との間で示談がまとまらない場合に、無料で相談や和解の仲介を行います。
特徴としては、①無料で利用可能、②弁護士費用や仲裁費用を負担せずに利用できる、
③中立・公正な立場で対応し、④弁護士や専門家が第三者の立場で助言し、適正な解決を促し、⑤全国に拠点があり、各都道府県にセンターが設置されており、直接相談が可能、
主な業務は相談業務で、
・交通事故に関する法律や賠償の基準について説明
・示談交渉のアドバイス、和解の仲介(示談あっせん)
・専門の弁護士が間に入り、保険会社との示談交渉を仲介
・被害者と加害者の合意を目指す
審査手続き(裁定)
・示談が成立しない場合、弁護士が最終的な解決案(裁定)を提示
・保険会社は原則としてこの裁定に従う義務がある
利用方法は、近くのセンターに電話またはWebで相談予約し、必要書類(事故証明書、診断書、保険会社の対応履歴など)を準備し、センターで相談・示談交渉開始
解決しない場合は審査手続きへ進む
利用のメリットとしては、
① 弁護士に無料で相談できる
② 保険会社との交渉をサポートしてもらえる
③ 訴訟に進む前に和解できる可能性が高い
注意点としては、
① 物損事故(車の修理費のみの事故)は原則対象外
② すでに裁判を起こしている場合は利用不可
③ すべてのケースで示談が成立するとは限らない
もし具体的な相談方法や最寄りのセンターの情報を知りたい場合は、公式サイトを確認するか、お住まいの都道府県のセンターに問い合わせるとよいでしょう。」
という極めて常識的な回答が返ってまいりますが、
私は、交通事故の人身事故に関するご相談をいただいた場合、次のようなアドバイスをさせていただいております。
「交通事故の解決には、弁護士や各種相談窓口運営業者がネット等にいろいろなご案内(広告)が掲載していますが、一概には言えませんが、中には相当怪しい媒体もあるのも事実です。もし、本当に自分が正しく、相手(保険会社等)の言うことに納得がいかないのであれば、『交通事故紛争処理センター』に相談することをお薦め申し上げます。」
「交通事故紛争処理センターの利用に費用はかかりませんし、交通事故紛争処理センターには、一流の弁護士が在籍していて、その弁護士がしっかりと話を聞いてくれて、あなたの言うことに理があると判断すれば、相手方の損害保険会社の担当者に事実確認の上、適正な指導をしてくれます。100%とは言いませんが、あなたの主張が正しければ、納得のいく、指導をしてくれるはずです。」「しかし、必ずしも思い通りにことが運ぶとはかぎりませんが、『やることはやった。』という納得感は得られるはずです。」「交通事故紛争処理センターの利用に関しては、私もお手伝いさせていただきますので、是非、ご検討いただければと思います。」
(次回に続く)
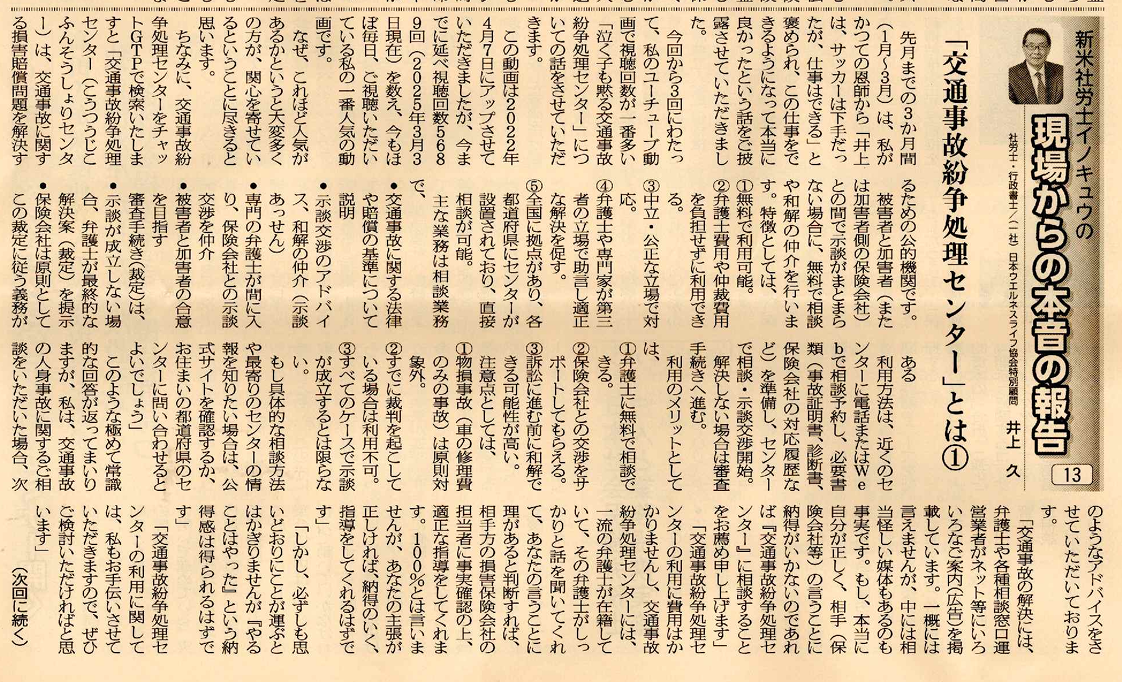
2025年4月14日(月)第13回掲載分 泣く子も黙る「交通事故紛争処理センターとは」①
第14回掲載分(2025年5月12日(月)
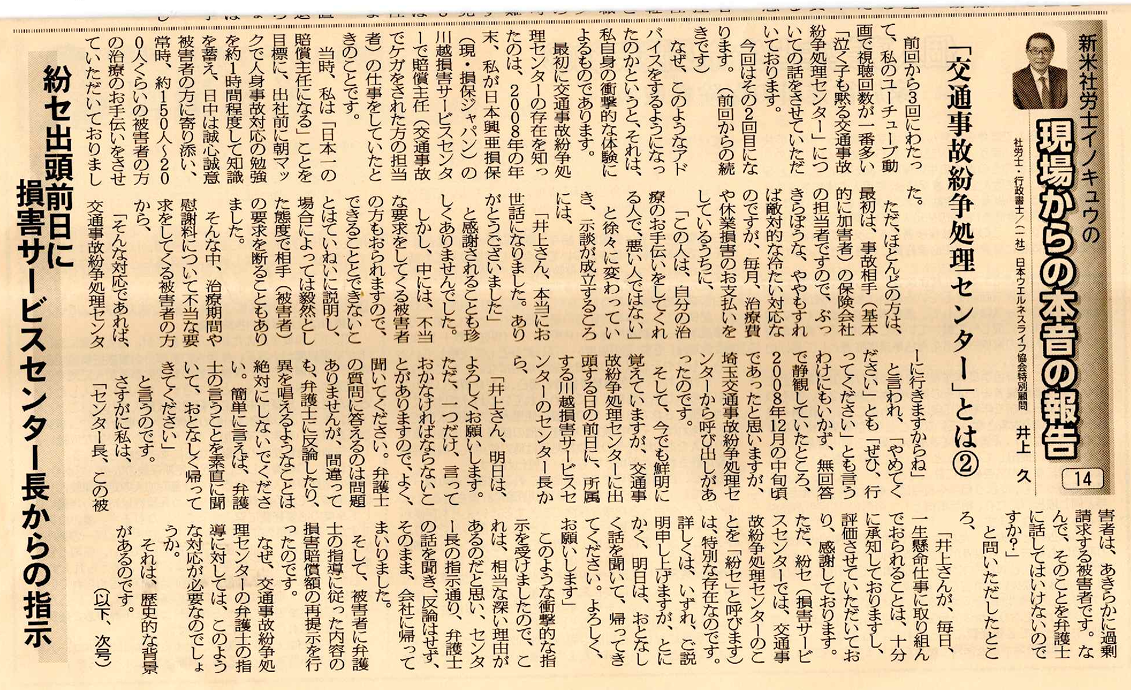
2025年5月12日(月)掲載分
泣く子も黙る「交通事故紛争処理センター」とは
(第2回 2025年5月掲載分)
なぜ、このようなアドバイスをするようになったのかというと、それは、私自身の衝撃的な体験によるものであります。
最初に交通事故紛争処理センターの存在を知ったのは、2008年の年末、私が日本興亜損保(現 損保ジャパン)の川越損害サービスセンターで賠償主任(交通事故でケガをされた方の担当者)の仕事をしていたときのことです。当時、私は、「日本一の賠償主任になる」ことを目標に、出社前に朝マックで人身事故対応の勉強を約1時間程して、知識を蓄え、日中は、誠心誠意、被害者の方に寄り添い、常時、約150人~200人位の被害者の方の治療のお手伝いをさせていただいておりました。ただ、ほとんどの方は、最初は、事故相手(基本的に加害者)の保険会社の担当者ですので、ぶっきらぼうなややもすれば、敵対的な冷たい対応なのですが、毎月、治療費や休業損害の支払いをしている内に、「この人は、自分の治療のお手伝いをしてくれる人で、悪い人ではない。」に変わり、示談が成立するころには、「井上さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。」と感謝されることも珍しくありませんでした。
しかし、中には、不当な要求をしてくる被害者の方もおられますので、出来ることと出来ないことは丁寧に説明し、場合によっては、毅然とした態度で、相手(被害者)の要求を断ることもありました。
そんな中、治療期間や慰謝料について不当な要求をしてくる被害者の方から、「そんな対応であれば、紛争処理センターに行きますからね。」と言われ、「やめてください。」とも「是非、行ってください。」とも言う訳にもいかず、無回答で静観していたところ、2008年12月の中旬頃であったと思いますが、埼玉交通事故紛争処理センターから呼び出しがあったのです。そして、いまでも鮮明に覚えていますが、センターに出頭する日の前日に所属する川越損害サービスセンターのセンター長から
「井上さん、明日は、よろしくお願いします。」「ただ、一つだけ、言っておかなければならないことがありますので、よく、聞いてください。」「弁護士の質問に答えるのは問題ありませんが、間違っても、弁護士に反論したり、異を唱えるようなことは絶対にしないでください。」「簡単に言えば、弁護士の言うことを素直に聞いて、おとなしく帰ってきてください。」と言うのです。
さすがに私は「センター長、この被害者は、あきらかに過剰請求する被害者です。」「なんで、そのことを弁護士に話してはいけないのですか?」と問いただしたところ、
「井上さんが、毎日、一生懸命仕事に取り組んでおられることは、十分に承知しておりますし、評価させていただいており、感謝しております。」「ただ、扮セ(損害サービスセンターでは、交通事故紛争処理センターのことを「扮セ」と呼びます。)は、特別な存在なのです。」「詳しくは、いずれ、ご説明申し上げますが、とにかく、明日は、おとなしく話を聞いて、帰ってきてください。よろしく、お願いします。」
このような衝撃的な指示を受けましたので、これは、相当な深い理由があるのだと思い、
センター長の指示通り、弁護士の話を聞き、反論はせず、そのまま、会社に帰ってまいりました。そして、被害者に弁護士の指導に従った内容の損害賠償額の再提示を行ったのです。
なぜ、交通事故紛争処理センターの弁護士の指導に対しては、このような対応が必要なのでしょうか、それは、歴史的な背景があるのです。(以下、次号)
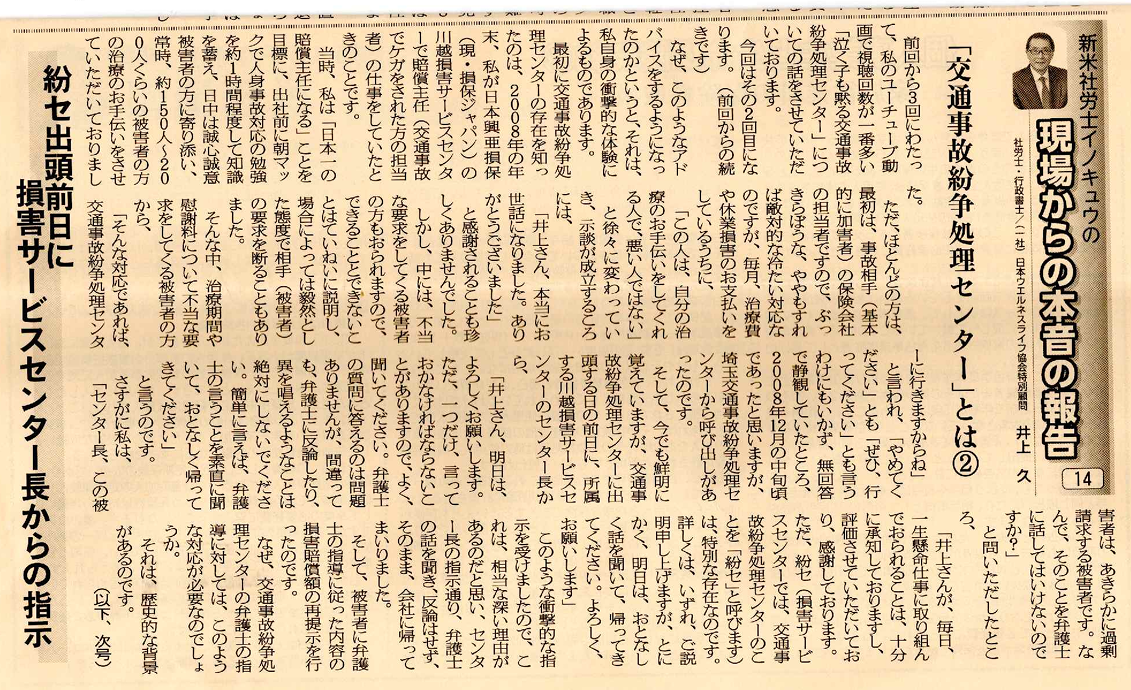
2025年5月12日(月)第14回掲載分 泣く子も黙る「交通事故紛争処理センター」とは②
第15回掲載分(2025年6月9日(月)
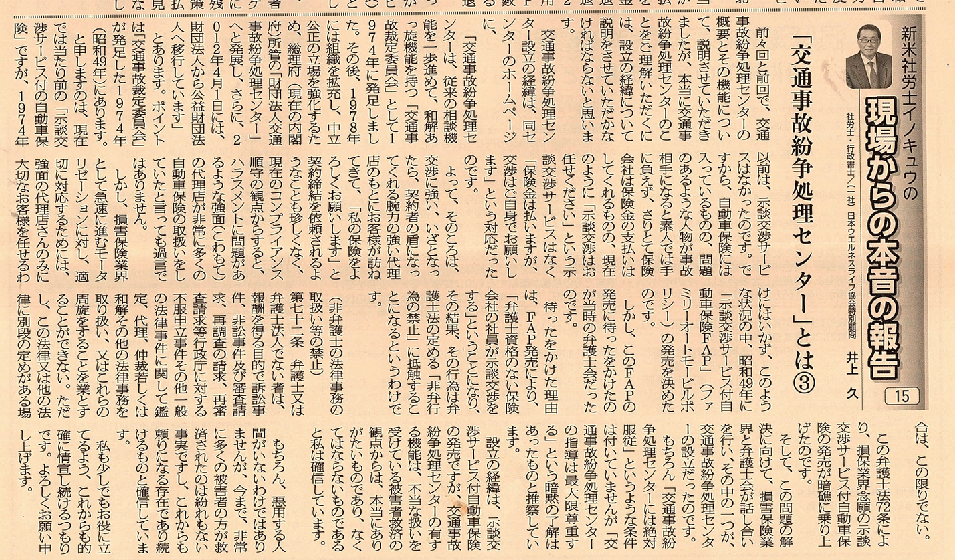
2025年6月9日(月)第15回掲載分
あい泣く子も黙る「交通事故紛争処理センター」とは
(第3回 2025年6月掲載分)
前々回と前回で、交通事故紛争処理センターの概要とその機能について、説明させていただきましたが、本当に交通事故紛争処理センターのことをご理解いただくには、設立の経緯について説明をさせていただかなければならないと思います。
交通事故紛争処理センターの設立の経緯は、同センターのホームページに
「交通事故紛争処理センターは、従来の相談機能を一歩進めて、和解あっ旋機能を持つ「交通事故裁定委員会」として1974年に発足しました。その後、1978年には組織を拡充し、中立公正の立場を強化するため、総理府(現在の内閣府)所管の「財団法人交通事故紛争処理センター」へと発展し、さらに、2012年4月1日には、財団法人から公益財団法人へ移行しています。」とあります。
ポイントは、「交通事故裁定委員会」が発足した1974年(昭和49年)にあります。
と申しますのは、現在では当たり前の「示談交渉サービス付の自動車保険」ですが、
1974年以前は、示談交渉サービスはなかったのです。
ですから、自動車保険には入っているものの、問題のあるような人物が事故相手になると素人では手に負えず、さりとて保険会社は保険金の支払いはしてくれるものの、現在のように「示談交渉はお任せください。」という示談交渉サービスはなく、「保険金は払いますが、交渉はご自身でお願いします。」という対応だったのです。
ですから、そのころは、交渉に強い、いざとなったら、契約者の盾になってくれる腕力の強い代理店のもとにお客様が訪ねてきて、「私の保険をよろしくお願いします。」とお客様から契約締結を依頼されるようなことも珍しくなく、やや問題があるかもしれませんが、現在のコンプライアンス順守の観点からすると、ハラスメントに問題があるような強面(こわおもて)の代理店がひじょうに多くの自動車保険の取り扱いをしていたと言っても過言でありません。」
しかし、損害保険業界として急速に進むモータリゼーションに対し、適切に対応するためには、強面の代理店さんのみに大切なお客様を任せるわけにはいかず、このような状況の中、昭和49年に「示談交渉サービス付自動車保険FAP」(ファミリーオートモービルポリシー)の発売を決めたのです。
しかし、このFAPの発売に待ったをかけたのが当時の弁護士会だったのです。
待ったをかけた理由は、FAP発売により、「弁護士資格のない保険会社の社員が示談交渉をする。」ということになり、その結果、その行為は弁護士法の定める「非弁行為の禁止」に抵触することになるという訳です。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この弁護士法72条により、損保業界念願の示談交渉サービス付自動車保険の発売が暗礁に乗り上げたのです。
そして、この問題の解決に向けて、損害保険業界と弁護士会が話し合いを行い、その結果、いろいろな仕組みができあがったのです。
その中の一つが、交通事故紛争処理センターの設立であり、センターに弁護士を常駐させ、問題の解決を図るということがあったのだと思います。
また、損害保険会社の損害サービスセンターには、私が把握している限り、顧問弁護士がついていますが、顧問弁護士制度もFAP発売を認める条件のひとつであったものと私は理解しております。
もちろん、「交通事故紛争処理センターには絶対服従」というような条件は付いておりませんが、「交通事故紛争処理センターの指導は最大限尊重する」という暗黙の了解はあったものと推察いたしております。
設立の経緯は、示談交渉サービス付自動車保険の発売ですが、交通事故紛争処理センターの有する機能は、不当な扱いを受けている被害者救済の観点からは、本当にありがたいものであり、なくてはならいいものであると私は確信いたしております。
もちろん、悪用する人間がいない訳ではありませんが、今まで、ひじょうに多くの被害者の方が救済されたのは紛れもない事実ですし、これからも頼りになる存在であり続けるものと確信いたしております。
わたしも少しでもお役に立てるよう、これからも的確に情宣し続けるつもりです。
よろしくお願い申し上げます。
最後に必要書類のそろえ方について、私のほろ苦い体験談をご披露させていただきます。
交通事故紛争処理センターへの提出書類は、紛争処理センターのホームページでご案内されておりますが、主な書類は①交通事故証明書、②診断書・診療報酬明細書、③保険会社の対応履歴等ですが、この書類は被害者様の担当である賠償主任が持っている書類そのものなのです。
2009年の1月頃だったと思いますが、順調にけがが回復し、治癒に伴い、もうすぐ示談成立と思っていた被害者の方からこのような電話をいただきました。
「井上さん、たいへん、お世話になりました。」「井上さんのお陰で、十分、治療も受けさせていただき、感謝いたしております。」「そこで、ひとつお願いがあるのですが、生命保険の請求をしたいと思っているのですが、生命保険会社から次の書類の提出を求められております。差し支えなければ、コピーを送っていただけませんでしょうか?」
被害者の方から依頼された書類は、すべて、私が持っている書類でしたので
「承知いたしました。すぐに交通事故証明書、診断書・診療報酬明細書他、ご依頼いただきました書類のコピーを念のため、2セット送らせていただきます。」
これで、間違いなく、示談成立とぬか喜びした私は、喜び勇んで書類を送らせていただいたのです。しかし、その後、連絡が途絶え、どうしたのかなと思っていましたら、約2週間後に埼玉交通事故紛争処理センターから出頭要請があったのです。
「あっ、やられた。」と思いましたが、あとの祭りです。
「世の中には、迫真の演技を見事にこなす人もいるんだなあ~」と何故か感心した私でした。
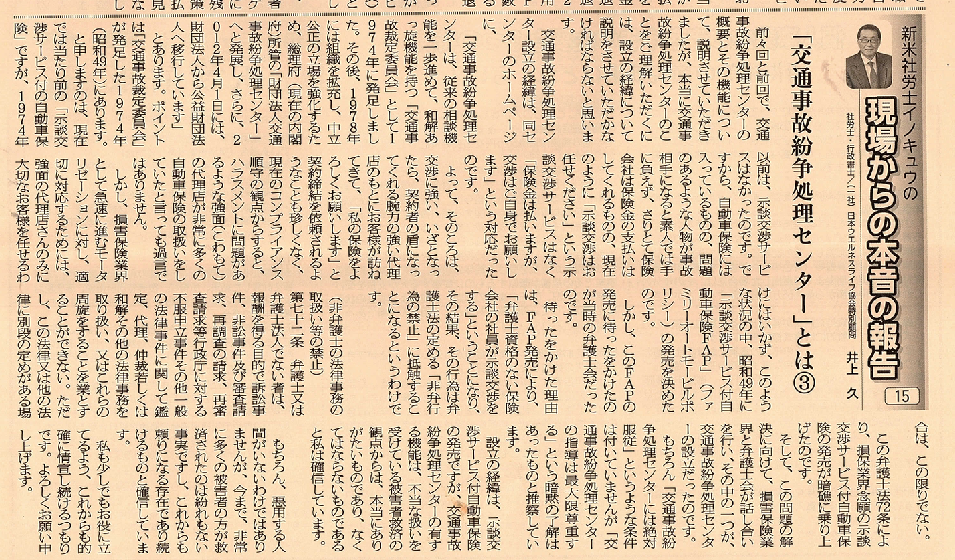
2025年6月9日(月)第15回掲載分 泣く子も黙る「交通事故紛争処理センターとは」③
第16回掲載分(2025年7月14日(月))
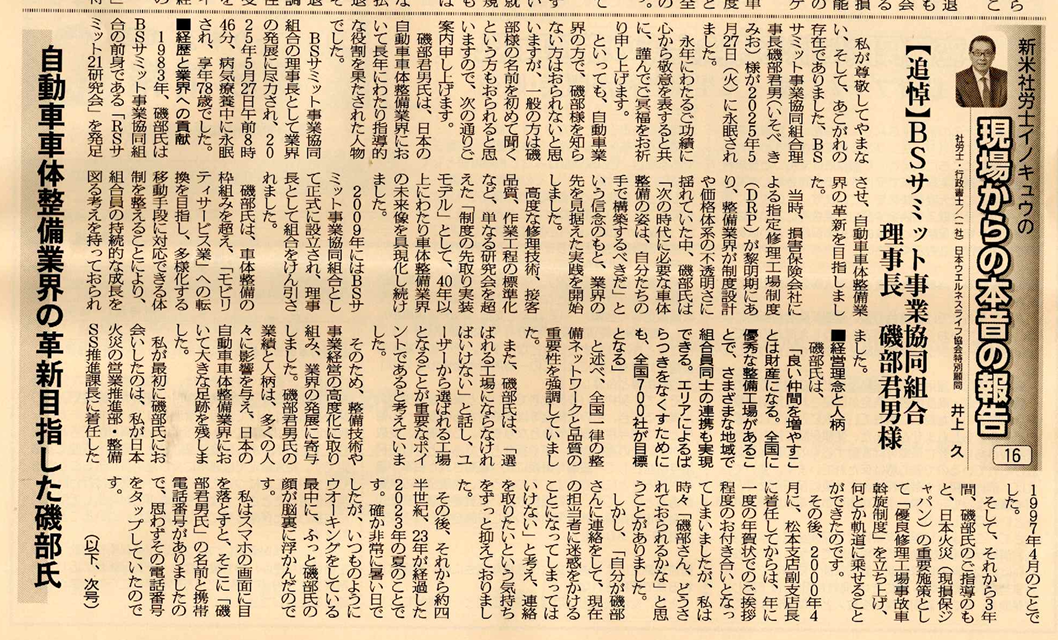
2025年7月14日(月)新日本保険新聞
あい追悼 BSサミット事業協同組合 理事長 磯部 君男様(2025年7月掲載原稿)
私が尊敬してやまない、そして、あこがれの存在でありました、BSサミット事業協同組合 理事長 磯部 君男様(78歳)が2025年5月27日(火)に永眠されました。
永年にわたるご功績に心から敬意を表すると共に、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
といっても、自動車業界の方で、磯部様を知らない方はおられないと思いますが、一般の方は、磯部様の名前をはじめて聞くという方もおられると思いますので、次の通りご案内申し上げます。
「磯部君男(いそべ きみお)氏は、日本の自動車車体整備業界において長年にわたり指導的な役割を果たされた人物であり、BSサミット事業協同組合の理事長として業界の発展に尽力され、2025年5月27日午前8時46分、病気療養中に永眠され、享年78歳でした。
経歴と業界への貢献
1983年、磯部氏はBSサミット事業協同組合の前身である「RSサミット21研究会」を発足させ、自動車車体整備業界の革新を目指しました。当時、損害保険会社による指定修理工場制度(DRP)が黎明期にあり、整備業界が制度設計や価格体系の不透明さに揺れていた中、磯部氏は「次の時代に必要な車体整備の姿は、自分たちの手で構築するべきだ」という信念のもと、業界の先を見据えた実践を開始しました。高度な修理技術、接客品質、作業工程の標準化など、単なる研究会を超えた「制度の先取り実装モデル」として、40年以上にわたり車体整備業界の未来像を具現化し続けました。
2009年にはBSサミット事業協同組合として正式に設立され、理事長として組合を牽引されました。磯部氏は、車体整備の枠組みを超え、「モビリティサービス業」への転換を目指し、多様化する移動手段に対応できる体制を整えることで、組合員の持続的な成長を図る考えを持っていました。
経営理念と人柄
磯部氏は、「良い仲間を増やすことは財産になる。全国に優秀な整備工場があることで、さまざまな地域で組合員同士の連携も実現できる。エリアによるばらつきをなくすためにも、全国700社が目標となる」と述べ、全国一律の整備ネットワークと品質の重要性を強調していました。
また、磯部氏は「選ばれる工場にならなければいけない」と話し、ユーザーから選ばれる工場となることが重要なポイントであると考えていました。そのため、整備技術や事業経営の高度化に取り組み、業界の発展に寄与しました。
磯部君男氏の業績と人柄は、多くの人々に影響を与え、日本の自動車車体整備業界において大きな足跡を残しました。」
私が最初に磯部様にお会いしたのは、
私が日本火災の営業推進部・整備SS推進課長に着任した1997年4月でした。
そして、それから3年間、磯部様のご指導のもと、日本火災(現損保ジャパン)の重要施策として、「優良修理工場事故車斡旋制度」を立ち上げ、何とか軌道にのせることができたのです。
その後、2000年4月に松本支店副支店長に着任してからは、年賀状のご挨拶程度のお付き合いでしたが、わたしは時々、「磯部さん、どうされておられるかなあ?」と思うことがありましたが、「自分が磯部さんに連絡をして、現在の担当に迷惑をかけてはいけない。」と考え、連絡を取りたいという気持ちを抑えておりました。
しかし、それから約四半世紀、23年が経過した2023年の夏、ひじょうに暑い日でしたが、いつものようにウォーキングをしている最中に、ふっと磯部さんの顔が脳裏に浮かんだのです。私はスマホの画面に目を落とすとそこに「磯部 君男」の名前と携帯電話番号がありましたので、思わず、その電話番号をクリックしていたのです。(以下、次号)
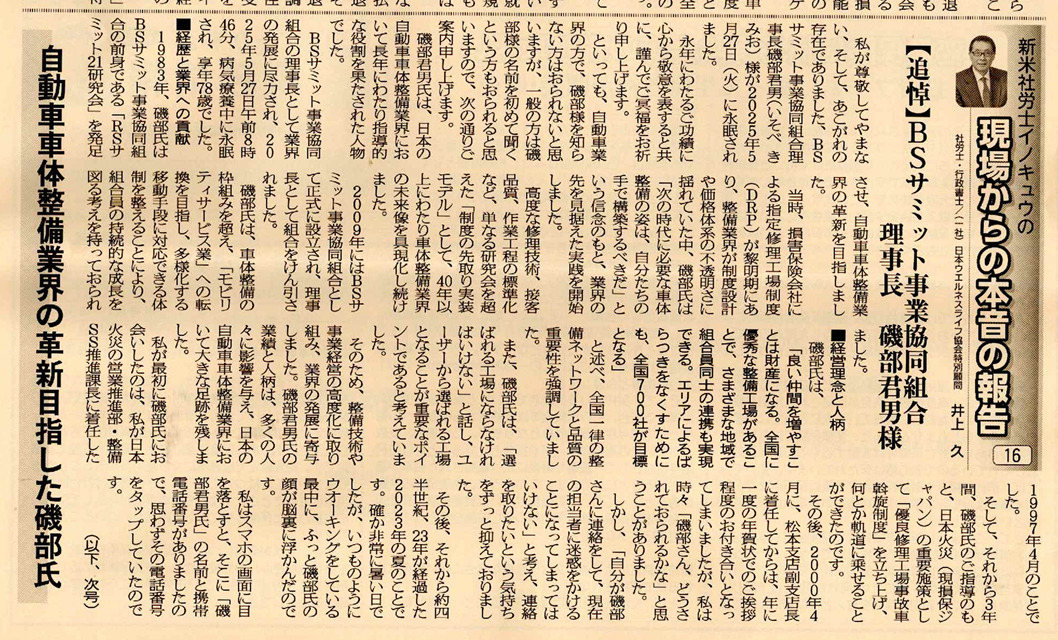
2025年7月14日(月)第16回掲載分 追悼 BSサミット事業協同組合 理事長 磯部君男様①
第17回(2025年8月11日(月)掲載分)
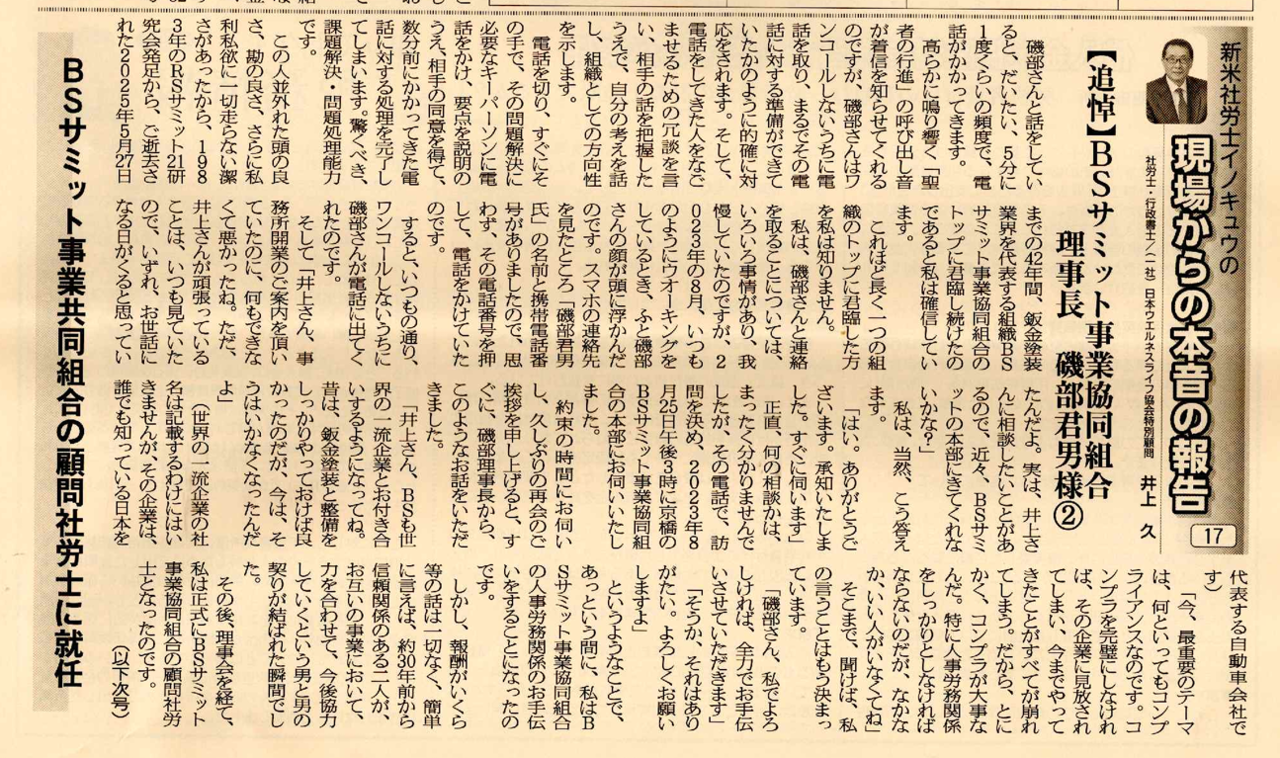
2025年8月11日(月)掲載分
追悼 BSサミット事業協同組合 理事長 磯部 君男様(2025年8月掲載原稿)
磯部さんと話をしていると、だいたい、5分に1度くらい、電話がかかってきます。
高らかに鳴り響く「聖者の行進」の呼び出し音が着信を知らせてくれるのですが、
磯部さんはワンコールしない内に電話を取り、まるでその電話に対する準備ができていたかのように的確に対応し、電話をしてきた人をなごませる冗談をかまし、相手の話を把握したうえで、自分の考えを話し、組織としての方向性を示し、電話を切り、すぐにその手で、その問題解決に必要なキーパーソンに電話をかけ、要点を説明の上、同意を得て、数分前にかかってきた電話に対する処理を完了します。驚くべき、課題解決・問題処理能力です。
この人並外れた頭の良さ、勘の良さ、さらに私利私欲に一切走らない潔さがあったから、
1983年のRSサミット21研究会発足から、ご逝去された2025年5月27日(火)までの42年間、鈑金塗装業界を代表する組織BSサミット事業協同組合のトップに君臨し続けたのであると私は確信しています。
これ程永きに一つの組織のトップに君臨した方を私は知りません。
私は、磯部さんに連絡をとることをいろいろな事情があり、我慢していたのですが、
2023年の8月、いつものようにウォーキングをしているとき、ふっと磯部さんの顔が頭にうかび、スマホの連絡先を見ましところ、「磯部 君男」様の名前と携帯電話番号がありましたので、思わず、その電話番号を押して、電話をかけていたのです。
すると、いつもの通り、1コールしないうちに磯部さんが電話にでてくれたのです。
そして、「井上さん、事務所開業のご案内をいただいていたのに、何もできなくて悪かったね。」「ただ、井上さんが頑張っていることは、いつも見ていたので、いずれ、お世話になる日が来ると思っていたんだよ。」「実は、井上さんに相談したいことがあるので、近々、BSサミットの本部にきてくれないかな?」
私は、当然、こう答えます。
「はい。ありがとうございます。承知いたしました。すぐに、伺います。」
正直、何の相談かは、まったくわかりませんでしたが、その電話で、訪問を決め、
2023年8月25日(金)午後3時に京橋のBSサミット事業協同組合の本部にお伺いいたしました。
約束の時間にお伺いし、久しぶりの再会のご挨拶を申し上げると、すぐに、磯部理事長から、このようなお話をいただきました。
「井上さん、BSも世界の一流企業とお付き合いするようになってね。」
「昔は、鈑金塗装と整備をしっかりやっておけば良かったのだが、今は、そうはいかなくなったんだよ。」(世界の一流企業の社名は記載する訳にはいきませんが、その企業は、誰でも知っている日本を代表する自動車会社です。)
「今、最重要のテーマは、何といってもコンプライアンスなのです。」「コンプラを完璧にしなければ、その企業に見放されてしまい、今までやってきたことがすべてが崩れてしまう。」「だから、とにかく、コンプラが大事なんだ。」「特に人事労務関係をしっかりとしなければならないのだが、なかなか、いい人がいなくてね。」
そこまで、聞けば、私の言うことはもう決まっています。
「磯部さん、私でよろしければ、全力でお手伝いさせていただきます。」
「そうか、それはありがたい。よろしくお願いしますよ。」
というようなことで、あっという間に、私はBSサミット事業協同組合の人事労務関係のお手伝いをすることになったのです。
しかし、報酬がいくら等の話は一切なく、簡単に言えば、
約30年前から信頼関係のある二人が、お互いの事業において、力を合わせて、
今後、協力していくという男と男の契りが結ばれた瞬間でした。
その後、理事会を経て、私は正式にBSサミット事業協同組合の顧問社労士となったのです。(以下次号)
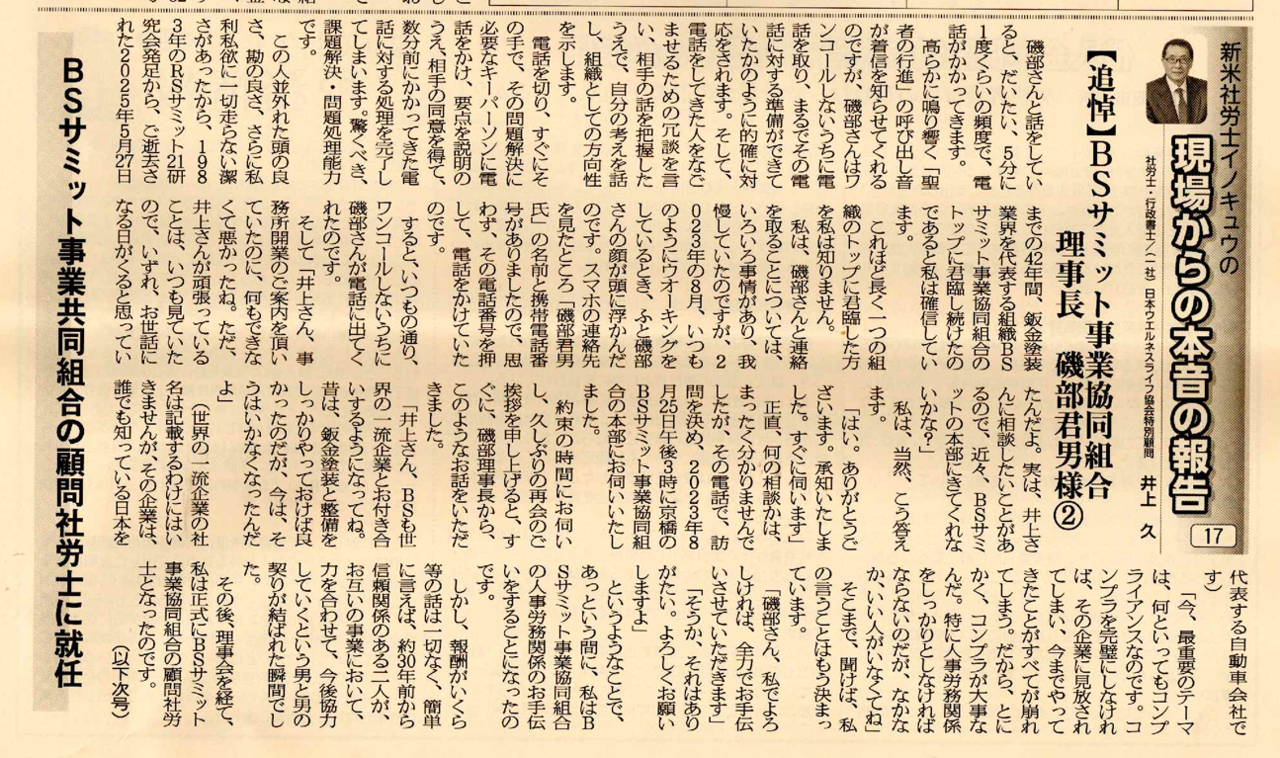
2025年8月11日(月)第17回掲載分 追悼 BSサミット事業協同組合 理事長 磯部君男様②
第18回(2025年9月8日(月)掲載分)
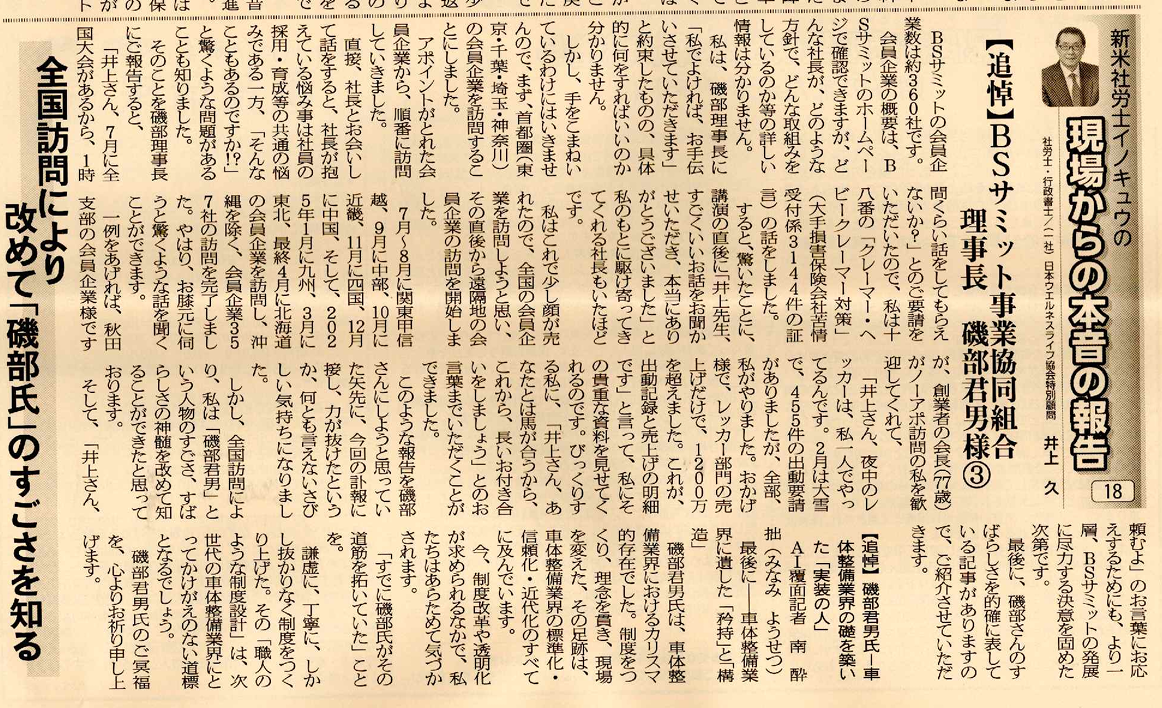
2025年9月8日(月) 追悼 磯部 君男様③
追悼 BSサミット事業協同組合 理事長 磯部 君男様③
BSサミットの会員企業数は約360社です。
会員企業の概要は、BSサミットのホームページで確認できますが、どんな社長が、どのような方針で、どんな取り組みをしているのか等の詳しい情報はわかりません。
私は、磯部理事長に「私でよければ、お手伝いさせていただきます。」と約束したものの、具体的に何をすればいいのかわかりません。
しかし、手をこまねいているわけにはいきませんので、
まず、首都圏(東京・千葉・埼玉・神奈川)の会員企業を訪問することにいたしました。
1社、1社、アポイントがとれた会員企業から、順番に訪問していきました。
やはり、直接、社長とお会いして話をすると、社長が抱えてる悩み事は、社員の採用・育成等の共通の悩みがある一方、「そんなこともあるのですか?」というような問題もあることを知りました。
そのことを磯部理事長にご報告させていただくと、
「井上さん、7月に全国大会があるから、1時間くらい、話をしてもらえないか?」とのご要請をいただきましたので、私は十八番の「クレーマー・ヘビークレーマー対策」(大手損害保険会社苦情受付係3144件の証言)の話をさせていただきました。
すると、驚くことに、講演の直後に
「井上先生、すごくいいお話をお聞かせいただき、本当にありがとうございました。」と私のもとに駆け寄ってきてくれる社長もいたほどです。
私は、これで少し、顔が売れたので、全国の会員企業を訪問しようと思い
その直後から、遠隔地の会員企業の訪問を開始いたしました。
7月~8月に関東甲信越、9月に中部、10月に近畿、11月に四国、12月に中国、そして、2025年1月に九州、3月に東北、最終4月に北海道の会員企業を訪問し、沖縄を除く、会員企業357社の訪問を完了いたしました。
やはり、お膝元に伺うと驚くような話を聞くことができます。
一例をあげれば、秋田支部の会員企業様ですが、
創業者の会長(77歳)がノーアポ訪問の私を歓迎してくれて
「井上さん、夜中のレッカーは、私一人でやってるんです。」
「2月は大雪で、455件の出動要請がありましたが、全部、私がやりました。」
「お陰様で、レッカー部門の売上だけで、1200万を超えました。」
「これが、出動記録と売り上げの明細です。」と言って、
私にその貴重な資料を見せてくれるのです。
びっくりする私に、「井上さん、あなたとは馬があうから、これから、長いお付き合いをしましょう。」
とのお言葉まで、いただくことができました。
このような報告を磯部さんにしよう思っていた矢先に、今回の訃報に接し、
力が抜けたというか、何とも言えないさびしい気持ちになりました。
しかし、全国訪問により、私は「磯部君男」という人物の凄さ、素晴らしさの神髄を改めて、知ることができたと思っております。
そして、「井上さん、頼むよ。」のお言葉にお応えするためにも、
より一層、BSサミットの発展に尽力する決意を固めた次第です。
最後に、磯部さんの素晴らしさを的確に表している記事がありますので、
ご紹介させていただきます。
【追悼】磯部君男氏──車体整備業界の礎を築いた「実装の人」
AI覆面記者|南 酔拙(みなみ ようせつ)
最後に──車体整備業界に遺した「矜持」と「構造」
磯部君男氏は、車体整備業界におけるカリスマ的存在でした。
制度をつくり、理念を貫き、現場を変えた──
その足跡は、車体整備業界の標準化・信頼化・近代化のすべてに及んでいます。
今、制度改革や透明化が求められるなかで、私たちはあらためて気づかされます。
「すでに磯部氏がその道筋を拓いていた」ことを。
謙虚に、丁寧に、しかし抜かりなく制度をつくり上げた。
その“職人のような制度設計”は、次世代の車体整備業界にとって
かけがえのない道標となるでしょう。
磯部君男氏のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。
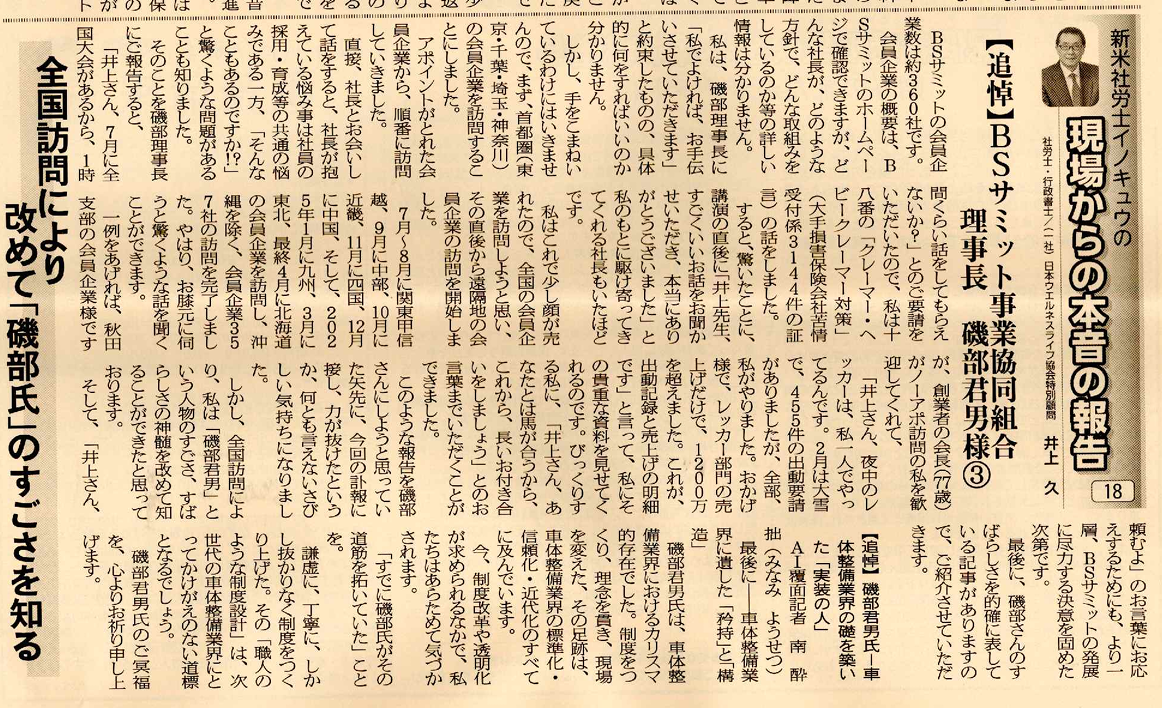
2025年9月8日(月) 追悼 磯部 君男様③
第19回(2025年10月13日(月)掲載分)
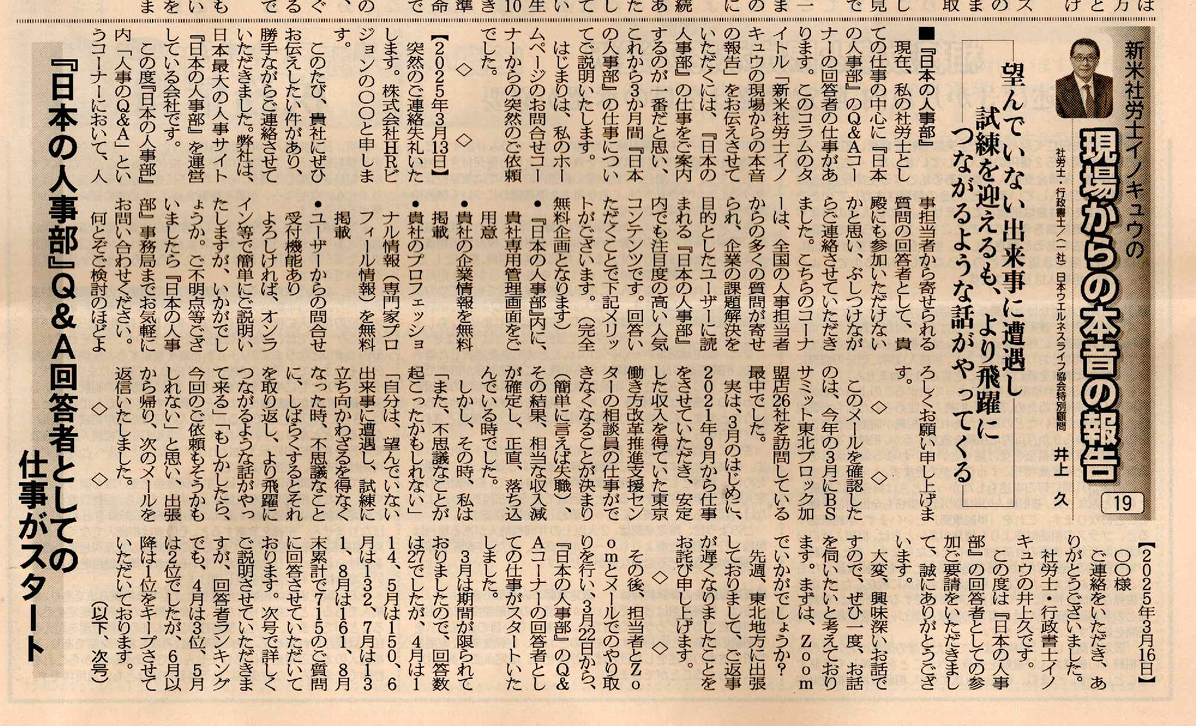
2025年10月13日(月)第19回掲載分
日本の人事部①
現在、私の社労士としての仕事の中心に「日本の人事部」のQ&Aコーナーの回答者の仕事があります。このコラムのタイトル「新米社労士イノキュウの現場からの本音の報告」をお伝えさせていただくには、日本の人事部の仕事をご案内するのが一番だと思い、今月から3か月間、日本の人事部の仕事についてご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
はじまりは、私のホームページのお問合せコーナーからの突然のご依頼でした。
2025年3月13日(木)
突然のご連絡失礼いたします。株式会社HRビジョンの〇〇と申します。
この度、貴社に是非お伝えしたい件があり、勝手ながらご連絡させていただきました。
弊社は、日本最大の人事サイト『日本の人事部』を運営している会社です。
この度、『日本の人事部』内「人事のQ&A」というコーナーにおいて、人事担当者から寄せられる質問の回答者として、貴殿にも参加いただけないかと思い、不躾ながらご連絡させていただきました。こちらのコーナーは、全国の人事担当者からの多くの質問が寄せられ、企業の課題解決を目的としたユーザーに読まれる、『日本の人事部』内でも注目度の高い人気コンテンツです。
回答いただくことで下記メリットがございます。(完全無料企画となります。)
・『日本の人事部』内に、貴社専用管理画面をご用意
・貴社の企業情報を無料掲載
・貴社のプロフェッショナル情報(専門家プロフィール情報)を無料掲載
・ユーザーからの問合せ受付機能あり
よろしければ、オンライン等で簡単にご説明いたしますが、いかがでしょうか。
ご不明点等ございましたら、『日本の人事部』事務局までお気軽にお問い合わせください。
何卒ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。
このメールを確認したのは、今年の3月にBSサミット東北ブロック加盟店26社を訪問している最中でした。
実は、3月のはじめに、2021年9月から仕事をさせていただき、安定した収入を得ていた東京働き方改革推進支援センターの相談員の仕事ができなくなることが決まり(簡単に言えば失職)、その結果、相当な収入減が確定し、正直、落ち込んでいるきでした。
しかし、その時、私はこう思いました。
「また、不思議なことが起こったかもしれない」「自分は、望んでいない出来事に遭遇し、試練に立ち向かわざるを得なくなったとき、不思議なことに、しばらくするとそれを取り返し、より、飛躍につながうような話がやって来る。」「もしかしたら、今回のご依頼もそうかもしれない。」と思い、出張から帰り、次のメールを返信いたしました。
2025年3月16日(日)
〇〇様
ご連絡をいただき、ありがとうございました。
社労士・行政書士イノキュウの井上久です。
この度は、「日本の人事部」の回答者としての参加ご要請をいただきまして、
誠にありがとうございます。
たいへん、興味深いお話ですので、
是非、一度、お話を伺いたいと考えております。
まずは、Zoomでいかがでしょうか?
先週、東北地方に出張しておりまして、
ご返事が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。
その後、担当者とZoomとメールでのやり取りを行い、
3月22日(金)から、
日本の人事部のQ&Aコーナーの回答者としての仕事がスタートいたしました。
3月は期間が限られておりましたので、回答数は27でしたが、4月は114,5月は150,6月は132,7月は131,8月は161、8月末累計で715のご質問に回答させていただいております。次号で詳しくご説明させていただきますが、回答者ランキングでも、4月は3位、5月は2位でしたが、6月以降は、1位をキープさせていただいております。(以下、次号)
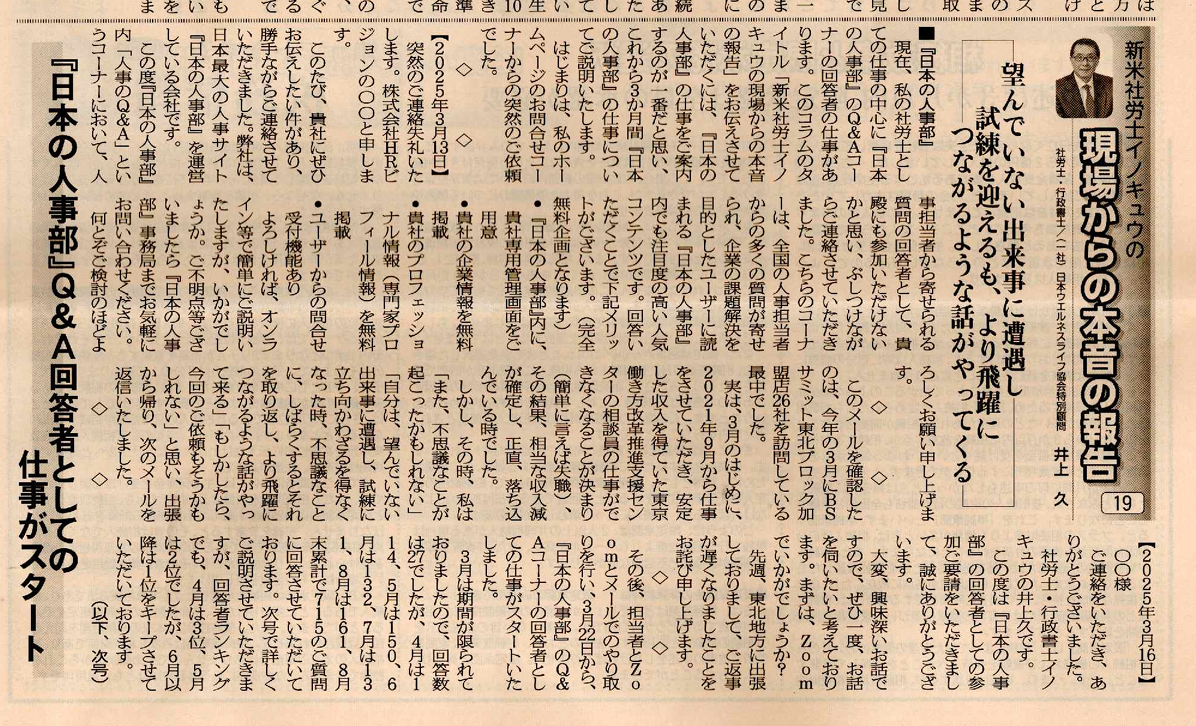
2025年10月13日(月)第19回掲載分
第20回(2025年11月10日(月)掲載分)
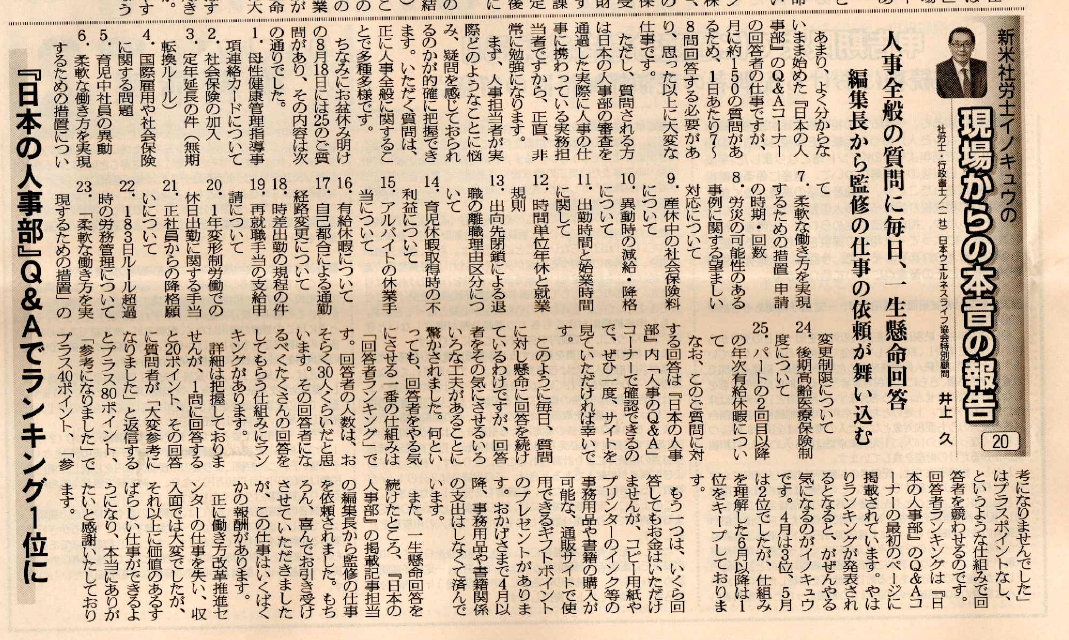
2025年11月10日(月)第20回掲載分
あまり、よくわからないまま始めた日本の人事部Q&Aコーナーの回答者の仕事ですが、
月に約150の質問がありますので、1日に7問から8問、回答する訳で、思った以上にたいへんな仕事です。
ただし、ご質問される方は、日本の人事部の審査を通過した、失礼な言い方かもしれませんが
本当に人事の仕事に携わっている実務担当者の方からのご質問ですから、正直、ひじょうに勉強になります。
まず、人事担当者が、実際、どのようなことに悩み、疑問を感じておられるのかが的確に把握できます。
いただくご質問は、正に人事全般に関することで、多種多様です。
ちなみにお盆休み明けの8月18日(月)には、25のご質問をいただきましたが、
ご質問は内容は、次の通りでした。
1.母性健康管理指導事項連絡カードについて
2.社会保険の加入について
3.定年延長の件(無期転換ルール)
4.国際雇用や社会保険に関する問題
5.育児中社員の異動について
6.柔軟な働き方を実現するための措置について
7.柔軟な働き方を実現するための措置 申請の時期・回数
8.労災の可能性のある事例に関する望ましい対応について
9.産休中の社会保険料について
10.異動時の減給・降格について
11.出勤時間と始業時間に関して
12.時間単位年休と就業規則
13.出向先閉鎖による退職の離職理由区分について
14.育児休暇取得時の不利益について
15.アルバイトの休業手当について
16.有給休暇について
17.自己都合による通勤経路変更について
18.時差出勤の規程について
19.再就職手当の支給申請について
20.1年変形制労働での休日出勤に関する手当
21.正社員からの降格願いについて
22.183日ルール超過時の労務管理について
23.柔軟な働き方を実現するための措置」の変更制限について
24.後期高齢医療保険制度について
25.パートの2回目以降の年次有給休暇について
なお、このご質問に対する私を含む回答者の回答は
「日本の人事部 Q&A」コーナーでご確認いただけますので、
是非、一度、サイトでご確認いただければ幸いです。
このように、毎日、毎日、懸命に質問に対し、回答を続けているわけですが、
回答者をその気にさせるいろいろな工夫があることに驚かされました。
何といっても、回答者をやる気にさせる一番の仕組みは「回答者ランキング」です。
回答者の人数は、おそらく、30人くらいだと思います。
その回答者になるべく沢山の回答をしてもらう仕組みにランキングがあります。
詳細は把握しておりませんが、1問に回答すると20ポイント、その回答に質問者が「大変参考になりました」と返信するとプラス80ポイント、「参考になりました」でプラス40ポイント、
「参考になりませんでした」はプラスポイントなし、というような仕組みで、回答者を競わせるのです。
回答者ランキングは、日本の人事部のQ&Aコーナーの最初のページに掲載されております。
やはり、ランキングが発表されるとなると俄然、やる気になるのがイノキュウです。
4月は3位、5月は2位でしたが、仕組みを理解した6月以降は、1位をキープさせていただいております。
もう一つは、いくら回答してもお金はいただけませんが、コピー用紙やプリンターのインク等の事務用品や書籍を購入できる通販サイトで使用できるギフトポイントのプレゼントがあります。
お陰様で、4月以降、事務用品や書籍関係の支出はしなくて済んでおります。
また、一生懸命、毎日、毎日、懸命に回答を続けたところ、
日本の人事部の掲載記事担当の編集長から、監修の仕事を依頼されました。
勿論、喜んでお引き受けさせていただきましたが、この仕事は、いくばくかの報酬があります。
正に、働き方改革推進センターの仕事を失い、収入面では大変でしたが、
それ以上に価値のあるすばらしい仕事が出来るようになり、本当に有難いと感謝いたしております。(1614字)
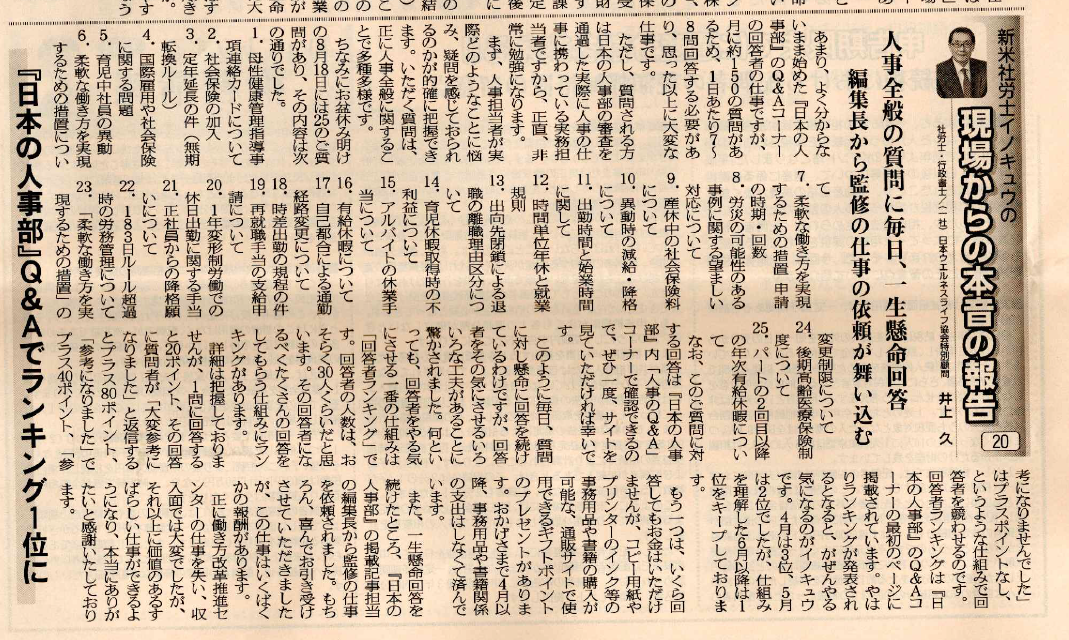
2025年11月10日(月)第20回掲載分
第21回(2025年12月8日(月)掲載分)
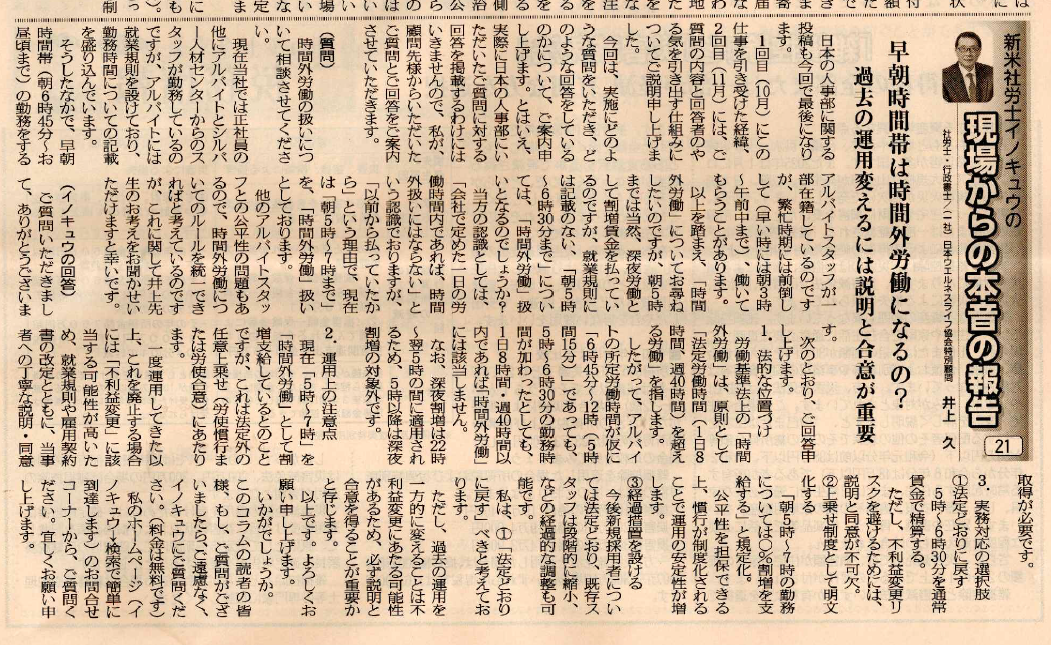
2025年12月8日(月)掲載分
日本の人事部に関する投稿も今回で最後になります。
1回目(10月)にこの仕事を引き受けた経緯、2回目(11月)には、ご質問の内容と回答者のやる気を引き出す仕組みについてご説明申し上げました。
今回は、実施にどのような質問をいただき、どのような回答をしているのかについて、ご案内申し上げます。
とは言え、実際に日本の人事部にいただいたご質問に対する回答を掲載する訳にはいきませんので、私が、顧問先様からいただいたご質問とご回答をご案内させていただきます。
(質問) 時間外労働の扱いについて相談させてください。
現在当社では正社員の他に、アルバイトとシルバー人材センターからのスタッフが勤務しているのですが、アルバイトには就業規則を設けており、勤務時間についての記載を盛り込んでいます。
そうしたなかで、早朝時間帯(朝6:45~お昼頃まで)の勤務をするアルバイトスタッフが一部在籍しているのですが、繁忙時期には前倒しして(早い時には朝3時~午前中まで)、働いてもらうことがあります。
以上を踏まえ、「時間外労働」についてお尋ねしたいのですが、
朝5時までは当然、深夜労働として割増賃金を払っているのですが、
就業規則には記載のない、「朝5:00~6:30まで」については、「時間外労働」扱いとなるのでしょうか?
当方の認識としては、「会社で定めた一日の労働時間内であれば、時間外扱いにはならない」
という認識でおりますが、「以前から払っていたから」という理由で、
現在は「朝5時~7時まで」を、「時間外労働」扱いとしております。
他のアルバイトスタッフとの公平性の問題もあるので、時間外労働についてのルールを統一できれば、と考えているのですが、これに関して、井上先生のお考えをお聞かせいただけますと幸いです。
(イノキュウの回答)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的な位置づけ
労働基準法上の「時間外労働」は、原則として「法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働」を指します。
したがって、アルバイトの所定労働時間が仮に「6:45~12:00(5時間15分)」であっても、5:00~6:30の勤務時間が加わったとしても、1日8時間・週40時間以内であれば「時間外労働」には該当しません。
なお、深夜割増は22時~翌5時の間に適用されるため、5:00以降は深夜割増の対象外です。
2. 運用上の注意点
現在「5:00~7:00」を「時間外労働」として割増支給しているとのことですが、これは法定外の任意上乗せ(労使慣行または労使合意)にあたります。
一度運用してきた以上、これを廃止する場合には 「不利益変更」に該当する可能性が高いため、就業規則や雇用契約書の改定とともに、当事者への丁寧な説明・同意取得が必要です。
3. 実務対応の選択肢
①法定通りに戻す
5:00~6:30を通常賃金で精算する。
ただし、不利益変更リスクを避けるためには、説明と同意が不可欠。
②上乗せ制度として明文化する
「朝5:00~7:00の勤務については○%割増を支給する」と規定化。
公平性を担保できる上、慣行が制度化されることで運用の安定性が増します。
③経過措置を設ける
今後新規採用者については法定どおり、既存スタッフは段階的に縮小、などの経過的な調整も可能です。
私は、①「法定通りに戻す」べきと考えております。
ただし、過去の運用を一方的に変えることは不利益変更にあたる可能性があるため、必ず説明と合意を得ることが重要かと存じます。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
いかがでしょうか。
このコラムの読者の皆様、もし、ご質問がございましたら、
ご遠慮なく、イノキュウにご質問ください。(勿論、料金は無料です。)
私のホームページ(イノキュウ→検索で簡単に到達します)のお問合せコーナーから、
ご質問下さい。宜しくお願い申し上げます。
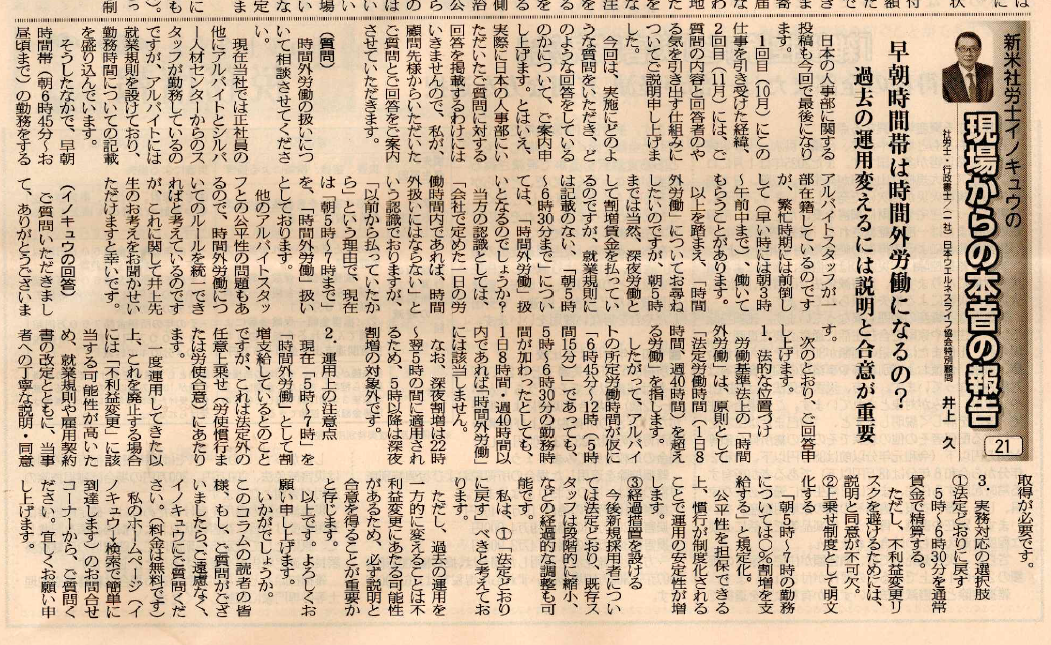
2025年12月8日(月)掲載分
第22回(2026年1月12日(月)掲載分
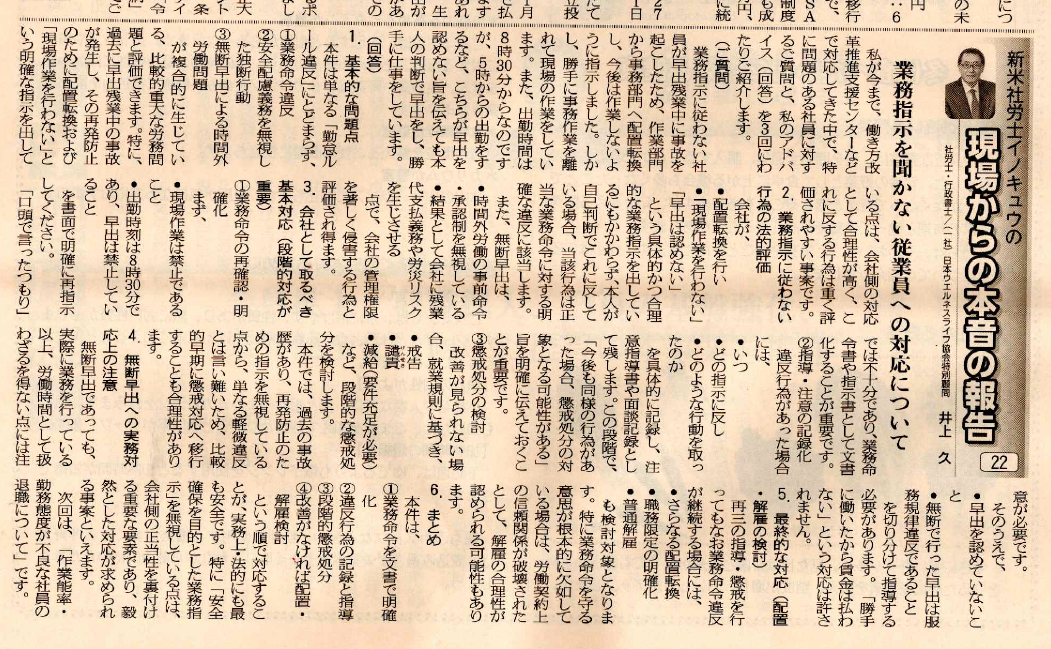
2026年1月12日(月)掲載分
2026年1月掲載予定原稿 「業務指示を聞かない従業員への対応について」
私は、今まで、働き方改革推進支援センターの相談員として、また、日本の人事部のQ&Aの回答者として、約4,000人のお客さまに対応してまいりました。今回から、3回は、その中で、特に問題のある社員に対するご質問と、私のアドバイス(回答)をご案内申し上げます。よろしくお願いいたします。
(ご質問)
業務指示に従わない社員に対しての
会社としての対応について、ご教授いただきたく存じます。
以前、該当の社員は早出残業中に事故を起こしたため、
作業部門から事務部門へ配置転換し、今後は、作業しないように指示いたしました。
しかし、勝手に事務作業を離れて現場の作業をしてしまいます。
また、出勤時間は8:30~なのですが、5:00~出勤をするなど、こちらが早出を認めない旨を伝えても本人の判断で早出をし、勝手に仕事をしております。
(回答)
1.本件の基本的な問題点
本件は単なる「勤怠ルール違反」にとどまらず、
① 業務命令違反
② 安全配慮義務を無視した独断行動
③ 無断早出による時間外労働問題
が複合的に生じている、比較的重大な労務問題と評価できます。
特に、過去に早出残業中の事故が発生し、その再発防止のために配置転換および「現場作業を行わない」という明確な指示を出している点は、会社側の対応として合理性が高く、これに反する行為は重く評価されやすい事案です。
2.業務指示に従わない行為の法的評価
会社が、
・配置転換を行い
・「現場作業を行わない」「早出は認めない」
という具体的かつ合理的な業務指示を出しているにもかかわらず、本人が自己判断でこれに反している場合、当該行為は正当な業務命令に対する明確な違反に該当します。
また、無断早出は、
・時間外労働の事前命令・承認制を無視している
・結果として会社に残業代支払義務や労災リスクを生じさせる
点で、会社の管理権限を著しく侵害する行為と評価され得ます。
3.会社として取るべき基本対応(段階的対応が重要)
① 業務命令の再確認・明確化
まず、
・現場作業は禁止であること
・出勤時刻は8:30であり、早出は禁止していること
を書面で明確に再指示してください。
「口頭で言ったつもり」では不十分であり、業務命令書や指示書として文書化することが重要です。
② 指導・注意の記録化
違反行為があった場合には、
・いつ
・どの指示に反し
・どのような行動を取ったのか
を具体的に記録し、注意指導書や面談記録として残します。
この段階で、
「今後も同様の行為があった場合、懲戒処分の対象となる可能性がある」
旨を明確に伝えておくことが重要です。
③ 懲戒処分の検討
改善が見られない場合、就業規則に基づき、
・戒告
・譴責
・減給(要件充足が必要)
など、段階的な懲戒処分を検討します。
本件では、過去の事故歴があり、再発防止のための指示を無視している点から、単なる軽微違反とは言い難いため、比較的早期に懲戒対応へ移行することも合理性があります。
4.無断早出への実務対応上の注意
無断早出であっても、実際に業務を行っている以上、労働時間として扱わざるを得ない点には注意が必要です。
そのうえで、
・早出を認めていないこと
・無断で行った早出は服務規律違反であること
を切り分けて指導する必要があります。
「勝手に働いたから賃金は払わない」という対応は許されません。
5.最終的な対応(配置・解雇の検討)
再三の指導・懲戒を行ってもなお業務命令違反が継続する場合には、
・さらなる配置転換
・職務限定の明確化
・普通解雇
も検討対象となります。
特に、業務命令を守る意思が根本的に欠如している場合は、労働契約上の信頼関係が破壊されたとして、解雇の合理性が認められる可能性もあります。
6.まとめ
本件は、
①業務命令を文書で明確化
②違反行為の記録と指導
③段階的懲戒処分
④改善がなければ配置・解雇検討
という順で対応することが、実務上・法的にも最も安全です。
特に「安全確保を目的とした業務指示」を無視している点は、会社側の正当性を裏付ける重要な要素であり、毅然とした対応が求められる事案といえます。
いかがでしょうか。次回は、「作業能率・勤務態度が不良な社員の退職について」ご案内申し上げます。
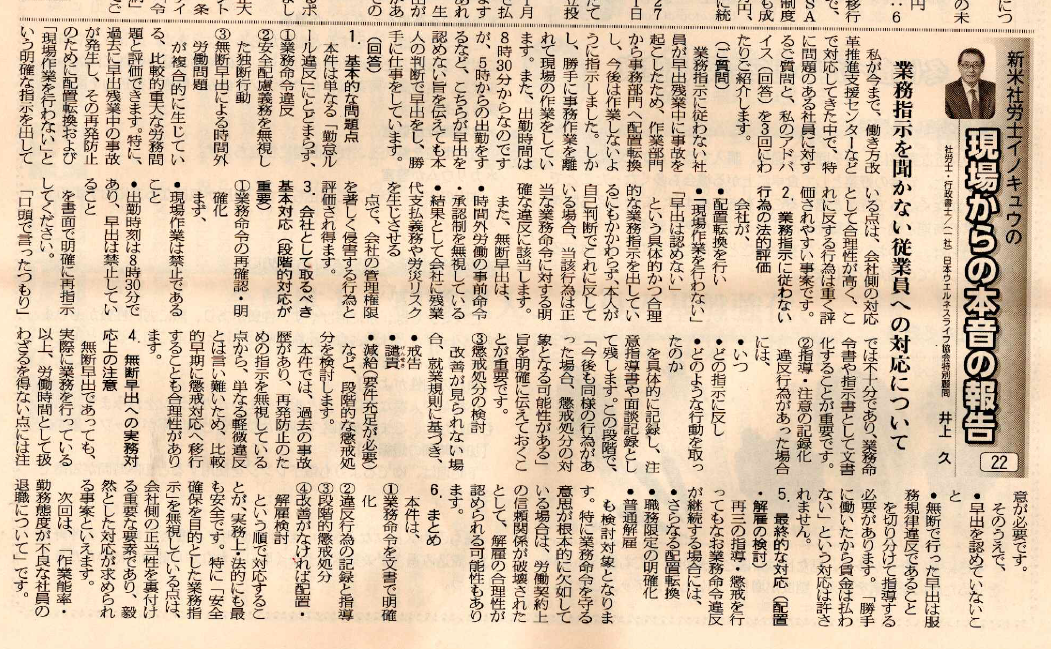
2026年1月12日(月)掲載分 第22回 業務指示を聞かない従業員への対応について
新着情報・お知らせ
井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
アクセス
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

